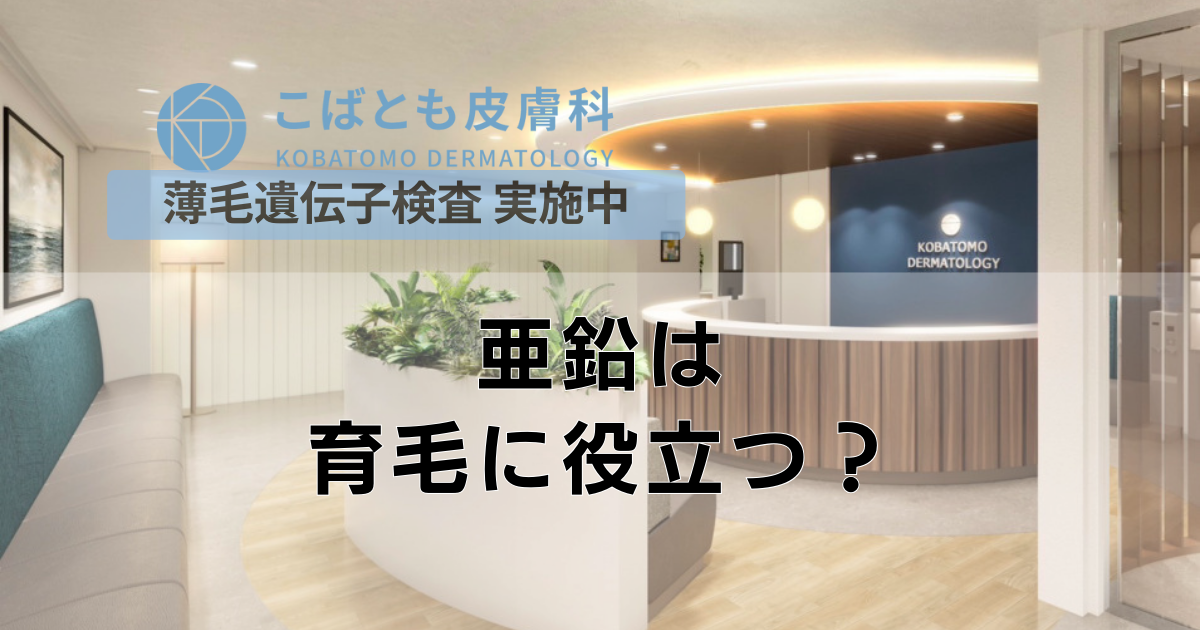抜け毛の増加や髪のハリ不足を感じると、不安や焦りを覚える方は多いです。髪の健康を保つには、頭皮の環境や生活習慣の見直しが大切です。その中でも注目したい栄養素が亜鉛です。
体内で多くの働きを支えるミネラルのひとつであり、髪や頭皮を丈夫に導くために意識して摂取する方も増えています。
とはいえ、ただむやみに量を増やせばいいというわけではありません。亜鉛の働きや摂取量の目安、食品の選び方を知り、適切な取り入れ方を考えてみましょう。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
亜鉛と育毛の関係性~薄毛予防に欠かせない栄養素
髪の成長にはタンパク質やビタミンだけでなく、さまざまな栄養の存在が重要です。亜鉛は酵素の働きをサポートし、髪の主成分であるケラチンを生成するときにも関わるといわれています。
ここでは、亜鉛が髪とどのように関わるのかをひも解きながら、薄毛予防の観点から確認します。
亜鉛が関与する髪の合成プロセス
髪の大部分はケラチンと呼ばれるタンパク質です。体内でタンパク質を合成するときに亜鉛が酵素の働きをサポートし、その結果として丈夫な毛髪を育みやすい土台を作ります。
頭皮や毛母細胞が元気に働くには栄養バランスが大切で、亜鉛を含むミネラル群も意識的に摂取するとよいでしょう。不足すると髪が弱くなりやすいため、生活習慣に沿った食事計画に亜鉛を組み込みたいところです。
亜鉛不足で髪や頭皮に起こる変化
亜鉛が不足すると、ケラチンの合成が円滑に行われにくくなります。さらに、皮膚や爪などにも影響を与え、頭皮のターンオーバーが乱れる恐れがあります。
こうした状態が続くと髪のコシが失われたり、抜け毛が増えたりする可能性があるため、健やかな毛髪を維持するうえでも亜鉛は大切です。
AGA治療の観点から見た亜鉛の意義
AGA(男性型脱毛症)はホルモンバランスが関係すると考えられますが、治療や対策の一環として栄養面を整えることがすすめられる場合があります。
そのときに亜鉛を積極的に補うことで、頭皮のコンディションを整えやすくする考え方も存在します。ただし、AGAの進行度や体質は人それぞれ異なるので、医療機関で相談しながら十分な情報を得ることが大切です。
亜鉛の主な役割
亜鉛が関係する主な働きを、簡単にまとめると次のようになります。髪の生成だけでなく、細胞の増殖や免疫機能など幅広い役割を担っていることがわかります。
| 亜鉛の働き | 具体的な例 |
|---|---|
| 髪の合成 | ケラチン生成を助ける |
| 免疫機能 | 免疫力を整え体調維持をサポート |
| 酵素活性 | 体内の代謝プロセスを円滑にする |
このように、亜鉛は多方面から健康維持に貢献します。髪のトラブルが気になる方だけでなく、体力や免疫を保つうえでも重要な栄養素です。
髪のために気をつけたいポイント
- 過度のアルコール摂取を避ける
- たんぱく質・ビタミンとのバランスを心がける
- 加工食品ばかりに偏らない食事内容を意識する
上のようなポイントにも気を配ることで、亜鉛の吸収を妨げる要因を減らしやすくなります。髪の成長を内側から支えるには、日常生活全体をととのえる姿勢が必要です。
薄毛予防のための亜鉛の1日の目安量
亜鉛を摂ることが大切だとわかっても、適量を把握しておかないと、摂り過ぎや不足を招く可能性があります。
特に髪のために意識的に取り入れたい方は、厚生労働省が示す推奨量の数値を参考にすることで、バランスを保ちやすくなります。ここでは、1日にどの程度の亜鉛が理想的かを解説します。
推奨量の目安と男女差
厚生労働省は亜鉛の1日あたりの摂取目安量を示しています。一般的には男性が約12mg、女性が約9mgが参考値です。
ただし、年齢や体格、健康状態などに応じて必要量は変わることがあるので、自身のライフスタイルに合わせて調整するとよいでしょう。
過不足のリスクと髪への影響
1日の目安量を無視して極端な過剰摂取をすると、体内の他のミネラルバランスが乱れる恐れがあります。たとえば銅の吸収が妨げられることがあり、逆効果になる可能性も否定できません。
一方、あまりに少ないと髪や頭皮の栄養不足を招きやすいです。適度な範囲内で摂取し、薄毛予防につなげることが大切です。
年齢と生活習慣に合わせた摂取バランス
成長期や妊娠中、運動量が多い人などは栄養需要が高まる傾向があります。生活習慣が多様化する中で、年齢を重ねるごとに胃腸の働きが低下しやすく、亜鉛の吸収率も落ち込むケースがあります。
そのため、食事だけでまかないにくいと感じる方は、かかりつけ医に相談する方法も検討するとよいでしょう。
亜鉛摂取量の目安
厚生労働省が示す目安を参考に、男女別に整理すると以下のようになります。あくまで一般的な目安なので、個別の事情に合わせて調整してください。
| 性別 | 亜鉛の推奨量(1日あたり) |
|---|---|
| 男性 | 約12mg |
| 女性 | 約9mg |
この推奨量は成人を対象にしているので、成長期の子どもや妊娠中、授乳期の女性などは別途考慮が必要です。
よくある疑問点
- サプリメントと食事はどのように組み合わせるべきか
- 体調不良時に亜鉛量を増やしたほうがよいのか
- 栄養素同士の相互作用をどう意識すればよいのか
このような疑問を解決するには、日ごろから自分の食事内容を見直し、気になる点があれば医療の専門家に相談すると安心です。
亜鉛を多く含む食品と効果的な取り方・過剰摂取の注意点
亜鉛が多く含まれる食品はいくつかありますが、食材の特徴を知り、日常の食事に取り入れる工夫が大切です。また、亜鉛は他のミネラルやビタミンとの組み合わせによって吸収効率が左右されることがあります。
ここでは、食材選びや摂り方のコツを解説し、過剰摂取にならないよう注意すべきポイントも整理します。
亜鉛を含む主な食材の特徴
代表的なものとして挙げられるのが、牡蠣や牛肉、レバーなどの動物性食品です。ほかにも、ナッツ類や大豆製品、全粒穀物などにも含まれています。
動物性食品は吸収率が比較的高いとされ、植物性食品でも組み合わせ次第では効果的に摂取できます。いずれにしても、偏った食事ではなく多彩な食材を選ぶことが大切です。
調理方法と吸収効率
亜鉛は加熱による損失がさほど大きくありませんが、食品中のフィチン酸や食物繊維が多いと吸収率が低下する場合があります。
大豆製品を摂取するときは発酵食品や加工食品の形で食べると、亜鉛を摂りやすくなる可能性があります。また、レモン汁や酢などで酸味を加えるとミネラルの吸収をサポートするといわれています。
サプリメント利用時の注意点
忙しい現代社会では、サプリメントで亜鉛を補う方も珍しくありません。食事だけでは十分な量を摂りにくい状況では役立つこともありますが、用量を守ることが大切です。
過剰に摂ると他のミネラル吸収を妨げるほか、胃腸に負担がかかるおそれがあります。特定の病気や持病のある方は、服用前に医師へ相談しましょう。
過剰摂取のリスクと対策
亜鉛を必要以上に摂ると、体内のバランスを乱し、銅や鉄の吸収に影響することがあります。長期的に見ると貧血につながる恐れもあります。
薄毛を気にして積極的に亜鉛をとることを意識する方ほど、過剰分に注意することが重要です。適切な範囲内で上手に摂り入れ、かえってマイナスにならないよう気をつけましょう。
亜鉛を豊富に含む主な食材と含有量の目安
以下の表では、代表的な食材の亜鉛含有量の一例をまとめています。一度に大量に摂るのではなく、複数の食品から少しずつ取り入れる工夫をすると過不足を抑えやすくなります。
| 食材名 | 亜鉛含有量(約100gあたり) |
|---|---|
| 牡蠣 | 13mg前後 |
| 牛もも肉 | 5mg前後 |
| レバー(豚) | 6mg前後 |
| 大豆 | 3mg前後 |
| アーモンド | 3mg前後 |
含有量は目安なので、実際の料理のレシピや加工状態によって変動します。食品をうまく組み合わせることで、無理なく必要量を満たせるでしょう。
亜鉛と相性のよい食事の工夫
- 酸味を加えてミネラルの吸収を後押し
- 動物性と植物性の食品をバランスよく取り入れる
- 加工食品やレトルト食品の多用を控える
- 大豆製品は味噌や納豆など発酵食品の形で活用する
上記のような視点を取り入れると、亜鉛を効果的に摂取しつつほかの栄養もバランスよく得ることが期待できます。食事だけでなく、休養やストレスケアも含めた生活スタイル全体を振り返る姿勢が大切です。
亜鉛だけを過剰に意識すると、ほかの栄養バランスが崩れてしまう恐れがあります。サプリメントの活用や医師への相談などを視野に入れながら、過不足のない摂取を心がけてください。
参考文献
KONDRAKHINA, Irina N., et al. Plasma zinc levels in males with androgenetic alopecia as possible predictors of the subsequent conservative therapy’s effectiveness. Diagnostics, 2020, 10.5: 336.
EL‐ESAWY, Fatma Mohamed; HUSSEIN, Mohamed Saber; IBRAHIM MANSOUR, Amira. Serum biotin and zinc in male androgenetic alopecia. Journal of Cosmetic Dermatology, 2019, 18.5: 1546-1549.
OZTURK, Perihan, et al. BMI and levels of zinc, copper in hair, serum and urine of Turkish male patients with androgenetic alopecia. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2014, 28.3: 266-270.
WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2400652.
FAMENINI, Shannon; GOH, Carolyn. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol, 2014, 13.7: 809-812.