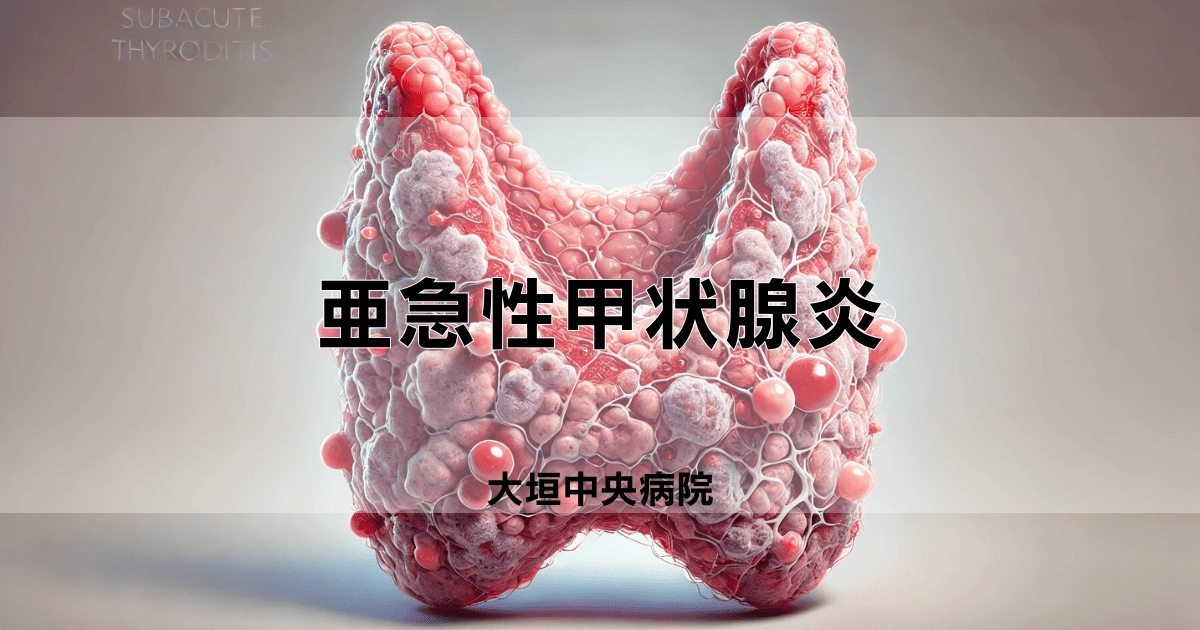亜急性甲状腺炎とは、主に甲状腺の一部が炎症を起こして痛みや腫れを伴う疾患です。
多くの場合は一過性の経過をたどりますが、発熱や頸部の強い痛み、甲状腺ホルモンの変動による全身症状など、日常生活に支障を及ぼすほどつらい状態になることもあります。
この病気を放置してしまうと痛みが増して睡眠や食事に大きな影響を与え、さらに甲状腺ホルモンの異常による不快な症状が長引くこともあるため、早めの受診や検査が重要です。
亜急性甲状腺炎はしっかりと診断して正しい治療を受ければ、比較的安定した回復が見込めます。
亜急性甲状腺炎の病型
亜急性甲状腺炎にはいくつかの特徴的な病型があり、それによって発症の仕方や経過の長さ、痛みの程度が異なります。
いずれも甲状腺に強い炎症を生じ、主に痛みと腫脹を特徴としますが、甲状腺機能の変動の仕方や症状の強さが異なる場合があります。
病型の概要
亜急性甲状腺炎は、主にウイルス感染などが要因で甲状腺の組織が破壊されることで生じると考えられています。
この炎症が始まると甲状腺ホルモンが過剰に血中へ放出されることで甲状腺機能亢進期が生じ、その後徐々にホルモンが不足して機能低下期を迎え、最終的には正しい機能を取り戻していくという一過性の流れを取るのが典型です。
一過性の経過と甲状腺機能の変動
亜急性甲状腺炎では、最初に急な甲状腺機能亢進状態になりやすく、動悸や発汗過多などが目立ち、その後、一時的な機能低下状態へ移行し、全身の倦怠感やむくみ、体温調節のしづらさなどが出やすくなります。
最終的には甲状腺の組織が回復し、元のホルモン分泌状態に戻るパターンを取ることが多いです。
典型的な病型と稀な病型
典型的には痛みを伴う亜急性甲状腺炎が多いですが、痛みが軽度で気づきにくいケースや痛みがほとんどない「無痛性亜急性甲状腺炎」と呼ばれる病型も知られています。
無痛性の場合は気づかないまま経過し、偶然の検査で発覚することもあります。
病型の診断の重要性
亜急性甲状腺炎であるかどうかや、どの程度炎症が進んでいるかを早めに判断することが大切です。検査やホルモン値の変動でおおよその見通しを立てることができ、治療の進め方を決める際に役立ちます。
ただし病型は人によって経過が異なり、状況や症状から総合的に診断します。
代表的な亜急性甲状腺炎の病型
| 病型名 | 症状の特徴 | 経過の特徴 |
|---|---|---|
| 痛みを伴う亜急性甲状腺炎 | 発熱、頸部の腫脹、強い痛み、嚥下時の不快感などが目立つ | 甲状腺機能亢進期→機能低下期→回復 |
| 無痛性亜急性甲状腺炎 | 痛みがほぼない、微熱程度、疲れやすさや動悸などに留まる | 痛みの少ない亢進期・低下期を経て回復 |
| 軽症タイプ | 痛みや発熱が軽度で、軽い倦怠感や軽度の喉の痛みが続く程度 | 亢進や低下の幅が小さく経過は比較的短い |
亜急性甲状腺炎全体としては上記のような分類を目安に考えますが、実際には個人差があり、必ずしもすべての人が同じプロセスをたどるわけではありません。
亜急性甲状腺炎の症状
亜急性甲状腺炎を疑うきっかけとなる症状には、発熱や強い頸部痛が挙げられ、甲状腺周辺の痛みは特徴的で、炎症の強さに比例して日常生活に支障をきたすほどになることがあります。
さらに甲状腺ホルモンの乱れによって全身症状が顕著に表れる場合があります。
首周辺の痛みと腫れ
亜急性甲状腺炎の代表的な症状は、首の正面やや下あたりの強い痛みです。痛みは片側から始まることが多く、数日かけて甲状腺全体や反対側へ広がります。腫れも伴う場合、頸部に軽く触れるだけでも強い痛みを感じる人がいます。
食事の際に物を飲み込むだけで痛むことも多く、普段の食生活に支障が出ます。
甲状腺ホルモンの亢進に伴う症状
甲状腺機能亢進が起こる時期には、動悸、発汗過多、手指の震え、落ち着かない気分、体重減少などが生じやすくなります。これらは甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、体の代謝が急激に高まるためです。
機能低下時の症状
機能亢進期を過ぎると、一時的に甲状腺ホルモンが足りなくなる機能低下期に移行するケースが少なくありません。この時期には、倦怠感、体重増加、むくみ、寒がり、便秘などが目立ちます。
急な体調の変化に戸惑う人も多いため、医師と相談しながら対応すると安心です。
日常生活への影響
首の痛みがひどいと会話や食事、睡眠姿勢などに影響が出、また、甲状腺ホルモンの異常が続くと、身体的な負担だけでなく精神的な不安も増します。
ある程度痛みを抑えるために鎮痛薬の服用が必要となる場合もありますし、外出や運動などの活動性が制限されることもあります。
よくみられる症状
- 首の痛み(片側から広がる場合が多い)
- 発熱(微熱から高熱まで幅広い)
- 食事や会話時の痛み
- 強い倦怠感
- 動悸、発汗増加
- むくみや体温調節の乱れ
甲状腺ホルモンの変動に応じて症状が変わることが特徴なので、経過を観察しながら自分の体調の変化をこまめに医師へ伝えることが大切です。
亜急性甲状腺炎の主な症状
| 主な症状 | 出現しやすいタイミング | 注意点 |
|---|---|---|
| 首の痛み | 炎症が始まる初期~中期 | 片側から始まり次第に反対側へ広がることが多い |
| 発熱 | 痛みと同時期、炎症が強い時期 | 微熱~38℃台以上まで、個人差がある |
| 甲状腺機能亢進症状 | 痛みと同時か、痛みの後に生じることも | 動悸や発汗過多が顕著 |
| 甲状腺機能低下症状 | 亢進期の後 | むくみ、倦怠感、体重増加など |
原因
亜急性甲状腺炎の直接の原因としては、はっきりと確立されていない部分もありますが、一般的にはウイルス感染が深く関与していて、上気道感染や風邪をきっかけに発症するケースが多いのではないかと推測されています。
ウイルス感染との関連
ウイルスによって甲状腺が刺激され、組織が破壊されたり炎症を起こしたりする可能性が指摘され、インフルエンザやコクサッキーウイルスなど、上気道炎の原因とされるウイルスとの関連が報告されています。
さらに、免疫反応が過剰に働くことで甲状腺の細胞にダメージが及び、亜急性甲状腺炎が引き起こされるという考え方があります。
遺伝的な要素
遺伝的な背景が関わる可能性も指摘されており、同一の家系で複数人が経験している例もあります。ただし、遺伝要因のみで亜急性甲状腺炎が起こるわけではなく、複数の要因が重なった結果です。
生活習慣との関係
激しいストレスや過労、睡眠不足などによって一時的に免疫力が落ちているときにウイルスに感染すると、亜急性甲状腺炎が発症しやすくなります。
また、食生活の乱れや喫煙・過度な飲酒も免疫機能に影響を与えるため、間接的に関連している可能性があります。
発症のきっかけ
特定の時期に風邪のような症状が続いたあとに首の痛みが始まったり、高熱とともに急激に頸部が腫れてきたりするなど、発症のタイミングはさまざまです。
- インフルエンザ後に急に首周辺が痛みはじめる
- 引っ越しや仕事の繁忙期などストレスの多い時期に発熱が長引く
- 家族が同じ時期に風邪を引いていたが自分だけ甲状腺の炎症を起こした
このように原因は複数要因が考えられ、生活環境やストレス、免疫状態が複雑に絡み合って発症することが多いと考えられます。
亜急性甲状腺炎と関連が指摘される主な要因
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| ウイルス感染 | インフルエンザウイルス、コクサッキーウイルスなど、多くの報告例がある |
| 免疫反応 | 体内の免疫が甲状腺を攻撃する自己免疫現象が加わり炎症が強くなる可能性がある |
| ストレス | 過労や精神的負担がかかる時期に発症リスクが高まることがある |
| 遺伝的要因 | 家族内発症例があることから遺伝的感受性が存在する可能性がある |
亜急性甲状腺炎の検査・チェック方法
亜急性甲状腺炎を疑った場合、診察時の問診や視診・触診だけでなく、血液検査や画像検査などを組み合わせて総合的に診断します。
痛みの原因が甲状腺なのかどうか、他の病気の可能性はないかなどを見極めるためにも、複数の検査を行うことが多いです。
問診と触診
医師はまず首の痛みの状況や発症時期、発熱の有無、前駆症状として風邪のような状態があったかどうかなど、患者さんが抱える症状を丁寧に聞き取ります。
触診では甲状腺の腫大の有無や痛みの程度を確認し、痛みを伴い、触れると非常に敏感になっているのは、亜急性甲状腺炎を強く疑う症状です。
血液検査によるホルモン値の測定
血液検査では甲状腺ホルモン(T3、T4)や甲状腺刺激ホルモン(TSH)を測定し、機能亢進や機能低下の状態をチェックします。
さらに炎症の度合いを示すCRPや白血球数などの数値も確認します。亜急性甲状腺炎の場合はCRPが著しく高値を示すことが多いです。
- 甲状腺ホルモン(T3、T4)の変動
- TSHの低下または上昇
- 炎症マーカー(CRP、赤沈)の上昇
- 白血球数の変化
甲状腺エコー検査
首にゼリーを塗って超音波装置を当て、甲状腺の形態や内部の状態を画像で確認する検査です。
亜急性甲状腺炎では、甲状腺内部に低エコー域が点在することがあり、典型的には不均一なパターンを示し、また、腫大の有無や全体的な血流の変化などを把握できます。
放射性ヨード摂取率検査
放射性ヨードを使って甲状腺の取り込み状態を調べる検査です。亜急性甲状腺炎の初期には、甲状腺組織の破壊によって血中にホルモンが放出されるため、甲状腺の実質的なヨード取り込みは低下する傾向があります。
バセドウ病など他の甲状腺機能亢進症と区別するのに役立ちます。
その他検査の選択
必要に応じてCTやMRIといった画像検査を行い、頸部のリンパ節や他の組織に病変がないか確認する場合もあります。首の痛みが甲状腺以外の病気に由来する可能性や、他の疾患との合併を調べるために追加検査を行うことがあります。
亜急性甲状腺炎の診断過程における主な検査
| 検査種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 問診・触診 | 痛みの程度、腫脹、発症状況などを詳しく確認 | 痛みが甲状腺由来かどうか、急性度や病型の推定 |
| 血液検査 | 甲状腺ホルモン、TSH、CRP、白血球数などを測定 | 甲状腺機能の変動と炎症の度合いの評価 |
| 甲状腺エコー | 超音波画像で甲状腺の形態や血流を確認 | 腫大の有無、低エコー域の存在確認 |
| 放射性ヨード摂取率 | 甲状腺が放射性ヨードを取り込む割合を測定 | バセドウ病など他の機能亢進症との鑑別 |
| CT/MRI | 頸部や周辺組織の精密検査 | 他疾患の可能性や合併症の有無をチェック |
検査におけるポイント
- 血液検査の甲状腺ホルモンと炎症マーカーを同時に確認する
- 痛みが強い場合はエコー検査で炎症領域を視覚的に把握する
- 疑いがあれば放射性ヨード摂取率で他の甲状腺疾患と区別する
- 痛みや病状経過を定期的に医師に伝える
亜急性甲状腺炎の治療方法と治療薬について
亜急性甲状腺炎の治療は、主に炎症と痛みを抑えることを目的に行われ、甲状腺ホルモンの異常による不快症状がある場合は、その制御も同時に行うことが必要です。症状の強さや甲状腺機能の変化度合いによって治療の選択肢は異なります。
鎮痛薬や抗炎症薬の使用
首の痛みが強い亜急性甲状腺炎の患者には、痛みを抑える薬が重要です。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、比較的軽症の亜急性甲状腺炎に広く用いられ、炎症を抑制し、首の痛みや腫れ、発熱などの症状を和らげることが期待できます。
ステロイド薬の利用
痛みや炎症が非常に強い場合や、NSAIDsで十分な改善が得られないときには、ステロイド薬(副腎皮質ホルモン)が検討されます。
ステロイド薬には炎症を強力に抑える効果があり、甲状腺ホルモンの異常による症状の悪化を防ぐ目的でも使われます。ただし、ステロイド薬は効果が高い反面、副作用のリスクもあるため、正しい量と期間を考慮しながら医師が処方します。
ステロイド薬の比較
| 薬剤名 | 特徴 | 対象となるケース |
|---|---|---|
| プレドニゾロン | 経口ステロイドの代表的な薬 | 重症例やNSAIDsでコントロール困難な場合 |
| メチルプレドニゾロン | プレドニゾロンよりやや強めの効果 | 初期に症状が急速に悪化している場合 |
| デキサメタゾン | ステロイドの中で効果が強め | 短期集中治療が必要な時 |
甲状腺機能亢進や機能低下への対応
一時的に甲状腺機能が亢進して動悸や発汗が続く場合は、β遮断薬などで症状を緩和し、また、低下期に移行して疲れやすさやむくみが強い場合には、甲状腺ホルモン製剤を使用して症状を緩和することがあります。
亜急性甲状腺炎の場合は経過とともに自然回復することも多いので、機能低下が一時的なものか持続するものかを見極めることが重要です。
安静と日常生活の工夫
首の痛みが強い場合は首を動かすのがつらく、日常生活にも支障をきたし、痛みが増す動作や激しい運動はできるだけ避け、首の保温や軽いストレッチなどでこりを和らげる工夫も考えられます。
過労や睡眠不足は免疫低下につながるため、できるだけ休養をとりながら回復を目指すことが望ましいです。
治療方針を考えるうえでのポイント
- 軽症ならNSAIDsで炎症を抑え、痛みの軽減を図る
- 強い痛みや炎症にはステロイド薬が有力な選択肢
- 甲状腺機能異常が顕著な時期は症状対策を重点的に行う
- 体調や血液検査結果を見ながら投薬内容や量を段階的に調整する
- 首を冷やしすぎず、適度に保温して違和感を和らげる
亜急性甲状腺炎の主な治療薬
| 治療薬カテゴリ | 具体例 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) | ロキソプロフェン、イブプロフェンなど | 炎症と痛み、発熱の軽減 |
| ステロイド薬 | プレドニゾロンなど | 強い炎症や甲状腺機能異常の制御 |
| β遮断薬 | プロプラノロールなど | 甲状腺機能亢進による動悸や不安感の緩和 |
| 甲状腺ホルモン製剤 | レボチロキシンなど | 機能低下期が長引く場合の補充 |
治療期間
亜急性甲状腺炎は一過性の疾患といわれ、通常は数週間から数か月程度で回復が見込まれることが多いです。ただし、個人差が大きく、2~3か月ほどでほぼ症状が落ち着く人もいれば、半年以上かけてじっくり治療を続ける例もあります。
回復までの一般的な流れ
最初の数週間は痛みや炎症が強く、NSAIDsやステロイド薬で症状のコントロールを行う期間になり、その後、痛みが和らいできた段階で薬の量を徐々に減らし、経過観察に移行します。
甲状腺機能の変動が激しい場合は、症状がなくなっても定期的に血液検査を受け、機能亢進や低下が続いていないかチェックします。
ステロイドを使用する場合の期間
ステロイド薬を使う場合は、いきなり中断せずに段階的に減量していく方法が一般的です。
短期間で急に中止するとリバウンドが起こり、痛みや炎症が再燃することがあるので、多くの人は1~2か月かけてゆっくり減量し、症状の再発の有無を確認しながら治療を終えていきます。
回復を促進するために大切なこと
回復期間は個人の体力や免疫力、ストレス状況などにも左右されます。十分な睡眠と栄養バランスのとれた食事、適度な運動やストレス解消などを心がけることで、症状の和らぎやすさや再発のリスクをコントロールしやすくなります。
治療期間中のフォローアップ
痛みがほとんどなくなっても、炎症が残っていたり甲状腺機能の低下や亢進が持続している場合があります。治療期間中は定期的な通院で血液検査やエコー検査を受け、内服薬や生活習慣の調整を続けることが大切です。
治療期間中に心がけたいこと
- 痛みが落ち着いても定期的に甲状腺ホルモン値をチェックする
- 薬の量は医師の指示に従って段階的に調整する
- 首の冷えや過労を避け、回復を妨げないようにする
- 痛みがぶり返したり発熱が再度起きた場合は早めに受診する
亜急性甲状腺炎薬の副作用や治療のデメリットについて
亜急性甲状腺炎の治療薬には、主にNSAIDsとステロイド薬がありますが、それぞれ効果と同時に副作用のリスクを伴います。
大半は医師の管理のもと、重篤な副作用を回避できますが、治療の継続にあたってはリスクを理解しておくことが大切です。
NSAIDsの副作用
NSAIDsの長期使用は胃や腸の粘膜に刺激を与え、胃痛や下痢、胃潰瘍などを起こす可能性があり、さらに、体質によっては腎機能への影響やアレルギー反応(発疹やかゆみ、まれに喘息発作)が現れることがあります。
胃の保護薬を併用することも検討され、そうした対策によって多くの場合は安全に使用することが可能です。
ステロイド薬の副作用
ステロイド薬には炎症を強力に抑える効果がある反面、多様な副作用が知られていて、代表的ものは、血糖値の上昇、体重増加、むくみ、骨密度の低下、感染症にかかりやすい、などです。
また、精神面にも影響する場合があり、気分の浮き沈みや不安感を訴える人もいます。ステロイドを中断する際に減量を急ぐと症状が逆戻りしてしまうことがあるので、医師と相談しながら慎重に減量計画を立てます。
治療期間が長引くデメリット
亜急性甲状腺炎では、多くのケースで完治を見込めるものの、症状が長引けば通院や薬の服用も続きます。薬の副作用対策やライフスタイルの調整に注意を払い続ける必要があるため、精神的にも経済的にも負担になることがあります。
症状緩和と副作用リスクのバランス
どの薬を使用しても副作用の可能性がゼロになるわけではありませんが、正しい容量と期間を守ることで多くの場合は重大な合併症を避けられます。
亜急性甲状腺炎は一時的な炎症と捉えられることが多いため、痛みが落ち着いてきたら薬の量を減らし、最終的には服用を終了できる見通しがある点は大きな利点です。
副作用と対策
| 治療薬 | 主な副作用 | 対策・注意点 |
|---|---|---|
| NSAIDs | 胃腸障害、腎機能障害など | 胃の保護薬併用、水分摂取量や体調を管理 |
| ステロイド薬 | 体重増加、血糖値上昇、骨量減少、精神面の変調など | 長期使用を避け、定期的な検査と慎重な減量 |
| β遮断薬 | 血圧低下、めまいなど | 低血圧や既往症の有無を事前に確認 |
| ホルモン製剤 | 動悸や興奮など | 適切な量を守り、甲状腺機能の変化をチェック |
副作用に注意するポイント
- 胃痛やむくみ、体重増加などの変化を自己観察する
- 不安定な精神状態が続く場合は早めに医師へ報告する
- 生活習慣を整えて薬以外のリスクを減らす
- 定期検査で血液検査や骨密度測定などを行い状態を把握する
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
診察・検査・薬剤の費用
亜急性甲状腺炎の診断や経過観察に必要な血液検査や甲状腺エコー検査、放射性ヨード摂取率検査などはいずれも保険が適用されます。
複数の検査を行うことが多いですが、一般的な自己負担割合(3割負担の場合)で計算すると、検査一式で数千円から1万円程度です。
薬代の目安
亜急性甲状腺炎で使う薬は、多くが保険適用内の医薬品でNSAI、Dsやステロイド薬であれば、1か月分で数百円~数千円程度の範囲に収まるケースが多いです。
ステロイド薬は処方量によって金額が変動しやすいため、炎症が強い時期には薬代がやや高くなることもあります。甲状腺ホルモン製剤やβ遮断薬を併用する場合も、標準的な用量なら数百円~千円台です。
治療費の目安
| 項目 | 内容 | 費用目安(3割負担の場合) |
|---|---|---|
| 診察費 | 医師による診察・問診・触診 | 数百円~1,000円前後 |
| 血液検査 | ホルモン値、炎症マーカー、白血球数など | 1,000~3,000円程度 |
| 甲状腺エコー | 甲状腺の状態を超音波で確認 | 1,000円台~2,000円前後 |
| 放射性ヨード摂取率検査 | 甲状腺の取り込み量を測定 | 3,000円~5,000円前後 |
| NSAIDs等の薬代 | 炎症・痛みを抑える薬 | 1か月分で数百円~千円台 |
| ステロイド薬 | 重症例などで処方される副腎皮質ホルモン | 処方量によって数百円~数千円 |
以上
参考文献
Greene JN. Subacute thyroiditis. The American journal of medicine. 1971 Jul 1;51(1):97-108.
Stasiak M, Lewiński A. New aspects in the pathogenesis and management of subacute thyroiditis. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. 2021 Dec;22(4):1027-39.
Alfadda AA, Sallam RM, Elawad GE, AlDhukair H, Alyahya MM. Subacute thyroiditis: clinical presentation and long term outcome. International journal of endocrinology. 2014;2014(1):794943.
Daminov AT, Kuchkorova MZ. Subacute Thyroiditis. International Multi-disciplinary Journal of Education. 2024 Aug 12;2(8):121-9.
Görges J, Ulrich J, Keck C, Müller-Wieland D, Diederich S, Janssen OE. Long-term outcome of subacute thyroiditis. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2020 Nov;128(11):703-8.
VOLPÉ R. The management of subacute (DeQuervain’s) thyroiditis. Thyroid. 1993;3(3):253-5.
Burman KD. Subacute thyroiditis. UpToDate. Waltham (MA): UpToDate.[accessed 2021 Nov 11]. 2022.
Zhao N, Wang S, Cui XJ, Huang MS, Wang SW, Li YG, Zhao L, Wan WN, Li YS, Shan ZY, Teng WP. Two-years prospective follow-up study of subacute thyroiditis. Frontiers in endocrinology. 2020 Feb 28;11:47.
Ray I, D’Souza B, Sarker P, Agarwal P. Management of subacute thyroiditis–a systematic review of current treatment protocols. International Journal of General Medicine. 2022;15:6425.
Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I. Subacute thyroiditis: clinical characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 1999 and 2005. Journal of endocrinological investigation. 2007 Sep;30:631-5.