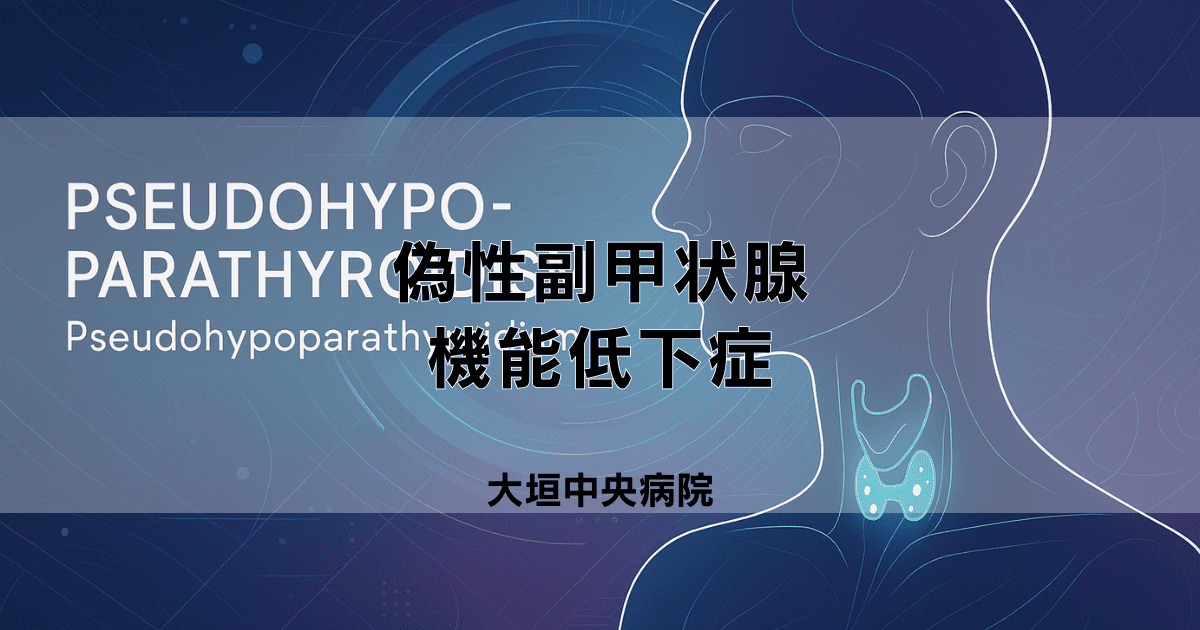偽性副甲状腺機能低下症とは、副甲状腺ホルモン(PTH)の分泌量が十分であるにもかかわらず、標的となる臓器がPTHにうまく反応できないことで血中カルシウムやリンの濃度調整が乱れる稀な内分泌系の疾患の総称です。
いわゆるホルモン抵抗性に分類され、全身の骨や歯、さらには神経や筋肉にも影響を及ぼしやすい傾向があります。
正しく理解することで、自分自身が置かれた状態や将来のリスクを把握し、適切な治療や日常生活での対策につなげることが重要です。
偽性副甲状腺機能低下症の病型
偽性副甲状腺機能低下症にはいくつかの病型があり、それぞれ遺伝的な要因や症状の強弱、血液検査の結果などで区別します。
病型の分類概要
偽性副甲状腺機能低下症を理解するうえで、まずは各病型の概要を把握する必要があります。
・PHP1aはAlbrightの遺伝性骨異栄養症(AHO)と呼ばれる骨や軟部組織の特徴的な症状を伴う傾向があります
・PHP1bはAHOの特徴が乏しく、主に腎臓におけるPTH抵抗性が目立ちます
・PHP2はPTH抵抗性の原因がPHP1aや1bとは異なる経路が示唆されます
病型を正しく区別するときには骨や軟組織の異常、ホルモン抵抗性の程度、遺伝子レベルでの解析などが助けになります。
偽性副甲状腺機能低下症の病型
| 病型 | 特徴的症状 | 遺伝子変異の主な例 | 代表的な所見 |
|---|---|---|---|
| PHP1a | AHO様症状(短指、満月様顔貌など) | GNAS遺伝子変異 | 甲状腺ホルモンにも抵抗性が出やすい |
| PHP1b | AHO様症状が少ない、腎臓のPTH抵抗性 | GNAS遺伝子のメチル化異常 | 血中カルシウム低下やリン上昇 |
| PHP2 | AHO様症状はなし、詳細メカニズム不明 | 不明 | PTH抵抗性はあるが遺伝変異は限定的 |
PHP1aとPHP1bの違い
PHP1aはAHOと呼ばれる身体的特徴を伴うことが多く、身長の低さや手指の短さ、丸い顔などが認められます。さらに甲状腺ホルモンや成長ホルモンなど、複数のホルモンに対する抵抗性がみられる場合がある点も注目すべき点です。
一方でPHP1bはAHOのような目立つ身体的特徴が少なく、主に腎臓のPTH抵抗性により低カルシウム血症や高リン血症が生じる点が大きな違いです。
PHP2型の特徴
PHP2はPHP1aやPHP1bよりさらに稀なタイプであり、GNAS遺伝子変異が明確に同定されていない場合が多いです。
臨床的にはPTHに対する反応不全が見られ、血中カルシウムとリンに異常が生じますが、AHO様症状を認めず、検査でもPHP1系統の特徴を示さないという特徴を持ちます。
まだ研究の段階で不明点も多く、原因遺伝子を特定する試みが続けられています。
遺伝的要因との関連
偽性副甲状腺機能低下症の多くは遺伝的要因を背景に持ち、家族歴がある場合もありますが、発現パターンや表現型は一様ではありません。
GNAS遺伝子変異を持つから必ず症状が出るとは限らず、同じ変異を持っていても症状の程度に差があることも知られています。遺伝カウンセリングを通して、今後の計画や日常生活の注意点、家族への説明を行うことが重要です。
偽性副甲状腺機能低下症の症状
病型だけでなく、それに伴う症状を理解することが、早期の対処や治療の選択に役立ち、偽性副甲状腺機能低下症はカルシウムやリンの調整不全によって骨や神経筋系などに多彩な症状を示しやすいことが特徴です。
加えて、身体的な外見変化や発育の遅れを伴うケースもあり、生活の質に影響を及ぼす可能性があります。
低カルシウム血症による症状
偽性副甲状腺機能低下症では、PTHが十分に分泌されていても体内の標的器官がうまく反応できないため、血中カルシウム濃度が低下しやすいです。
低カルシウム血症が進むと、手足のしびれや筋肉のけいれん、テタニー症状(手足の強いこわばり)などが起こりやすくなり、ときには口唇や舌先がピリピリとする感覚を訴えることもあります。
低カルシウム血症関連症状の特徴
| 症状名 | 主な特徴 | 関連する感覚 |
|---|---|---|
| テタニー | 手足の筋肉が強い痙攣を起こす | ピリピリする違和感 |
| 口唇のしびれ | 口周囲の感覚が鈍くなる | うずくような軽い痛み |
| 四肢のしびれ | 手足にビリビリする感覚が生じる | 筋肉の収縮を誘発しやすい |
上記のような症状があると、日常生活で手作業や歩行が不自由になることがあり、頻度や強度が増すと不安も高まるため、早めに医療機関で相談することが大切です。
高リン血症による骨や歯のトラブル
偽性副甲状腺機能低下症では、腎臓でのリン排泄がうまくいかず、高リン血症になりやすく、リンが骨や歯の組成に影響を与え、骨密度の低下を起こすことや、歯のエナメル質に問題が生じることが懸念されます。
骨折リスクの増加や虫歯になりやすい状態になる可能性があり、骨や歯の健康管理にも注意が必要です。
AHO様症状と見た目の変化
PHP1aの場合、手足の短さや丸顔などの特徴的な身体的変化が認められることがあり、AHO(Albrightの遺伝性骨異栄養症)と呼ばれる症候群に関連しており、しばしば短指症や体重増加、知的発達面の遅れがみられます。
外見上の特徴が顕著であるため、学童期や思春期で本人の心理面に影響が出るケースもあります。
その他の全身症状
偽性副甲状腺機能低下症では、神経筋症状だけでなく、慢性的な倦怠感や発育不全、内分泌器官への影響が出る場合もあります。
成長ホルモンや甲状腺ホルモンなど他のホルモン抵抗性が並存すると、全体的な発育や体重増加に影響が及ぶ可能性があります。症状が複合的に現れるときは、専門医のフォローが重要です。
偽性副甲状腺機能低下症に伴い起こりうる症状
| 症状・所見 | 生活への影響 | フォローアップの例 |
|---|---|---|
| 骨密度の低下 | 転倒リスクの増加 | 定期的な骨密度測定 |
| 歯のエナメル質障害 | 虫歯や歯肉炎のリスク上昇 | 歯科検診と適切なケアの実施 |
| 身体的特徴 | 社会・心理的な影響 | カウンセリングの活用や周囲の理解 |
| 神経筋症状 | 日常動作や集中力の低下 | 症状の変化を医療スタッフに相談 |
偽性副甲状腺機能低下症の原因
偽性副甲状腺機能低下症は、副甲状腺ホルモンそのものは十分に作られているにもかかわらず、体内の標的組織がうまく反応できないことによって起こります。
おもにGNAS遺伝子変異などの遺伝的要因が深く関わっているとされていますが、詳細にはホルモン受容体やシグナル伝達経路の異常が複雑に関与しています。
GNAS遺伝子の役割
GNAS遺伝子は、ホルモンシグナル伝達に重要なGタンパク質をコードする遺伝子として知られています。
Gタンパク質が正常に機能しないと、副甲状腺ホルモンが細胞に信号を伝えても反応が得られないため、血中カルシウム濃度やリン濃度の制御が難しくなります。
GNAS遺伝子の突然変異がある場合、偽性副甲状腺機能低下症の家族内発症がみられることが多いです。
・Gタンパク質は多くのホルモン受容体のシグナル伝達を担う
・変異の種類により症状の出方が異なる
・PHP1aとPHP1bの遺伝子変異部位やメチル化異常の違いが病型を決めることがある
GNAS遺伝子はホルモン抵抗性の根幹に関連し、他の内分泌腺機能の異常も引き起こす可能性が指摘されています。
エピジェネティクスによる影響
PHP1bでは、必ずしもGNAS遺伝子自体の配列変異をもたない症例もあり、メチル化異常と呼ばれるエピジェネティックな変化がPTH抵抗性の原因になる可能性があります。
GNAS遺伝子とエピジェネティック変化の主なポイント
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| GNAS遺伝子変異 | 塩基配列レベルでの変化が確認される場合 |
| メチル化異常 | 遺伝子自体の配列ではなくメチル化の変化 |
| 発現調節 | エピジェネティクスの変化によりmRNAの量が変わる |
| PHP1a・PHP1bの関係性 | PHP1aは配列変異が多く、PHP1bはメチル化異常が多い |
ホルモン受容体の異常
PTH受容体そのものに異常があるケースも考えられ、受体遺伝子の一部に変異があると、副甲状腺ホルモンが結合しても細胞内にうまくシグナルが伝わりません。
その結果、カルシウム再吸収やリン排泄が正常に進まず、偽性副甲状腺機能低下症と似た症状が出ることがありますが、PTH受容体の遺伝子変異は比較的まれです。
環境因子の関与
偽性副甲状腺機能低下症の主たる要因は遺伝的背景ですが、環境要因も関与しています。
骨や腎臓への負担が大きくなるような栄養バランスの乱れや、極端なダイエットなどがあると、潜在的にPTH抵抗性が顕在化しやすくなる可能性があります。
ただし、根本的には遺伝的要因が強く、環境因子だけで偽性副甲状腺機能低下症を起こすことはあまりありません。
・無理な食事制限や特定栄養素の欠乏
・慢性的なストレスや不規則な生活リズム
・骨や腎臓に負担をかける過度な運動や喫煙習慣
このような要素が重なると、症状が目立ちやすくなる場合があるため、生活習慣の見直しも視野に入れることが大切です。
検査・チェック方法
偽性副甲状腺機能低下症かどうかを調べる際には、カルシウムやリン、PTH値を調べる血液検査だけではなく、ホルモン負荷試験や遺伝子検査などを組み合わせて総合的に判断します。
症状が似ていても、真性の副甲状腺機能低下症と偽性の場合では治療アプローチが異なるため、正確な診断が大切です。
血液検査でのポイント
まずは血清カルシウム(Ca)、リン(P)、副甲状腺ホルモン(PTH)などの値を測定して、PTH分泌がどの程度行われているか、カルシウムやリンのバランスがどう崩れているかを調べます。
偽性副甲状腺機能低下症では、PTHが高値または正常高値にもかかわらず、低カルシウム血症や高リン血症が認められる傾向があります。
・血清Ca:低め
・血清P:高め
・PTH:高め~正常上限
結果のパターンが疑わしい場合、偽性か真性かを区別する追加検査が重要です。
代表的な血中検査項目と臨床的意義
| 項目 | 主なチェックポイント | 偽性副甲状腺機能低下症の傾向 |
|---|---|---|
| 血清カルシウム | 正常値8.5~10.5mg/dL程度 | 低下 |
| 血清リン | 正常値2.5~4.5mg/dL程度 | 上昇 |
| PTH | 正常値10~65pg/mL程度(測定法で変動) | 高めまたは正常高値 |
PTH負荷試験の実施
PTH負荷試験では、外因性にPTHを投与して体内反応を見ることで、腎臓や骨などの標的器官がどの程度ホルモンに応答しているかを確認します。
通常、PTH投与後は腎臓によるリン排泄が促進され、血中カルシウムが上昇してリンが下降しますが、偽性副甲状腺機能低下症では十分な反応が得られず、これによりホルモン抵抗性を評価できます。
遺伝子検査の必要性
GNAS遺伝子などに変異やメチル化異常がある場合、遺伝子検査によって確定診断に近づける可能性があり、特に家族内発症が疑われるケースや、PHP1aとPHP1bを厳密に区別したい場合に行うことがあります。
ただし、検査の費用や実施施設に限りがあることがあるため、医師との相談が欠かせません。
遺伝子検査の特徴と注意点
| 検査名 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| GNAS遺伝子解析 | 変異の有無や変異部位の特定 | 施設によって検査体制が異なる |
| メチル化解析 | PHP1bで指摘されるメチル化異常の判定 | 結果判定に時間や専門知識が必要 |
| 家系調査 | 家族内発症や遺伝子連鎖の確認 | プライバシー保護に配慮する必要あり |
他ホルモンの検査
偽性副甲状腺機能低下症では、甲状腺ホルモンや性ホルモン、成長ホルモンなど、他のホルモン系統でも抵抗性がみられる可能性があり、症状や病型に応じて、適宜追加のホルモン検査を行い、総合的な内分泌機能の評価を実施します。
特にPHP1aでは、多系統のホルモン抵抗性を示すケースもあるため、定期的な確認が必要です。
・甲状腺ホルモン(TSHやT4など)
・成長ホルモン(GH)
・性腺刺激ホルモン(LH、FSH)
検査結果や臨床症状を組み合わせて総合的に判断することで、偽性副甲状腺機能低下症の正確な病態像に近づけます。
治療方法と治療薬について
偽性副甲状腺機能低下症の治療は、主として低カルシウム血症や高リン血症をコントロールすることが目的です。
副甲状腺ホルモン自体を補充しても標的器官が反応しにくいので、カルシウムやビタミンD製剤の補給が中心で、また、高リン血症の改善を図るためにリン吸着薬を使用する場合もあります。
カルシウム補充療法
低カルシウム血症の改善を目的として、カルシウム製剤やビタミンD活性化薬を使用します。
カルシウム製剤には内服タイプが多く、継続的な内服で血中カルシウム濃度の安定化を図り、ビタミンDはカルシウムの吸収を助けるため、併用するケースが多いです。
・カルシウム製剤(カルシウム塩など)
・活性型ビタミンD(カルシトリオールなど)
・適度な日光浴と食事中のカルシウム摂取も検討
上記のような組み合わせで治療を行い、症状が安定するようにコントロールを目指します。
偽性副甲状腺機能低下症に使われる主な薬剤
| 薬剤名 | 主な作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| カルシウム製剤 | 血中カルシウム濃度の補正 | 腹部不快感や便秘に留意 |
| 活性型ビタミンD | 腸管からのカルシウム吸収を促進 | 高カルシウム血症のリスク |
| リン吸着薬 | 腸管でリンを吸着し排泄を促進 | 腸閉塞や消化器症状に注意 |
リン吸着薬の使用
血中のリン濃度が高い場合は、リン吸着薬を用いて食事中のリンを抑える方法をとることがあり、リン吸着薬は食事と一緒に摂取し、腸管内でリンと結合して吸収を阻害します。
ただし、過剰に使用すると他の栄養素の吸収に影響を与える可能性があるため、用量調整が必要です。
併発症への対応
偽性副甲状腺機能低下症では、骨粗鬆症や虫歯、甲状腺機能異常などを併発しやすい場合があるため、それぞれに応じた治療が必要です。
骨粗鬆症に対しては骨吸収抑制薬や運動療法、虫歯リスクに対しては歯科医による定期的ケアなど、総合的な管理を行うと生活の質を維持しやすくなります。
運動と食事療法
適度な運動は骨の健康維持に役立ち、カルシウムの骨への取り込みをサポートする可能性があります。無理のない範囲でウォーキングや軽い筋力トレーニングを行うとよいでしょう。
また、食事面ではカルシウムを豊富に含む牛乳や乳製品、小魚、豆類などをバランスよく摂取することが望ましいです。一方でリンを多く含む加工食品や清涼飲料水の摂取は控えめにする工夫が必要になります。
主な栄養素と例となる食品
| 栄養素 | 代表的な食品 | 注意点 |
|---|---|---|
| カルシウム | 牛乳、ヨーグルト、小魚など | 過剰に摂取しすぎると腎結石リスクがある場合がある |
| ビタミンD | 鮭、きのこ類、いくらなど | 日光浴との組み合わせが望ましい |
| リン | 加工肉、清涼飲料水 | 摂取過剰に留意 |
偽性副甲状腺機能低下症の治療期間
偽性副甲状腺機能低下症は慢性的な疾患であり、ホルモン抵抗性そのものを完治させるのは難しいと考えられています。
しかし、治療薬の使用や食事・生活習慣の管理によって、低カルシウム血症や高リン血症などの症状をコントロールすることが可能です。治療期間は基本的に生涯にわたって継続することを視野に入れる必要があります。
治療継続の重要性
カルシウム製剤やビタミンD製剤を中断すると、すぐに低カルシウム血症や高リン血症が再発しやすくなるため、自己判断で薬をやめたり減量したりせず、医師の指示に従って継続した投薬が大切です。
定期的に血液検査を行い、カルシウムやリンの値をチェックしながら調整していきます。
治療管理において意識しておきたいポイント
・血液検査の頻度を定期的に確認し、値の推移を追う
・サプリメントなどの自己判断での追加は避け、医師に相談する
・症状が軽快しても一時的なものである可能性がある
継続的な医療サポートを受けながら自分の身体の変化を把握することが重要です。
年齢や生活ステージに応じた対応
小児期から思春期にかけては骨や身体の発達が進む時期なので、カルシウムやビタミンDが不足しないように注意が必要です。
成人になってからも妊娠や出産などでホルモンバランスが変化する場合は、医師と連携して治療方針をその都度相談します。加齢に伴い骨粗鬆症のリスクが高まるので、高齢期に入ってからも同様に継続的な管理が必要です。
生活習慣の見直し期間
薬による治療に加えて、生活習慣の見直しや食事療法も長期間にわたって行い、特にリンの制限やカルシウム摂取バランスの調整には、慣れるまでに時間がかかることがあります。
焦らずに少しずつ食事の内容を工夫し、適度な運動を取り入れることで、身体全体の健康を維持しながら症状の悪化を防ぎます。
| 時期 | 主なフォーカス | 合わせて行う治療・ケア |
|---|---|---|
| 小児期〜思春期 | 骨や歯の発達の支援、学習面のサポート | 定期的な内分泌検査、歯科健診 |
| 成人期 | 仕事・妊娠などライフステージの変化 | カルシウム・ビタミンDの適切な投与 |
| 高齢期 | 骨粗鬆症リスクの増加 | 骨密度測定と転倒防止策、栄養ケア |
定期的なフォローアップの必要性
定期的なフォローアップでは、投薬による血中カルシウムやリンのコントロール状態や、副作用の有無を確認し、また、骨密度や甲状腺機能など、他の内分泌器官の状態も並行してチェックします。
ビタミンDの過剰投与による高カルシウム血症や腎機能障害のリスク、リン吸着薬の使用で便秘や消化器トラブルが起きていないかなど、こまめな確認が大切です。
薬の副作用や治療のデメリットについて
偽性副甲状腺機能低下症で用いる薬剤は、血中カルシウムやリンをコントロールするために有用ですが、薬によっては副作用が起きることもあります。
カルシウム製剤の副作用
カルシウム製剤を多めに摂取すると、高カルシウム血症を誘発する場合があり、高カルシウム血症になると、口渇や多尿、便秘などの症状が現れたり、腎結石のリスクが高まることもあります。
腎機能に不安がある場合や、そのほかの基礎疾患がある場合は、医師が用量を細かく調整します。
・カルシウム製剤の過剰投与による高カルシウム血症
・便秘や胃腸障害などの不調
・長期的に腎機能へ影響を及ぼすリスク
服用量や投与間隔に注意を払い、定期的な血液検査でカルシウム濃度を確認します。
活性型ビタミンDのリスク
ビタミンDはカルシウムの吸収を促進するため、偽性副甲状腺機能低下症の治療において重要な役割を果たしますが、過剰投与すると高カルシウム血症や高リン血症をさらに悪化させる可能性があります。
薬の種類によって作用の強さが異なるため、処方量の管理が欠かせません。
薬による主な副作用と注意点
| 薬剤名 | 主な副作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| カルシウム製剤 | 高カルシウム血症、便秘など | 定期的な血液検査が必要 |
| 活性型ビタミンD | 高カルシウム血症、高リン血症 | 用量調節をしながら定期モニタリング |
| リン吸着薬 | 消化器症状(便秘や下痢) | 他の薬との飲み合わせに注意 |
リン吸着薬のデメリット
リン吸着薬は高リン血症を抑えるために用いられる一方で、消化器系の不調が発生することがあり、便秘や腹部膨満感を訴える人もいれば、反対に下痢が続く場合もあります。
また、腸管内で他の薬剤や栄養素と結合してしまい、ほかの薬の効果が低下したり、栄養吸収を阻害するリスクがあります。
・便秘や下痢などの消化器症状
・同時に服用する薬の吸収に影響する可能性
・服用タイミングを分けるなど工夫が必要
偽性副甲状腺機能低下症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
診断時の検査費用
血液検査やホルモン負荷試験、場合によっては遺伝子検査を行い、保険が効くため、自己負担が数千円程度になることが多いです。
遺伝子検査の実施頻度はそれほど高くないものの、専門施設で行う場合、保険適用される範囲内の検査でも自己負担額が1万円前後になる可能性があります。
| 検査項目 | 保険適用範囲内の自己負担目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般的な血液検査 | 約1,000円~2,000円 | Ca、P、PTHなどを同時測定する |
| ホルモン負荷試験 | 数千円~1万円程度 | 負荷試験の時間や方法により変動 |
| 遺伝子検査 | 約5,000円~1万円程度 | 検査施設や検査項目数によって変動が大きい |
治療薬の費用
偽性副甲状腺機能低下症で使用する薬の多くも保険適用の範囲内で、カルシウム製剤や活性型ビタミンDなどは、月あたりの自己負担が数百円から1,000円前後になるケースも多いです。
リン吸着薬は薬の種類によって価格差がありますが、こちらも数百円から1,500円程度となります。
・カルシウム製剤:月数百円~1,000円程度
・活性型ビタミンD:月1,000円程度
・リン吸着薬:月数百円~1,500円程度
以上
参考文献
Hasegawa M, Sakakibara Y, Takeuchi Y, Sugitani I, Ozono K, Castriota F, Ayodele O, Sakaguchi M. Prevalence and characteristics of postoperative and nonoperative chronic hypoparathyroidism in Japan: a nationwide retrospective analysis. JBMR plus. 2024 Sep;8(9):ziae100.
Nakamura Y, Matsumoto T, Tamakoshi A, Kawamura T, Seino Y, Kasuga M, Yanagawa H, Ohno Y. Prevalence of idiopathic hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism in Japan. Journal of Epidemiology. 2000;10(1):29-33.
Sano S, Nakamura A, Matsubara K, Nagasaki K, Fukami M, Kagami M, Ogata T. (Epi) genotype-phenotype analysis in 69 Japanese patients with pseudohypoparathyroidism type I. Journal of the Endocrine Society. 2018 Jan 1;2(1):9-23.
Tamada Y, Kanda S, Suzuki H, Tajima T, Nishiyama T. A pseudohypoparathyroidism type Ia patient with normocalcemia. Endocrine journal. 2008;55(1):169-73.
Kanatani M, Sugimoto T, Kaji H, Ikeda K, Chihara K. Skeletal responsiveness to parathyroid hormone in pseudohypoparathyroidism. European journal of endocrinology. 2001 Mar;144(3):263-9.
YASUDA T, NIIMI H. Hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism. Pediatrics International. 1997 Aug;39(4):485-90.
Matsuura N, Kaname T, Niikawa N, Ooyama Y, Shinohara O, Yokota Y, Ohtsu S, Takubo N, Kitsuda K, Shibayama K, Takada F. Acrodysostosis and pseudohypoparathyroidism (PHP): adaptation of Japanese patients with a newly proposed classification and expanding the phenotypic spectrum of variants. Endocrine Connections. 2022 Oct 1;11(10).
MANABE Y, ARAKI M, TAKEDA K, YOKOTA S, KiMURA T. Pseudohypoparathyroidism with Striopallidodentate Calcification A Case Report and Review of the Literature. Japanese Journal of Medicine. 1989;28(3):391-5.
Seki T, Yamamoto M, Kimura H, Tsuiki M, Ono M, Miki N, Takano K, Sato K. Vitamin D deficiency in two young adults with biochemical findings resembling pseudohypoparathyroidism type I and type II. Endocrine journal. 2010;57(8):735-44.
Mizunashi K, Furukawa Y, Miura R, Yumita S, Sohn HE, Yoshinaga K. Effects of active vitamin D3 and parathyroid hormone on the serum osteocalcin in idiopathic hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism. The Journal of clinical investigation. 1988 Sep 1;82(3):861-5.