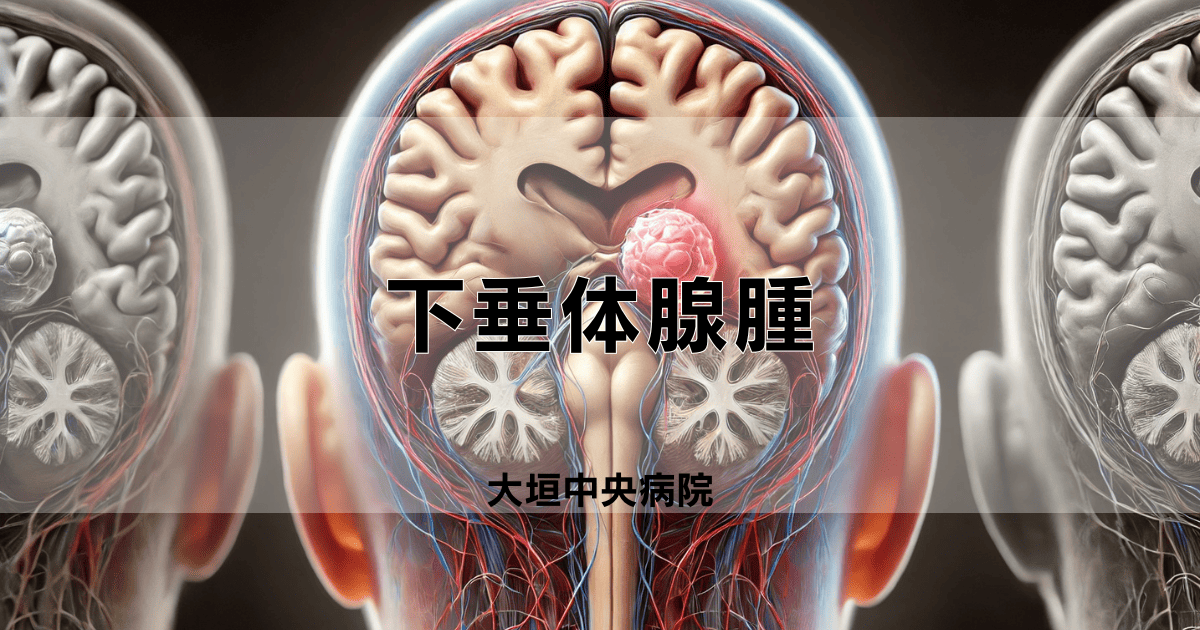下垂体腺腫とは、脳の底部にある下垂体という内分泌腺に発生する良性腫瘍のことです。
ホルモン分泌に深く関わる部位に異常が生じるため、日常生活における全身の調子や健康状態に大きく影響することがあります。
下垂体は体内のホルモンバランスを維持するうえで非常に重要な役割を担う器官で、ここに腫瘍が生じた場合、無症状で経過するケースがある一方で、腫瘍の大きさや部位、産生するホルモンの種類などによって多彩な症状を起こします。
下垂体腺腫の病型
下垂体腺腫は、ホルモンを分泌するかしないか、および腫瘍の大きさや部位によっていくつかの病型に分類できます。
腫瘍のホルモン分泌による分類
腫瘍がホルモンを分泌する「機能性下垂体腺腫」と、ホルモンをほとんど分泌しない「非機能性下垂体腺腫」に大きく分けられます。
機能性の場合は分泌されるホルモンの種類に応じて症状が異なるため、早期発見につながりやすいケースもありますが、一方で非機能性の場合は腫瘍の大きさが大きくなるまで症状が目立たない場合があり、発見が遅れることもあります。
ホルモンの種類別の特徴
機能性下垂体腺腫の中でも、分泌されるホルモンによってさらに細分化されます。
代表的なものは、プロラクチン(PRL)を過剰分泌する「プロラクチノーマ」、成長ホルモン(GH)を分泌する「成長ホルモン産生腺腫」、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を分泌する「ACTH産生腺腫」などです。
ホルモン産生の主な例
| ホルモン名 | 分泌する腺腫の名称 | 代表的な症状 |
|---|---|---|
| プロラクチン(PRL) | プロラクチノーマ | 月経異常、乳汁分泌、性欲減退など |
| 成長ホルモン(GH) | 成長ホルモン産生腺腫 | 先端巨大症、末端肥大、関節痛など |
| ACTH | ACTH産生腺腫 | クッシング症候群(肥満や血圧上昇など) |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン産生腺腫 | 甲状腺機能亢進症状(動悸や体重減少など) |
腫瘍の大きさによる分類
腫瘍の大きさによっても分類され、一般的には直径1cm未満を「マイクロアデノーマ」、1cm以上を「マクロアデノーマ」と呼び、マクロアデノーマになると、周囲構造(視神経や動眼神経など)への圧迫症状を起こしやすくなります。
また、マクロアデノーマの中には、視交叉を圧迫することで視野障害を呈するものもあり、注意が必要です。
非機能性腺腫の特徴
非機能性の場合は、ホルモン過剰分泌による症状は起こりにくいですが、そのかわり腫瘍が大きくなるまで自覚症状が乏しいことがあります。
頭蓋内圧の上昇や視神経周囲への圧迫による頭痛や視野異常などが発見のきっかけになることが多いです。
下垂体腺腫の症状
下垂体腺腫は、腫瘍の大きさやホルモン分泌の有無によって症状が多彩で、ホルモン過剰分泌に伴う症状や、周囲組織への圧迫症状などが代表的であり、身体のいろいろな部位に影響を及ぼす場合があります。
ホルモン異常に伴う症状
腫瘍が特定のホルモンを過剰分泌する場合には、それぞれのホルモン異常に応じて特徴的な症状が現れます。
例えばプロラクチン過剰なら乳汁分泌や月経不順、性欲低下を伴う可能性があり、成長ホルモンが過剰な場合は手足や顔などが大きくなる先端巨大症、関節痛や骨変形などをきたすことがあるのです。
ホルモン異常の症状リスト
- プロラクチン上昇:月経異常や乳汁分泌
- 成長ホルモン上昇:手足のサイズ拡大、下顎突出など
- ACTH上昇:満月様顔貌、体幹肥満、高血圧など(クッシング症候群)
- 甲状腺刺激ホルモン上昇:甲状腺機能亢進症状
腫瘍の圧迫による神経症状
非機能性の腺腫や大型の機能性腺腫は、物理的に周辺組織を圧迫してさまざまな症状を起こします。
視神経交叉付近を圧迫すると、両耳側の視野が欠ける「両耳側半盲」や視力低下などが見られ、また脳神経を圧迫することで眼球運動障害や複視、頭痛などが生じる場合もあります。
圧迫症状を引き起こしやすい部位
| 圧迫部位 | 主な症状 | 原因 |
|---|---|---|
| 視神経交叉 | 視野欠損、視力低下 | 腫瘍が視神経を押し上げる |
| 海綿静脈洞 | 複視、眼球運動障害 | 脳神経(III, IV, VI)が障害される |
| 側頭葉や前頭葉 | 頭痛、痙攣、認知機能の低下 | 腫瘍の大きさによる脳実質への圧迫 |
下垂体機能低下による症状
腫瘍が大きくなって下垂体本来の組織を圧迫したり、ホルモン分泌を阻害したりすると、逆にホルモン不足が生じ、二次性副腎不全や二次性甲状腺機能低下などを引き起こし、倦怠感や低血圧、体重増加などの症状を伴うことがあります。
微妙な変化を見逃さない大切さ
下垂体腺腫による症状は多様であり、頭痛やわずかな視野異常、ホルモン分泌異常による体重増減、月経異常など、最初は軽微なものが多いと考えられます。
しかし放置すると、腫瘍の増大とともにより深刻な症状へ進行する可能性があるため、気になる変化があれば専門医に相談することが重要です。
原因
下垂体腺腫は「良性腫瘍」であり、悪性腫瘍のように他臓器へ転移することは稀ですが、なぜ下垂体に腺腫が発生するのかは明確にはわかっていません。
遺伝的要因や細胞増殖因子、成長因子など、いくつかの因子が複合的に関係していると推測されています。
遺伝的素因
家族性に下垂体腺腫を発症するケースは多くはありませんが、まれに多発性内分泌腺腫症(MEN1)など、特定の遺伝性疾患の一部として下垂体腺腫が発生する場合もあり、遺伝的素因が疑われるケースでは、同じ家系内で同様の腺腫や内分泌疾患が確認されることがあります。
遺伝要因が疑われるケース
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| MEN1 | 下垂体腺腫、パラ甲状腺腺腫、膵内分泌腫瘍などが同時に発生 |
| MEN2 | 甲状腺髄様がんや褐色細胞腫が関与するため、下垂体腺腫は少ない |
細胞レベルの増殖因子
下垂体のホルモン分泌細胞が何らかの遺伝子異常をきっかけに過剰増殖し、腺腫を形成するケースも考えられています。
これには細胞周期をコントロールする遺伝子や、細胞増殖を促す遺伝子の変異が関わっていると推測されますが、すべての下垂体腺腫で原因が特定できているわけではありません。
環境因子やホルモン刺激
直接的な環境因子が腫瘍発生と結びつくという証拠は限定的ですが、慢性的なホルモン刺激が特定の下垂体細胞を増殖させる可能性があるとも言われています。
例えば、長期にわたる甲状腺機能低下によりTSHが高水準で分泌され続けると、TSH産生細胞が過形成を起こし、やがて腺腫化するなどのメカニズムが考えられます。
病因不明なケースが多い
多くの下垂体腺腫は、はっきりとした原因が不明のままで、ある日たまたま検診や頭部MRIなどで発見されることが少なくありません。
症状が出て初めて発覚するケースも多いため、自覚症状の有無にかかわらず、頭蓋内での異常を疑う場合は検査を受けることが大切です。
下垂体腺腫の検査・チェック方法
下垂体腺腫を疑う場合には、まず視野やホルモン検査を含む総合的な評価が必要となり、その後に画像診断を行って腫瘍の存在を確定する流れが一般的で、各検査の組み合わせによって、腫瘍の大きさや位置、ホルモン分泌の状況などを詳細に把握できます。
視野検査や視力検査
マクロアデノーマの場合視神経交叉を圧迫して視野障害が出ることが多いため、視野検査(ゴールドマン視野計やハンフリー視野計など)によって視野異常の有無を確認し、視野狭窄や半盲などが見つかると、腫瘍の位置関係を推測する手がかりになります。
視機能検査リスト
- 視力測定
- 視野計測(ハンフリー視野計など)
- 眼底検査(視神経乳頭の状態評価)
- 眼圧検査(頭蓋内圧亢進の影響観察)
ホルモン検査
血液検査により、下垂体から分泌される各種ホルモンや、下垂体が刺激する他の内分泌腺のホルモン濃度を測定します。
プロラクチン、成長ホルモン、ACTH、TSHなどが代表的な測定対象となり、過剰や不足が確認された場合は腺腫の存在をより強く疑います。
画像診断(MRI・CT)
脳MRI(特に造影MRI)は下垂体腺腫の診断において有用です。
CTでもある程度は確認できますが、MRIの方が軟部組織コントラストに優れており、下垂体の小さな腫瘍や周囲構造との関係を詳細に把握しやすいです。
画像検査方法の比較
| 項目 | MRI | CT |
|---|---|---|
| 解像度 | 軟部組織コントラストに優れ精密 | 骨構造の評価には優れるが軟部組織はMRIに劣る |
| 被ばく | なし | X線による被ばくがある |
| 腫瘍識別 | 微小腺腫の検出に適している | マクロアデノーマのサイズ把握には有用 |
負荷試験や高次検査
成長ホルモンやACTHの異常を確定するためには、ブドウ糖負荷試験やデキサメタゾン抑制試験など、高次のホルモン負荷検査が行われることもあり、検査結果を踏まえ、腺腫の種類や活動度を推定し、治療方針が立てられます。
下垂体腺腫の治療方法と治療薬について
下垂体腺腫の治療は、腫瘍の大きさやホルモン分泌の有無、患者さんの症状や全身状態などを考慮して決定され、外科的切除、放射線治療、薬物治療などを組み合わせることで、腫瘍の制御やホルモン異常の改善を目指します。
薬物治療
ホルモン過剰分泌を抑える目的で、ドパミン作動薬(例:ブロモクリプチンやカベルゴリン)が使われることが多く、特にプロラクチノーマの場合には高い効果が期待されます。
また成長ホルモン産生腺腫に対して用いられるのはソマトスタチンアナログ(例:オクトレオチド)やGH受容体拮抗薬(ペグビソマント)などです。
代表的な薬物
| 分類 | 主な薬剤例 | 対象となる腺腫 | 目的 |
|---|---|---|---|
| ドパミン作動薬 | ブロモクリプチン | プロラクチノーマ | プロラクチン分泌抑制 |
| ソマトスタチンアナログ | オクトレオチド | GH産生腺腫 | 成長ホルモン分泌抑制 |
| GH受容体拮抗薬 | ペグビソマント | GH産生腺腫 | 成長ホルモン作用阻害 |
| 副腎皮質ステロイド合成阻害薬 | メチラポンなど | ACTH産生腺腫 | コルチゾール過剰を抑制 |
外科的切除
大きな腫瘍や周囲組織を圧迫している場合、外科的切除が選択されることがあり、経蝶形骨洞アプローチと呼ばれる鼻腔から下垂体へアプローチする術式が一般的で、頭蓋を大きく開くことなく腫瘍を摘出することが可能です。
ただし、腫瘍の位置や大きさによっては開頭手術が必要になる場合もあります。
放射線治療
外科的切除が難しい症例、もしくは術後残存腫瘍が確認された場合には、ガンマナイフやサイバーナイフなどの定位放射線治療が検討されることがあります。
腫瘍の増殖を抑制する目的で行われ、ホルモン過剰分泌が続く場合にも補助的に利用されます。
治療期間
下垂体腺腫の治療期間は、腫瘍の種類や大きさ、治療法、患者の個別要因によって大きく異なり、腫瘍切除を行った場合でも、ホルモン分泌状態の安定を図るために長期にわたるフォローアップが必要となるケースが多いです。
薬物治療の継続期間
ドパミン作動薬やソマトスタチンアナログなどの薬物治療を行う場合、早期にホルモン値が正常化することもありますが、その後の再発や腫瘍の再増大を防ぐために、数年単位で継続することがあります。
プロラクチノーマであれば、一定期間薬物治療を行い、ホルモン値が安定した後に減量・中止を試みる場合もありますが、長期フォローは欠かせません。
治療期間に影響する要素リスト
- 腫瘍の大きさ(マイクロ or マクロ)
- ホルモン過剰分泌の程度
- 薬に対する反応性
- 患者の全身状態や合併症の有無
外科手術後の経過
外科手術を行った場合、術後しばらくは入院が必要となりますが、経鼻的手術では入院期間が短くなる傾向があります。
その後もホルモンバランスの経過観察や画像検査が継続的に行われ、数カ月から数年にわたり腫瘍の再発や残存部位の変化をチェックすることが重要です。
外科治療と術後フォローアップ
| タイミング | 主なチェック内容 |
|---|---|
| 術後1週間以内 | 創部の状態、感染リスク管理、初期ホルモン検査 |
| 退院~1カ月 | 頭痛や視野異常など急性期合併症の有無 |
| 3カ月、6カ月後 | MRIによる腫瘍残存・再発の有無、ホルモン検査 |
| 1年以降 | 年1~2回程度の定期検査 |
放射線治療の期間と経過観察
放射線治療は1回のみで完了する定位放射線(ガンマナイフなど)から、複数回に分けて行う外部照射までさまざまですが、効果が現れるまでの期間は、数カ月以上です。
放射線治療後も、定期的に画像検査とホルモン検査を行い、腫瘍や内分泌機能を長期にわたり観察します。
下垂体腺腫薬の副作用や治療のデメリットについて
下垂体腺腫に対する治療薬は、ホルモン分泌を抑制するものや、腫瘍の増大を防ぐ目的のものが中心ですが、それぞれ副作用や使用にあたってのデメリットがあります。
また手術や放射線治療にもリスクが伴うため、治療選択の際には利点と欠点を十分に理解することが必要です。
薬物治療の副作用
- ドパミン作動薬(ブロモクリプチン、カベルゴリンなど):吐き気、めまい、便秘、血圧低下などが生じる場合があります。投与量の調整や使用時期によって症状が軽減されることも多く、医師の指導が大切です。
- ソマトスタチンアナログ(オクトレオチドなど):消化器症状(下痢や便秘など)や胆石形成などが報告されています。
- GH受容体拮抗薬(ペグビソマント):肝機能障害や注射部位反応などに注意が必要で、定期的な血液検査が望まれます。
| 薬剤名 | 代表的な副作用 | 対応策 |
|---|---|---|
| ブロモクリプチン | 吐き気、めまいなど | 徐々に増量し、食後投与などで軽減可能 |
| カベルゴリン | 低血圧、倦怠感 | 血圧モニタリング、症状あれば減量を検討 |
| オクトレオチド | 腹部痛、下痢、胆石形成 | 定期的な腹部エコー検査、症状観察 |
| ペグビソマント | 肝機能障害、注射部位炎症 | 血液検査による肝機能モニタリング |
手術や放射線治療のリスク
- 手術のデメリット:全身麻酔によるリスク、重要構造への損傷、術後感染など。経鼻的アプローチでは侵襲が比較的少ないとされますが、腫瘍の位置やサイズによっては再発率や合併症が変動します。
- 放射線治療の副作用:放射線照射により正常組織への影響が懸念され、ホルモン分泌の低下や神経障害などを引き起こす可能性があります。ガンマナイフなどの定位放射線治療では周辺組織への影響が最小限に抑えられる利点がありますが、長期的なモニタリングは不可避です。
ホルモンバランスの崩れ
治療によってホルモン分泌が急激に変化する場合、体内のホルモンバランスが乱れ、倦怠感や倦うつ、体重の増減などの症状が出ることがあります。
特に腫瘍切除による下垂体機能低下や、薬による過度なホルモン抑制には注意が必要で、定期的な血液検査などで変動を監視することが大切です。
下垂体腺腫の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
検査費用の目安
血液検査(ホルモン測定)、MRI検査、視野検査などを組み合わせると、複数回の来院が必要となることが多いです。保険適用後の実際の金額としては、数千円から数万円程度になるケースが一般的ですが、検査の種類や回数次第で変動します。
検査と費用例の概略リスト
- 血液ホルモン検査:保険適用後1回あたり数千円
- MRI検査:保険適用後1回数千円~数万円程度
- 視野検査:数百円~数千円程度(医療機関や検査内容により異なる)
手術や放射線治療の費用
経鼻的手術の場合、入院費や手術室利用費などを合わせると、保険適用後でも数十万円規模の負担が発生する可能性があります。
放射線治療(ガンマナイフなど)は1回の照射で高額になるケースもありますが、保険適用が認められている範囲で受けることが可能です。
治療費目安の比較
| 治療法 | 保険適用後の費用目安 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 経蝶形骨洞下垂体手術 | 数十万円程度 | 入院日数や術式により大きく変動する |
| 放射線治療(ガンマナイフ等) | 数十万円程度(1回照射の場合) | 再照射が必要な場合あり |
| 薬物治療 | 毎月数千円~数万円(薬剤による) | 処方される薬剤や組み合わせで変わる |
以上
参考文献
Molitch ME. Diagnosis and treatment of pituitary adenomas: a review. Jama. 2017 Feb 7;317(5):516-24.
Lake MG, Krook LS, Cruz SV. Pituitary adenomas: an overview. American family physician. 2013 Sep 1;88(5):319-27.
Ezzat S, Asa SL, Couldwell WT, Barr CE, Dodge WE, Vance ML, McCutcheon IE. The prevalence of pituitary adenomas: a systematic review. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society. 2004 Aug 1;101(3):613-9.
Melmed S, Kaiser UB, Lopes MB, Bertherat J, Syro LV, Raverot G, Reincke M, Johannsson G, Beckers A, Fleseriu M, Giustina A. Clinical biology of the pituitary adenoma. Endocrine reviews. 2022 Dec 1;43(6):1003-37.
Daly AF, Beckers A. The epidemiology of pituitary adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Sep 1;49(3):347-55.
Asa SL, Ezzat S. The cytogenesis and pathogenesis of pituitary adenomas. Endocrine reviews. 1998 Dec 1;19(6):798-827.
Johnson MD, Woodburn CJ, Vance ML. Quality of life in patients with a pituitary adenoma. Pituitary. 2003 Jun;6:81-7.
Kovacs K, Horvath E, Vidal S. Classification of pituitary adenomas. Journal of neuro-oncology. 2001 Sep;54:121-7.
Chanson P, Salenave S. Diagnosis and treatment of pituitary adenomas. Minerva endocrinologica. 2004 Dec 1;29(4):241-75.
Tritos NA, Miller KK. Diagnosis and management of pituitary adenomas: a review. Jama. 2023 Apr 25;329(16):1386-98.