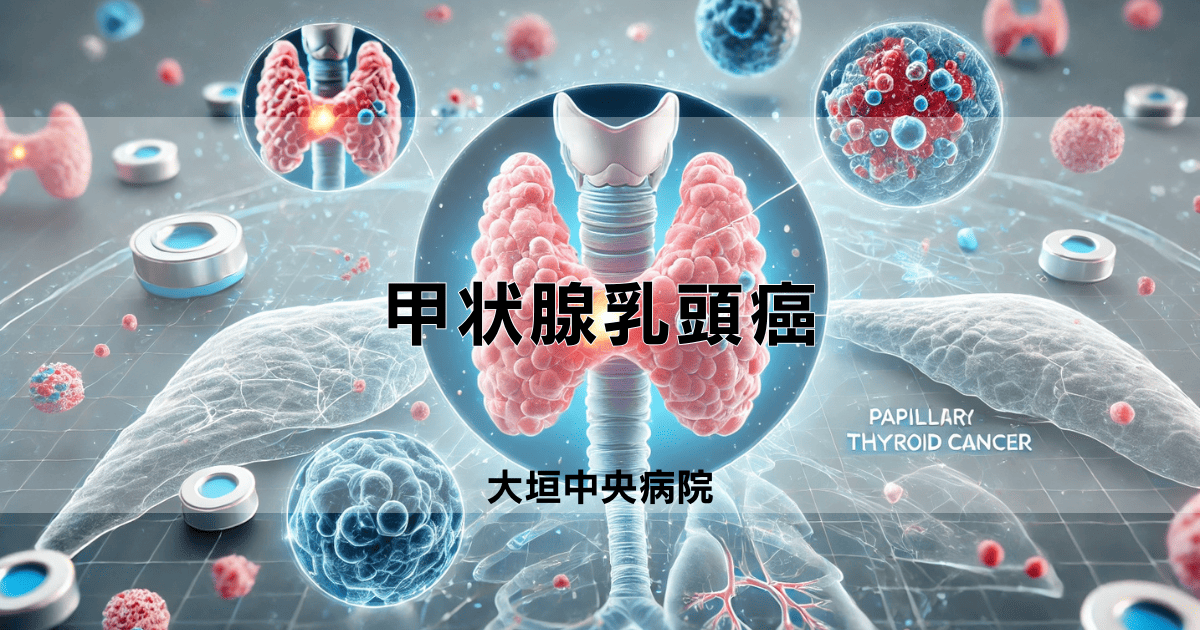甲状腺乳頭癌とは、甲状腺に発生する悪性腫瘍の中で最も多くみられる病型です。
進行がゆっくりした特徴をもち、検査を通じて早期に見つかる事例が多い一方で、病型や治療法にはさまざまな選択肢があり、正しい情報を得ることが重要です。
症状が軽度なうちから疑問を解消し、納得しながら治療を続けるために、病気に関する正確な知識や費用を含めたトータルな見通しを知ることが大切になってきます。
甲状腺乳頭癌の病型
甲状腺乳頭癌は、甲状腺がんの中で最も多いタイプに分類され、増殖の速度が比較的遅い特徴があり、同じ甲状腺乳頭癌でも、腫瘍の大きさや転移の有無によって、さまざまなリスク分類や病期が設けられています。
全体的に予後は良好な場合が多いものの、個人ごとに進行度や併発症の有無などに違いがあり、病型の把握は治療方針を考えるうえで重要です。
微小病変と進行病変の特徴
わずか数ミリメートルほどの微小な腫瘍から、数センチメートル規模に成長した進行病変まで幅広い病巣が存在し、微小病変は甲状腺の中に留まって周囲組織への影響が少ない場合が多いです。
進行病変はリンパ節への転移や周辺組織への浸潤を伴うことがあり、症状の強さや検査結果に応じて治療内容も変わってきます。発見時の腫瘍の大きさや局在位置、転移の有無が治療方針に直接関係し、その点で早期発見は非常に大切です。
甲状腺乳頭癌の大きさと病期
| 腫瘍の大きさ | 主な特徴 | 代表的な進行度合い |
|---|---|---|
| 1cm未満 | 微小がん、転移は少ない傾向 | 早期の段階、局所が中心 |
| 1~2cm | 転移リスクがやや増加 | リンパ節転移の可能性あり |
| 2~4cm | 症状が出やすくなる | リンパ節や周辺組織へ浸潤 |
| 4cm以上 | 症状が明確、合併症の恐れ | 進行期、積極的治療が必要 |
リスク分類における違い
甲状腺乳頭癌では、腫瘍の大きさや年齢、性別、浸潤や転移の有無などを考慮してリスク分類を行い、リスク分類が高まるほど、より集中的な治療や経過観察が必要となり、術後フォローの期間も長くなる傾向があります。
極めて小さな病変であれば、すぐに大がかりな治療を行わずに経過観察を続ける場合がありますが、明らかにリンパ節転移を伴う場合は外科的切除や放射性ヨウ素内用療法の導入を検討します。
治療戦略を検討する際に意識したい要素は、以下のような点です。
- 腫瘍の成長速度
- 甲状腺外への浸潤状況
- 年齢や性別によるリスク差
- 他の甲状腺疾患の併発状況
リスク分類は専門医の診察と画像検査、病理検査などを総合的に見たうえで確定します。
組織学的な特徴
甲状腺乳頭癌の組織像は、細胞核が特徴的な形を持ち、乳頭状の増殖構造がみられ、この組織学的特徴が診断の決め手となり、甲状腺細胞診や生検で乳頭状の構造が確認されると、甲状腺乳頭癌の可能性が高いです。
一方で、同じ甲状腺乳頭癌の中にも亜型があり、腫瘍の性質や悪性度が微妙に異なるケースがあります。
典型的な乳頭がん細胞とやや異なる形態を持つ「濾胞状変化」や、「高細胞密度型」などの特殊なパターンがあり、治療法の選択や経過観察の間隔が変わる場合もあります。
甲状腺乳頭癌の一部亜型
| 亜型名 | 主な特徴 |
|---|---|
| 古典型 | 乳頭状構造が顕著、最も頻度が高い |
| 濾胞状変化型 | 乳頭状よりも濾胞状の構造が多い |
| 高細胞密度型 | 細胞密度が高く、やや積極的に成長しやすい |
| 高度硬化型 | 硬化が強く、周囲組織への浸潤が見られやすい |
病型による予後の違い
予後は年齢やリスク分類、腫瘍の大きさ、転移状況などに大きく左右され、統計的には他の甲状腺がんに比べて長期生存率が高い傾向があります。
ただし、局所進行や遠隔転移がある場合は経過が長引きやすく、再発リスクも上昇するので、定期的な経過観察と適切な治療の選択が欠かせません。
特に微小病変で発見した場合は外科的治療や放射性ヨウ素内用療法などの組み合わせによって再発を防ぎやすく、長期的な健康を維持できる確率が高まります。
症状
甲状腺乳頭癌は進行が遅い場合が多く、早期段階ではあまり顕著な症状が出ない傾向があるので、検診や人間ドックなどで偶然見つかるケースも珍しくありません。
ただし、腫瘍が大きくなるに従って、首の腫れや嚥下障害、声のかすれなどが出現する可能性があります。こうした症状の有無を知っておくと、早い段階で異変に気づけることがあり、重要なポイントです。
早期症状の有無
甲状腺乳頭癌の初期には、自覚症状がほとんどないか、あってもごく軽度の違和感にとどまる場合が多いです。首の前面にわずかな腫れや張りを感じる程度で、痛みや強い違和感を訴えることは少ないといわれています。
人によってはたまたま首に手が触れた際にしこりを見つけることもありますが、多くは症状の進行とともに発見されるケースが目立ちます。
早期発見に向けて首の状態をセルフチェックするコツ
- 首の正面や甲状腺部分を定期的に触って柔らかさや腫れを確認する
- 鏡を見ながら首を上下左右に動かし、見た目の左右差を確かめる
- 声の調子や飲み込みの感覚をなんとなく意識しておく
小さなしこりの段階で気づくと、治療の幅が広がる場合が多いです。
首のしこり
甲状腺乳頭癌で最も多い症状が、甲状腺付近にできるしこりです。甲状腺は首の前側にあるため、腫瘍の発育により目で見てもわかるほど首の輪郭が変化することがあります。
触った際に硬さを感じたり、しこりが動く様子がわかったりする場合もあり、気になる症状があれば超音波検査や血液検査などで詳細を調べることが大切です。
しこりが大きいほど周囲への圧迫症状が出やすいため、腫瘍の増大が確認されたら専門医の診察を受けてください。
首に触れたときに感じるしこりと腫瘤の主な違い
| 分類 | 触ったときの特徴 | 代表的な原因例 |
|---|---|---|
| しこり(結節) | 弾力がある場合が多い | 甲状腺乳頭癌、良性結節など |
| 腫瘤 | 硬さが強く動きにくい傾向 | 悪性腫瘍や炎症性病変 |
声の変化と嚥下障害
腫瘍が声帯や気管付近を圧迫するほど大きくなると、声がかすれたり出しづらくなったりするケースがあります。
また、甲状腺周辺には気管や食道などが近接してあり、がんがこれらの組織に影響を及ぼすと呼吸苦や嚥下障害が生じることもあるので、普段とは違う違和感を感じたら放置せず、医師に相談した方が安心です。
特に声のかすれが長期間改善しないときは甲状腺や声帯近辺の病変を疑って検査を受けることが推奨されます。
声の変化や嚥下障害が出やすいタイミングとしては、以下のような状況があります。
- 大声を出した後に声がかすれたまま改善しにくいとき
- 水や食べ物が飲み込みづらく、喉につかえる感覚が継続するとき
- 喉の狭さや詰まった感覚を感じるとき
これらの症状が続く場合、甲状腺乳頭癌以外にも甲状腺炎などの可能性があります。
体のだるさや倦怠感
甲状腺機能の異常があると全身の代謝バランスに影響を及ぼし、疲れやすさや倦怠感を覚えることがあります。
甲状腺乳頭癌自体は甲状腺ホルモンの分泌に大きな乱れを引き起こさないケースが多いですが、合併症などで機能に変化が起こることも考えられます。
慢性的なだるさや体重の変動が見られた場合は血液検査を行い、甲状腺ホルモンの値を確認し、早めに対処すれば日常生活に支障をきたしにくいので、気になる症状があれば医師に申し出ることが望ましいです。
甲状腺乳頭癌の原因
甲状腺乳頭癌の具体的な原因は、一つに特定できない複合的な要素が関与しています。遺伝や放射線被曝、生活習慣など複数の因子が重なって発症リスクを高めると考えられますが、詳細をすべて解明するには至っていないのが現状です。
遺伝的要因と家族歴
家族や近親者に甲状腺がんが多い場合は、遺伝的な素因を持つ可能性が考えられ、特に甲状腺髄様癌など一部の甲状腺がんは明確な遺伝性が示されていますが、甲状腺乳頭癌に関しても家族内集積がみられるケースがあります。
遺伝子変異が存在するかどうかは専門的な検査で調べることが可能ですが、家族歴がある人は早めに定期検診を受けておくほうが安心です。
遺伝に関係するリスクを意識する際は、次のような点を検討するとよいでしょう。
- 両親や兄弟姉妹に甲状腺がんの診断歴があるか
- 遺伝子検査を受けて異常が発見されたことがあるか
- 他の内分泌疾患や自律神経系の異常が家族内にみられるか
放射線被曝の影響
子どもの頃に放射線治療を受けたり、大きな原子力事故の影響を受けたりした場合、甲状腺乳頭癌のリスクが上昇するといわれています。
特に成長期の甲状腺は放射線に対して敏感であり、被曝量が多いとがんの発症につながるリスクが高まる可能性があり、これはチェルノブイリ原発事故や福島第一原発事故の後に行われた疫学調査でも示唆されています。
ただし、通常の生活レベルで受ける放射線量は微量であり、日常的な放射線被曝だけで大きなリスク上昇が生じるとは考えにくいです。
過去に甲状腺周辺への放射線治療を行ったことがある場合や、医療現場で放射線を扱う業務に長年従事している場合は、定期検査で甲状腺の状態をチェックすることが大切です。
甲状腺乳頭癌に影響すると考えられる放射線被曝要因
| 被曝要因 | 主な具体例 | リスク度合い |
|---|---|---|
| 放射線治療 | 頭頸部がんに対する放射線治療など | 中~高 |
| 原子力事故による放射線放出 | 大規模事故の周辺住民 | 中~高 |
| 医療診断用のX線検査 | 胸部X線やCT検査など | 少~中 |
生活習慣と環境要因
食事、喫煙、ストレスなどの生活習慣も、甲状腺乳頭癌を含むがん全般のリスクに影響を及ぼします。
特にヨウ素の過剰摂取や不足が甲状腺の機能に影響する可能性があるため、日本では昆布や海苔などヨウ素を含む海藻類を日常的に摂取する食文化が甲状腺機能との関連で注目されています。
一方で、過剰摂取による甲状腺機能低下も指摘されることがあるため、偏りすぎないバランスのよい食生活が大切です。
また、ストレスが甲状腺ホルモンの分泌バランスを乱す一因になるとも考えられており、慢性的な疲労や睡眠不足は免疫力の低下と関係するといわれています。
生活習慣を整えることで発症を完全に防げるわけではありませんが、リスク管理の観点で自身の食習慣や睡眠状況を振り返ることが有益です。
複合的な要因
甲状腺乳頭癌の原因は、遺伝や放射線被曝、生活習慣などが複雑に絡み合って生じると推測され、一つのリスク要因だけで直接的に発症を決定づけるわけではなく、体質や環境が組み合わさって最終的にがん化が進行すると考えられています。
そのため、「特別なリスクがないから大丈夫」と過信するよりも、定期的な検診やセルフチェックで早期発見を心がけることが安心につながります。
複合的な要因の特徴
| 要因 | 関連度合い | コメント |
|---|---|---|
| 遺伝的素因 | 中~高 | 家族内発症例があると注意を要する |
| 放射線被曝 | 中~高 | 特に成長期の被曝に注意、リスク上昇が示唆される |
| 生活習慣・環境 | 低~中 | ヨウ素摂取やストレス、喫煙などが間接的に影響しうる |
| 加齢や性別 | 低~中 | 女性にやや多い傾向、加齢とともに発症リスクは増加 |
検査・チェック方法
甲状腺乳頭癌の疑いがある場合、初期段階での検査と診断は治療を進めるうえで大切です。検査には血液検査や画像診断、場合によっては細胞診や病理検査など多角的なアプローチが必要になります。
超音波検査(エコー)の重要性
甲状腺の形状や腫瘤の有無を調べるために、最も一般的に行う画像検査が超音波検査です。放射線の被曝がなく、リアルタイムで甲状腺の状態を観察できるため、しこりの大きさや性質をある程度把握するのに適しています。
検査は痛みが少なく、短時間で実施できる点も大きなメリットで、甲状腺内部の小さな結節まで確認できるため、甲状腺乳頭癌の早期発見につながるケースがよくあります。
超音波検査の際に医師が注目する点
- 結節の形状(円形か不整形か)
- 辺縁の境界の明瞭さ
- 内部エコーの強弱や石灰化の有無
- 周辺リンパ節の腫れ
これらの所見をもとに、甲状腺乳頭癌の可能性を評価します。
血液検査とホルモン測定
甲状腺機能を確認するために、TSH(甲状腺刺激ホルモン)やT3、T4などのホルモン値を調べる血液検査を行います。
甲状腺乳頭癌そのものがホルモン値を大きく乱すケースは多くありませんが、甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症などを合併していないかどうかを把握するうえで重要です。
また、カルシトニンやサイログロブリンといったマーカーも必要に応じて測定し、手術後の再発チェックなどに応用します。
甲状腺機能検査で測定する主な項目
| 検査項目 | 役割 | 参考値の目安 |
|---|---|---|
| TSH | 甲状腺ホルモン分泌を調節 | 約0.4~4.0μIU/mL |
| FT4 | 甲状腺ホルモンの主要成分 | 約0.9~1.7ng/dL |
| FT3 | 代謝に深くかかわるホルモン | 約2.3~4.1pg/mL |
| サイログロブリン | 甲状腺細胞由来のタンパク質の一種 | 参考値は施設による |
針生検(細胞診)と病理検査
超音波検査で怪しい結節が見つかった場合、より正確な診断のために細い針を使って細胞や組織を採取する検査(穿刺吸引細胞診や針生検)を行います。
取り出した細胞を顕微鏡で観察し、乳頭状の構造が確認されれば甲状腺乳頭癌の可能性が高まります。一時的に痛みや不快感を伴うことがありますが、診断精度が高いため、治療方針の決定に大きく寄与する検査です。
場合によっては組織を少し多めに取って病理検査を行い、詳細な組織学的特徴を調べることもあります。
針生検を行うタイミング
- 超音波検査で5mm以上の結節が疑わしく映った
- 腫瘍マーカーの値が上昇傾向にある
- 首のリンパ節が腫れていて転移が疑われる
CT、MRI、その他の画像診断
超音波検査の結果だけでははっきりしない場合や、周辺リンパ節や他の臓器への転移を詳細に確認したい場合に行うのが、CT検査やMRI検査です。
CT検査は甲状腺だけでなく胸部や上縦隔リンパ節の状態を把握しやすく、MRI検査は組織の性質や周辺組織との境界をより明確にみることができます。
診断精度をさらに高めるため、PET-CTが使われる場合もありますが、その必要性は患者さんの状況や専門医の判断によって異なります。
治療方法と治療薬について
甲状腺乳頭癌の治療は、外科的切除を中心に放射性ヨウ素内用療法や薬物療法を組み合わせることが多いです。
病気の進行度やリスク分類、患者さんの全身状態に応じて治療計画を立てる必要があり、治療方法の選択肢が豊富な点も甲状腺乳頭癌の特徴の一つといえます。
外科的治療の選択肢
甲状腺乳頭癌の治療では、甲状腺の全摘出あるいは一部切除を行う手術が主な選択肢です。
腫瘍の大きさや位置、患者さんの年齢や合併症の有無などを総合的に考慮し、甲状腺の全摘出を行うのか、もしくは患部側の片葉だけ切除するのかを決定します。
リンパ節への転移が確認されている場合は、同時にリンパ節郭清(リンパ節の切除)を行うことがあります。
外科的治療に関する主な方法
| 手術方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 全摘出 | 甲状腺を全て取り除く | 再発リスクを抑えやすい |
| 片葉切除 | 甲状腺の病変側だけを切除 | 正常な甲状腺機能が残る可能性がある |
| リンパ節郭清 | 転移がみられるリンパ節を合わせて切除 | 再発防止に役立つ |
放射性ヨウ素内用療法
甲状腺細胞はヨウ素を取り込む性質があるため、放射性ヨウ素(ヨウ素131)を使うと、甲状腺乳頭癌の残存組織や転移巣を効率的に破壊できる可能性があります。
手術後に甲状腺組織が残っている場合や、リンパ節や遠隔転移が確認された場合によく用いられる治療法です。内用療法を始める前にはヨウ素制限食をしばらく続け、甲状腺細胞が放射性ヨウ素を取り込みやすい状態を作る必要があります。
放射性ヨウ素内用療法
- 手術だけでは取りきれなかった甲状腺組織にも効果が期待できる
- 副作用として、一時的に唾液腺の痛みや炎症が出現する場合がある
- 入院して治療を行うことが多く、数日間の放射線管理が必要になる
薬物療法(分子標的薬やホルモン補充薬など)
分子標的薬は、特定の分子を標的にしてがん細胞の増殖を抑える薬であり、切除不能または再発した甲状腺乳頭癌に対して使用するケースがあります。
従来の抗がん剤に比べて副作用を比較的コントロールしやすいとされますが、下痢や倦怠感、食欲不振などの副作用がみられることもあり、使用にあたっては慎重なモニタリングが必要です。
また、手術で甲状腺を全摘出した後は、甲状腺ホルモン(レボチロキシン)の補充薬を使って体内のホルモンバランスを維持し、TSHの過剰分泌を抑え、再発リスクを下げる意味合いもあります。
ホルモン補充量は定期的な血液検査の結果に基づき調整します。
経過観察や積極的治療の判断
非常に小さい乳頭癌(1cm以下)でリスクが低い場合は、すぐに手術を行わずに経過観察を続ける選択肢も検討されます。
近年、一部の微小癌では積極的な治療を行わなくても長期間大きさが変わらないことが報告されており、患者さんの生活の質を重視する観点から経過観察を選ぶ例があります。
ただし、定期的に検査を受けて腫瘍の変化を見極める努力が必要となり、少しでも拡大傾向が確認されたら治療を始めるかどうか再検討します。年齢や健康状態を考慮したうえで、自分に合った治療戦略を立てることが大切です。
甲状腺乳頭癌の治療期間
小さな腫瘍でリスクが低い場合は短期間で手術を済ませ、その後の経過観察も比較的負担が少ないケースが多いですが、進行性の病変や再発リスクの高い場合は長期的なフォローアップが必要です。
手術と入院期間の目安
甲状腺全摘出術や片葉切除術を行うときの入院期間は、通常1週間から10日程度が一般的です。手術前後の検査や身体状態の安定化を図る目的でこの程度の入院を要し、その後は外来通院で傷の様子やホルモン補充薬の調整を行います。
実際の入院日数は病院の方針や患者の状態により前後することがあり、リンパ節郭清など大きめの手術を伴う場合はもう少し長引くケースもあります。
入院期間中に行う主な処置の流れ
- 手術前の最終検査(血液検査、心電図、胸部X線など)
- 手術当日の麻酔管理と手術後の集中管理
- 数日間の疼痛管理と合併症の確認
- 退院前のホルモン補充薬の処方と指導
放射性ヨウ素内用療法の期間
放射性ヨウ素内用療法を行う場合は、数日から1週間程度の入院が必要です。
放射性ヨウ素を内服すると体内から放射線が放出されるため、放射線管理が整った施設で行う必要があり、食事やトイレなども放射線被曝の観点から一定の制限を受けます。
治療後に体外への放射線量が基準値以下になるまで入院し、その間に唾液腺炎や甲状腺機能変動の有無を確認し、退院後も定期的に検査を受けて治療効果を評価し、再投与が必要かどうかを判断する場合があります。
放射性ヨウ素内用療法のスケジュール
| 時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 治療前2週間程度~治療直前 | ヨウ素制限食やホルモン調整 |
| 入院初日 | 放射性ヨウ素の内服、治療開始 |
| 入院中(2~7日程度) | 放射線管理エリアでの生活 |
| 退院後 | 外来フォロー、唾液腺のケアなど |
ホルモン補充治療と経過観察の期間
甲状腺を全摘出した場合は、長期的にホルモン補充薬を飲み続け、定期的に血液検査でTSHやT4、T3を測定しながら薬の量を調整し、甲状腺機能のバランスを整えます。
補充治療自体は一生涯にわたるケースが多く、外来通院で適宜フォローを受けることになり、治療期間といえる時間軸は長くなりますが、服薬管理がきちんとできていれば日常生活に支障をきたしにくいです。
ホルモン補充治療のモニタリングで重視する点
- 血液検査でのホルモン値の動き
- 身体症状(動悸、倦怠感、むくみなど)
- 再発や転移を示唆する症状の有無
再発リスクとフォローアップ
甲状腺乳頭癌は他のがんに比べて再発リスクが低いといわれますが、まったく再発しないわけではありません。
特にリンパ節転移を伴う進行病変であった場合は、術後しばらくしてから再発が見つかるケースも報告されているため、手術や放射性ヨウ素内用療法を終えた後も定期的に超音波検査や血液検査を受け、異常の有無を確認します。
フォローアップ期間は数年から10年以上にわたることがあり、患者さんの年齢や初診時のリスク分類によっても変わり、小まめに通院しながら体調管理を続けていくことが大切です。
甲状腺乳頭癌薬の副作用や治療のデメリットについて
外科手術や放射性ヨウ素内用療法、分子標的薬など、どの選択肢にも一定のリスクがありますが、それぞれの特徴を把握して対応策を考えることで、副作用を最小限に抑えながら治療を継続できる可能性が高まります。
外科手術による合併症のリスク
甲状腺の手術では、頸部の神経や血管が密集した部分を扱うため、慎重な手技が求められ、手術後に起こり得る合併症としては、声帯麻痺や低カルシウム血症などが代表的です。
甲状腺全摘出を行った場合、副甲状腺が傷ついてカルシウムの調節が乱れ、しびれや筋肉のけいれんを感じる可能性があります。
こうした症状があっても一時的な場合が多いですが、一部の患者さんは長期的にカルシウム製剤やビタミンD製剤を補う必要があります。
手術に伴う合併症やデメリット
- 声のかすれや声帯麻痺
- 一時的または持続的な低カルシウム血症
- 傷痕による頸部の違和感
- リンパ液の貯留によるむくみ感
症状の多くは時間とともに緩和する場合が多いですが、長引く場合は専門医と相談して対処法を検討します。
放射性ヨウ素内用療法の副作用
放射性ヨウ素内用療法は手術で取り切れなかった甲状腺組織やリンパ節転移への有効策として注目度が高い一方で、唾液腺や涙腺に放射性ヨウ素が取り込まれて炎症を起こすことがあります。
唾液腺炎になると、顎下の腫れや痛み、口の渇きなどを感じる可能性があり、場合によっては味覚が変化するので、必要に応じて鎮痛薬や水分摂取をこまめに行い、症状を緩和することが推奨されます。
また、甲状腺機能のコントロールが乱れる可能性があるため、治療後はホルモン測定を継続し、異常がみられたら補充薬の量を調整することが重要です。
唾液腺炎を予防するための対策
- ガムや飴を利用して唾液分泌を促す
- 水やお茶などをこまめに飲んで口腔内を潤す
- 食事の味付けをやや濃いめにして味刺激を与える
分子標的薬の副作用
分子標的薬は、再発や切除不能な甲状腺乳頭癌に使用することがあり、がん細胞の増殖シグナルを阻害する特定の分子に作用し、一般的な副作用には、下痢、食欲不振、皮膚障害、高血圧などがあります。
副作用が強いときは休薬や減量を検討して症状の改善を図ります。
分子標的薬の代表的な副作用
| 副作用 | 症状例 | 対応策 |
|---|---|---|
| 消化器症状 | 下痢、悪心、食欲不振 | 整腸剤や制吐剤の使用、水分補給 |
| 皮膚障害 | 皮疹、乾燥、かゆみ | 保湿クリームの使用、皮膚科専門医の相談 |
| 血圧上昇 | 高血圧症状(頭痛、めまいなど) | 抗高血圧薬の使用、減塩食の実施 |
| 倦怠感 | だるさや疲労感 | 休養の確保、必要に応じて休薬・減量 |
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
手術費用の目安
甲状腺を部分的に切除する片葉切除術や、全摘出術などの手術費用は、手術や麻酔の技術料、入院費などを総合して決まります。
公的医療保険を適用した後の自己負担額は、手術の種類や症状の複雑さにもよりますが、入院費を含めておよそ10万円前後になることが多いです。
リンパ節郭清など大掛かりな処置を行う場合は、追加費用が発生して合計で15万円前後になるケースもあります。
放射性ヨウ素内用療法の費用
放射性ヨウ素内用療法の場合、放射性ヨウ素薬剤の費用と入院費用を合わせた費用負担が発生し、入院期間は数日から1週間ほどが多いため、3割負担を想定した場合で総額が10万円前後になるケースがみられます。
リンパ節や遠隔転移の状況によって放射性ヨウ素の投与量が増えると、それに伴って費用も増える可能性がありますが、保険の適用範囲内で治療が行われることがほとんどです。
分子標的薬の費用
分子標的薬は高額な薬剤が多く、1か月あたりの薬剤費が10万円を超えることもありますが、保険適用による自己負担は3割となるため、7割分は公的保険がカバーします。
| 治療法 | 自己負担費用の目安 | コメント |
|---|---|---|
| 甲状腺切除術(片葉切除・全摘出) | 約10万円~15万円前後 | 手術方式と入院日数により変動 |
| 放射性ヨウ素内用療法 | 約10万円前後(入院含む) | 投与量と入院期間によって増減 |
| 分子標的薬 | 月あたり数万円~10万円超 | 薬剤の種類と投与量で大きく差が出る |
検査費や外来通院の費用
定期検査や外来通院の費用は、血液検査や超音波検査などの実施内容によって異なり、保険適用後の負担で数千円から1万円程度の範囲になることが多いです。
術後のホルモン補充薬なども月々数千円程度かかる場合がありますが、自己負担は安定した額となります。
以上
参考文献
Sosa JA, Udelsman R. Papillary thyroid cancer. Surgical Oncology Clinics. 2006 Jul 1;15(3):585-601.
Randle RW, Bushman NM, Orne J, Balentine CJ, Wendt E, Saucke M, Pitt SC, Macdonald CL, Connor NP, Sippel RS. Papillary thyroid cancer: the good and bad of the “good cancer”. Thyroid. 2017 Jul 1;27(7):902-7.
Tuttle RM, Leboeuf R, Martorella AJ. Papillary thyroid cancer: monitoring and therapy. Endocrinology and metabolism clinics of North America. 2007 Sep 1;36(3):753-78.
Caron NR, Clark OH. Papillary thyroid cancer. Current treatment options in oncology. 2006 Aug;7:309-19.
Ulisse S, Baldini E, Lauro A, Pironi D, Tripodi D, Lori E, Ferent IC, Amabile MI, Catania A, Di Matteo FM, Forte F. Papillary thyroid cancer prognosis: An evolving field. Cancers. 2021 Nov 7;13(21):5567.
Bilimoria KY, Bentrem DJ, Ko CY, Stewart AK, Winchester DP, Talamonti MS, Sturgeon C. Extent of surgery affects survival for papillary thyroid cancer. Annals of surgery. 2007 Sep 1;246(3):375-84.
McLeod DS, Sawka AM, Cooper DS. Controversies in primary treatment of low-risk papillary thyroid cancer. The Lancet. 2013 Mar 23;381(9871):1046-57.
Jonklaas J, Nogueras-Gonzalez G, Munsell M, Litofsky D, Ain KB, Bigos ST, Brierley JD, Cooper DS, Haugen BR, Ladenson PW, Magner J. The impact of age and gender on papillary thyroid cancer survival. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012 Jun 1;97(6):E878-87.
Fiore E, Vitti P. Serum TSH and risk of papillary thyroid cancer in nodular thyroid disease. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012 Apr 1;97(4):1134-45.
Lubitz CC, Sosa JA. The changing landscape of papillary thyroid cancer: epidemiology, management, and the implications for patients. Cancer. 2016 Dec 15;122(24):3754-9.