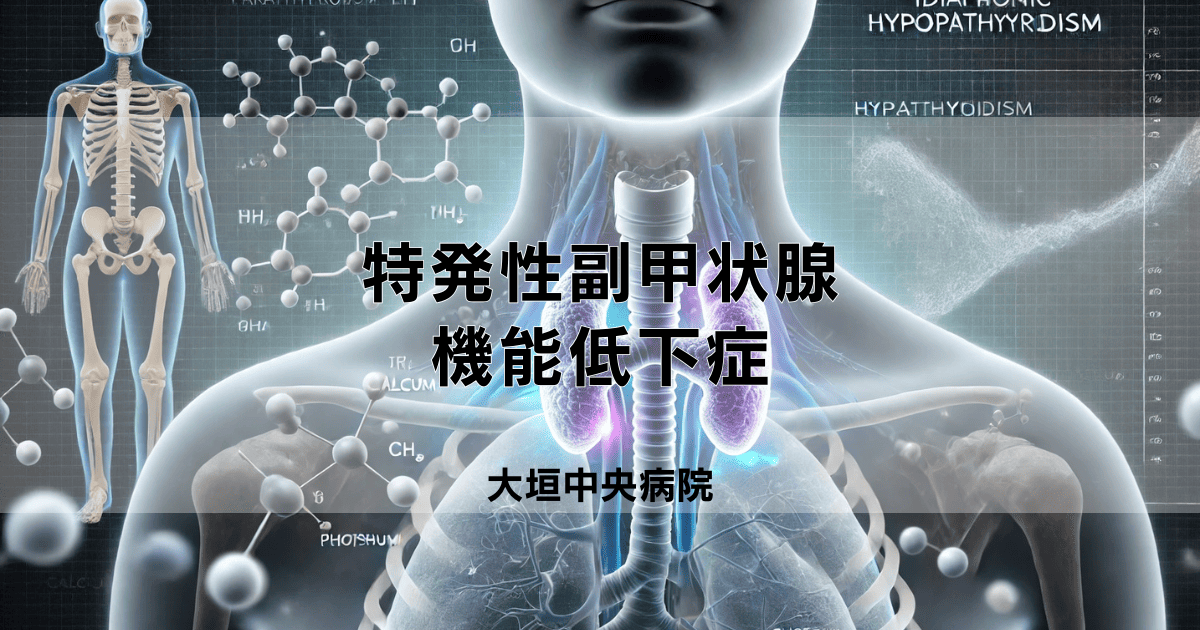特発性副甲状腺機能低下症とは、副甲状腺ホルモン(PTH)が何らかの原因で十分に分泌されず、血中のカルシウム濃度が慢性的に低下する病気です。
診断や治療開始が遅れると、しびれや筋肉のけいれん、骨や歯への影響など多岐にわたる症状が表れ、日常生活にも支障をきたすおそれがあります。
とはいえ原因がはっきりしないケースも多く、どのように治療を進めればよいか悩む方が少なくありません。
特発性副甲状腺機能低下症の病型
特発性副甲状腺機能低下症と呼ばれる病気には、いくつかの区分があります。
いずれの区分も副甲状腺ホルモンの分泌量が低下して血中カルシウム濃度が不足する点では共通していますが、その原因や臨床的特徴によって異なるタイプに分類されることがあります。
先天性のタイプ
生まれつき副甲状腺の形成異常がある場合や、免疫の発達に関連する遺伝的要因によって、先天的に副甲状腺機能が十分に保たれないタイプがあります。
出生直後から低カルシウム血症による症状がみられ、特に新生児期に筋肉のけいれんや哺乳不良、成長不良などの問題が早い段階で現れることがあり、先天性タイプの症状は軽度から重度まで幅広く、家族性に遺伝するケースもあります。
少し混乱しがちですが、先天性のタイプには腎臓の形態異常や免疫機能の不全など副甲状腺以外に問題が併発するケースもあるので注意が必要です。
出生前診断などによって事前に検出されることもあれば、幼少期のうちに筋緊張低下などで病気が疑われ、検査によって確認される場合もあります。
先天性のタイプに関連した特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 発症時期 | 新生児〜幼少期に症状が確認される場合が多い |
| 症状の現れ方 | 筋肉のけいれんや哺乳不良、成長障害など |
| 関連する遺伝性疾患 | 22q11.2欠失症候群など |
| 他の臓器への影響 | 心臓や腎臓などにも合併症が見られる場合がある |
自己免疫性のタイプ
身体が自分自身の副甲状腺を攻撃してしまう免疫反応が原因で、副甲状腺ホルモンの分泌が低下するタイプも知られています。
自己免疫性甲状腺炎や膵臓の自己免疫疾患などと併発することがあり、単独で発症するよりも多くの臓器に影響を及ぼす場合があります。
このタイプは、成人期以降に初めて低カルシウム血症の症状が発現するケースもあり、病状の経過が比較的ゆっくりなことが多いです。
ただし、症状が進むと慢性的なしびれや筋肉のけいれんを引き起こし、カルシウム補給や副甲状腺ホルモン製剤の投与が必要になります。
特発性と診断されるタイプ
明らかな遺伝的異常や自己免疫性疾患の兆候が見つからないにもかかわらず、副甲状腺ホルモンの分泌不全が起こるケースを特発性と呼ぶことがあります。
何らかの微細な遺伝変異や未解明の免疫反応がある可能性も指摘されていますが、検査を行ってもはっきりした要因を同定できないことが多いです。
特発性の場合も他の病型と同様に血中カルシウムの管理が重要で、遺伝的問題が明らかでない分、生活習慣や環境因子の影響なども検討し、症状を細かく観察していくことが求められます。
特発性と診断されるタイプにおける特徴と注意点
| 区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| 原因不明とされる理由 | 明確な免疫異常や遺伝的欠陥が見当たらない |
| 検査での発見 | 血液検査で低カルシウム血症が判明 |
| 治療方針 | 症状管理を重視しながら補充療法を検討 |
| 経過観察の必要性 | 長期的なフォローアップが重要 |
その他の稀なタイプ
過去に放射線治療を受けたことが原因となる場合や、副甲状腺を含む頸部領域への外傷が影響して機能低下を起こすケースもあります。
ほかにも遺伝子変異を伴うさまざまな先天性疾患の一症状として、稀に特発性副甲状腺機能低下症の状態が出現することがあります。
このような稀なタイプでは、複数の臓器にまたがる合併症が存在するため、幅広い観点からのアプローチが望ましいです。
特に手術歴や放射線治療歴がある場合は、医療機関でのカウンセリングと詳細な検査を受けることが治療を検討する第一歩になります。
症状
低カルシウム血症を主体とする特発性副甲状腺機能低下症では、多彩な症状が現れます。血中カルシウム濃度は、神経や筋肉の機能だけでなく、骨や歯の健康、さらに心臓の働きにも関わるため、全身的な症状に目を向けることが必要です。
しびれや筋肉のけいれん
神経や筋肉は体内のカルシウム濃度によって興奮しやすさが変化し、低カルシウム血症が継続すると、手足のしびれや不快感、さらには筋肉のけいれん(テタニー)やけいれん発作といった症状が発現しやすくなります。
特に手指や足先のしびれは、普段の生活でも気になりやすい症状のひとつです。
しびれやけいれんが起こるきっかけとしては、過換気(不安やストレスが原因で呼吸が浅く早くなる状態)や興奮などが挙げられます。
このような状況で血液のpHが変化し、いっそうカルシウムが不足している細胞内環境を顕在化させるため、症状が強まることがあります。
しびれや筋肉けいれんへの対処
- ゆっくり深呼吸をしてリラックスする
- 重度の場合は医療機関を受診し、点滴などでカルシウム補給を検討
しびれや筋肉のけいれんに関する代表的な症状と特徴
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 口周囲のしびれ | 唇や口の周囲の異常感覚が生じる |
| 手指のけいれん | チャボ手(Trousseau徴候)のように手指が硬直する |
| 足の筋肉のけいれん | 長時間立ち仕事をした際に発生しやすく歩行にも影響が出る |
| 全身性のけいれん | 意識障害を伴う重度の場合は救急対応が必要になることがある |
骨や歯への影響
副甲状腺ホルモンは骨から血液へのカルシウム移動を促す働きも担っているため、このホルモンが不足すると骨密度や歯のエナメル質に影響が及びます。
骨がもろくなると骨折しやすくなる可能性が指摘され、歯の場合は虫歯や歯周病などのリスクが高まることがあります。
カルシウム不足に伴い、身体が骨や歯の組織からカルシウムを十分に取り出せず、結果として骨の形成や歯の再石灰化が追いつかない状態になりやすいです。
成長期にこの状態が継続すると、骨格の成長や歯の形成に影響してしまう恐れがあります。
皮膚や爪への影響
特発性副甲状腺機能低下症で低カルシウム状態が続くと、皮膚や爪の変化もみられることがあり、皮膚が乾燥して硬くなり、湿疹やかゆみを伴う場合もあります。
爪に関しては、割れやすくなったり、表面がでこぼこしたりするケースがあるため、栄養補給や保湿ケアが大切です。
低カルシウム血症による皮膚症状は、自己免疫性の特発性副甲状腺機能低下症の方でより顕著になるケースも指摘されていて、ホルモンの乱れだけでなく、免疫機能の異常が皮膚に対しても影響を与えるのではないかと考えられています。
特発性副甲状腺機能低下症の原因
特発性副甲状腺機能低下症は、名前のとおり原因がはっきりしないケースも珍しくありません。ただし、病名のとおり副甲状腺自体に問題があることが多く、自己免疫や遺伝的要因、外傷や治療歴など多角的に原因を探る必要があります。
自己免疫的要因
自分の身体が誤って副甲状腺組織を異物とみなして攻撃してしまうと、副甲状腺ホルモンを産生する細胞が破壊されてしまい、機能低下を起こします。
免疫関連の疾患を持つ方や、家族に自己免疫疾患の歴史がある方では、このパターンの病型になるリスクが高いです。
免疫機能の異常は甲状腺や副腎など、ほかの内分泌器官にも及ぶことがあるため、複数の内分泌疾患が同時に発症する可能性も視野に入れなくてはなりません。
自己免疫的要因と関連があると考えられている主な疾患
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| 自己免疫性甲状腺炎 | 甲状腺ホルモンの分泌異常と併発する可能性が高い |
| 1型糖尿病 | 膵臓のβ細胞を免疫が攻撃し、インスリン分泌が低下する |
| Addison病(副腎不全) | 副腎皮質ホルモンが不足し、電解質の異常や血圧低下を引き起こす |
遺伝的要因
特発性と呼ばれつつも、一部の患者さんでは家族内に副甲状腺機能低下症がみられる場合があります。
遺伝子異常が見つかるケースでは、常染色体優性遺伝や劣性遺伝の形態をとることもありますが、必ずしも同じ症状が家族全員に現れるわけではありません。
遺伝的要因が疑われる場合、専門の医療機関で遺伝カウンセリングを受けることが有用で、将来的な対策を講じるために、家族や親戚の病歴や症状を把握することが大事です。
外傷や手術歴
頸部手術や放射線治療など、首周辺に大きな負荷がかかる医療行為を受けた後に副甲状腺機能が低下するケースがあります。
副甲状腺は甲状腺の裏側や近傍に位置しているため、甲状腺手術や甲状腺がん治療の合併症として、一時的あるいは永続的に機能が低下することがあるのです。
特発性とは少し異なるように思われるかもしれませんが、術後の経過中に炎症や免疫反応が長引いてはっきりした原因を特定できなくなる場合もあるため、結果的に特発性のカテゴリーに含まれることもあります。
手術や放射線治療による副甲状腺損傷は、早期発見と対処が重要です。
外傷や手術歴と関係しやすい状況
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| 甲状腺手術の合併症 | 手術中に副甲状腺を誤って切除したり血流が途絶する可能性 |
| 放射線治療 | 副甲状腺組織が放射線によって損傷を受ける可能性 |
| 首の外傷 | 交通事故やスポーツによる強い衝撃が副甲状腺を損傷する恐れ |
原因不明とされる場合
上記のいずれにも該当しない方、あるいは部分的に疑わしい要因がありながら決定的ではないという場合に、特発性副甲状腺機能低下症と診断されることがあります。
現在の医学では解明されていない微細な要因があると想定されますが、治療上はどのようなタイプであっても低カルシウム血症をコントロールして症状を抑えるアプローチが共通します。
原因特定が難しい場合でも、根気強い検査と日常的な症状管理が必要です。
検査・チェック方法
特発性副甲状腺機能低下症が疑われる場合、複数の検査を組み合わせて、血中カルシウム濃度の状態や副甲状腺ホルモンの分泌量、ビタミンD代謝などを総合的に評価し、血液検査の結果と臨床症状を突き合わせながら診断を進めていきます。
血液検査
診断の要となるのが血液検査です。総カルシウム値、イオン化カルシウム値、リン、マグネシウム、アルカリホスファターゼ、腎機能など、幅広い項目を評価します。
低カルシウム血症が確認されれば、次のステップとして副甲状腺ホルモン(PTH)の値を測定し、その濃度が不足しているかどうかを確かめます。
血液検査でチェックする主な項目
- 総カルシウム
- イオン化カルシウム
- リン
- 副甲状腺ホルモン(PTH)
- クレアチニン(腎機能)
- マグネシウム
イオン化カルシウム値は、カルシウムの中でも実際に生理活性を持つ成分をより正確に反映するので、総カルシウム値だけでなくイオン化カルシウム値を測定することが大切です。
血液検査の項目
| 検査項目 | 意味 |
|---|---|
| 総カルシウム | 血液中のカルシウム全体量を示す |
| イオン化カルシウム | 生理活性を持つカルシウム分画を反映 |
| リン | 副甲状腺ホルモンと逆相関関係にある可能性 |
| 副甲状腺ホルモン(PTH) | 不足しているか過剰かを判定する |
| マグネシウム | カルシウム代謝にも影響を与える電解質 |
画像診断
副甲状腺の大きさや位置、形態に異常がないかを確認するために、頸部の超音波検査(エコー)やCT、MRIなどを行うことがあります。
副甲状腺は非常に小さい臓器であり、甲状腺の後ろに埋もれるようにあるため、画像診断によって構造的な異常が見つからないケースもありますが、腫瘍や明らかな萎縮などがあれば原因を突き止める手がかりです。
自己免疫的要因の場合は、画像で異常が確認されないことが多いですが、術後の癒着や放射線治療の痕跡など、原因を探るうえで参考になる情報を得られることがあります。
骨密度検査
副甲状腺ホルモンが不足することで骨密度に影響が及ぶことがあるため、骨粗鬆症検査と同様の骨密度測定(DXAなど)を実施する場合があります。
骨密度の減少が顕著であれば、骨折リスクが高まります。早めに骨密度の変化を把握することで、カルシウムやビタミンDの補給計画の見直し、運動療法の導入など、追加の対策を考えることができます。
骨密度検査のポイント
| 検査の種類 | 特徴 |
|---|---|
| DXA(デキサ) | 腰椎や大腿骨頸部などの骨密度を測定する標準的な方法 |
| 超音波検査 | かかとなど簡易的に骨の状態をチェックできる |
| CT検査による骨密度測定 | より詳細な立体的評価が可能(一般的に費用は高め) |
遺伝子検査や自己抗体検査
先天性や自己免疫性が疑われる場合、詳しい遺伝子検査や自己抗体の有無を調べる血液検査を検討することもあり、若い世代や家族歴がある方では、遺伝子異常の有無を調べることで将来を見据えた治療計画を立てる材料になります。
自己抗体検査では、抗副甲状腺抗体の存在や自己免疫性甲状腺炎の抗体などを含めて評価し、他の自己免疫疾患との関連性を探ることが可能です。
遺伝子・自己抗体検査で調べる項目
- 特定の遺伝子変異
- 抗副甲状腺抗体
- 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
- 抗甲状腺ミクロソーム抗体
特発性副甲状腺機能低下症の治療方法と治療薬について
特発性副甲状腺機能低下症の治療では、血中カルシウム濃度を維持して症状を抑え、骨や神経、筋肉への負担を減らすことが大きな目標です。
治療には、カルシウムやビタミンDの補給が中心となり、場合によっては人工的な副甲状腺ホルモン(PTH製剤)の投与も検討されます。
カルシウム製剤の使用
血中カルシウム濃度が明らかに低い場合や症状が強い場合には、カルシウム製剤を内服あるいは静脈注射で補給します。
内服薬にはグルコン酸カルシウムや乳酸カルシウムなどのタイプがあり、食事とともに摂取することで胃腸障害を軽減しつつ吸収を促す工夫が必要です。また、急性期や重症例では点滴での投与が速やかに行われることもあります。
カルシウム製剤使用時の留意点
- 過剰投与による高カルシウム血症を防ぐために定期的に血液検査を受ける
- 経口摂取の場合は胃腸障害を起こすことがあるため、症状に応じて製剤を調整する
カルシウム製剤の一例
| 製剤名 | 用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| グルコン酸カルシウム | 内服・点滴いずれも使用可 | 過剰に投与すると高カルシウム血症 |
| 乳酸カルシウム | 主に内服で使用される | 胃腸への負担を感じる場合もある |
活性型ビタミンDの補給
カルシウムを効率よく吸収するためには、ビタミンDの働きが欠かせず、腎臓で活性化されたビタミンDは腸管からのカルシウム吸収を高める役割を担っています。
特発性副甲状腺機能低下症では、もともと副甲状腺ホルモンが不足しているため、ビタミンDが十分に活性化されないケースが多くいので、活性型ビタミンD製剤を服用し、カルシウムの吸収をサポートすることが大切です。
活性型ビタミンD製剤の代表例として、カルシトリオールやアルファカルシドールなどが挙げられますが、定期的に血中カルシウム濃度や腎機能をチェックし、投与量を細かく調整していく必要があります。
副甲状腺ホルモン(PTH)製剤
重症例や難治性の特発性副甲状腺機能低下症では、副甲状腺ホルモン製剤(テリパラチドなど)の注射を検討する場合があります。
もともと骨粗鬆症治療薬として使われるテリパラチドはPTHと類似の作用を持ち、骨に対してカルシウムを放出させやすくする作用などを示します。
ただし、長期間の使用には骨代謝への影響があり、投与期間や用量に制限が設けられることが多いです。
PTH製剤は基本的に自己注射となる場合が多く、1日1回など決められたタイミングで投与を行います。
患者さん自身が注射を継続する負担や、高カルシウム血症などのリスクを踏まえながら、専門医と相談の上で治療計画を立てることが必要です。
主に使用される治療薬
| 治療薬 | 主な効果 | 投与方法 |
|---|---|---|
| カルシウム製剤 | 血中カルシウム補給 | 内服または点滴 |
| 活性型ビタミンD製剤 | カルシウム吸収促進 | 内服 |
| PTH製剤(テリパラチド) | 骨代謝の調整、カルシウム放出促進 | 皮下注射(自己注射) |
合併症対策や補助療法
自己免疫性の場合には、免疫抑制剤や副腎皮質ステロイドを併用する選択も考慮されることがありますが、特発性副甲状腺機能低下症だけの治療でステロイドが必須となるケースは多くありません。
また、骨密度の維持や精神神経症状への対応として、運動療法やカウンセリングを組み合わせることも検討されます。
日常生活では、カルシウムとビタミンDを豊富に含む食事を心がけ、適度な日光浴や散歩などを通してビタミンDを体内で生成しやすくする工夫も役立ちます。
ただし、PTHの不足が原因である以上、食事療法のみでの改善は難しく、やはり医療機関での治療薬による補充が必要となることが多いです。
特発性副甲状腺機能低下症の治療期間
特発性副甲状腺機能低下症の治療期間は、原因や病型、症状の重症度によって大きく左右されます。先天性や自己免疫性、あるいは外科的治療の影響が残っている場合など、それぞれ個々の背景を踏まえて長期的な治療計画を組む必要があります。
急性期の対応
しびれやけいれん、ひどい倦怠感などの症状が強い急性期では、点滴や注射を使ったカルシウム補給を集中的に行い、数日から数週間である程度症状を安定させることを目標とします。
この段階で治療を受けると、症状は比較的短期間で軽快し、日常生活に復帰できるケースも多いです。
急性期の治療と目標
| 治療方法 | 目的 |
|---|---|
| カルシウム点滴 | 血中カルシウム濃度を速やかに改善 |
| 活性型ビタミンDの投与 | カルシウム吸収を強化し、症状を早期に緩和 |
| 電解質バランスの調整 | ナトリウムやマグネシウムなども補正 |
慢性期の内服管理
急性期が落ち着いた後は、慢性的に副甲状腺ホルモンが不足している状況を補うため、カルシウム製剤や活性型ビタミンDを継続的に内服するフェーズに移行します。
投与量は血液検査の結果をもとに細かく調整し、高カルシウム血症や腎機能への負担を最小限に抑えながら症状のコントロールを図ります。
慢性期は数か月から数年単位で治療を続けることが一般的ですが、症状が安定すれば通院の頻度は徐々に減らすことが可能です。
ただし、低カルシウム血症が長期化すると骨密度の低下や精神症状が繰り返し起こる可能性があるため、定期的な検査で状態を確認することが重要です。
重症・難治性の場合
自己免疫性や複数の内分泌疾患を併発しているケース、遺伝子異常の関与が疑われるケースなどでは、予後が不透明になりやすく、半永久的にホルモン補充療法を継続する場合もあります。
また、副甲状腺ホルモン製剤(PTH製剤)を使用する場合は、一定の使用期間を経過した後に投与量を見直す必要があり、その調整過程で治療期間がさらに長期化することがあります。
重症・難治性の場合に考慮される治療の特徴
- PTH製剤を自己注射で継続
- 骨密度の変化や腎機能悪化のリスクを注視
- 他の自己免疫疾患の治療との兼ね合いが必要なことがある
特発性副甲状腺機能低下症薬の副作用や治療のデメリットについて
治療によって血中カルシウム濃度をコントロールすることは欠かせませんが、その過程で薬剤の副作用や治療継続に伴う負担が発生することも事実です。
カルシウム製剤の副作用
カルシウム製剤を内服する場合、主な副作用には消化器系の不調があり、高濃度のカルシウムが消化管に負荷をかけ、吐き気や便秘、腹部膨満感などを引き起こす可能性が指摘されています。
症状がひどい場合は製剤の種類を変えたり、摂取タイミングを調整したりして対処し、また、点滴で大量のカルシウムを急速に補給すると、高カルシウム血症に陥り、頭痛や吐き気、腎機能への負荷が出る場合があります。
カルシウム製剤使用時の主な副作用
| 副作用 | 出現しやすい場面 |
|---|---|
| 吐き気 | 内服直後や濃度の高いカルシウム摂取時 |
| 便秘 | カルシウムが腸内で固まりやすくなる場合 |
| 腹部膨満感 | 多量摂取または消化機能が弱っている場合 |
| 高カルシウム血症 | 点滴投与や服用量過多で血中濃度が急上昇した場合 |
活性型ビタミンD製剤の副作用
活性型ビタミンD製剤はカルシウム吸収を増やすため、適切な量を超えて服用すると高カルシウム血症を引き起こすリスクが高まります。
また、腎機能が低下している場合には腎臓への負担が増す可能性があるので、定期的にカルシウムやリン、腎機能の数値を確認しながら服用量を調整することが大切です。
PTH製剤の副作用と負担
PTH製剤を使った治療は、骨代謝の調整を行う一方で、過剰な骨吸収を引き起こすリスクや、高カルシウム血症のリスクが伴います。自己注射が基本となるため、注射の手技習得や注射部位の皮膚トラブルに対するケアが必要です。
主な治療薬とデメリット
| 治療薬 | デメリット |
|---|---|
| カルシウム製剤 | 消化器症状、高カルシウム血症リスク |
| 活性型ビタミンD製剤 | 高カルシウム血症や腎機能への影響 |
| PTH製剤(テリパラチド) | 自己注射の手間、投与期間や骨代謝へのリスク |
特発性副甲状腺機能低下症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
カルシウム製剤と活性型ビタミンD製剤の費用
カルシウム製剤はジェネリックを含め複数の種類がありますが、1か月あたり2,000円~3,000円程度の自己負担です。
また、カルシウム製剤とビタミンD製剤を併用することが多いので、1か月あたり3,000円~5,000円程度の自己負担を目安に考えるとよいでしょう(3割負担の場合)。
| 製剤 | 使用頻度 | 1か月あたりの概算費用 (3割負担時) |
|---|---|---|
| カルシウム製剤 | 毎食後など | 2,000円~3,000円 |
| 活性型ビタミンD製剤 | 毎日 | 2,000円~4,000円 |
副甲状腺ホルモン(PTH)製剤の費用
PTH製剤は骨粗鬆症治療薬としても用いられていますが、特発性副甲状腺機能低下症の治療に使う場合も保険が適用されることがあり、1か月あたりの自己負担額が1万円以上になるケースも珍しくありません。
検査費用
特発性副甲状腺機能低下症の診断・治療の過程では、血液検査だけでも1回あたり1,000円~3,000円程度の自己負担が発生し、骨密度検査やCT、MRIなどの画像診断を組み合わせるとさらに費用が加算されます。
| 検査内容 | 頻度 | 1回あたりの自己負担(3割負担時) |
|---|---|---|
| 血液検査 | 月1~2回 | 約1,000円~3,000円 |
| 骨密度検査(DXA) | 数か月に1回 | 約2,000円~4,000円 |
| 画像検査(CT/MRI) | 必要に応じて | 約3,000円~5,000円 |
以上
参考文献
Nakamura Y, Matsumoto T, Tamakoshi A, Kawamura T, Seino Y, Kasuga M, Yanagawa H, Ohno Y. Prevalence of idiopathic hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism in Japan. Journal of Epidemiology. 2000;10(1):29-33.
Abe S, Tojo K, Ichida K, Shigematsu T, HASEGAWA T, MORITA M, SAKAI O. A rare case of idiopathic hypoparathyroidism with varied neurological manifestations. Internal medicine. 1996;35(2):129-34.
Takatani R, Kubota T, Minagawa M, Inoue D, Fukumoto S, Ozono K, Nakamura Y. Prevalence of pseudohypoparathyroidism and nonsurgical hypoparathyroidism in Japan in 2017: A nationwide survey. Journal of Epidemiology. 2023 Nov 5;33(11):569-73.
Kudoh C, Tanaka S, Marusaki S, Takahashi N, Miyazaki Y, Yoshioka N, Hayashi M, Shimamoto K, Kikuchi K, Iimura O. Hypocalcemic cardiomyopathy in a patient with idiopathic hypoparathyroidism. Internal Medicine. 1992;31(4):561-8.
Hasegawa M, Sakakibara Y, Takeuchi Y, Sugitani I, Ozono K, Castriota F, Ayodele O, Sakaguchi M. Prevalence and characteristics of postoperative and nonoperative chronic hypoparathyroidism in Japan: a nationwide retrospective analysis. JBMR plus. 2024 Sep;8(9):ziae100.
Yamamoto M, Akatsu T, Nagase T, Ogata E. Comparison of hypocalcemic hypercalciuria between patients with idiopathic hypoparathyroidism and those with gain-of-function mutations in the calcium-sensing receptor: is it possible to differentiate the two disorders?. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2000 Dec 1;85(12):4583-91.
Mizunashi K, Furukawa Y, Miura R, Yumita S, Sohn HE, Yoshinaga K. Effects of active vitamin D3 and parathyroid hormone on the serum osteocalcin in idiopathic hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism. The Journal of clinical investigation. 1988 Sep 1;82(3):861-5.
Ubara Y, Fushimi T, Tagami T, Sawa N, Hoshino J, Yokota M, Katori H, Takemoto F, Hara S. Histomorphometric features of bone in patients with primary and secondary hypoparathyroidism. Kidney international. 2003 May 1;63(5):1809-16.
Yoshioka K, Ohsawa A, Yoshida T, Yokoh S. Insulin-dependent diabetes mellitus associated with Graves’ disease and idiopathic hypoparathyroidism. Journal of endocrinological investigation. 1993 Sep;16:643-6.
Terada T, Kakimoto A, Yoshikawa E, Kono S, Bunai T, Hosoi Y, Sakao-Suzuki M, Konishi T, Miyajima H, Ouchi Y. The possible link between GABAergic dysfunction and cognitive decline in a patient with idiopathic hypoparathyroidism. Internal Medicine. 2015;54(17):2245-50.