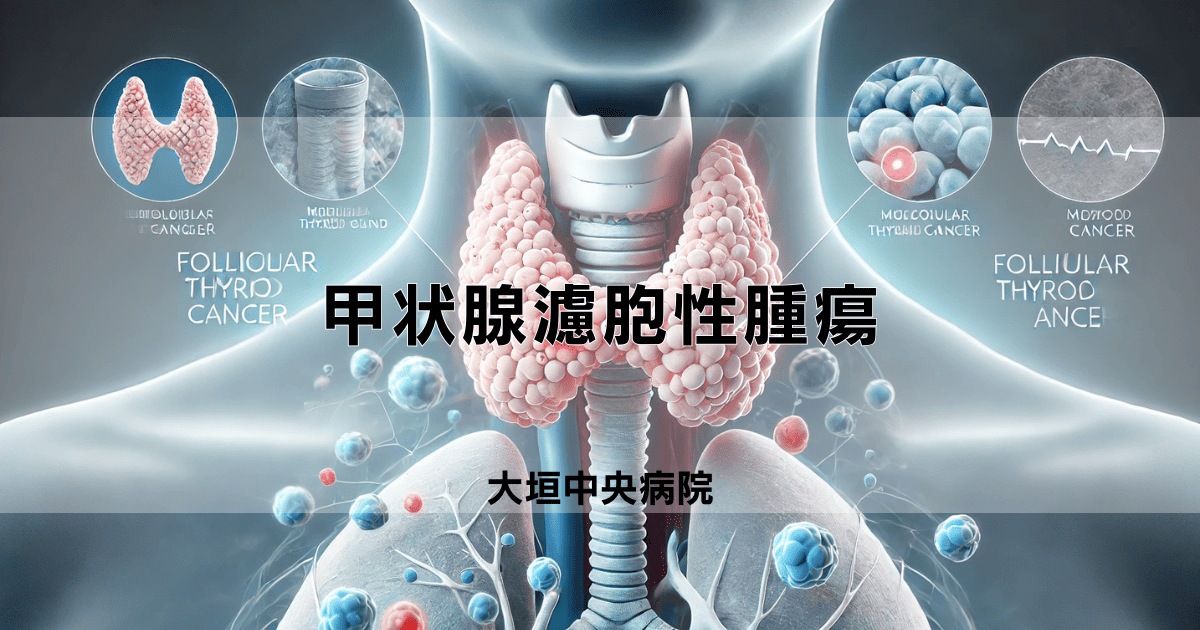甲状腺濾胞性腫瘍とは、甲状腺にできる腫瘍の一種であり、甲状腺全体の腫瘍のなかでも比較的まれなタイプに分類されます。
乳頭癌ほど頻度は高くないものの、発見が遅れると周辺組織や骨などへの転移が起こる可能性があるため、正しい診断や治療が重要です。
甲状腺は首の前面に位置し、新陳代謝やホルモンバランスを維持するうえで大切な役割を担っていて、この部位の腫瘍を疑う場合は、症状が軽微であっても医療機関に相談し、検査を受けることが望ましいです。
甲状腺濾胞性腫瘍の病型
甲状腺濾胞性腫瘍は、甲状腺を構成する濾胞細胞が異常増殖することで生じる病変ですが、腫瘍の進行度や性質によって複数の病型に分かれます。
濾胞腺腫と濾胞癌の違い
甲状腺濾胞性腫瘍を語るうえで、良性の濾胞腺腫と悪性の濾胞癌を区別することが重要です。
濾胞腺腫は良性腫瘍の1つで、一般的にはほかの組織への浸潤や転移が起こりにくいと考えられている一方、悪性の場合は濾胞癌と呼ばれ、組織の境界を越えて血管や周囲組織への浸潤が生じるリスクが高まります。
ただし画像検査だけで区別するのは難しく、病理検査(細胞診や手術後の病理組織検査)を行わないと明確に診断しにくいのが特徴です。
低侵襲型と高侵襲型
濾胞癌のなかにも、周囲組織への浸潤度合いや転移のしやすさによって、比較的進行が緩やかな型と、積極的に周囲へ侵攻する型があります。
早期発見できれば治療による良好な経過が期待できますが、発見が遅れて侵襲性の高い型だと判断された場合は、手術や放射性ヨード内用療法なども積極的に検討することが必要です。
包膜の有無と血管浸潤
濾胞性腫瘍の病理組織検査で特に注目されるのが、腫瘍を包む膜の状態と血管侵襲の有無で、腫瘍の周囲を包む膜が完全で、血管への侵入が確認されない場合は良性の可能性が高まります。
しかし、包膜を破って血管内に腫瘍細胞が入り込むと、遠隔転移(骨や肺など)を引き起こしやすいので、悪性と判定されることが多いです。
病型分類を理解する意義
甲状腺濾胞性腫瘍の病型を把握することは、診断後の治療方針や予後の見通しを立てるうえで大切です。
濾胞腺腫に近い性質であれば経過観察や部分切除で済むケースもありますが、浸潤性が強いと診断された場合は、甲状腺全摘あるいは放射性ヨード内用療法などの追加治療も考慮されます。
濾胞性腫瘍に関して確認する主な病理所見
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 包膜の有無 | 腫瘍全体を覆う膜が完全か不完全か、破壊されているかを確認 |
| 血管浸潤の有無 | 腫瘍細胞が血管の中に入り込んでいるかどうかをチェック |
| 濾胞構造の形態 | 濾胞の配列や大きさ、細胞の核の特徴などを評価 |
| 周辺組織との境界 | 腫瘍が周囲に接する状態、境界の明瞭さや不明瞭さの程度 |
包膜への浸潤や血管浸潤が確認されるかどうかで治療方針は大きく変わるため、組織検査の結果はとても大切です。
病型別の治療への影響
濾胞腺腫や低侵襲タイプの濾胞癌であれば、外科手術のみで十分治療が可能な場合もあります。
しかし高侵襲型の濾胞癌の場合は、甲状腺全摘手術の後に放射性ヨード内用療法を行うことが考えられるなど、より集中的な治療を要する可能性があります。
症状
甲状腺濾胞性腫瘍に特有の症状は目立ちにくいこともあり、見落としにつながる恐れがあり、甲状腺腫瘍全般に共通する症状を含め、濾胞性腫瘍に関連する兆候を知っておくと早期受診へのヒントです。
頚部のしこりや腫れ
甲状腺に腫瘍ができた場合、比較的初期から触れてわかるしこりや腫れが生じることがあります。
鏡を見たときに首の前面がふくらんで見えたり、飲み込む動作にあわせてしこりが上下に動くようであれば、甲状腺の異常を疑ったほうがよいかもしれません。
ただし、腫瘍の大きさが小さいときは目視や触診では判断が難しいので、定期的な検診や画像検査によるチェックが重要です。
声のかすれや飲み込みづらさ
甲状腺が大きくなると、喉周辺の組織を圧迫することで声帯や食道に影響を及ぼす場合があり、特に甲状腺の後ろ側に伸びるように腫瘍が発達すると、声のかすれ(嗄声)や飲み込みづらさ(嚥下障害)を訴える方もいます。
ただしこれらの症状は他の病気でも起こりうるため、自己判断だけで済ませず検査を受けることが大切です。
甲状腺の腫瘍が大きくなった場合にみられやすい主な症状
- 首の前側が盛り上がるように見える
- 嚥下時に圧迫感や違和感を覚える
- 声のトーンが変わったり、かすれる
- 呼吸が苦しくなる(重症例)
こうした兆候があれば、早めに医師の診察を受けてください。
ホルモン異常による全身症状
甲状腺ホルモンの分泌に異常が生じると、代謝や体温調節、心拍数、血圧などに影響が及ぶことがあります。
濾胞性腫瘍の場合でも、腫瘍の部位や大きさなどによっては甲状腺機能が変化し、甲状腺機能亢進または低下に伴い、体重減少、動悸、発汗過多、倦怠感、便秘などが起こります。
| ホルモンの変動 | 主な症状例 |
|---|---|
| 亢進 | 動悸、発汗過多、体重減少、手の震えなど |
| 低下 | 倦怠感、むくみ、体重増加、寒がり、便秘など |
ホルモン異常のサインは日常のストレスや加齢の影響でも見られることがあるため、明確な自覚症状がないまま進行するケースもあります。
転移による症状
濾胞癌が血行性転移を起こすと、骨や肺、肝臓などに腫瘍が広がる可能性があり、骨への転移では骨痛や骨折リスクの上昇、肺への転移では呼吸困難や慢性的な咳などがみられることがあります。
転移の段階まで進むと治療も複雑になるので、早期発見が望ましいです。
症状が乏しい理由
甲状腺濾胞性腫瘍の発生初期は、腫瘍が小さいため自覚症状がほとんどないケースが多く、また、乳頭癌よりも少ない頻度で発症するため、情報が行き届かず見逃されがちな一面があります。
健康診断や人間ドックでの甲状腺エコー検査などを活用して定期的にチェックすることが症状の発現前に異常を見つけるための近道です。
甲状腺濾胞性腫瘍の原因
甲状腺濾胞性腫瘍が生じる原因は単一ではなく、複数の要因が重なって発症リスクを高めると考えられています。
遺伝的な背景や放射線被曝、ヨウ素摂取量など、さまざまな因子が関与する可能性があるため、予防策を講じるには総合的な理解が大切です。
遺伝的素因
甲状腺腫瘍のなかには、家族性の背景をもつケースがあり、すべての濾胞性腫瘍が遺伝によるわけではありませんが、血縁者に甲状腺癌や他の内分泌腫瘍がみられる場合は注意が必要です。
特に多発性内分泌腺腫症(MEN症候群)の一部など、特定の遺伝子異常が引き金となって甲状腺腫瘍を含む複数の内分泌関連の病気を発症しやすいとされることもあります。
甲状腺腫瘍と関連する可能性が示唆される主な遺伝的素因
- 家族性甲状腺腫瘍(濾胞性、乳頭性などの混在)
- 多発性内分泌腺腫症(MEN)遺伝子異常
- その他のまれな遺伝疾患
ただし、遺伝子変異があっても発症には環境要因や生活習慣なども影響があります。
放射線被曝
甲状腺は放射線に対して比較的敏感であり、放射線被曝のリスクが高いと甲状腺癌全般の発症率が上昇することが知られています。
放射線治療を受けた既往や原子力事故の影響で高濃度の放射線を浴びた歴史がある場合は、甲状腺検査を定期的に行い、早期発見を目指します。
食事とヨウ素摂取
甲状腺ホルモンの材料となるヨウ素は、海藻類などに豊富に含まれ、過度のヨウ素過剰摂取、あるいは逆に極端なヨウ素不足が甲状腺の病気に影響を及ぼす可能性があります。
ただし、日本人は一般的に海藻類から十分なヨウ素を摂取していることが多く、過剰でも不足でもないバランスが取れた食事が理想的です。
| ヨウ素関連 | 例 |
|---|---|
| ヨウ素を多く含む食材 | 海苔、昆布、わかめ、ひじきなど |
| 過剰摂取の可能性 | 昆布茶や昆布エキスの過度な摂取など |
| 不足の可能性 | 海藻類をまったく食べない食生活 |
実際にヨウ素摂取量がどの程度甲状腺濾胞性腫瘍に関与しているかは明確には断定されていませんが、極端な偏食は身体全体のバランスを崩しやすいです。
加齢とホルモンバランス
甲状腺濾胞性腫瘍は中高年以降に多く見られる傾向があり、加齢による細胞増殖制御の乱れや、ホルモンバランスの変化が一因です。
また、女性は男性よりも甲状腺疾患がやや多い傾向が指摘されるため、閉経前後のホルモン変動なども影響している可能性があります。
その他の生活習慣
喫煙や過度の飲酒、肥満などの生活習慣が甲状腺腫瘍リスクを高めるかどうかは、乳頭癌に比べて濾胞癌では明確な結論が出ていない部分もあります。
しかし、生活習慣の乱れは免疫機能や体内環境のバランスを崩す要因になる可能性があるため、健康的な食事や適度な運動、ストレス管理などを心がけることが大切です。
甲状腺に良いと考えられる生活習慣
- 適度な運動を継続する
- バランスの取れた食事を心がける
- 過度な喫煙・飲酒を控える
- ストレスを溜め込みすぎない
こうした健康管理によって甲状腺を含む全身の状態を維持することは、多方面から見ても有益です。
検査・チェック方法
甲状腺濾胞性腫瘍を疑うときや、健康診断などで甲状腺に異常を指摘されたときは、より精密な検査を通じて腫瘍の有無や性質を確かめることが重要です。
画像診断や血液検査、細胞診など複数の方法があるため、医師の判断で組み合わせが行われます。
超音波(エコー)検査
甲状腺疾患のスクリーニングとして広く行われるのが超音波検査であり、首の前部にプローブを当てて甲状腺の形や大きさ、内部の構造を観察し、腫瘍があれば、その位置やサイズ、境界、エコーパターンなどを確認できます。
非侵襲的かつ痛みが少なく、短時間で済むため、初期評価には欠かせない手段です。
血液検査(甲状腺ホルモンや腫瘍マーカー)
血中の甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4など)の測定によって、甲状腺機能が亢進や低下を起こしていないかを調べます。
また、甲状腺腫瘍においてはサイログロブリン(Tg)と呼ばれる腫瘍マーカーが活用される場合があり、腫瘍を切除した後の再発チェックなどにも用いられます。
ただし、サイログロブリン値だけで良悪性を判断することはできないので、あくまで総合的な判断を行うことが大切です。
血液検査で測定することが多い項目
| 検査項目 | 主な目的 |
|---|---|
| TSH | 甲状腺刺激ホルモンの濃度を測定 |
| FT3、FT4 | 甲状腺ホルモンの分泌状態を把握 |
| サイログロブリン (Tg) | 腫瘍マーカーの一種。治療後の再発監視などに利用 |
血液検査だけでは濾胞性腫瘍の確定診断に至らないことがほとんどですが、ホルモンバランスの異常を把握するうえで重要な情報を得られます。
細胞診(穿刺吸引細胞診)
超音波ガイド下で甲状腺の腫瘍部分に細い針を刺して細胞を吸引し、顕微鏡で観察する検査です。
乳頭癌の場合は細胞診で比較的正確に良悪性を判定できることが多いですが、濾胞性腫瘍に関しては、血管浸潤や包膜への浸潤を確認しないと確定診断が難しい場合があります。
そのため細胞診では「濾胞性腫瘍の疑い」とされることが少なくありません。
穿刺吸引細胞診に関する一般的な利点と限界
- 利点:比較的低侵襲で実施でき、短時間で細胞レベルの情報を得られる
- 限界:濾胞腺腫と濾胞癌を明確に区別することは困難な場合がある
画像検査(CT、MRI、シンチグラフィ)
腫瘍の広がりや周辺組織への圧迫、転移の有無を詳しく調べるためにCTやMRIが利用され、特に濾胞癌が血行性転移を起こしやすい骨や肺などの評価には胸部CT、骨シンチグラフィなどを用いることがあります。
複数の画像検査を組み合わせることで、腫瘍の正確なステージングや手術の方針を立てやすくなります。
代表的な画像検査
| 検査種類 | 特徴 | 目的 |
|---|---|---|
| CT検査 | X線を使い断面像を撮影 | 腫瘍の大きさや周囲組織との関係、遠隔転移の有無を把握 |
| MRI検査 | 磁気を利用し体内の詳細な構造を描出 | 軟部組織の描写に優れ、神経や血管との位置関係などを評価 |
| 骨シンチグラフィ | 放射性薬剤を注射し骨の代謝を映し出す | 骨への転移状況を早期に発見しやすくなる |
病理検査による確定診断
濾胞性腫瘍を確定的に良性・悪性と診断するためには、手術で摘出した腫瘍を詳細に病理検査することが重要です。包膜や血管への浸潤が認められれば濾胞癌と診断され、そうでなければ濾胞腺腫などの良性腫瘍と考えられます。
細胞診や画像検査で「濾胞性腫瘍」と分類された時点で、医師は手術の適応などを含めて相談を進めることが多いです。
治療方法と治療薬について
甲状腺濾胞性腫瘍の治療方針は、良性か悪性か、悪性の場合はどの程度侵襲性が高いかなどに応じて決定されます。
悪性が疑われる場合や、細胞診だけでは判断がつかない場合でも、安全性を考慮して外科的な手術を優先的に検討することが一般的です。また、術後や遠隔転移がある場合には放射性ヨード内用療法などが選択される場合があります。
甲状腺部分切除術
腫瘍の位置や大きさ、性質によっては甲状腺の一部分のみを切除する方法(葉切除や部分切除)が検討され、良性の濾胞腺腫であれば、病変部位を取り除くだけで症状の改善が期待できます。
また、検体を病理検査に回して良悪性を判定し、必要に応じて追加手術を行う場合もあります。
| 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 部分切除術 | 健康な甲状腺組織を温存しやすい | 再発リスクや追加手術の可能性が残る |
| 甲状腺葉切除術 | 一葉のみ摘出し、もう片方は残すことができる | ホルモン産生能力が低下する場合は投薬が必要になることがある |
甲状腺全摘術
悪性と判明している、あるいは悪性が強く疑われる場合や、大きな腫瘍が広範囲にわたって存在する場合には甲状腺全摘術が行われることがあります。
全摘手術を行うことで残存腫瘍や再発のリスクを最小限に抑えられる一方、術後に甲状腺ホルモン補充療法が必要になる点が特徴です。
甲状腺全摘術
- 腫瘍の取り残しリスクが最小化しやすい
- 甲状腺ホルモンを産生する組織がなくなるため、生涯にわたりホルモン薬(レボチロキシン)を内服する必要がある
放射性ヨード内用療法
濾胞癌はヨウ素を取り込みやすい性質があり、これを利用した治療法が放射性ヨード内用療法です。
手術後に残存している甲状腺組織や微小転移がある場合、放射性ヨウ素を服用すると腫瘍細胞がそれを取り込んで内部から破壊される効果が期待でき、骨や肺などへの遠隔転移を抑える目的で行われます。
TSH抑制療法
手術後の再発予防や、腫瘍の増殖を抑える目的で甲状腺刺激ホルモン(TSH)の分泌を低下させる治療が行われる場合があり、レボチロキシンなどの甲状腺ホルモン製剤を服用し、下垂体からのTSH分泌を抑制する方法です。
TSHが高い状態だと甲状腺組織が刺激されて腫瘍の増殖リスクが増す恐れがあるため、投薬量を調整しながらTSHを抑制します。
| 治療法 | 主な役割や目的 |
|---|---|
| 手術(部分切除・全摘) | 腫瘍の切除による根治を目指す |
| 放射性ヨード内用療法 | 残存腫瘍や転移の制御。濾胞癌の特性を活かして腫瘍細胞に放射性ヨードを取り込ませる |
| TSH抑制療法 | ホルモン剤を服用してTSHを低下させ、腫瘍の増殖を抑える |
| レボチロキシンなどの補充療法 | 甲状腺ホルモン機能を補い、術後の代謝バランスを維持 |
化学療法や分子標的薬
濾胞癌は一般的に放射性ヨード内用療法の効果が得られやすいとされますが、なかにはヨードを取り込みにくいタイプや、進行度が高いタイプもあり、その場合は化学療法や分子標的薬の使用を検討します。
分子標的薬はがん細胞に特異的に作用するよう開発されている薬剤であり、従来の抗がん剤に比べて副作用が異なる性質をもちます。
甲状腺濾胞性腫瘍の治療期間
甲状腺濾胞性腫瘍の治療期間は、腫瘍の悪性度や病期、選択する治療法、患者の体力や年齢などによって大きく変動します。
手術の入院期間や術後の経過観察、さらに放射性ヨード内用療法を追加するかどうかなど複数の要素が関わるため、個々の事情を踏まえて計画が立てられます。
手術に要する期間
甲状腺の手術は入院治療が基本であり、手術前の検査や術後の経過観察を含めると、1週間から2週間程度を見込むケースが多いです。ただし、患者の回復状況や手術の範囲によっては入院期間が短縮されたり長期化したりすることもあります。
手術から退院までの一般的な流れ。
- 入院初日~2日目:術前検査(血液検査、画像検査など)や麻酔の説明
- 手術日:半日~1日かけて手術を行う
- 術後2日~5日:痛みの管理やドレーン管理、歩行練習などを行う
- 退院前検査:術後の合併症チェックや病理検査結果の確認
放射性ヨード内用療法の期間
濾胞癌の確定診断後、再発や遠隔転移のリスクが高いと判断された場合は手術後数週間~数か月後に放射性ヨード内用療法を行うことがあります。
放射性ヨードを服用する際は、数日間は放射線防護の観点から個室で過ごすことを求められるケースがあり、入院期間はおおむね3日から1週間程度です。
投与量によっては複数回に分けて行うこともあるため、トータルの治療期間が延びる場合があります。
術後フォローアップ
手術や放射性ヨード内用療法が完了した後も、定期的なフォローアップ(外来受診)が必要で、血液検査で甲状腺ホルモンやサイログロブリンを測定し、画像検査で再発や転移の有無を確認するという流れが一般的です。
最初は3か月~6か月ごとに受診することが多いですが、状態が落ち着いていれば1年ごとなど間隔を伸ばす場合もあります。
長期的な服薬
甲状腺を全摘した場合や機能が大きく低下した場合は、甲状腺ホルモン製剤(レボチロキシンなど)を生涯にわたって服用し、TSHの抑制や代謝バランスの維持を図ります。
服薬量は定期的な血液検査で調整し、副作用が出ない範囲で最適化することが必要で、こうした長期的なアフターケアを含めると、治療期間は数か月~数年単位で考える必要があるでしょう。
副作用や治療のデメリットについて
甲状腺濾胞性腫瘍の治療は手術が中心となりますが、補助療法や再発対策としてホルモン剤、放射性ヨード内用療法、化学療法、分子標的薬などが用いられる場合があります。
いずれも一定の副作用やデメリットがあるため、メリットとのバランスを踏まえて選択することが大切です。
甲状腺ホルモン製剤(レボチロキシン)の副作用
TSH抑制療法や甲状腺機能補充のために使用されるレボチロキシンは、過剰投与になると甲状腺機能亢進のような症状が生じることがあります。
動悸や手の震え、発汗、体重減少などが見られ、血液検査でホルモン値を確認しながら投与量を維持する必要があり、投与量が少なすぎると甲状腺機能低下の症状が残るため、定期的なモニタリングが欠かせません。
甲状腺ホルモン製剤の過不足で起こりやすい主な症状
| 状態 | 症状例 |
|---|---|
| 過剰(亢進状態) | 動悸、体重減少、多汗、手指の震えなど |
| 不足(低下状態) | 倦怠感、便秘、むくみ、寒がりなど |
放射性ヨード内用療法の副作用
放射性ヨード内用療法では、放射性物質を体内に取り込むため、一時的に唾液腺や消化管への影響が生じることがあり、唾液腺が炎症を起こして口腔内が乾燥する、味覚に異常が出るなどの訴えがみられる場合があります。
骨髄抑制による白血球や血小板の減少などが起こる可能性もあるため、治療前後は血球数のモニタリングも行われます。
化学療法・分子標的薬の副作用
通常の抗がん剤を使った化学療法では、吐き気、脱毛、倦怠感、骨髄抑制などの副作用が一般的に知られていて、一方、分子標的薬では発疹や高血圧、肝機能障害など、薬剤ごとに特有の副作用が現れやすいです。
濾胞癌のなかでも放射性ヨードが効きにくいタイプや転移が広範囲に及ぶ場合、これらの治療を検討する必要があるため、副作用への対処と適切なフォローアップが欠かせません。
化学療法や分子標的薬でみられる代表的な副作用
- 吐き気、嘔吐
- 食欲不振や体重減少
- 皮膚障害(発疹、乾燥、かゆみ)
- 疲労感、脱力感
- 下痢や便秘、口内炎
甲状腺濾胞性腫瘍の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
検査費用
甲状腺エコー検査や血液検査、細胞診などは保険適用されるため、一部負担で実施でき、初期の検査費用は数千円から数万円程度になり、腫瘍が見つかった場合はCTやMRIなどの画像検査費用も追加されます。
手術費用
甲状腺の部分切除や全摘術はいずれも外科手術となり、保険適用の範囲内で実施されることがほとんどです。手術そのものの費用は数十万円程度かかりますが、患者負担は3割前後です。
ただし、入院日数や部屋のタイプ(個室を希望する場合など)、手術の難易度などによって費用は変わります。
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 甲状腺部分切除術 | 保険適用後で10万円~15万円前後 |
| 甲状腺全摘術 | 保険適用後で15万円~20万円前後 |
| 入院管理費や検査費用 | 数万円~10万円程度 |
放射性ヨード内用療法の費用
放射性ヨード内用療法も保険適用される治療の1つであり、放射性薬剤や入院管理費を含めると、1回の治療で保険適用後の自己負担額は10万円~20万円程度です。
薬剤費
ホルモン補充や化学療法、分子標的薬などの薬剤費も基本的には保険適用で、ホルモン補充薬(レボチロキシン)は比較的安価ですが、分子標的薬など高額な薬剤の場合は自己負担分が高めになります。
| 薬剤種類 | 費用目安 |
|---|---|
| レボチロキシン | 数百円~1,000円程度(月あたり) |
| 放射性ヨード製剤 | 1回あたり数万円~10万円程度 |
| 分子標的薬 | 月あたり数万円~数十万円程度 |
以上
参考文献
Grebe SK, Hay ID. Follicular thyroid cancer. Endocrinology and metabolism clinics of North America. 1995 Dec 1;24(4):761-801.
Grani G, Lamartina L, Durante C, Filetti S, Cooper DS. Follicular thyroid cancer and Hürthle cell carcinoma: challenges in diagnosis, treatment, and clinical management. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2018 Jun 1;6(6):500-14.
Mazzaferri EL, Kloos RT. Current approaches to primary therapy for papillary and follicular thyroid cancer. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2001 Apr 1;86(4):1447-63.
DeGroot LJ, Kaplan EL, Shukla MS, Salti G, Straus FH. Morbidity and mortality in follicular thyroid cancer. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1995 Oct 1;80(10):2946-53.
Odate T, Oishi N, Vuong HG, Mochizuki K, Kondo T. Genetic differences in follicular thyroid carcinoma between Asian and Western countries: a systematic review. Gland Surgery. 2020 Oct;9(5):1813.
Kamma H, Kameyama K, Kondo T, Imamura Y, Nakashima M, Chiba T, Hirokawa M. Pathological diagnosis of general rules for the description of thyroid cancer by Japanese Society of Thyroid Pathology and Japan Association of Endocrine Surgery. Endocrine Journal. 2022;69(2):139-54.
Hirokawa M, Higuchi M, Suzuki A, Hayashi T, Kuma S, Miyauchi A. Prevalence and diagnostic significance of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features among tumors previously diagnosed as follicular adenoma: a single-institutional study in Japan. Endocrine Journal. 2020;67(10):1071-5.
Ito Y, Onoda N, Okamoto T. The revised clinical practice guidelines on the management of thyroid tumors by the Japan Associations of Endocrine Surgeons: Core questions and recommendations for treatments of thyroid cancer. Endocrine journal. 2020;67(7):669-717.
Yasumoto K, Miyagi C, Nakashima T, Baba H, Katsuta Y. Papillary and follicular thyroid carcinoma: the treatment results of 357 patients at the National Kyushu Cancer Centre of Japan. The Journal of Laryngology & Otology. 1996 Jul;110(7):657-62.
Ito Y, Hirokawa M, Hayashi T, Kihara M, Onoda N, Miya A, Miyauchi A. Clinical outcomes of follicular tumor of uncertain malignant potential of the thyroid: real-world data. Endocrine Journal. 2022;69(7):757-61.