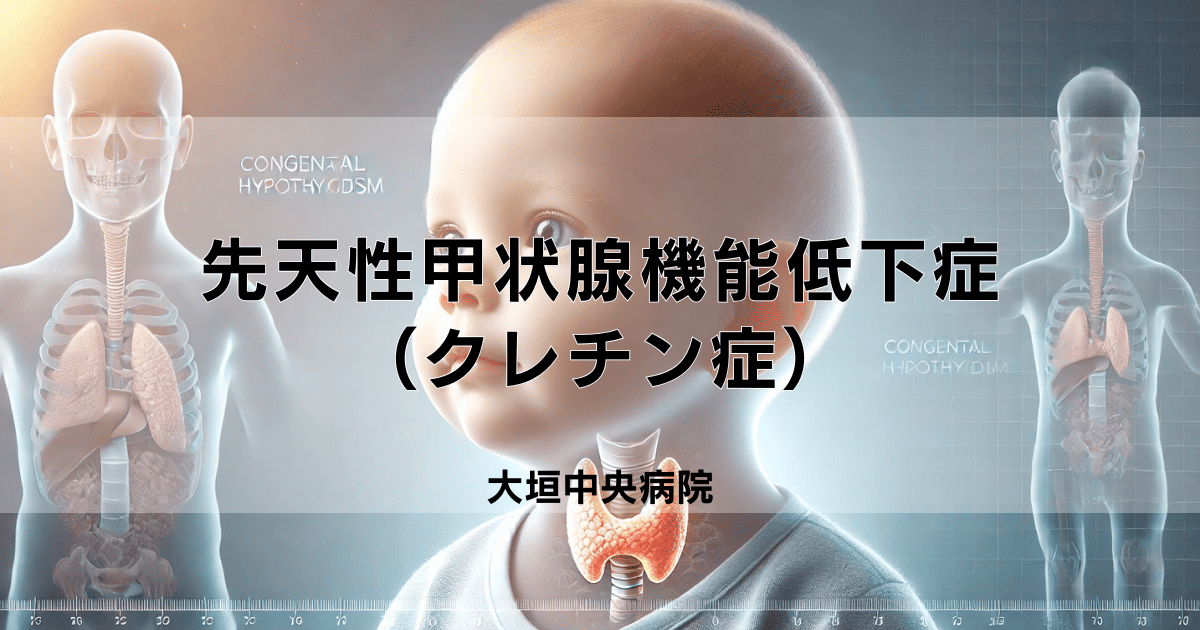先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)とは、甲状腺ホルモンの産生量や作用が生まれつき不足する状態で、新生児や乳児期からの発育や発達に影響を与える可能性がある病気です。
甲状腺ホルモンは体のさまざまな機能を助ける重要なホルモンで、心身の成長や代謝に大きくかかわっています。
早期に気づいて治療を始めると、通常の日常生活を送ることが期待できますが、放置すると学習面や身体発育にさまざまな負担がかかる場合があります。
先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の病型
先天性甲状腺機能低下症には、生まれつき甲状腺ホルモンを十分に合成できない場合や、甲状腺自体に形態異常がある場合など、多彩なタイプがあります。
体の成長や代謝調整に必要な甲状腺ホルモンが不足すると、乳児の脳や骨などの発達に大きく影響します。早期発見と早期治療が重要な理由は、病型にかかわらず、甲状腺ホルモン補充による治療が有効であるためです。
甲状腺形成異常による病型
甲状腺そのものの形態や位置に異常があると、ホルモン分泌に障害が起こりやすくなり、甲状腺が生まれつき欠損している無甲状腺症、正常の位置とは違う場所にある異所性甲状腺症、または小さな甲状腺しかない発育不全などが挙げられます。
これらは先天的に見られる主要なタイプで、出生後の検査で判明するケースが多いです。
甲状腺ホルモン合成障害による病型
甲状腺の形態は正常でも、ホルモン合成に必要な酵素やタンパク質がうまく働かないことで、十分なホルモンをつくれないこともあります。
合成障害にはさまざまな遺伝子の異常が関係し、甲状腺が小さいわけではないにもかかわらず、体に必要な量のホルモンを生産できません。
中枢性甲状腺機能低下症
脳の下垂体や視床下部に何らかの障害があることで、甲状腺ホルモンを分泌させる命令が十分に伝わらず、体がホルモン不足になるタイプです。下垂体ホルモンの分泌異常全体を含む症候群の一部として見られる場合もあります。
一過性の甲状腺機能低下
先天的な甲状腺機能低下症とは少し異なりますが、新生児期に母体の甲状腺機能異常などの影響で一時的に甲状腺ホルモン値が低下する例があり、一過性の場合は回復傾向が見られるため、専門的な検査で慎重に診断します。
病型分類のポイント
- 甲状腺そのものの形成不全や欠損でホルモン不足になる場合
- 甲状腺の形態は正常だが、合成過程の酵素異常でホルモンが作れない場合
- 脳からの指令が十分に届かず、ホルモン量が不足する場合
- 母体由来の影響で生じる一過性の低下
共通するのは甲状腺ホルモンが不足した状態である点です。
代表的な先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の病型
| 病型 | 特徴 | 原因の主な部位 |
|---|---|---|
| 甲状腺形成異常 | 甲状腺の欠損や発育不全などの形態異常 | 甲状腺組織 |
| 甲状腺ホルモン合成障害 | 甲状腺の形態は正常だが合成に必要な酵素が不足 | 甲状腺内の酵素システム |
| 中枢性甲状腺機能低下症 | 下垂体または視床下部の指令ホルモンが不足 | 脳(下垂体・視床下部) |
| 一過性の甲状腺機能低下 | 母体甲状腺機能の影響などによる一時的低下 | 母体由来の環境要因や先天的要因 |
症状
ここでは先天性甲状腺機能低下症の代表的な症状について解説します。
甲状腺ホルモンは乳児の体内で細胞分裂や代謝を活発化させる働きを担うため、それが不足すると新生児期から複数の兆候が現れることがありますが、症状が分かりづらいケースもあるため注意が必要です。
新生児期の主な症状
新生児期には、母体から受け継いだホルモンが一定期間残っているので、症状が軽度で気づきにくい場合もあり、代表的な症状としては哺乳不良や体温が低めである、元気があまりないなどが挙げられます。
長い黄疸が続く場合もあり、通常より長引く傾向がある点は見過ごせないポイントです。
乳児期の身体的な特徴
哺乳力が弱い、体重増加が遅いなどのほか、顔がむくんだようになる、肌が乾燥している、泣き声が弱々しいといった特徴もあります。便秘がちになる乳児も多く、排便間隔が長くなることでお腹の張りが気になることもあります。
成長や発達への影響
治療が遅れると、骨の成長や歯の発育が遅れやすく、身長の伸びが他の子どもに比べて遅れる場合があり、さらに知的発達や言語発達の遅れも見られる可能性があります。
甲状腺ホルモンは脳の発達に深く関わっており、特に出生後から乳児期にかけての早い段階で不足していると、学習面や行動面での影響を受けやすくなります。
日常生活の様子からの気づき
赤ちゃんの活動量や表情が乏しいように見えたり、首がすわる時期が遅いと感じたりした場合は、ほかの要因も含めて早期に医師の判断を受けると安心です。
また、肌の乾燥や低体温など、甲状腺機能低下症に特徴的とされる症状は、日常ケアの中で見つけやすい場合があります。
主な兆候
- 黄疸が長引く
- 哺乳不良や体温が低め
- 便秘や体重増加不良
- 泣き声が小さくむくみも見られる
症状には個人差があるため、疑いがあるときは専門家に相談し、検査を受けてください。
症状が確認される時期ごとの特徴
| 時期 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 新生児期 | 長引く黄疸、哺乳力の低下、体温低下など | 乳児に多い一般的症状と区別が難しい |
| 乳児期 | むくみ、便秘、肌乾燥、体重増加不良など | 育児中の観察が重要 |
| 幼児期 | 運動発達・言語発達の遅れ、体格の伸び悩みなど | 成長曲線のチェックが大切 |
| 学童期 | 学習面の遅れ、集中力不足など | 乳児期に治療していない場合に進行が目立つことも |
先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の原因
先天性甲状腺機能低下症の主な原因は、先天性の場合、生まれ持った甲状腺の形態異常や遺伝的要因が関与するケースが多いです。ただし、すべてが遺伝性とは限らず、原因不明のケースも珍しくありません。
甲状腺形成の発育異常
胎生期の甲状腺形成の段階で、甲状腺組織の位置や形態が充分に発達しないときに起こります。
甲状腺が完全に形成されない無甲状腺症のほか、通常より小さい形態をした甲状腺低形成、あるいは胸骨の近くや舌根部などに甲状腺組織が存在する異所性甲状腺などが該当します。
これらは子どもが成長するにつれて治るわけではなく、構造上の問題として残るため、出生後の検査で発見します。
甲状腺ホルモンの合成経路の異常
甲状腺でホルモンをつくる過程には、ヨウ素の取り込みからホルモン分泌にいたるまで多くの酵素が関わり、一つでも異常が生じると、ホルモン産生が円滑に行えなくなります。
特定の遺伝子変異によって起こる場合があり、兄弟や親族内で同様の症例がみられることも考えられます。
中枢神経系の指令ホルモン異常
脳の下垂体や視床下部から分泌されるTSH(甲状腺刺激ホルモン)やTRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)が不足している場合、甲状腺自体は正常でも、ホルモンの産生を促す指令が十分に行えません。
これにより二次的・三次的に甲状腺ホルモンが不足し、先天性甲状腺機能低下症の症状を起こします。
母体要因と環境要因
母親の甲状腺機能が妊娠中に低下していた場合や、免疫異常を持つ母親からの影響で胎児の甲状腺機能に影響が及ぶケースがあります。
ただし母体因子で生じるケースは、一時的に低下する一過性甲状腺機能低下であることもあるため、経過を観察しながら専門医が原因を特定します。
考えられる原因
- 胎生期の甲状腺形成異常
- 酵素異常などによる甲状腺ホルモン合成障害
- 中枢性のホルモン指令不足
- 母体の甲状腺機能や免疫異常の影響
主な原因と関係するメカニズム
| 原因タイプ | 具体例 | 発生機序 |
|---|---|---|
| 甲状腺形成異常 | 無甲状腺症、異所性甲状腺など | 胎生期における甲状腺組織の発育不全や欠損 |
| ホルモン合成障害 | 酵素欠損症、ヨウ素取り込み障害など | 合成に必要な特定の酵素が働かない |
| 中枢性ホルモン異常 | TSH・TRH分泌の不足 | 下垂体・視床下部の障害により指令ホルモン不足 |
| 母体由来・環境要因 | 母親の甲状腺機能低下など | 胎児へのホルモン供給や免疫の影響 |
原因が特定できなくても、早期に治療を進めれば予後の改善が期待できるため、診断段階での詳細な検査が大切です。
先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の検査・チェック方法
ここでは先天性甲状腺機能低下症の主な検査・チェック方法を紹介します。
早期発見をめざして、生後間もない時期に新生児マススクリーニングを行うことが日本では一般的で、その後も状況に応じて血液検査などを追加で実施し、総合的に評価していきます。
新生児マススクリーニング
生後数日以内に赤ちゃんのかかとなどから採血して、先天的な疾患の有無を一斉に調べる方法が新生児マススクリーニングです。
先天性甲状腺機能低下症もこの検査の対象となっており、血中TSHやT4(甲状腺ホルモン)濃度を測定し、ここで異常がみられた場合、確定診断を行うため、追加の血液検査を行います。
血液検査
確定診断のために、TSH、T3、T4、さらに甲状腺ホルモンの合成に関連する抗体や酵素活性などを調べ、必要に応じて、下垂体機能の検査も行い、中枢性の問題かどうかを評価します。
甲状腺関連ホルモンの値から、甲状腺ホルモン量の過不足や、ホルモン合成能の程度を判断します。
超音波(エコー)検査
首の前方にある甲状腺の位置や大きさ、形態を調べるために、超音波(エコー)検査を行い、無甲状腺症や異所性甲状腺の存在を確認できます。超音波検査は痛みも少なく、小さな子どもでも比較的負担が軽い検査です。
その他の画像検査
ホルモン合成障害や中枢性甲状腺機能低下症が疑われる場合、詳細な原因を探るためにMRIやCT検査を行うこともあります。下垂体や視床下部の形態異常を評価したいときに、脳の画像検査を組み合わせます。
検査・チェック時には、以下の項目に注目すると診断を進めやすくなります。
- 血液中のTSH値、T4値
- 首元の超音波所見(甲状腺の位置や大きさ)
- 母体の甲状腺機能や家族歴の有無
- 必要に応じた脳や下垂体の画像検査
検査内容と目的
| 検査方法 | 主な目的 | メリット |
|---|---|---|
| 新生児マススクリーニング | 早期発見 | 生後数日で判定し、早期治療につなげやすい |
| 血液検査 | 甲状腺ホルモン(T3、T4、TSH)や酵素活性の測定 | 確定診断に必要なデータを得られる |
| 超音波検査 | 甲状腺の位置や大きさ、形態異常の有無を確認 | 非侵襲的で赤ちゃんの負担が少ない |
| MRI・CT検査 | 中枢性要因のチェックや構造的異常の評価 | 脳や下垂体などの詳細を画像で把握できる |
先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の治療方法と治療薬について
先天性甲状腺機能低下症の治療では、不足する甲状腺ホルモンを補充することが中心となります。甲状腺ホルモンは体内の代謝や発育を広くコントロールしているため、早期に補充して体の機能を安定させることが大切です。
甲状腺ホルモン補充療法
レボチロキシンナトリウム(LT4)などの甲状腺ホルモン製剤を内服し、体内のホルモンバランスを整え、乳児期からの服用が必要になる場合が多く、初期の投与量は医師が体重や血液検査の結果をもとに細かく設定します。
服薬後も定期的に血液検査を行い、ホルモン濃度をモニタリングしながら投与量を調整することが重要です。
錠剤やシロップの使い分け
赤ちゃんや幼児の場合、錠剤をそのまま飲むのが難しいことがあり、粉砕できる錠剤や、溶かして飲むシロップタイプを活用するときもあります。成長に応じて服薬形態を変更し、より飲みやすい方法を選ぶと長期的な治療を続けやすくなります。
合併症や他のホルモン異常への対処
中枢性甲状腺機能低下症の場合、下垂体や視床下部の障害によってほかのホルモンにも異常が及ぶことがあり、その場合は、甲状腺ホルモンだけでなく、副腎皮質ホルモンなど他のホルモン補充治療も必要になることがあります。
いずれも専門医による総合的な診断と治療方針が大切です。
日常生活での補助的なケア
薬物療法だけでなく、発達面のサポートや栄養面のサポートなども行うと、子どもの成長を円滑に促せる可能性があります。定期検診でのフォローアップや保育・教育機関との連携も、子どもが快適に生活していくために欠かせない要素です。
甲状腺ホルモン補充療法でよく使う薬の特徴は以下の通りです。
- レボチロキシンナトリウム(LT4)が標準的な治療薬
- 体重や症状に応じて投与量を調整
- 定期的に血液検査で効果を確認
- 服用形態は粉砕可能な錠剤や液剤など複数ある
甲状腺ホルモン補充療法で使用する薬
| 薬剤名 | 特徴 | 用量調整のポイント |
|---|---|---|
| レボチロキシンナトリウム(LT4) | 甲状腺ホルモン(T4)の補充が主目的 | 血液検査(TSH、T4)を基に細かく調節 |
| リオチロニンナトリウム(LT3) | T3を補充する場合もあるが主流ではない | 特別な症例で追加的に使用することが多い |
治療期間
先天性甲状腺機能低下症の治療は、早期に始めると効果が高く、特に脳の発達が著しい乳児期から甲状腺ホルモンを補充し続けることが重要です。
病型や原因によっては、一生涯の服薬が必要になる場合と、ある程度成長してから甲状腺機能が回復し、治療が軽減する場合があります。
乳児期から学童期までの流れ
基本的には、出生後すぐに治療を開始すると脳や骨の発育への影響を小さくでき、成長の節目ごとに血液検査で甲状腺ホルモン量を確認しながら、投与量の変更が行われます。
学童期まで定期的なフォローアップを継続し、症状の改善状況をチェックすることが必要です。
一過性の場合の治療完了
母体要因などで一時的に甲状腺ホルモンが不足していただけで、後に自力でホルモンを十分に作れるようになる場合もあり、そのときは医師の判断で投与量を段階的に減らし、最終的に服用を中止することがあります。
経過観察の期間は個人差がありますが、焦らず慎重に進めることが大切です。
中枢性の場合の継続性
下垂体や視床下部に原因がある中枢性甲状腺機能低下症では、根本的にホルモンを分泌する指令が不足しているため、一生甲状腺ホルモン補充が必要になる可能性があります。
副腎皮質ホルモンや成長ホルモンなど、ほかのホルモン異常を併発している場合は、それらも同時に補充する必要があります。
定期検査の意義
治療期間中は、血液検査によるホルモン値の確認を継続的に行い、成長期では体格の変化が急速に進むため、投与量や投与方法を適宜見直します。症状が安定しているように見えても、検査なしに断薬すると再度症状が出現することがあります。
治療期間について押さえておきたいポイント
- 病型により一生続く場合と、一定期間で終了できる場合がある
- 一過性の場合、自己の甲状腺機能が改善すると治療を打ち切る可能性がある
- 定期的な血液検査とフォローアップで投与量を調節しながら進める
治療期間に影響する主な要因
| 要因 | 内容 | 治療の継続性 |
|---|---|---|
| 甲状腺形成異常の程度 | 無甲状腺症や重度の低形成など | 長期的に服薬を行うことが多い |
| 合成障害の種類 | 酵素の機能低下や遺伝的要因によるものなど | 程度により一生継続または一定期間で終了可能 |
| 中枢性甲状腺機能低下症 | 下垂体や視床下部の根本的障害 | 一生継続するケースが多い |
| 一過性の甲状腺機能低下 | 母体由来や軽度の機能低下による一時的な低下 | 改善が確認できれば、途中で治療を終了 |
副作用や治療のデメリットについて
甲状腺ホルモン補充療法は、多くの乳児や子どもにとって必要な治療ですが、薬の投与である以上、副作用や服用に伴う負担がゼロではありません。ここでは、代表的な副作用や治療上のデメリットについて触れます。
副作用の可能性
レボチロキシンナトリウム(LT4)は体内の甲状腺ホルモンと同一成分に近い薬ですが、過量投与になると心拍数の増加や落ち着きのなさ、発汗など甲状腺機能亢進症のような症状が出ることがあります。
一方で投与量が不十分だと甲状腺ホルモンの不足状態が続き、症状が改善しにくくなります。定期的な血液検査による投与量の調整で、リスクを低減することが大事です。
用量調整の煩雑さ
子どもは成長や体重増加が著しいため、薬の用量も年齢や体重に合わせて細かく変更しなければなりません。頻繁に血液検査を受け、効果と副作用をバランスよく監視しながら用量を設定する必要があります。
長期服用に伴う負担
先天性甲状腺機能低下症の多くは、長期にわたる服用が必要で、毎日の服薬管理や、定期的な医療機関への通院、血液検査などを継続するには、家族のサポートが欠かせません。
服薬をうっかり忘れるとホルモン補充が途切れ、症状の悪化につながる可能性があるため、家族で協力して治療を支える体制づくりが重要です。
ほかのホルモン異常や合併症の管理
中枢性甲状腺機能低下症など、甲状腺以外のホルモン異常を併発している場合は、服薬管理がさらに複雑です。
複数の薬を飲み分けたり、副腎皮質ホルモンなど他のホルモンも補充したりする状況では、薬同士の相互作用などに配慮する必要があります。
治療中に注意すべきポイント
- 薬を正しいタイミングと用量で与える
- 日常の変化(発熱や下痢など)があるときは医師に相談する
- 投与量過多や不足により症状が現れた場合は速やかに受診する
- 他の病気や感染症にかかったときは甲状腺ホルモンの調整が必要な場合がある
治療のデメリットと対処法
| デメリット | 対処法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 過量投与による副作用リスク | 定期的な血液検査で用量を細かく調整 | 医療者との密な連携が大切 |
| 用量調整が頻繁で、保護者の負担が大きい | 成長に合わせた検査スケジュールとフォローアップを行う | コミュニケーションによるサポート |
| 毎日の服薬管理が必要 | 服薬カレンダーやリマインダーを使用 | 忘れた場合は次の受診時に医師へ相談 |
| 他のホルモンや合併症がある場合の複雑な治療管理 | 内分泌専門医との連携で統合的に治療を行う | 複数の医療情報を共有・管理する必要がある |
先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
先天性甲状腺機能低下症の診察や血液検査、甲状腺ホルモン薬(レボチロキシンナトリウムなど)は、基本的に健康保険の適用対象です。
検査費用の目安
血液検査は、検査項目の数や医療機関の設定によって異なるものの、保険適用後の自己負担分がおよそ1,000〜2,000円程度になるケースが多いです。超音波検査も保険適用内に含まれるため、検査料の自己負担は数百円から数千円程度になります。
MRIやCTを追加で行うとやや費用が上がりますが、これも保険適用になるため、自己負担額は通常の範囲内に収まります。
治療薬の費用
甲状腺ホルモン薬は長期服用する場合が多いですが、医療保険が適用されていれば、月々数百円から数千円程度の自己負担で済むことが一般的です。
治療にかかる主な費用目安
| 費用項目 | 保険適用後の自己負担目安(1〜3割負担) | 備考 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 約1,000〜2,000円 | 項目数や医療機関によって変動 |
| 甲状腺ホルモン薬 | 月々数百円〜数千円程度 | 処方量や処方期間により変動 |
| 超音波検査 | 数百円〜数千円程度 | 保険適用により大きな負担にはなりにくい |
| MRI・CT検査 | 数千円〜1万円程度になる可能性 | 画像検査の種類や項目数による |
以上
参考文献
Rastogi MV, LaFranchi SH. Congenital hypothyroidism. Orphanet journal of rare diseases. 2010 Dec;5:1-22.
Wassner AJ. Congenital hypothyroidism. Clinics in perinatology. 2018 Mar 1;45(1):1-8.
Park SM, Chatterjee VK. Genetics of congenital hypothyroidism. Journal of medical genetics. 2005 May 1;42(5):379-89.
Agrawal P, Philip R, Saran S, Gutch M, Razi MS, Agroiya P, Gupta K. Congenital hypothyroidism. Indian journal of endocrinology and metabolism. 2015 Mar 1;19(2):221-7.
LaFRANCHI ST. Congenital hypothyroidism: etiologies, diagnosis, and management. thyroid. 1999 Jul;9(7):735-40.
Grüters A, Krude H. Detection and treatment of congenital hypothyroidism. Nature Reviews Endocrinology. 2012 Feb;8(2):104-13.
Cherella CE, Wassner AJ. Congenital hypothyroidism: insights into pathogenesis and treatment. International journal of pediatric endocrinology. 2017 Oct 2;2017(1):11.
Rovet JF. Congenital hypothyroidism: long-term outcome. Thyroid. 1999 Jul;9(7):741-8.
Rose SR, Wassner AJ, Wintergerst KA, Yayah-Jones NH, Hopkin RJ, Chuang J, Smith JR, Abell K, LaFranchi SH, Bethin KE, Brodsky JL. Congenital hypothyroidism: screening and management. Pediatrics. 2023 Jan 1;151(1).
Jain V, Agarwal R, Deorari AK, Paul VK. Congenital hypothyroidism. The Indian Journal of Pediatrics. 2008 Apr;75:363-7.