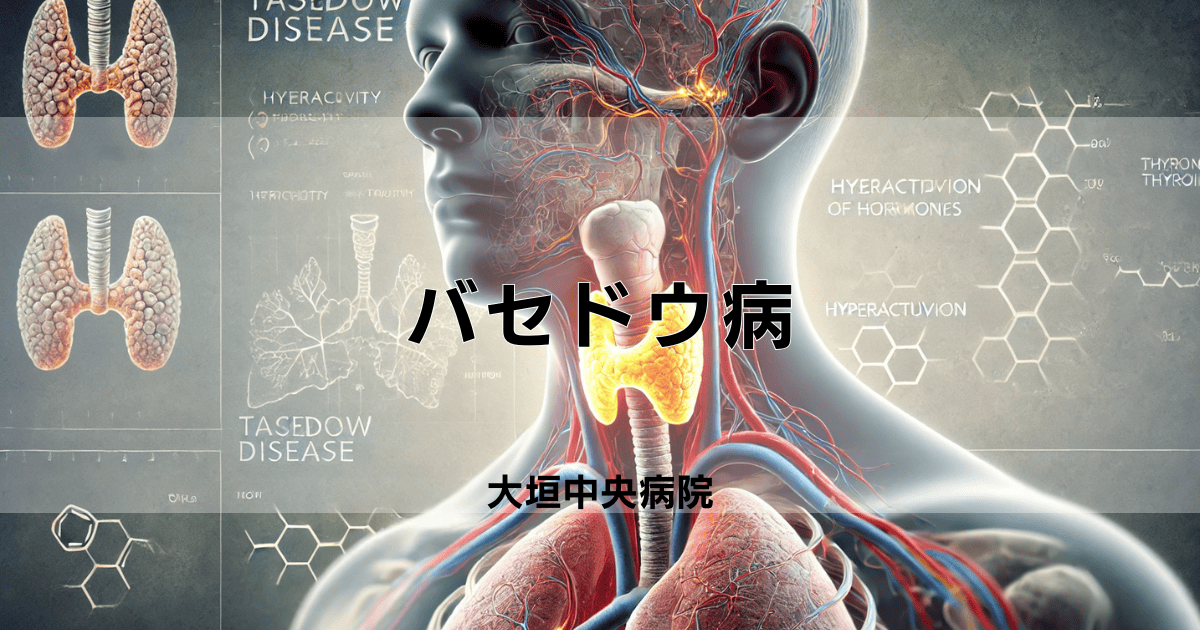バセドウ病とは、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることによって全身の代謝が亢進し、動悸・発汗・体重減少・目の突出などの多彩な症状を引き起こす疾患です。
比較的若い世代、とりわけ女性に多いという特徴があり、自己免疫の異常が関連し、命に関わる病気ではありませんが、治療せずに放置すると心臓や骨などに負担がかかり、日常生活を困難にします。
早期に症状を把握し、適切な検査・診断・治療を行うことで、より良い体調や生活の質を保ちやすくなります。
バセドウ病の病型
バセドウ病は甲状腺ホルモンの過剰分泌、すなわち甲状腺機能亢進症をもたらす代表的な疾患で、同じ甲状腺機能亢進症の中でも原因や症状の程度により複数の病型があり、それぞれアプローチが異なります。
甲状腺機能亢進症全般との関係
バセドウ病以外にも、甲状腺の過剰活動状態(甲状腺機能亢進症)は他の疾患でも起こりえますが、バセドウ病は自己免疫反応により甲状腺を刺激する自己抗体が作られることで甲状腺ホルモンが大量に放出されるのが特徴です。
自己免疫疾患としての分類
バセドウ病は自己免疫疾患に分類され、体内で作られる自己抗体によって甲状腺が刺激され、ホルモン産生が過剰になります。
通常、自己抗体は体の組織を攻撃して機能を阻害するイメージがあるものの、バセドウ病では逆に甲状腺を駆り立ててしまう点が他の自己免疫疾患とは異なります。
軽症・中等症・重症
甲状腺ホルモン値や症状の強さによって、軽症から重症まで段階的に病状が整理される場合があります。
軽症の段階であれば、ホルモン値の僅かな上昇に留まるため日常生活に大きな支障はありませんが、重症になると心拍数の著しい上昇や精神神経症状などが顕著に現れ、早急な治療が必要です。
再発や寛解の可能性
バセドウ病は長期的に経過を観察する必要がありますが、薬の効果や時間の経過によってホルモン産生が正常化(寛解)することもあります。
ただし、その後に再発する例も少なくないため、治療を中断する際は担当医に相談することが重要です。
バセドウ病の主な病型と特徴
| 病型 | 特徴 | 治療のポイント |
|---|---|---|
| 軽症 | 甲状腺ホルモン値が軽度の上昇 | 内服薬を少量から開始する |
| 中等症 | 動悸・多汗・疲労感などの日常生活への影響が大きい | 薬の増量・適切な合併症チェックが必要 |
| 重症 | 心拍数の顕著な上昇、体重減少、精神症状など | 早急な内科的治療や場合によっては手術・アイソトープ治療など |
症状
バセドウ病では甲状腺ホルモンの過剰分泌により多彩な症状がおこり、身体の新陳代謝が亢進することで生じる症状が顕著です。
身体的な症状
- 動悸や息切れ:安静時でも心臓がドキドキと早く脈打つ感覚
- 発汗過多・暑がり:体内の代謝が高まり、汗をかきやすくなる
- 体重減少:食欲が旺盛でも代謝が活発化し、体重が落ちやすい
- 震え・手指の振戦:緊張時の手の震えが常時起こりやすい
- 疲労感・筋力低下:活動性が増す反面、筋肉が疲れやすくなる
精神・神経症状
- 落ち着きがなくなる・イライラ:精神が高ぶりやすく情緒不安定
- 不眠:興奮状態が続き、睡眠障害を招く
- 注意力散漫:集中力が続かず、作業効率が低下する
眼症状(バセドウ眼症)
- 眼球突出:甲状腺自己抗体による炎症性変化が眼窩周囲組織にも及び、眼球が突出する
- まぶたの腫れ:眼周囲の組織浮腫や炎症でまぶたが厚ぼったくなる
- 眼痛・涙が出やすい:乾燥感や刺激感など不快症状が出る
症状が出やすい部位
- 心臓(動悸、頻脈など)
- 筋肉(筋力低下、疲れやすさ)
- 自律神経(発汗、イライラ)
- 目(突出、違和感)
- 皮膚(汗、湿り気)
症状の強弱と個人差
バセドウ病の症状は人によって強弱があり、初期の段階では「少し動悸がする」「最近イライラしやすい」程度であることも少なくありません。
自覚症状だけでは他の疾患と間違いやすいため、違和感が続く場合は早めに専門医への受診を検討してください。
よく見られる症状と原因
| 症状 | 原因 |
|---|---|
| 動悸・息切れ | 甲状腺ホルモン過多による心拍数・代謝の上昇 |
| 体重減少 | カロリー消費増加とエネルギー需要の高まり |
| 眼球突出 | 眼窩周囲組織への炎症、抗体による浮腫、組織増殖 |
| イライラ・不眠 | 交感神経優位による興奮状態 |
| 多汗・暑がり | 基礎代謝亢進による体温上昇と発汗増加 |
バセドウ病の原因
バセドウ病は自己免疫疾患に分類され、甲状腺を刺激する抗体(TSH受容体抗体:TRAbなど)が作られることで甲状腺ホルモンが過度に産生され、このような自己免疫の仕組みには、遺伝的要因や環境的要因が絡みます。
自己免疫と抗体のメカニズム
本来、体の免疫系は細菌やウイルスのような外敵を排除しますが、自己免疫疾患の場合、免疫系が自分自身の臓器や組織を標的にしてしまいます。
バセドウ病ではTSH受容体に対して刺激的に働く抗体が生成され、それが甲状腺を過剰に動かす結果、甲状腺ホルモンが必要以上に分泌されるのです。
自己免疫に影響を与える要因
- 遺伝的素因
- ウイルス感染による免疫暴走
- ストレスや生活習慣の乱れ
- ホルモンバランスの変化
遺伝との関連
家族や近親者に甲状腺疾患、自己免疫疾患を持つ人がいる場合、バセドウ病を発症しやすい傾向があり、遺伝的に自己免疫反応を引き起こしやすい体質が受け継がれていると考えられます。
しかし必ずしも全員が発症するわけではなく、環境要因との複合作用が大きいです。
環境・生活習慣との関連
食生活やストレス、喫煙などが免疫系に影響を及ぼし、バセドウ病の発症に関与する可能性が示唆されていて、特にストレスは免疫バランスを乱す要因となるため、ストレス過多の環境にいる人は注意が必要です。
発症リスクを高める可能性のある因子
| 因子 | 内容 |
|---|---|
| ストレス | 免疫系を不安定にし、抗体生成が進む可能性 |
| 喫煙 | 甲状腺ホルモンや免疫に影響を及ぼす一因となる |
| ウイルス感染 | 一時的に免疫の過剰反応を引き起こし、自己抗体を誘導 |
| ホルモンバランス | 女性ホルモンなどの変動が自己免疫反応を助長することも |
バセドウ病の検査・チェック方法
バセドウ病の診断は、血液検査での甲状腺ホルモン値や自己抗体の測定、甲状腺の超音波検査、場合によっては甲状腺シンチグラフィなどを用いて行い、精密検査を受けることでバセドウ病かどうかを確定し、重症度を判断します。
血液検査
甲状腺ホルモン(T3、T4)と甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定することで、甲状腺機能の亢進があるかどうかを確認します。
加えて、TSH受容体抗体(TRAb)や抗サイログロブリン抗体などの自己抗体価も調べ、バセドウ病ではTRAbが陽性になる例が多いです。
主な血液検査項目
- T3(トリヨードサイロニン)
- T4(サイロキシン)
- TSH(甲状腺刺激ホルモン)
- TRAb(TSH受容体抗体)
- 抗TPO抗体、抗サイログロブリン抗体など
甲状腺超音波検査
甲状腺のサイズや形状、血流量の増大などを確認でき、バセドウ病では甲状腺がびまん性に腫大して血流が増加していることが多いため、エコー(超音波)によって病変の有無や程度をある程度把握します。
シンチグラフィ
放射性ヨードやテクネチウムを用いた甲状腺シンチグラフィでは、甲状腺の取り込み率や分布を画像化し、バセドウ病では甲状腺全体が放射性元素を取り込みやすく、全体的に高い取り込み像が見られることが特徴です。
各検査の目的と特徴
| 検査 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 甲状腺ホルモン値・自己抗体の測定 | 必須の検査。異常値の組み合わせでバセドウ病を推定 |
| 甲状腺超音波 | 甲状腺の形態・血流量の確認 | 痛みがなく短時間で行える。血流増加を評価 |
| 甲状腺シンチグラフィ | 甲状腺全体の取り込み率や分布を画像化 | バセドウ病は高い取り込み。投薬前などに実施される |
自己チェックリストの活用
もし以下のような症状が続く場合、医療機関に相談してください。
- 近頃、動悸や息切れがしやすい
- 暑さに弱く汗をかきやすい
- 食欲はあるのに体重が減っている
- イライラしやすくなった
- 目が飛び出しているように感じる
バセドウ病の治療方法と治療薬について
バセドウ病の治療は、主に薬物療法・放射性ヨード内用療法・手術療法の3種類があり、それぞれ患者さんの年齢や症状、甲状腺の大きさ、合併症の有無などによって選択されるため、医師の判断が重要です。
薬物療法(抗甲状腺薬)
抗甲状腺薬として代表的なのがメチマゾール(チアマゾール)とプロピルチオウラシル(PTU)です、甲状腺ホルモンの合成を阻害し、甲状腺ホルモン濃度を正常に近づけます。
主な抗甲状腺薬
- メチマゾール(チアマゾール)
- プロピルチオウラシル(PTU)
放射性ヨード内用療法
ヨード131を経口投与することで甲状腺組織に取り込ませ、放射線によって甲状腺細胞を破壊し、過剰なホルモン産生を抑える方法です。
手術や長期の服薬を避けたい場合に選択されることがありますが、放射線被ばくや甲状腺機能低下を起こす可能性があり、妊娠中や小児に対しては制限があります。
手術療法(甲状腺切除)
甲状腺の一部または大部分を切除する手術療法は、大きく腫大した甲状腺による圧迫症状が強い場合などに考慮されます。
手術後は甲状腺機能低下が起こる可能性が高いため、甲状腺ホルモン補充が必要となる場合もあります。
治療方法の比較
| 治療方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 抗甲状腺薬 | 内服で治療できる、合併症が少ない | 長期投薬が必要になる場合が多い、薬の副作用 |
| 放射性ヨード内用療法 | 通院回数が少なく効果も高い | 一定期間放射線管理が必要、妊娠女性には適さない場合がある |
| 手術療法 | 甲状腺腫大が著しい場合に有効 | 手術リスク(麻酔、出血など)、術後の甲状腺ホルモン補充が必要な場合 |
治療の流れ
- 血液検査・画像検査で診断
- 抗甲状腺薬を用いた内科的治療の開始
- 症状や再発リスクを考慮して放射性ヨード療法・手術を検討
バセドウ病の治療期間
バセドウ病の治療期間は個人差がありますが、多くの場合で長期の経過観察や治療が求められ、抗甲状腺薬の場合、早ければ半年~1年程度で症状が落ち着き、寛解に至る方もいますが、5年以上内服が必要なケースも珍しくありません。
内科的治療の期間
抗甲状腺薬を服用している間は、定期的に血液検査を受けてホルモン値をチェックしながら薬の量を調整し、症状とホルモン値が安定し、寛解と判断されるまでには数年かかる例もあります。
治療中の通院間隔
- 治療初期は2~4週に1回程度
- 安定後は2~3か月に1回程度
- 長期フォロー時には半年に1回程度
放射性ヨード内用療法後
放射性ヨード内用療法後は、甲状腺機能が低下することがあり、その場合は甲状腺ホルモン補充薬の服用が必要で、放射線の効果が完全に出るまで数か月から半年ほどかかり、その間も定期的なホルモン値確認が大切です。
手術後
手術後のリカバリー期間は数週間ですが、長期的には甲状腺機能低下のリスクが高くなるため、甲状腺ホルモン補充が必要になる方が多いです。
また、場合によっては副甲状腺機能の低下によるカルシウム調節障害なども起こり得るため、継続的な通院が求められます。
代表的治療とおおよその期間
| 治療法 | 治療開始~症状安定 | 維持期間 |
|---|---|---|
| 抗甲状腺薬(メチマゾール) | 3~6か月である程度のコントロール | 1~5年、または更に長期 |
| 放射性ヨード内用療法 | 3か月~半年で甲状腺ホルモン正常化 | 術後の甲状腺機能低下に対する補充治療が継続的に必要な場合あり |
| 手術療法 | 数週間で術後経過観察 | 甲状腺ホルモン補充が必要な場合は終生(個人差あり) |
副作用や治療のデメリットについて
抗甲状腺薬や放射性ヨード内用療法、手術など、それぞれの治療法にはメリットだけでなく副作用やデメリットがあるので、これらを理解したうえで治療を受けることが大切です。
抗甲状腺薬の副作用
- 肝機能障害:定期的な血液検査でチェック
- 無顆粒球症:白血球の一種が著しく減少し、感染症にかかりやすくなる
- 発疹・かゆみ:アレルギー反応
放射性ヨード内用療法のリスク
- 甲状腺機能低下:治療効果で甲状腺が破壊されすぎる可能性
- 一時的な咽頭痛:治療後に痛みや違和感を覚える場合がある
- 放射性被ばくに対する抵抗感:安全は確保されているものの心理的抵抗がある
手術療法の注意点
- 手術リスク:全身麻酔のリスクや出血、声帯神経障害など
- 甲状腺ホルモン補充:過度に切除した場合、甲状腺機能低下を招く
- 副甲状腺の障害:カルシウム調節が乱れ、しびれやけいれんを起こすケースがある
| 治療法 | デメリット・注意点 |
|---|---|
| 抗甲状腺薬(メチマゾールなど) | 無顆粒球症や肝機能障害に注意、定期検査が必要 |
| 放射性ヨード内用療法 | 一時的に甲状腺機能低下を起こしやすく、再度補充療法 |
| 手術療法 | 手術のリスク、術後の甲状腺ホルモン補充、声帯神経障害など |
治療デメリットの回避
- 定期的な通院:血液検査・症状観察で早期に異変を捉える
- 適切な治療選択:生活環境や合併症の有無、患者の希望も加味する
- 充分な情報収集と主治医とのコミュニケーション:疑問や不安を解消しつつ治療を進める
バセドウ病の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
内服薬の費用
抗甲状腺薬は保険適用となっており、具体的な金額は薬の種類や量、処方期間によって異なり、メチマゾールの場合、1か月あたりの薬剤費は数千円程度です。
放射性ヨード内用療法の費用
放射性ヨードを使う内用療法も保険適用があるため、実際の治療費は自己負担割合に応じた金額で済みます。
代表的治療法と保険適用の状況
| 治療法 | 保険適用の有無 | 治療費の目安 |
|---|---|---|
| 抗甲状腺薬 | あり | 数千円/月(薬剤費) |
| 放射性ヨード療法 | あり | 数万円程度(入院・外来で異なる) |
| 手術療法 | あり | 手術費・入院費は合計で数十万円の場合も |
手術・入院費用
甲状腺摘出手術や入院が必要なケースでも、保険適用により自己負担割合で支払います。比較的大掛かりな手術の場合は費用が高額になりやすいですが、退院後の外来フォローや甲状腺ホルモン補充の費用も保険が使えます。
以上
参考文献
Nishimura M, Yamamoto T, IUIMA H, Moriwaki Y, Takahashi S, Hada T. Basedow’s disease and chronic ulcerative colitis: a case report and review of the Japanese literature. Internal medicine. 2001;40(1):44-7.
Torimoto K, Okada Y, Kurozumi A, Narisawa M, Arao T, Tanaka Y. Clinical features of patients with Basedow’s disease and high serum IgG4 levels. Internal Medicine. 2017 May 1;56(9):1009-13.
Saito T, Kawano T, Saito T, Ikoma A, Namai K, Tamemoto H, Kawakami M, Ishikawa SE. Elevation of serum adiponectin levels in Basedow disease. Metabolism. 2005 Nov 1;54(11):1461-6.
Hidaka M, Osaki M, Yamaguchi S, Sayama T, Arakawa S, Kitazono T. Fluctuations in moyamoya vasculopathy associated with basedow disease depending on thyroid hormone status. Case Reports in Neurology. 2020 Sep 22;12(2):140-7.
Ito K, Tsuchiya T, Sugino K, Murata M. An evaluation of the incidence of hyperparathyroidism after 131I treatment for Basedow disease (part II). Kaku igaku. The Japanese Journal of Nuclear Medicine. 1996 Jul 1;33(7):737-42.
Minamitani K, Sato H, Ohye H, Harada S, Arisaka O. Guidelines for the treatment of childhood-onset Graves’ disease in Japan, 2016. Clinical Pediatric Endocrinology. 2017;26(2):29-62.
Yamashita H, Noguchi S, Murakami N, Adachi M, Kato R, Kato S, Ishimatsd T, Nakayama L, Mannen K, Mifune K, Obata T. Induction of peroxidase and thyroglobulin by TSH in cultured thyroid cells from patients with Basedow’s disease and its inhibition by actinomycin D. Acta Patholigica Japonica. 1989 Feb;39(2):121-6.
Abe Y, Sato H, Noguchi M, Mimura T, Sugino K, Ozaki O, Yoshimura H, Ito K. Effect of subtotal thyroidectomy on natural history of ophthalmopathy in Graves’ disease. World journal of surgery. 1998 Jul;22:714-7.
Vargas-Uricoechea H, Bonelo-Perdomo A, Sierra-Torres CH, Meza-Cabrera I. Autoimmune thyroid disease (flajani-parry-graves-von basedow disease): Etiopathogenesis, clinical manifestations and diagnosis. Thyroid Disorders: Basic Science and Clinical Practice. 2016:61-83.
Kimura A, Horiguchi N, Yoshida K, Ishizaki M, Endo Y, Motegi SI, Sato H, Kanazashi S, Hirayama Y, Ohyama Y, Kawai-Kowase K. A case of anti-MDA5-positive clinically amyopathic dermatomyositis presenting acrodermal erythromelalgia complicated with Basedow’s disease. JOURNAL OF HOSPITAL GENERAL MEDICINE. 2024 May 31;6(3):62-7.