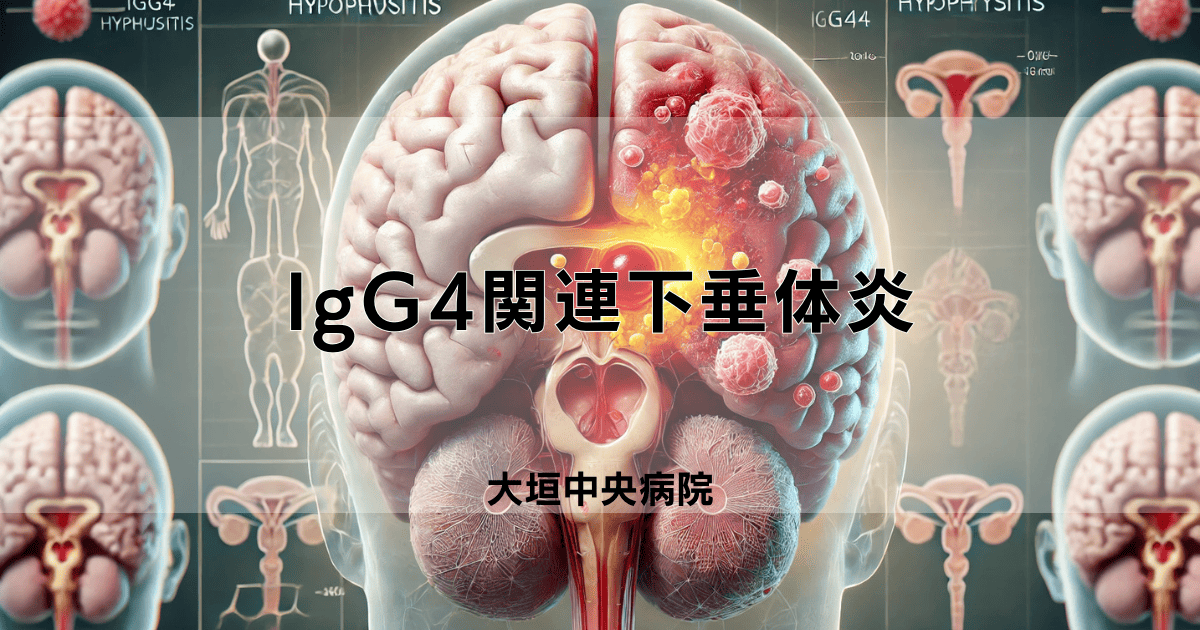IgG4関連下垂体炎とは、免疫グロブリンであるIgG4の血中濃度が高まり、下垂体というホルモン分泌を司る重要な臓器に慢性的な炎症がおこる疾患で、全身のさまざまな臓器や腺組織に病変が広がりやすいIgG4関連疾患です。
視野障害やホルモンバランスの乱れ、全身の倦怠感などが徐々に生じる場合もあり、検査画像で下垂体や周辺組織に腫大や炎症所見を認めることがありますが、症状の出方には個人差があります。
IgG4関連下垂体炎の病型
IgG4関連下垂体炎は下垂体に炎症や腫大が生じる比較的まれな自己免疫性疾患で、下垂体前葉や後葉、さらには周辺の視床下部や鞍隔膜付近にも影響が及ぶ場合があります。
下垂体の前葉中心型か後葉中心型か
IgG4関連下垂体炎は、下垂体前葉の機能低下が中心となるケースと、後葉の機能低下が主にみられるケースに大別されます。
前葉が主体の場合は、副腎皮質刺激ホルモンや甲状腺刺激ホルモンなど、複数のホルモン分泌が減少して倦怠感や低血糖発作、甲状腺機能低下症状などを起こしやすいです。
後葉が関与する場合は尿崩症状を認める可能性があり、口渇感や多尿などの症状が目立つことがあります。
下垂体前葉型と後葉型の特徴
| 病型 | 主な病変部位 | 代表的症状 |
|---|---|---|
| 前葉主体型 | 下垂体前葉 | 倦怠感、食欲不振、低血糖、甲状腺機能低下 |
| 後葉主体型 | 下垂体後葉 | 多尿、口渇感、夜間頻尿 |
局所型か全身型か
IgG4関連下垂体炎が下垂体に限局している局所型の場合、主な症状が下垂体機能障害となることが多いです。
また、IgG4関連疾患として他の臓器と同時に病変が進行している全身型の場合は、膵臓や唾液腺、涙腺など多岐にわたって腫大や線維化が生じ、全身のさまざまな不調が同時に現れることがあります。
全身型でよくみられる臓器病変
- 涙腺や唾液腺の腫大(ミクリッツ病に類似する変化)
- 膵臓の硬化(自己免疫性膵炎)
- 腎臓やリンパ節の炎症
- 胆管の狭窄(IgG4関連硬化性胆管炎)
病気の進行度合いによる分類
IgG4関連下垂体炎は慢性経過をたどる場合が多いですが、急性期には炎症が急速に強まって頭痛や視野障害などが一気にあらわれるケースもあります。
画像検査で下垂体の腫大が顕著になっている急性期には、速やかなステロイド治療を行わないと視神経に圧迫が及ぶことがあり、日常生活に影響を及ぼしかねません。
慢性期に移行すると、下垂体機能低下症状が中心となり、複数のホルモン補充が長期的に必要なケースも出てきます。
進行度合いによる特徴
| 進行度 | 主な特徴 | 治療上のポイント |
|---|---|---|
| 急性期 | 強い炎症、視野障害や頭痛 | ステロイドの投与が重要 |
| 慢性期 | 徐々にホルモン分泌が低下 | ホルモン補充療法が長期化する可能性 |
病型の把握と治療方針
IgG4関連下垂体炎は病型によって治療方針や症状の現れ方が変わるため、画像検査や血液検査、ホルモン負荷試験などの総合的な評価に基づき、患者さんごとに個別の計画を立てることが大切です。
下垂体に限局した病変か、他の臓器にも波及しているかを見極めながら、ステロイド治療や免疫抑制薬の使用を検討することがあります。
- 前葉優位か後葉優位かをまず区別する
- 急性期か慢性期かを判断して処方を考える
- 他の臓器病変の有無を確認し、全身管理を視野に入れる
IgG4関連下垂体炎の症状
IgG4関連下垂体炎の症状は、下垂体のどの部分が炎症の中心となるかや炎症の強さ、急性か慢性かという経過によって大きく変わります。
初期には軽度の頭痛程度で済む場合もありますが、病変が進むと視覚障害や全身倦怠感、ホルモンバランスの乱れによる多彩な症状が見られるようになります。
頭痛と視野障害
頭蓋内で腫大した下垂体が周囲を圧迫すると、特に視交叉付近が影響を受けて視野障害が起こりやすくなります。
多くの場合は両耳側の視野が欠ける両耳側半盲と呼ばれるパターンをとり、物が見えにくくなる、視野が狭まったように感じるなどの訴えにつながります。
さらに炎症が急速に進んだ場合は頭痛をともなうことが多いです。
頭痛の特徴と視野障害パターン
| 症状 | 特徴 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 頭痛 | 慢性~急性で変化 | 腫大や炎症の程度に左右される |
| 視野障害 | 両耳側半盲が多い | 視交叉への圧迫が関係 |
ホルモン分泌異常に伴う症状
下垂体は複数のホルモンをコントロールする中枢で、以下のようなホルモン分泌が低下すると、さまざまな症状が出現します。
- ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)の低下:倦怠感、低血圧、食欲不振、ストレス耐性の低下
- TSH(甲状腺刺激ホルモン)の低下:寒がり、体重増加、便秘、うつ状態などの甲状腺機能低下症状
- LH・FSH(性腺刺激ホルモン)の低下:月経異常、性欲減退、性機能低下
- GH(成長ホルモン)の低下:疲労感、筋力低下
後葉機能の障害による多尿・口渇
下垂体後葉が関与すると抗利尿ホルモン(ADH)の分泌が不十分になり、尿崩症様の症状を示すことがあり、1日に数リットルにもおよぶ多尿と、それに伴う強い口渇感が代表的です。
夜間のトイレ回数が多くなる夜間頻尿を訴える方も多く、日中の活動や睡眠に影響が及ぶ場合があります。
後葉障害時にみられる主な症状の特徴
| 症状 | 具体例 |
|---|---|
| 多尿 | 1日3~5リットル以上の排尿 |
| 口渇 | 水分補給を繰り返してしまう |
| 夜間頻尿 | 睡眠不足につながる可能性 |
慢性的な倦怠感や精神面への影響
下垂体ホルモンは体のエネルギーバランスや精神面の安定にも関係しているため、慢性的な炎症が進むと、うつ状態に類似した意欲の低下や集中力の欠如、イライラ感などを訴える方もいます。
こうした症状は病気の発見が遅れてしまう原因にもなるため、早期の段階で「何となく調子が悪い」「やる気がおきない」と感じたときに、総合的な検査を受けることは大切です。
- 長引く倦怠感、朝起きられない
- 仕事や家事への集中が難しくなる
- ささいなことで落ち込みやすい
IgG4関連下垂体炎の原因
IgG4関連下垂体炎の原因は自己免疫メカニズムが深く関わると考えられており、IgG4という免疫グロブリンが下垂体や周辺組織に蓄積して慢性的な炎症と線維化を起こします。
IgG4とは何か
IgG4は免疫グロブリンG(IgG)のサブクラスの1つで、本来は体内に侵入した病原菌や異物を排除する免疫作用の一端を担っていまが、何らかの誘因によって過剰に産生されると、自己組織を攻撃し、特定の臓器や腺に慢性的な炎症をもたらすことがあります。
IgG4の特徴
- IgGは免疫グロブリンの中で主に血中に多く存在する抗体
- IgG4はIgGのサブクラスのうち約5%前後を占める
- IgG4関連疾患ではIgG4が著しく上昇することが多い
自己免疫の関与
IgG4関連疾患においては、身体の免疫システムが誤作動し、まるで外敵のように自己の臓器や組織を攻撃します。
下垂体はホルモン分泌の司令塔ともいえる繊細な組織であり、そこに慢性的な炎症がおきるとホルモン分泌のバランスが崩れ、さまざまな症状を起こす可能性が高まるのです。
IgG4関連疾患の発症に関わる要因
| 要因 | 説明 |
|---|---|
| 遺伝的素因 | 免疫系の制御に個人差があり、家族内発症がみられることも |
| 環境要因 | 特定のウイルス感染やアレルギー反応など |
| 自己免疫反応 | 誤って自己組織を攻撃する免疫メカニズムが関与 |
他のIgG4関連疾患との関連
IgG4関連疾患は下垂体に限らず、自己免疫性膵炎や唾液腺炎、硬化性胆管炎、涙腺腫大など、全身の多岐にわたる臓器で同様の病理所見を示します。
下垂体炎の発症が確認された際は、胸部画像なども含めて他の臓器に病変がないかチェックすることが重要で、全身的なアプローチを行わないと症状の再発リスクや合併症の見落としにつながることがあります。
| 疾患名 | 主な病変部位 | IgG4関連の特徴 |
|---|---|---|
| 自己免疫性膵炎 | 膵臓 | 膵臓の腫大、線維化、IgG4陽性形質細胞浸潤 |
| IgG4関連唾液腺炎 | 耳下腺、顎下腺など | 腺腫大や口腔内乾燥、顕著なIgG4陽性細胞浸潤 |
| IgG4関連硬化性胆管炎 | 胆管 | 胆管狭窄、黄疸、IgG4陽性細胞浸潤 |
生活習慣との直接的な関係
IgG4関連下垂体炎の発症は、他の生活習慣病(肥満や喫煙、アルコール過多など)との直接的な関係がはっきりしているわけではありません。
しかし、慢性的なストレスや不規則な生活が免疫機能全体に影響を及ぼす可能性もあるため、バランスのよい食事や適度な休息など健康管理が発症リスクを間接的に下げる一助となることが期待されます。
IgG4関連下垂体炎の検査・チェック方法
IgG4関連下垂体炎かどうかを診断するには、血液検査や画像検査、ホルモン負荷試験など複数のアプローチが必要で、早期に的確な検査を実施すると、重症化を防ぎ、視神経障害などの取り返しのつかない合併症を避ける可能性が高まります。
血液検査
IgG4関連下垂体炎では、血中のIgG4濃度が高まるケースが多く、一定のカットオフ値(おおむね135 mg/dL以上)を超えるとIgG4関連疾患を疑う目安です。
また、甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンなど、下垂体ホルモン軸の異常を評価するためにさまざまなホルモン値を測定します。
血液検査項目
- IgG4(免疫グロブリンG4)濃度
- TSH、フリーT4、フリーT3(甲状腺ホルモン)
- ACTH、コルチゾール(副腎皮質機能)
- LH、FSH、エストロゲン、テストステロン(性腺機能)
- GH、IGF-1(成長ホルモン軸)
画像検査(MRIやCT)
下垂体やその周囲の構造を詳細に把握するために、頭部MRIが最もよく活用され、IgG4関連下垂体炎の場合、下垂体の腫大や強い造影効果がみられ、鞍隔膜や視交叉付近への浸潤が確認できる場合があります。
また、炎症が進むと鞍上部へ波及し、視神経や視床下部の形態にも影響が及ぶことがあるため、MRI画像を比較しながら病勢を評価することが大切です。
CTは骨構造や石灰化の有無を確認するときなどに参考にすることがあります。
画像検査ごとの特徴
| 検査法 | 特徴 | 留意点 |
|---|---|---|
| MRI | 軟部組織の描出が得意 | 造影剤使用時にはアレルギーに注意 |
| CT | 骨・石灰化の評価が可能 | 放射線被ばくがあるので頻回は避けたい |
ホルモン負荷試験
血中のホルモン値だけでははっきりしない場合や、下垂体機能の予備能を詳しく調べたい場合は、ホルモン負荷試験を行います。
- インスリン低血糖負荷試験:人工的に血糖値を下げ、体のストレス応答をみる
- CRH負荷試験:中枢からのホルモン分泌能をチェック
- TRH負荷試験:甲状腺刺激ホルモン(TSH)の応答を確認
代表的な負荷試験と評価対象
| 負荷試験 | 評価対象 |
|---|---|
| インスリン低血糖負荷 | ACTH・コルチゾール分泌機能 |
| CRH負荷試験 | ACTH分泌能 |
| TRH負荷試験 | TSH・甲状腺ホルモン応答 |
組織生検や下垂体生検
非常にまれではありますが、腫瘍との鑑別が難しい場合や、IgG4陽性形質細胞の浸潤を確認したい場合には、下垂体生検が検討されることがあります。
生検によってIgG4陽性形質細胞の集簇や線維化の所見を直接確認できれば確定診断に至ることがありますが、下垂体生検は侵襲度が高く、慎重に検討しなければなりません。
- 下垂体腺腫との鑑別
- 他の肉芽腫性疾患やリンパ球性下垂体炎との鑑別
治療方法と治療薬について
IgG4関連下垂体炎の治療は、主にステロイドを用いた免疫抑制療法と、不足したホルモンの補充が柱です。
病態に応じて免疫抑制薬や生物学的製剤を併用する場合もありますが、中心的な位置づけとなるのはステロイドであり、急性期には特に効果が期待されます。
ステロイド療法の概要
IgG4関連下垂体炎では、プレドニゾロンなどのステロイド薬を使い、炎症と免疫反応を抑えることを目指します。
急性期に視神経の圧迫が強い場合は、初期に高用量ステロイドのパルス療法を行うこともあり、その後は徐々に減量しつつ維持量を続ける形をとることが多いです。
ステロイド療法で期待されるポイント
- 炎症の抑制により視野障害や頭痛の改善が期待できる
- 下垂体の腫大が軽快し、画像上でも縮小が見られる可能性がある
- 他臓器に病変を伴う場合にも、全身的な炎症抑制作用を発揮できる
ホルモン補充療法
ステロイド療法とは別に、下垂体機能が低下しているホルモンを補うための治療を行います。
副腎皮質機能が落ちている場合はヒドロコルチゾン、甲状腺機能が落ちている場合はレボチロキシンを補充し、性腺機能低下時には男性にはテストステロン補充、女性にはエストロゲン製剤などが選択肢です。
代表的なホルモン補充治療
| 不足ホルモン | 補充薬剤の例 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 副腎皮質ホルモン | ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン | ステロイド自体を補充し、低血糖や倦怠感を防ぐ |
| 甲状腺ホルモン | レボチロキシン | 代謝調節を回復し、寒がりやむくみを改善 |
| 性腺ホルモン | テストステロン、エストロゲン | 月経異常や性機能低下に対応 |
免疫抑制薬や生物学的製剤の使用
IgG4関連下垂体炎が難治性でステロイド単独では十分な効果が得られない場合や、副作用のためにステロイドの長期使用が難しい場合には、アザチオプリンやメトトレキサートなどの免疫抑制薬、あるいは生物学的製剤のリツキシマブなどが選択肢となります。
このような薬剤は免疫系の暴走を抑えることが主目的ですが、その分感染症リスクが増大するなど、慎重なモニタリングが必要です。
- アザチオプリンやメトトレキサート:細胞増殖を抑える
- リツキシマブ:B細胞を標的とするモノクローナル抗体
外科的治療の必要性
下垂体腫瘍と鑑別が難しいケースや、ステロイドで炎症が十分に抑えられずに視神経への圧迫が解除されないケースでは、経蝶形骨洞手術など外科的アプローチで腫大組織の一部を切除し、視野障害の進行を抑止することがあります。
また、手術と同時に組織生検を行い、IgG4陽性細胞浸潤を確認することで確定診断につながる場合もあります。
IgG4関連下垂体炎の治療期間
IgG4関連下垂体炎の治療期間は人によって大きく差があり、ステロイドに対する反応性や下垂体機能の残存度合い、合併症の有無などが影響します。
急性期から慢性期までの流れ
急性期には、視神経障害を含めた深刻な症状を抑えるために高用量ステロイドやパルス療法を短期間行い、早期に炎症をコントロールすることが目標です。
その後、炎症が落ち着いたらステロイドを徐々に減量しつつ、ホルモン補充を継続するかどうかを判断します。
治療期間の目安とポイント
| 時期 | 治療内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 急性期 | 高用量ステロイドなど | 視神経圧迫や頭痛などを迅速に抑えたい |
| 移行期 | ステロイドの減量 | 副作用を抑えつつ最小限の量で維持 |
| 慢性期 | ホルモン補充主体 | 機能回復が望めない場合は継続補充が必要 |
ステロイド治療の減量期間
ステロイドは長期に高用量を使用すると骨粗鬆症や糖尿病、感染症リスクの増大など、多面的な副作用が懸念されるので、症状と炎症所見をみながら数週~数か月かけて徐々に量を減らすアプローチが一般的です。
ただし、急激に中止すると副腎不全を起こす可能性があるため、医師の指示のもとで慎重に進める必要があります。
ステロイド減量時に注意すべき点
- 倦怠感や低血圧、食欲不振など副腎不全を疑う症状がないか確認
- 感染症(特に呼吸器感染など)の兆候に注意
- 血糖値や骨密度の定期チェックを継続し、副作用が強くならないよう配慮
ホルモン補充の継続期間
IgG4関連下垂体炎で低下したホルモン分泌能は、ステロイド治療によってある程度回復する可能性もありますが、完全には戻らず、長期にわたって補充療法が必要となることがあります。
甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモン、性腺ホルモンなど、それぞれ不足分を補って生活の質を保つことが重要です。
| 不足ホルモン | 補充期間 |
|---|---|
| 副腎皮質 | 数か月~数年単位で継続する場合あり |
| 甲状腺 | 経過観察しながら長期補充になる可能性 |
| 性腺 | 症状や年齢によって変動 |
定期的な再評価
治療後もMRIなどで下垂体の状態やホルモン分泌能を定期的に再評価し、再燃やほかの臓器病変の発生に注意を払う必要があります。
IgG4関連疾患は全身のさまざまな部位に影響が及ぶことがあるため、他の診療科との連携を密にしながら総合的にチェックすると安心です。
- 数か月に1回のMRIで炎症や腫大の再発確認
- 血液検査でIgG4値やホルモン値を追跡
- 視野検査で進行する視野障害の有無を確認
IgG4関連下垂体炎薬の副作用や治療のデメリットについて
IgG4関連下垂体炎の治療にはステロイドや免疫抑制薬などの薬剤が主に用いられますが、副作用やデメリットもあります。
ステロイドの副作用
ステロイドは強力な抗炎症作用を持つ一方、長期・高用量になると以下のような副作用が現れることがあります。
- 体重増加やむくみ
- 糖尿病の悪化や高血糖
- 骨粗鬆症による骨折リスクの上昇
- 免疫抑制による感染症リスク増大
- 精神症状(うつ状態、気分の変調など)
ステロイドの代表的副作用
| 副作用 | 内容 |
|---|---|
| 体重増加 | 食欲増進や水分貯留により体重が増える |
| 高血糖 | インスリン抵抗性が高まり血糖が上がる |
| 骨粗鬆症 | 骨密度が低下し骨折しやすくなる |
| 精神症状 | イライラ感、うつ症状、不眠などが生じる |
免疫抑制薬や生物学的製剤のデメリット
免疫抑制薬(アザチオプリン、メトトレキサートなど)や生物学的製剤(リツキシマブなど)は免疫機能を低下させることで炎症を抑えますが、そのぶん感染症リスクが高まるため注意が必要です。
特にウイルス性や細菌性の感染に対して抵抗力が下がる可能性があるため、定期的な血液検査や感染症検査を受けながら治療を進めることになります。
- 肝機能や腎機能のチェックが欠かせない
- 貧血や白血球減少が起こるケースもある
- 適正量の判断に慎重さが必要
ホルモン補充の副作用
ホルモン補充療法も、過剰投与や急激な投与量変更によって副作用が生じるリスクがあります。
甲状腺ホルモンを過剰に補充した場合は動悸や息切れ、不眠などの症状が出ることがあり、また、副腎皮質ホルモン補充が不足すると倦怠感や血圧低下が再燃する可能性があります。
ホルモン補充時に注意が必要な点
- 自己判断で薬の量を増減しない
- 医師の指示に従って定期的に血中濃度を測定
- 症状が変化したときは早めに報告
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険診療の範囲
基本的な外来受診や血液検査、MRI検査などは保険診療の範囲に含まれます。
主な診療項目と保険適用の有無
| 診療項目 | 保険適用 | 自己負担の目安(3割負担時) |
|---|---|---|
| 初・再診料 | あり | 数百円~数千円 |
| 血液検査 | あり | 数百円~数千円 |
| MRI・CT検査 | あり | 数千円~1万円前後になることも |
IgG4関連下垂体炎に使用される主な薬剤費
| 薬剤の種類 | 1か月あたり薬価総額の目安 | 3割負担時の自己負担 | 補足説明 |
|---|---|---|---|
| ステロイド薬 | 3,000~8,000円程度 | 1,000~2,400円程度 | 病状や患者の体重によって用量が増減し、服用期間が長くなるほど費用がかさみます。 |
| 免疫抑制薬(アザチオプリンなど) | 10,000~20,000円程度 | 3,000~6,000円程度 | ステロイド減量が難しい場合や副作用が強い場合に併用します。 |
| 生物学的製剤(リツキシマブなど) | 1回投与あたり10万円前後になることも | 高額療養費制度の利用で一定上限を超えた分が戻る | 比較的高額で、投与回数は病状により異なります。副作用や感染症リスクに注意が必要です。 |
| ホルモン補充薬(ヒドロコルチゾン、レボチロキシン、性ホルモンなど) | 2,000~5,000円程度 | 600~1,500円程度 | 不足ホルモンの種類と用量によって異なり、複数のホルモン補充が必要な場合は合計費用が上がります。 |
以上
参考文献
Shikuma J, Kan K, Ito R, Hara K, Sakai H, Miwa T, Kanazawa A, Odawara M. Critical review of IgG4-related hypophysitis. Pituitary. 2017 Apr;20:282-91.
Takagi H, Iwama S, Sugimura Y, Takahashi Y, Oki Y, Akamizu T, Arima H. Diagnosis and treatment of autoimmune and IgG4-related hypophysitis: clinical guidelines of the Japan Endocrine Society. endocrine journal. 2020;67(4):373-8.
Amirbaigloo A, Esfahanian F, Mouodi M, Rakhshani N, Zeinalizadeh M. IgG4-related hypophysitis. Endocrine. 2021 Aug;73:270-91.
Bando H, Iguchi G, Fukuoka H, Taniguchi M, Yamamoto M, Matsumoto R, Suda K, Nishizawa H, Takahashi M, Kohmura E, Takahashi Y. The prevalence of IgG4-related hypophysitis in 170 consecutive patients with hypopituitarism and/or central diabetes insipidus and review of the literature. European journal of endocrinology. 2014 Feb;170(2):161-72.
Iwata N, Iwama S, Sugimura Y, Yasuda Y, Nakashima K, Takeuchi S, Hagiwara D, Ito Y, Suga H, Goto M, Banno R. Anti-pituitary antibodies against corticotrophs in IgG4-related hypophysitis. Pituitary. 2017 Jun;20:301-10.
Hori M, Makita N, Andoh T, Takiyama H, Yajima Y, Sakatani T, Fukumoto S, Iiri T, Fujita T. Long-term clinical course of IgG4-related systemic disease accompanied by hypophysitis. Endocrine Journal. 2010;57(6):485-92.
Yamano T, Kanda M, Mizushima I, Matsui S, Saeki T, Amaike H, Masaki Y, Yamada K, Takahashi H, Kawano M. AB0387 CLINICAL CHARACTERISTICS AND LITERATURE REVIEW OF 17 PATIENTS WITH IgG4-RELATED HYPOPHYSITIS. Annals of the Rheumatic Diseases. 2024 Jun 1;83:1439-40.
Ohkubo Y, Sekido T, Takeshige K, Ishi H, Takei M, Nishio SI, Yamazaki M, Komatsu M, Kawa S, Suzuki S. Occurrence of IgG4-related hypophysitis lacking IgG4-bearing plasma cell infiltration during steroid therapy. Internal Medicine. 2014;53(7):753-7.
Shimatsu A, Oki Y, Fujisawa I, Sano T. Pituitary and stalk lesions (infundibulo-hypophysitis) associated with immunoglobulin G4-related systemic disease: an emerging clinical entity. Endocrine journal. 2009;56(9):1033-41.
Kanie K, Bando H, Iguchi G, Shiomi H, Masuda A, Fukuoka H, Nishizawa H, Fujita Y, Sakai A, Kobayashi T, Shiomi Y. IgG4-related hypophysitis in patients with autoimmune pancreatitis. Pituitary. 2019 Feb 15;22:54-61.