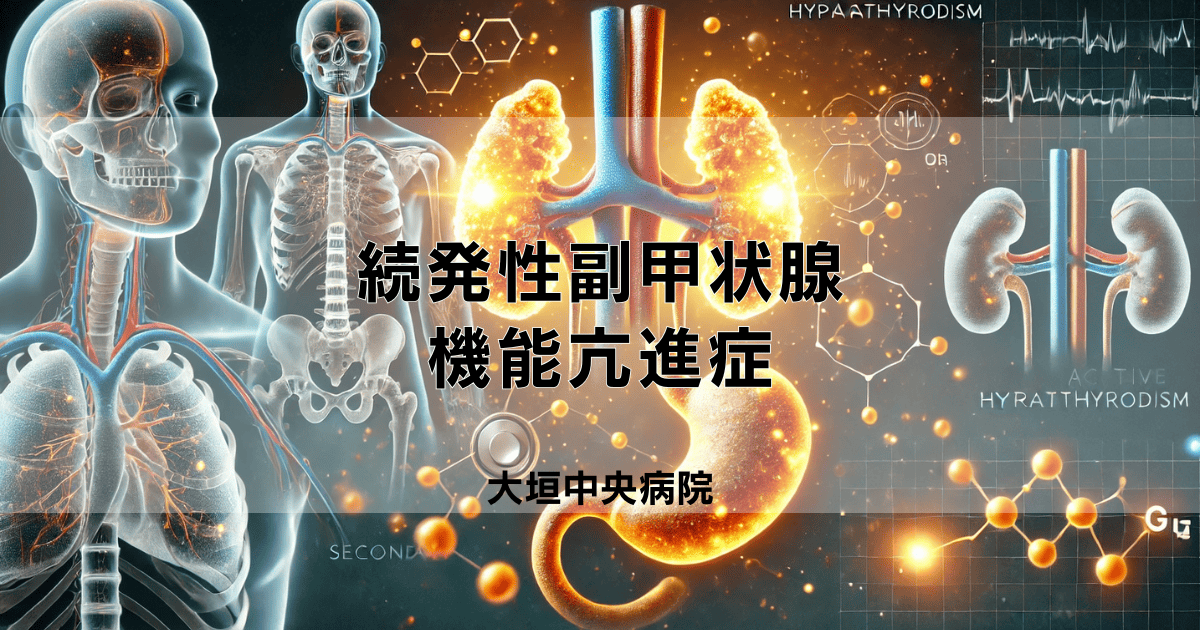続発性副甲状腺機能亢進症とは、慢性腎臓病などがきっかけとなって血液中のカルシウムやリンのバランスが崩れ、副甲状腺が過度に活発化し、ホルモン分泌が増加してしまう状態です。
血液中のカルシウム調整に大きく関与する副甲状腺ホルモンが増えすぎると、骨や血管など多方面に悪影響を及ぼす恐れがあります。
骨折リスクの上昇や血管の石灰化、筋力低下など、日常生活の質を下げる合併症につながりかねないので、正しい治療方針を知っておくことが重要です。
続発性副甲状腺機能亢進症の病型
病型によって原因の背景や病態進行のしかたに違いがあり、ここでは代表的な病型や発症のしくみを考えながら、どのような病態が含まれるかを掘り下げます。
血中カルシウムやリンのバランスが崩れると、副甲状腺がそれを補おうとして働きすぎる傾向がありますが、各病型の特徴を把握することで自分の状態を理解しやすくなります。
慢性腎不全に伴う病型
慢性腎不全、特に末期腎不全に至ると腎臓が血中リンを十分に排出できず、リンが体内に蓄積しやすくなり、高リン血症が起こると血中カルシウムは低下傾向となり、低カルシウム状態を補うため副甲状腺が過度にホルモンを分泌し始めます。
このメカニズムが続発性副甲状腺機能亢進症の代表的な病型で、慢性腎臓病が進行するほど重症化しやすいです。
慢性腎不全由来の病型
| 要素 | 特徴 | 影響 |
|---|---|---|
| 高リン血症 | 腎機能低下によりリン排泄が不十分になる | 血中リン上昇→血中カルシウム低下 |
| 低カルシウム血症 | カルシウム低下を補うために副甲状腺ホルモンが増加 | 骨代謝異常→骨がもろくなるリスクが上昇 |
| 副甲状腺肥大 | 慢性的なホルモン分泌過剰で副甲状腺組織が大きくなる | 治療介入が遅れると遺残性亢進へ移行する可能性 |
慢性腎不全による透析治療を受けている方の多くが、この病型を抱えることがありますが、腎臓の状態やカルシウム・リンのコントロール次第で症状の度合いが変わってきます。
主な注意点
- 血清リン値とカルシウム値のバランスが大きく崩れたときにリスクが高まる
- 長期にわたってホルモン分泌が過剰になり、副甲状腺肥大が進む
- 骨や血管の石灰化をきっかけに全身症状を引き起こすことがある
食事制限やリン吸着薬の使用で血中リンを管理することで、副甲状腺の過活動を抑える手段が見いだせますが、状況によっては手術などの検討が必要です。
胃腸障害やビタミンD吸収障害による病型
慢性腎臓病以外にも、消化管にかかわる疾患やビタミンDの吸収障害によってカルシウム代謝が乱れるケースがあります。
慢性膵炎やクローン病など、腸管から十分にビタミンDを吸収できない病態では血中カルシウムが低下しやすく、副甲状腺機能亢進につながることがあります。
ビタミンD吸収障害の主な原因
| 原因 | 具体例 | カルシウムへの影響 |
|---|---|---|
| 腸管吸収障害 | 炎症性腸疾患、短腸症候群など | 脂溶性ビタミンDの吸収が難しくなる |
| 膵機能低下 | 慢性膵炎など消化酵素の不足 | 脂質分解不十分でビタミンD取り込み低下 |
| 低栄養状態 | 極端な食事制限や摂食障害など | ビタミンD不足→血中カルシウムも低下 |
吸収障害が続くと骨代謝に深刻な負担をかけるため、骨粗鬆症の合併リスクがさらに高まる可能性があります。胃腸障害が長期化している方は、血液検査やビタミンレベルのチェックによって早期に問題点を把握することが大切です。
一次性との違い
副甲状腺機能亢進症には一次性と呼ばれる病型もあり、これは副甲状腺自体に腺腫や腫瘍が発生して直接的にホルモンが過剰に分泌されるものです。
一方、続発性ではあくまでも他の要因(たとえば腎機能低下)によって血中カルシウムやリンのバランスに乱れが生じ、その結果として副甲状腺が反応しすぎてしまうことが主となります。
この違いを理解しておくと、なぜ治療方針が異なるのかが分かりやすいです。
続発性副甲状腺機能亢進症の症状
続発性副甲状腺機能亢進症では、カルシウムやリンなどのミネラルバランスが崩れた影響が骨や筋肉、血管などに波及するため、症状の幅が広いです。
初期はわずかな骨の違和感や全身の倦怠感として表れることもありますが、進行すると生活の質を大きく左右する変化が出る可能性が高まります。
骨や関節への影響
副甲状腺ホルモンは骨からカルシウムを血液中へ放出させる作用があり、過剰に分泌されると骨密度が低下し、骨粗鬆症や骨折リスクが高まる恐れがあります。
腰や背中、膝などに痛みを感じやすく、レントゲンで骨の変性や骨密度の低下が確認される方も少なくありません。透析患者の場合、骨の脆弱化が急激に進むケースもあるので、自覚症状がなくても定期的にチェックすることが重要です。
骨にまつわる主な症状
- 骨折を起こしやすくなる
- 歯がもろくなることがある
- 立ち上がりや歩行に苦痛を伴う
骨関連のトラブルは段階的に進行していき、日常的な運動機能にも影響するため、見過ごしてしまうと活動範囲が制限され、筋力低下を招きやすくなります。
筋肉や神経系の異常
カルシウムは神経伝達や筋肉の収縮にも関わるため、低カルシウム血症や血清リン値の異常によって筋肉や神経が刺激を受けやすくなります。
慢性的なだるさ、筋力の低下、しびれ感などが生じ、重度の場合は筋肉の痙攣や筋肉痛が続くこともあります。
意識がぼんやりするなどの神経症状を訴える患者もいるので、体のだるさだけでなく、精神的な不調を感じるときは早めの受診が大切です。
筋肉や神経に現れやすい変化
| 症状 | 主な特徴 | 影響 |
|---|---|---|
| 筋力低下 | 階段の昇り降りなどで特に疲れやすくなる | 生活動作に支障が出ることがある |
| しびれ感 | 手や足の末端に軽度のしびれを感じる場合が多い | 長時間続くと集中力や作業効率の低下につながる |
| 痙攣 | カルシウムコントロールの乱れが強いと生じやすい | 運動中や就寝時に痛みを伴う痙攣が起こることもある |
| 意識の混濁 | ごく重度の場合にみられる | 思考力や判断力が落ち、日常生活に大きな支障をきたす |
血管や心臓への影響
血液中のリンとカルシウムのバランスが崩れると、血管壁にカルシウムが沈着しやすくなる可能性があり、石灰化が進むと血管の弾力性が失われ、動脈硬化が加速するリスクが高まります。
心臓弁の石灰化や冠動脈疾患のリスク上昇も指摘されているため、腎臓が悪い方や透析患者は特に注意が必要で、血管に関わる症状は自覚しにくい部分もあるので、定期的な画像検査や血液検査が欠かせません。
全身倦怠感や不眠
骨や筋肉、血管へのトラブルが背景にあると、全身のだるさや不眠傾向などを感じる場合が増え、慢性腎臓病の透析を受けている方にとっては疲れが抜けにくく、睡眠の質も落ちるなど、生活全般に支障が及ぶことが珍しくありません。
痛みやしびれなどの症状と複合的に起こるため、日常生活での小さな違和感も見逃さないように意識することが大切です。
日常生活に影響する要素
- 眠りが浅くなる
- 朝起きると体が重く感じる
- やる気や集中力が続かない
自律神経の乱れとも関わりやすく、自己判断のみで放置するとストレスや抑うつ状態に陥る恐れがあるため、根本的な原因を突き止めるためにも診察が重要です。
原因
原因の多くは慢性腎臓病やビタミンD不足などですが、それ以外にも複数の要因が絡み合って発症や進行に至ります。
血液中のリンやカルシウム、ビタミンDの代謝は複雑であり、一つのトラブルが波及し、副甲状腺が過剰反応を起こす状態へ発展しやすい構造があります。
慢性腎臓病の進行
腎臓は体の老廃物を排泄するだけでなく、ビタミンDを活性化する役割も担っており、腎機能が低下するとリンの排泄やビタミンDの活性化が滞り、血中リンが高くなってカルシウムは低下しやすくなります。
副甲状腺ホルモンが増える理由として、腎機能の悪化は最も大きなウエイトを占めています。
慢性腎臓病が続発性副甲状腺機能亢進症を起こす流れ
| 主なステップ | 体内での変化 |
|---|---|
| 腎機能低下 | リン排泄低下、ビタミンD活性化障害 |
| 血中リン上昇 | 血中カルシウムが下がりやすくなる |
| 副甲状腺ホルモン増加 | カルシウムを補おうとする反応が持続し、副甲状腺が肥大してホルモンを多量に分泌 |
このような状態が長期におよぶと副甲状腺自体が過形成を起こし、薬物や食事制限だけではコントロールしにくくなる可能性があります。
ビタミンD不足や吸収障害
慢性腎臓病に限らず、外から摂取したビタミンDが腸で十分に吸収されない状況もカルシウム不足を招きます。胃腸の切除後や炎症性腸疾患などでビタミンDの吸収が落ちるケースや、脂肪分解酵素が不足する病態などは、とくに注意が必要です。
ビタミンD不足が続くと小腸からのカルシウム吸収が滞り、結果的に副甲状腺が過活動を起こすリスクが高まります。
吸収障害の原因
- クローン病などの炎症性腸疾患
- 膵液の不足を招く慢性膵炎
- 胆汁分泌不全による脂溶性ビタミンの吸収不全
食事だけで充分なビタミンDやカルシウムを補えない場合は、サプリメントの活用や日光浴なども考慮に入れて、医師に相談するとよいでしょう。
リンの過剰摂取
リンは食品添加物や加工食品に多く含まれ、過度に摂取したリンは、腎臓が健康な状態であれば排泄できますが、腎機能が落ちていると排泄が追いつかず血中リン濃度が高まりやすくなります。
そうなるとカルシウムが減少して副甲状腺ホルモンの分泌過剰を招きやすいです。
食習慣に潜むリン過剰のリスク
| 食品の例 | ポイント |
|---|---|
| 加工肉・ハム・ソーセージ | 添加物としてリン塩が使われることが多い |
| インスタント食品 | うま味調味料や保存料にリン化合物が含まれる |
| 炭酸飲料 | リン酸が含まれるタイプは摂取過剰に注意が必要 |
特に慢性腎臓病を抱える人は、日常的に過剰なリンを摂らないように意識しながら食事管理を行うことが大切です。
ホルモンや遺伝的要因
稀にホルモンバランスの異常や遺伝子の変異が関与する例もありますが、続発性副甲状腺機能亢進症の大半は外部要因(主に腎機能低下や消化管吸収障害)が引き金となります。
血液検査でカルシウム、リン、パラトルモン値が安定しているかどうかを定期的に観察することで、早期発見と対策が可能です。
続発性副甲状腺機能亢進症の検査・チェック方法
症状やリスクが疑われる際は、血液検査や画像検査、骨密度の測定などを組み合わせて総合的に病態を判断することが多く、継続的な検査で経過を追うことが治療選択の参考になります。
血液検査
続発性副甲状腺機能亢進症を疑ったときに最初に行われるのが血液検査で、カルシウム、リン、パラトルモン(PTH)、そして腎機能の指標となるクレアチニン値などを確認し、総合的に評価していきます。
特にPTHの値が基準値より高いかどうかは、副甲状腺の過活動を直接示唆する重要な指標です。
血液検査でチェックする主な項目
| 項目 | 意義 |
|---|---|
| カルシウム | 血中カルシウム低下が副甲状腺機能亢進を誘発する |
| リン | 慢性腎臓病があると排泄が難しくなりやすい |
| PTH(副甲状腺ホルモン) | 高値だと副甲状腺過活動が強く疑われる |
| クレアチニン | 腎機能評価の中心的な指標 |
結果を踏まえて必要に応じた追加検査や治療方針を医師が提示するため、定期的に血液検査を受けると早期発見の可能性が高まります。
画像検査
超音波検査やCT、MRIなどを活用して、副甲状腺や骨、腎臓の状態を詳しく調べることがあり、副甲状腺の大きさや結節、骨の構造変化、血管の石灰化などの異常を把握できるため、手術の検討や薬物治療の効果判定にも役立ちます。
透析患者さんの場合、血管の石灰化が進んでいないかどうかを定期的に確認し、予防的アプローチをとることが重要です。
代表的な画像検査
| 検査法 | 特徴 | よく用いられるケース |
|---|---|---|
| 超音波検査 | 副甲状腺の大きさや形態、腎臓の状態などを非侵襲的に観察 | 副甲状腺の肥大を簡易的に評価したいとき |
| CT | 腎臓、血管、骨の石灰化などを断面で立体的に評価 | 合併症の有無や手術計画を立てる前に活用 |
| MRI | 軟部組織の描出に優れ、副甲状腺の明確な評価が可能 | 他の検査で判断が難しい場合や腫瘍が疑われる際 |
骨密度測定
骨のミネラル状態を把握するために骨密度測定が行われることがあり、腰椎や大腿骨などの骨密度を測定し、基準値からどの程度減少しているかを評価します。
続発性副甲状腺機能亢進症では骨代謝が乱れやすいため、骨折リスクを早期に把握する意味でも定期的な測定が望ましいです。
尿検査
カルシウムやリンの尿中排泄量を把握するために尿検査が実施されることもあります。腎臓の働きに異常がある場合、尿へのリンやカルシウムの排泄パターンが変化しやすく、そこから治療の方針を決定する材料を得られます。
チェックする要素
- 尿中カルシウム濃度
- 尿中リン濃度
- 糸球体ろ過量(推算GFR)との関連性
尿検査と血液検査を併用することで、腎臓と副甲状腺、骨代謝の連動具合を把握しやすくなります。
治療方法と治療薬について
治療の基本は、原因となる血液中のカルシウムやリンの不均衡を整えることで、腎臓の状態が影響している場合は、透析や食事療法、リン吸着薬などを用いてリンをコントロールしながらカルシウムバランスを調整していきます。
副甲状腺ホルモンそのものを抑制する薬も登場しており、これらを組み合わせながら病状に応じた対策を図ります。
食事療法や透析管理
腎機能が低下してリンが排泄できないことが大きな原因である場合、まずはリンを抑えた食事療法や、人工透析によるリン除去を強化する方法が検討されます。
日常の食事ではリン含有量の高い加工食品や乳製品、炭酸飲料などを控えめにすることがポイントで、透析を受けている方は、透析効率を高めて血中リンをコントロールすることが大切です。
食事管理で気をつけたい点
- 加工食品やインスタント食品の頻度を減らす
- 魚や肉を過剰に摂取しないよう注意する
- リンバインダーなどリン吸着薬の服用タイミングを守る
食事だけでカバーしきれない場合は、透析の回数や時間を調整するなどの対策も合わせて検討されます。
薬物療法
続発性副甲状腺機能亢進症の治療でよく使われる薬には、大きく分けてリン吸着薬、カルシウム製剤、ビタミンD製剤、副甲状腺ホルモンの分泌を調整する薬などがあります。
組み合わせることで、血中リンを低下させたり、カルシウム濃度を維持したり、副甲状腺の過活動を抑えたりします。
主な治療薬
| 薬の種類 | 例 | 主な作用 |
|---|---|---|
| リン吸着薬 | 炭酸ランタン、セベラマーなど | 食事中のリンを吸着して体外へ排出を促す |
| ビタミンD製剤 | アルファカルシドール、カルシトリオール | 小腸でのカルシウム吸収促進、副甲状腺ホルモン抑制効果 |
| カルシウム製剤 | グルコン酸カルシウムなど | 血中カルシウムの補充 |
| カルシミメティクス | シナカルセトなど | 副甲状腺カルシウム受容体を刺激しホルモン分泌を抑制 |
カルシミメティクスは、続発性副甲状腺機能亢進症の管理において強力な手段ですが、投与量の調整や副作用にも注意が必要です。
外科的治療
薬物治療や食事・透析管理でコントロールが難しくなると、副甲状腺そのものを外科的に摘出する手術が検討されます。副甲状腺全摘出や、3つ半だけを摘出する手術などが一般的で、抜去後はカルシウムやビタミンDの補充が欠かせません。
手術によって症状の改善が期待できる一方、低カルシウム血症に陥るリスクがあるため、術後の管理が重要です。
ライフスタイルの調整
日常生活の中でできる対策としては、リンを抑えるだけでなく、適度な運動や十分な水分補給も考慮に入れたいところです。
骨や筋肉を維持するために軽い筋トレやウォーキングを継続し、循環を良好に保つ努力が役立ちます。慢性疾患と共存する場合は、ストレスケアや睡眠の質向上も含め、総合的な健康管理を意識することが大切です。
ライフスタイルで意識したい習慣
- ウォーキングなどの有酸素運動を定期的に行う
- 就寝前のスマートフォン利用を減らし、睡眠の質を高める
- 腎臓や骨をサポートする栄養バランスに配慮する
これらのポイントを踏まえて治療薬や食事内容を調整しながら、体調の変化をチェックすると、より安定した症状管理が期待できます。
続発性副甲状腺機能亢進症の治療期間
治療期間は、原因となる疾患や患者の状態、治療法の選択によって大きく変わり、一度副甲状腺が過度に肥大し、ホルモン分泌が持続的に高まった場合、薬物や透析だけでは十分に抑えきれない期間が続くこともあります。
慢性腎臓病など原疾患の管理が欠かせないため、多くのケースで長期的な治療や経過観察を想定しておくことが必要です。
長期管理の重要性
慢性的な腎機能低下が背景にある続発性副甲状腺機能亢進症は、一時的に薬でPTH値を下げても、腎臓の状態が変わらない限り再度上昇する可能性があります。
治療は短期間で完結することは少なく、透析を受けている場合は特に、透析スケジュールや薬剤調整を長期にわたって継続することになります。
長期フォローアップのポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期血液検査 | PTH値、カルシウム、リンなどの推移を確認し、治療方針を見直す |
| 画像検査や骨密度測定 | 進行度合いや合併症のリスクを早期に把握できる |
| 生活習慣の評価 | 食事、運動、休養などの改善点を適宜見直す |
治療薬の副作用や手術の適応も考慮しながら、主治医と相談のうえ定期的に計画をアップデートしていくことが大切です。
手術後の観察期間
手術によって副甲状腺を摘出した場合でも、術後に低カルシウム血症が生じる可能性があり、補正のためのカルシウムやビタミンD投与が必要です。
個人差はありますが、手術直後から数か月にわたりカルシウム値の安定性を確認しつつ、段階的に薬の調整を行い、場合によってはホルモン補充が長く続くこともあるため、術後のフォローアップの重要性は軽視できません。
原疾患の管理が治療期間を左右する
腎臓病や消化器の吸収障害など、続発性副甲状腺機能亢進症を引き起こしている要因をどの程度コントロールできるかが、治療期間に大きく影響します。
腎移植によって腎機能が改善すると、続発性副甲状腺機能亢進症も軽快に向かうケースがある一方、コントロール不良の場合は数年以上にわたる根気強い管理が重要です。
治療期間に意識しておきたいこと
- 原因疾患(慢性腎臓病や吸収障害など)のケアを徹底する
- 食事や薬の服用タイミング、運動習慣などを継続的に見直す
- 定期検査を通じて病状の変化を把握し、早めに対応する
副作用や治療のデメリットについて
薬物療法は大きな役割を果たしますが、同時に副作用や治療上の負担が生じる可能性もあり、症状を抑えるために必要な手段であっても、体質や併用薬との兼ね合いで体調を崩しやすくなる場合があります。
リン吸着薬の副作用
リン吸着薬は食事に含まれるリンを腸管で吸着し、体外へ排出させる効果が期待できますが、便秘や胃腸の不快感を感じる方がいます。
高カルシウム血症の傾向がある方がカルシウム系リン吸着薬を多用すると、カルシウム値が上がりすぎるリスクがあるため、適宜検査データを確認しながら用量を調整します。
リン吸着薬で想定される主な不調
- 便秘や腹部膨満感
- 軽い下痢や腹痛
- 血中カルシウム上昇による倦怠感
腎機能や他の薬物治療とのバランス次第で副作用の出方が変わるため、定期的な血液検査が欠かせません。
ビタミンD製剤の注意点
ビタミンD製剤はカルシウムの吸収促進と副甲状腺ホルモンの抑制効果を狙う上で重要ですが、過剰に摂取すると高カルシウム血症を起こす可能性があります。
血液中のカルシウム値が急上昇すると、意識障害や脱水症状、腎機能の悪化などにつながるリスクがあるため、用量を厳密に管理します。
カルシミメティクスの副作用
カルシミメティクス(シナカルセトなど)は、副甲状腺にあるカルシウム受容体を刺激してホルモンの過剰分泌を抑える薬ですが、効果が高い一方で、吐き気や嘔吐、低カルシウム血症、低リン血症などを招くことがあります。
慢性腎臓病で透析を受けている患者さんは、透析条件や他の薬と組み合わせる形になるため、身体への影響を丁寧にモニタリングが必要です。
カルシミメティクスの副作用
| 症状 | 背景 |
|---|---|
| 吐き気・嘔吐 | 急激なカルシウム値変動に反応する |
| 低カルシウム血症 | ホルモン抑制が強く出すぎる場合がある |
| 低リン血症 | カルシウムとリンのバランス調整が崩れる |
外科的治療のデメリット
外科的に副甲状腺を摘出する場合、手術の侵襲や麻酔リスクが伴います。
術後には低カルシウム血症や甲状腺機能への影響が生じる可能性もあり、病院での経過観察や再手術の検討が必要になるケースもあります。
外科的治療は薬物療法でコントロールできない場合の選択肢として有用ですが、メリットと同時にリスクを受け止めることが大切です。
治療に伴う精神的・経済的負担
長期にわたる通院や検査、複数の薬を服用する状況は、患者さんにとって精神的な負担になることがあります。
仕事や家庭との両立、通院にかかる時間や費用など、多面的な悩みが生じる可能性がありますが、主治医や医療スタッフと相談して治療計画を柔軟に組み立てることで、日常生活とのバランスを見出しやすいでしょう。
続発性副甲状腺機能亢進症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
血液検査や画像検査の費用目安
続発性副甲状腺機能亢進症では、血液検査(カルシウム、リン、PTHなど)や骨密度測定、超音波検査、CTなど多岐にわたる検査が必要になる可能性があります。
保険適用後の自己負担額(3割負担の場合)の目安としては、血液検査が1,000円~3,000円、骨密度検査が1,000円前後、CT検査が5,000円~8,000円程度です。
検査費用
| 検査項目 | 保険適用後の自己負担目安 |
|---|---|
| 血液検査 | 約1,000円~3,000円 |
| 骨密度測定 | 約1,000円 |
| 超音波検査 | 約1,500円~3,000円 |
| CT検査 | 約5,000円~8,000円 |
状況によっては複数の検査をまとめて行うため、合計金額がさらに増える可能性もあります。
薬物治療の費用
リン吸着薬やビタミンD製剤、カルシミメティクスなどが保険適用されるため、定期的な処方を受けながら治療を続けることになります。
薬の種類や用量によって変動は大きいものの、1か月あたりの自己負担額(3割負担の場合)の目安としては数千円から1万円程度です。カルシミメティクスのようにやや高価な薬を使うと、負担額が増える傾向があります。
薬物治療にかかる主な費用
- リン吸着薬:1か月あたり数千円前後
- ビタミンD製剤:1か月あたり1,000円~2,000円程度
- カルシミメティクス:1か月あたり5,000円~1万円程度
継続的に服用する必要があるため、効果と費用を考慮しながら薬物選択を行うことが多いです。
手術費用
副甲状腺全摘や一部摘出などの手術に踏み切る場合、保険適用になるので高額な自費手術にはなりませんが、入院費や手術費、術後の管理費を合わせると自己負担額として10万円前後から20万円程度になります。
手術費用の目安
| 項目 | 自己負担額(3割負担の場合)の例 |
|---|---|
| 手術費(摘出術) | 5万円~10万円前後 |
| 入院費用(数日~1週間程度) | 5万円~10万円程度 |
| 術後フォローアップ | 検査費や通院費が追加 |
術前には血液検査や画像診断などを集中的に行うため、検査代も含めた総額を把握しておくと、精神的な負担を軽減しやすいでしょう。
以上
参考文献
Komaba H, Taniguchi M, Wada A, Iseki K, Tsubakihara Y, Fukagawa M. Parathyroidectomy and survival among Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Kidney international. 2015 Aug 1;88(2):350-9.
Fukagawa M, Kazama JJ, Shigematsu T. Management of patients with advanced secondary hyperparathyroidism: the Japanese approach. Nephrology Dialysis Transplantation. 2002 Sep 1;17(9):1553-7.
Komaba H, Kakuta T, Fukagawa M. Management of secondary hyperparathyroidism: how and why?. Clinical and experimental nephrology. 2017 Mar;21:37-45.
Tominaga Y. Current status of parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidism in Japan. NDT plus. 2008 Aug 1;1(suppl_3):iii35-8.
Tominaga Y, Kakuta T, Yasunaga C, Nakamura M, Kadokura Y, Tahara H. Evaluation of parathyroidectomy for secondary and tertiary hyperparathyroidism by the Parathyroid Surgeons’ Society of Japan. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2016 Feb;20(1):6-11.
Komaba H, Moriwaki K, Goto S, Yamada S, Taniguchi M, Kakuta T, Kamae I, Fukagawa M. Cost-effectiveness of cinacalcet hydrochloride for hemodialysis patients with severe secondary hyperparathyroidism in Japan. American journal of kidney diseases. 2012 Aug 1;60(2):262-71.
Akizawa T, Kido R, Fukagawa M, Onishi Y, Yamaguchi T, Hasegawa T, Fukuhara S, Kurokawa K. Decreases in PTH in Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism: associations with changing practice patterns. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2011 Sep 1;6(9):2280-8.
Koizumi M, Komaba H, Nakanishi S, Fujimori A, Fukagawa M. Cinacalcet treatment and serum FGF23 levels in haemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Nephrology Dialysis Transplantation. 2012 Feb 1;27(2):784-90.
Kazama JJ. Japanese Society of Dialysis Therapy treatment guidelines for secondary hyperparathyroidism. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2007 Oct;11:S44-7.
Tsukamoto Y, Hanaoka M, Matsuo T, Saruta T, Nomura M, Takahashi Y. Effect of 22-oxacalcitriol on bone histology of hemodialyzed patients with severe secondary hyperparathyroidism. American journal of kidney diseases. 2000 Mar 1;35(3):458-64.