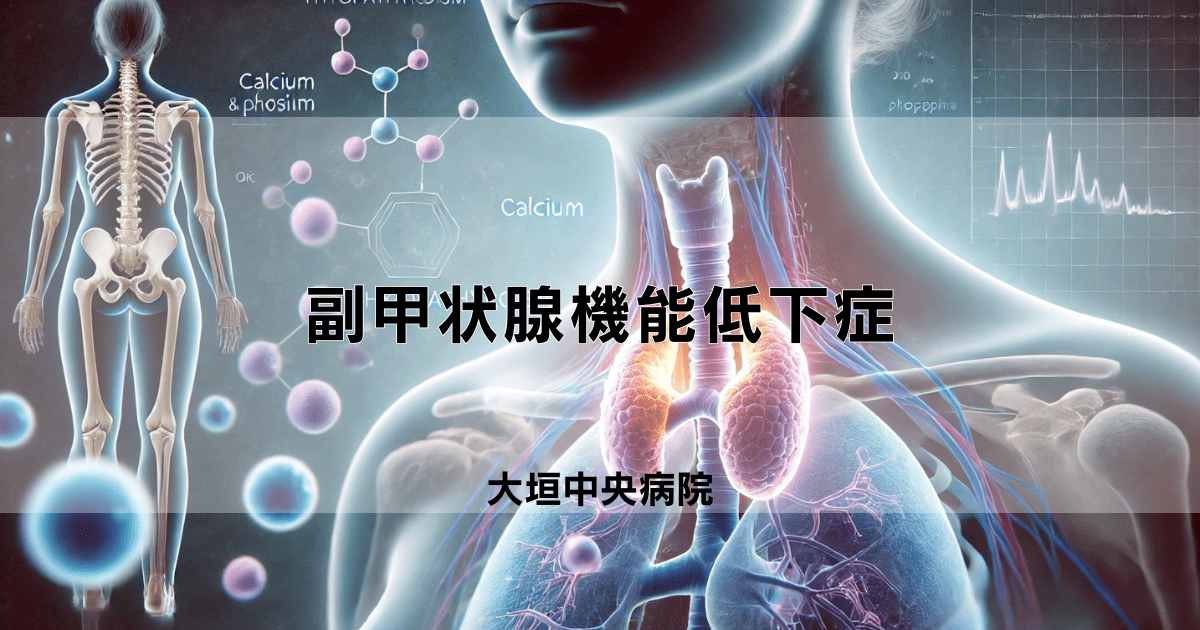副甲状腺機能低下症とは、副甲状腺から分泌されるパラトルモン(PTH)の量が低下し、血液中のカルシウム濃度が下がりやすくなる病気です。
カルシウムは骨や歯の健康を支えるだけでなく、筋肉の収縮や神経の伝達など体の働きを幅広く支えるため、カルシウム濃度の異常は身体に多様な影響を与えます。
血中カルシウムが不足した状態が長く続くと、筋肉のけいれんや知覚異常、骨の脆弱化などが生じる可能性があります。
近年、手術や他の病気などの影響で副甲状腺機能低下症を発症する方が増えており、早めに病態を認識し、検査と治療を受けることが重要です。
副甲状腺機能低下症の病型
副甲状腺機能低下症には、先天性の要因や手術後の合併症など、いくつかの病型があり、どの病型であっても、パラトルモンの分泌不足が原因となり、血中カルシウム量の低下を起こします。
先天性副甲状腺機能低下症
生まれつきパラトルモンの分泌が不十分な状態で、遺伝子変異などが背景にあり、幼少期から発症することがあります。先天性の場合、早期から低カルシウム血症が続き、成長期の骨や歯の形成にも影響を及ぼします。
特発性副甲状腺機能低下症
遺伝子異常が明確には判明しない一方で、副甲状腺がうまく機能しない病型です。特定の自己免疫疾患が関与している可能性も指摘され、別の疾患との複合的な症状として副甲状腺機能低下が起きる場合もあります。
手術後副甲状腺機能低下症
甲状腺全摘など、頸部の外科手術によって副甲状腺を傷つけたり、血流が途絶したりすることで起こります。
甲状腺がんの手術や甲状腺機能亢進症の手術後によくみられる病型で、術後に低カルシウム血症が持続すると、このタイプの副甲状腺機能低下症と診断されることがあります。
二次性副甲状腺機能低下症
腎不全やビタミンD欠乏など、他の疾患や栄養バランスの乱れが原因で副甲状腺ホルモンが十分に分泌されなくなるものです。
腎臓の機能が低下すると、カルシウムの再吸収やビタミンDの活性化に影響が及び、結果としてパラトルモンの動きが悪くなるケースがあります。
| 病型 | 特徴 | 代表的な背景 |
|---|---|---|
| 先天性 | 生まれつき副甲状腺が働きにくい | 遺伝子変異など |
| 特発性 | 理由がはっきりしないが副甲状腺機能が落ちる | 自己免疫異常が疑われることがある |
| 手術後 | 頸部手術による副甲状腺の損傷や血流障害による | 甲状腺摘出など |
| 二次性 | 他の病気に伴って副甲状腺ホルモンが分泌されにくくなる | 腎不全、ビタミンD欠乏など |
各病型を知ることで、自分の症状や背景に合ったアプローチを検討しやすくなります。ただし、実際の診断では専門的な検査と医師の判断が必要になるため、自分だけで判断せず、不安がある場合は早めに医療機関を受診してください。
副甲状腺機能低下症の症状
副甲状腺機能低下症の主な問題は、血中カルシウム値の低下による多彩な症状で、最初は軽微な症状から始まることがありますが、放置すると深刻な状態に移行する可能性があります。
治療を受ける前に、どのような兆候を自覚しておくべきか知っておくことはとても重要です。
低カルシウム血症による筋肉症状
カルシウム不足によって筋肉が過敏になり、手足や顔面のけいれん(テタニー)を引き起こすことがあります。また、軽度の痺れやこわばりを感じることもあり、特に指先や口の周囲にピリピリとした感覚が出やすいです。
日常生活では、ペンを持ちづらくなったり、スマートフォンの操作がうまくいかなくなったりするケースもあります。
神経症状や精神症状
カルシウムは神経系の働きにも関係し、副甲状腺機能低下症の患者さんは、集中力の低下や不安感、倦怠感などを感じ、時に気分が落ち込みやすくなったり、不安定な精神状態になることもあるため、心のケアが必要になる場合もあります。
骨や歯への影響
骨や歯はカルシウムによって構成される部分が多いため、血中カルシウムが不足すると骨からカルシウムを補おうとする動きが起こります。
ただし、副甲状腺機能低下症ではPTHが十分に分泌されないため、その調整がうまく働かず、骨密度が低下したり歯のエナメル質が弱くなったりすることがあります。
皮膚や髪、爪の変化
カルシウムとビタミンDのバランスが崩れると、皮膚や髪、爪の状態にも変化が現れ、髪が抜けやすくなったり、爪が割れやすくなったりするケースがあります。
皮膚が乾燥しやすくなり、ひび割れや肌荒れといったトラブルを抱える患者さんも少なくありません。
このように症状が多岐にわたるため、「単なる疲れ」や「栄養不足」と見誤りやすいですが、そうした誤解を避けるために、次のような点を日常生活で振り返ると発見が早くなります。
- 指先の痺れや口周りの違和感が長引いている
- 筋肉がピクピクと痙攣する感覚がしばしば起こる
- 意欲の低下や不安感、集中力の欠如が続いている
- 爪が割れやすい、髪が抜けやすい
- 歯がしみやすくなったり、歯のトラブルが増えたりしている
症状の強さや組み合わせは個人差が大きいですが、こうしたサインが複数当てはまり、数日から数週間の間に繰り返し続くなら、一度医療機関で検査を受けることを考えたほうが良いでしょう。
| 症状カテゴリ | 具体的な例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 筋肉症状 | テタニー、痺れ、こわばり | ペンをうまく持てない、細かい作業がしづらい |
| 神経・精神症状 | 不安感、うつ気味、集中力低下 | 動悸や不眠をともなうことがある |
| 骨・歯の異常 | 骨折しやすい、歯がしみる | 長期的に骨密度が下がり、骨粗鬆症リスクが高まる可能性がある |
| 皮膚・毛髪・爪の変化 | 髪が抜けやすい、爪が割れやすい | おしゃれや身だしなみに気を配っていてもトラブルが増えることがある |
症状の把握は治療の第一歩で、一つひとつは小さな違和感でも、複数の部位にわたって問題が起こっている場合は副甲状腺機能低下症を含めた内分泌系のトラブルを疑い、速やかに専門家のアドバイスを受けることが大切です。
原因
副甲状腺機能低下症にはさまざまな原因がありますが、主に副甲状腺がうまくパラトルモンを分泌できなくなることで起こります。
背景には先天的な問題や外科手術の影響、自己免疫反応、他の疾患が絡むことがあり、原因究明は治療の方向性を決めるうえで非常に重要です。
遺伝的要因
先天性副甲状腺機能低下症を引き起こす遺伝子変異がいくつか知られており、家系内で同じような症状を持つ人がいる場合は遺伝的要因を考えます。
ただし、遺伝子検査が可能な医療機関は限られる場合があるため、症状や血液検査の結果、家族の病歴などを総合的にみて診断を進めます。
手術による影響
甲状腺の手術や、頸部における他の手術(副甲状腺切除を伴う腫瘍の摘出など)によって副甲状腺が物理的に傷ついたり、血管の流れが悪くなったりしてパラトルモン分泌能力が失われることがあります。
特に甲状腺がんや重度の甲状腺機能亢進症などで全摘手術を受けた後に、副甲状腺機能低下症を発症するケースが少なくありません。
自己免疫疾患
自己免疫疾患は、身体が自分自身の組織を外敵と誤認して攻撃する状態で、副甲状腺に対する自己抗体が生じると、パラトルモン分泌細胞が破壊される可能性があります。
自己免疫性甲状腺炎(橋本病やバセドウ病)を抱えている人が、副甲状腺機能低下症を合併することもあるため、注意が必要です。
他の内分泌異常や栄養状態
副甲状腺機能低下症は、単独ではなく他のホルモン異常とともに起こる場合があり、慢性腎不全があるとカルシウムとリンのバランスが乱れ、パラトルモンの分泌が抑えられることがあります。
また、ビタミンDの摂取不足や吸収障害があるとカルシウムバランスに影響を与え、副甲状腺が十分に機能しなくなります。
- 甲状腺手術や頸部手術の既往がある
- 自己免疫疾患(橋本病や全身性エリテマトーデスなど)がある
- 長期的な腎臓病や消化器の疾患でビタミンD不足が懸念される
- 家族や近親者に同様の病気を持つ人がいる
こうした項目に当てはまる場合は、副甲状腺機能低下症のリスクを考慮したうえで定期的な検査を行い、早期に原因を把握することが大切です。
| 主な原因 | 具体例 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 遺伝的要因 | 先天性副甲状腺機能低下症 | 遺伝子異常によるパラトルモン分泌の障害 |
| 手術による影響 | 甲状腺全摘、頸部腫瘍摘出など | 術中の副甲状腺損傷や血流障害 |
| 自己免疫疾患 | 副甲状腺に対する自己抗体 | 橋本病やバセドウ病など甲状腺疾患との合併の可能性がある |
| 他の内分泌異常など | 腎不全、ビタミンD欠乏 | カルシウム・リン代謝異常による連鎖的な副甲状腺機能低下 |
原因は一人ひとり異なりますが、手術歴があるのか、他のホルモン異常を抱えているのか、あるいは自己免疫反応が疑われるのかといった点を確認し、総合的に判断することが重要です。
医師はこれらの要因を踏まえて必要な検査を選択し、治療につなげていきます。
検査・チェック方法
副甲状腺機能低下症を診断するには、血液検査や画像検査、時には遺伝子検査などを組み合わせて包括的に調べることが必要です。
カルシウム値が低いだけでは確定できず、パラトルモンの分泌状態やリン、マグネシウムなどの値も確認しながら、原因を特定していきます。
血液検査によるホルモン・電解質チェック
副甲状腺機能低下症を疑ったとき、医師はまず血液検査でカルシウム値を測り、同時にパラトルモン値(PTH)やリン、マグネシウム、ビタミンDなどを測る場合が一般的です。
カルシウムだけでなく、これらの値を総合的に見ることで、副甲状腺機能低下症であるか、他の内分泌異常が潜んでいるかを検討します。
このタイミングで、腎機能や肝機能をチェックすることもよくあり、カルシウムのバランスは腎臓や肝臓の働きと連動しているため、他の臓器の状態を把握することも診断には重要です。
| 検査項目 | 意義 |
|---|---|
| 血清カルシウム | 低カルシウム血症の有無を評価 |
| PTH(パラトルモン) | 副甲状腺の分泌能力を直接反映 |
| 血清リン | カルシウムとのバランスを確認、二次性低下症の可能性も |
| マグネシウム | 神経や筋肉の機能に関与し、パラトルモン分泌にも関連 |
| ビタミンD | カルシウム吸収に重要、欠乏していると症状が悪化しやすい |
画像検査(エコーやCT、MRI)
副甲状腺の形態や腫瘍、血流の状態を調べるために、超音波検査(エコー)やCT、MRIが用いられることがあり、手術歴がある場合や腫瘍の可能性がある場合に画像検査が有効です。
副甲状腺の大きさや位置関係を把握しておくと、手術で取り除かれたかどうか、あるいは血管の状態が原因で分泌が落ちていないかを推測できます。
尿検査
カルシウムやリンが尿中にどの程度排泄されているかを調べることも、病態把握の一助となり、血液検査と合わせて尿検査を行うことで、体内のカルシウムバランス全体をより正確に掴めます。
慢性腎不全や他の代謝異常が疑われる場合は、尿検査の結果が治療方針を検討するうえで役立ちます。
遺伝子検査
先天性副甲状腺機能低下症が疑われる場合や、特定の遺伝子異常が関与している可能性が高い場合は、遺伝子検査を提案されることがあります。
ただし、遺伝子検査は特殊な設備が必要であること、保険診療の範囲外になる可能性があることなどから、すべての患者さんに行うわけではなく、医師と相談しながら必要性を検討すると良いでしょう。
検査の流れ
- 医師が問診と視診で症状の度合いや背景(手術歴、他の疾患)を確かめる
- 血液検査、尿検査でカルシウムやPTHなどを測定する
- 必要に応じてエコー、CT、MRIなどの画像検査を追加し、副甲状腺の状態や他の臓器の異常を確認する
- 特殊なケースでは遺伝子検査も考慮する
問診と検査結果を組み合わせることで正確な診断に近づき、副甲状腺機能低下症の疑いがあるとわかったら、これらの検査を受けることで原因の特定と治療方針の決定がスムーズになります。
- 血液検査でPTHが低下している
- カルシウム値も基準値より低い
- リンが基準値より高いことがある
- マグネシウムやビタミンDに異常がないかも確認
- 画像検査で副甲状腺が小さくなっている、あるいは血流が減少している
上記のような結果が出れば、副甲状腺機能低下症の可能性が高まります。一部、似た症状を示す別の内分泌疾患(偽性副甲状腺機能低下症など)も考えられるため、専門的な知識を持った医師との相談が必要です。
副甲状腺機能低下症の治療方法と治療薬について
副甲状腺機能低下症の主な治療目的は、カルシウムバランスを整えて症状を軽減し、合併症のリスクを抑えることです。
治療では、カルシウム製剤やビタミンD製剤の内服が中心となり、必要に応じて合併症対策を行い、病型によっては手術の検討やその他ホルモン療法を組み合わせることもあります。
カルシウム製剤の内服
副甲状腺機能低下症で不足しがちな血中カルシウムを補うために、カルシウム製剤の内服を行い、炭酸カルシウムやクエン酸カルシウムなどがよく使われ、食事のタイミングにあわせて服用します。
カルシウム製剤は吸収率に個人差があるため、医師は血液検査の結果を見ながら用量を調節することが大切です。
| カルシウム製剤名 | 主な特徴 | 服用上の注意 |
|---|---|---|
| 炭酸カルシウム | 一般的に処方される | 食事中や食後に飲むことが推奨される |
| クエン酸カルシウム | 胃酸が少ない人に適している場合がある | 吸収率が高いが、個人差に注意が必要 |
| グルコン酸カルシウム | 点滴など注射剤にも使用される | 点滴や静注の場合は医療機関でモニタリングを行う |
活性型ビタミンD製剤
カルシウムの吸収を助けるために、活性型ビタミンD製剤(アルファカルシドールやカルシトリオールなど)を併用することがよくあります。
副甲状腺機能低下症の場合、パラトルモンが不足しているため、腸管からカルシウムを取り込みづらい状況です。活性型ビタミンD製剤を内服すると、腸管でのカルシウム吸収効率が上がり、血中カルシウムを維持しやすくなります。
パラトルモン補充療法
近年、重症の副甲状腺機能低下症や、長期的なカルシウム製剤とビタミンD製剤だけではコントロールが難しい場合に、パラトルモン(PTH)を補充する治療も選択肢です。
パラトルモン製剤は注射で投与するため、比較的重症な方が対象となり、日本では適用条件が限られている場合があるため、医師と相談しながら導入を検討します。
他のホルモン療法や手術
副甲状腺機能低下症が、腎不全や甲状腺の病気などと深く関係している場合は、併発疾患に対して別のホルモン療法を行ったり、必要であれば外科的処置を行ったりします。
特に手術後に生じた副甲状腺機能低下症で一部の副甲状腺組織が残っている場合、再建手術が検討されることもありますが、実際に行うかどうかは患者さんの症状やリスクとの兼ね合いで総合的に判断します。
- カルシウム製剤とビタミンD製剤を組み合わせて血中カルシウムを維持
- 重症例ではパラトルモン製剤の注射を導入
- 原因となっている合併症や手術歴がある場合は追加治療を検討
副甲状腺機能低下症の治療は多角的ですが、基本的には薬物療法を軸とし、生活習慣の改善や定期的なモニタリングを続けていくことが大切です。
治療期間
治療期間は、原因や病型、症状の重さなどによって変化します。
先天性や手術後の完全な損傷によるものは、長期または一生にわたりカルシウム補充などが必要になることが多く、自己免疫性や一時的な副甲状腺障害の場合は、ある程度の期間で機能が回復する場合も考えられます。
先天性や手術後などの長期的治療
先天性副甲状腺機能低下症の場合は、生涯を通して経口カルシウム製剤やビタミンD製剤を服用しながら症状をコントロールする方が多いです。
骨の成長やホルモンのバランスが変化する思春期や、更年期以降に治療方針を見直すタイミングが生じることがあります。手術後に副甲状腺が永久的に機能を失ったケースも似たような流れで、根気強い治療と定期検査が必要です。
軽度や可逆性のある副甲状腺機能低下症
一時的に副甲状腺の機能が落ちている場合や、栄養状態の改善、別のホルモン治療の導入によって回復が見込める場合は、短期間で薬の量を調整しながら最終的に治療を終了できる可能性があります。
ただし、自己判断で薬をやめると再び症状が出現することがあるため、医師の指示に従って慎重に経過観察を行います。
再発リスクと定期検査
手術による損傷や自己免疫疾患などは再発リスクを伴うことがあり、治療を一旦終えても定期的な血液検査が必要です。カルシウム濃度が再び下がっていないかを定期的にチェックしておけば、万が一再発しても迅速に対応できます。
| 治療期間のタイプ | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 短期的(数週間~数か月) | 可逆的な栄養不良やホルモンバランスの乱れによるもの | 症状が改善しても定期的な検査で確認しながら薬を減量 |
| 中期的(数か月~数年) | 自己免疫疾患の寛解・再燃と関連 | 症状が落ち着いた後も再燃を想定して経過観察が必要 |
| 長期的(一生涯) | 先天性、手術で完全に副甲状腺を失ったケース | ライフステージごとに治療内容や薬の量を見直す場合がある |
治療期間は個人差が大きく、年齢や性別、併存症の有無によっても変わります。自分の病型や治療方針を医師と十分に話し合い、定期検査を受けながら生活習慣を含めたトータルでの管理を行うことが大切です。
- 自分の症状や血液検査の結果を定期的に記録して変化を見逃さない
- 医師から処方された薬を自己判断で中断しない
- 症状の変化に気づいたら早めに受診して薬の調整などを検討する
こうした日常の意識が治療期間の長さや質に大きな影響を与えます。
副甲状腺機能低下症薬の副作用や治療のデメリットについて
副甲状腺機能低下症の治療では、カルシウム製剤やビタミンD製剤、必要に応じてパラトルモン補充療法などを使いますが、副作用が起こる可能性があります。
治療を継続するときは、副作用のリスクと症状改善のメリットを比較しながら、定期的なモニタリングを実施してバランスを保つことが大切です。
カルシウム製剤の副作用
カルシウム製剤を過剰に摂取すると、高カルシウム血症になるリスクがあり、吐き気や便秘、口の渇き、頻尿、稀に意識障害などを起こす可能性があります。腎機能に問題がある人や利尿剤を使っている人は、慎重なモニタリングが必要です。
また、カルシウム製剤は腸の動きを変化させることがあるため、便秘や消化不良を感じる場合があります。
ビタミンD製剤の副作用
ビタミンD製剤も、過剰摂取で高カルシウム血症を起こすことがあります。さらに、サプリメントや他のビタミン剤を併用している場合は、総摂取量が増えすぎる可能性があるため、医師や薬剤師にきちんと相談してください。
長期的に過剰投与された場合、腎臓や血管への石灰化リスクも指摘されています。
| 薬剤 | 主な副作用 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| カルシウム製剤 | 高カルシウム血症、便秘など | 定期的な血液検査が必要 |
| ビタミンD製剤 | 高カルシウム血症、腎機能への影響 | 他のサプリと重複しないよう注意 |
| パラトルモン製剤 | 注射部位の痛み、過度の骨吸収 | 骨密度の推移を定期的に確認 |
パラトルモン補充療法のデメリット
パラトルモン補充製剤は注射での投与が必要になり、自己注射を行う場合もあります。注射部位の痛みや腫れが起こることがあり、注射のタイミングをきちんと守らないとカルシウム値が大きく変動してしまう恐れがあります。
また、長期的に使用すると骨吸収が進むリスクが指摘されることがあるため、骨粗鬆症や骨折リスクの観点から定期的な骨密度測定が必要です。
治療の継続による精神的負担
副甲状腺機能低下症の治療は、慢性的かつ長期にわたることが多く、薬の副作用だけでなく精神的な負担も無視できません。服薬管理が煩雑になったり、副作用の兆候を常に気にしなければならないことがストレスにつながる場合があります。
医師とのコミュニケーションを密にして、疑問や不安を早めに解消することが治療継続のうえで大切です。
- 薬の効果だけでなく、副作用リスクの説明を受ける
- 血液検査や骨密度検査を定期的に受け、早めに異常を察知する
- 不安や疑問があれば医師や薬剤師に相談し、薬の使い方を調整する
副甲状腺機能低下症の治療にはメリットとデメリットの両面があり、副作用を予防しながら症状を抑えるために、医師の指示に沿った継続的なモニタリングが重要です。
副甲状腺機能低下症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
血液検査費用の目安
カルシウム値、PTH、リン、マグネシウム、ビタミンDなどを調べる基本的な血液検査は、保険適用後でおおよそ1,000~3,000円程度です。
検査項目が増えたり、特殊なホルモンや遺伝子検査などを追加する場合は、さらに費用が上がる可能性があります。
薬剤費用の目安
カルシウム製剤やビタミンD製剤は一般的な種類であれば1か月あたり数百円から1,500円程度になることが多いです。パラトルモン製剤を使う場合は、注射の方法や頻度にもよりますが、月あたり数千円から1万円程度になるケースがあります。
| 治療内容 | 費用目安(保険適用後) | 備考 |
|---|---|---|
| 血液検査(基本項目) | 1,000~3,000円前後 | 検査項目が多いと費用は上がる |
| カルシウム製剤(経口) | 1か月あたり500~1,500円程度 | 用量や製剤の種類によって変動 |
| ビタミンD製剤(経口) | 1か月あたり500~1,500円程度 | 活性型ビタミンDの場合はやや高め |
| パラトルモン製剤(注射) | 1か月あたり数千円~1万円程度 | 病状や注射頻度による |
画像検査の費用
エコーやCT、MRIといった画像検査は、保険適用後でも数千円から数万円程度かかります。
副甲状腺機能低下症の診断や原因特定のために行う画像検査の頻度はそこまで高くありませんが、精密な検査を複数回受ける場合は費用面にも注意が必要です。
以上
参考文献
Takatani R, Kubota T, Minagawa M, Inoue D, Fukumoto S, Ozono K, Nakamura Y. Prevalence of pseudohypoparathyroidism and nonsurgical hypoparathyroidism in Japan in 2017: A nationwide survey. Journal of Epidemiology. 2023 Nov 5;33(11):569-73.
Hasegawa M, Sakakibara Y, Takeuchi Y, Sugitani I, Ozono K, Castriota F, Ayodele O, Sakaguchi M. Prevalence and characteristics of postoperative and nonoperative chronic hypoparathyroidism in Japan: a nationwide retrospective analysis. JBMR plus. 2024 Sep;8(9):ziae100.
Akizawa T, Kinugasa E, Akiba T, Tsukamoto Y, Kurokawa K. Incidence and clinical characteristics of hypoparathyroidism in dialysis patients. Kidney International Supplement. 1997 Nov 2(62).
Takahashi T, Yamazaki K, Shodo R, Ueki Y, Horii A. Actual prevalence of hypoparathyroidism after total thyroidectomy: a health insurance claims-database study. Endocrine. 2022 Oct;78(1):151-8.
Nakamura Y, Matsumoto T, Tamakoshi A, Kawamura T, Seino Y, Kasuga M, Yanagawa H, Ohno Y. Prevalence of idiopathic hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism in Japan. Journal of Epidemiology. 2000;10(1):29-33.
Ubara Y, Fushimi T, Tagami T, Sawa N, Hoshino J, Yokota M, Katori H, Takemoto F, Hara S. Histomorphometric features of bone in patients with primary and secondary hypoparathyroidism. Kidney international. 2003 May 1;63(5):1809-16.
Abate EG, Clarke BL. Review of hypoparathyroidism. Frontiers in endocrinology. 2017 Jan 16;7:172.
Yang YY, Deng YH, Sun LH, Rejnmark L, Wang L, Pietschmann P, Glüer CC, A Khan A, Minisola S, Liu JM. Hypoparathyroidism: Similarities and differences between Western and Eastern countries. Osteoporosis International. 2025 Jan 8:1-2.
Abe S, Tojo K, Ichida K, Shigematsu T, HASEGAWA T, MORITA M, SAKAI O. A rare case of idiopathic hypoparathyroidism with varied neurological manifestations. Internal medicine. 1996;35(2):129-34.
Yashiro T, OKAMOTO T, TANAKA R, ITO K, HARA H, YAMASHITA T, KANAJI Y, KODAMA T, ITO Y, OBARA T, FUJIMOTO Y. Prevalence of chondrocalcinosis in patients with primary hyperparathyroidism in Japan. Endocrinologia japonica. 1991;38(5):457-64.