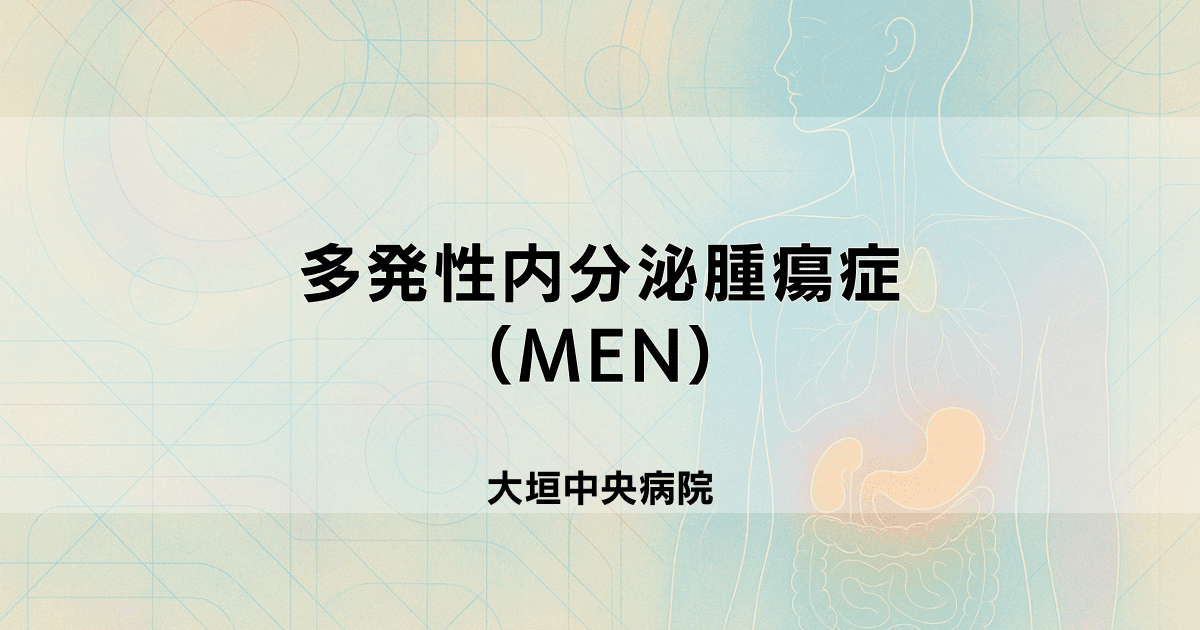多発性内分泌腫瘍症(MEN)とは、複数の内分泌腺に腫瘍が同時、あるいは時間をずらして生じる先天的な体質による疾患です。
ホルモンの分泌を担うさまざまな臓器が影響を受ける可能性があるため、甲状腺や副甲状腺、膵臓などの異常をきっかけに、多彩な症状を示す点が大きな特徴となります。
家族内で連鎖的に発症するケースが多く認められ、早期発見と早期の治療計画によって、患者のQOL向上をめざすことが大切です。
病型
複数の内分泌臓器に腫瘍が発生する多発性内分泌腫瘍症には、遺伝子変異の違いなどに基づいていくつかの病型があります。
MEN1型(Wermer症候群)
MEN1型は、主に副甲状腺、膵臓、下垂体の3つの内分泌腺に腫瘍が発生しやすいタイプで、副甲状腺の過形成や腺腫が起こることで、高カルシウム血症や骨量減少などを引き起こす場合があります。
膵臓にできる腫瘍では、インスリノーマやガストリノーマと呼ばれるホルモン産生腫瘍を生じることが多く、低血糖や胃酸分泌過剰などの症状につながることがあります。
下垂体腺腫によって、プロラクチンや成長ホルモンなどが過剰に分泌し、月経異常や巨人症などをもたらす可能性もあります。
また、早期に副甲状腺機能亢進が見つかると、カリウムやカルシウムバランスの異常が深刻化するリスクを下げやすいです。
MEN1型に関わる代表的な腫瘍
| 腫瘍の種類 | 主な症状の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 副甲状腺腺腫 | 高カルシウム血症、骨粗鬆症傾向 | 甲状腺機能異常との混同に注意 |
| 膵内分泌腫瘍 | 低血糖、胃潰瘍 | 腫瘍の種類ごとに症状が異なる |
| 下垂体腺腫 | 月経異常、巨人症、視野異常 | ホルモン過剰分泌が大きい場合は要対処 |
MEN2A型(Sipple症候群)
MEN2A型は、RET遺伝子の変異によって生じることが多く、甲状腺髄様癌、副甲状腺機能亢進症などが組み合わさるタイプです。
MEN2A型の特徴的な点として、甲状腺髄様癌を発症する家系が多いことが挙げられ、遺伝子検査によって家族歴が確認される場合、成人前の段階で甲状腺摘出手術を行うことを推奨する専門医もいます。
MEN2B型
MEN2B型もRET遺伝子の変異が原因となることが多く、甲状腺髄様癌などとともに、粘膜神経腫、骨格異常、副腎髄質腫瘍(副腎腫瘍)などが目立つタイプです。
特徴的な体つきや容貌、唇や舌に神経腫が生じることで、幼少期から症状を自覚しやすい場合があります。
MEN2B型の患者さんは、内分泌症状だけでなく、粘膜神経腫による見た目の変化や頑固な便秘などの消化管症状に悩むことがあります。
成長期の子どもの段階で診断されるケースもあるため、骨格形成と並行して多角的に治療方針を検討することが必要です。
その他の稀な病型
MEN1型やMEN2型以外にも、臨床的には非常に稀な病型や、はっきりした遺伝子変異が同定されていないタイプの多発性内分泌腫瘍症が報告されています。
きわめてまれな例として、副腎皮質や卵巣など、内分泌的な機能を持つ臓器に病変が起こるタイプもあり、診断が難航することがあります。
家族性に同様の腫瘍がみられるにもかかわらず、MEN1型やMEN2型の特有の遺伝子変異が確認できない状況もあるため、総合的な検査や診察が必要です。
MEN1型、MEN2A型、MEN2B型の発症年齢や主要な特徴
| 病型 | 発症年齢の目安 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| MEN1型 | 思春期~成人期 | 下垂体・副甲状腺・膵臓の腫瘍 |
| MEN2A型 | 幼少期~成人期 | 甲状腺髄様癌・副甲状腺・褳腎髄質腫瘍 |
| MEN2B型 | 幼少期~青年期 | 甲状腺髄様癌・褳腎髄質腫瘍・粘膜神経腫 |
多発性内分泌腫瘍症(MEN)の症状
多発性内分泌腫瘍症に伴う症状は、腫瘍が発生する臓器とホルモンの種類によって多岐にわたります。
病型ごとに特徴的な徴候はありますが、早期にははっきりした自覚症状がないこともあるため、いくつかの共通点や注意点を把握し、日頃から観察しておくことが大切です。
ホルモン過剰分泌による症状
内分泌腫瘍がホルモンを過剰に分泌すると、血糖値や骨代謝、血圧、胃酸分泌などに影響が及び、副甲状腺の過形成や腺腫でパラトルモンが増加し、高カルシウム血症を起こすと、倦怠感や多飲多尿が目立ったり、骨がもろくなったりすることがあります。
膵内分泌腫瘍ではインスリノーマによる低血糖発作や、ガストリノーマによる重症の消化性潰瘍などが見られる可能性があります。
副腎髄質腫瘍(副腎腫瘍)の場合は、アドレナリンやノルアドレナリンが多量に産生され、血圧の急激な上昇や動悸、発汗過多などの自律神経症状が顕著です。
ホルモン過剰分泌に関わる主な症状
| 腫瘍部位 | 過剰分泌されるホルモン | 典型的な症状 |
|---|---|---|
| 副甲状腺 | パラトルモン | 骨量減少、腎結石、倦怠感 |
| 膵内分泌腫瘍 | インスリン、ガストリンなど | 低血糖、胃酸過剰、潰瘍 |
| 褳腎髄質腫瘍 | カテコールアミン類 | 血圧上昇、動悸、発汗 |
| 下垂体腺腫 | 成長ホルモン、プロラクチンなど | 巨人症、月経異常、視野障害 |
痛みや腫瘍による圧迫症状
内分泌腫瘍の一部は、サイズが大きくなるにつれて周囲の組織を圧迫し、痛みやしびれといった症状を生むことがあります。
下垂体腺腫が大きくなると、視神経を圧迫して視野の欠損を起こす場合があり、膵内分泌腫瘍が拡大すると胃や腸を圧迫して腹痛や嘔気につながることも考えられます。
全身倦怠感や体重変化
内分泌系のトラブルは、代謝全般に影響を与えやすいため、原因不明の疲労感や意欲低下、体重減少や体重増加などとして現れるケースもあります。
甲状腺機能の異常がある場合、交感神経系の乱れや基礎代謝の急変動が生じやすく、動悸や発汗といった症状に加え、精神的にも不安定になりやすい人も見受けられます。
日常生活で大きなストレスや生活習慣の乱れが見当たらないのに、明らかな疲労や体重変動が続く場合には、内分泌に関わる異常の可能性も疑ってみることが大切です。
症状に注意したいポイント
- 倦怠感が慢性化している
- 高血圧や低血糖がくり返される
- 胃潰瘍や骨粗鬆症などを若くして経験している
外見や成長への影響
小児期や思春期に多発性内分泌腫瘍症が起こると、成長ホルモンの分泌異常や甲状腺・副甲状腺機能の異常によって、骨格や体型の変化が目立つことがあります。
骨端線が閉じる前に成長ホルモンが過剰に分泌すると、手足が過度に大きくなったり、身長が急激に伸びたりする可能性があります。
成長期ではなく成人になってから成長ホルモンが増え過ぎると、先端肥大症という形で手足や顎が大きくなる現象が生じます。
甲状腺に腫瘍があると甲状腺ホルモンのバランスが乱れ、新陳代謝や体温調節、発育そのものに影響を及ぼすため、周囲が気づいてあげることも重要です。
症状の早期サイン
- 血糖値の乱高下や突然の低血糖発作
- 動悸や息切れ、急な血圧上昇
- 病的な骨密度低下や頻繁な骨折
- 過度な発汗や手足の大きさの変化
| 主な症状 | 関連する臓器やホルモン異常の例 | 早期発見のヒント |
|---|---|---|
| 骨の痛みや骨折 | 副甲状腺機能亢進(高カルシウム血症) | 通常より骨折が頻繁に起こる、レントゲンで骨密度低下が見つかる |
| 胃潰瘍や下痢 | ガストリノーマ、カルシトニン過剰など | 胃薬が効きにくい、腹痛や吐き気を繰り返す |
| 激しい動悸や発汗 | 褳腎髄質腫瘍(カテコールアミン過剰) | 発作的な高血圧や心拍数の上昇 |
多発性内分泌腫瘍症(MEN)の原因
多発性内分泌腫瘍症の多くは遺伝性の要因によって引き起こされ、MEN1型はMEN1遺伝子、MEN2A型とMEN2B型はRET遺伝子の変異が主な原因です。
遺伝的素因のメカニズム
MEN1型の原因とされるMEN1遺伝子は、腫瘍抑制遺伝子として働き、通常は細胞の増殖を抑える機能を担いますが、この遺伝子に変異が起こると、細胞分裂の制御がうまくいかなくなり、内分泌腺に腫瘍が生じやすくなります。
MEN2型(2A・2B型)の原因とされるRET遺伝子は、細胞の増殖と分化を調整する受容体型チロシンキナーゼをコードしており、変異によって細胞が過度に増殖するようになり、特定の臓器に腫瘍が集中的に発生し、特徴的な病型を示します。
MEN1遺伝子とRET遺伝子の特徴
| 遺伝子名 | 主な病型 | 働き |
|---|---|---|
| MEN1遺伝子 | MEN1型 | 腫瘍抑制に関連するタンパク質をコード |
| RET遺伝子 | MEN2A・MEN2B型 | 細胞増殖を促す受容体をコード |
両者とも常染色体優性遺伝の形式をとるため、片方の親から変異を受け継ぐだけでも発症リスクが高まります。
スポラディック(孤発性)のケース
多発性内分泌腫瘍症の多くは遺伝性ですが、まれに家族に同様の病歴がなくとも発症する孤発性ケースもあり、この場合、親からの遺伝子変異を受け継いでいないのに、本人の生殖細胞や体細胞で新たな変異が生じた可能性が考えられます。
孤発性のケースでも同じように複数の内分泌腺に腫瘍が発生し得るため、家族歴の有無にかかわらず症状や検査結果から多発性内分泌腫瘍症の疑いがある場合は、遺伝子検査を含めた対応をすることが多いです。
遺伝子以外の影響
遺伝的要因が主な発症メカニズムですが、生活習慣や環境要因が発症や症状の進行に無関係とは断定できません。
内分泌系はストレスや食生活、睡眠パターンなどから間接的な影響を受けることがあるため、もともと遺伝的リスクを抱えている人は、規則正しい生活や定期検診を継続しながら、自身の体調変化に敏感になっておくことが重要です。
| 発症要因 | 主な特徴 | 代表的な例 |
|---|---|---|
| 遺伝子変異 | 常染色体優性遺伝、MEN1遺伝子、RET遺伝子の変異など | MEN1型、MEN2A型、MEN2B型 |
| 孤発性の変異 | 親からの変異を受け継いでいなくても新規変異が生じる場合 | スポラディックMEN |
| 生活習慣・環境要因 | 遺伝子変異がない場合も腫瘍が偶発的に発生する可能性あり | ストレス、栄養バランスの乱れなど |
多発性内分泌腫瘍症(MEN)の検査・チェック方法
多発性内分泌腫瘍症を診断するためには、血液検査や画像検査、遺伝子検査など、さまざまな角度からアプローチすることが必要です。
血液検査やホルモン検査
多発性内分泌腫瘍症を疑う場合、ホルモン値の異常が確認できるかどうかが最初の目安です。
副甲状腺機能亢進の疑いがあれば血中カルシウムやパラトルモン量を測定し、膵内分泌腫瘍の可能性を探るときは血糖値やインスリン、ガストリンなどの値を詳細に調べます。
甲状腺髄様癌が想定される場合は、血中カルシトニン値やCEA(腫瘍マーカー)の測定が欠かせません。副腎髄質腫瘍が疑われるときは、血中や尿中のカテコールアミン類(アドレナリンやノルアドレナリンなど)の濃度を確認します。
血液・ホルモン検査項目
| 検査項目 | 主な対象疾患の例 | 検査の目的 |
|---|---|---|
| 血中カルシウム・PTH | 副甲状腺機能亢進 | 高カルシウム血症や副甲状腺腺腫の有無を確認 |
| 血糖値・インスリン・ガストリン | 膵内分泌腫瘍(インスリノーマ、ガストリノーマなど) | 低血糖や胃潰瘍の原因究明 |
| カルシトニン、CEA | 甲状腺髄様癌 | 腫瘍の活動性や早期発見の目安 |
| カテコールアミン類 | 褳腎髄質腫瘍 | 血圧上昇や動悸の原因調査 |
画像検査による腫瘍の位置特定
血液やホルモン検査で異常が認められた場合、次のステップとして画像検査を行い、腫瘍の存在や大きさ、位置を詳しく調べます。
超音波(エコー)検査やCT、MRIなどの画像診断機器を使い、甲状腺や副甲状腺、膵臓、下垂体、副腎などをチェックし、必要に応じて造影剤を使いながら細部まで確認することもあります。
遺伝子検査
多発性内分泌腫瘍症の診断のなかでは、遺伝子検査も重要な役割を果たし、MEN1型ではMEN1遺伝子、MEN2型ではRET遺伝子に変異があるかどうかを調べることで、確定診断に近づける場合があります。
多発性内分泌腫瘍症(MEN)の治療方法と治療薬について
多発性内分泌腫瘍症の治療は、腫瘍の種類や悪性度、ホルモン分泌の程度、患者さんの年齢や生活状況などによって決定します。
外科的治療
外科的なアプローチは、過剰にホルモンを分泌している腫瘍や悪性度の高い腫瘍を直接取り除く手段として有力で、たとえば、副甲状腺腺腫による高カルシウム血症が続いている場合には、副甲状腺の摘出手術が選択肢に入ります。
膵内分泌腫瘍(インスリノーマやガストリノーマなど)がはっきり局在している場合には、その部分を切除して低血糖や潰瘍などの症状を軽減します。
また、MEN2型で甲状腺髄様癌のリスクが高い場合、甲状腺全摘術を早期に考慮するケースがあり、こうした外科手術は、病巣そのものを取り除くため、ホルモン過剰分泌による症状の改善効果が得やすいです。
代表的な手術
| 手術名 | 対象となる腫瘍 | 目的 |
|---|---|---|
| 副甲状腺摘出術 | 副甲状腺腺腫・過形成 | 高カルシウム血症の改善 |
| 甲状腺全摘術 | 甲状腺髄様癌 | 甲状腺癌による転移や再発予防 |
| 膵腫瘍切除術(膵体尾部切除など) | インスリノーマ、ガストリノーマ | 低血糖や胃潰瘍などのホルモン異常症状の軽減 |
薬物治療
手術が困難なケースや、術後に再発を抑える目的などで薬物治療を組み合わせることがあります。
副甲状腺機能亢進では、血中カルシウムをコントロールする薬剤(ビスホスフォネート製剤など)を使って骨へのダメージを軽減したり、利尿剤を使ってカルシウム排泄を促進したりします。
膵内分泌腫瘍に対しては、ソマトスタチンアナログというホルモン分泌を抑える薬を用いる場合があり、胃酸過多や血糖値の乱高下をある程度コントロールが可能です。
副腎髄質腫瘍による高血圧に対しては、αブロッカーやβブロッカーといった降圧薬を使うことで、血圧や心拍数を安定化させます。
放射線治療や放射性同位元素治療
甲状腺髄様癌が進行しやすいケースや、転移が確認された場合には、放射線治療を併用することがありますが、甲状腺髄様癌は放射線への感受性が低いとされるため、十分な効果が得られるかどうかは腫瘍の性質によって異なります。
また、膵内分泌腫瘍などに対しては放射性同位元素を用いた治療(PRRT:ペプチド受容体放射性核種療法)が選択肢です。
術後や長期治療のモニタリング
多発性内分泌腫瘍症の特性上、いったん手術や薬物治療が成功しても、別の臓器に新たな腫瘍が生じたり、再発したりする可能性があるため、術後も定期的にホルモン値や画像検査を行い、必要に応じて薬物治療の種類や量を調整します。
甲状腺全摘術後は甲状腺ホルモンを補充する薬を使ってホルモンバランスを保つケースもあるので、自分に合った治療計画を定期的に見直すことが重要です。
| 治療法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 外科的治療 | 根本的に腫瘍を取り除く | 再発リスクや別の内分泌腺への発生リスクを考慮 |
| 薬物治療 | 症状やホルモン分泌をコントロールしやすい | 長期投与による副作用や効果不足の可能性 |
| 放射線治療・放射性同位元素治療 | 手術が困難なケースなどで腫瘍を縮小する場合がある | 腫瘍の性質によって効果にばらつきがある、周辺組織への影響 |
治療期間
多発性内分泌腫瘍症は、基本的に根治をめざす治療を行っても、再発の可能性や別の臓器への新たな腫瘍発生リスクがあり、長期的な視野で経過観察と治療の調整を続ける必要があります。
外科手術後の経過
手術を受ける場合、術後の回復期は数日から数週間ほどで大まかに落ち着くことがありますが、ホルモン補充の必要性や他の腫瘍発症リスクを考えると、その後も定期的な検査が欠かせません。
甲状腺全摘術を行った場合は、術後すぐに甲状腺ホルモンを補充するための薬を始める必要があり、投薬量を調整しながらホルモン状態を維持します。
副甲状腺を摘出した場合も、カルシウムやビタミンDなどの補給を検討しながら経過を観察します
薬物治療のスパン
多発性内分泌腫瘍症では、外科的治療だけでなく薬物治療も長期的に続けるケースが珍しくありません。
副腎髄質腫瘍による高血圧をコントロールするために、αブロッカーやβブロッカーを服用し続けることがありますし、ソマトスタチンアナログを定期的に注射し、膵内分泌腫瘍の症状をコントロールする場合もあります。
治療はすぐに終了するわけではなく、腫瘍の活動性が低くなるまで続くことがあり、ときに数年単位で継続する可能性があります。
再発・新規発生のリスク管理
MENでは「手術で腫瘍を取り除いたから終わり」ではなく、別の臓器に腫瘍が発生するリスクや、残存腫瘍の増大による再発リスクを常に念頭に置かなければなりません。
副甲状腺や膵内分泌腫瘍は再発の頻度が高いとされるため、数か月から半年ごとの定期検査でホルモン値や腫瘍マーカーの推移を確認することが必要です。
治療期間の流れ
| 時期 | 主なイベント・検査 | 治療の例 |
|---|---|---|
| 診断~治療開始 | 遺伝子検査、ホルモン検査など | 外科手術、薬物療法 |
| 術後~半年程度 | 傷口の回復、術後ホルモンバランス調整 | ホルモン補充、薬剤投与の開始や変更 |
| その後の長期フォロー | 定期的な血液検査、画像検査 | 必要に応じて再手術、薬物治療の継続・変更など |
生涯にわたるケアの重要性
多発性内分泌腫瘍症は、長く付き合うことが前提となる疾患で、再発や新たな腫瘍の発生だけでなく、加齢や生活習慣の変化に伴ってホルモンバランスも変動します。
自身の体調をよく理解し、専門医と情報交換しながら定期検査を受け続けることで、早期段階で対処しやすくなり、一時的に症状が落ち着いても、油断せず検査を怠らないよう心がけることが大切です。
多発性内分泌腫瘍症(MEN)薬の副作用や治療のデメリットについて
多発性内分泌腫瘍症の治療では、外科手術や薬物治療を組み合わせることが多いですが、治療にはそれぞれ副作用やデメリットがあります。
外科手術に伴うリスク
副甲状腺や甲状腺、膵臓などの外科手術を行うと、術後に他のホルモンバランスに影響が及ぶ場合や、手術部位の炎症、感染、出血などの一般的な外科的合併症が生じる可能性があります。
甲状腺摘出術を受けると、甲状腺ホルモンを自前で産生できなくなるため、生涯にわたり外部から補充することが必須です。
副甲状腺を広範囲に切除すると低カルシウム血症になりやすく、痺れや筋けいれんを起こすリスクが高くなるため、カルシウム剤やビタミンD製剤の服用が不可欠になるケースがあります。
薬物治療の副作用
ソマトスタチンアナログなどのホルモン抑制薬を使う場合、消化器症状(腹痛、下痢、脂肪便など)や注射部位の痛み、稀に血糖コントロールの乱れなどが生じる可能性があります。
αブロッカーやβブロッカーを使って高血圧をコントロールする場合は、めまいや脱力感、低血圧などが生じることがあり、日常生活での活動に支障をきたすケースもあります。
また、ビスホスフォネート製剤などカルシウム代謝を調整する薬剤は、長期投与による顎骨壊死などのリスクを少数ながら報告しており、定期的な歯科検診や注意が必要です。
治療選択時のバランス
外科手術のリスクを嫌って薬物療法を選んだ場合でも、腫瘍が大きくなりすぎると結局は手術を要する可能性がありますし、薬物治療が効きにくくなる場合もあります。
早期に大きな手術を行った場合でも、その後別の臓器に腫瘍が発生し、追加の手術や新たな薬物治療が必要になることもあります。
| 治療手段 | デメリット | 考慮すべき点 |
|---|---|---|
| 外科手術 | 周術期リスク、再発の可能性、ホルモン補充の必要性 | 病巣の切除効果は大きいが長期フォローが重要 |
| 薬物治療 | 副作用、長期投与による負担 | 術後管理や手術不可のケースに有力な選択肢 |
| 放射線治療・放射性同位元素 | 術前・術後の負担増、効果のばらつき | 一部の腫瘍に対しては有効性が限定的な場合がある |
多発性内分泌腫瘍症(MEN)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
外科手術の費用目安
甲状腺全摘術を行う場合、術後の入院期間が約1週間前後となることが多く、トータルで保険適用後の自己負担額が10万円前後になるケースもあります。
副甲状腺摘出術は甲状腺手術ほど大きな傷口にならない場合が多いですが、それでも数日から1週間程度の入院と術前術後の検査費用などを含めると、同程度の範囲での費用を想定することが考えられます。
膵内分泌腫瘍の手術では、切除範囲が大きくなったり合併症対策が必要になったりする場合があり、保険適用後でも自己負担分が10万円~20万円程度です。
薬物治療の費用目安
ソマトスタチンアナログの注射剤は、月に数回の投与が必要となる場合があり、保険適用後でも月あたり自己負担が1万円~2万円程度になるケースがあります。
ビスホスフォネート製剤やαブロッカー、βブロッカーといった経口薬については、一般的な薬剤費として月数千円から1万円程度の自己負担を想定することが多いです。
画像検査や遺伝子検査の費用
多発性内分泌腫瘍症は定期的なフォローアップが重要であり、複数の画像検査を組み合わせます。
CTやMRI検査は1回あたりの自己負担額が数千円から1万円程度で、超音波検査はもう少し費用が低いです。
遺伝子検査に関しては、条件を満たす場合に保険適用となるケースが増えているものの、検査の種類によっては自己負担額が数万円に達する場合もあります。
| 治療・検査内容 | 保険適用後の費用例(自己負担2~3割) | 期間・回数 |
|---|---|---|
| 甲状腺全摘術 | 10万円前後 | 入院1週間前後 |
| 副甲状腺摘出術 | 10万円前後 | 入院数日~1週間程 |
| 膵内分泌腫瘍手術 | 10万円~20万円程 | 合併症有無で変動 |
| ソマトスタチンアナログ | 月1万~2万円程 | 月数回の注射 |
| αブロッカー・βブロッカー | 月数千円~1万円程 | 長期継続が多い |
| CT・MRI検査 | 1回数千円~1万円程 | 定期的に(半年~1年ごとなど) |
| 遺伝子検査 | 数万円程度になる場合あり | 1度の検査で判定可能(条件による保険適用) |
以上
参考文献
Sakurai A, Suzuki S, Kosugi S, Okamoto T, Uchino S, Miya A, Imai T, Kaji H, Komoto I, Miura D, Yamada M. Multiple endocrine neoplasia type 1 in Japan: establishment and analysis of a multicentre database. Clinical endocrinology. 2012 Apr;76(4):533-9.
Yoshimoto K, Saito S. Clinical characteristics in multiple endocrine neoplasia type 1 in Japan: a review of 106 patients. Nihon Naibunpi Gakkai Zasshi. 1991 Jul 1;67(7):764-74.
Sakurai A, Yamazaki M, Suzuki S, Fukushima T, Imai T, Kikumori T, Okamoto T, Horiuchi K, Uchino S, Kosugi S, Yamada M. Clinical features of insulinoma in patients with multiple endocrine neoplasia type 1: analysis of the database of the MEN Consortium of Japan. Endocrine Journal. 2012;59(10):859-66.
Sakurai A, Yamazaki M, Suzuki S, Fukushima T, Imai T, Kikumori T, Okamoto T, Horiuchi K, Uchino S, Kosugi S, Yamada M. Clinical features of insulinoma in patients with multiple endocrine neoplasia type 1: analysis of the database of the MEN Consortium of Japan. Endocrine Journal. 2012;59(10):859-66.
Takai SI, Miyauchi A, Matsumoto H, Ikeuchi T, Miki T, Kuma K, Kumahara Y. Multiple endocrine neoplasia type 2 syndromes in Japan. Henry Ford Hospital Medical Journal. 1984;32(4):246-50.
KATAI M, SAKURAI A, ITAKURA Y, IKEO Y, NAKAJIMA K, HARA M, IIJIMA S, KANEKO T, KOBAYASHI M, ICHIKAWA K, AIZAWA T. Multiple endocrine neoplasia type 1 is not rare in Japan. Endocrine journal. 1997;44(6):841-5.
Yoshimoto K, Iwahana H, Itakura M. Relatively good prognosis of multiple endocrine neoplasia type 2B in Japanese: review of cases in Japan and analysis of genetic changes in tumors. Endocrine journal. 1993;40(6):649-57.
Abe T, Yoshimoto K, Taniyama M, Hanakawa K, Izumiyama H, Itakura M, Matsumoto K. An unusual kindred of the multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) in Japanese. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2000 Mar 1;85(3):1327-30.
Sakurai A, Katai M, Yamashita K, FUKUSHIMA Y, HASHIZUME K. Long-term follow-up of patients with multiple endocrine neoplasia type 1. Endocrine journal. 2007;54(2):295-302.
Sakurai A, Imai T, Kikumori T, Horiuchi K, Okamoto T, Uchino S, Kosugi S, Suzuki S, Suyama K, Yamazaki M, Sato A. Thymic neuroendocrine tumour in multiple endocrine neoplasia type 1: female patients are not rare exceptions. Clinical Endocrinology. 2013 Feb;78(2):248-54.