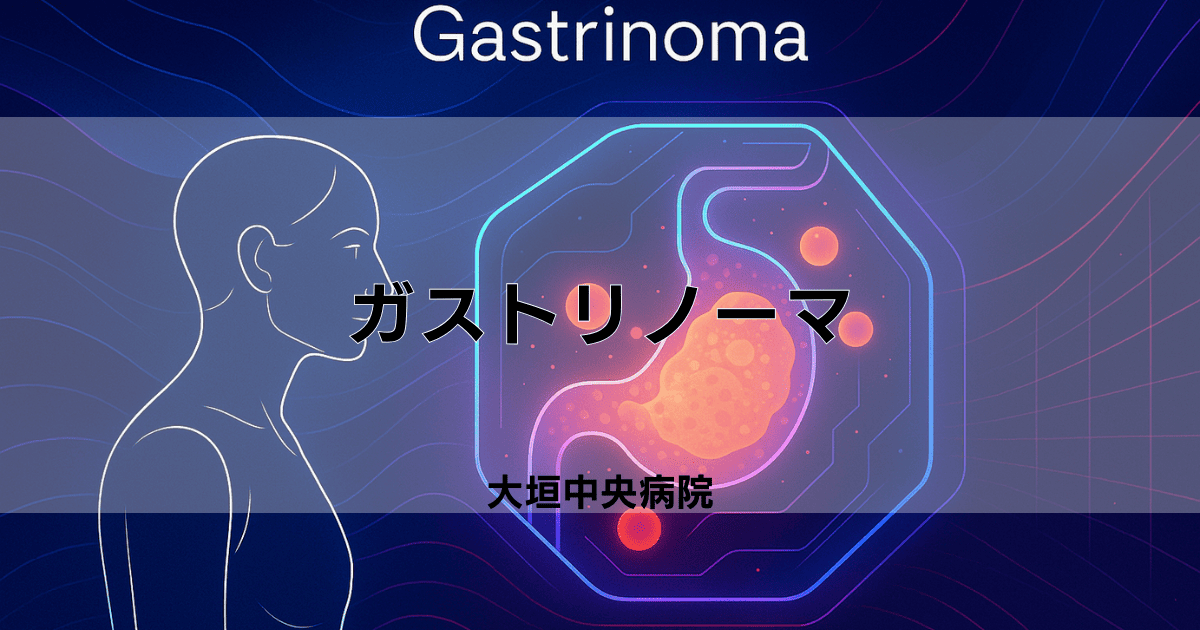ガストリノーマとは、胃酸の分泌を過剰に刺激するホルモンであるガストリンを産生する腫瘍のことで、多くは膵臓や十二指腸付近に発生し、胃酸分泌が極端に増えることで、難治性の潰瘍や腹痛、下痢などが続くケースがよく見られます。
ガストリノーマ自体は比較的まれな疾患ですが、遷延する消化性潰瘍やそれに伴う合併症を引き起こすリスクが高いため、検査と治療を受けるかどうか迷っている方にとっては、情報収集が大切です。
この腫瘍は良性の場合と悪性の場合がありますが、その区別や治療計画を正しく立てるには専門医の診察が欠かせません。
ガストリノーマの病型
ガストリノーマには複数の病型があり、腫瘍の存在場所や性質によって治療アプローチや経過観察の仕方が異なってきます。
病型の違いを知ることで、どのように検査を進めるかや、どのタイミングで医師の診察を受けるべきかを判断する材料になるでしょう。
良性と悪性の区分
ガストリノーマは良性と悪性に分けられますが、見た目だけでは判断が難しい場合が多く、腫瘍細胞の増殖スピードや浸潤状況、転移の有無などで総合的に判断します。
悪性ガストリノーマは他臓器への転移リスクがあり、予後を左右する大きな要素になりますが、良性であっても胃酸過剰分泌が強い場合は消化管潰瘍が深刻化することがあるため油断は禁物です。
単発か多発か
ガストリノーマの腫瘍が単発で存在する場合と、複数個が同時もしくは段階的に発生する場合があります。
特に多発性内分泌腫瘍症(MEN1)と関連しているケースでは、膵臓や副甲状腺など複数の臓器に腫瘍が生じることがあり、その場合は包括的な検査と治療計画が必要です。
単発の場合でも膵内のほかの領域に新たな腫瘍が生じることがゼロではないため、定期的なフォローアップが大切になります。
部位別の特徴
ガストリノーマが好発する代表的な部位としては膵臓や十二指腸が挙げられ、膵臓の頭部付近に多くみられるケースがある一方、十二指腸壁に発生する例も少なくありません。
部位によっては周囲の組織への圧迫症状や転移リスクが変わってくるため、検査の段階で場所を正確に把握することが非常に重要です。
予後との関連性
ガストリノーマの予後は良性・悪性のほか、腫瘍の大きさや発見時の病期にも左右されます。
また、腫瘍が複数発生している場合や、すでにリンパ節や肝臓などへ転移している場合は治療難度が上がり、経過観察や追加治療が長期に及ぶ可能性があります。いずれにしても早期発見と適切な対応が、長期的な予後を左右するカギです。
病型と関連する主なポイント
| 病型分類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 良性ガストリノーマ | 転移リスクが低いが、過剰胃酸分泌による潰瘍リスクは存在 |
| 悪性ガストリノーマ | 転移が起こりやすく、早期発見が遅れるほど生命予後に影響が大きい |
| 単発性 | 腫瘍が1つだけ存在し、手術で取り除けるケースが比較的多い |
| 多発性 | 複数の腫瘍が同時または段階的に発生し、MEN1などとの関連が指摘される |
ガストリノーマの病型は治療方針や経過観察に大きく影響を与えるため、検査時にどのタイプに属するのかを正確に知ることが重要です。
- 良性でも過剰胃酸分泌の症状は深刻化しやすい
- 悪性の場合は転移があるかどうかで治療計画が大きく変わる
- 部位が膵臓か十二指腸かで症状の出方も微妙に変わる
- MEN1症候群が疑われるなら他の内分泌臓器も要チェック
ガストリノーマの症状
ガストリノーマの主な症状は、胃酸過剰分泌に由来する消化管の障害ですが、腫瘍のサイズや部位によって微妙に差が現れることがあります。
慢性的に続く症状を放置すると、潰瘍が拡大・悪化し、重大な合併症を起こす可能性が高まるため、自覚症状がある場合は早めに対応したほうが安心です。
難治性の胃潰瘍や十二指腸潰瘍
通常の胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、ピロリ菌感染やNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用などが原因になることが一般的ですが、ガストリノーマによる潰瘍は、あり余る胃酸によって治りづらい特徴を持ちます。
再発を繰り返す潰瘍はガストリノーマを疑う一つの目安になり、強い腹痛や出血をともなっている場合は早急に検査を検討することが必要です。
下痢や脂肪便
過剰な胃酸が小腸にも流れ込むため、消化吸収のプロセスが乱れ、慢性的な下痢や脂肪便が出現することがあります。
脂肪便は油分を十分に吸収できずに排出されるため便が脂っぽくなる現象で、消化管の機能低下を示唆するサインとして注目され、このような症状が長期間続くと、栄養障害につながるおそれがあります。
腹痛や胸焼け
強い胸焼けやみぞおち付近の痛みが長期間にわたり改善しない場合、ガストリノーマによる胃酸過剰分泌を考慮すべきかもしれません。
通常の制酸薬を飲んでも症状が和らがない、あるいは一時的に改善しても再び痛みがぶり返すなら、腫瘍によるガストリン分泌過剰の可能性があります。
消化管出血
胃潰瘍や十二指腸潰瘍が深部にまで達すると、潰瘍部位から出血することがあり、吐血や下血が見られる場合は、既に潰瘍がかなり進行している可能性が高く、緊急対応が求められるケースも少なくありません。
出血量が多いと急激に血圧が下がり、ショック状態を招くリスクがあるため、油断は禁物です。
症状の把握に役立つ視点
| 症状 | 主な原因や状況 |
|---|---|
| 難治性の潰瘍 | 過剰胃酸が潰瘍の治癒を妨げ、繰り返し悪化する |
| 下痢・脂肪便 | 消化吸収が乱れ、小腸で脂肪が吸収されにくくなる |
| 胸焼け・腹痛 | 強い胃酸が食道や胃の粘膜を刺激する |
| 出血 | 潰瘍が深く進行し血管を傷つけて大量出血を引き起こす場合あり |
- 普通の胃酸抑制剤が効きにくい
- 便の状態が目に見えて変化(脂っぽさなど)
- 食後の腹部不快感が続く
- 潰瘍が再発しやすく、検査の度に潰瘍が増えている
いずれの症状も放置すると身体的な負担が大きくなるだけでなく、合併症リスクを高めるため、一定期間続く場合は早期受診を考慮してください。
原因
ガストリノーマの原因には遺伝的要因や、細胞の遺伝子変異による腫瘍化などが挙げられますが、ピロリ菌や生活習慣病のように多くの人に当てはまる明確なリスクファクターが確立されていません。
遺伝子異常とMEN1
ガストリノーマは、遺伝的素因があるとされる多発性内分泌腫瘍症(MEN1)と深い関連が見られることがあります。
MEN1は、膵臓や副甲状腺、下垂体など複数の内分泌臓器に腫瘍が生じる病態で、ガストリノーマはその一部として発生することがあります。
家族にMEN1が確認されている場合は、ガストリノーマが疑われる症状が出たときに早めの検査を受けることが重要です。
細胞のがん化プロセス
膵臓や十二指腸の一部の細胞が何らかの原因で異常増殖を起こすことで、ガストリンを大量生産する腫瘍が形成される場合があります。
細胞ががん化するメカニズムには多くの要因が絡んでおり、遺伝的背景や環境要因、その他の体内環境などが複雑に影響を及ぼすため、特定の生活習慣だけが原因とは言い切れません。
ホルモンバランスの乱れ
内分泌系の働きは非常に繊細で、どこか1つのホルモンバランスが崩れると連鎖的にほかのホルモン分泌にも影響が及ぶことがあります。
ガストリンを分泌する細胞の増殖がこの乱れと関連している場合、気づかないうちにホルモン過剰状態が進んでしまう可能性があります。
ただし、一般的なストレスなどによる一時的なホルモン変動が直接ガストリノーマの発生につながるわけではないため、正しい理解が大切です。
膵臓や十二指腸の炎症
慢性的な膵炎や十二指腸炎を繰り返していると、組織の再生過程で細胞の異常増殖が起こる可能性があり、炎症が長く続くと細胞のDNAにもダメージが蓄積しやすくなり、腫瘍化リスクが高まる懸念があります。
とはいえ、炎症が直接ガストリノーマを起こす明確な因果関係は完全に解明されていません。
ガストリノーマ発生に関わる可能性のある要因
| 要因 | 特徴や関連性 |
|---|---|
| MEN1 | 複数の内分泌腫瘍を誘発し、ガストリノーマを含む場合あり |
| 遺伝子の変異 | 細胞レベルの異常増殖が腫瘍化へとつながる |
| ホルモンバランス乱れ | 過剰なガストリン分泌を誘発する要因の1つになる場合がある |
| 慢性的な炎症 | 膵臓や十二指腸の炎症が細胞ダメージを蓄積させる可能性 |
- 家族にMEN1の既往がある場合は特に注意
- 細胞レベルの原因は複合的で単一要因で説明しきれない
- ホルモンの過剰や不足は身体全体に影響を及ぼしやすい
- 慢性膵炎などで膵臓に負荷がかかっているなら定期検査を検討
ガストリノーマは特定の原因を一概には断定しにくい病気ですが、複数の要素を組み合わせて総合的に判断し、疑わしい場合は早めに専門医へ相談すると安心です。
ガストリノーマの検査・チェック方法
ガストリノーマを診断するためには、血液検査や画像検査、内視鏡検査など、さまざまな手段を組み合わせて腫瘍の存在とその機能を確かめることが重要です。
どの検査をどのタイミングで行うかは症状の強さや、ほかの病気を併発していないかなどによって変わります。
血液検査(血中ガストリン濃度)
ガストリノーマを疑う際にまず行われることの多い検査が血液検査で、特に血中のガストリン濃度を測定し、通常の基準値より大幅に高い数値が出た場合は、ガストリンを過剰に分泌する腫瘍の存在を疑いやすくなります。
ただし、胃酸抑制薬を服用しているとガストリン値が上昇することもあるため、服薬状況を医師に正確に伝えることが重要です。
画像検査(CTやMRI)
腫瘍の位置や大きさを確認するために、CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)を撮ることがあります。
ガストリノーマは膵臓や十二指腸にできることが多いため、その部位を集中的に撮影し、異常な陰影や腫瘍らしき構造物がないかをチェックします。
MRIは腫瘍と周囲組織との境界を詳しく捉えやすいという利点がありますが、CTにも短時間で広範囲をスキャンできるメリットがあり、医師の判断で選択されることが多いです。
画像検査で見られる代表的な所見
| 検査方法 | 特徴 |
|---|---|
| CT | 短時間で広範囲を撮影し、腫瘍や転移の有無を把握しやすい |
| MRI | 軟部組織のコントラストが得意で、境界判定を詳細に行いやすい |
内視鏡検査(上部消化管内視鏡)
消化管に潰瘍や出血がないかを調べるために、胃カメラなどの上部内視鏡検査を行う場合があり、ガストリノーマは胃や十二指腸に重度の潰瘍を形成することが多いため、その評価を行いながら一部組織を採取し、生検することが可能です。
直接、腫瘍を可視化できるわけではありませんが、間接的に潰瘍の状態や出血部位の確認に役立ちます。
専門的ホルモン負荷試験
血中ガストリン濃度をさらに正確に把握するために、特定の薬剤を投与してガストリン値の変化を観察する負荷試験を行うことがあります。
セクレチンというホルモンを投与すると、ガストリノーマがある場合はガストリン値が大きく変動することが多く、この変化パターンが診断の補助です。
- 血中ガストリン濃度の測定は基本中の基本
- 胃酸抑制薬の内服状況を伝えないと誤診の恐れ
- CTやMRIで腫瘍の位置や大きさを把握
- 上部内視鏡で潰瘍の状態を詳細に確認
一連の検査結果を総合してガストリノーマの有無を判断し、その後の治療方針を検討する流れが一般的です。
検査の概要と目的
| 検査名 | 目的 |
|---|---|
| 血液検査(ガストリン濃度) | ホルモン過剰を数値化し、腫瘍の機能評価を行う |
| 画像検査(CT/MRI) | 腫瘍の存在部位、大きさ、転移状況を視覚的に確認 |
| 上部消化管内視鏡 | 潰瘍の有無や程度、出血箇所を直接観察 |
| ホルモン負荷試験 | ガストリン値の変動パターンを分析し、ガストリノーマを特定 |
治療方法と治療薬について
ガストリノーマの治療は、腫瘍を直接取り除く手術療法から、胃酸分泌を抑える薬物療法、そして転移がある場合には化学療法など、さまざまな手段が選択肢として挙げられます。
患者さんの状態や病型によっては、複数の治療法を組み合わせることもあり、一人ひとりに適したアプローチを医師が検討します。
手術療法
腫瘍が単発で、周囲の組織や臓器に大きく浸潤していない場合、外科的に腫瘍を切除することが最も有力な治療選択肢になることがあります。
膵臓の一部を切除したり、十二指腸壁を一部切り取ったりして腫瘍を取り除く形で、術後には一定期間の入院と経過観察が必要になり、再発リスクを下げるためにも術後フォローが大切です。
手術療法のメリットと留意点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 根治が期待できる可能性 | 腫瘍を完全に取り除くことで、ガストリン過剰の原因を排除 |
| 手術の侵襲性 | 開腹手術または腹腔鏡手術などがあり、術式によって負担が異なる |
| 術後の合併症 | 膵液漏や感染症などのリスクがあるため注意深い管理が求められる |
| 再発リスク | 病型や腫瘍特性により、定期的な画像検査や血液検査が重要になる |
胃酸分泌抑制薬(PPIやH2ブロッカー)
ガストリノーマによって過剰に分泌された胃酸を抑えるために、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2受容体拮抗薬などが使用されることがあり、潰瘍による痛みや出血のリスクを低減し、日常生活の質を向上させる効果が期待されます。
ただし、根本的な腫瘍の消滅には至らないため、手術やほかの治療と併用する場合が多いです。
化学療法
悪性度が高く転移が認められる場合は、化学療法を検討することがあります。
抗がん剤を使用して腫瘍細胞の増殖を抑えるアプローチですが、腫瘍の性質によって効果が大きく異なるため、使用する薬剤や治療期間などは専門医が慎重に判断します。
ストレプトゾトシンやサンドスタチン
ガストリノーマ治療に特化した薬は、ストレプトゾトシンやサンドスタチン(オクトレオチド製剤)などです。
ストレプトゾトシンは膵臓の腫瘍細胞に作用しやすいとされ、一方のサンドスタチンはガストリンなどのホルモン分泌を抑制する効果が期待されます。
- 手術で根治を目指すケース
- PPIやH2ブロッカーで胃酸過多症状の緩和
- ストレプトゾトシンなどの化学療法を併用する場合もある
- サンドスタチンでホルモン分泌を抑制するアプローチ
いずれの治療を選択するかは、腫瘍の病期や患者の全身状態、ライフスタイルなどを加味した総合的な判断となります。
治療法と期待される効果
| 治療法 | 期待される主な効果 |
|---|---|
| 外科手術 | 腫瘍を直接切除し、ガストリン過剰の根本原因を除去 |
| 胃酸分泌抑制薬 | 潰瘍や胸焼けを軽減し、症状緩和に寄与 |
| 化学療法 | 転移がある場合に腫瘍の増殖速度を抑える |
| ホルモン抑制薬 | ガストリンなどのホルモン分泌を抑え、症状緩和を図る |
ガストリノーマの治療期間
ガストリノーマの治療期間は、腫瘍の大きさや転移の有無、そして治療法の選択によって大きく左右されます。
早期発見で手術が可能な場合は、術後の入院期間を含め数週間から数カ月程度で経過観察フェーズに移行することがありますが、悪性度が高い腫瘍や転移が見つかった場合、化学療法や薬物療法を長期にわたって継続する必要があるかもしれません。
手術中心の場合
単発のガストリノーマを外科的に切除し、術後の合併症も少ないケースでは、おおむね1カ月前後の入院と、退院後の数回の外来検診で経過を見守ることが多いです。
術後2~3カ月程度で日常生活に戻れる場合もありますが、再発リスクを見極めるために定期的な血液検査や画像検査を半年~1年おきに行い、3~5年程度はフォローアップします。
薬物治療が中心の場合
悪性度が高い場合や手術が困難な部位に腫瘍がある場合、PPIやサンドスタチンなどで症状をコントロールしつつ、化学療法を並行することが考えられます。
その際の治療期間は数カ月から1年以上に及ぶこともあり、副作用や腫瘍の進行度合いに合わせて治療内容の変更や休薬期間を設けることもあります。
治療の終了と再発予防
一度治療を終えたあとでも、転移や再発の可能性はゼロではありません。胃酸分泌状態や肝臓などのほかの臓器の状況をモニタリングするため、定期的な検査と診察が重要です。
症状が落ち着いても、数年程度はフォローアップを続けるケースが少なくありません。
治療期間の目安に関する要素
| 要素 | 期間の目安 |
|---|---|
| 手術後の入院 | おおむね2~4週間程度 |
| 外来フォローアップ | 半年に1回~1年に1回を数年継続 |
| 化学療法のスケジュール | 1コースあたり数週間で、その後の休薬期間を含め数カ月 |
| ホルモン抑制薬の継続 | 症状緩和が得られるまで長期に及ぶ場合がある |
- 単発か多発かで治療計画が大きく変わる
- 手術が適用になるかどうかが期間に直結する
- 悪性度が高いと長期にわたるフォローと治療が必要となる
- 完治後も定期検診を受けることで再発リスクを早期に把握
ガストリノーマ薬の副作用や治療のデメリットについて
ガストリノーマの治療薬には胃酸抑制薬やホルモン抑制薬、化学療法剤などが含まれますが、それぞれに副作用があり、副作用の程度は個人差が大きいです。
胃酸抑制薬の副作用
PPIやH2受容体拮抗薬のような胃酸抑制薬は、長期間使用すると骨密度の低下や腸内細菌叢のバランス異常を起こす可能性があると指摘されています。
また、急に使用を中止すると胃酸分泌が反動的に増えるリバウンド現象が起こるケースもあるため、中止する際は医師の指示を受けるほうが安全です。
化学療法剤の副作用
化学療法剤は腫瘍細胞の増殖を抑える効果が期待される一方、正常細胞にも影響を及ぼしやすいため、吐き気や嘔吐、脱毛、倦怠感、血球減少などの副作用が起こり得ます。
ストレプトゾトシンなども膵臓がんや膵内分泌腫瘍の治療で用いられますが、腎機能障害や肝機能障害のリスクがあるので、投与中は定期的な血液検査が行われることが多いです。
サンドスタチン(オクトレオチド製剤)の副作用
サンドスタチンはホルモン分泌を抑制する働きを持つ薬ですが、投与初期には便秘や下痢、腹部膨満などの消化器症状が起こることがあります。
その他、低血糖や高血糖といった血糖値のコントロール異常が見られる場合もあり、糖尿病患者や糖代謝に不安がある方は注意が必要です。
主な副作用とデメリットの概要
| 薬剤・治療 | 代表的な副作用・デメリット |
|---|---|
| 胃酸抑制薬(PPI/H2) | 骨密度低下、リバウンド増酸、腸内細菌叢の乱れ |
| 化学療法剤(ストレプトゾトシン等) | 吐き気、脱毛、倦怠感、腎機能障害など |
| ホルモン抑制薬(サンドスタチン) | 腹部症状、血糖値変動、注射部位痛み |
| 手術 | 麻酔リスク、傷跡、術後合併症、長期入院など |
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
検査費用の目安
血液検査やCT、MRIなどの画像検査、内視鏡検査は保険適用される場合がほとんどで、複数の検査を一度に行うことが多いため、初期の検査費用だけで約1万~2万円(3割負担の場合)です。
必要に応じて追加で特殊なホルモン負荷試験などを行うと、さらに数千円から1万円ほど加算されます。
手術費用の目安
外科的手術を行う場合、入院や手術にかかる費用は、手術の種類や術式の難易度で大きく変わりますが、保険適用であれば自己負担3割として数十万円程度になることが一般的です。
膵臓の部分切除や十二指腸切開などを行う場合、入院期間が2~3週間必要なこともあり、差額ベッド代や食事代などの諸経費を含めると、トータルで50万円前後の負担がかかるケースも考えられます。
| 項目 | おおよその自己負担目安(3割負担) |
|---|---|
| 手術基本費用 | 30万~40万円程度 |
| 入院諸経費 | 10万~15万円程度 |
| その他検査費 | 5万~10万円程度 |
| 合計 | 45万~65万円程度 |
薬物療法の費用
PPIやH2ブロッカーなどの制酸薬は、ジェネリックが存在するものもあり、1カ月あたり数千円程度の自己負担に収まる場合が多いです。サンドスタチンのようなホルモン抑制薬は比較的高価で、月に1~2万円ほどかかります。
化学療法剤は点滴での投与や通院治療が必要になる場合があり、1コースで数万円から十数万円の自己負担が発生します。
追加検査や長期通院の出費
定期的に再発や転移の有無を確認するための検査が必要になる場合は、1回数千円から1万円程度の負担が継続します。
- 血液検査や画像検査の組み合わせで初期費用が1万~2万円程度
- 外科手術は数十万円単位の負担が発生する可能性
- 薬物療法は薬剤種類によって数千円~数万円の幅がある
- 長期的なフォローアップには継続的な通院費用が必要
代表的な費用目安
| 治療内容 | 自己負担(3割負担の目安) |
|---|---|
| 初期検査一式 | 1万~2万円程度 |
| ホルモン負荷試験など | 数千円~1万円程度 |
| 手術 | 数十万円程度 |
| PPIやH2ブロッカー | 月数千円~1万円前後 |
| サンドスタチンなど特殊薬 | 月1~2万円程度 |
| 化学療法(1コース) | 数万円~十数万円程度 |
| 定期検診・再発チェック | 年間数万円程度 |
参考文献
Jensen RT. Gastrinoma. Baillière’s clinical gastroenterology. 1996 Dec 1;10(4):603-43.
Li ML, Norton JA. Gastrinoma. Current Treatment Options in Oncology. 2001 Jul;2:337-46.
Townsend JR CM, Thompson JC. Gastrinoma. InSeminars in Surgical Oncology 1990 (Vol. 6, No. 2, pp. 91-97). New York: John Wiley & Sons, Inc..
Townsend Jr CM, Lewis BG, Gourley WK, Thompson JC. Gastrinoma. Current Problems in Cancer. 1982 Oct 1;7(4):1-33.
Stabile BE, Passaro Jr E. Benign and malignant gastrinoma. The American journal of surgery. 1985 Jan 1;149(1):144-50.
Zhang WD, Liu DR, Wang P, Zhao JG, Wang ZF, Chen LI. Clinical treatment of gastrinoma: A case report and review of the literature. Oncology Letters. 2016 May;11(5):3433-7.
Klöppel G, Anlauf M. Gastrinoma–morphological aspects. Wiener Klinische Wochenschrift. 2007 Nov 1;119.
Mignon M, Ruszniewski P, Haffar S, Rigaud D, Rene E, Bonfils S. Current approach to the management of tumoral process in patients with gastrinoma. World journal of surgery. 1986 Aug;10(4):703-10.
Sanabria C, Pérez-Ferre N, Lecumberri E, De Miguel P. Gastrinoma. Endocrinología y Nutrición. 2007 Jan 1;54:21-30.
Liu TH, Zhong SX, Chen YF, Lin Y, Chen J, Li DC, Wang DT, Gu CF, Ye SF. Gastric gastrinoma. Chinese Medical Journal. 1989;102(10):774-82.