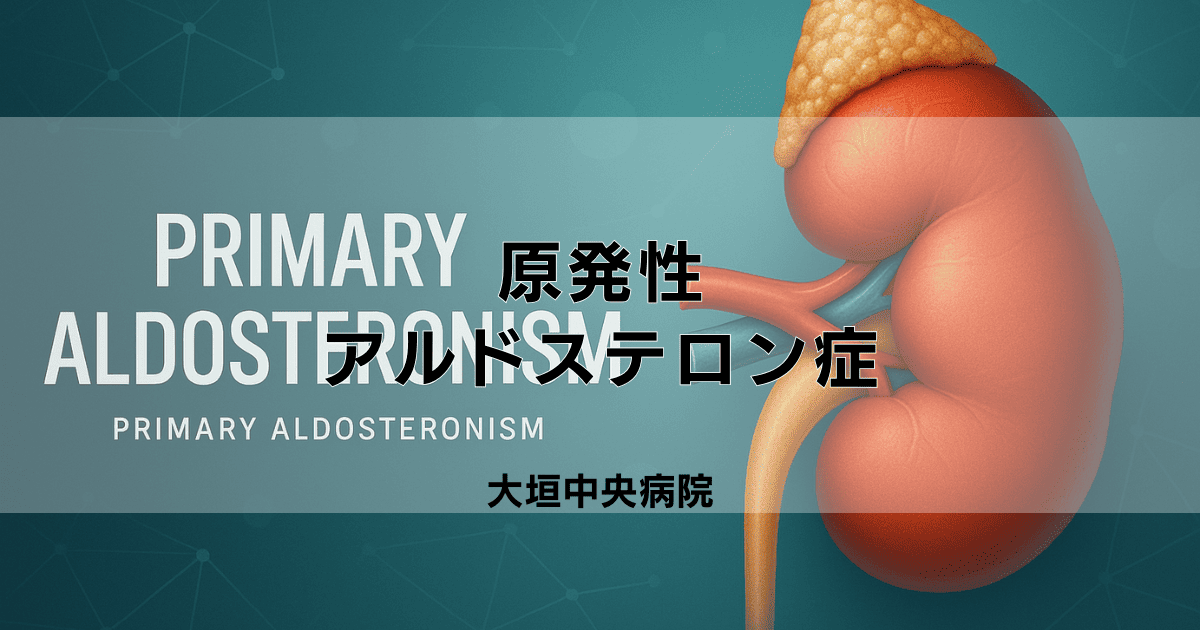原発性アルドステロン症とは、副腎で作られるアルドステロンというホルモンが過剰に分泌されることにより、高血圧や低カリウム血症を中心とした様々な不調を引き起こす病気です。
血圧が下がりにくい、持続的な倦怠感、むくみなどが続くため、単なる高血圧ではないのではと疑問に思う方もいるかもしれません。
血液検査や画像診断を含む複数のステップを踏むことで、過剰なアルドステロン分泌の原因を特定し、外科的治療や薬物療法により症状の改善を目指せます。
原発性アルドステロン症の病型
原発性アルドステロン症は副腎からアルドステロンが過剰に分泌される病気であり、片側の副腎に問題がある場合と、両側の副腎に異常がある場合で治療方針が変わります。
高血圧の原因が見えづらい時でも、この病気の病型を正しくつかむと、その後の治療内容や経過観察の進め方がわかりやすいです。
アルドステロンの過剰分泌とは
アルドステロンは体内のナトリウムやカリウムのバランス、血圧の調整にかかわるホルモンで、通常は必要な量だけ分泌され、ナトリウムを体内に保持して血圧を一定に保ったり、不要になったカリウムを排出して濃度を調整したりします。
しかし原発性アルドステロン症の場合、何らかの要因によって分泌量が増え、高血圧や電解質異常を起こし、持続的にホルモンの過剰分泌が進むと血圧は下がりづらくなり、腎臓や心臓など全身に負担が及びます。
アルドステロンの体内での働き
- 血液中のナトリウム濃度を上げて、水分貯留を促しやすくする
- カリウムの排出を促し、濃度を正常範囲に保つ
- 体液量を調整し、血圧を上昇させる方向に働く
片側性と両側性の病型
原発性アルドステロン症のなかでも、片側の副腎に原因がある場合と両側の副腎に過形成がある場合とで、治療アプローチは大きく異なります。
片側性の代表例は、Conn(コン)症候群と呼ばれる副腎皮質の腺腫であり、腺腫からアルドステロンが過剰に分泌され、一方、両側性の場合は両方の副腎が過形成を起こし、多量のアルドステロンが産生されるケースです。
外科的に摘出することでアルドステロン産生を減らすことが期待できる片側性と異なり、両側性は副腎を両方とも摘出するわけにはいかないため、薬物療法による血圧コントロールが中心になります。
病型別の特徴
| 病型 | 特徴 | 治療方針の例 |
|---|---|---|
| 片側性 (Conn症候群など) | 片側副腎の腺腫が原因 | 外科的摘出+必要に応じて薬物療法 |
| 両側性 | 両側副腎の過形成 | 主に薬物療法(アルドステロン拮抗薬など) |
ホルモンバランスの乱れが引き起こす影響
アルドステロンはレニンやアンギオテンシンと共に腎臓や血管に作用し、血圧や電解質のバランスを常に調整しています。
このうちアルドステロンだけが多く分泌されすぎると、ナトリウムや水分が体に溜まりやすくなり、高血圧が持続して血管や臓器に影響を与えやすいです。
さらに、カリウムの喪失が起こり続けることで低カリウム血症の状態が進行し、倦怠感や脱力感、不整脈を生む一因になります。
副腎とホルモン分泌の位置づけ
| 部位 | 分泌されるホルモン | 主な役割 |
|---|---|---|
| 副腎皮質(球状帯) | アルドステロン | ナトリウム保持、カリウム排出、血圧調整 |
| 副腎皮質(束状帯) | コルチゾール | 糖代謝・免疫調整 |
| 副腎髄質 | アドレナリン、ノルアドレナリン | 血圧や心拍数の急激な調整 |
病型を知ることの意義
原発性アルドステロン症には片側性と両側性があり、原因となる副腎の状態によって手術を行うかどうか、あるいは薬物でコントロールするかなど、方針が大きく分かれます。
自分がどの病型に当たるのかを知ると、今後の治療の流れや期待できる効果をイメージしやすくなり、高血圧治療の中でなかなか血圧が下がらないとき、もしかしたら原発性アルドステロン症なのでは、と考えることが大切です。
病型にまつわるポイント
- 治療アプローチの違いによって手術の適応か薬物療法が中心かが決まる
- 副腎の状態を確定させるために画像検査や副腎静脈採血が活躍する
症状
原発性アルドステロン症の主な特徴には高血圧がありますが、それだけではなく、電解質異常による多彩な身体の不調が起こる場合があります。
単に血圧が高いからといって、全員が同じ症状を訴えるわけではなく、低カリウム血症に伴う脱力感や筋肉のけいれん、倦怠感などが初めて気づくきっかけになる方もいます。
普段の血圧治療では改善が見られにくく、頭痛やめまい、息切れなど多方面に影響が及ぶケースがあるので注意が必要です。
高血圧の特徴
通常の高血圧よりもコントロールが難しく、降圧薬を何種類も使っているのに思うように下がらないことが多く、朝晩の血圧測定で常に高値を示し、生活習慣を見直してもあまり改善しにくいのが特徴です。
持続的に血圧が高い状態が続くと、脳卒中や心不全など心血管リスクが高まります。
降圧薬の効果を実感しにくい場合に意識しておきたい点
- 複数の降圧薬を併用しているのに高血圧が改善しづらい
- 血液検査でカリウム値が低い傾向がある
- 腎機能の評価をしても他の原因が見つからない
低カリウム血症による症状
低カリウム血症になると、筋肉や神経伝達の機能が落ちやすくなり、全身の倦怠感や脱力感、筋力低下などが生じ、ひどい場合は、軽い動作でも足がつったり、こむら返りが頻発したり、不整脈が出る可能性もあります。
慢性的なカリウム不足は腎機能にも影響を及ぼし、さらに高血圧が進む悪循環に陥いるので注意が必要です。
腎機能への影響
アルドステロンの過剰分泌は腎臓におけるナトリウムとカリウムの再吸収バランスを崩すため、長期的には腎機能の低下を引き起こすことがあります。
尿量の増加や血中クレアチニンの上昇、さらには軽度の蛋白尿などを認める場合があり、そのまま放置すると慢性腎不全を進行させるリスクが高まります。
アルドステロンが腎機能に及ぼす影響
| 影響 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ナトリウム再吸収促進 | 体内の水分量増加 | むくみ、高血圧 |
| カリウム排泄増加 | 低カリウム血症 | 脱力感、倦怠感、不整脈 |
| 腎への負担増大 | 糸球体や尿細管の機能低下 | 慢性腎不全のリスク上昇 |
全身症状の多様性
高血圧と低カリウム血症以外にも、脱水症状を訴えたり、動悸や息切れを感じる方もいます。疲れやすさやイライラ感などの精神的ストレスが先行し、じっくり検査してみたら実は原発性アルドステロン症だったという例もあります。
高血圧の背景には、このようにホルモン異常が潜んでいる可能性があるため、疑わしいときは専門的な検査を受けることが重要です。
原因
アルドステロン過剰分泌の原因としては、大きく副腎皮質の腺腫と副腎の両側過形成に分かれます。
いずれの場合も副腎という小さな臓器のホルモン分泌に異常が起こるため、血圧や電解質のコントロールが正常に保てなくなり、原因の特定は治療戦略の基盤です。
副腎皮質の腺腫
Conn(コン)症候群に代表されるように、副腎皮質に良性の腺腫ができて、これがアルドステロンを過剰に産生する場合があります。
腺腫は良性であってもホルモンを過剰分泌する性質をもち、放置すると血圧がどんどん上昇し、低カリウム血症も長期化するので、腺腫が片側の副腎のみであれば、外科的にその部分を取り除くことで、過剰分泌を抑えることが可能です。
遺伝的要因とホルモンの関連
稀に家族性の原因によって、若い頃から高血圧を発症するタイプの原発性アルドステロン症もあり、家系内で高血圧の既往が多い場合や、他の内分泌疾患も併発している場合には、遺伝的要因を視野に入れた精密検査が役立ちます。
遺伝子異常が見つかると特定の治療法が考えられるケースもあり、早期に把握することが大切です。
副腎の両側性過形成
両側の副腎で細胞が増殖し、アルドステロンを多量に作り出す状態を示し、この場合は部分的に摘出しても過剰分泌が十分には改善しないため、通常はアルドステロン拮抗薬などの薬物療法を長期にわたって行う必要があります。
病気の進行度や患者の体質によっては血圧の管理が難航する場合もあり、複数の降圧薬と併用して様子を見ることが多いです。
原因解明の重要性
高血圧の要因が何なのか不明なまま治療を進めると、いつまでも血圧が安定しなかったり、重い合併症へと進行するおそれがあります。
アルドステロンが関与するのかどうかを調べる検査を行い、原因が特定できれば、治療方針を組み立てやすくなり、無闇に薬の種類を増やすよりも、一度内分泌的な視点から検査を行うことが高血圧の根本原因解消につながるかもしれません。
アルドステロン産生の原因
| 原因分類 | 特徴 | 治療アプローチ |
|---|---|---|
| 腺腫(片側) | 良性の腫瘍による過剰分泌 | 外科的切除+必要に応じて薬物療法 |
| 両側過形成 | 両方の副腎が過形成 | 薬物療法中心(アルドステロン拮抗薬など) |
| 遺伝的要因 | 若年発症や家族内発症の高血圧 | 専門的な遺伝子検査と治療検討 |
原発性アルドステロン症の検査・チェック方法
原発性アルドステロン症が疑われる場合、まずは血液検査でアルドステロンとレニンの値、さらにカリウムなどの電解質を確認し、その後確認検査や画像検査、時には副腎静脈サンプリングなど侵襲的な検査を行って原因を確定します。
どの検査をどのタイミングで実施するかは主治医の判断により異なりますが、正しい診断を行ううえで大切なプロセスです。
アルドステロンとレニンの測定
アルドステロン値とレニン活性、さらに両者の比率(アルドステロン・レニン比:ARR)は原発性アルドステロン症のスクリーニングに重要です。
高アルドステロン・低レニン状態が見られれば、過剰分泌を疑い、血液検査と同時に電解質(特にカリウム)のチェックも行い、低カリウム血症の程度も評価します。
スクリーニング時に意識する指標
- アルドステロン/レニン比(ARR)が高い
- 低カリウム血症が顕著、または正常範囲上限ぎりぎり
- 普通の高血圧治療で改善が乏しい
確認検査の意義
スクリーニング検査で原発性アルドステロン症が疑わしい場合、食塩負荷試験やカプトプリル負荷試験、生理食塩水負荷試験といった確認検査を行うことがあります。
アルドステロン分泌が正常であれば食塩負荷などにより抑制がかかるはずですが、原発性アルドステロン症の場合には抑制が不十分です。
画像検査でわかること
CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)を利用して、副腎に腫瘍や過形成がないかをチェックし、片側に明らかな腺腫が確認されれば、外科的なアプローチが選択肢です。
しかし、画像検査で明確に腺腫が見つからない場合でも、機能的な異常があるケースは存在するため、さらなる検査が必要になる場合があります。
画像検査で得られる情報
| 検査法 | 特徴 | 考えられる診断所見 |
|---|---|---|
| CT | X線を用いる | 副腎の腺腫や大きさの評価 |
| MRI | 磁気を用いる | 軟部組織の詳細な描写 |
| 超音波 | 簡易評価 | 大きな病変の有無の確認程度 |
後続の侵襲的検査
副腎静脈採血(アドレナル・ベノグラフィー)など、直接副腎から血液を採取する検査を行うケースがあります。
これは片側か両側かを判定するのに非常に有効であり、どちらの副腎がアルドステロン過剰を生じさせているかを正確に突き止める手段です。
ただし、カテーテルを用いて副腎静脈から直接採血するため、身体的な負担やリスクを伴うことがあるため、必要に応じて専門医のもとで適切に検討して実施します。
検査の流れをポイント
- 血液検査でスクリーニング(アルドステロン・レニン値+電解質測定)
- 確認検査(食塩負荷試験、カプトプリル負荷試験など)
- 画像検査(CTやMRIで副腎の形態をチェック)
- 副腎静脈採血(片側か両側かを特定し、病型を確定)
治療方法と治療薬について
原発性アルドステロン症の治療は、片側性(腺腫などが原因)と両側性(両副腎の過形成)で大きく異なります。
手術で問題のある副腎を摘出する方法が選択肢になる場合もあれば、薬物療法で血圧と電解質のバランスを安定させる方針が求められることもあり、個々の病態に合わせて柔軟に治療を組み立てることが大切です。
外科的治療の選択肢
片側の副腎に腺腫があると判明した場合、外科的に腺腫を含む副腎を摘出する手段が検討され、腹腔鏡手術で行うことが多く、手術によって過剰なアルドステロン分泌源が取り除かれるため、血圧やカリウム値が改善する可能性があります。
ただし、必ずしも血圧が正常化するとは限らず、残った副腎の機能が十分かどうかなども考慮することが必要です。
手術のメリット・留意点
| 項目 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 腹腔鏡手術 | 傷が小さい、回復が比較的早い | 術後に血圧が下がらない場合もある |
| 開腹手術 | 広い視野で確実に腫瘍を摘出 | 体への負担が大きくなる |
薬物療法の種類
片側性でも手術を行わない場合や、両側性過形成の場合には、アルドステロン拮抗薬(スピロノラクトン、エプレレノンなど)をメインに血圧と電解質の調整を行います。
アルドステロン拮抗薬は腎でのナトリウム再吸収を抑制し、カリウムの排出を減らして血清カリウム値を安定させる働きが期待でき、また、他の降圧薬を併用しながら、血圧を狙った範囲内に落ち着けるようコントロールすることが大切です。
アルドステロン拮抗薬の特徴
- スピロノラクトン:長年の実績があるが、男性の乳房肥大など副作用に注意が必要
- エプレレノン:副作用が比較的軽いとされるが、費用はやや高め
食事と生活習慣の見直し
原発性アルドステロン症に限らず、高血圧を含む生活習慣病には、減塩食やバランスの良い食事が重要で、特にアルドステロン拮抗薬を使用している場合、カリウムが過剰にならないように注意する必要があります。
むやみにカリウムを多く含む食品を摂取しすぎると、逆に高カリウム血症のリスクが高まるため、主治医と相談しながら摂取バランスを整えていくことが大切です。
長期的な血圧コントロール
手術で摘出した後でも、血圧が完全に正常化する保証はなく、長期間にわたるフォローアップが必要であり、場合によっては引き続き降圧薬の内服を継続することもあります。
両側性過形成の場合は、アルドステロン拮抗薬を含めた薬物療法を長期間継続し、血圧と電解質を安定化させ、定期的な血液検査を行いながら、病状の進行や合併症を防ぐために細やかな調整を続けることが重要です。
原発性アルドステロン症の治療期間
治療期間は、病型や手術の有無、患者の年齢や合併症の状況などによって異なり、手術で一気に症状が改善するケースもあれば、長期間にわたって薬を飲み続け、血圧と電解質を管理する必要がある場合もあります。
治療開始から安定までの流れ
まずはアルドステロン過剰分泌を疑う段階から、各種検査を経て病型が確定するまでに時間がかかることがあり、その後、手術適応か薬物療法かを決定し、実際の治療を開始します。
早い段階で血圧がコントロールできる人もいれば、薬の調整に数か月かかる人もいて、安定した状態に落ち着くまでの期間は個人差が大きいです。
治療期間に関するポイント
- 手術を受ける場合、術後数週間~数か月で血圧とカリウム値の安定を期待できる
- 両側性過形成の場合、長期の内服治療が続くことが多い
術後フォローアップの期間
腺腫を摘出した場合でも、血圧とカリウム値がすぐに安定しない方もいて、術後のホルモンバランスが回復していく過程で、降圧薬やカリウム補給の量などを調整することが必要です。
退院後も定期的に通院して検査を受け、血液検査やホルモン値を測定しつつ、薬の減量や追加などを慎重に行います。
薬物調整のタイミング
アルドステロン拮抗薬や降圧薬を使用する場合、最初から適切な用量が決まるわけではなく、血圧の推移やカリウム値を見ながら、少しずつ増量や減量を行い、いかに良いバランスを保つかが重要です。
特にカリウム値が変動しやすいため、定期的な血液検査でモニタリングしながら調整し、治療薬の種類や量を変えるときは、医師だけでなく、薬剤師などとの連携も大切になります。
治療プロセスと必要な期間の目安
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 検査確定まで | 血液検査、確認試験、画像検査 | 数週間~数か月 |
| 治療開始 | 手術または薬物療法のスタート | 1~3か月程度で効果判定 |
| 安定化 | 薬物調整やフォローアップ | 半年以上かかることもある |
個人差と回復の目安
手術直後に劇的に血圧が改善する人もいますが、何割かの人は血圧が完全に正常値まで下がらず、降圧薬を継続して内服することが必要です。
高血圧歴が長い方や動脈硬化が進行している方では、血管の硬化が原因で血圧が下がりにくいこともあり、また、両側性過形成などで手術ができないケースでは、アルドステロン拮抗薬によるコントロールを一生続ける場合もあります。
副作用や治療のデメリットについて
治療を進めるうえで、副作用やデメリットを正しく理解しておくことは大切です。外科的治療には手術特有のリスクがあり、薬物療法にはホルモンバランスの変化や別の合併症のリスクが伴います。
薬物が引き起こすホルモン変化
アルドステロン拮抗薬を使用すると、体内でナトリウムやカリウムのバランスが変わり、高カリウム血症になるリスクがあり、男性の場合はスピロノラクトンによって乳房の張りや大きさの変化(女性化乳房)が生じる可能性があります。
また、女性でも月経周期に変動が出ることがあるので、こうしたホルモン由来の副作用については、服用開始時に医師から十分な説明を受けることが重要です。
外科的治療の合併症
腹腔鏡手術は比較的安全性が高いとはいえ、麻酔のリスクや術後出血、感染など一般的な手術の合併症が起こる可能性があります。
また、片側の副腎を摘出しても残った副腎の機能が低下している場合には、充分に血圧やカリウム値が改善しないケースもあります。術後に急激なホルモンバランスの変化が起こると、一時的に不整脈や倦怠感を強く感じる人もいます。
日常生活への影響
長期間の薬物療法が必要な場合、毎日薬を飲み続ける手間や、定期的な通院による時間的負担を感じるかもしれません。
また、カリウムやナトリウムのバランスを考慮しながら食事を選ぶ必要があるため、外食や旅行などで食事内容を自由に決めにくいと感じる方もいます。
ただし、医師や管理栄養士のアドバイスを受けながら調整すれば、無理なく続けられる方法を見つけやすいです。
日常生活で注意しておきたい点
- 血圧やカリウム値のチェックを定期的に行う
- 塩分の摂りすぎやカリウムサプリの過剰摂取に注意する
- 運動や睡眠など基本的な生活リズムにも配慮する
定期的な検査の負担
治療を受けている間は定期的に血液検査を受け、アルドステロン・レニン比や電解質、腎機能などをチェックする必要があり、これによって副作用の早期発見や、薬の用量調整を行い、理想的な状態を保てます。
ただし、採血や通院が続くと心理的・経済的負担を感じる方もいるため、医療スタッフとコミュニケーションをとりながら無理のないスケジュールを組むことが大切です。
原発性アルドステロン症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
代表的な費用の目安
初期検査から手術まで行うと、合計で数十万円の費用がかかるケースもあり、CTやMRIなどの画像検査費用、血液検査やホルモン負荷試験などの検査費用、そして手術や入院費用が主な内訳です。
ただし、公的保険が適用されるため、自己負担は医療機関により異なるものの3割負担が基本になります。
主な項目と保険適用後のおおよその自己負担
| 項目 | 内容 | 自己負担目安 |
|---|---|---|
| 血液検査(ホルモン測定) | アルドステロン・レニン値など | 数千円~1万円程度 |
| 画像検査(CT/MRI) | 副腎の状態確認 | 5千円~1.5万円程度 |
| 手術(腹腔鏡など) | 片側副腎の摘出 | 10万円~20万円程度 |
| 薬物療法(1か月) | アルドステロン拮抗薬など | 数千円~1万円前後 |
採血やホルモン検査の費用
原発性アルドステロン症のスクリーニングや確認検査では、アルドステロンとレニンの測定がポイントで、一般的な血液検査と同様に保険が適用され、自己負担は数千円ほどです。
ただし、カプトプリル負荷試験などの特殊な負荷検査を受ける場合、多少費用が上乗せにされます。
画像検査の費用
副腎の形態を評価するために行うCTやMRIは、検査1回あたりで5千円から1.5万円程度の自己負担が目安で、造影剤を使う場合や撮影範囲が広い場合などで変動し、医療機関ごとに設定料金は異なります。
検査費用の考え方
- 初回の検査でCTやMRIを行い、腺腫の有無などを確認する
- 病型が確定しない場合は追加検査が必要になる可能性がある
- 保険適用後の自己負担額は撮影内容や医療機関によって変わる
手術と薬物療法の費用
片側性の腺腫による原発性アルドステロン症で手術を行う場合、入院費用を含めて保険適用後でも10万円~20万円程度を目安に考えておくと良いでしょう。
入院日数や手術方法によっても費用に幅があり、開腹手術より腹腔鏡手術のほうが入院期間がやや短いです。両側性過形成などで薬物療法を選択すると、アルドステロン拮抗薬の費用が継続的にかかります。
1か月あたりで数千円~1万円前後の負担が見込まれますが、薬の種類や併用する降圧薬の有無で変化します。
治療法別の費用
- 片側性の腺腫で手術を受ける場合、まとまった額の出費が必要になる
- 薬物療法は月々の費用負担が続くが、手術に比べて急な高額支出は少ない
- 病型と患者の状況によって最終的な費用は大きく変わる
以上
参考文献
Takeda Y, Karashima S, Yoneda T. Primary aldosteronism, diagnosis and treatment in Japan. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. 2011 Mar;12:21-5.
Ohno Y, Sone M, Inagaki N, Yamasaki T, Ogawa O, Takeda Y, Kurihara I, Itoh H, Umakoshi H, Tsuiki M, Ichijo T. Prevalence of cardiovascular disease and its risk factors in primary aldosteronism: a multicenter study in Japan. Hypertension. 2018 Mar;71(3):530-7.
Naruse M, Katabami T, Shibata H, Sone M, Takahashi K, Tanabe A, Izawa S, Ichijo T, Otsuki M, Omura M, Ogawa Y. Japan Endocrine Society clinical practice guideline for the diagnosis and management of primary aldosteronism 2021. Endocrine Journal. 2022;69(4):327-59.
Miyake Y, Tanaka K, Nishikawa T, Naruse M, Takayanagi R, Sasano H, Takeda Y, Shibata H, Sone M, Satoh F, Yamada M. Prognosis of primary aldosteronism in Japan: results from a nationwide epidemiological study. Endocrine journal. 2014;61(1):35-40.
Satoh F, Morimoto R, Iwakura Y, Ono Y, Kudo M, Takase K, Ito S. Primary aldosteronism: a Japanese perspective. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. 2011 Mar;12:11-4.
Sato M, Morimoto R, Seiji K, Iwakura Y, Ono Y, Kudo M, Satoh F, Ito S, Ishibashi T, Takase K. Cost-effectiveness analysis of the diagnosis and treatment of primary aldosteronism in Japan. Hormone and Metabolic Research. 2015 Oct;47(11):826-32.
Nishikawa T, Omura M, Saito J, Matsuzawa Y. Primary aldosteronism: comparison between guidelines of the Japanese and the US Endocrine Society. Expert Review of Endocrinology & Metabolism. 2012 Nov 1;7(6):637-45.
Morisaki M, Kurihara I, Itoh H, Naruse M, Takeda Y, Katabami T, Ichijo T, Wada N, Yoshimoto T, Ogawa Y, Sone M. Predictors of clinical success after surgery for primary aldosteronism in the Japanese nationwide cohort. Journal of the Endocrine Society. 2019 Nov;3(11):2012-22.
Nishikawa T, Omura M. Clinical characteristics of primary aldosteronism: its prevalence and comparative studies on various causes of primary aldosteronism in Yokohama Rosai Hospital. Biomedicine & pharmacotherapy. 2000 Jun 1;54:83s-5s.
Saiki A, Otsuki M, Mukai K, Hayashi R, Shimomura I, Kurihara I, Ichijo T, Takeda Y, Katabami T, Tsuiki M, Wada N. Basal plasma aldosterone concentration predicts therapeutic outcomes in primary aldosteronism. Journal of the Endocrine Society. 2020 Apr;4(4):bvaa011.