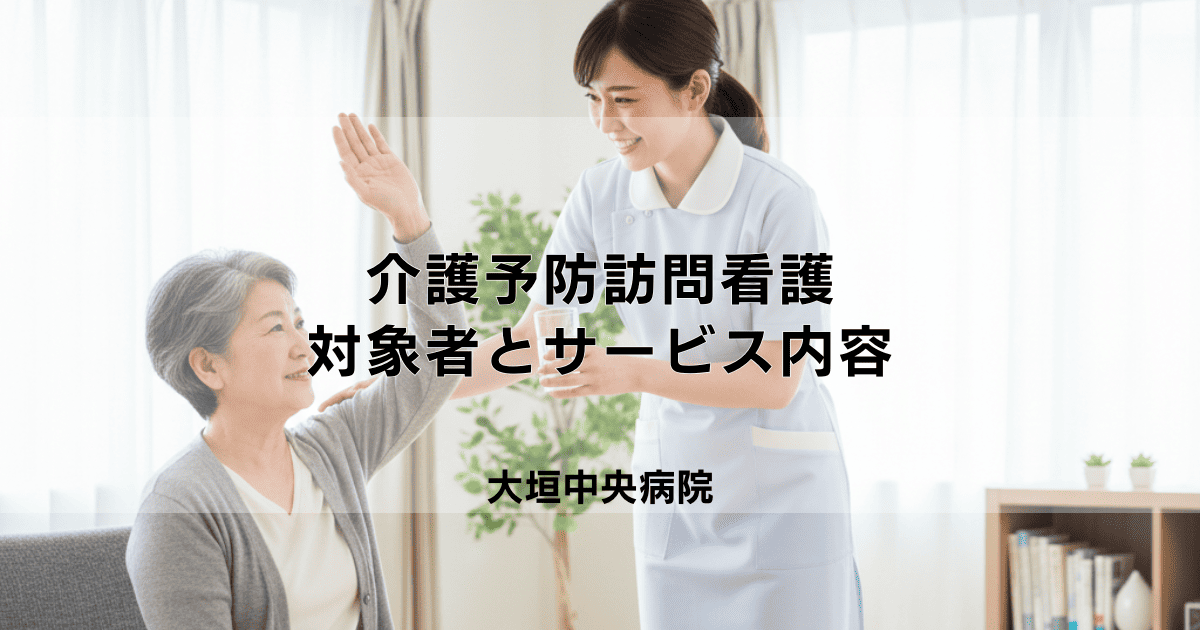年齢を重ねても、できるだけ自分らしく住み慣れた地域で生活を続けたいと願う方は多いでしょう。介護予防訪問看護は、そうした思いを支えるためのサービスの一つです。
介護が必要な状態になるのを防ぐ、また、状態の悪化を遅らせることを目的として、看護師や保健師がご自宅を訪問します。
この記事では、介護予防訪問看護がどのようなサービスなのか、どのような方が利用できるのか、サービス内容や利用目的について、わかりやすく解説していきます。
介護予防訪問看護の基本的な考え方
介護予防訪問看護を理解するためには、まず背景にある介護予防という考え方を知ることが大切です。単に病気の治療を行うだけでなく、生活全体を見据えた支援が求められます。
介護予防とは何か
介護予防は、高齢者が要介護状態(寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態)になることを可能な限り防ぐ、あるいはその状態になっても悪化を遅らせるための取り組みのことです。
健康寿命の延伸を目指す
平均寿命が延びる一方で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、いわゆる健康寿命との差が問題視されています。介護予防は、この健康寿命を延ばし、生涯にわたって生き生きとした生活を送ることを支援する考え方です。
単に長生きするだけでなく、質の高い生活を維持することを目指します。
介護が必要になる前の取り組み
多くの場合介護が必要になるまで、ご自身の身体機能や認知機能の小さな変化に気づきにくいものです。介護予防では、そうしたわずかな兆候を早期に発見し、適切な運動や栄養改善、社会参加などを通じて、機能の維持・向上を図ります。
自覚症状がないうちからの継続的な取り組みが、将来の生活を大きく左右します。
訪問看護が果たす予防的役割
訪問看護と聞くと、病気や怪我で寝たきりの方のケアを想像するかもしれません。
介護予防において訪問看護は、医療の専門家である看護師が早期から関わることで、重症化を防ぐという重要な役割を担い、利用者の生活の場であるご自宅で、個々の状態に合わせた専門的な支援を行います。
- 健康状態の観察
- 生活リズムの構築支援
- 低栄養や脱水の予防
- 転倒リスクの評価
- 服薬管理の助言
地域包括ケアシステムにおける位置づけ
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が進められています。
介護予防訪問看護は、このシステムの中で、予防と医療の側面から在宅生活を支える重要なサービスとして位置づけられていて、地域の医療機関や介護サービス事業者と連携し、利用者を多角的に支援します。
地域包括ケアシステムの主な構成要素
| 要素 | 主な内容 | 介護予防訪問看護との関わり |
|---|---|---|
| 医療 | かかりつけ医、病院など | 医療機関と連携し、健康状態を共有 |
| 介護・予防 | ケアマネジャー、デイサービスなど | 予防的な視点での看護を提供 |
| 生活支援 | 配食サービス、見守りなど | 生活上の課題を発見し、関係機関につなぐ |
介護予防訪問看護の対象となる方
介護予防訪問看護は、どなたでも利用できるわけではなく、特定の条件を満たす方が対象です。ご自身やご家族が該当するかどうか、確認してみましょう。
要支援認定(要支援1・2)の方が対象
介護予防訪問看護の主な対象者は、介護保険の要介護認定において要支援1または要支援2と認定された方です。
要支援とは、日常生活の基本的な動作は自分で行えるものの、家事や身支度などの一部の動作において見守りや支援が必要な状態で、この段階から適切な支援を受けることで、要介護状態への進行を防ぐことを目指します。
要支援1の状態とは
要支援1は、要支援2に比べて、より状態が軽い段階です。立ち上がりや歩行に多少の不安定さが見られることがありますが、日常生活の大部分は自立して行えます。しかし、掃除や買い物など、少し複雑な動作には支援が必要な場合があります。
要支援2の状態とは
要支援2は、要支援1よりも支援の必要性が高い状態です。立ち上がりや歩行が不安定で、杖や手すりが必要になることがあります。
また、入浴や排泄、食事などの日常生活動作(ADL)の一部にも、見守りや手助けが必要となるケースが増えてきて、この段階での介入が、機能低下の予防に大きく影響します。
要支援1と要支援2の比較
| 項目 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 状態の目安 | 日常生活の一部に見守りや支援が必要 | 要支援1より支援の必要性が高い状態 |
| 移動能力 | 不安定さがあるが、概ね自立 | 杖や手すりが必要な場合がある |
| 生活支援 | 複雑な家事(掃除など)に支援が必要 | 入浴や更衣などにも見守りが必要な場合がある |
基本チェックリスト該当者(事業対象者)
要支援認定を受けていなくても、地域包括支援センターなどが行う基本チェックリストによって、生活機能の低下が見られ、介護予防が必要と判断された方も、介護予防訪問看護を利用できる場合があります。
この場合介護予防訪問看護は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の一環として提供されます。
基本チェックリストの目的
基本チェックリストは、高齢者ご自身が生活機能(運動、栄養、口腔、認知、社会参加など)の状態を簡易的に確認するためのツールで、早期に支援が必要な方を把握し、適切なサービスにつなげることが目的です。
特定の疾患や状態は問わない
医療保険の訪問看護が特定の疾患(厚生労働大臣が定める疾病など)を対象とすることが多いのに対し、介護予防訪問看護は、要支援認定や基本チェックリストに該当すれば、特定の疾患名や医療的な状態を問いません。
生活機能の低下を防ぎ、自立した生活を支援するという予防的な側面に重点が置かれています。
医療的ケアがなくても利用可能
介護予防訪問看護は、医療的な処置(点滴や褥瘡のケアなど)が日常的に必要ない方でも利用できます。医療的ケアが必要になる前の段階で、健康管理やリハビリテーション、生活指導を通じて、状態の維持・改善を図ることが主な目的です。
看護師が関わることで、病気の早期発見や重症化予防にもつながります。
介護予防訪問看護で受けられるサービス内容
介護予防訪問看護では、どのようなサービスを受けられるのでしょうか。利用者の状態や目標に合わせて、看護師が専門的な視点で支援計画を立て、実施します。
健康状態の確認と助言
看護師がご自宅を訪問し、利用者の健康状態を定期的に確認し、血圧、脈拍、体温などのバイタルサインの測定はもちろん、表情や話し方、皮膚の状態など、多角的に観察します。
ちょっとした変化に早期に気づき、病気の予防や悪化防止につなげるための重要な時間です。季節の変わり目の体調管理や、持病との付き合い方についても助言します。
主な健康チェック項目
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| バイタルサイン | 血圧、脈拍、体温、呼吸状態、血中酸素飽和度など |
| 全身状態 | 顔色、浮腫(むくみ)、皮膚の乾燥や傷、食欲、睡眠状態など |
| 服薬状況 | 薬の飲み忘れ、副作用の有無、管理方法の確認 |
日常生活の訓練と指導
自立した生活を続けるためには、日常生活の動作を安全かつ確実に行えることが大切です。
介護予防訪問看護では、食事、排泄、入浴、更衣など、日々の生活動作について、利用者の身体能力や生活環境に合わせて、より安全で楽に行うための工夫や訓練を支援し、ご自身でできることを維持・拡大できるような方法を一緒に考えます。
食事や栄養に関する支援
年齢とともに食が細くなったり、食事の準備が億劫になったりすることで、低栄養状態に陥ることがあります。
看護師が食生活の状況を聞き取り、栄養バランスの取れた食事の工夫や、調理しやすい方法、必要な栄養補助食品の活用などを助言します。低栄養は体力低下に直結するため、早期の対応が重要です。
口腔ケアのサポート
お口の健康は、食事をおいしく食べるためだけでなく、全身の健康や誤嚥性肺炎の予防にも深く関わっているので、看護師が口腔内の状態を観察し、ご自身でできる効果的な歯磨きや義歯の手入れの方法、うがいの仕方などを指導します。
必要に応じて、歯科医師や歯科衛生士との連携も図ります。
身体機能の維持・向上支援
要支援状態の方は、運動機能が低下しやすい傾向にあり、看護師が利用者の状態に合わせて、自宅で安全に行える簡単な体操やストレッチ、筋力トレーニングなどを指導します。
無理なく継続できる運動を生活に取り入れることで、筋力や柔軟性、バランス能力の維持・向上を目指します。
転倒予防のためのアドバイス
高齢者の転倒は、骨折や入院につながり、そのまま要介護状態へと進行する大きな原因です。
看護師がご自宅の環境をチェックし、手すりの設置や段差の解消、滑りやすい敷物の撤去など、転倒リスクを減らすための具体的な住環境の整備について助言し、また、ふらつきにくい歩き方や、履き物の選び方なども指導します。
- 住環境の確認
- 履き物の選定
- 筋力トレーニング
- バランス訓練
認知機能低下の予防
身体機能だけでなく、認知機能の維持・向上も介護予防の重要な柱です。看護師が訪問時に、計算問題やパズル、昔の思い出を話す回想法などを取り入れ、脳の活性化を促します。
また、日々の生活の中で、新聞を読む、日記をつける、人と会話するといった習慣を続けるよう助言することで、物忘れなどの初期症状に気づき、早期に対応するきっかけにもなります。
認知機能低下予防の取り組み例
| 分類 | 具体例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 知的活動 | 計算、音読、パズル、囲碁、将棋 | 脳の活性化、思考力の維持 |
| 社会活動 | 趣味の会、ボランティア、友人との交流 | 社会とのつながり、意欲の向上 |
| 運動 | ウォーキング、体操、軽い筋トレ | 脳血流の改善、身体機能の維持 |
介護予防訪問看護の主な利用目的
介護予防訪問看護を利用する方々は、さまざまな目的を持っています。ご自身の状況と照らし合わせながら、どのような目的で利用できるのかを見ていきましょう。
自宅での自立した生活を長く続けるため
最も多くの利用者が持つ目的が、住み慣れた自宅で、できるだけ長く自立した生活を続けることです。看護師が定期的に訪問することで、健康状態や生活上の小さな変化を早期に察知し、大きな問題になる前に対処できます。
専門家の見守りがあるという安心感が、在宅生活を続ける上での大きな支えとなります。
自分でできることを増やす
介護予防訪問看護は、単にできないことを手伝うサービスではありません。利用者が持っている能力を最大限に活かし、ご自身でできることを一つでも増やしていくことを支援します。
安全な入浴方法を一緒に練習したり、簡単な調理をご自身で行えるように工夫したりするなど、主体的な生活再建を目指します。
身体機能の低下を防ぐ
要支援状態になると、動くことが億劫になり、活動量が減少しがちで、さらなる身体機能の低下を招く悪循環につながります。介護予防訪問看護では、前述のような運動指導やリハビリテーションを通じて、筋力や体力の低下を防ぎます。
定期的な訪問が、運動を継続する動機づけにもなるのです。
身体機能低下のサイン
| 項目 | 具体的なサイン |
|---|---|
| 歩行 | 歩く速さが遅くなった、ふらつく、つまずきやすくなった |
| 立ち座り | 椅子から立ち上がるのに手すりが必要になった |
| 日常生活 | 重いものを持つのが辛くなった、階段の上り下りがきつい |
心身の健康に関する不安を解消する
一人暮らしの高齢者や、日中一人で過ごす時間が長い方は、ご自身の健康や将来の生活について漠然とした不安を抱えていることが少なくありません。介護予防訪問看護では、看護師が定期的に訪問し、ゆっくりと話を聞く時間を設けます。
体調のことはもちろん、生活上の困りごとや不安な気持ちを話せる相手がいることで、精神的な安定にもつながります。
専門家への相談機会
看護師は医療と介護の両方の知識を持つ専門家です。
病院に行くほどではないけれど気になる体調の変化や、介護サービスに関する疑問など、さまざまな相談に応じることができるので、利用者は安心して在宅生活を送ることができ、ご家族の介護負担感の軽減にも寄与します。
社会参加の促進
閉じこもりがちな生活は、心身の機能を低下させる大きな要因で、介護予防訪問看護では、利用者の興味や関心、地域の社会資源(デイサービス、趣味のサークル、地域の集まりなど)の情報を踏まえ、社会参加を促すことも目的の一つです。
他者との交流や役割を持つことが、生活への意欲や張り合いにつながります。
- デイサービス
- 地域のサロン
- 趣味の教室
- ボランティア活動
医療保険の訪問看護との違い
訪問看護には、介護保険を使う介護予防訪問看護のほかに、医療保険を使う訪問看護があり、この二つは似ているようで、目的や対象者、サービス内容に違いがあります。
目的の違い(治療・看護 vs 予防・自立支援)
医療保険の訪問看護は、主に病気や怪我の治療を目的とし、医師の指示に基づいた医療的処置(点滴、カテーテル管理、褥瘡のケアなど)や、症状の悪化防止、終末期のケアなどが中心となります。
介護予防訪問看護は、要支援状態の方の自立支援と要介護状態への進行予防が主な目的です。医療的な処置よりも、生活指導やリハビリテーション、健康管理の側面に重点が置かれます。
介護予防訪問看護と医療保険訪問看護の目的比較
| 項目 | 介護予防訪問看護(介護保険) | 医療保険訪問看護 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 介護予防、自立支援、重症化予防 | 病気や怪我の治療、医療的処置、ターミナルケア |
| 重点 | 生活指導、リハビリ、健康管理 | 医療的ケア、症状のモニタリング |
| 根拠 | ケアプラン | 医師の訪問看護指示書 |
対象者の違い
介護予防訪問看護の対象者は、要支援1・2の認定を受けた方、または基本チェックリストで事業対象者と判断された方です。
対して、医療保険の訪問看護は、年齢を問わず、医師が訪問看護の必要性を認めた方(赤ちゃんから高齢者まで)が対象となります。特に、厚生労働大臣が定める特定の疾病(がん末期、難病など)の方は、医療保険での訪問看護が優先されます。
サービス内容の重点
サービス内容にも重点の違いがあり、介護予防訪問看護では、利用者が自分でできることを増やすための訓練や指導が中心です。転倒予防のための筋力トレーニングや、低栄養を防ぐための食事指導など、予防的な関わりが主となります。
医療的処置の有無
医療保険の訪問看護では、点滴の管理、インスリン注射、気管カニューレの管理、褥瘡の処置といった専門的な医療的処置を日常的に行うことが多くあります。
介護予防訪問看護では、こうした医療的処置が主な目的となることは少なく、健康相談や生活指導が中心です。ただし、利用者の状態に応じて、かかりつけ医と連携し、必要な医療的ケアを(医療保険で)行う場合もあります。
介護予防訪問看護の利用開始までの流れ
実際に介護予防訪問看護を利用したいと考えた場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。一般的な利用開始までの流れを説明します。
相談窓口(地域包括支援センター)
まず最初の窓口となるのが、お住まいの地域にある地域包括支援センターで、地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口であり、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が配置されています。
ここで、ご自身やご家族の現在の状況や困りごと、介護予防訪問看護の利用希望などを相談します。
まずは相談から
まだ要支援認定を受けていない場合や、どのサービスが適切かわからない場合でも、まずは地域包括支援センターに相談することが第一歩です。専門家が状況を整理し、必要な手続きや利用できるサービスについて案内します。
要支援認定または基本チェックリストの確認
相談の結果、介護予防サービスの利用が必要と判断された場合、要支援認定の申請手続きを行い、すでに要支援認定を受けている場合は、その旨を伝えます。
また、要支援認定に至らない場合でも、基本チェックリストにより事業対象者と判断されれば、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス(介護予防訪問看護を含む)を利用できる可能性があります。
- 地域包括支援センターへの相談
- 要支援認定の申請
- (または)基本チェックリストの実施
ケアプランの作成
要支援認定または事業対象者となると、地域包括支援センターの担当者(または委託された居宅介護支援事業所のケアマネジャー)が、利用者や家族と面談し、介護予防ケアプランを作成します。
ケアプランは、利用者の心身の状態や生活環境、希望する生活を踏まえて作ることが大切です。
目標の設定
ケアプラン作成において重要なのが、目標の設定です。例えば、「一人で安全に近所のスーパーまで買い物に行けるようになる」「趣味の集まりに月2回参加する」など、利用者本人の意欲を引き出すような目標を一緒に考えます。
介護予防訪問看護は、この目標を達成するための一つの手段として位置づけられます。
ケアプラン作成の大まかな流れ
| 段階 | 主な内容 | 関わる人 |
|---|---|---|
| 1. 相談・把握 | 利用者の状況や希望を聞き取る | 本人、家族、地域包括支援センター職員 |
| 2. 目標設定 | 生活上の課題を整理し、目標を決める | 本人、家族、地域包括支援センター職員 |
| 3. 計画作成 | 目標達成のためのサービス(訪問看護など)を決定 | 地域包括支援センター職員、サービス事業者 |
訪問看護ステーションとの契約
ケアプランに介護予防訪問看護の利用が組み込まれたら、利用する訪問看護ステーションを決定し、契約を結びます。
契約時には、サービス内容や利用料金、緊急時の連絡方法などについて、重要事項の説明を受けるので、内容をよく確認し、不明な点は質問しましょう。
契約後、訪問看護ステーションの看護師が、ケアプランに基づいた訪問看護計画を作成し、サービスの提供が開始されます。
介護予防訪問看護を利用する上でのポイント
介護予防訪問看護の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの大切なポイントがあり、サービスを受ける側の心構えとしても参考にしてください。
本人の主体的な取り組みが重要
介護予防は、看護師がすべてを行ってくれるものではなく、看護師はあくまでサポーターであり、主役は利用者ご本人です。
看護師からの助言や指導を日常生活に取り入れ、ご自身で「やってみよう」とする主体的な姿勢が、機能の維持・改善に直結します。
目標の共有
何のために介護予防に取り組むのか、目標を看護師としっかり共有することが大切です。「転ばずに散歩を続けたい」「孫と元気に遊びたい」などの目標を持つことで、日々のリハビリや生活改善への意欲も高まります。
目標が明確であれば、看護師もより的確な支援を提供できます。
家族の理解と協力
ご家族の理解と協力も、介護予防を進める上で大きな力です。
利用者が自宅で安心してリハビリに取り組めるよう環境を整えたり、看護師から指導された内容を一緒に実践したりするなど、家族の励ましやサポートが利用者のやる気を引き出します。
また、ご家族が利用者の日々の小さな変化に気づき、看護師に伝えることも、質の高いケアにつながります。
定期的な見直しの必要性
利用者の心身の状態は時間とともに変化し、生活環境や本人の希望が変わることもあるため、一度立てたケアプランや訪問看護計画が、常に最適な状態とは限りません。
定期的に(例えば3ヶ月や半年に一度)ケアプランを見直し、現在の状態や目標に合っているかを確認することが重要です。
定期的な見直しの視点
| 視点 | 確認する内容 |
|---|---|
| 目標の達成度 | 設定した目標は達成できているか |
| 心身の状態 | サービス開始時と比べて状態に変化はないか(改善・悪化) |
| 本人・家族の意向 | 新たな希望や困りごとはないか |
看護師との良好な関係づくり
介護予防訪問看護は、看護師が利用者のご自宅というプライベートな空間に入り、一定期間継続して関わるサービスのため、利用者と看護師との信頼関係が非常に大切です。
ご自身の体調や不安、生活の中で感じていることを素直に話せる関係を築くことで、看護師も利用者のニーズを深く理解し、より質の高い支援を提供できます。
- 体調の変化を伝える
- 不安なことを相談する
- 生活での困りごとを話す
- 目標を共有する
介護予防訪問看護に関するよくある質問
最後に、介護予防訪問看護に関して多く寄せられる質問と回答をまとめました。利用を検討する際の参考にしてください。
- どのくらいの頻度で利用できますか?
-
利用頻度は、ケアプランに基づいて決定され、利用者の状態や目標に応じて、週に1回、あるいは2週に1回など、必要な回数が設定されます。
介護予防訪問看護は、集中的に介入するというよりも、定期的に関わりを持つことで生活リズムを整え、健康状態を維持することを目的とする場合が多いです。
頻度については、地域包括支援センターの担当者やケアマネジャーにご相談ください。
- 家族も一緒に指導を受けられますか?
-
ご家族も一緒に指導や助言を受けることができます。ご家族が利用者の状態や必要なケアについて理解を深めることは、介護予防の効果を高める上で非常に重要です。
転倒予防のための環境整備の方法や、安全な介助の方法、利用者との関わり方など、ご家族の不安や疑問にも看護師がお答えします。訪問日時にご家族が在宅できるよう調整することもできます。
- 途中で体調が悪化したらどうなりますか?
-
介護予防訪問看護の利用中に体調が悪化した場合、訪問看護師はまず利用者の状態を評価し、かかりつけ医と速やかに連携を取ります。
必要に応じて、医療保険による訪問看護に切り替えて訪問回数を増やしたり、より医療的な処置を行ったりするなど、迅速に対応します。状態が安定すれば、再び介護予防訪問看護に戻ることも可能です。
- どんな服装で待っていればよいですか?
-
特別な服装を用意する必要はありません。普段ご自宅でリラックスして過ごしている服装で大丈夫です。ただし、看護師が血圧を測ったり、皮膚の状態を見たり、あるいは一緒に軽い体操をしたりすることがあります。
腕まくりがしやすい服装や、少し体を動かしやすい服装(例:ジャージやゆったりしたズボン)であると、よりスムーズにケアを受けられます。
以上
参考文献
Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.
Kono A, Izumi K, Yoshiyuki N, Kanaya Y, Rubenstein LZ. Effects of an updated preventive home visit program based on a systematic structured assessment of care needs for ambulatory frail older adults in Japan: a randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. 2016 Dec 14;71(12):1631-7.
Ishibashi T, Ikegami N. Should the provision of home help services be contained?: validation of the new preventive care policy in Japan. BMC Health Services Research. 2010 Aug 2;10(1):224.
Murashima S, Nagata S, Magilvy JK, Fukui S, Kayama M. Home care nursing in Japan: a challenge for providing good care at home. Public health nursing. 2002 Mar;19(2):94-103.
Kono A, Izumi K, Kanaya Y, Tsumura C, Rubenstein LZ. Assessing the quality and effectiveness of an updated preventive home visit programme for ambulatory frail older Japanese people: research protocol for a randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing. 2014 Oct;70(10):2363-72.
Kono A, Fujita T, Tsumura C, Kondo T, Kushiyama K, Rubenstein LZ. Preventive home visit model targeted to specific care needs of ambulatory frail elders: preliminary report of a randomized trial design. Aging clinical and experimental research. 2009 Apr;21(2):167-73.
Kono A, Kanaya Y, Tsumura C, Rubenstein LZ. Effects of preventive home visits on health care costs for ambulatory frail elders: a randomized controlled trial. Aging Clinical and Experimental Research. 2013 Oct;25(5):575-81.
Igarashi A, Yamada Y, Ikegami N, Yamamoto‐Mitani N. Effect of the Japanese preventive‐care version of the Minimum Data Set–Home Care on the health‐related behaviors of community‐dwelling, frail older adults and skills of preventive‐care managers: A quasi‐experimental study conducted in Japan. Geriatrics & Gerontology International. 2009 Sep;9(3):310-9.
Ito T, Mori T, Takahashi H, Shimafuji N, Iijima K, Yoshie S, Tamiya N. Prevention services via public long-term care insurance can be effective among a specific group of older adults in Japan. BMC Health Services Research. 2021 May 30;21(1):531.
Yamada Y, Ikegami N. Preventive home visits for community‐dwelling frail elderly people based on Minimum Data Set‐Home Care: Randomized controlled trial. Geriatrics & Gerontology International. 2003 Dec;3(4):236-42.