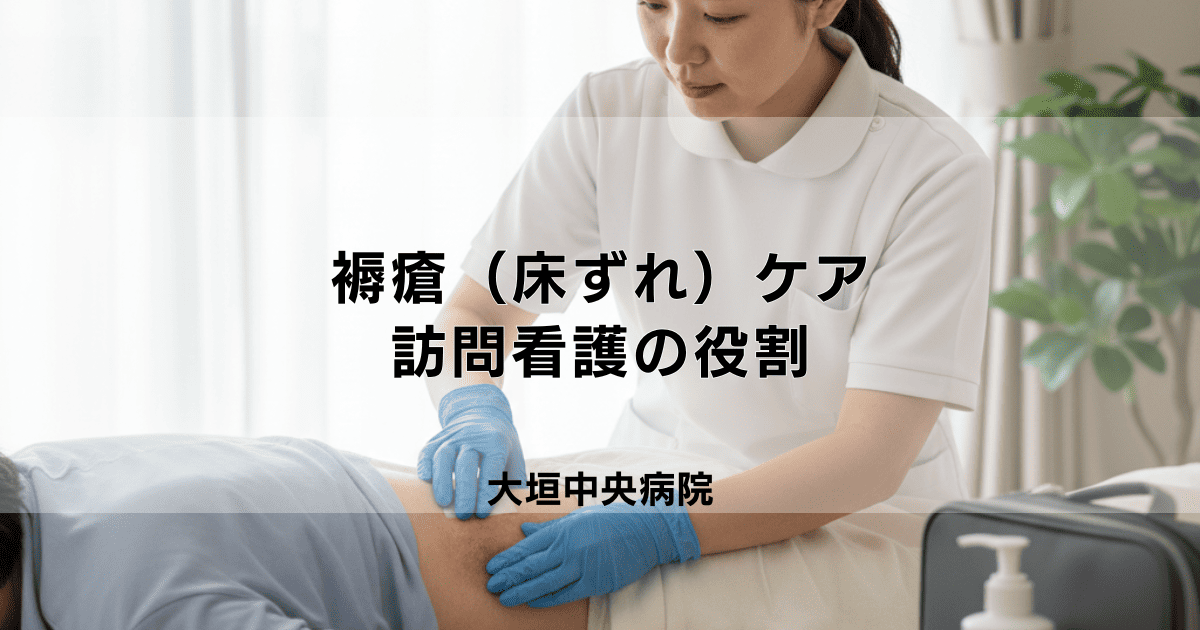ご自宅で療養生活を送る中で、褥瘡(床ずれ)は多くの方が直面する可能性のある皮膚のトラブルです。
一度できてしまうと治りにくく、患者さんの苦痛が大きいだけでなく、介護を行うご家族の負担も増えてしまいますが、褥瘡は適切な知識とケアによって予防でき、悪化を防ぐことができます。
この記事では、在宅療養における褥瘡ケアの重要な担い手である訪問看護の役割に焦点を当て、褥瘡の基本的な知識から、予防策、発生してしまった場合の処置、日々の管理のポイントまでを詳しく解説します。
褥瘡(床ずれ)とは?発生の主な原因
褥瘡とは、一般的に床ずれとも呼ばれ、長時間同じ体勢で寝ていたり、車椅子に座り続けたりすることで、体の特定の部分が圧迫され続け、皮膚やその下の組織が傷ついてしまう状態です。
ご自身で体勢を変えることが難しい方に起こりやすく、皮膚の血行が悪くなることが直接的な引き金となり、組織の壊死に至ることもあります。
皮膚への圧力と血行障害
褥瘡発生の最も大きな原因は、体重によって骨の突出した部分(骨突部)の皮膚が長時間圧迫されることです。
通常、私たちの体は無意識のうちに寝返りを打ったり、座り直したりして、同じ場所に圧力がかかり続けないように調整していますが、病気や加齢によって寝たきりの状態や、座ったままの状態が続くと、自己調整が難しくなります。
皮膚が圧迫されると、その部分の血管も圧迫されて細くなり、血液の流れが滞ってしまいます。血液は酸素や栄養を細胞に届け、老廃物を運び去る重要な役割を担っているため、血行障害が続くと皮膚の細胞は死んでしまい、褥瘡が発生します。
褥瘡が発生しやすい体の部位
- 仙骨部(お尻の中央の骨)
- 踵骨部(かかと)
- 大転子部(太ももの付け根の骨)
- 腸骨部(腰骨)
- 肩甲骨部
摩擦とずれが引き起こす皮膚へのダメージ
圧力に加えて、摩擦とずれも褥瘡の大きな原因です。
摩擦は、ベッドの上で体を引きずって移動させる時などに、シーツと皮膚がこすれて起こり、こすれによって皮膚の表面にある角質層が剥がれ、皮膚のバリア機能が低下し、傷つきやすくなります。
ずれは、ベッドの頭側を上げた際に、体(特にお尻)が足元へ滑り落ちようとする力によって生じます。
この時、皮膚の表面はシーツに固定されたまま、体の中の骨格だけが下にずれるため、皮膚と皮下組織の間で血管が引っ張られ、ねじれてしまい、血行がさらに悪化し、褥瘡のリスクを高めます。
栄養状態や皮膚の湿潤などの全身的な要因
褥瘡の発生には、局所的な圧迫や摩擦だけでなく、体全体の健康状態も深く関わっています。特に栄養状態の悪化は、皮膚を弱くし、褥瘡を発生しやすく、また治りにくくする大きな要因です。
皮膚や筋肉を作るために必要なたんぱく質や、皮膚の健康を保つビタミン、ミネラルが不足すると、皮膚は弾力性を失い、わずかな刺激でも傷つきやすくなります。
また、汗や失禁によって皮膚が常に湿った状態(湿潤)にあると、皮膚がふやけて傷つきやすくなり、バリア機能が低下します。その他、むくみ(浮腫)や糖尿病、血行障害などの持病も褥瘡のリスクを高める要因です。
褥瘡の発生に関わる全身的な危険因子
| 危険因子 | 内容 | 皮膚への影響 |
|---|---|---|
| 低栄養 | たんぱく質やビタミン、ミネラルなどの不足 | 皮膚の弾力低下、治癒能力の低下 |
| 湿潤 | 汗、尿、便などによる皮膚の蒸れ | 皮膚のバリア機能低下、損傷しやすくなる |
| 加齢 | 皮膚の菲薄化、皮下脂肪の減少 | クッション性の低下、外的刺激への脆弱性 |
なぜ褥瘡(床ずれ)の早期発見と対策が重要なのか
褥瘡は、一度発生すると急速に悪化することがあり、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させる可能性があります。
褥瘡を発生させないための予防はもちろんのこと、万が一発生してしまった場合に、いかに早い段階で発見し対策を講じるかが極めて重要です。
痛みや不快感による生活の質の低下
褥瘡は、初期の段階では赤みが見られる程度ですが、進行すると皮膚が破れ、傷口が深くなり、強い痛みを伴うようになり、痛みは、体位変換の時だけでなく、安静にしている時でさえ続くことがあり、患者さんにとって大きな苦痛となります。
痛みのために十分な睡眠がとれなくなったり、食欲が低下したりすることもあり、また、傷口からの滲出液や臭いが気になり、精神的なストレスを感じる方も少なくありません。
感染症のリスクと重症化
褥瘡によってできた傷口は、細菌が侵入しやすい状態にあり、皮膚のバリア機能が破れているため、黄色ブドウ球菌や緑膿菌などの細菌が繁殖しやすく、局所的な感染を起こすことがあります。
感染が起こると、傷の治りが悪くなるだけでなく、傷の周囲が赤く腫れたり、熱を持ったり、膿が出たりし、さらに重症化すると、細菌が血流に乗って全身に広がり、敗血症という命に関わる状態に陥る危険性もあります。
抵抗力が低下しているご高齢の方や、持病をお持ちの方にとって、褥瘡からの感染症は極めて深刻な問題です。
褥瘡の深さの分類(ステージ)
| 分類 | 皮膚の状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| ステージⅠ | 消えない発赤 | 指で押しても赤みが消えない。皮膚の損傷はない。 |
| ステージⅡ | 真皮までの欠損 | 水ぶくれやびらん(ただれ)が生じ、痛みがある。 |
| ステージⅢ | 皮下組織までの欠損 | 脂肪層まで傷が達し、くぼみができる。 |
| ステージⅣ | 筋肉・骨までの欠損 | 筋肉や腱、骨が見える状態。壊死組織が付着。 |
治療の長期化と介護負担の増大
褥瘡は、一度深くなってしまうと、治癒までに数ヶ月から一年以上かかることも珍しくなく、治療が長引けば、それだけ医療費の負担も大きくなります。
また、ご家庭で介護を行うご家族にとっては、毎日の傷の処置や体位変換、おむつ交換など、介護にかかる時間的・身体的な負担が大幅に増大します。精神的な負担も大きく、介護者が疲弊してしまう原因にもなりかねません。
褥瘡を早期に発見し、悪化させないように努めることは、患者さんの苦痛を和らげるだけでなく、介護を行うご家族の負担を軽減するためにも非常に大切です。
訪問看護における褥瘡(床ずれ)ケアの全体像
在宅での褥瘡ケアにおいて、訪問看護師は専門的な知識と技術を活かし、中心的な役割を果たします。
単に傷の処置をするだけでなく、褥瘡の発生リスクを評価し、予防計画を立て、患者さんやご家族への指導を行いながら、総合的に療養生活を支援します。
専門的なアセスメントとケア計画の立案
訪問看護師は、まず患者さんの全身状態を詳しく観察し、褥瘡の発生リスクがどの程度あるかを評価(アセスメント)し、ご自身で動ける能力、皮膚の状態、栄養状態、持病の有無、使用している寝具などを多角的に評価することが含まれます。
アセスメントの結果に基づき、一人ひとりの状態に合わせた個別のケア計画を立案し、体圧分散寝具の導入を検討したり、体位変換の方法やスケジュールを提案したり、必要な栄養素を補うための食事内容を助言したりします。
この計画は、医師やケアマネジャー、ご家族と共有し、チーム全体で取り組んでいくための指針です。
褥瘡リスク評価の視点
- 活動性(自力で動けるか)
- 可動性(体の向きを変えられるか)
- 知覚の認知(痛みや不快感を感じるか)
- 湿潤(失禁の有無など)
- 栄養状態
医師の指示に基づいた適切な創傷処置
褥瘡が発生してしまった場合、訪問看護師は医師の指示のもとで専門的な創傷処置(創傷ケア)を行います。
まず傷口を洗浄して清潔に保つことが含まれ、その後、褥瘡の深さや大きさ、滲出液の量、感染の有無などを的確に判断し、その状態に合ったドレッシング材(傷を保護するシート)を選択・使用します。
ドレッシング材には様々な種類があり、適切なものを選択することが、痛みを和らげ、治癒を促進する上で非常に重要です。また、傷の状態を継続的に観察し、変化があれば速やかに医師に報告し、指示を仰ぎながら処置方法を調整していきます。
ご本人とご家族への療養指導と精神的支援
訪問看護師の重要な役割の一つに、患者さんと介護を行うご家族への指導があります。
褥瘡を予防するためのスキンケアの方法、無理のない体位変換の工夫、栄養バランスの取れた食事の摂り方など、日常生活の中で実践できるケアの方法をお伝えし、また、介護用品の選び方や使い方についてもアドバイスすることも大切な役割です。
褥瘡ケアは長期にわたることが多く、ご家族は身体的にも精神的にも大きな負担を感じることがあるので、訪問看護師は、ご家族の悩みや不安に耳を傾け、話を聞くことで精神的な支えとなり、在宅療養を継続していけるよう支援します。
訪問看護師が行う主な療養指導の内容
| 指導項目 | 具体的な内容例 | 目的 |
|---|---|---|
| スキンケア指導 | 洗浄剤の選び方、洗い方、保湿剤の塗り方 | 皮膚のバリア機能を維持・強化する |
| ポジショニング指導 | クッションの使い方、安楽な姿勢の保持方法 | 特定の部位への圧迫を軽減する |
| 栄養指導 | たんぱく質を多く含む食品、補助食品の紹介 | 創傷治癒に必要な栄養を確保する |
褥瘡(床ずれ)の予防に向けた訪問看護の支援
褥瘡ケアにおいて最も重要なのは、何よりもまず褥瘡を発生させないことです。訪問看護では、専門的な視点からご自宅の療養環境を評価し、褥瘡予防のための支援を行います。
体圧分散の徹底と環境整備
褥瘡予防の基本は、皮膚にかかる圧力をできるだけ小さくし、分散させることです。訪問看護師は、ご本人様の体格や身体機能に合った体圧分散寝具(マットレスやクッション)の選定を支援します。
体圧分散寝具には、圧力を広範囲に分散させる静止型マットレスや、空気圧を変化させて圧迫部位を移動させる圧切替型エアマットレスなどがあります。
福祉用具は介護保険のレンタル対象となる場合が多く、ケアマネジャーと連携して導入を調整します。また、ベッド周りの環境を整え、患者さんが少しでも動きやすいように、またご家族が介護しやすいように工夫することも大切な支援の一つです。
体圧分散用具の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 対象となる方(目安) |
|---|---|---|
| 静止型マットレス | ウレタンフォームなどで体圧を分散させる | 自力で寝返りが少しできる方 |
| 圧切替型エアマットレス | 空気のセルが膨張・収縮し、圧迫部位を変える | 自力で全く動けない方、リスクが非常に高い方 |
| 体位変換クッション | 体の隙間を埋め、安楽な姿勢を保つ | 体位変換を行うすべての方 |
皮膚の清潔を保つスキンケアの実践
健康な皮膚を保つためには、スキンケアが欠かせません。皮膚の清潔を保ち、適切な潤いを維持することで、外部からの刺激に対するバリア機能を高めることができます。
訪問看護師は、ご本人様の皮膚の状態に合わせて、洗浄、保湿、保護の3つの基本に沿ったスキンケアを実践・指導します。洗浄時には、皮膚に優しい弱酸性の洗浄剤を使い、泡で優しく洗い、こすらないように注意してください。
洗浄後は、水分を優しく押さえるように拭き取り、乾燥しやすい部分には保湿剤を塗布して皮膚の潤いを保ち、失禁がある場合には、撥水効果のあるクリームなどを塗って皮膚を保護し、排泄物による刺激から守ります。
栄養状態の評価と食事内容への助言
皮膚も体の一部であり、健康は食事から摂る栄養によって支えられているので、栄養状態が悪いと、皮膚は薄く弱くなり、褥瘡ができやすいです。
訪問看護師は、定期的に体重測定を行ったり、血液検査のデータを確認したりしながら、患者さんの栄養状態を評価します。さらに、低栄養状態が疑われる場合には、医師や管理栄養士と連携し、食事内容の改善を支援します。
新しい皮膚を作る材料となるたんぱく質や、コラーゲンの生成を助けるビタミンC、細胞の再生に必要な亜鉛などを十分に摂取できるよう、食品や調理法について助言し、食事が十分に摂れない方には、栄養補助食品の活用を提案することもあります。
褥瘡(床ずれ)発生後の処置と悪化防止
予防策を講じていても、様々な要因が重なり褥瘡が発生してしまうことがあり、その場合は、傷を悪化させず、できるだけ早く治癒に導くための処置が重要です。訪問看護師は、医師と連携しながら、専門的な創傷ケアを提供します。
褥瘡の進行度に応じたドレッシング材の選択
褥瘡の処置では、傷の状態に合ったドレッシング材を選ぶことが治癒を左右する鍵となり、褥瘡は、深さ(ステージ)や滲出液の量、感染の有無などによって状態が刻々と変化します。
傷が浅く滲出液が少ない場合には、傷の乾燥を防ぎ、湿潤環境を保つタイプのドレッシング材を使用し、滲出液が多い場合には、余分な滲出液を吸収する能力の高いドレッシング材が必要です。
訪問看護師は、毎回傷の状態を注意深く観察し、その時点での最適なドレッシング材を医師の指示のもとで選択し、交換を行います。
ドレッシング材の主な種類と役割
| ドレッシング材の種類 | 主な役割 | 適した創の状態 |
|---|---|---|
| ハイドロコロイド | 湿潤環境の維持、自己融解の促進 | 滲出液が少ない~中等量の浅い創 |
| フォーム材 | 高い吸収力、創の保護 | 滲出液が多い創 |
| アルジネート材 | 高い吸収力、止血作用 | 滲出液が非常に多い創、出血を伴う創 |
創部の洗浄と壊死組織の管理
傷の治癒を促進するためには、創部を常に清潔に保つことが基本です。訪問看護師は、処置の際に生理食塩水や水道水を用いて、傷の表面やポケット(傷の奥の空洞)内部の細菌や異物を優しく洗い流します。
洗浄作業は、感染を予防し、新しい組織の再生を促すために非常に重要です。また、褥瘡が進行すると、黒色や黄色の硬い壊死組織が付着することがあり、壊死組織は細菌の温床となり、治癒を妨げるため、取り除く必要があります。
訪問看護師は、医師の指示に基づき、軟膏を使って壊死組織を柔らかくしたり、安全な範囲で物理的に除去したりする処置(デブリードマン)を行うことがあります。
痛みを最小限に抑えるケアの工夫
褥瘡の処置は、痛みを伴うことが少なくありません。患者さんの苦痛を少しでも和らげるため、訪問看護師は細心の注意を払ってケアを行います。
ドレッシング材を剥がす際には、皮膚を傷つけないようにゆっくりと剥がしたり、皮膚保護剤を使用したりします。創部の洗浄時にも、強い水圧をかけず、体温に近い温度の洗浄液を用いるなどの配慮をします。
また、処置を行うタイミングを、痛み止めの薬が効いている時間帯に合わせるなどの調整も行います。
痛みを緩和するためのケアのポイント
- 処置前に声かけを行う
- ドレッシング材はゆっくり剥がす
- 洗浄液の温度を調整する
- 鎮痛薬の効果時間に合わせて処置を行う
- 安楽な姿勢で処置を受ける
ご家庭でできる褥瘡(床ずれ)ケアとご家族の役割
在宅での褥瘡ケアは、訪問看護師だけで完結するものではなく、日々、患者さんのそばにいるご家族の協力が大きな力です。訪問看護師はご家族と連携し、安全で無理なく続けられるケアの方法を一緒に考えていきます。
日常的な皮膚の観察と早期発見のコツ
ご家族に期待される最も重要な役割の一つが、毎日の皮膚の観察です。褥瘡ができやすい骨の突出した部分を中心に、おむつ交換や着替え、体を拭く際などに皮膚の状態をチェックする習慣をつけましょう。
赤くなっている部分はないか、水ぶくれができていないか、皮膚が硬くなっていないかなどを確認します。赤くなっている部分を指で軽く押してみて、赤みが消えずに残る場合は褥瘡の初期段階(ステージⅠ)のサインです。
このような小さな変化に早く気づくことが、重症化を防ぐ第一歩となり、何か気になる変化を見つけたら、些細なことでも訪問看護師に伝えることが大切です。
ご家庭での皮膚観察のチェックポイント
| チェック項目 | 確認する内容 | 異常のサイン |
|---|---|---|
| 皮膚の色 | 赤み、紫色の変色、白っぽさ | 押しても消えない赤み |
| 皮膚の温度 | 周りの皮膚と比べて熱いか冷たいか | 局所的な熱感や冷感 |
| 皮膚の硬さ | むくみ、腫れ、硬さ | 周りと比べて硬くなっている |
無理のない範囲での体位変換への協力
定期的な体位変換は、褥瘡の予防と改善に効果的です。訪問看護師は、患者さんにとって楽で、かつ圧力が分散できるような姿勢の取り方や、クッションの使い方を指導します。
ご家族には計画に沿って、無理のない範囲で体位変換に協力していただくことがあります。
全ての体位変換をご家族だけで行うのは大変な負担になるため、訪問看護師が訪問しない時間帯に、少し体の向きを変えたり、お尻を少し浮かせたりするだけでも効果があります。小さな工夫でも、圧迫される時間を短縮することが重要です。
清潔保持と保湿を心がける生活習慣
皮膚を清潔に保ち、適度な潤いを与えることは、ご家庭でできる基本的な褥瘡予防策です。入浴やシャワーが難しい場合でも、蒸しタオルで体を拭いたり、部分的に洗浄したりすることで清潔を保つことができます。
排泄物で汚れやすいお尻周りは、こまめに洗浄し、清潔に保つことが大切です。体を拭いた後や、乾燥が気になる季節には、保湿剤を優しく塗ってあげると、皮膚のバリア機能が高まり、外部からの刺激に強い健康な皮膚を維持できます。
褥瘡(床ずれ)管理における多職種連携の重要性
褥瘡のケアは、訪問看護師一人の力で成し遂げられるものではなく、様々な専門職がそれぞれの役割を果たし、連携することによって、より質の高いケアが実現します。
かかりつけ医との密な情報共有
訪問看護師は、かかりつけ医の指示に基づいてケアを行うため、医師との連携は不可欠です。
訪問看護師は、ご自宅での患者さんの様子や褥瘡の状態の変化、処置への反応などを定期的に医師に報告し、写真を用いて傷の状態を正確に伝えることもあります。
報告に基づき、医師は治療方針を決定し、必要な薬の処方や処置の変更を指示します。緊急時や状態が悪化した際には、速やかに医師に連絡を取り、指示を仰ぎます。
情報を共有することで、ご自宅にいながらも、医師の専門的な判断に基づいた医療ケアを受け続けることが可能です。
ケアマネジャーと連携した福祉用具の活用
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険サービス全体の調整役を担います。褥瘡の予防や管理には、体圧分散寝具や車椅子用のクッション、体位変換を補助する用具などの福祉用具の活用が非常に有効です。
訪問看護師は、患者さんの状態をアセスメントした結果、必要だと判断した福祉用具についてケアマネジャーに情報提供します。
ケアマネジャーは、情報をもとにケアプランに必要なサービスとして位置づけ、福祉用具のレンタルや購入の手配を行います。
理学療法士や栄養士など他職種との協働
褥瘡ケアには、さらに多くの専門職が関わることがあり、理学療法士や作業療法士は、患者さんの残っている身体機能を活かした動き(起き上がりや移乗など)を指導し、活動性を高めることで褥瘡のリスクを減らす支援をします。
また、患者さんに合った車椅子の調整(シーティング)も行い、管理栄養士は、訪問看護師からの情報をもとに、褥瘡の治癒を促進するために必要な栄養素を考慮した食事プランを提案し、献立や調理法の指導を行います。
専門職がそれぞれの専門性を発揮し、情報を共有しながら協働することで、より包括的で効果的な褥瘡ケアを提供することが可能です。
在宅褥瘡ケアに関わる主な専門職と役割
| 専門職 | 主な役割 | 連携内容 |
|---|---|---|
| 医師 | 治療方針の決定、薬剤の処方、処置の指示 | 状態報告、指示受け |
| ケアマネジャー | ケアプラン作成、サービス調整、福祉用具手配 | 情報提供、サービス導入の相談 |
| 理学療法士 | リハビリテーション、ポジショニング指導 | ADL評価共有、動作指導の依頼 |
褥瘡(床ずれ)ケアに関するよくある質問
ここでは、褥瘡ケアに関して患者様やご家族からよく寄せられる質問についてお答えします。
- 褥瘡は一度できたら治らないのでしょうか?
-
治癒にかかる期間は褥瘡の深さや大きさ、患者さんの栄養状態や全身状態によって大きく異なります。浅い褥瘡であれば数週間で治ることもありますが、深い褥瘡の場合は数ヶ月以上かかることもあります。
大切なのは、諦めずに専門家と協力しながら、根気強くケアを続けることです。訪問看護師は、治癒に向けた道のりを一緒に歩み、サポートします。
- 訪問看護師は毎日来てもらえるのでしょうか?
-
訪問看護の頻度は病状や褥瘡の状態、ご家族の介護力などを考慮し、かかりつけ医の指示書とケアプランに基づいて決定します。重度の褥瘡があり、毎日の処置が必要な場合など、状態によっては毎日訪問することも可能です。
どのような頻度で訪問が必要かについては、主治医やケアマネジャー、訪問看護ステーションにご相談ください。
- 円座クッションは褥瘡予防に使っても良いですか?
-
一般的に、ドーナツ型の円座クッションの使用は推奨されていません。
円座クッションは、お尻の真ん中を浮かせるものの、その周囲の狭い範囲に圧力が集中してしまい、かえって血行を悪化させて褥瘡のリスクを高めることがあるからです。
褥瘡の予防や治療のためには、体圧を広範囲に分散できる専用のクッションやマットレスを使用することが重要です。どのような用具が良いかについては、訪問看護師や理学療法士などの専門家にご相談ください。
- 褥瘡を予防するために、皮膚をマッサージしても良いですか?
-
かつては血行を良くするためにマッサージが良いと考えられていた時期もありましたが、現在は推奨されていません。
特に骨が出っ張っている部分の皮膚はデリケートで、マッサージによってかえって皮膚の下の組織を傷つけてしまう危険性があるためです。赤くなっている部分を強くこすったり揉んだりすることは避けてください。
血行を促進するためには、マッサージよりも、優しく体を動かしたり、定期的に体位を変えたりする方が安全で効果的です。
以上
参考文献
Inoue T. The Present Situation and the Problem of Visiting Nursing: Team Care Management of Pressure Ulcers in the Elderly. Japan Medical Association Journal: JMAJ. 2015 Jun 1;58(1-2):19.
Yamashita R, Hisada R, Mori M, Nishino S, Daibatake M. Practices and Challenges of Home Care Pressure Ulcer Management; Perception of Home-visit Nurses Who Have Completed the Specified Medical Acts Training. The Journal of Medical Investigation. 2024;71(3.4):346-55.
Igarashi A, Yamamoto-Mitani N, Gushiken Y, Takai Y, Tanaka M, Okamoto Y. Prevalence and incidence of pressure ulcers in Japanese long-term-care hospitals. Archives of gerontology and geriatrics. 2013 Jan 1;56(1):220-6.
Noguchi K, Ochiai R, Imazu Y, Tokunaga-Nakawatase Y, Watabe S. Incidence and prevalence of infectious diseases and their risk factors among patients who use visiting nursing Services in Japan. Journal of Community Health Nursing. 2020 Jul 2;37(3):115-28.
Lee HJ, Ju YJ, Park EC, Kim J, Lee SG. Effects of home-visit nursing services on hospitalization in the elderly with pressure ulcers: a longitudinal study. The European Journal of Public Health. 2017 Oct 1;27(5):822-6.
Fact-finding Committee of the Japanese Society of Pressure Ulcers, Konya C, Takeuchi Y, Nakagami G, Kitamura A, Morita K, Ishizawa M, Abe Y, Higuchi H, Mizuki T, Motegi SI. Nationwide time-series surveys of pressure ulcer prevalence in Japan. Journal of Wound Care. 2022 Dec 1;31(Sup12):S40-7.
Yoshikawa Y, Maeshige N, Tanaka M, Uemura M, Hiramatsu T, Fujino H, Sugimoto M, Terashi H. Relationship between the cleaning frequency and healing time of pressure ulcers in elderly receiving home care: An observational pilot study. Journal of Wound Care. 2024 Jun 6;33(6).
Ibe T, Ishizaki T, Oku H, Ota K, Takabatake Y, Iseda A, Ishikawa Y, Ueda A. Predictors of pressure ulcer and physical restraint prevalence in Japanese acute care units. Japan Journal of Nursing Science. 2008 Dec;5(2):91-8.
Nakashima S, Yamanashi H, Komiya S, Tanaka K, Maeda T. Prevalence of pressure injuries in Japanese older people: a population-based cross-sectional study. PloS one. 2018 Jun 7;13(6):e0198073.
Yoshikawa Y, Maeshige N, Tanaka M, Uemura M, Hiramatsu T, Fujino H, Sugimoto M, Terashi H. Relationship between cleaning frequency and pressure ulcer healing time in older people receiving home care. Journal of Wound Care. 2024 Jun 2;33(6):418-24.