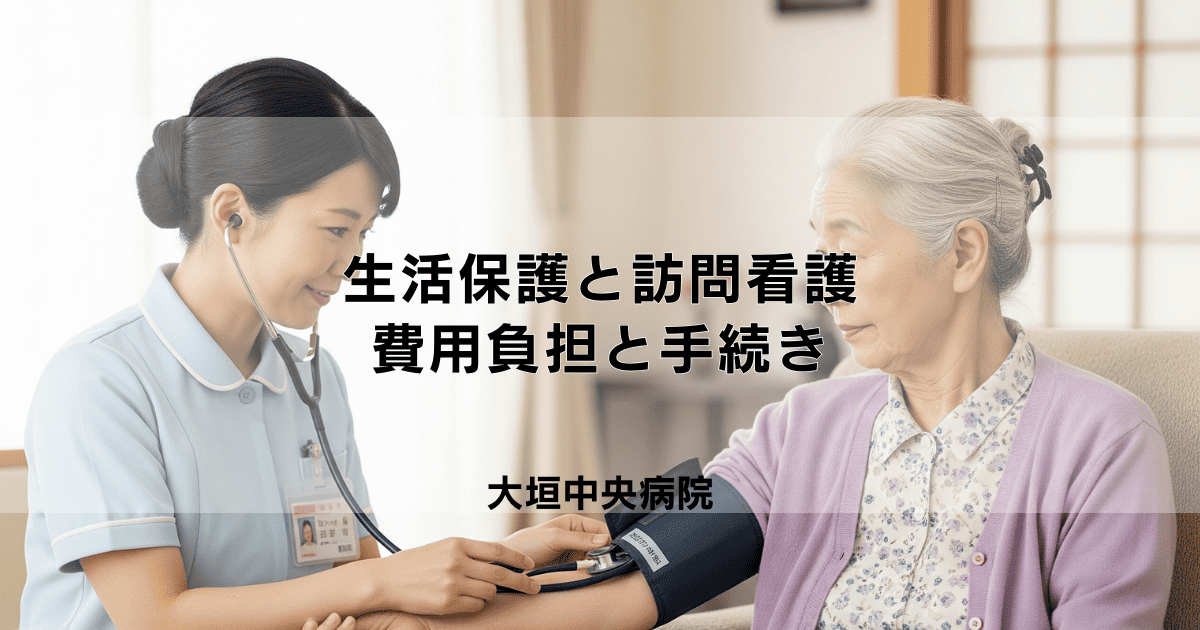病気やけがによりご自宅での療養が必要になったとき、専門家による看護を住み慣れた環境で受けられる訪問看護は、心強い支えとなりますが、生活保護を利用している方にとって、費用の心配は大きな問題です。
この記事では、生活保護を受けている方が訪問看護を利用する際の費用負担の仕組みや、サービス内容、利用開始までの手続きについて詳しく解説します。
経済的な負担なく、安心して在宅での療養生活を送るために、正しい知識を身につけていきましょう。
生活保護受給者の訪問看護利用 自己負担は原則無料
生活保護を受けている方が医師の指示に基づいて訪問看護を利用する場合、費用は公的制度によって賄われるため、自己負担は原則として発生しません。経済的な心配をすることなく、必要な医療ケアをご自宅で受けることが可能です。
医療扶助による費用負担の仕組み
生活保護制度には、生活を営む上で必要となるさまざまな費用に対応するため、8種類の扶助があります。その中の一つである医療扶助は、病気やけがの治療に要する費用を国が保障する制度です。
訪問看護は、医師が治療上必要と認めた医療サービスの一環として、この医療扶助の対象となります。利用者が医療機関の窓口で費用を支払うのではなく、医療機関が福祉事務所(公費負担者)へ直接費用を請求する現物支給という形をとります。
医療扶助の主な対象範囲
| 項目 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 診察・治療 | 医師による診察や治療、検査 | 外来受診、入院治療、手術 |
| 薬剤 | 医師が処方した薬の費用 | 内服薬、外用薬、注射薬 |
| 在宅療養 | 居宅で受ける医療関連サービス | 訪問看護、訪問リハビリ、在宅酸素療法 |
なぜ自己負担なしで利用できるのか
日本の生活保護法は、憲法第25条が保障する生存権の理念に基づいています。
国の責任において、生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することが目的です。この理念に基づき、医療を受ける権利も等しく保障されています。
訪問看護にかかる費用を医療扶助で全額支給することは、経済状況によって必要な医療を受けられないという事態を防ぎ、すべての人が尊厳を保ちながら療養生活を送れるようにするための重要な制度です。
介護保険ではなく医療保険が適用される理由
訪問看護の費用は、通常、年齢や疾患によって医療保険か介護保険のどちらかが適用されます。65歳以上の方や40歳以上65歳未満で特定の16疾病に該当する方は、原則として介護保険が優先されます。
しかし、生活保護を受けている方の場合、たとえ介護保険の被保険者であっても、訪問看護の費用は原則として医療扶助(医療保険の枠組み)から支給されます。
これは「生活保護法優先の原則」と呼ばれるもので、他の法律による保障で補えない部分を生活保護が補うという考え方に基づきます。
保険適用の優先順位
| 対象者 | 適用される制度 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 一般の高齢者(65歳以上) | 介護保険 | 原則1割〜3割 |
| 生活保護受給者(年齢問わず) | 医療扶助(生活保護) | 原則0円 |
| 若年層(医療保険加入者) | 医療保険 | 原則1割〜3割 |
交通費などの追加費用は発生するのか
訪問看護師が利用者の自宅へ訪問する際にかかる交通費も、原則として医療扶助の対象に含まれ、訪問看護の基本料金の一部として扱われます。そのため、利用者が別途、実費として交通費を請求されることはありません。
ただし、これは訪問看護ステーションが定める通常の訪問エリア内に限られます。エリア外への訪問を希望するなど、特別な事情がある場合は追加料金が発生する可能性も否定できません。
訪問看護で受けられるサービス内容
訪問看護では、看護師や理学療法士、作業療法士などの専門家がご自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて多岐にわたるケアを提供します。
健康状態の観察と管理
看護師が定期的に訪問し、血圧、体温、脈拍、呼吸、血中酸素飽和度などのバイタルサインを測定し、全身の状態を専門的な視点から詳しく観察します。病状の変化や薬の副作用の有無を早期に発見し、速やかに主治医と連携して対応策を講じます。
継続的なモニタリングは、病状の急な悪化を防ぎ、安定した在宅療養を維持するための基盤です。食事や水分摂取量、排泄の状況、睡眠の状態なども含めて総合的にアセスメントします。
健康管理の主なチェック項目
- バイタルサイン(血圧・体温・脈拍・呼吸)
- 病状や症状の変化(痛み、苦痛など)
- 薬の服用状況と副作用の有無
- 食事や水分の摂取量、排泄の状況
- 精神的な状態の変化(不安、不眠など)
日常生活の援助と療養上の世話
身体の清潔を保つための清拭や入浴介助、洗髪、口腔ケア、食事や排泄の介助など、日常生活を送る上で必要な援助を行います。
利用者の残存能力を最大限に活かし、自立を促す視点を持ちながら、安全で快適な療養生活を送れるように環境を整えることも大切な役割です。
例えば、床ずれ(褥瘡)ができやすい方には、予防のための体位交換やスキンケアを計画的に実施し、できてしまった場合には医師の指示のもとで処置を行います。
日常生活援助
| 援助の種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 清潔保持 | 入浴介助、清拭、洗髪、口腔ケア | 感染予防、爽快感の維持、血行促進 |
| 食事・排泄 | 食事介助、水分補給、排泄の援助、摘便 | 栄養状態の維持、脱水予防、尊厳の保持 |
| 環境整備 | ベッド周りの整理、療養環境の調整 | 安全確保、快適性の向上、事故防止 |
医師の指示に基づく医療処置
主治医が発行する訪問看護指示書に基づき、専門的な医療処置を自宅で実施するので、通院が困難な方でも必要な医療を継続できます。
含まれるものは、点滴や中心静脈栄養の管理、インスリン注射や血糖測定、気管カニューレや胃ろうなどのカテーテル類の管理、床ずれや創傷の処置、在宅酸素療法の管理などです。
医療機器の操作や管理方法について、利用者や家族に指導することも行います。
在宅でのリハビリテーション
病気やけが、加齢によって低下した心身機能の回復・維持を目的として、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを実施します。
関節の動きを良くする訓練や筋力トレーニング、起き上がりや歩行などの基本動作訓練、食事や着替えといった日常生活動作の訓練などを、利用者の自宅という実際の生活の場で行うことで、より実践的な能力の向上を目指します。
リハビリテーションの主な内容
- 関節可動域訓練、筋力増強訓練
- 基本動作訓練(寝返り、起き上がり、立ち上がり)
- 歩行訓練、福祉用具の選定相談
- 日常生活動作訓練(食事、更衣、トイレ動作)
- 嚥下(飲み込み)訓練、言語訓練
家族への支援と相談対応
在宅療養は、ご本人だけでなく、介護を担うご家族にとっても身体的・精神的に大きな負担となることがあります。
訪問看護師は、ご家族の介護に関する悩みや不安に耳を傾け、適切な介護方法を具体的にアドバイスしたり、精神的なサポートを行ったりします。
また、利用できる他の公的サービスや地域のサポート体制について情報提供を行い、家族が孤立しないよう、社会資源とつなぐことも大切な役割です。
生活保護で訪問看護を利用するための条件
生活保護を受けている方が訪問看護を利用するには、いくつかの公的な条件を満たす必要があり、条件は、税金を財源とする制度を適切に運用するために定められています。
医師による訪問看護指示書の必要性
訪問看護を開始するための絶対的な条件は、主治医が専門的な見地から「訪問看護が必要である」と判断し、その旨を記載した訪問看護指示書を発行することです。指示書がなければ、訪問看護ステーションはサービスを提供できません。
指示書には、利用者の病名、現在の病状、必要とされる観察項目や医療処置、リハビリの内容、訪問回数の目安などが明記され、看護師はこの指示に基づいてケア計画を立案・実行します。
訪問看護指示書の主な記載内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 患者の氏名、生年月日、住所、要介護度など |
| 傷病名 | 訪問看護が必要となった主な傷病名や医学的管理の要点 |
| 指示内容 | 必要な観察、処置、リハビリテーション、薬の指導など |
対象となる疾患や心身の状態
訪問看護の利用は、特定の疾患に限定されるものではありません。
がん、脳血管疾患後遺症、心臓病、呼吸器疾患、糖尿病などの慢性疾患、国が指定する難病、精神疾患など、疾患の種類や重症度を問わず、医師が在宅での継続的な看護が必要と判断すれば対象となります。
また、終末期(ターミナルケア)を自宅で過ごしたいと希望される方、病院から退院した直後で状態が不安定な時期、医療的なケアが常時必要な乳幼児や小児も対象です。
訪問看護ステーションとの契約
主治医から訪問看護指示書が発行される見込みがついたら、次にサービスを提供してくれる訪問看護ステーションを選び、利用契約を結びます。どのステーションを選ぶかは基本的に利用者の自由です。
病院の地域連携室やソーシャルワーカー、担当のケアマネジャー、福祉事務所のケースワーカーに相談し、自宅からの距離や提供しているサービス内容、ステーションの専門性などを考慮して、希望に合う事業所を紹介してもらうと良いでしょう。
契約時には、サービス内容、料金(この場合は公費負担)、緊急時の連絡方法などについて詳しく説明を受け、納得した上で契約書を取り交わします。
ケースワーカーへの事前相談の重要性
生活保護を利用している場合、福祉事務所の担当者であるケースワーカーとの密な連携が非常に重要です。訪問看護の利用を考え始めたら、できるだけ早い段階でケースワーカーにその意向を伝えて相談しましょう。
ケースワーカーは、医療扶助の申請(医療券や調剤券の発行)を円滑に進めるための助言をしたり、地域の訪問看護ステーションに関する情報を提供してくれたりします。
事前の相談なく話を進めてしまうと、後から手続き上の問題が生じたり、公費負担が認められないといったトラブルにつながる可能性もあります。必ず報告・連絡・相談を徹底してください。
ケースワーカーへの相談事項
- 訪問看護の利用を検討していること
- 主治医の意見や現在の詳しい病状
- 利用手続きの具体的な方法や必要書類の確認
- 訪問看護ステーションの選び方に関する助言
訪問看護の利用開始までの基本的な流れ
実際に訪問看護サービスを受け始めるまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。利用者ご本人やご家族が主体となりつつ、主治医やケースワーカー、訪問看護ステーションと連携しながら、一つずつ着実に進めていくことが大切です。
主治医への相談と意思表示
すべての始まりは、かかりつけの主治医への相談です。現在の病状や日常生活で困っていること、ご自身の療養に関する希望を具体的に伝え、自宅で療養を続けるために訪問看護を利用したいという意思を明確に示します。
医師が必要性を認め、同意を得ることが最初の関門です。このとき、どのような点に不安を感じているのか、どんな支援を望むのかを具体的に話すと、医師も状況を理解しやすくなり、その後の指示書作成がスムーズに進みます。
訪問看護指示書の発行依頼
主治医が訪問看護の必要性を認めたら、訪問看護指示書の発行を正式に依頼します。指示書は、利用者が選んだ、あるいはこれから選ぶ訪問看護ステーション宛てに作成されます。
まだ利用するステーションが決まっていない場合は、この段階で病院のソーシャルワーカーや地域連携室に相談して候補を探し始めると良いでしょう。
指示書は法的に定められた文書であり、発行には数日から1週間程度かかる場合があるため、退院の日程などが決まっている場合は特に早めに依頼することが重要です。
ケースワーカーへの報告と情報共有
主治医から訪問看護利用の同意を得て、指示書の発行を依頼したら、速やかに担当のケースワーカーへ報告します。医療扶助の申請手続き(医療券の発行など)を進めてもらうために、この報告は必須です。
どの訪問看護ステーションを利用する予定か、いつ頃から開始したいかといった情報を共有します。
利用開始までのステップ概要
| 段階 | 行うこと | 関係者 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 利用の相談と意思表示 | 本人、家族、主治医 |
| 第2段階 | 訪問看護指示書の発行依頼 | 主治医、訪問看護ステーション |
| 第3段階 | ケースワーカーへの報告と手続き | 本人、ケースワーカー、福祉事務所 |
訪問看護ステーションの選定と面談
利用する訪問看護ステーションが決まったら、ステーションの管理者や担当予定の看護師が利用者の自宅などを訪問し、契約のための面談(初回訪問)を行います。
面談では、利用者の心身の状態や生活環境、療養に関するご意向などを詳しく確認し、それに基づいてケアの計画を作成します。
利用者や家族が安心してサービスを受けられるよう、疑問や不安な点はこの機会にすべて質問し、納得のいくまで説明を求め、解消しておくことが大切です。
訪問看護を利用する上での注意点
訪問看護は在宅療養の大きな支えとなりますが、サービスを円滑に利用するためにはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
医療扶助の範囲を理解する
訪問看護の費用は医療扶助で賄われますが、すべてのサービスが対象となるわけではありません。医療扶助の対象は、あくまで医師が必要と認めた医療的なケアや療養上の世話に限られます。
利用者本人以外のための調理や洗濯、大掃除や庭の手入れ、ペットの世話、金銭や預貯金の管理代行といった、直接的な医療や看護に関わらないサービスは対象外です。
医療扶助の対象外となるサービスの例
| 分類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 直接的な医療・看護でない行為 | 利用者本人以外のための家事、ペットの世話、庭の手入れ |
| 日常生活の範囲を超える行為 | 大掃除、模様替え、家具の移動、金銭や預貯金の管理 |
| その他 | 長時間の話し相手のみを目的とする訪問、趣味活動への付き添い |
サービス内容の変更や中止の手続き
利用者の体調が良くなったり悪くなったりした場合、あるいは入院することになった場合など、サービス内容の変更や一時的な中止が必要になることがあります。
そのような場合は、自己判断せず、必ず訪問看護ステーションと担当のケースワーカーの両方に速やかに連絡してください。
特に、入院したにもかかわらず連絡を怠ると、訪問看護費と入院費が二重に発生してしまい、制度の適正な運用を妨げることになります。
他の介護サービスとの連携
在宅療養では、訪問看護だけでなく、ヘルパーによる生活援助や身体介護(訪問介護)、デイサービス、福祉用具のレンタルなど、他の介護保険サービスを組み合わせて利用することも多くあります。
それぞれのサービスが円滑に連携し、一体的な支援を提供できるよう、訪問看護師に現在利用している他のサービスについて正確に伝えておくことが必要です。
情報共有により、各事業者が利用者の状況を多角的に把握し、重複や漏れのない、より効果的なサポートを提供できます。
精神疾患を持つ方の訪問看護利用について
身体的な疾患だけでなく、精神疾患を持つ方の在宅療養を支えるためにも訪問看護は積極的に活用されます。精神科訪問看護は、利用者が地域社会の中で安定した生活を送り、自分らしい生き方を実現するための重要な役割を担っています。
精神科訪問看護の役割と目的
精神科訪問看護は、精神疾患を持つ方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援することを目的としています。
看護師や作業療法士が定期的に自宅を訪問し、症状の自己管理や服薬のサポート、対人関係の悩みや日常生活での困りごとに関する相談に応じます。
病状の悪化を未然に防ぎ、再入院を回避しながら、その人らしい生活を再構築していく手助けをし、利用者との対話を通じて信頼関係を築き、孤立を防ぐことも大きな目的です。
利用対象となる精神症状
統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、パニック障害、依存症(アルコール、薬物、ギャンブルなど)など、さまざまな精神疾患を持つ方が対象です。
幻覚や妄想などの症状に悩んでいる、気分の浮き沈みが激しく生活リズムが乱れがち、対人関係への不安からひきこもりがちで社会との交流が難しいなど、日常生活に支障をきたしている場合に、精神科の主治医の判断で利用が開始されます。
精神科訪問看護の具体的な支援内容
支援内容は、画一的ではなく、利用者一人ひとりの状態やニーズ、生活背景に合わせて個別に計画されます。薬の飲み忘れや副作用に悩んでいる方には、服薬の意義を一緒に考え、自己管理できるようになるための工夫を提案します。
対人関係に不安を抱えている方には、SST(社会生活技能訓練)の手法を用いてコミュニケーションの練習をしたり、ストレス対処法を一緒に考えたりします。
また、利用者本人だけでなく、ご家族からの相談に応じ、病気への正しい理解を促したり、適切な関わり方について助言したりすることも重要な支援の一つです。
精神科訪問看護の支援内容例
| 支援の分類 | 具体的な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 症状管理 | 症状のセルフモニタリング支援、対処法の相談 | 症状の安定、自己対処能力の向上 |
| 服薬支援 | 服薬の確認、副作用のチェック、服薬意義の確認 | 確実な服薬、副作用の早期発見、治療継続意欲の向上 |
| 生活支援 | 生活リズムの調整、金銭管理の相談、家事遂行の援助 | 安定した日常生活の基盤構築 |
社会復帰に向けたサポート
精神科訪問看護は、病状の管理だけでなく、利用者が再び社会とつながりを持つためのサポートも積極的に実施します。
デイケアや地域活動支援センター、作業所といった日中の活動の場に関する情報を提供したり、利用に際しての不安を軽減するための同行支援を行ったりします。
また、ハローワークへの相談や就労継続支援事業所の利用など、その人の希望や回復段階に応じた社会復帰の道のりを一緒に考え、一歩ずつ進んでいけるよう支えていきます。
よくある質問
ここでは、生活保護を受けている方の訪問看護利用に関して、多く寄せられる質問と回答をまとめました。
- 訪問看護と訪問介護はどう違うのですか
-
訪問看護と訪問介護(ヘルパー)は、どちらも在宅生活を支える重要なサービスですが、役割と担い手が異なります。
訪問看護は看護師などが医師の指示に基づき医療行為や療養上の世話を行うのに対し、訪問介護は介護福祉士やヘルパーが食事や排泄、掃除、買い物などの日常生活の援助を行います。
両方を組み合わせて利用することで、より手厚いサポートを受けることが可能です。
- 訪問看護の利用回数に制限はありますか
-
訪問看護の利用回数や一回あたりの時間は、利用者の病状や主治医の指示によって決まります。
医療保険を使った訪問看護の場合、通常は週に3回までという基本的な制限がありますが、厚生労働大臣が定める特定の疾患(がん末期や神経難病など)の方や、急性増悪期にある方、特別管理加算の対象となる処置を受けている方などは、この制限なく毎日でも利用が可能です。
生活保護を受けている場合もこの基準がそのまま適用されるため、医学的に必要と判断されれば、十分な回数の訪問を自己負担なく受けられます。
- 家族が同居していても利用できますか
-
訪問看護は、家族の同居の有無にかかわらず、ご本人に専門的な看護が必要であると医師が判断した場合に対象となります。
介護を担うご家族の負担を軽減するという目的(レスパイトケア)も訪問看護の重要な役割の一つです。看護師が専門的なケアを行うことで、ご家族は介護の負担から一時的に解放され、心身のリフレッシュを図ることができます。
- 途中で病院が変わった場合の手続きはどうなりますか
-
転院などで主治医が変わった場合、サービスを継続するためには、新しい主治医から改めて訪問看護指示書を発行してもらう必要があります。
訪問看護は、常に主治医の指示に基づいて行われるため、指示を出す医師がいなくなるとサービスを提供できません。
主治医が変わることが決まったら、できるだけ早く訪問看護ステーションとケースワーカーにその旨を伝え、新しい指示書をスムーズに受け取れるように手続きを進めることが重要です。
以上
参考文献
Wende D, Karmann A, Sugawara S. Does the Design of Welfare Programs Stipulate Nursing Home Utilization? A Comparative Analysis of Long-Term Care Systems in Japan and Germany. Review of Economics. 2024 Apr 1;75(1):43-61.
You KS. Welfare Planning and Home Care Nursing on the Home Staying Silver Citizen in Japan. Journal of Home Health Care Nursing. 1995;2:77-88.
Imaiso J. Negative/positive home-based caregiving appraisals by informal carers of the elderly in Japan. Primary Health Care Research & Development. 2015 Mar;16(2):167-78.
Hotta S. Toward maintaining and improving the quality of long-term care: The current state and issues regarding home helpers in Japan under the Long-Term Care Insurance System. Social Science Japan Journal. 2007 Oct 1;10(2):265-79.
Murashima S, Nagata S, Magilvy JK, Fukui S, Kayama M. Home care nursing in Japan: a challenge for providing good care at home. Public health nursing. 2002 Mar;19(2):94-103.
Tamiya N, Noguchi H, Nishi A, Reich MR, Ikegami N, Hashimoto H, Shibuya K, Kawachi I, Campbell JC. Population ageing and wellbeing: lessons from Japan’s long-term care insurance policy. The lancet. 2011 Sep 24;378(9797):1183-92.
Fukui S, Yamamoto-Mitani N, Fujita J. Five types of home-visit nursing agencies in Japan based on characteristics of service delivery: cluster analysis of three nationwide surveys. BMC health services research. 2014 Dec 20;14(1):644.
Mikoshiba M. Universal insurance with in-kind transfers: the welfare effects of long-term care insurance in Japan. RIETI; 2025 Mar 21.
Campbell JC, Ikegami N. Japan’s radical reform of long‐term care. Social Policy & Administration. 2003 Feb;37(1):21-34.
Nakanishi M, Hattori K, Nakashima T, Sawamura K. Health care and personal care needs among residents in nursing homes, group homes, and congregate housing in Japan: why does transition occur, and where can the frail elderly establish a permanent residence?. Journal of the American Medical Directors Association. 2014 Jan 1;15(1):76-e1.