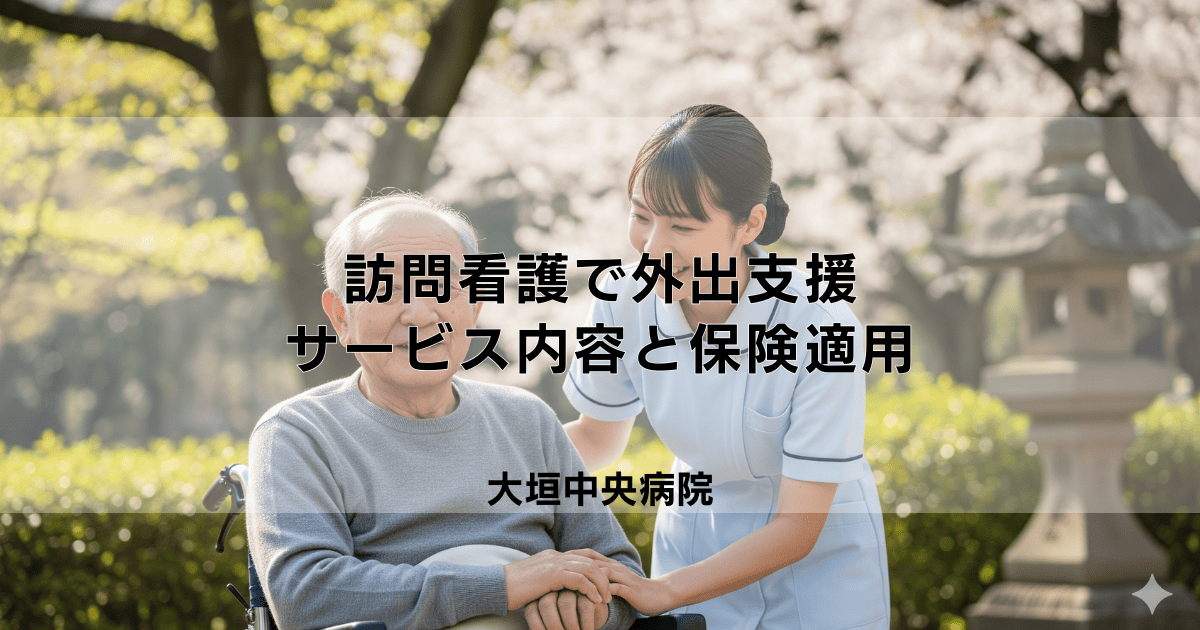訪問看護を利用している方やそのご家族の中には、自宅でのケアだけでなく、外出する際のサポートもお願いできないだろうかと考える方がいらっしゃるかもしれません。
特に、一人での外出に不安があったり、医療的なケアが必要だったりする場合、その悩みは切実です。
この記事では、訪問看護における外出支援のサービス内容、医療保険や介護保険の適用範囲、精神科訪問看護での支援、利用する際の流れや料金について詳しく解説します。
訪問看護における外出支援とは
訪問看護のサービスと聞くと、主に自宅内での医療的ケアや療養生活のサポートを想像する方が多いかもしれませんが、訪問看護の役割はそれだけにとどまりません。
訪問看護の基本的な役割
訪問看護の基本的な役割は、病気や障害を持つ方が住み慣れた地域や自宅で安心して療養生活を送れるように支援することです。看護師や理学療法士などの専門家が利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいてさまざまなケアを提供します。
血圧や体温の測定といった健康状態の確認、点滴や褥瘡の処置などの医療的ケア、入浴や食事の介助といった日常生活の援助、療養生活に関する相談や指導など、多岐にわたります。
利用者本人だけでなく、介護を行うご家族への支援も大切な役割の一つで、心身両面から利用者を支え、安定した在宅療養を可能にすることが訪問看護の基本です。
外出支援の定義と目的
訪問看護における外出支援とは、看護師などが利用者の外出に同行し、安全で安心な外出をサポートするサービスで、支援の目的は、単に移動を手伝うことだけではありません。
利用者の心身の状態や生活背景に応じて、さまざまな目的を持って計画されます。通院や役所での手続き、日用品の買い物といった生活に欠かせない外出を支えることは、在宅生活を維持する上でとても重要です。
また、趣味の活動や友人との交流、散歩など、社会的なつながりを持ち、気分転換を図るための外出も、利用者の精神的な健康や生活の質を高めるために大切な目的となります。
外出を通じて身体機能の維持や向上を目指したり、社会復帰への意欲を引き出したりすることも、外出支援が担う重要な役割です。
外出支援の目的
| 目的の分類 | 具体的な外出先 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 日常生活の維持 | 病院、市役所、銀行、スーパー | 在宅療養の継続、セルフケア能力の維持 |
| 社会参加の促進 | 趣味の会、友人宅、地域のイベント | 孤立感の軽減、QOLの向上 |
| 心身機能の回復 | 公園、リハビリ施設、散歩 | 身体機能の維持・向上、精神的な安定 |
看護師が付き添うことの意義
外出時に看護師が付き添うことには、大きな意義があり、最大の利点は、利用者の安全を確保し、医療的な観点から心身の状態を管理できることです。
外出中は、普段と違う環境や活動によって体調が変化しやすくなるので、看護師は、利用者の顔色や呼吸の状態などを専門的な視点で常に観察し、変化があれば迅速かつ適切に対応できます。
急な体調不良や転倒などのアクシデントが発生した際も、その場で必要な応急処置を行ったり、主治医や関係機関と連携したりすることが可能です。
また、精神的な不安を抱える利用者にとっては、信頼できる看護師がそばにいるだけで、外出への恐怖心が和らぎ、安心して行動できるようになります。
外出支援で受けられるサービス内容
訪問看護の外出支援は、利用者の目的や心身の状態に合わせて、さまざまな形で提供されます。単なる付き添いだけでなく、外出の準備から帰宅後のケアまで、一連の流れをトータルでサポートします。
日常生活に必要な外出のサポート
在宅で療養生活を送る上で、日常生活に必要な外出は避けて通れません。訪問看護の外出支援は、こうした必要不可欠な外出を安全に行えるようにサポートし、最も代表的なものは、病院への付き添いです。
診察の予約確認、移動手段の手配、病院内での移動介助、そして医師からの説明を一緒に聞いて内容を整理し、本人や家族に分かりやすく伝える役割も担います。
また、役所での公的な手続きや銀行での金銭管理、日用品や食料品の買い物など、生活を維持するために重要な外出にも同行します。
社会参加を促すための外出同行
病気や障害によって自宅に閉じこもりがちになると、社会的な孤立感を深め、心身の機能低下を招くことがあり、外出支援は、利用者が再び社会とのつながりを取り戻すための大切なきっかけとなります。
趣味のサークル活動や地域のイベント、友人との会食、美術館や映画館への外出など、利用者の楽しみや生きがいにつながる活動への同行を支援します。
看護師は、利用者の興味や関心を引き出しながら、無理のない範囲で楽しめる外出プランを一緒に考え、実行をサポートします。
- 地域のサロンや集いの場
- 趣味の教室(絵画、園芸など)
- 友人や知人との会食
- 冠婚葬祭への参列
- 思い出の場所への訪問
精神的な安定を目指す外出
特に精神疾患を抱える方にとって、外出は大きな不安や緊張を伴うことがあり、精神科の訪問看護における外出支援では、利用者の精神的な安定を第一に考えたサポートを行います。
人混みを避けて静かな公園を散歩する、目的を決めずにバスや電車に乗ってみるなど、ごく短い時間や簡単な行動から始め、少しずつ外出に慣れていく練習をし、暴露療法の一環としても行われることがあります。
看護師は、利用者の不安な気持ちに寄り添い、大丈夫だという安心感を与えながら、パニックや強い不安が生じた際の対処法を一緒に確認し、実践します。最終的には、一人でも安心して外出できるようになることが目標です。
外出先での医療的ケア
医療的なケアを必要とする利用者にとって、外出は大きな壁となることがありますが、訪問看護の外出支援では、外出先でも必要な医療的ケアを提供できるため、安心して活動範囲を広げることが可能です。
インスリン注射や血糖測定、たんの吸引、経管栄養の管理、ストーマケアなど、自宅で行っている医療処置を、外出先のトイレや休憩スペースを利用して適切に実施します。
また、痛みに対する薬剤の管理や、急な症状の変化に対する観察と対応も行います。
外出先で提供可能な医療的ケアの例
| ケアの種類 | 具体的な内容 | 実施場所の例 |
|---|---|---|
| 注射・血糖測定 | インスリン自己注射の補助、血糖値の測定 | 商業施設の多目的トイレ、休憩室 |
| 吸引・吸入 | 口腔・鼻腔内のたんの吸引、ネブライザーでの吸入 | 車内、個室 |
| 栄養管理 | 経管栄養(胃ろう・腸ろう)の注入 | 公園のベンチ、施設の休憩室 |
精神科訪問看護に特化した外出支援
精神疾患を持つ方の在宅療養を支える精神科訪問看護において、外出支援は治療的にも非常に重要な意味を持ちます。
自宅での対話や服薬管理だけでなく、地域社会での生活に再び適応していくための具体的な援助として、外出支援が積極的に活用されています。
精神疾患を持つ方の外出における課題
精神疾患を持つ方は、外出時に特有の困難や課題に直面することが少なくありません。
うつ病や不安障害の方は、外出すること自体に強いエネルギーを要し、予期せぬ不安発作(パニック発作)に襲われることがあります。
統合失調症の方は、幻覚や妄想などの症状によって、周囲の環境が脅威に感じられ、混乱してしまうこともあり、また、対人関係に敏感になり、他者の視線や言動が気になって外出が怖くなることもあります。
看護師は、こうした一人ひとりの課題を深く理解し、特性に合わせた支援を考えます。
精神疾患を持つ方が外出時に感じる不安
| 疾患の例 | 外出時の主な不安や困難 | 看護師による支援の視点 |
|---|---|---|
| 不安障害 | パニック発作、人混みへの恐怖 | 対処法の確認、安心できる環境設定 |
| うつ病 | 意欲の低下、外出への億劫さ | 小さな目標設定、気晴らしの提案 |
| 統合失調症 | 幻覚・妄想の悪化、周囲への過敏さ | 現実検討の補助、刺激の少ない場所の選択 |
不安を和らげ社会復帰を目指す支援
精神科の外出支援の大きな目的は、利用者の不安を和らげ、自信を回復し、段階的に社会復帰を目指すことです。
スモールステップの原則が用いられ、まずは自宅の周りを少し歩くことから始め、慣れてきたら近くのコンビニへ行く、次は電車に乗って一駅先まで行ってみる、というように、本人の状態に合わせて少しずつ目標の難易度を上げていきます。
このような関わりを通じて、利用者は失敗を恐れずに行動できるようになり、外出に対する成功体験を積み重ねていき、小さな成功体験が、自己肯定感を高め、次のステップへ進むための大きな力となります。
対人関係の練習の場としての外出
多くの精神疾患において、対人関係の構築は重要な課題となります。外出支援は、現実の社会生活の場面で、対人関係のスキルを練習する絶好の機会を提供します。
買い物でのやり取り、公共交通機関でのマナー、カフェでの注文など、日常生活には人との関わりがあり、看護師は、こうした場面で利用者がどのように振る舞えばよいかを一緒に考え、事前に練習(ロールプレイング)をすることもあります。
実際の場面ではすぐそばで見守り、必要に応じて助言をしたり、後で振り返りを行ったりし、就労や復学など、より大きな社会参加を目指す上での大切な土台作りとなります。
- 店員への質問や支払い
- バスの運転手への挨拶
- 図書館での本の貸し借り
- 役所での手続きの相談
- 美容院や理髪店の予約
症状の観察と早期対応
外出という非日常的な環境は、精神症状に変化をもたらすことがあります。看護師は、外出中に利用者の言動や表情、感情の起伏などを注意深く観察し、症状の変化を早期に察知する役割を担います。
不安が強まっているサインや、幻聴・妄想が出現している兆候などを捉えすぐに対応し、一度休憩して落ち着ける場所に移動したり、話題を変えて気分転換を図ったり、事前に処方されている頓服薬の服用を促したりします。
症状が悪化する前に介入することで、利用者はパニックに陥ることなく、安心して外出を続けることが可能です。また、外出時の様子は主治医への重要な情報提供となり、今後の治療方針を立てる上でも役立ちます。
訪問看護の外出支援を利用できる対象者
訪問看護の外出支援は、誰もが自由に利用できるわけではありません。基本的には、医師が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書を発行した方が対象です。
医療保険で利用できる方
医療保険を使って訪問看護を利用している方は、年齢にかかわらず外出支援の対象となり得ます。
厚生労働省が定める特定の疾病(がん末期や難病など)の方や、精神科訪問看護の対象者、あるいは要介護認定を受けていないが病気や障害のために在宅療養が必要な方などが該当します。
医療保険での外出支援は、主に治療や心身の機能回復を目的とした場合に認められることが多いです。
リハビリテーションを目的とした公園での歩行訓練や、精神科の治療の一環としての社会生活技能訓練(SST)のための外出などがこれにあたります。
利用にあたっては、訪問看護計画書に外出支援の必要性や目的、具体的な内容が明記されていることが重要です。
介護保険で利用できる方
介護保険制度における要支援・要介護認定を受けている方も、訪問看護の一環として外出支援を利用できます。
介護保険の対象者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方、または40歳から64歳までで特定の疾病(16特定疾病)により要支援・要介護認定を受けた方です。
介護保険での訪問看護は、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて提供されるため、外出支援を利用したい場合は、まずケアマネジャーに相談し、必要性をケアプランに位置づけてもらう必要があります。
介護保険における外出支援は、日常生活の維持(通院や買い物など)や、社会参加を通じた自立支援(デイサービスへの参加準備など)を目的とする場合に利用されることが一般的です。
医療保険と介護保険の主な違い
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 年齢制限なし、特定の疾病や精神疾患など | 要支援・要介護認定を受けた方 |
| 根拠となる計画 | 訪問看護計画書(主治医の指示に基づく) | ケアプラン(ケアマネジャーが作成) |
| 主な目的 | 治療の補助、心身の機能回復 | 日常生活の支援、自立支援 |
年齢や疾患による条件
訪問看護の利用対象は、年齢や疾患によって細かく定められています。
小児(乳幼児・学齢児)であっても、医療的ケアが必要な場合や発達に支援が必要な場合には、医療保険による訪問看護の対象となり、保育園や学校生活に慣れるための外出支援などが行われることがあります。
成人の場合、介護保険の対象となるか、医療保険の対象となるかが分かれますが、精神疾患を持つ方への精神科訪問看護は医療保険の適用となり、年齢にかかわらず利用が可能です。
外出支援が利用できるかどうか、またどの保険が適用されるかについては、個々の利用者の病状や身体状況、生活環境によって異なるため、まずは主治医やかかりつけの医療機関、または訪問看護ステーションに相談することが大切です。
医師による訪問看護指示書の重要性
どのような場合であっても、訪問看護サービス(外出支援を含む)を開始するためには、主治医による訪問看護指示書が必ず必要です。
訪問看護指示書とは、医師が利用者の病状や治療方針に基づき、訪問看護師に対して必要なケアの内容を具体的に指示する書類で、指示書がなければ、訪問看護ステーションはサービスを提供することができず、保険請求も行えません。
外出支援を希望する場合、目的(リハビリ、精神療法、社会参加など)が利用者の治療や療養生活の向上に資するものであると医師が判断し、指示書にその旨を記載してもらう必要があります。
外出支援における保険適用の範囲とルール
訪問看護の外出支援は便利なサービスですが、保険が適用される範囲には一定のルールがあります。
医療保険が適用される外出の条件
医療保険が適用される外出支援は、外出が治療の一環として明確に位置づけられている必要があります。単なる気晴らしや私的な楽しみのための外出は、原則として保険適用の対象外です。
保険適用の対象となるケース
- リハビリテーションを目的とした屋外での歩行訓練
- 精神科の治療プログラムとして行われる集団活動への参加
- 社会復帰に向けた、公共交通機関の利用練習
- 他の医療機関への受診(主治医の指示に基づく場合)
介護保険が適用される外出の条件
介護保険における外出支援は、利用者の自立支援と日常生活の維持に資するものであることが条件となり、ケアプランに位置づけられた上で、以下のような目的の外出が対象となることが一般的です。
- 定期的な通院の付き添い
- 生活必需品の買い物同行
- 役所や銀行での手続きの補助
- 地域包括支援センターやデイサービスの利用相談・見学
介護保険では、利用者の身体介護(移動や移乗の介助など)と関連付けてサービスが提供されますが、趣味や娯楽、旅行といった社会活動への参加は、原則として介護保険の対象外です。
保険適用外となるケースと自費サービス
保険適用のルールから外れる外出については、全額自己負担の自費サービスとして依頼できる場合があります。保険適用外となる代表的なケースは以下の通りです。
保険適用外となる外出の例
| 外出の種類 | 主な理由 | 備考 |
|---|---|---|
| 趣味・娯楽 | 映画鑑賞、観劇、コンサートなど | 直接的な治療や日常生活の維持に該当しない |
| 旅行・遠出 | 観光、里帰りなど長時間の拘束を伴うもの | 訪問看護のサービスの範囲を超える |
| 冠婚葬祭 | 結婚式、葬儀など個人的な行事への参加 | 社会通念上、公的保険の対象となりにくい |
自費サービスを利用する際は、料金体系やサービス内容、万が一の事故の際の補償範囲などを事前にしっかりと確認しましょう。
公費負担医療制度の活用
特定の疾患や状態にある方は、公費負担医療制度を利用することで、医療費の自己負担が軽減される場合があります。
自立支援医療(精神通院医療)の対象となる方は、精神科訪問看護の自己負担額に上限が設けられ、この制度は、外出支援が精神科治療の一環として行われる場合にも適用されます。
また、難病医療費助成制度や小児慢性特定疾病医療費助成制度なども、訪問看護の利用料に適用されることがあります。
ご自身が利用できる公費負担医療制度がないか、市町村の担当窓口や病院のソーシャルワーカー、訪問看護ステーションに確認してみましょう。
外出支援を利用する際の流れと料金
実際に訪問看護の外出支援を利用したいと考えた場合、どのような手順で申し込み、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、相談からサービス開始までの一般的な流れと、料金の目安について解説します。
相談からサービス開始までの手順
外出支援の利用を開始するまでの流れは、利用する保険の種類によって若干異なりますが、おおむね以下のようになります。
- 相談
- 主治医の同意と指示書の依頼
- 訪問看護ステーションとの契約・面談
- 計画書の作成
- サービス開始
まずは、主治医、ケアマネジャー(介護保険利用者の場合)、または直接訪問看護ステーションに「外出支援を利用したい」と相談すると、関係者が連携し利用者の状況や希望を確認します。
次に、外出支援の必要性を主治医が判断し、訪問看護指示書を発行してもらいます。
その後、訪問看護ステーションの担当者(管理者や看護師)が利用者の自宅を訪問して面談を行い、具体的な希望や心身の状態、注意事項などを詳しくヒアリングし、サービス利用の契約を結びます。
この情報をもとに、看護師が外出支援を含む訪問看護計画書(またはケアマネジャーがケアプラン)を作成し、利用者の同意を得た上で、いよいよサービスの開始です。
ケアプランへの位置づけ
介護保険を利用して外出支援を行う場合、サービスがケアプランに明確に位置づけられていることが不可欠です。ケアプランとは、利用者がどのような介護サービスを、どのくらいの頻度で、どの事業者から受けるのかを定めた総合的な計画書です。
担当のケアマネジャーは、利用者や家族の希望を聞きながら、専門的な視点で必要なサービスを組み合わせ、ケアプランの原案を作成します。
外出支援を希望する場合、その目的(例「月2回の通院介助」「近所のスーパーでの買い物同行による自立支援」)や具体的な内容、頻度などをケアマネジャーに伝え、プランに盛り込んでもらう必要があります。
利用料金の目安(保険適用と自費)
外出支援の料金は、保険が適用されるか、自費サービスとなるかで大きく異なります。
料金の目安
| サービス種別 | 料金の目安(1時間あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 保険適用(医療・介護) | 数百円〜千数百円程度 | 自己負担割合(1〜3割)による。滞在時間で計算。 |
| 保険適用外(自費) | 5,000円〜10,000円程度 | 事業者により料金設定が大きく異なる。 |
保険適用の場合は、訪問看護の滞在時間(20分未満、30分未満、30分以上1時間未満など)に応じて国が定めた単位数(料金)があり、そのうちの1割から3割が自己負担額です。
一方、保険適用外の自費サービスの場合は、各訪問看護ステーションが独自に料金を設定しています。一般的に、1時間あたりの料金設定が多く、保険サービスに比べて高額です。
交通費など別途発生する費用
訪問看護の外出支援を利用する際には、サービスの基本料金に加えて、別途費用が発生することがあり、最も一般的なものは、外出に伴う交通費です。
公共交通機関を利用した場合の運賃や、タクシー代など、利用者の移動にかかる費用は当然自己負担となります。
また、看護師の移動にかかる交通費についても利用者の負担で、利用者の自宅から目的地までの看護師のバス代や電車代などがこれにあたります。
その他、外出先での入場料(美術館など)や飲食代なども、利用者本人分と看護師分の両方が利用者負担となる場合があります。
別途費用については、事業者によって規定が異なるので、契約時にどのような費用が自己負担となるのか、精算方法なども含めて、書面でしっかりと確認しておくことがトラブルを防ぐ上で大切です。
よくある質問
ここでは、訪問看護の外出支援について、利用者やご家族からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- どのくらいの頻度で利用できますか
-
外出支援を利用できる頻度は、利用する保険の種類や心身の状態、ケアプランや訪問看護計画書の内容によって決まります。医療保険の場合、週に3回までといった訪問回数の上限があり、その範囲内で外出支援が計画されます。
介護保険の場合は、要介護度によって定められる支給限度額の範囲内であれば、ケアマネジャーが必要性を判断し、週に1回の通院、月に2回の買い物など、ケアプランに沿った頻度で利用することになります。
自費サービスであれば、事業者との契約次第で、より柔軟な頻度での利用が可能です。
- 好きな場所にどこでも行けますか
-
保険適用の範囲内では、残念ながら好きな場所にどこでも行けるわけではありません。保険が適用されるのは、あくまで治療や日常生活の維持、自立支援に資すると判断される外出に限られます。
趣味の活動や旅行など、娯楽目的の外出は原則として保険の対象外です。ただし、保険適用外の自費サービスを利用すれば、行き先の自由度は格段に高まります。
自費サービスでは、事業者が安全を確保できると判断する範囲であれば、利用者の希望に応じてさまざまな場所への外出を計画することが可能です。
- 家族も一緒に外出できますか
-
多くの場合、ご家族も一緒に外出することが可能です。ご家族が同行することで、利用者本人の安心感が増したり、外出先での介護方法や介助のコツを看護師から直接学んだりできるというメリットもあります。
通院に家族が同行し、医師からの説明を一緒に聞くことは、病状の理解を深め、今後の家庭での療養方針を共有する上で非常に有益です。
ただし、サービスの提供対象はあくまで利用者本人であるため、看護師は利用者のケアに専念します。ご家族の分の交通費や入場料などは、ご家族自身の負担です。
- 突然の依頼にも対応してもらえますか
-
訪問看護は、あらかじめ作成された計画に基づいてサービスを提供する仕組みであるため、原則として突然の依頼に即時対応することは困難です。
看護師は他の利用者の訪問スケジュールも組んでいるため、急なご要望にお応えできないことがほとんどです。外出支援のように、準備や移動に時間がかかるサービスは、事前の計画が重要になります。
ただし、緊急性のある受診など、やむを得ない事情がある場合は、まず訪問看護ステーションに電話で相談してみてください。
以上
参考文献
Fukui S, Yamamoto-Mitani N, Fujita J. Five types of home-visit nursing agencies in Japan based on characteristics of service delivery: cluster analysis of three nationwide surveys. BMC health services research. 2014 Dec 20;14(1):644.
Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.
Yamaoka Y, Ochi M, Fukui M, Isumi A, Doi S, Fujiwara T, Nawa N. Home visitors’ needs and perceptions of the benefits of a home visiting program for childcare support in Japan: A qualitative study of home visitors. Child Abuse & Neglect. 2024 Jul 1;153:106853.
Campbell JC, Ikegami N. Long-Term Care Insurance Comes To Japan: A major departure for Japan, this new program aims to be a comprehensive solution to the problem of caring for frail older people. Health affairs. 2000 May;19(3):26-39.
Ikegami N. Public long-term care insurance in Japan. Jama. 1997 Oct 22;278(16):1310-4.
Campbell JC, Ikegami N. Japan’s radical reform of long‐term care. Social Policy & Administration. 2003 Feb;37(1):21-34.
Yong V, Saito Y. National long-term care insurance policy in Japan a decade after implementation: some lessons for aging countries. Ageing International. 2012 Sep;37(3):271-84.
Innes A, Morgan D, Kostineuk J. Dementia care in rural and remote settings: a systematic review of informal/family caregiving. Maturitas. 2011 Jan 1;68(1):34-46.
Butler J, Smith T. Community care and rehabilitation after stroke in Japan. British Journal of Occupational Therapy. 2002 Aug;65(8):363-70.
Setoya N, Aoki Y, Fukushima K, Sakaki M, Kido Y, Takasuna H, Kusachi H, Hirahara Y, Katayama S, Tachimori H, Funakoshi A. Future perspective of psychiatric home-visit nursing provided by nursing stations in Japan. Global health & medicine. 2023 Jun 30;5(3):128-35.