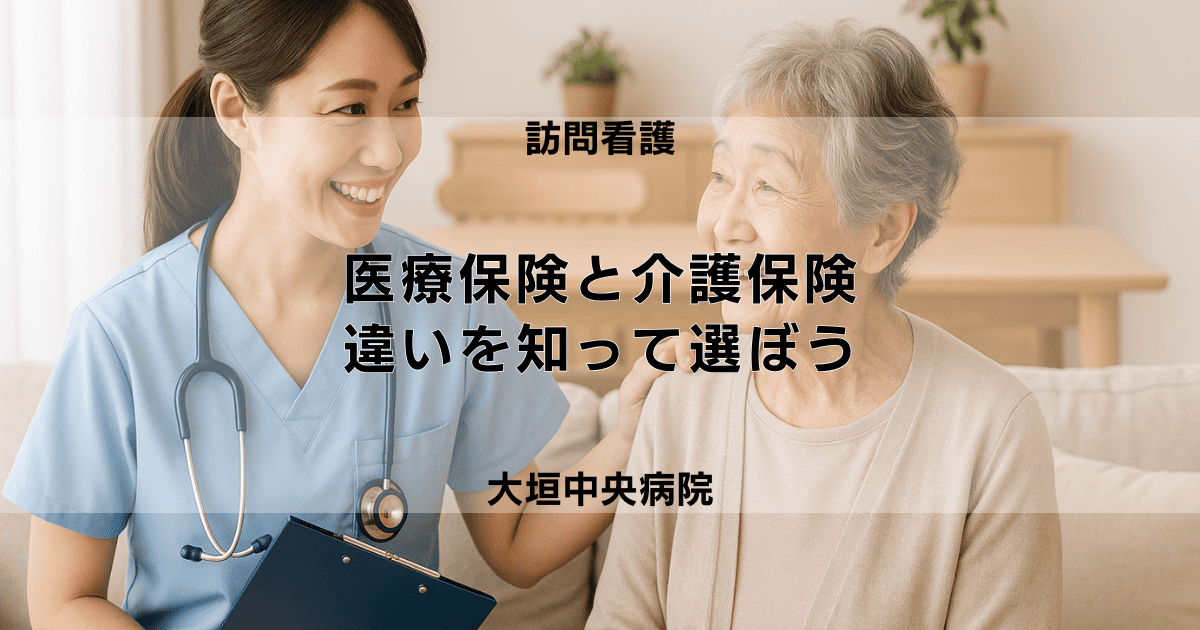ご自宅で療養生活を送るうえで、専門家による看護を受けられる訪問看護は、ご本人やご家族にとって心強い支えとなります。
しかし、訪問看護を利用する際には医療保険と介護保険の二つの制度があり、どちらが適用されるのか、どのような違いがあるのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、訪問看護における医療保険と介護保険の基本的な違いから、それぞれの対象者、サービス内容、費用負担について詳しく解説します。
そもそも訪問看護とは?自宅で受けられる看護ケア
訪問看護は、病気や障害を抱えながらご自宅で生活する方々のもとへ、看護師などの医療専門職が訪問し、必要なケアを提供するサービスです。
住み慣れた環境で安心して療養生活を送れるように、医療的な処置から日常生活の支援、さらには精神的なサポートまで、幅広く支えることを目的としています。
訪問看護の目的と役割
訪問看護の最大の目的は、利用者が地域社会の中でその人らしい生活を継続できるように、医療と生活の両面から支援することです。病状の悪化を予防し、健康状態を維持・改善するための専門的な観察や判断を行います。
血圧や体温、脈拍などの測定はもちろん、症状の変化を細やかに捉え、異常の早期発見に努め、また、主治医の指示に基づいた点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置といった医療処置を行い、療養上の不安や悩みの相談にも応じます。
ご家族が抱える介護の負担を軽減するための介護指導や精神的な支援も、訪問看護の大事な役割の一つです。
どんな専門職が訪問するのか
訪問看護では、さまざまな資格を持つ専門職がチームとして連携し、ケアを提供します。主となるのは看護師や准看護師ですが、利用者の状態に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーションの専門家も訪問します。
それぞれの専門性を活かし、利用者の状態に合わせた多角的な支援を行うことで、より質の高い在宅療養を実現します。
訪問する専門職とその主な役割
| 専門職 | 主な役割 |
|---|---|
| 看護師・准看護師 | 健康状態の観察、医療処置、服薬管理、療養上の世話、家族支援、関係機関との連携 |
| 理学療法士(PT) | 寝返り、起き上がり、歩行といった基本動作能力の回復・維持を目的としたリハビリ。福祉用具の選定相談も行います。 |
| 作業療法士(OT) | 食事、入浴、着替え、家事といった応用的動作能力や、趣味活動を通じた精神面のケアなど、社会適応能力の回復を目指すリハビリ。 |
| 言語聴覚士(ST) | 話す、聞くといった意思疎通の機能や、安全に飲み込む(嚥下)機能の回復・維持を目的としたリハビリ。食事形態の相談も受けます。 |
訪問看護で受けられる具体的なサービス内容
訪問看護で提供されるサービスは非常に多岐にわたります。主治医が作成する訪問看護指示書に基づいて、個々の利用者の心身の状態や生活環境、ニーズに応じたケア計画を立て、実行します。
単なる医療的なケアだけでなく、利用者の生活の質(QOL)を高めるための支援も含まれます。
- 病状の観察と健康管理(血圧・体温・呼吸・脈拍のチェック)
- 身体の清潔保持(清拭・洗髪・入浴介助)
- 食事や排泄の介助・指導
- 医療機器の管理(在宅酸素、人工呼吸器、経管栄養、ストーマケアなど)
- 褥瘡(床ずれ)の予防・処置、創傷処置
- 服薬管理・指導
- 終末期ケア(ターミナルケア)、緩和ケア
- 療養生活や介護方法に関する相談・助言
訪問看護で利用する医療保険と介護保険の基本
訪問看護を利用する際、医療保険と介護保険のどちらを使うかは、利用者の年齢や病状によって厳密に定められています。
この二つの保険制度は、成り立ちや目的が根本的に異なるため、提供されるサービスや利用のルールにも明確な違いがあり、正しい知識を持つことが、適切なサービス利用への第一歩です。
制度の目的が根本的に異なる
医療保険は、国民皆保険制度のもと、病気やけがの治療を目的とする公的な保険制度で、病気の早期発見と治療を通じて、国民の健康を保持することが理念です。
一方、介護保険は、2000年に施行された比較的新しい制度で、加齢に伴い要介護状態となった高齢者が、尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を送れるように、社会全体で支えることを目的としています。
目的の違いが、訪問看護におけるサービス内容や利用条件の違いに直接的に反映されます。
医療保険と介護保険の基本理念
| 保険制度 | 目的 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 医療保険 | 国民の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行う | 健康保険法など |
| 介護保険 | 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者の自立支援と介護負担の軽減 | 介護保険法 |
対象となる年齢層の違い
原則として、65歳以上の方は介護保険の対象者(第1号被保険者)となります。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、がん(末期)や関節リウマチなど、加齢との関係が深いとされる16種類の特定疾病により要介護認定を受けた場合に介護保険の対象者です。
それ以外、例えば65歳未満で特定疾病に該当しない方や、赤ちゃんから高齢者まで年齢にかかわらず、医師が訪問看護の必要性を認めた特定の状態にある方は医療保険を利用します。
どちらの保険が優先されるか
訪問看護を利用する際、もし利用者が医療保険と介護保険の両方の適用対象となる場合、原則として介護保険が優先され、これを介護保険優先の原則と呼びます。
65歳以上で要介護認定を受けている方が訪問看護を利用する場合は、基本的に介護保険でのサービス提供となります。
ただし、厚生労働大臣が定める特定の疾病などに該当する場合や、病状が急激に悪化した際には、医療保険が適用される例外規定が設けられており、医療ニーズの高さに応じて柔軟な対応が可能です。
医療保険で訪問看護を利用するケース
医療保険による訪問看護は、年齢に関わらず、病気やけがのために医師が専門的な看護の必要性を認めた場合に利用できます。急性期の疾患の治療後や、医療的な管理が常に必要な難病、精神疾患を持つ方が主な対象です。
医療保険が適用される主な対象者
医療保険の訪問看護は、介護保険の対象とならない方が利用の中心で、40歳未満の方、40歳から64歳で16特定疾病に該当せず要介護認定を受けていない方などが該当します。
また、要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等の状態にある方や、精神科訪問看護が必要な方は、介護保険ではなく医療保険の適用です。
医療保険の対象となる厚生労働大臣が定める疾病等
| 分類 | 主な疾病・状態の例 |
|---|---|
| 難病など | 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、パーキンソン病関連疾患、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など20種類 |
| 特別な状態 | 在宅人工呼吸器を使用している状態、気管カニューレを使用している状態、真皮を越える褥瘡の状態など |
| 急性増悪期 | 退院直後や病状の急な悪化により、頻回な訪問看護が必要と主治医が判断した場合(特別訪問看護指示書の発行) |
医師が発行する訪問看護指示書が重要
医療保険で訪問看護を開始するには、主治医が発行する訪問看護指示書が必ず必要です。
指示書は、訪問看護ステーションへの公的な依頼書であり、利用者の病名、状態、必要な看護の内容、訪問頻度などが詳細に記載されていて、訪問看護ステーションはこの指示に基づいてケアを提供します。
指示書の有効期間は最長6ヶ月で、継続して利用する場合には再度発行してもらう必要があります。病状が急変した際には、主治医の判断で特別訪問看護指示書が交付され、一時的に集中的な訪問看護が可能です。
利用できる日数や時間のルール
医療保険による訪問看護は原則として週3日まで利用でき、1回の訪問時間は30分から90分程度が一般的です。
ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、主治医から特別訪問看護指示書(有効期間は原則14日間)が発行された場合には、週4日以上の訪問や1日に複数回の訪問も可能です。
この制度により、病状が不安定な時期や退院直後にも、安心して在宅療養を継続するための集中的なケアを受けられます。
自己負担額の計算方法
自己負担額は、利用者が加入している医療保険の負担割合(通常1割〜3割)に応じて決まり、70歳未満の方であれば原則3割負担、70歳から74歳の方は原則2割負担、75歳以上の方は原則1割負担です(ただし現役並み所得者は3割)。
また、医療費には高額療養費制度が適用されるため、1ヶ月の医療費の自己負担額が所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超過分が払い戻されます。
年齢別の自己負担割合(原則)
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上 | 1割(現役並み所得者は3割) |
| 70歳~74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
| 70歳未満 | 3割 |
介護保険で訪問看護を利用するケース
介護保険による訪問看護は、高齢者の在宅療養を支える中心的なサービスの一つで、要介護認定を受けた方が、ケアプランに基づいて利用します。
病気の治療そのものよりも、心身機能の維持・回復を図り、できる限り自立した日常生活を送れるように支援するという、生活の視点に立ったケアが特徴です。
介護保険の対象者と要介護認定
介護保険で訪問看護を利用できるのは、市区町村から要支援・要介護認定を受けた方です。
65歳以上で日常生活に支援や介護が必要な状態の方(第1号被保険者)、または40歳から64歳で16特定疾病により介護が必要な状態となった方(第2号被保険者)です。
利用するには、まずお住まいの市区町村の窓口に申請し、訪問調査や主治医の意見書などをもとにした審査を経て、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかの認定を受ける必要があります。
- 第1号被保険者: 65歳以上のすべての方
- 第2号被保険者: 40歳から64歳で医療保険に加入している方
ケアプランに基づいたサービス提供
介護保険のサービスは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて提供されるのが大きな特徴です。
ケアプランには利用者の心身の状態や生活環境、本人や家族の希望に応じて、訪問看護を含むさまざまな介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)が、目標達成のために組み込まれます。
訪問看護ステーションは、ケアプランと主治医の訪問看護指示書の両方に基づいてサービスを提供し、定期的にケアマネジャーと情報共有を行います。
利用限度額とサービス内容の調整
介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用の上限(支給限度額)が単位で決められていて、訪問看護もこの限度額の範囲内で利用することになります。
限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となるため注意が必要です。
そのため、ケアマネジャーは、限度額内で必要なサービスが過不足なく受けられるよう、利用者や家族と十分に話し合いながら、サービスの種類や回数を調整します。
要介護度別の支給限度額(目安)
| 要介護度 | 1ヶ月あたりの支給限度額(単位) |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
※1単位の単価は地域やサービスの種類によって10円〜11.4円程度で変動します。上記は2024年時点の一例です。
自己負担額の仕組み
自己負担額は、サービスにかかった費用の原則1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割負担)です。1ヶ月に10,000円分のサービスを利用した場合、自己負担は1,000円(1割負担の場合)となります。
また、介護保険にも高額介護サービス費制度があり、1ヶ月の自己負担額の合計が所得に応じた上限額を超えた場合には、超過分が払い戻され、負担が軽減されます。
一目でわかる医療保険と介護保険の訪問看護の違い
ここまで解説してきた医療保険と介護保険による訪問看護の違いを、重要な項目に絞って比較し、整理します。ご自身の状況がどちらに該当するのか、またどのようなルールでサービスを利用することになるのかを確認する際の参考にしてください。
対象者の違いを比較
最も基本的で重要な違いは対象者です。年齢や病状、要介護認定の有無によって、どちらの保険が適用されるかが明確に分かれます。
保険別の主な対象者
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 赤ちゃんから高齢者まで全年齢。特に介護保険対象外の方、特定の疾病・状態の方(医療ニーズが高い方) | 65歳以上(第1号)または40~64歳で特定疾病のある方(第2号)で、要介護認定を受けた方(生活支援ニーズが高い方) |
サービス内容と訪問時間の比較
どちらの保険を利用するかによって、訪問のルールやリハビリテーションの提供方法が異なります。医療保険は医療的ケア、介護保険は生活支援に重点が置かれています。
サービス提供のルールの比較
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 訪問日数 | 原則週3日まで(厚生労働大臣が定める疾病等や急性増悪期は週4日以上も可) | ケアプランによる(支給限度額の範囲内であれば利用日数の制限はなし) |
| 1回の時間 | 30分~90分程度が一般的 | 20分未満、30分未満、30分~1時間未満、1時間~1時間半の4つの区分から選択 |
| リハビリ | 看護師によるリハビリも可能。理学療法士等の訪問も医師の指示で可能。 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問が中心。ケアプランに基づく必要がある。 |
費用負担と利用限度額の比較
費用に関するルールも大きく異なり、介護保険には支給限度額がある点が重要なポイントです。この限度額を意識したプランニングが求められます。
費用関連のルールの比較
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 自己負担 | かかった医療費の1~3割 | かかったサービス費用の1~3割 |
| 利用限度額 | なし(医療の必要性に基づくため) | あり(要介護度ごとに月々の上限が設定) |
| 高額療養費制度 | 適用あり | 高額介護サービス費制度が適用 |
訪問看護の利用を開始するまでの手順
実際に訪問看護を利用したいと考えたとき、どのような手順で進めればよいのでしょうか。慌てずにサービスを開始できるよう、一般的な流れを解説します。
主治医やケアマネジャーへの相談
まずは、かかりつけの主治医に相談することが最も確実な第一歩です。「自宅での療養生活で困っていること」「専門的な看護を受けたい」といった希望を具体的に伝えましょう。
訪問看護が必要だと判断されれば、訪問看護指示書を発行してもらえます。すでに要介護認定を受けている方は、担当のケアマネジャーに相談するのがスムーズです。
ケアマネジャーが主治医と連携を取り、ケアプランの作成やサービス事業所との調整など、必要な手続きを進めてくれます。
訪問看護ステーションの選択
次に、実際にサービスを提供してもらう訪問看護ステーションを選び、ケアマネジャーや病院の医療ソーシャルワーカーから、地域の事業所をいくつか紹介してもらうのが一般的です。
ステーションによって、24時間対応の可否、リハビリ専門職の在籍状況、特定の疾患(がん、精神疾患など)への対応経験などに特色があります。
それぞれの事業所の説明を聞き、ご自身の希望や状態に合った場所を慎重に比較検討することが大切です。
契約と利用開始
利用する訪問看護ステーションが決まり契約を結んだあと、事業所の管理者や担当看護師が自宅を訪問し、サービス内容や料金体系、緊急時の対応方法などについて詳しく説明します。
初回訪問では、利用者の心身の状態や生活環境の確認も行います。説明内容に十分に納得したうえで契約書を取り交わし、具体的な目標を盛り込んだ訪問看護計画が作成されると、サービスの開始です。
医療保険と介護保険の併用はできるのか
原則として医療保険と介護保険の訪問看護を同時に利用することはできませんが、特定の条件下では両方の制度を組み合わせて利用したり、一時的に切り替えたりすることがあります。
原則は介護保険が優先
繰り返しになりますが、要介護認定を受けている方が訪問看護を利用する場合、基本的には介護保険が優先適用されます。これは、介護保険制度が、高齢者の在宅生活を医療・介護の両面から総合的に支えるという役割を担っているためです。
特定の条件下で医療保険に切り替わる場合
介護保険が優先される方でも、以下のような医療ニーズが特に高い状態になった場合には、医療保険による訪問看護に切り替わります。
切り替えにより、介護保険の支給限度額を気にすることなく、より手厚い医療的ケアを集中的に受けることが可能になります。
- 厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん、ALSなど)に該当すると診断された場合
- 病状が急激に悪化し、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合(気管支炎の増悪、転倒による骨折後など)
- 精神科訪問看護が必要と判断された場合
例えば、介護保険で週2回の訪問看護を受けているパーキンソン病の方が、肺炎を併発して病状が悪化した場合、主治医の判断で特別訪問看護指示書が発行され、指示期間中(14日間)は医療保険で毎日訪問看護を受ける、といった利用ができます。
指示期間が終了すれば、また元の介護保険での利用に戻ります。
併用が必要となる病状
医療保険への切り替えが必要となるのは、在宅での高度な医療的な管理が不可欠な状態にある場合です。
末期がんで痛みのコントロールが必要な場合の頻回な訪問、在宅での中心静脈栄養や人工呼吸器の管理などは、専門的な医療処置を24時間体制で必要とすることが多く、医療保険の適用となります。
このような状態は、介護保険のケアプランの枠組みだけでは対応が難しいことから、医療保険による特別な扱いが定められています。
訪問看護の保険適用に関するよくある質問
最後に、訪問看護の保険適用に関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 40歳から64歳でも医療保険を使えますか
-
40歳から64歳の方で、がんや関節リウマチなどの16特定疾病に該当せず、要介護認定を受けていない場合は、医療保険で訪問看護を利用します。
また、16特定疾病に該当して要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、病状の急性増悪期には、介護保険ではなく医療保険が適用されます。
- 退院直後からすぐに利用したい場合はどうなりますか
-
退院直後は病状が不安定になりやすく、集中的な観察やケアが必要なため、医療保険による手厚い訪問看護が利用できる場合があります。
入院中に病院のソーシャルワーカーや退院調整看護師に、退院後の生活について早めに相談し、計画を立てておくことが大切です。
主治医が必要と判断すれば、退院日からすぐに訪問看護を開始できるよう、特別訪問看護指示書を発行してもらうことが可能です。
- 訪問看護の費用は医療費控除の対象ですか
-
医療保険、介護保険のどちらを利用した場合でも、訪問看護の自己負担額は医療費控除の対象です。
また、主治医の指示書があり、訪問看護と連携して訪問介護(生活援助中心のものを除く)を利用した場合は、その訪問介護の自己負担額も医療費控除の対象に含めることができます。
確定申告の際に必要となるため、領収書は大切に保管しておきましょう。
- ケアマネジャーが決まっていなくても相談できますか
-
まだ要介護認定を受けていない、あるいは申請中の方でも、地域の訪問看護ステーションに直接相談することが可能です。ステーションの看護師や相談員が、今後の手続きの流れや利用できる制度についてアドバイスをします。
必要に応じて、介護認定の申請手続きの支援や、地域包括支援センターへの橋渡しも行いますので、まずは気軽に連絡してみることをお勧めします。
以上
参考文献
Konishi T, Inokuchi H, Yasunaga H. Services in public long-term care insurance in Japan. Annals of Clinical Epidemiology. 2024;6(1):1-4.
Ikegami N. Public long-term care insurance in Japan. Jama. 1997 Oct 22;278(16):1310-4.
Matsuda S, Yamamoto M. Long-term care insurance and integrated care for the aged in Japan. International Journal of Integrated Care. 2001 Sep 1;1:e28.
Tsutsui T, Muramatsu N. Care‐needs certification in the long‐term care insurance system of Japan. Journal of the American geriatrics society. 2005 Mar;53(3):522-7.
Tamiya N, Noguchi H, Nishi A, Reich MR, Ikegami N, Hashimoto H, Shibuya K, Kawachi I, Campbell JC. Population ageing and wellbeing: lessons from Japan’s long-term care insurance policy. The lancet. 2011 Sep 24;378(9797):1183-92.
Iwagami M, Tamiya N. The long-term care insurance system in Japan: past, present, and future. JMA journal. 2019 Mar 4;2(1):67-9.
Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.
Yamada M, Arai H. Long-term care system in Japan. Annals of geriatric medicine and research. 2020 Aug 24;24(3):174.
Ohwaki K, Hashimoto H, Sato M, Tamiya N, Yano E. Predictors of continuity in home care for the elderly under public long-term care insurance in Japan. Aging clinical and experimental research. 2009 Aug;21(4):323-8.
Tomita N, Yoshimura K, Ikegami N. Impact of home and community-based services on hospitalisation and institutionalisation among individuals eligible for long-term care insurance in Japan. BMC Health Services Research. 2010 Dec 22;10(1):345.