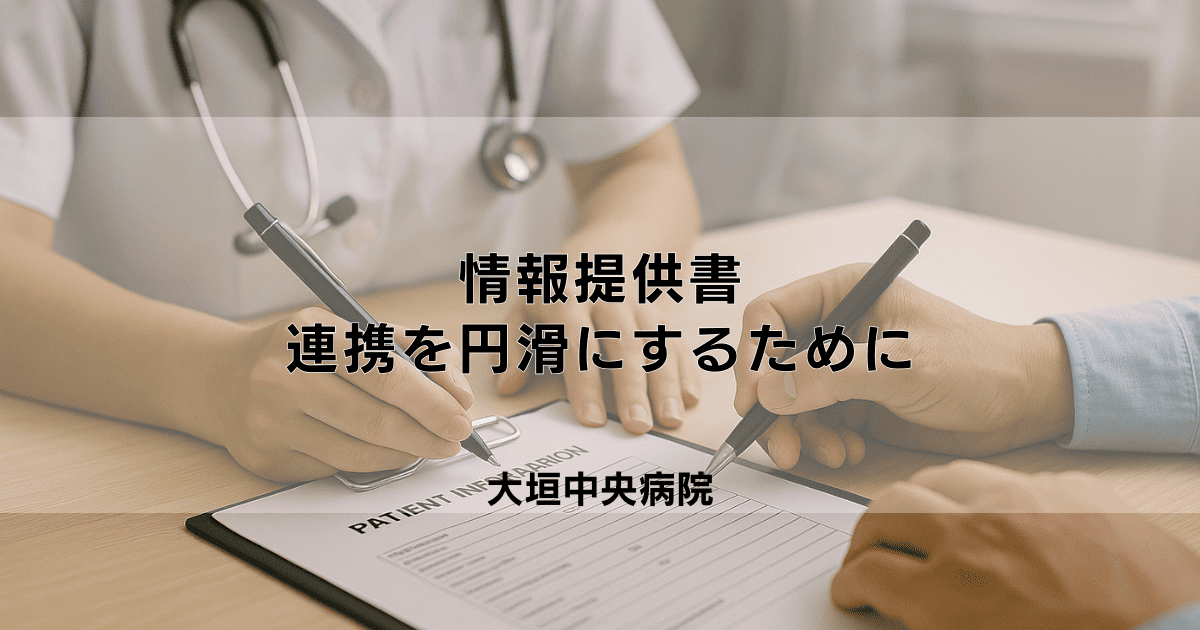訪問看護の情報提供書とは、利用者が安心して質の高い在宅療養を送れるように、関わる専門職同士が情報を共有するための重要な書類です。
病院の医師から訪問看護ステーションへ、あるいは訪問看護ステーションからケアマネジャーへといったように、様々な場面で作成されます。
書類があることで、利用者の病状や生活状況、意向などを正確に引き継ぎ、切れ目のないケアを提供できます。
この記事では、訪問看護の情報提供書がどのようなもので、なぜ重要なのか、そして関連する療養費の仕組みまで、訪問看護の利用を考える方が知っておきたいポイントを詳しく解説します。
そもそも訪問看護における情報提供書とは何か
在宅療養は、一人の専門職だけで支えるものではありません。医師、看護師、ケアマネジャー、リハビリ専門職など、多くの人がチームとなって一人の利用者を支え、チームが円滑に機能するために、情報提供書は欠かせない役割を果たします。
在宅療養を支えるチーム内の共通言語
情報提供書は、在宅療養に関わる多職種チームの共通言語であり、羅針盤のようなものです。利用者の病状や治療経過、日常生活の様子、価値観や家族背景といった多岐にわたる情報が一枚の書類に集約されています。
書類を全員が共有することで、それぞれの専門職が同じ認識を持ち、利用者一人ひとりの状況に合わせた、一貫性のあるケアを提供することが可能です。
情報が口頭での伝達だけだと、誤解や伝え漏れが生じるリスクがありますが、書面として残すことで、正確かつ確実に情報を引き継ぐことができます。
なぜ情報提供書が必要なのか
在宅療養の現場では、利用者の状態は日々変化します。また、関わる専門職も、毎日同じ人が訪問するわけではありません。
情報提供書がなければ、担当者が変わるたびに利用者の情報をゼロから聞き取らなければならず、非効率であるばかりか、必要なケアの質を保つことが難しくなります。
特に、病院から退院して在宅療養に移行する際には、入院中の詳細な情報を在宅チームに正確に伝えなければ、安全な療養生活を始めることができません。
情報提供書は、こうした場面で情報の断絶を防ぎ、スムーズな連携を実現するために必要です。
誰が作成し、誰に渡す書類なのか
情報提供書は、その場面に応じて様々な専門職が作成します。病院を退院する際には、病院の医師や看護師が作成し、退院後のケアを引き継ぐ訪問看護ステーションやケアマネジャーに提供します。
また、訪問看護ステーションが日々のケアで得た利用者の情報を、主治医である訪問診療医やケアプランを見直すケアマネジャーに提供することもあります。
情報提供書の主な作成者と提供先
| 主な作成者(情報の送り手) | 主な提供先(情報の受け手) | 目的 |
|---|---|---|
| 病院の医師・看護師 | 訪問看護ステーション、ケアマネジャー | 退院後の在宅療養への円滑な移行 |
| 訪問看護ステーション | 主治医(訪問診療医)、ケアマネジャー | 在宅での状態報告、治療方針の相談、ケアプランの見直し |
| ケアマネジャー | 各サービス事業所 | ケアプランに基づいたサービス提供の依頼 |
訪問看護指示書との違い
情報提供書と混同されやすい書類に、訪問看護指示書がありますが、この二つは、目的が全く異なります。
訪問看護指示書は、主治医が訪問看護ステーションに対して、利用者にどのような医療的ケア(点滴や処置など)を行うべきかを具体的に指示するための、法的に定められた公的な指示書です。
一方、情報提供書は、指示というよりも、より良いケアを提供するために専門職間で自発的に情報を共有・連携するための書類です。
指示書がケアの根拠となる法的書類であるのに対し、情報提供書はチームケアを円滑にするための潤滑油のような役割と考えると分かりやすいでしょう。
情報提供書に記載される内容
情報提供書には利用者の全体像を把握するために、医学的な情報から生活に関する情報まで、幅広い項目が含まれています。
利用者の基本情報
まず基本となるのが、氏名、生年月日、住所、連絡先といった個人情報です。それに加えて、要介護度や利用している公的制度、緊急時の連絡先、キーパーソンとなる家族の名前なども記載します。
情報は、全ての関係者が利用者を正確に特定し、緊急時に迅速に対応するために大事な土台となります。
病状や治療の経過
医学的な情報として、最も重要な部分です。診断名、現在の病状、これまでの治療の経過、服用している薬の内容、アレルギーの有無などが詳しく記載されます。
在宅で管理が必要な医療機器(在宅酸素、カテーテルなど)がある場合は、その種類や設定、管理上の注意点なども詳細に記入し、情報があることで、在宅チームは利用者の医学的なリスクを把握し、安全なケアを計画できます。
記載される主な医療情報
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 診断名・既往歴 | 脳梗塞後遺症、高血圧症、糖尿病など |
| 現在の病状 | 麻痺の程度、血圧の変動、血糖コントロールの状態など |
| 内服薬・使用中の医療機器 | 降圧薬、インスリン注射、在宅酸素濃縮器など |
日常生活の状況(ADL・IADL)
その人がどのような生活を送っているのかを把握するために、日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)に関する情報も記載します。ADLとは、食事、入浴、排泄、着替え、移動といった、日常生活を送る上で基本的な動作のことです。
IADLは、買い物、調理、洗濯、服薬管理、金銭管理といった、より複雑で応用的な動作を指し、どこまで自分でできて、どのような部分に介助が必要なのかを記述することで、必要な支援の内容を明確にします。
家族構成や介護者の状況
在宅療養は、ご家族の協力なしには成り立ちません。同居している家族は誰か、主な介護者は誰か、その方の年齢や健康状態、介護に対する意向や負担感なども重要な情報です。
また、日中は独居になる、近隣に住む親族のサポートがある、といった家庭環境も記載し、情報は、家族を含めた支援体制を考える上で参考になります。
在宅での療養に関する希望や目標
最も大切なのが、利用者本人がこれから始まる在宅療養で、どのように過ごしたいかという希望や目標です。例えば、自宅で最期まで過ごしたい、趣味の散歩を続けたい、家族と食卓を囲みたい、といった具体的な意向を記載します。
ご本人の思いをチーム全員で共有し、実現に向けてサポートしていくことが、利用者中心のケアの基本です。
情報提供書が活用される主な場面
情報提供書は、在宅療養における様々な連携の場面で力を発揮します。どのような時に作成され、活用されるのかを見ていきましょう。
病院から在宅へ移行する時(退院時)
情報提供書が最も重要な役割を果たすのが、病院を退院し、在宅療養へと移行する場面です。入院中の詳細な情報を、退院後のケアを担う訪問看護ステーションやケアマネジャーに正確に引き継ぐ必要があります。
この時に病院が作成する情報提供書は、一般的に診療情報提供書と呼ばれ、退院前カンファレンスなどの場で共有されます。書類があることで、在宅チームは利用者の状態を事前に把握し、退院当日からスムーズな支援を開始できます。
ケアマネジャーがケアプランを作成する時
ケアマネジャーは、利用者や家族の希望、そして心身の状態を評価(アセスメント)して、どのような介護サービスが必要かを盛り込んだケアプランを作成します。
アセスメントの際に、主治医や訪問看護ステーションからの情報提供書は、利用者の医学的な側面や在宅での様子を把握するための非常に重要な資料です。
正確な情報に基づいて、より利用者の実情に合ったケアプランを作成することが可能になります。
複数のサービス事業所が連携する時
在宅療養では、訪問看護だけでなく、訪問介護(ホームヘルパー)やデイサービス、訪問リハビリテーションなど、複数の事業所が同時に関わることが少なくありません。
それぞれの事業所が提供するサービスが、ばらばらにならないように連携するためにも、情報提供書は役立ちます。
訪問看護師が気づいた利用者の小さな変化を情報提供書にまとめ、ケアマネジャーを通じて各事業所に共有することで、チーム全体で一貫した対応をとることが可能です。
多職種連携における情報共有の例
| 情報の送り手 | 情報の受け手 | 共有される情報の内容例 |
|---|---|---|
| 訪問看護師 | 訪問介護員 | 褥瘡(床ずれ)の好発部位と、体位交換で注意してほしい点 |
| リハビリ専門職 | 訪問看護師 | リハビリの進捗状況と、日常で推奨される運動の内容 |
| 訪問歯科医師 | ケアマネジャー | 嚥下機能の評価結果と、食事形態で配慮すべき点 |
利用者の状態が変化し、方針を見直す時
利用者の病状が悪化したり、逆に入院治療を経て状態が改善したりした場合など、ケアの方針を見直す必要が生じた際にも、情報提供書が作成されます。
主治医や訪問看護師が、現状の評価と今後の見通しをまとめて関係者に提供することで、新しい状態に合わせたケアプランの変更や、サービスの調整を円滑に行うことができます。
訪問看護における情報提供と療養費の関係
質の高い連携を促進するため、医療保険や介護保険の制度では、専門職間の情報提供に対して公的な評価である診療報酬や介護報酬が設定されています。
訪問看護情報提供療養費とは
訪問看護情報提供療養費は、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、連携する他の医療機関や自治体などに対し、訪問看護の実施状況や利用者の情報を提供した場合に算定できる費用です。
医療保険の制度における名称で、介護保険にも同様の加算があります。この制度は、単に書類を作成したことに対する手間賃というわけではありません。
質の高い連携を推進し、結果として利用者が受けるケアの質を向上させることを目的としています。
療養費が算定できる3つのケース
医療保険における訪問看護情報提供療養費は、情報を提供する相手先によって、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの区分に分かれています。それぞれ、算定できる条件や場面が定められています。
- 訪問看護情報提供療養費Ⅰ:連携する保険医療機関(病院や診療所)に情報提供した場合。
- 訪問看護情報提供療養費Ⅱ:利用者が居住する地域の市町村や、児童相談所などに情報提供した場合。
- 訪問看護情報提供療養費Ⅲ:学校など(幼稚園、小・中学校、高校など)に情報提供した場合。
利用者が費用を負担することはあるのか
療養費や加算は、保険制度から事業所に対して支払われるもので、情報提供書の作成や交換によって、利用者が直接、追加の費用を請求されることは基本的にありません。
ただし、病院が作成する診療情報提供書(紹介状)については、文書作成料として自己負担が発生します。制度は複雑ですが、連携のための費用は、利用者に過度な負担がかからないように配慮されています。
訪問看護情報提供療養費の概要(医療保険)
| 種類 | 主な提供先 | 目的 |
|---|---|---|
| 療養費Ⅰ | 病院、診療所 | 主治医や他の専門医との医療的な連携強化 |
| 療養費Ⅱ | 市町村、保健所、児童相談所 | 医療と介護・福祉の連携、公的サービスの活用促進 |
| 療養費Ⅲ | 学校、幼稚園、保育所 | 医療的ケアが必要な児童の学校生活支援 |
※上記は医療保険の例です。介護保険にも同様の趣旨の「訪問看護情報提供加算」があります。
制度が目指す質の高い連携
情報提供に対して公的な費用が設定されている背景には、国として多職種連携を強く推進していくという意図があります。
それぞれの専門職が持つ情報を積極的に交換し、共有することで、地域全体で利用者を支える包括的なケア体制を構築することを目指しています。
円滑な連携を生む情報提供書のポイント
ただ単に書類を作成すれば良いというわけではありません。受け取った相手が本当に必要とする、質の高い情報提供書を作成するためには、いくつかのポイントがあります。
正確かつ最新の情報であること
情報提供書の基本は、記載されている情報が正確であることです。特に、内服薬の内容や医療機器の設定値などは、間違いがあれば利用者の生命に直接関わる可能性があり、また、情報は常に新しくなります。
古い情報のままでは、現在の利用者の状態に合った適切なケアはできません。作成する際には、必ず最新の情報を確認し、記載することが求められます。
具体的なエピソードや本人の言葉を盛り込む
病名や検査データといった客観的な情報だけでなく、その人らしさを伝える情報も非常に重要です。
例えば、痛みに対してどのような言葉で表現するか、どのような時に笑顔が見られるか、といったエピソードを盛り込むことで、受け手は利用者の人柄や生活の様子をより深く理解できます。
本人が語った言葉をそのまま引用することも、その人の価値観を伝える上で有効です。
プライバシーへの配慮
情報提供書には、非常にデリケートな個人情報が含まれます。情報が不必要に漏れることがないよう、取り扱いには最大限の注意を払う必要があり、情報の提供にあたっては、必ず事前に利用者や家族から文書で同意を得ることが原則です。
また、共有する相手も、ケアに直接関わる必要最小限の範囲にとどめるなど、個人情報保護のルールを遵守します。
利用者・家族として情報提供書とどう関わるか
情報提供書は専門職間でやり取りされる書類ですが、主役はあくまで利用者本人で、ご自身の情報がどのように扱われているのかを知り、療養生活に主体的に関わっていくことが大切です。
自分の情報が正しく伝わっているか確認する
専門職は細心の注意を払って情報提供書を作成しますが、思い込みや勘違いが全くないとは言い切れません。もし、ケアを受ける中で、自分の状況とは違う前提で話が進んでいると感じた場合は、遠慮なく確認することが大切です。
訪問看護師に「私の情報は、先生にどのように伝わっていますか」と尋ねてみることで、認識のズレを修正するきっかけになります。
療養生活での希望や不安を伝える機会
情報提供書は、専門職が利用者の希望や目標を共有するためのツールでもあります。日頃から、訪問看護師やケアマネジャーに、ご自身がどう過ごしたいか、何に困っているかを伝えておくことが重要です。
その思いが情報提供書に反映され、チーム全体に共有されることで、より希望に沿ったケアを受けられるようになります。
チームに伝えておきたいことの例
- 療養生活で一番大切にしたいこと
- 痛みや苦痛など、我慢できない症状
- 家族に対する思いや、かけてほしくない負担
- 好きなこと、楽しみしていること
同意と個人情報保護について
情報提供を行う際には、原則として事業者から利用者に対して、どこに、どのような目的で情報提供を行うのか説明があり、同意を求めます。内容をよく理解し、納得した上で同意することが大切です。
もし、特定の相手に知られたくない情報がある場合などは、相談することも可能できるので、ご自身の個人情報がプライバシーに配慮した上で、安全に管理されていることを確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
最後に、訪問看護の情報提供書に関して、多くの方から寄せられる質問と回答をまとめました。
- 情報提供書は自分で書く必要がありますか?
-
情報提供書は医師や看護師、ケアマネジャーといった専門職が、それぞれの専門的な視点から作成する書類です。利用者やご家族が直接、書類を作成することはありません。
ただし、作成にあたり、ご本人やご家族から生活の様子や希望について詳しくお話を伺うことはあります。
- 誰が情報提供書を見ることができますか?
-
情報提供書を閲覧できるのは、利用者のケアに直接関わる、同意を得た範囲の専門職に限られ、主治医、訪問看護師、ケアマネジャー、訪問介護員、リハビリ専門職などです。
ケアに関わらない第三者が、本人の同意なく情報を閲覧することは、個人情報保護の観点から固く禁じられています。
- 情報提供書の内容に間違いを見つけたらどうすればいいですか?
-
もし、ご自身の情報として伝えられている内容に、事実と異なる点や認識の違いがあることに気づいた場合は、訪問看護師やケアマネジャー)にその旨を伝えてください。
情報を訂正し、関係者間で再度、正確な情報を共有することは、安全で質の高いケアのために非常に重要です。
- 訪問看護情報提供療養費という費用は、毎回発生しますか?
-
訪問看護情報提供療養費(または介護保険の加算)は、定められた特定の相手先(他の医療機関や市町村など)に対して、定められた要件を満たす情報提供を行った場合に、月に1回などの頻度で算定されるものです。
日常的な報告や連絡で、その都度費用が発生するわけではありません。
以上
参考文献
Yoshimoto T, Nawa N, Uemura M, Sakano T, Fujiwara T. The impact of interprofessional communication through ICT on health outcomes of older adults receiving home care in Japan–a retrospective cohort study. Journal of general and family medicine. 2022 Jul;23(4):233-40.
Nishiguchi S, Sugaya N, Saigusa Y, Inamori M. Effect of interprofessional collaboration among nursing home professionals on end-of-life care in nursing homes. Drug Discoveries & Therapeutics. 2021 Apr 30;15(2):93-100.
Katahira N, Maruo S. Relationship between nurses’ perceptions of the benefits/challenges of nursing and degree of interprofessional and intraprofessional collaboration in all‐inclusive services combining day services, overnight stays and home‐visit nursing for the older people living at home. Journal of General and Family Medicine. 2024 Jan;25(1):10-8.
Ohta R, Ryu Y, Katsube T, Sano C. Rural homecare nurses’ challenges in providing seamless patient care in rural Japan. International journal of environmental research and public health. 2020 Dec;17(24):9330.
Yoshida Y, Hirakawa Y, Hong YJ, Mamun MR, Shimizu H, Nakano Y, Yatsuya H. Factors influencing interprofessional collaboration in long-term care from a multidisciplinary perspective: a case study approach. Home Health Care Services Quarterly. 2024 Oct 1;43(4):239-58.
Haruta J, Yoshida K, Goto M, Yoshimoto H, Ichikawa S, Mori Y, Yoshimi K, Otsuka M. Development of an interprofessional competency framework for collaborative practice in Japan. Journal of interprofessional care. 2018 Jul 4;32(4):436-43.
Sekanina U, Tetzlaff B, Mazur A, Huckle T, Kühn A, Dano R, Höckelmann C, Scherer M, Balzer K, Köpke S, Hummers E. Interprofessional collaboration in the home care setting: perspectives of people receiving home care, relatives, nurses, general practitioners, and therapists—results of a qualitative analysis. BMC Primary Care. 2024 Mar 4;25(1):79.
Kimura T, Chiba H, Nomura K, Mizukami J, Saka S, Kakei K, Ishikawa J, Yamadera S, Sakato K, Fujitani N, Takagi H. Communication between physicians, patients, their companions and other healthcare professionals in home medical care in Japan. Patient Education and Counseling. 2024 Jun 1;123:108239.
Katsuyama K, Kato K, Murata Y, Yoshinaga T, Yasukawa F, Nemoto A. Current Status and Issues with Japan’s Community-Based Integrated Care System: Health Information System and Health Information Exchange System Framework. Health Informatics: Translating Information into Innovation. 2020 Sep 15:155-74.
Nobuko S, Mikiko H, Sachiko M, Yayoko T, Miwa K. An analysis of the contents of home nursing training focusing on liaison: As a basis for guidance on interprofessional liaison. AINO JOURNAL. 2017 Mar 31;15:75-80.