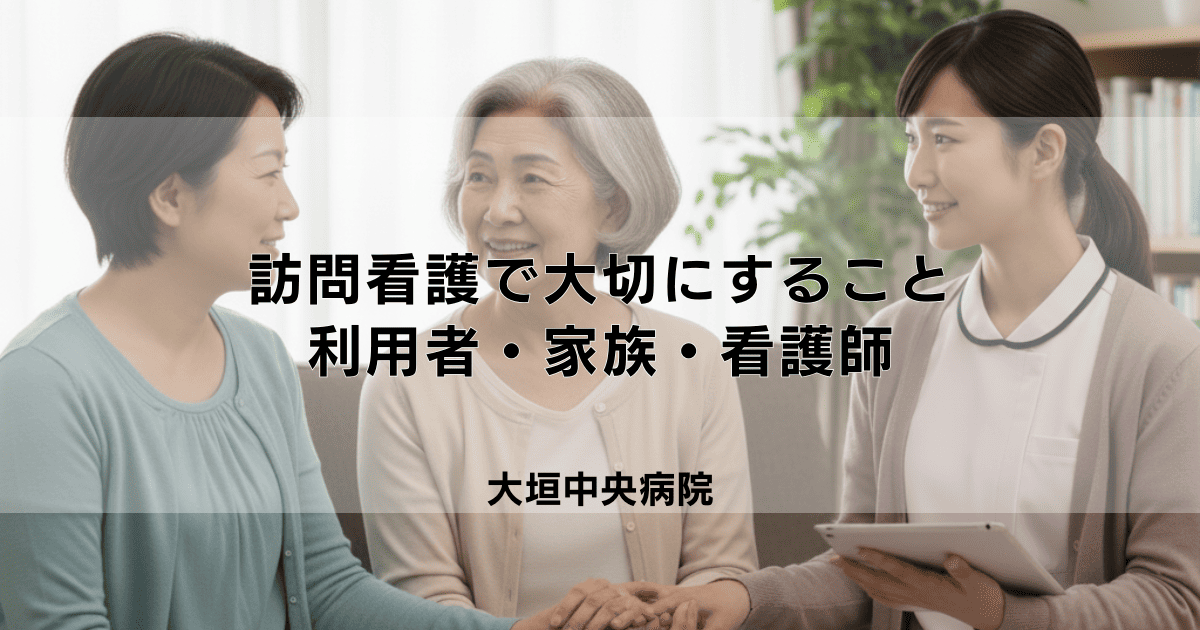訪問看護は、病気や障害があっても住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送るために、看護師などがご自宅を訪問しケアを提供するサービスです。
利用者ご本人、ご家族、そして私たち看護師、それぞれの立場から見て大切にしたいことがあります。
この記事では、訪問看護を利用する上で何が重要なのか、それぞれの視点から詳しく解説します。サービスを上手に活用し、より良い療養生活を送るためのヒントを見つけてください。
訪問看護の基本的な役割と目的
訪問看護の最も大きな役割は、療養生活を送るご本人とご家族が、住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい生活を続けられるよう支援することです。
医師の指示に基づき、看護師や理学療法士などの専門職がご自宅を訪問し、医療的なケアから日常生活の援助、ご家族の相談対応まで幅広く行います。
住み慣れた場所での療養を支える
病院ではなくご自宅で療養することには、大きな安心感があり、訪問看護は、安心感を医療的な側面から強力に後押しします。
ご自宅の環境に合わせて療養生活を整え、必要な医療処置やケアを提供することで、入院生活とは異なる、その人らしいリズムでの生活維持を目指します。
ご本人の生活スタイルや価値観を尊重しながら、専門的な視点で安全と安楽を守ることが、訪問看護の役目です。
訪問看護が支える生活場面
- 日常の健康管理
- 医療的な処置
- 身の回りのケア
- 精神的なサポート
このような場面で看護師が関わることにより、ご自宅での療養生活がより安定し、質の高いものになり、また、環境が変わらないことで、ご本人の精神的な安定にもつながります。
病状の管理と早期発見
訪問看護師は、定期的にご自宅を訪問し、ご本人の健康状態を継続的にチェックし、血圧、脈拍、体温、呼吸状態などのバイタルサインの測定はもちろん、皮膚の状態、食事や排泄の状況、痛みの有無など、全身の状態をきめ細かく観察します。
継続的な関わりにより、病状のささいな変化や新たな問題の兆候を早期に発見でき、異常の兆候を察知した場合は、速やかに主治医に報告し、指示を仰ぎ、適切な対応につなげることが可能です。
主なバイタルサインとその目安
| 項目 | 内容 | 観察のポイント |
|---|---|---|
| 体温 | 身体の熱の状態 | 発熱や低体温の有無、平熱との比較 |
| 脈拍 | 心臓の拍動数やリズム | 頻脈、徐脈、不整脈の有無 |
| 血圧 | 血液が血管を押す力 | 高血圧や低血圧、普段との変動 |
| 酸素飽和度 | 血液中の酸素の量 | 呼吸困難感との関連、低下の有無 |
数値を機械的に測るだけでなく、ご本人の自覚症状や表情、活気なども含めて総合的に健康状態を判断します。
療養生活の質(QOL)の維持・向上
訪問看護は、病気の治療や管理だけでなく、利用者ご本人の療養生活の質、すなわちQOL(Quality of Life)が大切です。ご本人が何を望み、どのような生活を送りたいかを理解し、実現するための方法を一緒に考えます。
例えば、痛みを和らげるケア、楽な姿勢の工夫、趣味活動の継続支援、外出の援助など、できる限りご本人の希望に沿った生活ができるようサポートします。生活の中に楽しみや役割を見いだせることも、療養生活を送る上で非常に重要です。
家族への支援と介護負担の軽減
ご自宅での療養は、ご家族の介護負担が大きくなりがちです。訪問看護師は、ご家族の健康状態や介護に対する不安、悩みにも耳を傾け、支援を行います。
日々の介護方法についてアドバイスを行ったり、医療的な処置をご家族に代わって実施したりすることで、直接的な負担を軽減します。
また、精神的なサポートを通じて、ご家族が介護を一人で抱え込まず、安心してご本人と向き合える環境を整えることも、訪問看護の大切な役割の一つです。
利用者にとって大切なこと
訪問看護サービスを最大限に活用し、ご自身にとってより良い療養生活を送るためには、利用者ご本人に意識していただきたい点がいくつかあります。
看護師はあくまで支援者であり、療養生活の主体はご本人なので、受け身になるのではなく、積極的にサービスを活用する姿勢が大切です。
自分の意思や希望を明確に伝える
ご自身がどのような療養生活を送りたいか、何を大切にしているか、どのようなケアを望むかを、ぜひ看護師に伝えてください。
朝はゆっくり起きたい、この時間に入浴したい、痛みはできるだけ早く取ってほしいなど、希望を伝えていただくことで、看護師はご本人の意向に沿った看護計画を立てやすくなります。
遠慮してしまうこともあるかもしれませんが、ご自身の生活に関する大切なことなので、小さなことでも構いませんので、意思表示をすることが重要です。
看護師に伝えておきたい希望の例
| 分類 | 具体例 | 伝えるポイント |
|---|---|---|
| 生活リズム | 起床・就寝時間、食事の時間 | 日々の習慣を尊重してほしい |
| ケアの好み | 入浴の方法、着替えの好み | 心地よいと感じる方法、不快なこと |
| 価値観 | 大切にしたい時間、やりたいこと | 生活の張り合いにつながる活動 |
看護師との信頼関係を築く
訪問看護師は、ご自宅という最も私的な空間にお邪魔するため、利用者ご本人と看護師との間に信頼関係がなければ、良いケアは提供できません。看護師はご本人のプライバシーを守り、尊重する姿勢で関わります。
ご本人も、看護師を一人の人間として受け入れ、対話を重ねてみてください。最初は緊張するかもしれませんが、訪問を重ねるうちに、徐々に気心知れた関係性を築いていけ、信頼関係が療養生活の安心感につながるのです。
日々の体調変化を正直に共有する
看護師が訪問していない時間の体調変化は、ご本人からの情報が頼りです。いつもと違う痛み、食欲の変動、睡眠の状態、気分の落ち込みなど、ご自身が感じた小さな変化を、訪問時に正直に教えてください。
こんなことを言っても仕方ないと思うようなことでも、看護師にとっては病状を判断する上で重要な情報になる場合があります。我慢したり、隠したりせず、ありのままの状態を共有することが、適切なケアを受ける第一歩です。
共有したい体調変化
- いつもと違う痛みやしびれ
- 食欲の変動、吐き気
- 睡眠の状態(眠れない、寝すぎる)
- 気分の落ち込み、不安感
- 排泄の回数や性状の変化
無理をせずサービスを活用する
ご自宅での療養では、つい頑張りすぎてしまうことがありますが、無理は禁物で、訪問看護は、ご本人が無理なく、安全に生活を送るために利用するものです。
自分でできることと、看護師に任せた方が良いことを見極め、支援を受け入れることも大切で、体調が優れない時や、不安な時は、看護師を頼ってください。
サービスを上手に活用することで、体力を温存し、安定した療養生活を長く続けることにつながります。
家族にとって大切なこと
利用者ご本人を支えるご家族も、訪問看護の重要なパートナーで、ご家族が心身ともに健康でなければ、ご本人を支え続けることは困難です。ご家族自身のことも大切にしながら、訪問看護と上手に連携していく視点を持ってください。
介護の悩みを一人で抱え込まない
ご家族による介護は、身体的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。日々の介護で困っていること、将来への不安、ご本人との関わり方についての悩みなど、どのようなことでも訪問看護師に相談してください。
看護師は、介護の専門家であると同時に、ご家族の良き相談相手でもあります。悩みを話すだけでも、心が軽くなることがあります。ご家族だけで全てを抱え込む必要はありません。
訪問看護で相談できる家族の悩み
| 悩みの種類 | 具体例 | 看護師の支援 |
|---|---|---|
| 身体的負担 | 体位交換、移乗、入浴介助 | 介護方法の指導、負担軽減の工夫 |
| 精神的負担 | 認知症の対応、将来への不安 | 傾聴、精神的サポート、情報提供 |
| 時間的拘束 | 常時の見守り、通院の付き添い | レスパイトケアの提案、他サービス連携 |
看護師との情報共有を密にする
ご家族は、利用者ご本人の一番近くにいる存在で、看護師が訪問していない間のご本人の様子、食事や睡眠、会話の内容など、ご家族だからこそ気づく小さな変化は、非常に貴重な情報源です。
訪問看護師にそれらの情報を伝えることで、よりきめ細やかな看護が可能になり、また、看護師からもご本人の状態やケアの内容について説明を受け、情報を共有することで、ご家族も安心して介護にあたれます。
連絡ノートなどを活用するのも良い方法です。
利用者本人の意向を尊重する
ご家族としては、ご本人に良かれと思っていろいろと世話を焼きたくなるものですが、大切なのはご本人がどうしたいか、という意思です。ご家族の希望とご本人の希望が異なる場合もあるかもしれません。
そのような時、訪問看護師は第三者の専門職として間に入り、双方の思いを受け止めながら、ご本人にとって最も良い方法を一緒に考えるお手伝いをします。ご家族も、まずはご本人の気持ちや意向に耳を傾ける姿勢を大切にしてください。
家族自身の休息も意識する
介護者が倒れてしまっては、共倒れになりかねません。ご家族がご自身の健康を維持し、休息を取ることは、結果としてご本人を長く支えることにつながります。
訪問看護師が訪問している時間は、ご家族が少し休息を取る時間にあてることもできます。
また、介護保険のショートステイやデイサービスなど、他のサービスを組み合わせて利用し、ご家族がリフレッシュできる時間を意識的に作ることも重要です。訪問看護師は、そのようなサービス利用についても相談に応じます。
看護師が大切にしている視点
訪問看護師も、質の高いケアを提供するために、常に大切にしている視点があり、利用者ご本人やご家族からは見えにくい部分かもしれませんが、このような視点が訪問看護の基盤です。
利用者の全体像(身体・精神・生活)を把握する
訪問看護師は、利用者ご本人を、単に病気や障害を持つ部分として見るのではなく、生活背景や価値観、精神的な状態も含めた一人の人間として、全体的に把握(アセスメント)することを大切にしています。
身体的な苦痛だけでなく、孤独感や不安感、ご家族との関係性、経済的な心配事など、さまざまな要因が療養生活に影響しまするので、情報を多角的に収集し、その人全体を理解した上で、必要な看護を考えます。
アセスメントで重視する情報
| 側面 | 確認項目 | 把握する目的 |
|---|---|---|
| 身体的側面 | 病状、ADL、栄養状態、痛み | 医療的ケアの必要性判断 |
| 精神・心理的側面 | 意欲、不安、認知機能、受容度 | 精神的ケア、意思決定支援 |
| 社会的側面 | 家族構成、住環境、介護力、社会資源 | 療養環境の調整、他サービス連携 |
個別性を重視した看護計画
同じ病名であっても、必要な看護は人それぞれ異なり、年齢、体力、生活環境、価値観、ご家族の状況などが違えば、当然、ケアの優先順位や方法も変わってきます。
画一的なケアではなく、利用者一人ひとりの個別性を重視した看護計画を作成することが大切です。ご本人やご家族と話し合いながら、その人にとっての目標を設定し、達成するためのケア内容を計画・実行・評価していきます。
主治医や他職種との連携
ご自宅での療養生活は、訪問看護師だけで支えられるものではありません。
主治医(かかりつけ医)の指示に基づき、ケアマネジャー、薬剤師、リハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、ホームヘルパーなど、多くの専門職が関わります。
訪問看護師は関係者と常に密に情報を交換し、連携を図る調整役としての役割も担い、チーム全体で情報を共有し、同じ目標に向かって支援することで、切れ目のない一貫したサービスを提供することが可能です。
主な連携先
- 主治医(かかりつけ医)
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- 薬剤師
- リハビリ専門職
- ホームヘルパー
倫理的な配慮と意思決定支援
在宅療養では、治療の選択や終末期の過ごし方など、難しい判断を迫られる場面もありますが、利用者ご本人の自己決定権を最大限に尊重します。
ご本人が十分な情報を得た上で、自らの意思で選択できるよう、分かりやすく説明し、一緒に考える支援を行います。
ご本人の意思が確認できない場合でも、ご家族や主治医と話し合い、ご本人にとっての最善は何かを倫理的な視点から追求することが第一です。
訪問看護における関係構築の重要性
訪問看護は、医療技術を提供するだけが仕事ではありません。利用者ご本人やご家族との良好な人間関係を築くことが、全てのケアの土台となります。
ご自宅というパーソナルな空間で、安心してケアを受けていただくためには、お互いの信頼が何よりも大切です。
初回訪問での丁寧な説明と傾聴
初めて訪問看護師が家に来る時は、利用者ご本人もご家族も緊張しているものです。訪問看護師は、まずご自身がどのような人間であるかを知っていただくことから始めます。
そして、訪問看護のサービス内容や役割について丁寧に説明し、ご契約内容を確認し、同時に、最も大切なこととして、ご本人やご家族が今、何に困り、何を望んでいるのか、思いをじっくりと傾聴します。
初回訪問での主な確認事項
| 確認内容 | 目的 | 双方の役割 |
|---|---|---|
| サービス内容の説明 | 提供できるケアの明確化 | 看護師が説明、利用者・家族が理解 |
| 利用者の希望・不安 | 個別的なニーズの把握 | 利用者・家族が表明、看護師が傾聴 |
| 緊急連絡体制 | 急変時の迅速な対応のため | 双方が連絡手段・手順を確認 |
定期的な対話による認識のすり合わせ
信頼関係は一度築いたら終わりではなく、日々の関わりの中で育んでいくものです。定期的な訪問のたびに、何気ない世間話も含めた対話を重ねていき、その中で、ご本人の体調や気持ちの変化、ご家族の様子の変化などを感じ取ります。
また、提供しているケアがご本人の意向に沿っているか、目標に近づいているかを常に確認し、必要であれば柔軟に計画を修正します。
小さな変化や気づきを尊重する姿勢
ご本人やご家族が口にする小さな言葉、ふとした表情の変化、いつもの様子とのわずかな違いが、重要なサインであることが少なくありません。訪問看護師は、小さな変化や気づきを見逃さず、尊重する姿勢を大切にしています。
背景に何があるのかを考え適切に対応しますが、本人やご家族からも、気になることがあれば、どんな些細なことでも伝えてほしいとお願いしています。
利用者と家族双方への配慮
訪問看護は、利用者ご本人だけでなく、ご家族も支援の対象です。時には、ご本人の思いとご家族の思いがすれ違うこともありますが、どちらか一方の味方をするのではなく、双方の気持ちを理解し、受け止める中立的な立場を保ちます。
ご本人にとっても、ご家族にとっても、訪問看護師が良き理解者であり、相談相手であると感じてもらえるよう、バランスの取れた関わりを心がけます。
訪問看護サービスを上手に活用するコツ
訪問看護は、利用の仕方次第で、療養生活をより豊かに、安心なものにできます。サービスを上手に活用するためのいくつかのコツを紹介します。
サービス内容と範囲を理解する
まず、訪問看護で何ができ、何ができないのか、範囲を理解しておくことが大切で、訪問看護は、医師の指示書に基づいて行われる医療行為や療養上の世話が中心です。
介護保険や医療保険のルール上、対応できないこともあります(ご家族の分の家事や、ペットの世話など)。サービス内容を正しく理解することで、過度な期待による失望を防ぎ、必要な支援を的確に受けることができます。
訪問看護のサービス範囲(一例)
| サービス分類 | できること(例) | できないこと(例) |
|---|---|---|
| 医療的ケア | 点滴、褥瘡処置、服薬管理 | 医師の指示がない医療行為 |
| 日常生活の援助 | 清拭、入浴介助(療養上必要) | 大掃除、利用者以外の家事 |
| 家族支援 | 介護相談、精神的サポート | 家族の分の食事作り |
必要なことは遠慮なく相談する
療養生活では、日々さまざまな疑問や不安が生じるものです。「こんなことを聞いていいのだろうか」「忙しい看護師さんに悪いな」と遠慮してしまうことがあるかもしれません。
しかし、小さな不安や疑問を放置することが、後々大きな問題につながることもあるので、体調のこと、介護のこと、生活のこと、何でも遠慮なく相談してください。
相談をためらいがちなこと
- 些細と感じる体調不良
- 介護に対する愚痴や不満
- 経済的な心配事(制度の紹介)
- 看護師への要望やケアの変更
緊急時の連絡体制を確認する
訪問看護ステーションは、多くの場合、24時間対応の体制を整えています。訪問時間外に体調が急変した場合や、緊急に相談したいことが発生した場合、どこにどのように連絡すればよいか、あらかじめ確認しておきましょう。
緊急時の連絡先や対応の流れを知っておくだけで、いざという時の安心感が大きく異なるので、体制の確認はサービスを活用する上で重要です。
複数のサービスを組み合わせて利用する
ご自宅での療養生活は、訪問看護だけで完結するものではありません。
必要に応じて、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問リハビリテーション、デイサービス、ショートステイ、福祉用具のレンタルなど、他の介護サービスや地域の社会資源を組み合わせて利用することが効果的です。
ケアマネジャーが中心となって、ご本人やご家族の状況に合わせたサービス利用計画(ケアプラン)を作成し、訪問看護師も、必要なサービスについて情報提供や助言を行います。
訪問看護でよくある不安と対応
訪問看護の利用を始めるにあたり、さまざまな不安を感じる方もいらっしゃいます。代表的な不安と、不安に対する訪問看護師の考え方や対応について説明します。
他人が家に来ることへの抵抗感
ご自宅は最もプライベートな空間で、そこに他人が入ってくることに抵抗を感じるのは自然なことです。
ご本人の許可なく部屋に入ったり、物品に触れたりすることはなく、訪問時間やケアを行う場所についても、ご本人の意向を最大限尊重します。
まずは短時間の訪問から始め、徐々に慣れていただくなど、ご本人のペースに合わせた関わり方を工夫します。
家族の介護負担が増えるのではないか
訪問看護を利用することで、かえって家族のやることが増えるのではないかと心配される方もいますが、目的は、ご家族の負担を軽減することです。訪問看護師が医療的な処置や専門的なケアを行うことで、ご家族の直接的な介護負担は減ります。
また、介護方法を指導することで、より楽に安全に介護できるよう支援します。何より、ご家族の悩みを聞き、精神的に支えることで、心理的な負担軽減をすることが目標です。
訪問看護が目指す家族の負担軽減
| 負担の種類 | 訪問看護による支援 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 技術的な負担 | 医療的処置の実施、介護指導 | 専門的ケアによる安心感 |
| 精神的な負担 | 傾聴、共感、助言、情報提供 | 孤独感の緩和、不安の軽減 |
| 時間的な負担 | 看護師によるケアの提供 | 家族自身の時間の確保(レスパイト) |
費用面での心配
訪問看護の利用には費用がかかります。どのくらいの費用になるかは、利用する公的保険(医療保険または介護保険)の種類や、利用頻度、提供されるサービス内容によって異なります。
利用開始前に、ケアマネジャーや訪問看護ステーションの担当者が、費用の概算について詳しく説明します。高額療養費制度など、自己負担を軽減するための制度もありますので、費用面で不安がある場合は、遠慮なくご相談ください。
訪問看護利用時の費用構成要素
| 費用の種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本利用料 | 訪問1回あたりの費用 | 利用する制度や時間により異なる |
| 加算料金 | 専門的なケアや時間外対応など | 必要なサービスに応じて追加 |
| 交通費など | 事業所規定の実費(範囲外など) | 事前に説明があります |
症状が急変した時の対応
ご自宅での療養で最も不安なことの一つが、夜間や休日などの急変時対応かもしれません。多くの訪問看護ステーションでは、24時間365日、電話相談や緊急訪問ができる体制を整えています。
ご契約時に、緊急時の連絡方法や対応の流れを詳しく説明し、万が一の時は、まずはステーションに連絡をください。看護師が電話で状況を伺い、必要に応じてご自宅に駆けつけ、主治医と連携しながら適切な対応をとります。
急変時対応の流れ(一例)
- 利用者・家族からステーションへ緊急連絡
- 看護師による電話での状況確認・助言
- 必要に応じて看護師が緊急訪問
- 主治医への報告・指示確認
- 必要な処置の実施、または救急搬送の判断
訪問看護で大切にしたいことに関するよくある質問
- 訪問看護師にどこまでお願いできますか
-
訪問看護師は、主治医の指示に基づき、療養上必要な医療的ケアや日常生活の援助を行います。点滴や褥瘡の処置、服薬管理、体調管理、入浴介助、リハビリテーション、ご家族への介護指導など、多岐にわたります。
ただし、家事全般(ご家族の分の食事作りや大掃除など)や、医師の指示がない医療行為は行えません。詳しくは担当の看護師やケアマネジャーにご相談ください。
- 訪問看護の頻度や時間はどのくらいですか
-
訪問の頻度や時間は、利用者ご本人の病状やご希望、ご家族の状況、主治医の指示などを総合的に判断して決定します。医療処置が毎日必要な方もいれば、週に1回の体調確認で十分な方もいます。
1回あたりの訪問時間は30分から90分程度が一般的です。ケアマネジャーや訪問看護ステーションと相談しながら、ご自身に合った利用計画を立てていきます。
- 看護師との相性が合わない場合はどうすればよいですか
-
まずは、訪問看護ステーションの管理者や担当のケアマネジャーに率直にご相談ください。訪問看護はご自宅という私的な空間で行うため、看護師との信頼関係が非常に大切です。
相性が合わないと感じる理由(話し方、ケアの方法など)を伝えていただけると、ステーション側も対応を検討しやすくなります。担当看護師の変更や、関わり方の調整などを相談できます。
- 訪問看護の利用をやめたい時はどうしますか
-
利用を中止したい場合は、まず担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションにご意向をお伝えください。理由をお伺いした上で、中止の手続きを進めます。
病状の変化や他のサービスへの切り替えなど、状況に応じて今後の療養生活についても一緒に考え、必要な支援が途切れないよう調整します。
以上
参考文献
Murashima S, Nagata S, Magilvy JK, Fukui S, Kayama M. Home care nursing in Japan: a challenge for providing good care at home. Public health nursing. 2002 Mar;19(2):94-103.
Ohta R, Ryu Y, Katsube T, Sano C. Rural homecare nurses’ challenges in providing seamless patient care in rural Japan. International journal of environmental research and public health. 2020 Dec;17(24):9330.
Igarashi A, Kurinobu T, Ko A, Okamoto Y, Matsuura S, Feng M, Yamamoto-Mitani N. Factors related to the provision of home-based end-of-life care among home-care nursing, home help, and care management agencies in Japan. BMC Research Notes. 2015 Sep 12;8(1):434.
Fujita K, Kushida K, Moles RJ, Chen TF. Home healthcare professionals’ perspectives on quality dimensions for home pharmaceutical care in Japan. Geriatrics & gerontology international. 2019 Jan;19(1):35-43.
Sakagami Y, Nakayama N, Konishi K. Reliability and validity of home-visit nursing quality indicators for children with medical complexity in Japan. Journal of Pediatric Nursing. 2022 Mar 1;63:136-42.
Matsuda S, Yamamoto M. Long-term care insurance and integrated care for the aged in Japan. International Journal of Integrated Care. 2001 Sep 1;1:e28.
Tanaka K, Hasegawa M, Nagayama Y, Oe M. Nursing Philosophy of community mental health nurses in Japan: A qualitative, descriptive study. International Journal of Mental Health Nursing. 2018 Apr;27(2):765-73.
Murashima S, Asahara K, White CM, Ryu S. The meaning of public health nursing: Creating 24 hour care in a community in Japan. Nursing & Health Sciences. 1999 Jun;1(2):83-92.
Sun Y, Iwagami M, Sakata N, Ito T, Inokuchi R, Komiyama J, Kuroda N, Tamiya N. Evaluation of enhanced home care support clinics regarding emergency home visits, hospitalization, and end-of-life care: a retrospective cohort study in a city of Japan. BMC Health Services Research. 2023 Feb 3;23(1):115.
Tsutsui T, Muramatsu N. Care‐needs certification in the long‐term care insurance system of Japan. Journal of the American geriatrics society. 2005 Mar;53(3):522-7.