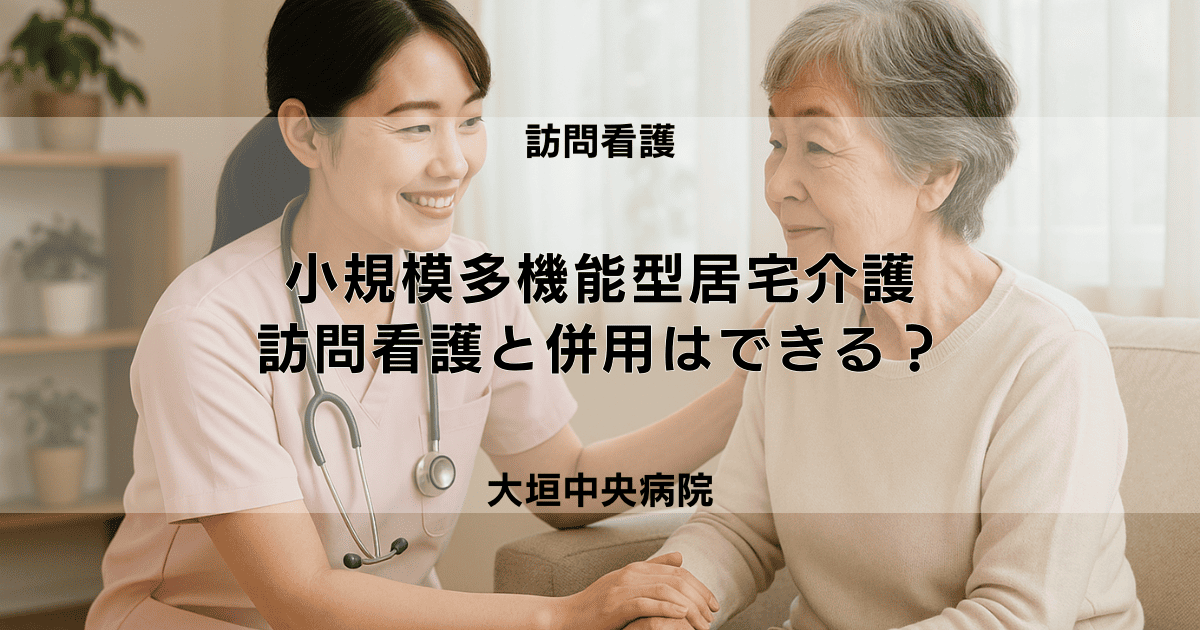住み慣れた地域で自分らしい生活を続けたいと願う方にとって、小規模多機能型居宅介護は心強いサービスです。しかし、医療的なケアが必要になったとき、訪問看護を一緒に利用できるのか疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用に関する基本的なルールから、併用が認められる特別な条件、手続き、そして注意すべき点までを詳しく解説します。
小規模多機能型居宅介護とは?
在宅での生活を継続するために重要な役割を担うのが、小規模多機能型居宅介護で、利用者が可能な限り自立した日常生活を送れるよう、多様な支援を一体的に提供する地域密着型のサービスです。
サービスの基本概要
小規模多機能型居宅介護は、要介護認定を受けた高齢者が、住み慣れた自宅や地域での生活を続けられるように支援する介護保険サービスの一つです。
事業所への通いを中心としながら、必要に応じて短期間の宿泊や自宅への訪問サービスを柔軟に組み合わせて利用できます。
利用者は一つの事業所と契約するだけで、顔なじみのスタッフから継続的なケアを受けることができ、環境の変化によるストレスを軽減できる点が大きな特徴です。
3つの中心的なサービス内容
このサービスは、主に「通い」「泊まり」「訪問」という3種類のサービスで構成されています。利用者の心身の状態や希望、家族の状況に応じて、サービスをケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、柔軟に組み合わせて提供します。
例えば、日中は通いでリハビリや交流を行い、ご家族が不在の夜間は泊まりを利用する、といった使い方が可能です。訪問サービスでは、安否確認や身体介護など、個別のニーズに対応します。
各サービスの特徴
| サービス種類 | 内容 | 利用シーンの例 |
|---|---|---|
| 通いサービス | 食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなどを提供 | 日中の活動の場、他者との交流 |
| 泊まりサービス | 通いと同じ事業所に宿泊し、夜間の介護を提供 | 家族の急な不在時、介護者の休息 |
| 訪問サービス | スタッフが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を提供 | 服薬確認、安否確認、身の回りの世話 |
利用できる対象者
小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、原則として事業所が所在する市区町村に住民票があり、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方です。地域密着型サービスであるため、その地域に住む住民が主な対象となります。
認知症の方や医療的ケアが必要な方でも、事業所の体制が整っていれば受け入れが可能です。
地域密着型サービスの特性
地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるように創設された仕組みです。市区町村が事業者の指定や監督を行うため、地域の実情に合わせたきめ細やかなサービス提供が期待できます。
小規模多機能型居宅介護もその一つであり、地域の高齢者を地域全体で支えるという考え方に基づいています。このため、利用者とスタッフ、さらには利用者同士が親密な関係を築きやすい環境が整っています。
訪問看護の役割とサービス内容
病気や障がいを抱えながら在宅で療養する方にとって、訪問看護は生活の質を維持・向上させるために重要な医療サービスです。看護師などの専門職が自宅を訪れ、医療的な側面から利用者を支えます。
訪問看護が提供する医療的ケア
訪問看護の最も中心的な役割は、主治医の指示に基づいた医療的ケアの提供です。これには、血圧や体温、脈拍などの健康状態のチェック、点滴や注射、インスリンの管理、褥瘡(床ずれ)の予防や処置、カテーテルの管理などが含まれます。
医療機関への通院が困難な方でも、自宅で必要な医療処置を受けられるため、安心して療養生活を送ることが可能です。
訪問看護で受けられる主な医療処置
| ケアの分類 | 具体的な内容 | 対象となる方の例 |
|---|---|---|
| 健康状態の観察 | バイタルサイン測定、病状のチェック | 慢性疾患を持つ方、退院直後の方 |
| 医療処置 | 点滴、注射、血糖測定、創傷処置 | 在宅で医療管理が必要な方 |
| 医療機器の管理 | 在宅酸素、人工呼吸器、カテーテルの管理 | 医療機器を利用しながら療養する方 |
医師の指示に基づく専門的な支援
すべての訪問看護サービスは、利用者の主治医が作成する「訪問看護指示書」に基づいて行います。看護師は、指示書に沿ってケア計画を立て、病状の悪化防止や回復に向けた専門的な支援を実施します。
また、利用者の状態に変化があった場合は速やかに主治医に報告し、指示を仰ぐなど、医療機関との密な連携が図られます。
日常生活の援助と家族へのサポート
訪問看護は医療的ケアだけでなく、療養生活を送る上での日常生活の援助も行います。身体を清潔に保つための清拭や入浴介助、食事や排泄の介助、リハビリテーションなどが含まれます。
さらに、介護を行う家族に対して、介護方法の指導や相談に応じることも重要な役割です。ご家族の介護負担を軽減し、精神的な支えとなることで、利用者と共に安心して生活できる環境を整えます。
精神的なケアの重要性
長期にわたる療養生活は、利用者に孤独感や不安をもたらすことがあります。訪問看護師は、定期的な訪問を通じて利用者と対話し、悩みや不安を聞き、精神的なサポートを提供します。
信頼関係を築きながら、利用者の心の状態にも配慮したケアを行うことは、治療意欲の向上や生活の質の維持に大きく貢献します。特に、精神疾患を抱える方への訪問看護では、精神的ケアが中心です。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用ルール
小規模多機能型居宅介護を利用しながら、別に訪問看護も利用したいと考えるケースは少なくありません。しかし、この二つのサービスを併用するには一定のルールがあります。
ここでは、併用の可否に関する基本的な考え方と、背景にある保険制度について解説します。
原則として併用はできない理由
介護保険制度では、小規模多機能型居宅介護のサービス費用は月額定額制(包括報酬)となっています。
定額料金には、「通い」「泊まり」に加えて「訪問」サービスも含まれており、訪問サービスの中には看護師によるケア(訪問看護)も想定されています。
小規模多機能型居宅介護の料金には、すでに基本的な訪問看護の費用が含まれていると解釈されるため、別に介護保険を使って他の訪問看護ステーションと契約することは、サービスの重複と見なされ、原則として認められていません。
併用が認められる特別なケースとは
原則として併用はできませんが、例外的に併用が認められる場合があります。それは、利用者の病状が重い、あるいは急激に悪化した場合など、主治医が専門的な医療的ケアの必要性が高いと判断し、特別な指示を出した場合です。
利用する保険が介護保険ではなく「医療保険」に切り替わります。医療保険による訪問看護は、小規模多機能型居宅介護の包括報酬とは別枠で算定されるため、併用が可能になるのです。
併用可否の判断基準
| 利用する保険 | 併用の可否 | 基本的な考え方 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 原則不可 | 小規模多機能の料金に訪問看護が含まれるため |
| 医療保険 | 可能 | 主治医の特別な指示があり、別枠での算定となるため |
介護保険と医療保険の使い分け
訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらでも利用できますが、どちらを優先するかは制度で決められています。要介護・要支援認定を受けている方は、原則として介護保険が優先されます。
しかし、厚生労働大臣が定める特定の疾病(末期がん、難病など)の方や、病状の悪化により主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合は、医療保険での訪問看護に切り替わります。
ケアプランにおける位置づけ
小規模多機能型居宅介護を利用する場合、ケアプランの作成は、事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)が担当します。
もし医療保険による訪問看護を併用することになった場合、小規模多機能のケアマネジャーは、訪問看護ステーションの看護師や主治医と連携し、全体のサービス内容を調整します。
医療と介護のサービスが一体的に提供されるよう、情報共有を行い、利用者の状態に合わせた最適な支援計画を立てることが必要です。
訪問看護の併用が認められる具体的な条件
小規模多機能型居宅介護を利用中に、医療保険を使った訪問看護を併用するためには、主治医による明確な医学的判断と、正式な指示が必要です。
特別訪問看護指示書が交付された場合
最も一般的な併用の根拠となるのが「特別訪問看護指示書」で、利用者の主治医が、急性増悪や退院直後などで一時的に頻回な訪問看護が必要だと判断した場合に交付するものです。
指示書が出されると、指示期間中(通常は月1回、最大14日間)、医療保険による訪問看護を受けることができます。この期間は、小規模多機能型居宅介護のサービスと並行して、専門的な医療ケアを集中的に受けることが可能です。
特別訪問看護指示書が交付される状態の例
| 状態 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 急性増悪期 | 病状が急激に悪化し、頻繁な状態観察や処置が必要な時 |
| 退院直後 | 病院から退院したばかりで、在宅療養への移行に支援が必要な時 |
| 終末期(ターミナル期) | 終末期で、苦痛緩和ケアや頻回な訪問が必要な時 |
精神科訪問看護指示書が交付された場合
精神疾患を持つ方が主治医(精神科医)から「精神科訪問看護指示書」の交付を受けた場合も、医療保険による訪問看護の併用が可能です。
この場合、精神症状の悪化を防ぎ、安定した在宅生活を支援することを目的とした専門的なケアが提供されます。
小規模多機能型居宅介護で日常的な支援を受けながら、精神科訪問看護で心のケアや服薬管理のサポートを受けるという形で、両方のサービスを有効に活用できます。
主治医が特に必要と判断した場合
上記の指示書以外にも、厚生労働大臣が定める特定の疾病等に該当する場合、主治医の判断により医療保険での訪問看護が適用され、末期がんや多発性硬化症、パーキンソン病関連疾患などの難病が含まれます。
このような疾病を持つ方は、病状の進行管理や専門的なケアが継続的に必要となるため、介護保険の枠にとらわれず、医療保険での訪問看護を併用することが認められています。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- パーキンソン病関連疾患
- その他、厚生労働大臣が定める疾病
併用する際の具体的な手続きと流れ
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用を決めた場合、スムーズにサービスを開始するためには、正しい手順を踏むことが大切です。主治医やケアマネジャー、訪問看護ステーションとの連携が鍵となります。
主治医への相談と指示書の依頼
すべての始まりは、主治医への相談です。現在の病状や在宅療養での不安を伝え、専門的な訪問看護が必要かどうかを相談します。
主治医が必要性を認めると、「特別訪問看護指示書」などの必要な指示書を作成し、訪問看護ステーションへ交付します。この指示書がなければ医療保険での訪問看護は開始できないため、最初の重要なステップです。
ケアマネジャーとの連携と情報共有
次に、小規模多機能型居宅介護事業所に所属するケアマネジャーに、主治医から訪問看護の指示が出たことを報告します。ケアマネジャーの役割は、全体のサービス計画を管理することです。
訪問看護が追加されることで、既存のサービス内容(特に訪問サービス)との調整が必要になる場合があり、ケアマネジャーが訪問看護ステーションと連絡を取り、情報共有を行うことで一体的な支援体制を構築します。
併用開始までの手続き概要
| ステップ | 担当者 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1. 相談と判断 | 利用者・家族、主治医 | 訪問看護の必要性を相談し、医師が判断する |
| 2. 指示書の交付 | 主治医 | 訪問看護ステーションへ指示書を交付する |
| 3. 連携と調整 | ケアマネジャー | 関係各所と情報共有し、ケアプランを調整する |
| 4. 契約と開始 | 利用者、訪問看護ステーション | サービス内容を確認し、契約後に訪問を開始する |
訪問看護ステーションとの契約
主治医からの指示書を受け取った訪問看護ステーションは、利用者または家族と面談を行い、具体的なサービス内容、訪問日時、緊急時の連絡方法、費用などについて詳しく説明があります。内容に同意できれば、正式に契約を結びます。
どの訪問看護ステーションを利用するかは、利用者が選ぶことができますが、主治医やケアマネジャーに相談して、地域で評判の良い事業所を紹介してもらうのが一般的です。
サービス開始までの調整事項
契約後、実際に訪問看護が開始されるまでに、最終的な調整が行われます。小規模多機能のスタッフと訪問看護師がカンファレンス(サービス担当者会議)を開き、それぞれの役割分担や情報共有の方法などを確認します。
「褥瘡の処置は訪問看護師が行い、日中の体位交換は小規模多機能のスタッフが行う」といった具体的な連携内容を決め、事前の調整により、重複や漏れのない質の高いサービス提供が可能です。
併用する上での注意点とポイント
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用は、在宅療養の質を高める上で非常に有効ですが、いくつかの注意点もあります。費用面や事業者間の連携など、
費用負担の仕組みを理解する
併用する場合、費用は2つの事業所からそれぞれ請求されます。小規模多機能型居宅介護の費用は月額定額の介護保険自己負担分、訪問看護の費用は医療保険の自己負担分(通常1〜3割)です。
両方の費用がかかるため、合計の自己負担額は増加し、また、医療保険には高額療養費制度があり、1か月の医療費自己負担額が上限を超えた場合は払い戻しを受けられます。
事前にケアマネジャーや各事業所に費用の概算を確認しておくことが重要です。
併用時の費用負担の内訳(例)
| サービス | 利用する保険 | 自己負担の仕組み |
|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 介護保険 | 月額定額制の1〜3割負担(所得による) |
| 訪問看護 | 医療保険 | 利用回数に応じた出来高制の1〜3割負担 |
各事業者との情報共有を密にする
サービスを提供する事業者が複数になるため、事業者間の密な情報共有が不可欠です。利用者の日々の状態変化や服薬状況、医師からの指示内容などを、小規模多機能のスタッフと訪問看護師が常に共有する体制が求められます。
連絡ノートの活用や定期的なカンファレンスの開催など、情報共有の方法を具体的に決めておくとスムーズです。家族からも、気づいたことがあれば積極的に両方の事業者に伝えるように心がけましょう。
- 連絡ノートの活用
- 定期的なカンファレンスの実施
- 電話やメールでの随時報告
サービスの提供範囲を確認する
併用を開始するにあたり、それぞれの事業者が担当するサービスの範囲を明確にしておくことが大切で、「このケアはどちらが担当するのか」といった混乱を避けるためです。
例えば、入浴介助は小規模多機能の通いサービスで行い、自宅での清拭は訪問看護で行うなど、役割分担を具体的に決めておきます。
内容はサービス担当者会議で話し合われますが、利用者やご家族も内容をしっかり把握しておくことが大事です。
状態変化があった場合の対応
利用者の容態が急に変化した場合に、どこに最初に連絡すべきかをあらかじめ決めておく必要があります。
日中は小規模多機能の事業所、夜間や緊急時は訪問看護ステーションの緊急連絡先など、時間帯や状況に応じた連絡体制を確認しておきましょう。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用に関して、利用者やご家族から寄せられることの多い質問と回答をまとめました。
- 費用はどのくらい変わりますか?
-
小規模多機能型居宅介護の月額定額料金に加えて、医療保険適用の訪問看護費用が上乗せされます。訪問看護の費用は、訪問回数やケア内容、お持ちの医療保険の自己負担割合(1〜3割)によって決まります。
正確な金額を知るためには、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに見積もりを依頼するのが最も確実です。高額療養費制度の対象になる可能性もあるため、併せて確認するとよいでしょう。
- どのタイミングで併用を相談すればよいですか?
-
併用を検討すべきタイミングはいくつかあります。
例えば、病院から退院して在宅療養に切り替わる時、病状が悪化して自宅での医療的ケアが必要になった時、あるいは家族の介護負担が増えて専門家の支援が必要だと感じた時などです。
少しでも不安や必要性を感じたら、まずはかかりつけの主治医や小規模多機能のケアマネジャーに相談することをお勧めします。早期に相談することでスムーズにサービスを導入できます。
- 家族が訪問看護を依頼することもできますか?
-
ご家族が主治医やケアマネジャーに相談し、訪問看護の利用を依頼することは可能です。
最終的に訪問看護が必要かどうかを判断し、指示書を出すのは主治医ですが、ご本人の状態を最もよく知るご家族からの情報は非常に重要です。
ご本人が希望をうまく伝えられない場合などは、ご家族が代わって状況を説明し、相談のきっかけを作ることが大切です。
- 途中で併用をやめることは可能ですか?
-
特別訪問看護指示書による集中的なケアが終了し、病状が安定した場合には、主治医の判断で医療保険による訪問看護は終了となります。
その後は、再び小規模多機能型居宅介護のサービスに含まれる訪問看護(介護保険)で対応することになります。も
利用者や家族の希望で併用を中止したい場合も、主治医やケアマネジャーに相談することで、サービス内容を見直すことができます。
以上
参考文献
Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Dec;13:1-1.
Fukui S, Yamamoto-Mitani N, Fujita J. Five types of home-visit nursing agencies in Japan based on characteristics of service delivery: cluster analysis of three nationwide surveys. BMC health services research. 2014 Dec;14:1-8.
Song P, Tang W. The community-based integrated care system in Japan: Health care and nursing care challenges posed by super-aged society. Bioscience trends. 2019 Jun 30;13(3):279-81.
Murashima S, Nagata S, Magilvy JK, Fukui S, Kayama M. Home care nursing in Japan: a challenge for providing good care at home. Public health nursing. 2002 Mar;19(2):94-103.
Matsuda S, Yamamoto M. Long-term care insurance and integrated care for the aged in Japan. International Journal of Integrated Care. 2001 Sep 1;1:e28.
Kayama M, Setoya N, Doyle C. Expanding use of nurse home visiting for community psychiatric care in Japan. Psychiatric Quarterly. 2020 Jun;91(2):571-6.
Setoya N, Aoki Y, Fukushima K, Sakaki M, Kido Y, Takasuna H, Kusachi H, Hirahara Y, Katayama S, Tachimori H, Funakoshi A. Future perspective of psychiatric home-visit nursing provided by nursing stations in Japan. Global health & medicine. 2023 Jun 30;5(3):128-35.
Majima T, Kusunoki J, Otsuka T. The role of the home-visit nursing system in the treatment of terminal cancer patients in Japan. Palliative Care for Chronic Cancer Patients in the Community: Global Approaches and Future Applications. 2021:543-7.
Kuwayama T, Hamabata K, Kamesaki T, Koike S, Kotani K. Research on home care nursing in Japan using geographic information systems: a literature review. Japanese clinical medicine. 2018 Nov;9:1179670718814539.
Tsutsui T. Implementation process and challenges for the community-based integrated care system in Japan. International Journal of Integrated Care. 2014 Jan 20;14:e002.