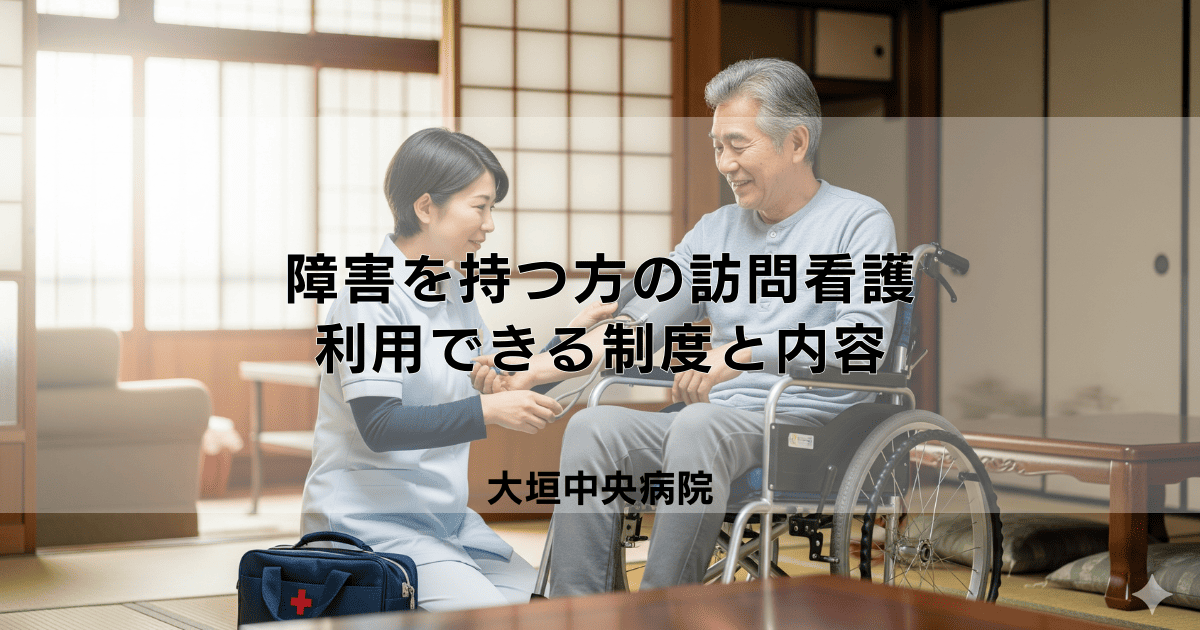障害や病気を抱えながらご自宅での生活を望む方々にとって、訪問看護は生活の質を維持、向上させるための重要なサービスです。
看護師などの専門家がご自宅へ訪問し、医療的ケアや日常生活の支援を行うことで、ご本人の自立した生活を支え、介護するご家族の負担を和らげます。
この記事では、障害を持つ方が訪問看護を利用する際に知っておきたい基本的な情報から、利用できる公的制度、サービス内容、そして気になる料金体系まで、幅広く解説します。
障害を持つ方への訪問看護とは
障害を持つ方への訪問看護は、病気や障害があっても、住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように、看護師や理学療法士などの専門職が生活の場へ訪問して支援するサービスです。
住み慣れた自宅で専門的なケアを提供
訪問看護の最大の特長は、ご本人が最も安心できる環境であるご自宅で、質の高い医療的ケアや看護を受けられる点です。病院や施設とは異なり、ご自身の生活リズムやプライバシーを保ちながら療養に専念できます。
看護師は定期的に訪問し、血圧や体温といった基本的な健康状態のチェックから、医師の指示に基づく専門的な医療処置、日々の服薬管理まで幅広く行います。
病状の悪化を未然に防ぎ、体調の小さな変化を早期に発見して迅速に対応することが可能になり、在宅というリラックスできる環境が、治療効果や精神的な安定にも良い影響を与えることが期待されます。
ご家族の介護負担を軽減する役割
ご家族が介護の中心的な役割を担っている場合、身体的、精神的な負担は計り知れません。特に医療的ケアが必要な場合、常に緊張感を強いられ、休息を取ることも難しくなります。
訪問看護は、専門的な知識と技術を持つ看護師が介護の一部を担うことで、ご家族の負担を直接的に軽減します。痰の吸引や経管栄養、褥瘡(床ずれ)の処置、複雑な医療機器の管理などを安心して任せることができます。
また、日々の介護方法に関する具体的なアドバイスを提供したり、介護の悩みや不安を聞いて精神的なサポートを行ったりすることも、訪問看護の重要な役割の一つです。
訪問看護が担う主な役割
- 病状の観察と健康管理
- 医師の指示に基づく医療処置
- 日常生活の支援
- 介護者であるご家族への支援
- 関係機関との連携
自立した生活を支えるための支援
訪問看護の目的は、単に医療的なケアを行い、身の回りのお世話をするだけではなく、ご本人が持つ能力を最大限に活かし、可能な限り自立した生活を送れるように多角的に支援することも大切な目的です。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門職が訪問するステーションでは、身体機能の維持・向上を目指す訓練はもちろん、日常生活動作の訓練や、コミュニケーション手段の確保、福祉用具の選定・使用方法に関する助言などの支援を行います。
ご本人の意思を何よりも尊重し、生活の中で達成したい目標を共有しながら個別性の高い支援計画を立て、チームとして共に歩んでいきます。
訪問看護の対象となる障害や疾患
訪問看護は、年齢や性別、障害の種類を問わず、病気や障害などにより居宅での支援を必要とする全ての方が対象となります。
障害を持つ方々にとっては、医療的なサポートを受けながら地域社会で自分らしく生きるための基盤となるサービスです。
身体障害を持つ方
脳卒中の後遺症による麻痺、脊髄損傷による四肢の機能不全、神経筋疾患に伴う筋力低下、事故による手足の切断など、様々な原因による身体機能の障害を持つ方が対象です。
訪問看護師は、身体の状態を専門的に評価し、床ずれの予防や処置、膀胱留置カテーテルの管理といった排泄ケア、在宅酸素療法や人工呼吸器の管理、主治医と連携したリハビリテーションの提供など、個々の状態に応じたケアを計画的に行います。
また、手すりの設置や段差の解消といったご自宅の環境整備に関するアドバイスも行い、転倒などを防ぎ安全で快適な生活空間づくりを支援します。
訪問看護の対象となる身体障害の例
| 障害の種類 | 原因となる疾患・状態の例 | 主な看護ケアの内容 |
|---|---|---|
| 肢体不自由 | 脳血管障害、脊髄損傷、筋ジストロフィー | 関節可動域訓練、褥瘡予防、排泄ケア |
| 内部障害 | 心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害 | 呼吸器管理、循環動態の観察、服薬管理、透析管理 |
| 視覚・聴覚障害 | 網膜色素変性症、メニエール病 | 服薬管理(点眼・内服)、安全な環境整備、コミュニケーション支援 |
精神障害を持つ方(精神科訪問看護)
統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、依存症などの精神疾患を持つ方も、訪問看護の対象です。特に精神科の専門知識を持つ看護師などが訪問するものを精神科訪問看護と呼びます。
地域社会で孤立しがちな方の良き理解者となり、対人関係の悩みや社会生活への不安を和らげ、症状の再発を防ぎ安定した日常生活を送れるよう支援します。
ご本人との対話を通じて信頼関係を築き、正しい服薬の管理、病状や副作用のモニタリング、生活リズムの調整、利用できる社会資源(作業所やデイケアなど)の活用に向けた相談など、多岐にわたる支援を行います。
また、ご家族からの相談に応じることも重要な役割です。
難病を抱える方
パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、脊髄小脳変性症といった、原因が不明で治療法が確立していない難病を抱える方も、訪問看護の重要な対象者です。
このような疾患は症状が多様で進行性であることが多く、専門的な知識に基づく長期的な視点でのケアプランが必要です。
訪問看護師は、症状の進行に合わせたケア内容の調整、人工呼吸器や胃ろうなどの医療機器の管理、痛みの緩和、コミュニケーションの支援、ご本人やご家族の精神的サポートなど、療養生活全般にわたって支援を提供します。
知的障害や発達障害を持つ方
知的障害や発達障害を持つ方の中には、健康管理や日常生活の様々な場面において、個別の支援を必要とする場合があり、加齢に伴う身体的な問題(生活習慣病など)や、環境の変化による二次的な精神症状を抱えるケースも少なくありません。
訪問看護では、ご本人の特性やこだわりを深く理解し、分かりやすい言葉や絵カードなどを用いてコミュニケーションを取りながら、健康管理の習慣化、服薬のサポート、金銭管理、対人関係スキルの向上などを支援します。
ご本人やご家族、相談支援専門員や就労支援機関など、関わる多くの関係機関と密に連携し、その人らしい豊かな生活が送れるようチームで支えることが大事です。
行動障害が見られる場合には、背景にある原因を探り、ご本人が安心して過ごせる環境調整を一緒に行います。
障害を持つ方が利用できる訪問看護の公的制度
障害を持つ方が訪問看護を利用する際には、主に医療保険と介護保険の二つの公的制度を活用し、どちらの保険が適用されるかは、年齢や疾患、心身の状態によって異なります。
また、保険制度と併用できる公費負担医療制度もあり、経済的な自己負担を軽減することが可能です。
医療保険の適用について
年齢にかかわらず、医師が訪問看護の必要性を認めたすべての方が医療保険で訪問看護を利用できます。
厚生労働大臣が定める疾病等の方や、精神科訪問看護を必要とする方、病状の急性増悪期にある方、退院直後で集中的な支援が必要な方などは、主に医療保険の対象です。
利用回数は原則として週3回までですが、病状が重い場合やターミナル期(終末期)など、医師が特別な指示(特別訪問看護指示書)を出した場合には、週4回以上の訪問や、毎日(最大14日間)の訪問も可能です。
自己負担割合は、年齢や所得に応じて1割から3割となります。
厚生労働大臣が定める疾病等
特定の疾病や状態にある方は、介護保険の認定を受けている場合でも、医療保険による訪問看護が優先され、利用回数の制限が緩和されるなど、より手厚いサービスを受けることが可能になります。
| 分類 | 主な疾病・状態の例 |
|---|---|
| 神経・筋疾患 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患、筋ジストロフィー |
| その他 | 末期の悪性腫瘍、人工呼吸器を使用している状態、気管カニューレを使用している状態 |
介護保険の適用について
介護保険制度では、65歳以上で市区町村から要介護・要支援認定を受けた方、または40歳から64歳で特定の16疾病により要介護・要支援認定を受けた方が対象です。
介護保険で訪問看護を利用する場合、担当のケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に沿ってサービスが提供されます。医療保険と介護保険の両方の適用条件を満たす場合は、原則として介護保険が優先されます。
ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の方は、介護保険の認定を受けていても医療保険が適用されるなど、例外もありますので注意が必要です。
介護保険の特定疾病(16種類)
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
自立支援医療制度の活用
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
いくつかの種類があり、精神疾患の治療を継続的に必要とする方が対象の精神通院医療、身体障害のある方が対象の更生医療・育成医療などがあります。
精神科訪問看護を利用する場合、自立支援医療(精神通院医療)を申請し認定されると、医療保険での自己負担額が原則1割に軽減されます。
さらに、世帯の所得に応じた月額自己負担上限額が設定されるため、経済的な負担を心配することなく、継続的な支援を受けやすくなります。申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
その他の公費負担医療制度
自立支援医療のほかにも、障害を持つ方の医療費負担を軽減する重要な制度があります。
代表的なものに、指定難病の医療費助成制度があり、認定されると医療費の自己負担割合が軽減され、また、お住まいの自治体が独自に行う心身障害者医療費助成制度(マル障など)も多くの場合利用できます。
制度を利用することで、医療保険や介護保険の自己負担分がさらに助成されたり、無料になったりする場合があります。
どの制度が利用できるかは、お持ちの障害の種類や等級、お住まいの自治体によって要件が異なりますので、市区町村の障害福祉担当窓口や、かかりつけの医療機関の医療ソーシャルワーカーなどに確認することが大切です。
訪問看護で受けられる具体的なサービス内容
訪問看護では、看護師やリハビリ専門職がご自宅を訪問し、療養生活を支えるための多岐にわたるサービスを提供します。
ご本人やご家族の希望を丁寧に伺い、主治医の指示に基づいて作成された個別の訪問看護計画に沿って、一人ひとりの状態に合わせた専門的な支援を行います。
健康状態の観察と管理
療養生活の基本は、日々の健康状態を正しく把握し、変化にいち早く気づくことです。
訪問看護師は、体温、脈拍、血圧、呼吸、酸素飽和度などのバイタルサインの測定はもちろん、病状や障害の状態、皮膚トラブルの有無、精神面の変化などを専門的な視点で注意深く観察します。
観察結果は主治医やケアマネジャーなど関係機関と密に共有し、異常の早期発見と迅速な対応につなげ、また、健康に関する不安や療養生活上の悩みの相談にも応じ、ご本人やご家族が安心して療養生活を送れるよう具体的な助言を行います。
医療的ケアと処置
主治医が発行する訪問看護指示書に基づき、ご自宅で必要とされる様々な医療的ケアや処置を実施します。病院で受けるような専門的なケアを住み慣れた環境で継続して受けられることは、在宅療養を支える上で大きな支えです。
また、在宅での看取り(ターミナルケア)も訪問看護の重要な役割で、ご本人が望む最期の時を住み慣れた家で穏やかに迎えられるよう、痛みや苦痛の緩和、精神的なケア、ご家族へのサポートなど、総合的な支援を行います。
訪問看護で提供する医療的ケアの例
| ケアの種類 | 具体例 | 目的 |
|---|---|---|
| 創傷・褥瘡の処置 | 床ずれや手術後の傷の洗浄・消毒・保護 | 感染予防、治癒促進 |
| カテーテル類の管理 | 尿道カテーテル、胃ろう、気管カニューレの管理 | 適切な機能維持、合併症予防 |
| 点滴・注射・血糖測定 | 脱水予防の点滴、インスリン注射、血糖値の管理 | 症状緩和、血糖コントロール |
| 医療機器の管理 | 在宅酸素療法、人工呼吸器、持続陽圧呼吸療法(CPAP)の管理 | 安全な機器の使用、状態のモニタリング |
日常生活の支援とリハビリテーション
食事、排泄、入浴、着替えといった日常生活の動作は、療養生活の質そのものです。
訪問看護では、身体の清潔を保つための清拭や入浴介助、シャワー浴の介助、栄養状態や嚥下機能(飲み込みの力)を考慮した食事指導、安全で尊厳を保った排泄の介助など、日常生活全般にわたる支援を行います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が在籍するステーションでは、関節の動きを維持するための運動や、起き上がり・立ち上がり・歩行といった基本動作訓練、嚥下訓練、高次脳機能障害に対するリハビリテーションなどの支援も提供します。
また、福祉用具の選定や住宅改修に関する相談・助言も行い、より安全で自立した生活環境を整えるお手伝いをします。
精神的なサポートと相談
長期にわたる療養生活は、ご本人だけでなく、支えるご家族にとっても、大きな不安やストレス、社会からの孤立感につながることがあります。
訪問看護師は、定期的な訪問を通じて信頼関係を築き、ご本人やご家族の言葉に真摯に耳を傾け、不安や悩みを共有する良き相談相手となります。
療養生活に関するアドバイスはもちろん、利用できる社会資源の情報提供や、他の専門職(医師、ケアマネジャー、相談支援専門員など)との連携調整も行い、療養生活をチームで包括的にサポートします。
障害者向け訪問看護の料金体系と自己負担額
障害を持つ方が訪問看護を利用する際の料金は、適用される保険制度(医療保険か介護保険か)によって計算方法が大きく異なり、また、各種公費負担医療制度の利用により、自己負担額を大幅に軽減できる場合があります。
医療保険利用時の料金の仕組み
医療保険で訪問看護を利用する場合、料金は国が定めた診療報酬に基づいて計算され、基本となる訪問看護基本療養費に、滞在時間や提供したサービス内容、事業所の体制に応じた各種加算が追加されます。
24時間対応体制をとっているステーションでは緊急時訪問看護加算、深夜や早朝に訪問した場合は深夜・早朝訪問看護加算、ターミナルケアを行った場合はターミナルケア加算などが算定されます。
最終的な自己負担額は、合計額に、ご自身の保険証に記載されている負担割合(1割~3割)を乗じた金額です。
医療保険利用時の自己負担額の目安(週1回・60分未満)
| 自己負担割合 | 1回あたりの料金目安 | 1ヶ月(4回)の料金目安 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 約800円~1,500円 | 約3,200円~6,000円 |
| 2割負担 | 約1,600円~3,000円 | 約6,400円~12,000円 |
| 3割負担 | 約2,400円~4,500円 | 約9,600円~18,000円 |
※上記はあくまで目安で、訪問時間や加算の有無、交通費などにより変動します。
介護保険利用時の料金の仕組み
介護保険で訪問看護を利用する場合、料金は介護報酬に基づいて計算され、サービス内容ごとに定められた「単位数」で示されます。
サービスの種別(看護師による訪問かリハビリ専門職による訪問か)や提供時間によって単位数が定められていて、1単位あたりの単価は地域によって異なり(例:10円~11.4円)、この単価に単位数を乗じて料金が計算されます。
自己負担額は、原則としてこの合計額の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)となります。ただし、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの量(支給限度額)が定められており、その範囲内でサービスを利用することが基本です。
保険適用外の費用について
訪問看護の料金には、医療保険や介護保険が適用されない自費負担分が発生することがあり、代表的なものは、訪問看護ステーションからご自宅までの交通費です。
また、サービス提供時間外の相談対応や、特別な消耗品(ガーゼや包帯など)の費用、利用者の都合による当日のキャンセル料などを別途定めている事業所もあります。
保険適用外の費用については、契約時にきちんと説明を受け、内容を理解しておくことがトラブルを防ぐ上で重要です。
訪問看護の利用を開始するまでの手順
実際に訪問看護サービスを利用したいと考えたとき、どのような手順で手続きを進めればよいのでしょうか。相談からサービス開始までにはいくつかの段階があります。
主治医やケアマネジャーへの相談
まず最初の入り口は、かかりつけの主治医や、介護保険を利用している場合は担当のケアマネジャーに「訪問看護を利用したい」と相談することです。
在宅での療養生活における困りごとや、訪問看護に期待することをできるだけ具体的に伝えましょう。訪問看護サービスを利用するためには、主治医がその必要性を認め、「訪問看護指示書」を発行することが絶対条件です。
主治医やケアマネジャーが、利用者の状況や地域性を考慮して、適した訪問看護ステーションを紹介してくれることもあります。
相談できる相手
- かかりつけの主治医
- 担当のケアマネジャー
- 入院・通院中の病院の医療ソーシャルワーカー
- 地域包括支援センター
- 市区町村の障害福祉担当窓口や保健センター
訪問看護ステーションの選択
相談先から紹介されたり、ご自身でインターネットなどで探したりして、利用したい訪問看護ステーションを選びます。
ステーションによって、精神科、小児、難病など特定の分野に強みを持っていたり、リハビリ専門職の在籍状況、24時間対応の可否などが異なり、ご自身の希望や必要なケアに対応できるステーションを選ぶことが大事です。
複数のステーションの話を聞いて、雰囲気や方針を比較検討してみましょう。
良い訪問看護ステーションを選ぶポイント
| チェックポイント | 確認する内容 |
|---|---|
| 緊急時対応 | 24時間365日、電話相談や緊急訪問に対応できる体制か |
| 専門性・実績 | 自分の疾患や障害に対応した経験が豊富か、専門資格を持つスタッフがいるか |
| 連携体制 | 主治医や他のサービス事業者と密に連携を取っているか |
契約と利用計画の作成
利用する訪問看護ステーションが決まったら、ステーションの管理者や担当者がご自宅などを訪問し、面談を行い、サービス内容や料金、緊急時の対応などについて重要事項の説明を受け、内容に同意できれば正式な契約を結びます。
その後、ご本人やご家族の意向を最優先し、主治医の指示を基に、具体的な目標や支援内容を盛り込んだ「訪問看護計画書」を作成します。計画書の内容を一緒に確認し、同意した上で、サービスが開始されます。
訪問看護の開始
契約と計画書の作成が完了したら、初回の訪問日を調整し、計画書に沿って看護師などがご自宅を訪問し、サービス開始後も、ご本人の状態の変化や新たな要望に応じて、定期的に計画の見直しを行います。
ご本人やご家族、主治医、ケアマネジャーなどと常に情報を共有し、連携を取りながら、その時々で最適なサービスを提供していきます。
よくある質問
ここでは、障害を持つ方が訪問看護の利用を検討する際によく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 一人暮らしでも利用できますか
-
問題なく利用でき、一人暮らしで障害や病気を抱える方にとって、訪問看護は地域で生活を続けるための心強い支えとなります。
定期的な訪問による健康管理はもちろん、緊急時の対応や、服薬、食事、身の回りのことに関する相談、他の介護サービスや行政サービスとの連携調整も行い、孤立を防ぎ、安心して在宅生活が送れるよう多角的にサポートします。
24時間対応のステーションと契約すれば、夜間や休日でも電話相談や緊急訪問が可能となり、万が一の体調変化の時も安心です。
- 他の介護サービスと併用できますか
-
訪問看護は、訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など、他の様々な介護保険サービスや障害福祉サービスと組み合わせて利用することが一般的です。
日中はデイサービスに通い、帰宅後の医療的ケアや入浴介助を訪問看護で受ける、といった利用が可能です。
担当のケアマネジャーや相談支援専門員が、ご本人の希望や必要性に応じて、訪問看護を含む各種サービスを組み合わせた最適なケアプランを作成します。
- 訪問看護の頻度はどのくらいですか
-
訪問の頻度は、ご本人の病状やご家族の介護状況、主治医の指示、適用される保険制度の規定などを総合的に判断して決まります。
医療保険では通常週3回までが基本ですが、病状が不安定な時期や退院直後など、医師が「特別訪問看護指示書」を発行した場合は、週4回以上、場合によっては毎日の訪問も可能です。
介護保険の場合は、ケアプランに位置づけられた範囲で、必要な回数を利用します。
- 家族が不在の時でも来てもらえますか
-
ご家族がお仕事などで日中不在にされるご家庭や、ご本人が一人暮らしの場合でも、計画した日時に訪問してケアを提供します。
ご家族が不在の時間帯に訪問することで、ご本人の安全確認や安否確認という重要な役割も果たします。
訪問時のご本人の様子や行ったケアの内容については、連絡ノートなどを活用してご家族にきちんと情報共有しますので、ご不在時でも安心してお任せください。
以上
参考文献
Naruse T, Matsumoto H, Fujisaki-Sakai M, Nagata S. Measurement of special access to home visit nursing services among Japanese disabled elderly people: using GIS and claim data. BMC Health Services Research. 2017 May 30;17(1):377.
Miyabayashi I, Washio M, Toyoshim Y, Ogino H, Hata T, Horiguchi I, Arai Y. Factors Related to Heavy Burden among Japanese Family Caregivers of Disabled Elderly with Home-Visiting Nursing Services under the Public Long-Term Care Insurance System. International Medical Journal. 2018 Jun 1;25(3).
Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.
Kim JI. A Study on Home Care and Home Visiting Nursing in Japan. Journal of Korean Community Nursing. 1999 Jun 1;10(1):106-20.
Sugisawa H, Shinoda T, Shimizu Y, Kumagai T, Sugisaki H, Ohira S. Unmet service needs evaluated by case managers among disabled patients on hemodialysis in Japan. International journal of nephrology and renovascular disease. 2018 Mar 15:113-23.
Tsutsui T, Muramatsu N. Japan’s universal long‐term care system reform of 2005: containing costs and realizing a vision. Journal of the American Geriatrics Society. 2007 Sep;55(9):1458-63.
Ogawa K. Outcomes research of home-visit nursing care in Japan. Home Health Care Management & Practice. 2006 Jun;18(4):286-92.
Taguchi A, Nagata S, Naruse T, Kuwahara Y, Yamaguchi T, Murashima S. Identification of the need for home visiting nurse: development of a new assessment tool. International Journal of Integrated Care. 2014 Mar 13;14:e008.
Naruse T, Fujisaki-Sakai M, Nagata S. Home visiting nurse service duration and factors related to institution admission. Home Health Care Management & Practice. 2017 Feb;29(1):46-52.
Ito Y, Asakura K, Sugiyama S, Takada N. Nurse–Mother Collaborations in Disability Day‐Service Centres for Individuals With Intellectual Disabilities. British Journal of Learning Disabilities. 2024 Dec 17.