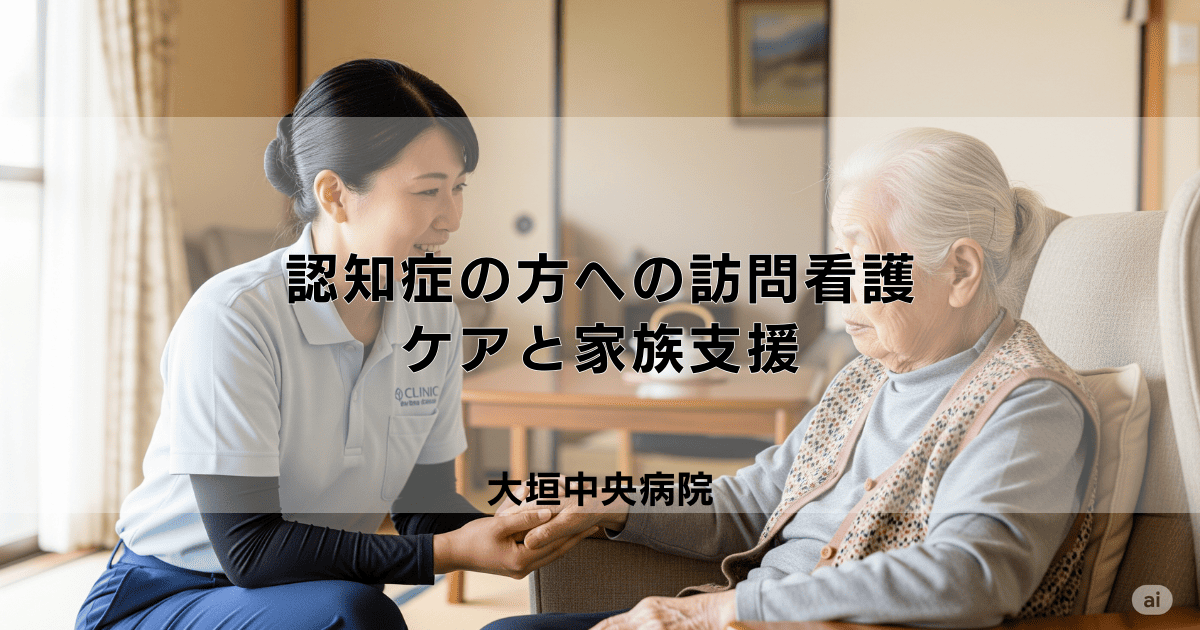認知症と診断されたご家族が、住み慣れたご自宅で穏やかに、そして安全に暮らし続けることは、ご本人とご家族双方の願いではないでしょうか。
しかし、症状の進行や日々の介護からくる負担に、大きな不安や戸惑いを感じることも少なくありません。訪問看護は、そのような状況でご本人への専門的なケアと、介護を担うご家族への支援を提供する心強い味方です。
この記事では、認知症の方への訪問看護が具体的にどのような役割を果たし、ご本人とご家族の生活の質をどのように支えるのかを、詳しく解説します。
認知症における訪問看護の役割とは
認知症の方への訪問看護は、単に医療的な処置を行うだけにとどまりません。ご本人がその人らしい生活を、可能な限り長くご自宅で維持できるよう、生活全体を包括的に支援する重要な役割を担います。
住み慣れた自宅での生活を支える
認知症の方は、環境の変化に対して非常に敏感であり、慣れない場所では混乱や不安が増大し、症状の悪化につながることがあります。
訪問看護は、ご本人が最も安心できる住み慣れた環境、つまりご自宅で、質の高い専門的なケアを受けられるようにします。看護師は、ご本人の長年の生活リズムや習慣、価値観を尊重しながら関わり、穏やかな日常生活が送れるよう支援します。
継続的な支援により、入院や施設入所を避け、愛着のある我が家での生活を続けるという、ご本人とご家族の願いを実現することが大きな目標です。
ご本人とご家族の安心感を育む
定期的な訪問は、ご本人の健康状態の微細な変化を早期に発見し、肺炎や脱水、褥瘡といった合併症の重症化を防ぐことにつながります。
また、介護を行うご家族にとっては、医療の専門知識を持つ看護師が定期的に訪れ、いつでも相談できる存在が身近にいるということが、何よりの安心です。
介護に関する日々の悩みや将来への不安を一人で抱え込まずに済むことで、精神的な負担が軽減され、より前向きに介護と向き合うための土台を築きます。
医療と介護の連携拠点
訪問看護ステーションは、在宅療養を支える様々な機関と連携する、地域のハブとしての機能も持ちます。多職種が情報を共有し、一体となって支援体制を構築します。
| 連携先 | 連携内容 | ご家族の利点 |
|---|---|---|
| 主治医 | 病状やBPSDの変化、処方薬の効果・副作用を詳細に報告し、治療方針を相談します。 | 医療的な判断が必要な際に、在宅での様子を踏まえた迅速で的確な対応が可能です。 |
| ケアマネジャー | ケアプランの目標達成度を共有し、ご本人の状態変化に応じてサービスの調整を提案します。 | 常に最適な介護サービスを、過不足なく円滑に利用できます。 |
| 薬剤師・歯科医師 | 服薬指導や口腔ケアについて専門的な助言を得て、日々のケアに反映させます。 | 薬の安全な管理や、生命に関わることもある誤嚥性肺炎の予防につながります。 |
医療機関との橋渡し役
訪問看護師は、ご本人の日々の状態を最もよく知る医療専門職として、主治医との重要な橋渡し役を務めます。
診察の短い時間だけでは伝わりにくい、ご自宅での様子や食事量、睡眠パターン、気分の変動、内服薬の効果や副作用などを、専門用語を用いて的確に主治医へ報告します。
また、ご家族が遠慮してしまったり、うまく説明できなかったりする細かな変化や懸念事項も、看護師が代弁し、整理して伝えることで、より実態に即した適切な医療判断につなげることが可能です。
ご本人への看護内容
訪問看護師は、認知症の症状だけでなく、加齢や持病に伴う全身の健康状態を総合的にアセスメント(評価)し、個々の状態に合わせたケアを計画・実行します。
日常生活の基本的な援助から、専門的な医療処置、精神的なケアまで、内容は非常に多岐にわたります。
健康状態の観察と管理
認知症の方は、痛みや息苦しさといったご自身の体調不良を的確に言葉で伝えられないことが多くあるため、看護師による専門的な観察、フィジカルアセスメントが非常に重要です。
定期的な訪問を通じて、表情や食欲、活動量の変化といったごくわずかなサインも見逃さず、病気の早期発見や重症化予防に努めます。
主な健康チェック項目
| 観察項目 | チェックする内容 | 重要性 |
|---|---|---|
| バイタルサイン | 血圧、脈拍、体温、呼吸状態、血中酸素飽和度などを測定します。 | 全身状態の基本的な指標です。継続的な測定で平常時との比較ができ、異常の早期発見につながります。 |
| 食事・水分摂取量 | 食事量や内容、水分が十分に摂れているか、むせ込みはないかなどを確認します。 | 脱水や低栄養は、せん妄や感染症のリスクを高めます。体力の維持に極めて大切です。 |
| 皮膚の状態 | 褥瘡(床ずれ)の有無、乾燥、発疹、むくみ、傷など全身の皮膚を観察します。 | 皮膚トラブルは感染症の原因や苦痛につながります。栄養状態や活動性の指標にもなります。 |
日常生活動作の援助
認知症が進行すると、これまで当たり前にできていた食事や着替え、排泄といった日常生活の動作(ADL)が難しくなることがあります。
訪問看護師は、ご本人の残された能力、つまり「できること」を最大限に活かしながら、必要な部分を支援します。
全てを介助するのではなく、ご本人が自分でできることは続けてもらうよう促し、時間がかかっても見守る姿勢を大切にすることが、ご本人の自立心を尊重し、生活への意欲を維持する上で重要な関わり方です。
内服薬の管理と指導
認知症の治療薬や高血圧、糖尿病などの持病の薬など、複数の薬を服用している方は少なくありません。薬の飲み忘れや飲み間違い、自己判断による中断は、病状の悪化に直結します。
看護師は、主治医の指示に基づき、薬を正しく服用できるよう管理し、お薬カレンダーや配薬ケースのセッティング、服薬後の体調変化の確認、副作用のモニタリングなどを行います。
ご家族へは管理方法を助言し、安全で確実な服薬体制を一緒に構築します。
身体の清潔を保つ援助
入浴や着替えを嫌がるなど、清潔を保つことが難しくなるのも認知症の症状の一つです。背景には、羞恥心や手順がわからない混乱、お湯の温度への不安など様々な理由があります。
不潔な状態は、皮膚トラブルや感染症のリスクを高めるだけでなく、ご本人の自尊心を損ない、社会的な孤立を深めることにもつながります。
看護師は、ご本人の気持ちに寄り添い、拒否の理由を探りながら、安心できる方法で清潔保持の援助を行います。
清潔ケアの内容
- 安全な環境を整えた上での入浴介助やシャワー浴の見守り
- 体力を消耗させない全身清拭(ベッド上でのケア)
- 手や足の部分浴、陰部の洗浄(陰部洗浄)
- 誤嚥性肺炎予防に直結する口腔ケア(歯磨き、義歯の手入れ、口腔内保湿)
- 整容(爪切り、ひげそり、整髪)による気分のリフレッシュ
認知症の症状に合わせた専門的ケア
認知症のケアでは、記憶障害や判断力低下といった中核症状に加えて、BPSD(行動・心理症状)と呼ばれる、ご本人にとってもご家族にとってもつらい症状への対応が大きな課題です。
訪問看護師は、認知症ケアに関する専門的な知識と技術を用いて症状を緩和し、ご本人とご家族の穏やかな生活を守ります。
BPSD(行動・心理症状)への対応
BPSDは、ご本人の不安や混乱、プライド、身体的な不快感、不適切な環境などが複雑に絡み合って現れると考えられています。
行動そのものを問題と捉えて抑え込もうとするのではなく、行動の背景にある原因やご本人のメッセージを探り、取り除くことが対応の基本です。
看護師は、ご本人の言動を丁寧に観察し、その世界観や感情を否定せず受け入れることで、安心感を提供し、症状の緩和を図ります。
BPSDの症状例と対応のポイント
| 症状の例 | 背景にある可能性 | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 徘徊 | 「家に帰りたい」「仕事に行かなくては」という思い、トイレの場所がわからない、目的や役割を探している。 | 危険がない限り行動を制止せず、安全を確保しながら一緒に歩き、気持ちを聞きます。安心できると落ち着くことがあります。 |
| 物盗られ妄想 | 置き場所を忘れたことによる不安や、それを認めたくない気持ち、身近な人への不信感。 | 話を頭から否定せず、「大変ですね、大切なものですよね」とまずは訴えを受け止め、一緒に探す姿勢を見せます。 |
| 攻撃的な言動 | 自尊心が傷つけられた、やりたいことを制止された、身体的な苦痛がある、混乱している。 | まずは距離をとり、穏やかな口調で対応します。ご本人を刺激しない静かで落ち着いた環境を整えることも大事です。 |
認知機能低下の進行を和らげる働きかけ
薬物療法と並行して、非薬物療法も認知症ケアの重要な柱です。訪問看護では、ご本人の興味や関心、これまでの生活歴や得意だったことなどを踏まえ、認知機能の維持・向上を目的とした様々な働きかけをケアの中に組み込みます。
活動は、脳に適度な刺激を与えるだけでなく、生活に楽しみや役割、達成感を見出し、ご本人の自信を回復させることにもつながります。
認知機能への働きかけの例
- 昔の写真を見ながら思い出を語り合う回想法
- 簡単な計算ドリルや漢字の書き取り
- 得意な料理や手芸、園芸などを一緒に行う作業療法
- 好きな音楽を聴いたり歌ったりする音楽療法
- 無理のない範囲での散歩や体操
安全な生活環境の整備
認知症の方は、注意力の低下や判断力の低下、加齢に伴う身体機能の衰えにより、ご自宅内での転倒や火傷、誤飲といった事故のリスクが高いです。
看護師は、ご自宅の中の危険な箇所を専門家の視点で評価し、ご家族と共に安全な環境づくりを進めます。
手すりの設置や段差の解消、照明の調整といったハード面の改善提案に加え、福祉用具の活用や生活動線の工夫など、ソフト面の助言も行います。
ご家族への支援と負担軽減策
認知症の方を在宅で介護するご家族の負担は、身体的なものだけでなく、精神的、時間的、経済的なものまで多岐にわたります。訪問看護は、ご本人のケアと全く同じ重みで、ご家族を支えることも極めて重要な役割と考えています。
介護に関する相談と助言
日々の介護で生じる様々な疑問や「これでいいのだろうか」という悩みに対し、看護師が専門的な視点から具体的なアドバイスをします。
効果的なオムツの当て方や皮膚トラブルの予防、食事形態の工夫、BPSDへの対応方法など、すぐに実践できる知識や技術を提供することで、介護の負担軽減を図ります。
「いつでも聞ける専門家」がいることは、ご家族の大きな力です。
精神的なサポートと傾聴
介護による慢性的なストレスや、症状の進行に対する不安、社会からの孤立感などから、ご家族が精神的に追い詰められてしまうケースは少なくありません。
訪問看護師は、ご家族の話にじっくりと耳を傾け、その苦労や葛藤、誰にも言えない複雑な感情に共感し、気持ちを受け止め、評価や批判をせずただ聴いてもらえるだけで、心が軽くなることがあります。
ご家族への精神的サポート
| サポート内容 | 具体的な関わり | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 傾聴と共感 | ご家族の言葉を遮らず、思いや感情、時には愚痴もそのまま受け止めます。 | カタルシス効果(話すことによる解放感)や、理解者がいるという安心感を得られます。 |
| 情報提供 | 公的な制度や地域のサービス、家族会など、役立つ社会資源の情報を提供します。 | 利用できる支援を知ることで、介護の選択肢が広がり、精神的な余裕が生まれます。 |
| 労いと承認 | 日々の介護の努力や工夫を具体的に認め、労いの言葉をかけます。 | 自己肯定感が高まり、「自分は一人ではない」と感じ、介護への意欲を維持しやすくなります。 |
介護負担を軽くするための具体的な提案
看護師は、ご家族の介護負担の状況を客観的に評価し、負担を軽減するための方法を一緒に考えます。
介護保険で利用できる他のサービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護など)の活用を積極的に提案し、ご家族が介護から離れて休息を取れる時間(レスパイト)を確保できるよう働きかけます。
提案により、介護者が自分のための時間を持つことは、心身のリフレッシュとなり、結果としてより良い介護につながるため、共倒れを防ぐ上で非常に重要です。
緊急時の対応方法の共有
ご本人の容体が急に変化した際に、ご家族がパニックにならず、落ち着いて行動できるよう、緊急時の対応方法をあらかじめ具体的に共有しておきます。
「こういう状態になったら、まずここに電話してください」といった明確なルールを決めておくことで、いざという時の不安を和らげます。
緊急連絡体制の整備
- 24時間対応の訪問看護ステーションの緊急連絡先
- 主治医のいる医療機関の夜間・休日の連絡先
- 救急車を呼ぶべき症状の具体的な判断基準(意識がない、呼吸が苦しそうなど)
- かかりつけ薬局の連絡先
訪問看護導入までの流れと費用
実際に訪問看護を利用したいと考えた場合、どのような手続きが必要で、どのくらいの費用がかかるのかは、誰もが気になる点だと思います。
ここでは、サービス開始までの一般的な流れと、費用の仕組みについて、分かりやすく説明します。
ご相談からサービス開始まで
訪問看護の利用は、原則として主治医からの訪問看護指示書が必要です。まずは、かかりつけの主治医や担当のケアマネジャー、または直接お近くの訪問看護ステーションにご相談いただくことから始まります。
サービス開始までの標準的な流れ
| 段階 | 内容 | 主な関係者 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センター、訪問看護ステーションなどに利用を相談します。 | ご本人、ご家族 |
| 2. 指示書の依頼 | 相談先と連携し、主治医に訪問看護の必要性を判断してもらい、指示書を作成してもらいます。 | 主治医、看護師、ケアマネジャー |
| 3. 事前面談・契約 | 訪問看護ステーションの担当者がご自宅を訪問し、サービス内容や料金を詳しく説明の上、契約を結びます。 | ご本人、ご家族、訪問看護師 |
| 4. サービス開始 | ケアプランと訪問看護計画書に基づき、看護師による定期的な訪問看護が始まります。 | 訪問看護師 |
訪問看護で利用できる保険制度
訪問看護は、主に介護保険または医療保険を使って利用し、どちらの保険が適用されるかは、ご本人の年齢や病状、要介護認定の有無によって決まります。
65歳以上で要介護認定を受けている方は原則として介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める特定の疾病(末期がん、パーキンソン病関連疾患など)がある場合や、病状の急性増悪期、精神科訪問看護などでは医療保険が適用されます。
保険適用時の費用目安
費用は、利用する保険の種類、訪問時間、提供されるサービス内容によって異なり、以下は、介護保険を利用した場合の自己負担額の目安です。
所得に応じて負担割合(1割~3割)が変わります。正確な料金については、契約時に訪問看護ステーションから書面で詳しく説明します。
介護保険利用時の費用目安(1割負担の場合)
| 訪問時間 | 1回あたりの自己負担額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 20分未満 | 約320円 | 緊急時や短時間の処置など |
| 30分以上1時間未満 | 約840円 | 全身状態の観察やケアで最も多い時間区分 |
| 1時間以上1時間半未満 | 約1,150円 | 入浴介助など、時間を要するケアの場合 |
※上記は基本料金であり、早朝・夜間・深夜の訪問や緊急時訪問、24時間対応体制の契約、複数名での訪問などには別途加算料金がかかります。
訪問看護と他の介護サービスとの連携
在宅療養を成功させるためには、訪問看護という一つのサービスだけで完結するのではなく、様々な介護サービスが連携し、多職種によるチームとしてご本人とご家族を支える体制を築くことが大切です。
ケアマネジャーとの情報共有
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、ご本人やご家族の希望に沿って、最適な介護サービスの組み合わせを計画する、在宅介護の司令塔です。
訪問看護師は、ご本人の心身の状態やBPSDの変化、ご家族の介護力の状況などをケアマネジャーと密に共有し、ケアプランが常に実態に即した最適なものになるよう協力して見直しを行います。
デイサービスやショートステイとの連携
デイサービスやショートステイなどの施設系サービスも、ご本人の社会参加やご家族のレスパイト(休息)のために欠かせない、在宅生活を支える重要な社会資源です。
訪問看護師は施設の職員と連絡を取り合い、連絡ノートなどを活用してご本人の情報を共有します。ご自宅での様子や注意点を施設に伝えたり、施設での日中の様子を伺ったりすることで、生活の場が変わっても一貫性のあるケアを提供できます。
主な連携介護サービス
- 居宅介護支援(ケアマネジャー)
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与・販売、住宅改修
地域の支援機関との協力体制
より広い視点でご本人とご家族を支えるため、行政や医療機関、地域の様々な機関とも連携します。それぞれの専門性を活かした協力体制を築くことで、医療・介護・福祉の垣根を越えた、多角的で切れ目のない支援が可能です。
連携する地域の支援機関
| 機関名 | 主な役割 | 連携による利点 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 高齢者に関する総合相談窓口。権利擁護や虐待防止、介護予防なども担います。 | 公的な支援や制度に関する包括的な情報を得られ、適切なサービスにつなげてもらえます。 |
| 認知症疾患医療センター | 認知症の鑑別診断や専門的な治療、BPSDへの対応、専門医療相談などを行います。 | 診断が難しいケースや、対応困難な症状について高度な医療的判断や専門的助言を受けられます。 |
| 地域の家族会 | 同じ立場の介護者同士が交流し、悩みを分かち合い、情報交換する自主的な集まりの場です。 | 精神的な支えや共感を得られるだけでなく、実践的な介護のヒントや地域情報を得られます。 |
よくある質問
ここでは、訪問看護の利用を検討されている方からよく寄せられる質問と回答を、まとめました。
- どのくらいの頻度で来てもらえますか?
-
訪問の頻度は、画一的に決まるものではなく、ご本人の病状やご家族の介護状況、主治医の指示、ケアプランに基づいて個別に決定します。
退院直後や病状が不安定な時期は訪問回数を週3回以上に増やし、状態が安定してきたら週1回に減らすなど、状況に応じて柔軟に対応します。
訪問頻度の目安
状態 頻度の目安(介護保険の場合) 状態が安定している 週に1~2回程度 医療的な処置やBPSD対応が必要 週に3回以上、または複数サービスの組み合わせ 終末期(ターミナルケア) 医療保険に切り替わり、毎日の訪問も可能です - 家族が留守中でも訪問は可能ですか?
-
事前にご本人やご家族と相談し、同意を得た上で、安全が確保できると判断された場合には、ご家族が不在の時間帯に訪問し、ケアを提供します。
お仕事などで日中ご自宅を空ける必要があるご家族も、安心してサービスを利用でき、訪問後には、看護記録や連絡ノートでその日のご様子やケア内容を必ず報告します。
- 主治医がいない場合でも利用できますか?
-
訪問看護の開始には、法律上、医師が発行する訪問看護指示書が必ず必要です。かかりつけの主治医がいない場合は、まず医療機関を受診していただく必要があります。
どの医療機関にかかればよいか分からない場合は、地域包括支援センターや当ステーションにご相談いただければ、地域の医療機関の情報提供や受診の調整をお手伝いすることも可能です。
- 認知症の進行度に関わらず利用できますか?
-
訪問看護は、物忘れが気になり始めたような認知症の初期段階から、医療的なケアが必要となる終末期まで、あらゆる段階で必要とされる支援を提供します。進行度に合わせて、ケアの目的や内容を調整していきます。
初期では進行予防や不安の軽減、中期ではBPSDの緩和や生活支援、後期では安楽なケアや看取りの支援が中心です。
以上
参考文献
Tsuda S, Ono M, Nakajima T, Ito K. Supporting Independent Living Among Individuals With Dementia Who Live Alone: A Qualitative Study With Home‐Visit Nurses. Journal of Advanced Nursing. 2025 Jun 30.
Schreiner AS, Yamamoto E, Shiotani H. Agitated behavior in elderly nursing home residents with dementia in Japan. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2000 May 1;55(3):P180-7.
Okamura H, Ishii S, Ishii T, Eboshida A. Prevalence of dementia in Japan: a systematic review. Dementia and geriatric cognitive disorders. 2013 Jul 13;36(1-2):111-8.
Kobayashi S, YAMAMOTO‐MITANI N, Nagata S, Murashima S. End‐of‐life care for older adults with dementia living in group homes in Japan. Japan Journal of Nursing Science. 2008 Jun;5(1):31-40.
Doyle C, Setoya N, Goeman D, Kayama M. The role of home nursing visits in supporting people living with dementia in Japan and Australia: cross-national learnings and future system reform. Health Systems & Reform. 2017 Jul 3;3(3):203-13.
Kitamura T, Tanimoto C, Oe S, Kitamura M, Hino S. Familial caregivers’ experiences with home‐visit nursing for persons with dementia who live alone. Psychogeriatrics. 2019 Jan;19(1):3-9.
Schreiner AS. Aggressive behaviors among demented nursing home residents in Japan. International journal of geriatric psychiatry. 2001 Feb;16(2):209-15.
Murashima S, Nagata S, Magilvy JK, Fukui S, Kayama M. Home care nursing in Japan: a challenge for providing good care at home. Public health nursing. 2002 Mar;19(2):94-103.
Nakanishi M, Nakashima T, Sawamura K. Quality of life of residents with dementia in a group-living situation An approach to creating small, homelike environments in traditional nursing homes in Japan. Nihon Koshu Eisei Zasshi (JAPANESE JOURNAL OF PUBLIC HEALTH). 2012;59(1):3-10.
Okumura A, Yamamoto-Mitani N, Kobayashi S, Okamoto Y, Fukahori H. P2‐043: Dementia homecare nursing in Japan: A descriptive study. Alzheimer’s & Dementia. 2010 Jul;6:S325-.