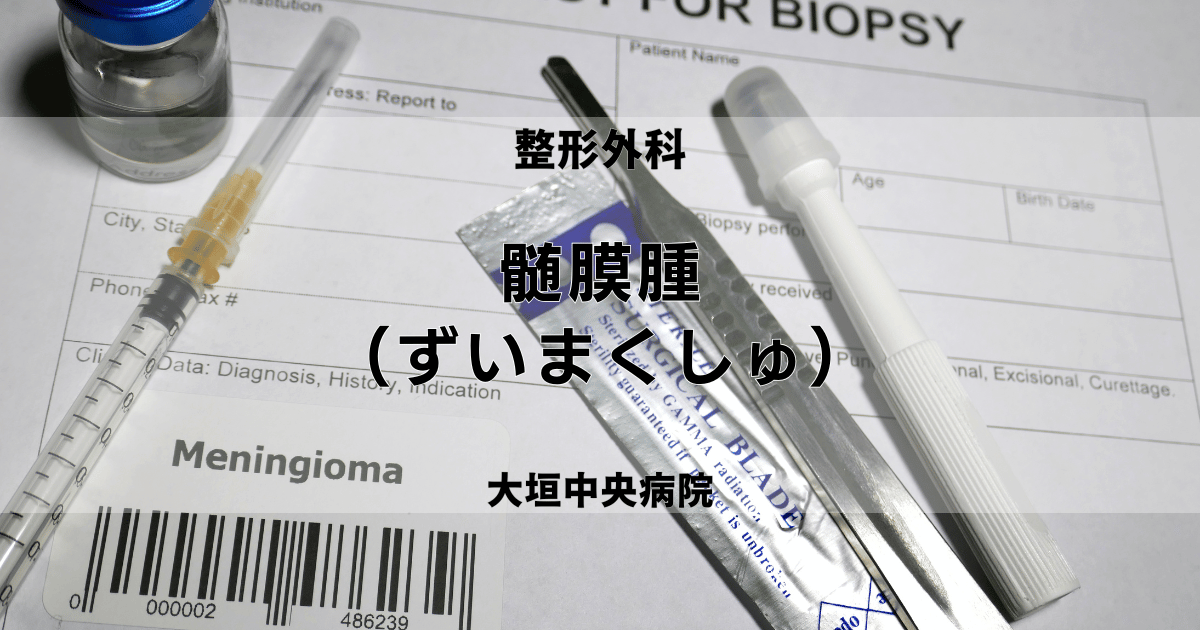髄膜腫(ずいまくしゅ、Meningioma)とは、脳や脊髄を包む髄膜から発生する腫瘍の一つです。
多くは良性ですが、頭蓋内圧の上昇や神経圧迫などによって日常生活に影響を及ぼすおそれがあり、早期の検査と治療が重要です。
また、一部は画像検査で偶発的に見つかる場合もあります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
髄膜腫の病型
髄膜腫(ずいまくしゅ)は、WHO(世界保健機関)の中枢神経腫瘍分類で組織学的サブタイプと悪性度グレードによって分類されます。
組織学的には約15種類の亜型(meningioma type)が定義され、2021年のWHO分類改訂では用語が整理されローマ数字表記がアラビア数字に変更されました。
WHOグレードは 1(良性)、2(中間悪性)、3(悪性) の3段階で、約80%がグレード1、18%がグレード2、2%がグレード3 と報告されています。
グレード判定基準には組織学的所見に加え、2021年より分子学的所見も一部組み込まれました。
例えば、TERTプロモーター変異やCDKN2A/Bのホモ欠失が認められる髄膜腫は、形態が良性でも自動的にグレード3と分類されます。
このような分類により治療方針や予後予測を立てます。
- グレードⅠ
- 核分裂像が少なく、壊死や浸潤がありません。組織亜型としては髄膜上皮型、遷移型、砂粒体型などがあります。再発リスクは比較的少なく、10年再発率は7~25%です。
- グレードⅡ
- 核分裂像が中等度であったり、脳実質への浸潤があったりするものはグレードⅡに該当します。組織亜型としては異型性髄膜腫などがあります。10年再発率は29~52%程度と中程度です。
- グレードⅢ
- 顕著は異型を呈し、核分裂像は多数で壊死を伴います。組織亜型としては悪性髄膜腫、乳頭型、リボイド型などがあります。再発率も高いです。
髄膜腫の症状
髄膜腫(ずいまくしゅ)の症状は腫瘍の発生部位と大きさに依存し、徐々に進行するのが典型です。
小さく無症状のうちは偶然のMRI検査で見つかるケースも多く、症状出現時にはかなり大きくなっている場合もあります。
腫瘍による脳圧迫や頭蓋内圧亢進により頭痛が生じたり、皮質の刺激でてんかん発作(けいれん)が起こったりするのが一般症状です。
髄膜腫は発生部位によって多彩な神経症状を呈しますが、症状が非特異的(例:頭痛や認知変化のみ)なことも多く、画像検査を行うまで診断がつかない場合もあります。
無症状で経過する髄膜腫も少なくなく、そのような偶発腫瘍(incidentaloma)は経過中4~5%が症状出現に至るとのメタ解析報告もあります。
以下に部位ごとの代表的な症状を示します。
大脳表面/凸面(脳回)付近
対側の手足の筋力低下や麻痺(運動野圧迫)が起こり、けいれん発作もしばしば見られます。
頭頂部中央(矢状静脈洞傍)では、とくに脚の麻痺が出やすいです。
前頭葉・嗅窩溝領域
人格変化・判断力低下・記憶障害などの前頭葉症状があらわれます。
嗅神経圧迫で嗅覚消失(片側の臭いが分からない)を来すこともあり、フォスター・ケネディ症候群(患側視神経萎縮と対側乳頭浮腫)を呈する例もあります。
鞍上部・傍鞍部(トルコ鞍近傍)
視交叉圧迫による視野欠損(両耳側の視野が欠ける)や視力低下、下垂体機能低下などがあらわれます。
蝶形骨翼・海綿静脈洞
動眼神経・滑車神経・三叉神経・外転神経といった脳神経麻痺(眼球運動障害、顔面知覚障害など)が生じます。
眼窩上部に及ぶと眼球突出を来す場合もあります。
小脳橋角部・錐体骨峰部
顔面神経麻痺や聴神経障害(難聴)、三叉神経痛、小脳失調(ふらつき)、嚥下障害、声音障害など(脳幹・小脳圧迫や下位脳神経群の障害)が生じます。
後頭蓋窩・大孔周囲
延髄圧迫による球麻痺症状(嚥下・発声障害)や頸部痛、上下肢の麻痺、呼吸循環障害など重篤な症状を呈し得ます。
脳室内髄膜腫
脳室を塞いで閉塞性水頭症となり、頭痛・嘔気、意識障害、乳頭浮腫など高ICP症状が急速に出現する場合があります。
脊髄髄膜腫
背部痛や神経根痛(患部レベルの神経根圧迫による痛み)、進行すると脊髄圧迫による運動麻痺や知覚障害、膀胱直腸障害などが生じます。
頸髄では四肢麻痺、胸髄以下では下肢の痙性麻痺など上位運動ニューロン徴候、馬尾神経付近では弛緩性麻痺など下位運動ニューロン症状があらわれます。
髄膜腫の原因
髄膜腫(ずいまくしゅ)の発生要因として代表的なのは年齢・性別・放射線被曝・遺伝的素因などです。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 遺伝的素因 | NF2など一部の遺伝性疾患が関係する |
| 過去の放射線治療 | 高線量の放射線照射を頭部に受けた経験 |
| 女性ホルモンの影響 | エストロゲン受容体との関連が示唆される |
遺伝的要因と関連疾患
一部の髄膜腫は遺伝的素因が関与する可能性があり、家族性に髄膜腫の素因を持つ疾患がいくつか知られています。
最も有名なのが神経線維腫症2型 (NF2)で、この疾患患者の45~58%に頭蓋内髄膜腫、約20%に脊髄髄膜腫が発生すると報告されています。
NF2遺伝子はMerlinという腫瘍抑制蛋白をコードしており、その変異により髄膜腫発生が促進されると考えられます。
NF2以外にも、髄膜腫の発症素因となりうる遺伝疾患として基底細胞母斑症候群(ゴーリン症候群)、多発性内分泌腫瘍症1型 (MEN1)、Cowden症候群、Werner症候群、BAP1腫瘍性素因症候群、ルービンスタイン・テイビ症候群などが挙げられます。
しかし、これらはまれな遺伝疾であり、実際の髄膜腫患者の大部分は散発性(家族歴や明確な遺伝要因を持たない)です。
放射線被曝との関連
電離放射線は髄膜腫発症の明確な危険因子です。
幼少期に頭部放射線治療を受けた集団の追跡調査で、髄膜腫発症リスクが約9.5倍に増加した報告があります。
例えば、イスラエルで1948~1960年に頭部の皮膚疾患(頭部白癬)治療として低線量X線照射を受けた児童では、その後の髄膜腫発生が対照より大幅に増加しました。
また、小児期に放射線診断(頭部CTや度重なる歯科X線)の被曝を受けた群でも将来のリスク上昇が示唆されています。
放射線誘発髄膜腫(radiation-induced meningioma, RIM)は一般に多発しやすく、組織学的にも異型~悪性が多く再発率が高いことが知られています。
分子レベルでも、自発性(散発性)髄膜腫とは異なる特徴が報告され、RIMではNF2遺伝子の不活化が少ない一方で1番染色体pや22qの欠失、サイクリンD1やp16の多型との相互作用などが指摘されています。
ホルモンバランスや性別の影響
女性に髄膜腫が多いことや、妊娠中に髄膜腫が増大する症例があることから、女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)との関連が指摘されています。
35~44歳で女性の発症率が男性の約3.15倍に達し、女性ホルモンの影響が示唆されます。
髄膜腫組織ではエストロゲン受容体やプロゲステロン受容体が発現していることが多く、月経周期や妊娠によるホルモン変動が腫瘍増殖に影響しうると考えられています。
さらに外因性ホルモンとして、一部の黄体ホルモン製剤(プロゲスチン)の長期使用と髄膜腫発生リスク増加が報告されました。
髄膜腫の検査・チェック方法
髄膜腫(ずいまくしゅ)を診断するときは、画像検査と神経学的検査を組み合わせて総合的に評価します。
画像検査(CT・MRI・造影検査)
髄膜腫を含む脳腫瘍の診断にはCTやMRIが重要です。
腫瘍の存在、形状、周囲組織への圧迫状況などを確認して治療計画を立案します。
CT検査
短時間で撮影でき、石灰化や骨変化の評価に有用で、髄膜腫に特徴的な頭蓋骨の肥厚(過形成)や腫瘍石灰化が確認できます。
MRI検査
軟部組織の描出に優れ、腫瘍の境界や硬膜との付着部位を詳細に確認できます。
MRI造影検査
造影剤を使うことで腫瘍の血流や脳血管との関係をより明確に把握できます。
典型的には、脳表面に接する硬膜に沿った均一に造影増強される腫瘤として描出され、周囲硬膜が線状に肥厚・増強される「硬膜テイルサイン(dural tail)」が約60~70%の症例で認められます。
- T1強調画像:腫瘍の信号強度、境界の明瞭さ
- T2強調画像:腫瘍内の水分量や浮腫の程度
- 造影T1強調画像:腫瘍の増強効果、硬膜付着部位の特徴
- 周辺構造との関係:血管や神経束への圧迫状況
神経学的検査
患者の筋力、感覚、反射、眼球運動、言語機能などを評価して、腫瘍が脳や脊髄のどの領域に影響を及ぼしているかを把握します。
とくに運動麻痺や視野欠損などがある場合は、病変部位と症状の関連がわかりやすくなります。
バイオマーカー検査
腫瘍マーカーの測定が標準的に行われるケースは少ないですが、一部の特殊な髄膜腫ではホルモン受容体の検査などを検討します。
今後、研究が進むことで治療方針の決定に役立つバイオマーカーが見つかる可能性があります。
病理組織学的検査
最終診断の確定には病理組織検査が不可欠です。
画像所見で髄膜腫が強く示唆され、無症状であれば経過観察となるケースもありますが、治療介入する場合は手術や生検で得た組織の病理組織学的検査を行います。
髄膜腫の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
髄膜腫(ずいまくしゅ)の治療方法は、腫瘍のサイズ、位置、悪性度、患者の全身状態などを総合的に判断して決定します。
経過観察や手術、放射線治療のほか、場合によっては薬物療法が必要です。
経過観察
無症状かつサイズが小さい良性髄膜腫では、定期的な画像フォローで経過をみる場合があります。例えば、6~12か月ごとにMRI検査を行い、腫瘍径の変化や新規症状の出現を監視します。
欧州のガイドライン(EANO 2021)でも、無症状のグレード1髄膜腫に対してはまず経過観察を推奨しています。
長期間安定していればフォロー間隔を延長しますが、腫瘍が増大したり症状が出現したりした場合は治療介入を検討します。
とくに若年者では将来的な増大リスクがあるため注意深いフォローが必要です。
手術療法(外科的切除)
髄膜腫治療の中心になるのが手術で、腫瘍の位置や周囲の血管、神経を考慮しながら、安全に腫瘍を切除します。
できるだけ腫瘍を完全切除して再発リスクを下げるのが理想ですが、重要な神経や血管と密着していると腫瘍の一部を残す場合もあります。
- 全摘出:再発リスクが低くなるメリットがある
- 部分切除:神経機能を温存しつつ、リスクを最小限に抑える方針
放射線治療
手術の補助や再発リスクを下げる目的で放射線治療を行う場合があります。
残存腫瘍が少量のときや、高齢や合併症などで手術のリスクが高いと判断されるときに放射線治療を選択するケースもあります。
- 外部照射:高エネルギーの放射線を腫瘍部位に照射して腫瘍細胞の増殖を抑える
- 定位放射線治療:ガンマナイフやサイバーナイフなどで精密に腫瘍を狙う方法で、正常組織へのダメージを軽減しやすい
薬物療法とホルモン療法
髄膜腫に対する化学療法の効果は限定的ですが、悪性度が高い場合や再発を繰り返す場合に試みることがあります。
ただし、化学療法はあくまでも補助的な位置づけであるケースが多いです。
リハビリテーションと治療期間の目安
手術後や放射線治療後には、運動機能や認知機能の回復を目的としたリハビリテーションが重要です。
理学療法士や作業療法士が個別のプログラムを組み、患者が日常生活を送りやすいようサポートします。
| リハビリ内容 | 目的 |
|---|---|
| 理学療法 | 筋力やバランス感覚の向上 |
| 作業療法 | 日常生活動作の獲得や社会復帰支援 |
| 言語療法 | 会話能力や嚥下機能の改善 |
| 認知リハビリ | 注意力・記憶力・判断力の改善 |
治療期間は腫瘍の状態によって大きく変わります。
- 手術後の入院期間:2~4週間程度が多い
- 放射線治療:数週間にわたって通院する場合が一般的
- リハビリテーション:数か月から半年以上行うケースもある
薬の副作用や治療のデメリット
髄膜腫(ずいまくしゅ)の治療法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。副作用や合併症のリスクを理解しておくと、治療中のトラブルを早期に発見できます。
手術のリスクと合併症
外科的手術では頭蓋内にアプローチするため、手術中や術後に何らかの合併症が起こる可能性があります。
- 脳内出血:出血部位によっては症状が重くなる場合がある
- 感染:脳や髄膜への感染リスクがある
- 脳浮腫:腫瘍を切除した部位周辺で脳浮腫が起こりやすい
- 神経損傷:微細な神経を損傷すると運動麻痺や感覚障害が生じる可能性がある
放射線治療の副作用
放射線治療は正常組織にも一定のダメージが及ぶため、頭皮の脱毛や炎症などの副作用が起こるおそれがあります。
ただし、定位放射線治療の導入によって、被ばく範囲を狭められる場合が増えています。
- 頭皮の脱毛:照射部位に限定的に発生する
- 頭皮の炎症や皮膚の色素沈着
- 放射線性脳壊死:まれだが後遺症を伴うケースがある
- 全身倦怠感:治療中から治療後しばらく続く場合がある
化学療法やホルモン療法の副作用
化学療法薬を使うと、吐き気や嘔吐、脱毛などが生じるおそれがあります。
また、ホルモン療法を行うと、ホルモンバランスが崩れて倦怠感や体重変化などが出現するケースがあります。
いずれも主治医や薬剤師と相談しながら副作用対策を検討します。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
髄膜腫(ずいまくしゅ)の治療は、保険適用の範囲内で行えるケースがほとんどです。
手術や放射線治療だけではなく、一部の化学療法薬やリハビリテーションも健康保険の対象となります。
ただし、先進医療や自由診療にあたる治療法を選択した場合は、自費負担が大きくなる可能性があります。
手術費用の目安
健康保険が適用される通常の脳神経外科手術では、入院費や手術費、薬剤費を含めると数十万円の自己負担が発生します。
- 手術費用:保険適用後の自己負担は20万~50万円程度
- 入院期間:2~4週間で入院費が加算される
放射線治療や化学療法の費用
放射線治療は、外部照射の場合1回あたり数千円~1万円程度が目安です。
定位放射線治療(ガンマナイフなど)の場合は機器の利用料も含まれるため、やや高額になりますが、基本的には健康保険の対象となります。
化学療法薬の費用も保険がきく場合は自己負担が3割程度です(年齢や所得によって1割~3割に変動)。
リハビリテーションや通院費
退院後のリハビリテーションにも健康保険が適用されますが、一定期間が過ぎると介護保険でのリハビリに切り替わる場合があります。
通院が必要になると交通費も考慮する必要があり、遠方の場合は宿泊費を含めて計画を立てることが大切です。
以上
参考文献
BI, Wenya Linda, et al. Meningioma genomics: diagnostic, prognostic, and therapeutic applications. Frontiers in surgery, 2016, 3: 40.
MAROSI, Christine, et al. Meningioma. Critical reviews in oncology/hematology, 2008, 67.2: 153-171.
FATHI, Ali-Reza; ROELCKE, Ulrich. Meningioma. Current neurology and neuroscience reports, 2013, 13: 1-8.
WIEMELS, Joseph; WRENSCH, Margaret; CLAUS, Elizabeth B. Epidemiology and etiology of meningioma. Journal of neuro-oncology, 2010, 99: 307-314.
APRA, Caroline; PEYRE, Matthieu; KALAMARIDES, Michel. Current treatment options for meningioma. Expert review of neurotherapeutics, 2018, 18.3: 241-249.
COMMINS, Deborah L.; ATKINSON, Roscoe D.; BURNETT, Margaret E. Review of meningioma histopathology. Neurosurgical focus, 2007, 23.4: E3.
ATHER ENAM, S., et al. Metastasis in meningioma. Acta neurochirurgica, 1996, 138: 1172-1178.
ROHRINGER, Martin, et al. Incidence and clinicopathological features of meningioma. Journal of neurosurgery, 1989, 71.5: 665-672.
LAMSZUS, Katrin. Meningioma pathology, genetics, and biology. Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, 2004, 63.4: 275-286.
HUNTOON, Kristin; TOLAND, Angus Martin Shaw; DAHIYA, Sonika. Meningioma: a review of clinicopathological and molecular aspects. Frontiers in oncology, 2020, 10: 579599.
SALONER, D., et al. Modern meningioma imaging techniques. Journal of neuro-oncology, 2010, 99: 333-340.