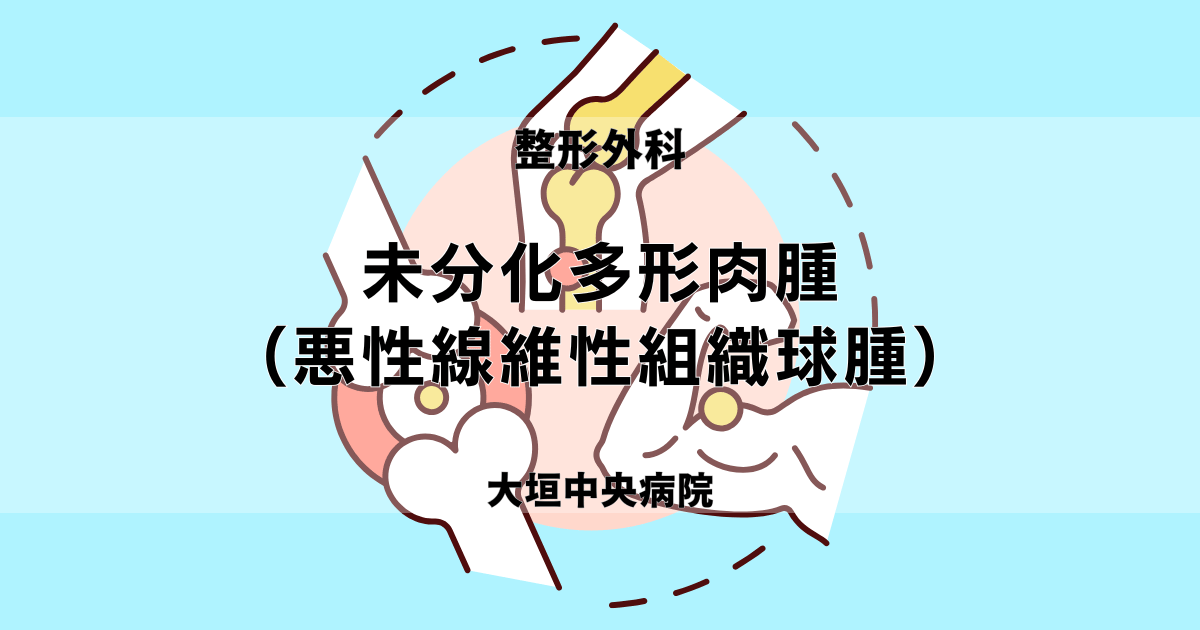未分化多形肉腫( Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma, UPS)とは、主に筋肉や脂肪などの軟部組織に発生するがんの一種です。
以前は「悪性線維性組織球腫」と呼ばれていましたが、細胞の由来が明確でない「未分化」な腫瘍という特徴があるため、「未分化多形肉腫」の名称が使われるようになりました。
四肢や体幹など幅広い場所に発症し、初期は痛みや腫れなど自覚症状が乏しいために発見が遅れやすいとされています。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
未分化多形肉腫(悪性線維性組織球腫)の病型
UPSは、最新のWHO分類(2020年)において「未分化/分類不能肉腫」のカテゴリに含まれる腫瘍です。
かつて用いられていた「MFH(悪性線維性組織球腫)」という診断名は、2013年のWHO分類で正式に廃止され、免疫組織化学や遺伝学的検査で他の型に特定できない高悪性度肉腫をUPSと呼ぶようになりました。
UPS自体は形態学的な多様性を示し、以下のような組織学的バリエーションが知られます。
最も一般的なタイプで、紡錘形細胞が渦巻き(storiform)状の配列を示す典型的UPSです。UPS症例の約50~60%を占めます。
腫瘍組織にリンパ球やマクロファージなどの炎症細胞浸潤が強く、発熱や体重減少など全身性炎症症状を呈する場合があります。
多数の多核巨細胞(破骨細胞様巨細胞)を含むタイプです。
高度な粘液変性を伴うタイプですが、現在では粘液線維肉腫(myxofibrosarcoma)として別個の分類に分けられることが多いです。
かつてMFHの亜型とされた血管肉腫様(angiomatoid)型は、現在は血管肉腫様線維組織球腫(angiomatoid fibrous histiocytomaとして若年者に発生する中低悪性度腫瘍※1に分類され、UPSとは異なる疾患とみなされています。(※血管肉腫様線維組織球腫は小児~若年者に好発する特殊型で、UPSとは臨床経過が異なります。)
※1中低悪性度腫瘍:「低悪性度」に分類されるが、その中でも「中悪性度」に近い、あるいは両者の中間的な特性を持つもの。
このように、UPSは「未分化」という名称の通り、顕微鏡下で特徴的な分化像を示さないため、診断は除外診断(他の肉腫や癌をすべて否定した上での診断)となります。
したがって、病理診断の際には免疫染色や分子検査で他の腫瘍(平滑筋肉腫、脂肪肉腫、悪性黒色腫、癌肉など)の除外が重要となります。
未分化多形肉腫(悪性線維性組織球腫)の症状
未分化多形肉腫は、腫瘍の進行度や発症部位によって症状が異なります。
初期段階ではほとんど痛みがないケースもあり、単なる「しこり」や「筋肉の張り」として見過ごされるケースがあります。
自分の体の変化に気づきにくい一方で、腫瘍が大きくなると周囲の組織を圧迫し、さまざまな症状が現れます。
ここでは具体的な症状について解説します。
初期症状:無痛性の腫瘤
未分化多形肉腫は発生したばかりの頃、無痛性の腫瘤として触れる場合があります。
日常生活で大きく支障をきたさない場合、放置されがちなため、腫瘤が大きくなってから受診するケースも珍しくありません。
| 初期段階で気づかれやすい身体のサイン | 内容 |
|---|---|
| 筋肉の張り感 | 腫瘍が筋肉内にある場合、運動時に違和感を覚えることがある |
| 部分的なむくみ | 腫瘍の成長により血流が滞り、局所的に腫れる感覚 |
| 軽度の痛みや違和感 | しこりを押したときにかすかな痛みを感じる場合がある |
| 局所的な熱感や赤み | 腫瘍の周囲で炎症反応が起きる場合 |
進行時症状:痛みと機能障害
腫瘍が大きくなると、周囲の神経や筋肉、血管などを圧迫します。
そのため、痛みやしびれが出る場合があります。
四肢の場合、神経障害により動かしづらさや感覚鈍麻が生じ、日常生活に支障をきたします。腫瘍部位に痛みがあって眠れない、歩行時に強い痛みが出るなどの段階まで進むと、かなり進行している可能性が高いです。
全身症状
大きな腫瘍が形成されると、体が慢性的に炎症や負荷を受けるため、倦怠感や食欲不振、体重減少などの症状を伴う場合があります。
これらの全身症状は病期がさらに進んだ状態で見られるケースも多いです。
炎症性UPSではサイトカイン産生※2により発熱などの全身症状を呈すると報告されています。
※2サイトカイン産生:細胞がサイトカインと呼ばれる生理活性タンパク質を作り出して、細胞の外に放出する動き。細胞間の情報伝達を担う「メッセンジャー」のような役割。
- 腫瘍による栄養消費の増大
- 長期にわたる炎症で起こる疲労感
- 痛みによる睡眠不足やストレス
症状が進行した場合のリスク
症状が重篤化した状態では、患部が変形したり、腫瘍からの出血が続いたりするリスクも否定できません。
転移のリスクも高まるため、痛みやしこりが続くときはできるだけ早く整形外科や腫瘍専門医に相談してください。
未分化多形肉腫(悪性線維性組織球腫)の原因
未分化多形肉腫の直接的な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの危険因子や誘発要因が報告されています。
特定の遺伝子変異や放射線暴露歴、免疫力の低下などが絡み合い、腫瘍の発生につながっていると考えられています。
放射線治療との関連
過去にほかのがんなどで放射線治療を受けた部位に、数年から十数年後に未分化多形肉腫が発症する事例が報告されています。
放射線照射によるDNA損傷が蓄積し、それが腫瘍化を誘発すると考えられています。
すべての患者様がリスクを抱えるわけではありませんが、放射線治療を受けた部位の硬いしこりや違和感は早期に受診して確認しましょう。
原疾患の治療から5~10年以上経過して発症するケースが多いです。
| 放射線治療歴がある場合の注意点 | 内容 |
|---|---|
| 観察期間 | 放射線治療終了後、約5年以上経過後に発症リスク |
| 定期的なフォロー | しこりや痛みなど、腫瘍が疑われる症状のチェック |
| 受診のきっかけ | 以前の照射部位付近に違和感が続く、または目視できる腫瘤 |
遺伝子異常の蓄積
がん細胞の発生には、遺伝子異常が深く関与しています。
一般的ながんと同様に、遺伝子の修復機構が破綻した細胞が異常増殖を始めると未分化多形肉腫を引き起こす可能性があります。
ただし、ほかの腫瘍と比べると、特定の遺伝子変異に限定されない場合が多く、多彩な分子異常が複合的に作用すると考えられています。
- DNA修復機能の低下
- 細胞増殖シグナルを制御する遺伝子の変異
- 遺伝子のエピジェネティックな変化
慢性的な炎症と刺激
慢性的な炎症が続くと、その部位で細胞増殖が盛んになります。
長年にわたる組織の修復過程で突然変異が起こり、腫瘍に進展する場合もあります。
潰瘍や外傷、または慢性疾患を抱えている方は、患部の状態をこまめに観察して異常があれば早めに受診するように心がけましょう。
免疫力や加齢の影響
加齢に伴い免疫力が低下すると、がん細胞を排除する機能が弱まり、腫瘍が発生・増殖しやすくなります。また、高齢の方は別の疾患を併発している可能性があり、がんを見逃しやすい状況になりやすいです。
四肢に触れるしこりなどがある場合は注意が必要です。
未分化多形肉腫(悪性線維性組織球腫)の検査・チェック方法
未分化多形肉腫の早期発見は、治療の見通しを改善するために重要です。
最初のステップでは、患者様の訴えや触診での腫瘤の有無、大きさ、硬さなどを確認します。続いて、画像検査や組織検査によって腫瘍の性質を把握し、最終的な診断へとつなげます。
触診と視診
患者様がしこりを自覚している場合、医師はその部位を直接触って大きさや形状、可動性、圧痛の有無を確かめます。
視診では、皮膚の変色や腫れ、浮き出た血管などがあるかを確認します。
これらの基本的な診察でも、ある程度の所見は得られます。
| 触診・視診で注目するポイント | 内容 |
|---|---|
| 腫瘤の大きさ | 直径や厚み、表面からの突出度 |
| 硬さ | 軟らかいか、硬いか、部分的に硬いか |
| 可動性 | 皮下組織と癒着しているか、動かせるか |
| 皮膚の状態 | 色素沈着、発赤、皮膚のびらんや熱感の有無 |
画像検査
未分化多形肉腫が疑われる場合、エコー(超音波検査)、CT検査、MRI検査などが利用されます。
病変の位置や大きさ、周辺組織への浸潤状況を把握するために、複数の画像検査を組み合わせて行います。
とくにMRIは軟部組織の描出が得意で、腫瘍の境界や内部構造をより詳しく調べる際に有用なため検査のゴールドスタンダードです。
| 画像検査の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 超音波検査(エコー) | 非侵襲的で短時間、軟部組織の硬さや血流を簡易的に評価 |
| CT | 骨や臓器の状態、遠隔転移が疑われる場合のスクリーニングに活用 |
| MRI | 腫瘍の広がりや内部構造、神経・血管などの周辺組織との関係を詳細に評価 |
組織検査(生検)
画像検査で腫瘍が疑われる場合、確定診断を行うために生検(バイオプシー)を行います。
腫瘍の一部を採取し、顕微鏡で病理医が観察して診断を下します。未分化多形肉腫は多彩な細胞像を示す場合が多いため、正確な病理検査が大切です。
生検標本の病理組織診断では、UPSに特徴的な高度な多形性を示す紡錘形細胞※3の密集、核異型※4と異常核分裂像※5、壊死などが観察されます。
※3紡錘形細胞:顕微鏡で観察した際に、その形が紡錘(糸を巻きつける道具、またはラグビーボールのような形)に似ている、細長く先端が尖った細胞。
※4核異型:細胞の核(DNAが存在し、細胞の機能を制御する部分)が、正常な細胞の核と比較して異常な形態や構造を示している状態。
※5異常核分裂像:細胞が分裂する際(核分裂)に、正常な分裂とは異なる異常な様式を示している像。
| 生検の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 針生検(CNB) | 太めの針で腫瘍組織の一部を吸引・切除して採取する方法 |
| 外科的生検 | 腫瘍の一部をメスや特殊器具で切り取って採取する方法 |
血液検査
未分化多形肉腫を直接特定できる腫瘍マーカーは確立されていません。
しかし、全身状態のチェックや、肝機能・腎機能・炎症の程度を把握するために血液検査を行います。
治療計画を立てる際には、患者様の基礎疾患や栄養状態も考慮するため、血液検査は重要な手がかりとなります。
未分化多形肉腫(悪性線維性組織球腫)の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
未分化多形肉腫の治療は、手術を中心に放射線治療や化学療法を組み合わせて行います。腫瘍の大きさや部位、悪性度、転移の有無などを総合的に判断しながら治療方針を決定します。
手術療法:腫瘍切除の基本方針
未分化多形肉腫では、腫瘍を可能な限り広範囲に切除することが基本的な治療方針です。
再発リスクを減らすために、腫瘍周辺の健常組織も含めて十分な切除マージン※6を確保する必要があります(R0切除)。
四肢の大きな腫瘍であっても、近年は患肢温存を重視し、機能を維持しながら腫瘍切除を行う症例が増えていますが、腫瘍が神経血管を広範囲に巻き込む場合などは患肢切断も検討されます。
※6切除マージン:がんなどの病変を手術で取り除く際に、病変の周囲に存在する「正常に見える組織」をどのくらいの幅で一緒に切除したかを示す用語。
- 腫瘍の大きさと周囲組織への浸潤範囲
- 術後の機能回復を見据えた切除方法
- 神経・血管を温存できるかどうか
- 切除後の再建手術の必要性
放射線治療
手術が難しい部位の腫瘍や、術後の局所再発リスクが高い場合などに放射線治療を行います。
単独で治療するよりも、手術前後に放射線を併用すると、腫瘍の縮小や再発リスクの低減が期待できます。また、根治的治療が難しい状況では、痛みの緩和を目的とした放射線治療も検討されます。
| 放射線治療の種類 | 実施タイミング |
|---|---|
| 術前治療(ネオアジュバント) | 手術前に照射し、腫瘍サイズを小さくして切除を容易にする |
| 術後治療(アジュバント) | 手術後に残存腫瘍細胞を制御し、再発予防を図る |
| 緩和治療 | 痛みや出血などの症状を軽減する目的で随時実施 |
化学療法
未分化多形肉腫には、ドキソルビシンやイホスファミドなどの抗がん剤が用いられる場合があります。
術前に化学療法を行って腫瘍を小さくし、切除しやすくする場合もあれば、術後に微小な病巣を制御するために行う場合もあります。
全身状態や腫瘍の悪性度、患者様の年齢や基礎疾患などを考慮して、単剤または多剤併用を検討します。
他に、分子標的薬(パゾパニブなど)や免疫チェックポイント阻害薬(ペンブロリズマブ)などが使用されるケースもあります。
| 使用される主な抗がん剤 | 特徴 |
|---|---|
| ドキソルビシン | アントラサイクリン系。幅広い適応がある |
| イホスファミド | アルキル化剤。高用量投与で効果を狙う |
| パクリタキセル | タキサン系。進行例で併用療法に用いる |
リハビリテーション
手術や放射線、化学療法を受けた後は、患部の機能回復と再発予防のためのリハビリテーションが大切です。
特に四肢の手術後は、筋力低下や関節可動域の制限が起きやすいため、専門的なリハビリ計画を立てます。
歩行訓練や筋力強化、ストレッチなどを行い、可能な限り元の生活に近づけることを目標とします。
- 筋力強化エクササイズ
- 関節可動域訓練
- 日常生活動作(ADL)の指導
- 義肢装具の適合調整(必要な場合)
治療期間の目安
治療期間は腫瘍の進行度や治療方針、患者様の体力などによって大きく変わります。
一般的には、手術前の化学療法や放射線治療に数週間から数カ月、手術後の回復に数週間以上、さらに術後の補助療法に数カ月以上要するケースもあります。
合計で半年から1年程度の治療期間になるケースが多いですが、早期発見で腫瘍が小さい場合は、より短期間で治療を終える場合もあります。
薬の副作用や治療のデメリット
未分化多形肉腫の治療に用いる薬には、抗がん剤や術後の痛み止めなどが含まれます。
これらの薬を使用するときは、副作用や治療そのもののデメリットをよく理解し、医師と相談しながら対処していきましょう。
ここでは主な抗がん剤や放射線治療、手術のデメリットについて説明します。
抗がん剤の副作用
抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響する可能性があります。
特に細胞分裂の活発な粘膜や骨髄などの細胞がダメージを受けやすいです。
| 副作用 | 対策・注意 |
|---|---|
| 嘔気・嘔吐 | 制吐剤の併用や食事回数の調整、刺激の少ない食材を選ぶ |
| 脱毛 | ウィッグや帽子などでカバー、精神的ケアも重要 |
| 骨髄抑制 | 定期的な血液検査で白血球・血小板減少をチェック、感染予防に注意 |
| 口内炎 | 口腔ケアを徹底、うがいや保湿剤の使用で口腔内を清潔に保つ |
手術のデメリット
大きな腫瘍を切除する場合、筋肉や神経、血管などを傷つける可能性があります。術後に患部の機能が大きく損なわれるリスクをどう回避するかが課題です。
また、再発を防ぐために広範囲切除を行うと、美容面・機能面での負担が大きくなる可能性があります。
ただし、近年は患肢温存や再建手術の技術が進んでおり、機能回復に配慮した治療計画を立てやすくなっています。
放射線治療のデメリット
放射線照射部位の皮膚や組織がダメージを受け、皮膚炎やむくみ、関節の硬化、血管障害などを引き起こす場合があります。
また、長期的には放射線による二次がんのリスクも報告されています。
メリット・デメリットを検討し、患者様の状態に適した照射範囲・線量の選択が重要です。
- 照射部位の皮膚炎(赤み、ただれなど)
- 関節が硬くなる、運動制限が残る
- むくみによる日常生活動作のしづらさ
- 神経障害
- 血管障害
- 二次性の悪性腫瘍
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
未分化多形肉腫の治療費は、手術費用や抗がん剤、放射線治療など、複数の要素で構成されます。
費用負担は大きくなる傾向がありますが、日本の公的医療保険制度(健康保険)を利用すれば、治療費の自己負担率は一定割合に抑えられます。
手術費用
手術費用は、腫瘍の大きさや切除範囲、再建術の有無によって上下します。
大掛かりな手術になる場合、入院費や麻酔費用なども含めると、保険適用前の総額が数十万円以上に及ぶ場合があります。
しかし、国民健康保険や社会保険に加入していれば自己負担は概ね3割、さらに高額療養費制度を利用すると、月々の自己負担額を一定の上限まで抑えることも可能です。
| 内容 | 費用目安(保険適用前) |
|---|---|
| 手術・麻酔費用 | 20万円~50万円以上 |
| 入院費 | 1日1万円前後(病院や部屋タイプで変動) |
| 再建手術費 | 10万円~30万円程度 |
放射線治療費
放射線治療は1回あたり数千円から1万円前後の費用がかかります(保険適用前)。
治療期間や照射回数は患者様ごとに異なるため、トータル費用は数十万円に達する可能性があります。
こちらも保険適用で3割負担となり、高額療養費制度の対象になります。
化学療法費
抗がん剤の種類や投与頻度によって費用は変わります。
入院での点滴投与を行う場合、薬剤費だけでなく入院費も加算されます。
薬剤によっては1回の投与で数万円から10万円近くかかるケースもありますが、保険適用で3割負担となります。
外来化学療法室がある病院に通院して投与を受けるスタイルで費用を抑えるケースもあります。
- 使用する抗がん剤の種類と組み合わせ
- 入院か外来かによる医療費の違い
- 治療期間の長さと投与スケジュール
高額療養費制度
高額療養費制度を利用すると、自己負担が一定の上限額を超えた分が後から払い戻されます。
上限額は所得や年齢によって異なりますが、がん治療においてはこの制度を活用することで大幅に自己負担額を軽減できる場合があります。
長期治療になることが多い未分化多形肉腫では、事前に医療ソーシャルワーカーや保険者に相談しておくと安心です。
高額療養費制度の基本的な流れ
| ステップ | 詳細 |
|---|---|
| ①病院などで一時的に支払う | 医療費をいったん全額または3割負担分を支払う |
| ②制度を申請する | 保険者に高額療養費の支給申請手続きを行う |
| ③差額分が払い戻される | 自己負担の上限を超えた分が後で払い戻される |
以上
参考文献
MATUSHANSKY, Igor, et al. MFH classification: differentiating undifferentiated pleomorphic sarcoma in the 21st Century. Expert review of anticancer therapy, 2009, 9.8: 1135-1144.
WINCHESTER, Daniel, et al. Undifferentiated pleomorphic sarcoma: Factors predictive of adverse outcomes. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 79.5: 853-859.
ROBLES-TENORIO, Arturo; SOLIS-LEDESMA, Guillermo. Undifferentiated pleomorphic sarcoma. 2021.
CHEN, Shiqi, et al. Undifferentiated pleomorphic sarcoma: long-term follow-up from a large institution. Cancer Management and Research, 2019, 10001-10009.
CRAGO, Aimee M., et al. Management of myxofibrosarcoma and undifferentiated pleomorphic sarcoma. Surgical Oncology Clinics, 2022, 31.3: 419-430.
KELLEHER, Fergal C.; VITERBO, Antonella. Histologic and genetic advances in refining the diagnosis of “undifferentiated pleomorphic sarcoma”. Cancers, 2013, 5.1: 218-233.
YOSHIMOTO, Masato, et al. Comparative study of myxofibrosarcoma with undifferentiated pleomorphic sarcoma: histopathologic and clinicopathologic review. The American Journal of Surgical Pathology, 2020, 44.1: 87-97.
LAZCANO, Rossana, et al. The immune landscape of undifferentiated pleomorphic sarcoma. Frontiers in Oncology, 2022, 12: 1008484.
SUN, Haitao, et al. Current research and management of undifferentiated pleomorphic sarcoma/myofibrosarcoma. Frontiers in Genetics, 2023, 14: 1109491.
RUBIN, Brian P., et al. Evidence for an unanticipated relationship between undifferentiated pleomorphic sarcoma and embryonal rhabdomyosarcoma. Cancer cell, 2011, 19.2: 177-191.