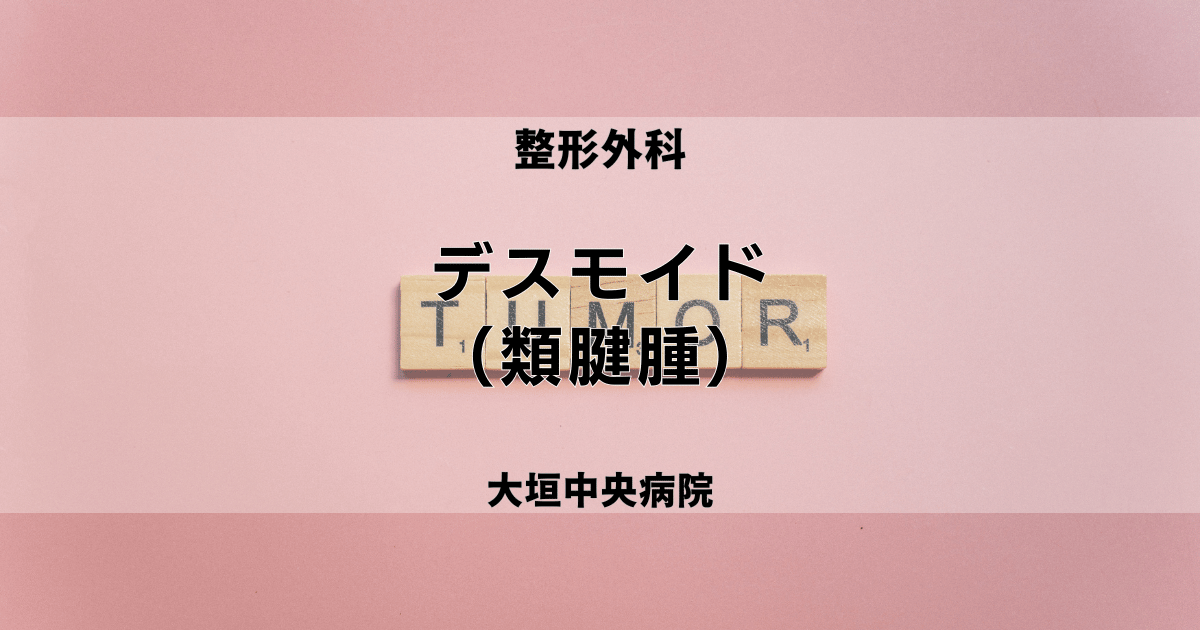デスモイド(類腱腫)(Desmoid tumor)とは、筋膜や腱、結合組織にできる線維芽細胞由来の良性腫瘍の一種です。
良性ではありますが、部位によっては周囲組織との癒着や圧迫が進み、痛みや運動機能の障害などを引き起こします。
また、局所的に再発しやすい特徴があるため、手術後も定期的な検査による経過観察が必要です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
デスモイド(類腱腫)の病型
デスモイドには、発生様式と発生部位による分類があります。
発生様式による分類
- 孤発性(Sporadic)
- 全体の約90%を占める
- 主に若年~中年女性に発症
- 体のあらゆる部位(四肢、体幹、腹壁など)に発生
- 遺伝性
- 家族性大腸腺腫症(FAP)に合併
- 男性に多い
- 腹腔内(腸間膜など)に発生する割合が高い
- FAP関連デスモイドはガードナー症候群と呼ばれることもあり
発生部位による分類
- 腹腔外デスモイド(Extra-abdominal)
- ほとんどが孤発性だが、10%程度に多発病変がみられる
- 手術痕や外傷部位に発生する
- 腹腔内デスモイド(Intra-abdominal)
- 家族性大腸腺腫症に合併し、他疾患の検査中に見つかることが多い
デスモイド(類腱腫)の症状
デスモイド(類腱腫)は良性の腫瘍ですが、発生部位や大きさに応じて多様な症状を引き起こします。
腫瘍が大きくなるにつれ、痛みや神経症状などを感じやすくなる可能性があります。
しこりや腫れ
まず、しこりや腫れがあらわれるのが一般的です。痛みがなくても、触れたときに硬さや違和感を覚える場合があります。
浅在性のデスモイドであれば視覚的に確認しやすいため、早期発見につながります。
痛みや圧迫感
痛みを訴えるケースでは、腫瘍の増大に伴って筋肉や神経が圧迫を受けている可能性があります。
特に深在性のデスモイドが骨や血管、神経に近いと、痛みだけではなく、しびれや麻痺などの症状が出る場合があります。
- 局所的な痛み:腫瘍が存在する部位に、限定的な痛みや違和感が生じる場合が多いです。
- 圧迫による神経症状:しびれ、筋力低下、動作時の強い痛みなどがある場合は、早めの受診が必要です。
可動域の制限
大腿や上腕など、運動に関わる部位に大きな腫瘍ができた場合、関節の可動域が制限されます。
痛みがなくても、筋肉や腱が伸縮しにくいため、日常動作に支障をきたすケースが少なくありません。たとえば、腕を上げにくくなる、歩行時に違和感を覚えるなどの症状がみられます。
腹部・内臓への影響
腹部に発生するデスモイド(腹壁デスモイドや腸間膜デスモイドなど)は、消化器やその他の臓器を圧迫する場合があります。
腹部膨満感や便秘、腸閉塞に近い症状を招くおそれもあるため、早期の受診が必要です。
腫瘍が大きくなると、腹部の張り、便秘や下痢などの消化器不調、食欲不振などの症状があらわれます。また、イレウス、腸管穿孔などの重篤な症状を呈する場合もあります。
デスモイド(類腱腫)の原因
デスモイド(類腱腫)の原因は、まだ完全には解明されていませんが、遺伝的要素やホルモンの影響、外傷や手術による刺激などが関連していると考えられています。
CTNNB1遺伝子の変異
多くの孤発性デスモイド腫瘍から、CTNNB1遺伝子(ベータカテニンをコードする遺伝子)の変異が確認されています。
ベータカテニンは細胞増殖に関連するタンパク質であり、その変異が腫瘍の形成や増殖を促進しているのではないかと考えられています。
| 役割 | 関連性 |
|---|---|
| 細胞間接着 | 細胞同士をつなぎとめる機能 |
| 転写因子の調節 | 遺伝子の発現を調節し、増殖をコントロール |
遺伝性疾患との関連
大腸ポリポーシスをはじめとする家族性大腸腺腫症(FAP)や、ガードナー症候群などの遺伝性疾患との関連も知られています。
これらの疾患をもつ方は、APC遺伝子変異が認められ、通常よりも高い確率でデスモイドを発症する傾向があります。
ホルモン環境の影響
女性ホルモン(エストロゲン)との関連が指摘されており、女性に多く発症する傾向があります。また、妊娠中や出産後に腫瘍が大きくなる例も報告されています。
ホルモン受容体を標的とした治療法の研究も行われており、ホルモン環境がデスモイドの発育に影響を及ぼす可能性があります。
外傷や手術痕
外傷や手術後の瘢痕組織でデスモイドを発症するケースがあり、外科手術や外傷によってできた炎症や繊維組織の増生が原因だと推測できます。
特に、腹部の手術痕から腹壁デスモイドが発生する例が多いです。
デスモイド(類腱腫)の検査・チェック方法
デスモイド(類腱腫)は症状だけで確定診断を下すことが難しく、画像検査や病理検査などを組み合わせて総合的に診断します。
触診と問診
まず触診と問診を行い、腫瘍の硬さ、動き、痛みの有無、最近の生活状況や既往歴などを確認します。
外傷歴や手術歴、家族に同様の疾患があるかどうかも重要な確認事項です。
- 腫瘍に気づいた時期
- 腫瘍の大きさの変化や痛みの程度
- 過去に受けた手術や外傷の有無
- 家族の病歴(ポリポーシスや腫瘍の有無)
- 妊娠や出産の経験・時期(女性の場合)
画像検査
デスモイドの性状や周囲組織との関係を把握するために、MRIやCT、超音波などの画像検査を行います。
MRI(磁気共鳴画像)
特に深在性のデスモイドではMRIが有力な検査で、腫瘍の境界や筋肉との関係をより詳細に把握できます。
デスモイドは線維成分が主体のため、MRIのT1強調像・T2強調像で低信号域として写る場合が多いですが、内部は不均一で一部にT2高信号(粘液成分や浮腫)が混在することがあります。
CT(コンピュータ断層撮影)
CTには、骨や臓器との位置関係を把握しやすいメリットがあります。
超音波(エコー)検査
超音波(エコー)検査は、浅在性のデスモイドが対象となる場合に利用しやすく、侵襲が少ないため繰り返し検査に適しています。
病理検査(生検)
画像検査でデスモイドが強く疑われる場合でも、確定診断には生検(患部の組織を一部採取して顕微鏡で観察する検査)が必要です。
線維芽細胞が豊富なコラーゲンに囲まれて増殖している特徴や、ベータカテニンの染色像などを調べます。
- 針生検
比較的太めの針を使って腫瘍の一部を採取します。局所麻酔下で行い、入院が不要なケースも多くあります。 - 組織生検
外科的に小さく切開し、腫瘍組織を切り取って検査します。腫瘍の位置や大きさによっては入院下で行います。
血液検査や遺伝子検査
デスモイドは炎症性疾患と違って血液検査による特徴的なマーカーが存在しないため、血液検査で確定診断はできません。
ただし、手術リスクの評価や全身状態の把握のために、一般的な血液検査を実施する場合があります。
また、ガードナー症候群や家族性大腸腺腫症が疑われる場合は、遺伝子検査が行われる可能性もあります。
- 一般血液検査
白血球数や炎症反応(CRP値)などを測定し、全身状態を評価します。 - 遺伝子検査
ガードナー症候群や家族性大腸腺腫症の診断補助として実施し、予後やリスク管理を考察する材料とします。
デスモイド(類腱腫)の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
デスモイド(類腱腫)は良性腫瘍でありながら、部位や大きさ、増殖速度、患者さんの状態によって治療方針が異なります。
腫瘍がゆっくりと成長するケースもあれば、急速に増大するケースもあり、個別対応が大切です。
積極的経過観察(active surveillance)
- 定期的な画像検査で腫瘍の大きさをモニタリングする。
- 痛みや可動域の制限など新たな症状が出た場合に再度治療方針を検討する。
症状が軽微または腫瘍の増大がゆるやかな場合、積極的に治療をせず経過を観察する選択肢もあります。
デスモイドのなかには自然に大きさが安定し、症状がほとんど進行しないケースや縮小するケースもあるからです。
手術療法(外科的切除)
- 腫瘍の大きさや部位、周辺組織への影響度を総合的に考慮して切除範囲を決定する。
- 広範囲な切除を行うと、機能障害が生じるリスクもあるため、術前に十分な検討とカウンセリングが必要となる。
腫瘍の根治をめざす場合、外科的に切除を行う方法が有効です。
ただし、デスモイドは再発率が高いため、周囲の正常組織を含めた広範囲切除が必要となる可能性があります。
手術後は定期検査を行い再発の有無を確認するほか、大きく切除した場合はリハビリテーションで筋力回復を図ることが重要です。
現在は「切除可能で機能障害が小さい症例や腹壁デスモイドで進行性の場合に限り、第一選択として手術を考慮する」方針が国際コンセンサスです。
| リハビリテーションの内容 | 目的 |
|---|---|
| ストレッチや軽い筋トレ | 切除部位周辺の柔軟性と筋力維持 |
| 温熱療法 | 血行促進による創部の回復サポート |
| 生活動作指導 | 日常動作をスムーズに行うための工夫 |
薬物療法
- ホルモン療法:エストロゲン受容体が陽性の場合、抗エストロゲン薬(たとえばタモキシフェンなど)を使用して腫瘍の成長を抑制します。
- NSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛剤):腫瘍増殖を抑える効果が期待でき、腫瘍の痛みや炎症を軽減する目的で使用されます。
- 分子標的薬:チロシンキナーゼ阻害薬やγセクレターゼ阻害薬など、特定の分子経路を狙った薬剤が検討されます。効果には個人差があるため、経過を慎重に見ながら投与します。
手術が困難な場所に腫瘍が存在する場合や、再発リスクが高い場合には薬物療法が選択肢となります。
放射線治療
過去には、手術後の再発予防や切除が困難な症例に対して放射線治療が行われていました。
しかし、放射線による周囲組織への影響や副作用などの問題もあるため、最近では薬物療法や厳密な経過観察を優先される場合もあります。
放射線治療を行うかどうかは、腫瘍の大きさや部位、患者さんの状態などを考慮して決定します。
治療期間の目安
デスモイドの治療期間は、腫瘍の大きさや部位、治療方法によって大きく異なります。
手術を行った場合でも、その後の経過観察を含めると数カ月から数年に及びます。
薬物療法を選択した場合は、効果があらわれるまでに数カ月かかる可能性があるため、長期的な通院が必要です。
手術療法のみの場合
手術後数週間の創部の回復期間に加えて、リハビリに数カ月程度かけるケースがあります。その後は半年から1年ごとにMRIやCTで再発がないかをチェックします。
薬物療法の場合
少なくとも3~6カ月程度は様子を見て効果判定を行い、必要に応じて治療方針を切り替えます。投薬期間が1年以上に及ぶケースもあります。
薬の副作用や治療のデメリット
デスモイド(類腱腫)の治療で用いる薬は副作用を伴うおそれがあります。
また、手術や放射線治療にもデメリットが存在し、身体に負担がかかる場合があります。
ホルモン療法の副作用
抗エストロゲン薬(タモキシフェンなど)を使用する場合、女性ホルモンのバランスに影響が及びます。
- 更年期障害に似た症状(のぼせ、発汗、イライラなど)
- 月経異常
- 骨密度の低下
NSAIDsの副作用
痛みや腫瘍増殖を抑える目的でNSAIDsを長期間服用する場合、胃腸障害や腎機能低下などのリスクが高まります。
また、血液凝固に影響を及ぼすため、出血しやすくなる可能性もあります。
- 胃痛や胃潰瘍
→胃を保護する薬(プロトンポンプ阻害薬など)を併用するケースがあります。 - 腎機能への負担
→定期的に血液検査で腎機能をチェックします。
分子標的薬の副作用
チロシンキナーゼ阻害薬などを使用した場合、下痢や皮疹、肝機能障害などが起こるおそれがあります。
個人差が大きいため、投与後は定期的に血液検査や問診を受け、副作用が強く出た場合は薬の調整や休薬を検討してください。
外科的切除のデメリット
手術による腫瘍切除は、一度に腫瘍を取り除けるメリットがありますが、再発や機能障害のリスクに注意が必要です。
- 再発リスク
デスモイドは良性でも再発率が高いため、完全切除しても再発する可能性があります。再発時には手術を繰り返すことは推奨されず、ほかの治療法を検討すべきです。 - 機能障害
筋肉や腱を大きく切除した場合、可動域や力が低下するリスクがあります。 - 手術自体のリスク
出血や感染など、一般的な手術リスクも伴います。
放射線治療のデメリット
腫瘍部位や照射範囲によっては、放射線が周囲の正常組織にダメージを与える危険性があります。
特に若年層では成長への影響や、将来的な放射線誘発腫瘍のリスクなども考慮しなければなりません。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
日本の公的医療保険制度では、医師が「必要」と判断した診療や治療行為に保険が適用され、デスモイドの場合も外科的切除や薬物治療などは通常保険適用です。
ただし、一部の新規薬剤や未承認薬を使用する場合は適用外となる可能性があります。
- 手術療法
一般的な外科手術に準じて、3割負担(または2割、1割負担)となる場合がほとんどです。 - 画像検査や血液検査
MRIやCT、採血なども医療保険の対象となります。 - 薬物療法
承認薬であれば保険が適用されますが、高額療養費制度の活用を視野に入れる場合があります。
外科的切除の費用目安
一般的な腫瘍摘出手術で保険適用を受けた場合、自己負担(3割負担と仮定)で10万~30万円前後が目安です。
大規模な再建術を伴う場合は、さらに費用がかさむ可能性があります。
| 項目 | 費用の目安(3割負担の場合) |
|---|---|
| 手術費用 | 約5万~15万円 |
| 入院費用(1週間程度) | 約3万~10万円 |
| 術前・術後の検査 | 数千円~数万円 |
薬物療法の費用
ホルモン療法やNSAIDsなどの一般的な薬剤であれば比較的安価で済みますが、分子標的薬などの高額な薬剤を使用する場合は、1カ月あたり数万円~数十万円かかります。
- ホルモン療法(タモキシフェンなど)
毎月数千円~数万円程度 - 分子標的薬
毎月数万円~数十万円に及ぶ場合もあり、医療保険+高額療養費制度の併用を検討します。
リハビリテーションや通院費用
手術後のリハビリテーションや定期的な通院にも継続的に費用が発生します。理学療法士によるリハビリ指導は保険適用となり、1回あたり数百円~数千円程度の自己負担が目安です。
高額療養費制度の活用
医療費が高額になる場合、高額療養費制度を利用すると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
所得や年齢によって限度額が異なるため、事前に制度を確認しておくと安心です。
以上
参考文献
SHINAGARE, Atul B., et al. A to Z of desmoid tumors. American Journal of Roentgenology, 2011, 197.6: W1008-W1014.
ESCOBAR, C., et al. Update on desmoid tumors. Annals of oncology, 2012, 23.3: 562-569.
SHIELDS, C. J., et al. Desmoid tumours. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 2001, 27.8: 701-706.
LEV, Dina, et al. Optimizing treatment of desmoid tumors. Journal of Clinical Oncology, 2007, 25.13: 1785-1791.
REITAMO, Jyrki J.; SCHELNIN, Teddy M.; HÄYRY, Pekka. The desmoid syndrome: new aspects in the cause, pathogenesis and treatment of the desmoid tumor. The American Journal of Surgery, 1986, 151.2: 230-237.
KASPER, Bernd, et al. Current management of desmoid tumors: a review. JAMA oncology, 2024, 10.8: 1121-1128.
SAKORAFAS, George H.; NISSOTAKIS, Christos; PEROS, George. Abdominal desmoid tumors. Surgical oncology, 2007, 16.2: 131-142.
KASPER, Bernd; STRÖBEL, Philipp; HOHENBERGER, Peter. Desmoid tumors: clinical features and treatment options for advanced disease. The oncologist, 2011, 16.5: 682-693.
ACKER, Jeffrey C.; BOSSEN, Edward H.; HALPERIN, Edward C. The management of desmoid tumors. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 1993, 26.5: 851-858.
DE BREE, Eelco, et al. Desmoid tumors: need for an individualized approach. Expert review of anticancer therapy, 2009, 9.4: 525-535.