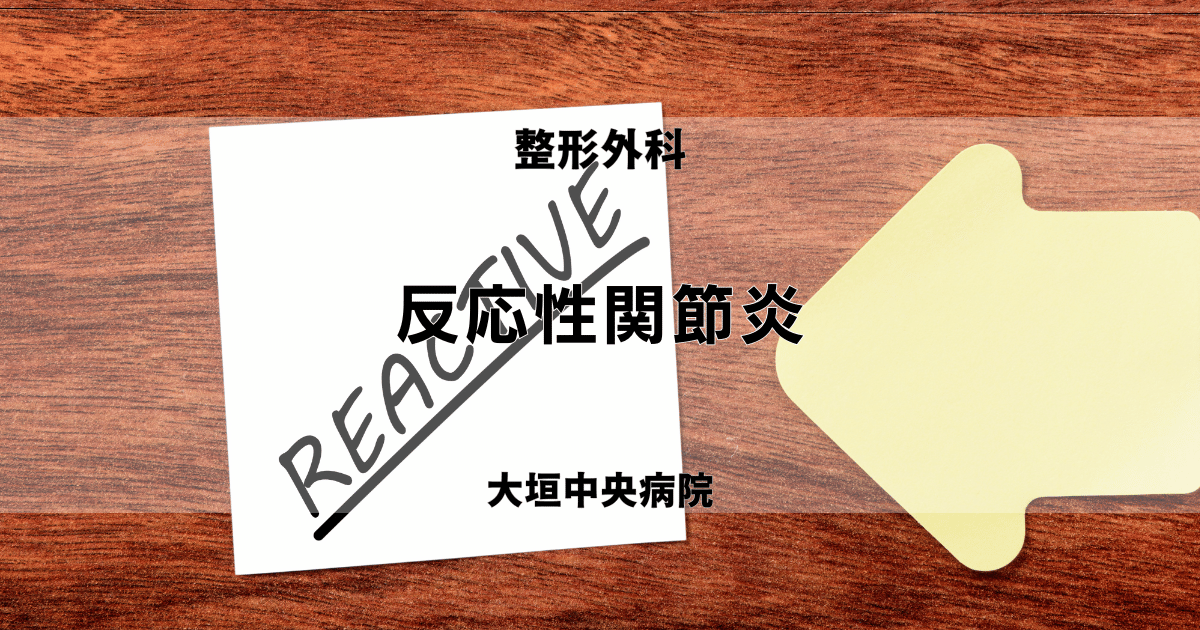反応性関節炎(Reactive arthritis, ReA)とは、先行する感染症などをきっかけにして関節の痛みや腫れなどの症状が起こる病気です。
血清反応陰性関節炎(リウマトイド因子陰性の関節炎)の一種であり、強直性脊椎炎や乾癬性関節炎、炎症性腸疾患関連関節炎などと共に脊椎関節炎(Spondyloarthritis, SpA)のグループに分類されます。
感染経路は尿路、生殖器、消化器などさまざまですが、典型的には腸管や尿路の感染で、関節炎だけではなく全身的な症状があらわれる場合もあります。
再発や慢性化のリスクに直面する人もいるため、早期発見と治療計画の立案が重要です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
反応性関節炎の病型
反応性関節炎の病型は「古典的ReA」と「非古典的な感染関連関節炎」に大別できます。
- 古典的ReA:GU/腸管感染後、HLA-B27関連
- 非古典的な感染関連関節炎:溶連菌、結核、BCGなど多様な感染後に発症するもの
反応性関節炎の分類は、1999年の国際ワークショップで整理されました。
それによれば「古典的反応性関節炎(classic ReA)」とはHLA-B27と関連し、脊椎関節炎様の症候(付着部炎やぶどう膜炎など)を伴う関節炎で、泌尿生殖器感染や腸管感染(および一部の呼吸器感染)が引き金となるものに限定されます。
これに該当する典型的な病原体は、クラミジア・トラコマチス(尿道炎/子宮頸管炎)、サルモネラ、シゲラ、カンピロバクター、エルシニアなどです。
古典的ReAは非対称性で下肢優位の少関節炎を呈し、HLA-B27との関連が強い点が特徴です。
一方で、化膿性関節炎(細菌が関節内で増殖する関節炎)を除く、その他の感染後の非化膿性関節炎は「感染症関連関節炎 (infection-related arthritis)」と呼ぶことが提唱されました。
反復性扁桃炎に伴う溶連菌感染後反応性関節炎(PSRA)や活動性結核に伴うPoncet病(結核性反応性関節炎)、膀胱癌のBCG膀胱内注入療法後に生じるBCG誘発関節炎(iBCG-ReA)などが含まれます。
これらは古典的ReAと発症メカニズムが類似するため反応性関節炎の広義のスペクトラムに含められる一方、誘因となる微生物やHLA-B27陽性率が異なるため鑑別上区別が必要です。
古典的ReAは、しばしばReiter症候群とも呼ばれた症例(尿道炎・結膜炎・関節炎の三徴を呈するケース)を包含しますが、三徴すべてが揃わなくとも先行感染+関節炎で診断します。
診断基準案では「下肢に多い非対称性少関節炎」かつ「4週間以内の下痢または尿道炎(あるいは検査で証明される感染症)の既往」が満たされれば他疾患除外後にReAと診断できるとされています。HLA-B27保有は診断必須条件ではありません。
成人と小児の分類の違い
小児の反応性関節炎は発症頻度が低く、明確な分類基準はありませんが、持続する場合は若年性特発性関節炎(JIA)の一型(特にHLA-B27陽性の付着部炎関連関節炎のカテゴリー)として扱われることがあります。
反応性関節炎が小児で6か月以上慢性化するのは稀ですが、慢性例では強直性脊椎炎への移行も報告されており、その際は強直性脊椎炎(脊椎関節炎)として扱い、難病認定の対象となり得ます。
一方、急性・一過性であればJIAの分類には含まれず、あくまで感染後反応性の一時的関節炎と位置づけます。
したがって、小児例では感染性関節炎(化膿性)との鑑別やJIAとの経過観察が重要です。
反応性関節炎の症状
反応性関節炎では、関節そのものの痛みや腫れだけではなく、全身のさまざまな部位に症状があらわれます。
典型的には、先行感染(下痢や尿道炎など)から数週間後に症状が出現し、日常生活に大きな影響を及ぼしかねません。
| 部位 | 具体的な症状 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 関節 | 膝や足首の腫れ、痛み | 歩行障害、階段の上り下りの困難 |
| 皮膚・粘膜 | 口腔内潰瘍、結膜炎、発疹 | 見た目の悩み、眼の痛み、視力低下 |
| 全身 | 発熱、倦怠感、リンパ節腫れ | 体力低下、疲労蓄積 |
反応性関節炎の関節症状は一過性であるケースが多く、患者の約半数は発症から6か月以内に全症状が消失します。
ほとんどの患者は1年以内に寛解しますが、一部(15~50%)では再発を繰り返したり、症状が6か月を超えて慢性化したりする場合があります。
関節痛と関節周囲の症状
反応性関節炎の最も特徴的な症状は関節痛で、主に下肢、特に膝や足関節など大きな関節に強い痛みや腫れが起こります。
- 歩行時に膝や足首が痛み、階段の上り下りが難しくなる
- 痛む関節が熱をもち、発赤や腫脹が見られる
- 安静時でも違和感やこわばりを覚える
関節周囲の腱付着部にも炎症が起こるため、かかとや足底などに痛みが生じる可能性もあります。
小児では自分で症状を訴えられず、跛行(ひょこひょこ歩き)などで気づくケースも少なくありません。
皮膚や粘膜の病変
反応性関節炎では、皮膚や粘膜に「付着部病変」と呼ばれる特徴的な症状が出る場合があります。
- 口腔内の無痛性潰瘍や口内炎
- 尿道や膣に分泌物が増える、排尿痛を伴う
- 眼の充血や目やにが増える(結膜炎)
皮膚の角質が厚くなる角化症など、赤みやかさぶたを伴う発疹が手のひらや足の裏に出現します。
眼症状
結膜炎が反応性関節炎患者の50~70%と高頻度に認められます。
片眼または両眼の結膜充血、異物感、掻痒感がみられ、しばしば発作的に寛解・再燃を繰り返します。
さらに、約5~10%ではぶどう膜炎(虹彩炎)を合併し、強い眼痛や羞明(まぶしさ)、視力低下を引き起こす場合があります。
全身症状
感染症が発端となるため、全身倦怠感や発熱、リンパ節の腫れなどが出る場合があります。
こうした全身症状が強い場合は、体力が低下している可能性が高く、病状が長引くと集中力や意欲の低下につながりかねません。
また、全身性の合併症として心血管系の病変が10%未満ながら報告されています。
反応性関節炎の原因
反応性関節炎は、感染症(細菌感染)に対する免疫反応が原因で発症します。
泌尿生殖器感染
クラミジア・トラコマチス(Chlamydia trachomatis)が最も多く、若年男性における性行為感染症後のReA誘因として有名です。
その他尿道や前立腺に感染しうるマイコプラズマやウレアプラズマも報告があります。
消化管感染
赤痢菌、サルモネラ属、カンピロバクター属、エルシニア属、クロストリジウム・ディフィシル(偽膜性大腸炎の菌)など、多くの腸管感染症がトリガーとなり得ます。
いわゆる細菌性赤痢や食中毒の後に発症する例です。
呼吸器感染
一部の呼吸器病原体も関節炎を誘導しうることが知られており、オウム病や肺炎の感染後ReAが報告されています。
頻度は高くありませんが、気道感染後に関節炎を呈する場合は原因の一つとして考慮されます。
その他特殊な感染
反応性関節炎の拡大概念として、溶連菌感染(特にA群溶連菌の扁桃炎)後の関節炎(PSRA)、結核(活動性結核中の無菌性関節炎:Poncet病)、BCG菌株の膀胱内注入療法後の関節炎(iBCG-ReA)が挙げられます。
さらに、ライム病(ボレリア感染)後や腸炎ビブリオなどの後に関節炎を呈する例も広義には反応性関節炎と呼ばれる場合があります。
ただし、これらは古典的ReAと異なり、HLA-B27との関連は弱い傾向があります。
発症機序
いずれの場合も関節そのものが直接感染されているわけではなく、感染に対する異常な免疫反応が原因です。
先行感染部位から関節内に運ばれた微生物の構成要素(抗原)が滑膜で免疫反応を引き起こし、関節炎が生じます。
実際、反応性関節炎患者の関節液から生きた細菌は培養されませんが、菌体成分やDNAが検出される場合があります。
例えばクラミジアでは、感染を受けた単球が関節に移行し、滑膜線維芽細胞内にクラミジアが持続感染して代謝的に活性な形で残存することが示唆されています。
一方、サルモネラや赤痢菌など腸管病原菌は関節内ですぐ死滅するものの「菌体ゴースト」や菌由来の分子が滑膜細胞内に残り、これが抗原刺激となって免疫T細胞を活性化する可能性があります。
結果として、滑膜でのサイトカイン応答の乱れ(Th1/Th17応答)を介し関節炎が引き起こされ、炎症が長引くと慢性化に至ると考えられます。
また近年、腸内細菌叢(マイクロバイオータ)の変化がReA発症に影響するとの知見も出てきており、感染後に腸管内で菌やその抗原が長期間潜伏するメカニズムなどが研究されています。
遺伝的素因
既述の通り、HLA-B27遺伝子が発症に大きく関与しています。
HLA-B27陽性者では感染後に関節炎を起こしやすく、特に強い炎症や関節外症状、慢性化を来しやすいことが知られます。
HLA-B27を持つ人は持たない人よりも発症率が高い(HLA-B27陽性集団ではReAの発症率が有意に高い)との疫学データがあります。
HLA-B27陽性者では感染微生物由来の抗原とHLA-B27との交差反応など免疫学的機序が指摘されていますが、詳細は未解明です。
小児における原因
小児の反応性関節炎でも、原因となる先行感染は概ね成人と同様です。
小児では腸管感染(例:エルシニア)に続発する関節炎が報告されています。
また、A群溶連菌感染後にリウマチ熱ではない関節炎を呈するPSRAは、小児~若年者で報告されてきました。
ただし、小児例の多くは予後良好で一過性に終わります。
HLA-B27陽性の思春期発症例では、まれに慢性化して強直性脊椎炎様に移行する場合もあり、遺伝素因が強く関与していると考えられます。
反応性関節炎の検査・チェック方法
反応性関節炎を診断するには、問診や視診だけではなくいくつかの検査が必要で、基本的には除外診断を含む総合的な臨床判断となります。
| 検査項目 | 主な目的 | メリット |
|---|---|---|
| 血液検査(CRPなど) | 炎症の程度と免疫状態を把握 | 短時間で全身の炎症指標を確認可能 |
| 遺伝子検査(HLA-B27) | 遺伝的素因の有無を確認 | 重症化リスクの推測に役立つ |
| 画像検査 | 関節や周囲組織の炎症・変形の有無を確認 | 関節内部の詳細が把握しやすい |
| 関節液検査 | 他の関節炎(感染性、結晶性)との鑑別 | 特異的な診断根拠を得られる |
問診と身体所見
問診と身体所見では、痛みや腫れの程度、過去2~4週間以内に下痢や尿道炎のような感染症状があったかを確認します。
- 患部の腫れや発赤の有無
- 痛みの程度や可動域
- 皮膚や粘膜の病変(結膜炎や口腔内潰瘍など)の有無
血液検査
血液検査では、炎症の程度や自己抗体の有無などをチェックします。
また、白血球数や免疫グロブリンなどから感染後の反応を推測する場合もあります。
- CRPや赤血球沈降速度(ESR)で体内の炎症を評価
- HLA-B27の保有の有無を調べる遺伝子検査(必要な場合)
- 感染症に関する抗体価や細菌培養検査
- リウマトイド因子や抗核抗体は陰性
- 先行感染の証明(尿培養検査など)
画像検査
関節の状態を把握するために、X線やMRI、超音波などを行う場合があります。
- X線検査:骨や関節の変形、骨膜反応の有無を確認
- MRI検査:軟骨や靭帯、腱付着部の微細な炎症を詳しく評価
- 超音波検査:関節の腫れ、関節液の貯留や血流を観察
これらの画像検査結果から、他の関節炎(リウマチ性疾患など)との鑑別を行います。
関節液の検査
関節の腫れが顕著な場合、関節内に液体がたまることがあります。
この関節液を採取して検査すると、感染性関節炎や痛風、偽痛風などの可能性を除外できる場合があります。
- 白血球数の増加や結晶の有無
- 培養検査で細菌が増殖するかどうか(基本的にはReAは無菌性)
- 炎症性の特徴かどうかの判定
反応性関節炎の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
反応性関節炎の治療は、(A) 誘発した感染症に対する治療と、(B) 関節炎自体の炎症を抑える治療の2本立てで行います。
A) 先行感染に対する治療
腸管感染に対する抗菌薬
サルモネラ、赤痢菌、カンピロバクターなどの腸炎後ReAでは、関節炎発症時点で腸管感染は自然治癒している場合が多く、抗菌薬による関節炎改善効果のエビデンスはありません。
したがって、ルーチンには抗生物質投与は推奨されません。感染性下痢が遷延する場合や重症例では感染症治療のため適宜抗菌薬を用いますが、関節炎予防目的での投与は有効性が示されておらず、腸管感染後ReAには対症療法が原則です。
クラミジア感染に対する抗菌薬
クラミジアによる泌尿生殖器感染が原因の場合(いわゆる性行為感染症後ReA)、抗菌薬治療が有益となり得ます。
マクロライド系(アジスロマイシンなど)やテトラサイクリン系(ドキシサイクリンなど)が一般に有効で、推奨される治療期間は1~3週間程度です(尿路のクラミジア根絶目的)。
関節炎症状そのものへの明確な効果は必ずしも証明されていませんが、感染源コントロールのため必ず実施します。
また、性感染症ではパートナーへの対策も重要で、ピンポン感染(再感染)を防ぐため性パートナーも同時に治療します。
小児(思春期)のクラミジア感染例ではドキシサイクリンは8歳未満に禁忌のため、年齢に応じた抗菌薬選択(例えばマクロライド系の使用)が必要です。
溶連菌感染に対する抗菌薬
PSRA(溶連菌感染後反応性関節炎)では、先行する溶連菌に対するペニシリン系抗生剤などによる治療を行います。
これはリウマチ熱の治療に準じた溶連菌除去目的で、通常10~14日間投与します。
加えて関節炎自体への抗炎症治療も同時に行います(後述のNSAIDsなど)。
PSRAでは抗菌薬+抗炎症薬の併用で多くは完治しますが、再発を繰り返す場合や慢性化例では扁桃摘出術が有効な場合があります。
特に、扁桃炎を繰り返す患者で関節炎が長引く場合、耳鼻科と連携して扁桃摘出を検討し、実施後3週間以内に関節炎が著明に改善するケースが報告されています。
結核に対する治療
Poncet病(結核関連反応性関節炎)の場合、背景に活動性結核があります。
したがって抗結核薬による治療が必須で、通常の結核治療レジメン(INH+RFPなど標準多剤療法を6~12か月)を行います。
関節炎症状は抗結核薬開始後1週間~4か月程度で消失することが多いと報告されています。
結核治療に準じるため、治療期間は少なくとも半年以上の長期となります。
B) 関節炎および症状に対する治療
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)
急性期の関節炎治療の第一選択はNSAIDsによる消炎鎮痛で、インドメタシン、ナプロキセン、ロキソプロフェン、セレコキシブなどを患者の状態に合わせて使用します。
NSAIDsは疼痛・炎症を速やかに軽減し、多くの患者では短期間(約2週間)の投与で十分な効果が得られます。
特に反応性関節炎は自然経過で数週間~数カ月で改善するケースが多いため、NSAIDsで急性期を乗り切れば追加治療なしで寛解に至る例も少なくありません。
効果不十分な場合は投与期間を延長するか、他のNSAIDに変更します。
なおNSAIDsは胃腸障害など副作用に注意が必要であり、胃粘膜保護薬の併用や短期間の使用を心がけます。
小児でもNSAIDs(小児用量のイブプロフェンなど)は第一選択で、特に小児では長期のNSAIDs単独で完解する例が多いです。
ステロイド療法
ステロイド療法には局所注射と全身投与があります。
単関節のみ強く腫脹疼痛する場合、副腎皮質ステロイドの関節内注射が極めて有効で、関節液除去とトリアムシノロンなどの注入で速やかに症状を緩和できます。
複数関節に炎症が及ぶ多関節炎やNSAIDsで抑えきれない重症例では、全身性のステロイド投与を検討します。
プレドニゾロン(PSL)の投与量は症状の重さによって調節し、軽症例ではPSL 15~20mg/日、中等症~重症例では30~40mg/日程度から開始します。
症状が落ち着き次第、比較的短期間で漸減・中止します(概ね数週間~2か月以内のテーパリングが多い)。
DMARDs(疾患修飾性抗リウマチ薬)
反応性関節炎の多くは上述のNSAIDsや短期ステロイドで寛解しますが、一部で症状が遷延・再燃し、慢性的な関節炎や付着部炎が続く場合があります。
その際にはサラゾスルファピリジン(SASP)やメトトレキサート(MTX)といったDMARDsの使用を検討します。
生物学的製剤
上記DMARDsまで行っても重症の関節炎が持続し、強い炎症や関節破壊進行が懸念される難治性ReAには、抗TNF-α抗体製剤などの生物学的製剤が選択肢となります。
インフリキシマブ(レミケード®)やアダリムマブ(ヒュミラ®)は既に強直性脊椎炎や乾癬性関節炎で保険適応があり、反応性関節炎でも症例報告やケースシリーズで有効性が示されています。
補助療法
ぶどう膜炎を発症した場合は眼科での治療が必要で、典型的にはステロイド眼滴と散瞳薬(癒着防止)を用います。
結膜炎や皮膚粘膜病変(口内炎・角化症)は特別な治療を要さず対症療法(洗眼やステロイド軟膏の塗布など)で自然軽快を待ちます。
治療期間の目安
急性期のNSAIDs投与は2~4週間程度で、その間に症状軽快すれば徐々に減量中止します。
ステロイド全身投与も1~2か月以内に減量終了とする短期集中療法が原則です。
SASPやMTXなどのDMARDsは効果判定まで2~3か月要するため、少なくとも3~4か月継続して効果を評価します。
薬の副作用や治療のデメリット
反応性関節炎の薬物治療には、副作用やデメリットも存在します。
症状の改善を最優先としつつ、リスクを把握して医師と相談しながら治療を継続することが大切です。
| 薬剤区分 | 副作用 | 対策 |
|---|---|---|
| NSAIDs | 胃腸障害、腎機能低下 | 胃保護薬の併用、水分摂取の十分な管理など |
| DMARDs | 肝機能障害、血球減少、発疹など | 定期的な血液検査、肝機能モニタリング |
| 抗生物質 | 下痢、腸内細菌叢の乱れ、耐性菌 | 処方量・期間の順守、乳酸菌製剤の活用など |
NSAIDsの副作用
- 胃痛、胸やけ、消化不良
- 胃潰瘍や出血のリスク上昇
- 腎機能低下(長期間の使用で注意)
非ステロイド性抗炎症薬は痛みを和らげるうえで有用ですが、消化器系の副作用が生じるおそれがあります。
DMARDsの副作用
- メトトレキサート:肝機能や肺の障害に注意
- サラゾスルファピリジン:発疹や消化器症状、まれに白血球減少
- レフルノミド:下痢や肝機能障害など
長期的な炎症コントロールに使用される抗リウマチ薬は、種類によっては肝機能障害や血球減少を引き起こすおそれがあり、定期的な血液検査や画像検査が大切です。
抗生物質のデメリット
- 下痢や腸内細菌叢の乱れ
- 特定の細菌に対する耐性が形成される
先行感染が原因の場合、抗生物質を使用して感染源を除去しますが、長期投与や乱用は耐性菌を生み出すリスクがあります。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
反応性関節炎の治療は基本的に健康保険の適用対象ですが、症状の度合いや治療内容によって自己負担額は変わります。
- 診察料:1,000~1,500円程度
- 血液検査:1,000~3,000円程度
- X線検査:500~1,500円程度
- MRI検査:5,000~10,000円程度
- NSAIDs:1種類あたり1週間分で500~1,500円程度
- DMARDs:種類によっては1か月分で3,000~5,000円程度
- 抗生物質:感染症の種類や投与期間によるが1週間分で500~2,000円程度
以上
参考文献
HANNU, Timo. Reactive arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2011, 25.3: 347-357.
SCHMITT, Steven K. Reactive arthritis. Infectious Disease Clinics, 2017, 31.2: 265-277.
TOIVANEN, Auli; TOIVANEN, Paavo. Reactive arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2004, 18.5: 689-703.
STAVROPOULOS, P. G., et al. Reactive arthritis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2015, 29.3: 415-424.
RIHL, Markus, et al. Reactive arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2006, 20.6: 1119-1137.
AHO, Kimmo; LEIRISALO-REPO, Marjatta; REPO, Heikki. Reactive arthritis. Clinics in rheumatic diseases, 1985, 11.1: 25-40.
GARCÍA-KUTZBACH, A., et al. Reactive arthritis: update 2018. Clinical rheumatology, 2018, 37: 869-874.
JUBBER, Ameen; MOORTHY, Arumugam. Reactive arthritis: a clinical review. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 2021, 51.3: 288-297.
KIM, Paul S.; KLAUSMEIER, Thomas L.; ORR, Donald P. Reactive arthritis: a review. Journal of Adolescent Health, 2009, 44.4: 309-315.
PETERSEL, Danielle Lauren; SIGAL, Leonard H. Reactive arthritis. Infectious Disease Clinics, 2005, 19.4: 863-883.