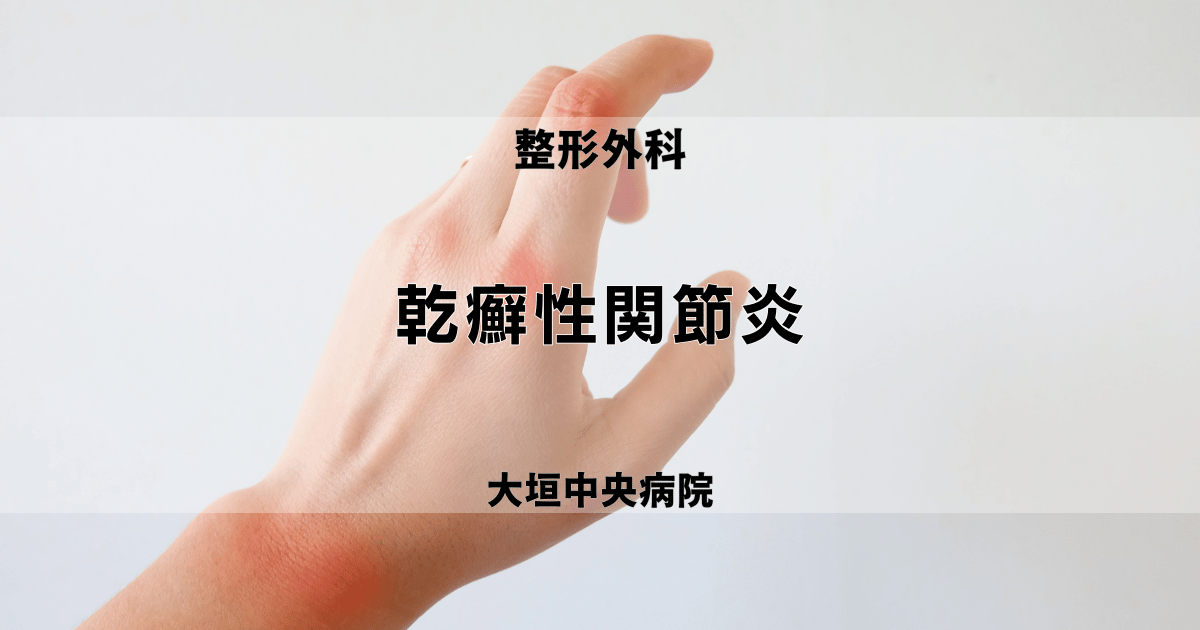乾癬性関節炎(Psoriatic arthritis, PsA)とは、皮膚に生じる乾癬と呼ばれる発疹と、関節痛や関節の変形などの症状が組み合わさった慢性炎症性関節炎です。
自己免疫が深くかかわる慢性疾患であり、年齢や性別を問わず発症します。皮膚症状だけでなく、手や指先といった小さな関節や、股関節・脊椎を含む大きな関節にまで影響が及ぶ場合もあります。
初期段階での適切な対応が重要で、放置すると関節破壊による機能障害をきたす可能性があるため、症状をコントロールして生活の質(QOL)の維持を目指すことが大切です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
乾癬性関節炎の病型
乾癬性関節炎(PsA)の病型は、古典的には1973年にMoll & Wrightによって提唱された臨床型に分類されます。
Moll & Wrightの分類
Moll & Wrightの分類は症状によって、遠位指節間関節(DIP)型、非対称性少数関節炎型、対称性多発関節炎型、関節炎性むち打ち様変形型、脊椎炎型の5つに分けられます。
遠位指節間関節(DIP)型
手指や足趾のDIP関節(末節部の関節)の炎症が主体となるタイプです。爪の乾癬病変を伴うケースが多く、他の関節リウマチなどでは珍しいDIP関節の腫脹が認められる点が特徴です。
非対称性少数関節炎型
1~4個程度の関節に炎症が生じるタイプで、左右対称にならない例が多いのが特徴です。膝や足関節など大関節の腫れや、指の単関節炎など様々なパターンがあります。初期のPsAでは約60%がこの型で発症します。
対称性多発関節炎型
多数の関節が左右対称性に侵されるタイプで、症状が関節リウマチに類似します。初期は少数関節炎でも経過とともに多関節炎に進展し、全PsA患者の50~60%で最終的に多関節炎(うち半数以上は左右対称)を呈するとの報告があります。
関節炎性むち打ち様変形型
手指や足趾の骨破壊が高度に進行し、オペラグラス変形(指骨の短縮や脱臼による著明な変形)を呈する重度のタイプです。頻度は稀ですがPsAの中で最も重症な病型であり、適切な治療が行われない場合に少数の患者さんで見られます。
脊椎炎型
仙腸関節や脊椎に炎症が起こるタイプで、強直性脊椎炎様の経過を辿ります。腰痛や背部痛を主症状とし、他の四肢関節炎を伴うこともあれば、軸骨格のみ侵される場合もあります。
軸関節炎を示すPsA患者ではHLA-B27遺伝子陽性率が高い場合があります。(例:軸関節型PsA患者の約30~50%がHLA-B27陽性との報告)
病型の多様性や時間経過による変化
以上のようにPsAは多様な病型を示し、1人の患者さんで複数の病型が重複する場合や、時間経過で病型が変化するケースもあります。
疾患活動性の評価や治療方針決定には、これら病型の把握に加え、末梢関節炎(手足の関節)・軸性関節炎(脊椎)・手指関節炎・腱付着部炎・皮膚/爪病変といった病変の領域ごとの重症度を評価するのも重要です。
診断分類基準
臨床分類とは別に診断分類基準としてCASPAR基準(Classification Criteria for Psoriatic Arthritis)が広く用いられています。
CASPAR分類基準では、「炎症性関節疾患(関節、脊椎または付着部の炎症)が存在する」を前提に、以下の特徴のうち合計3点以上を満たす場合にPsAと分類します(各項目の点数は括弧内に示します)。
- 現在乾癬の皮疹がある(2点)※最も高得点の項目
- 過去に乾癬の既往がある、または家族(1親等内)に乾癬患者がいる(各1点)
- 爪の乾癬(爪の点状陥凹や変形)がみられる(1点)
- 指または足趾の全体の腫脹を現在認める、または過去に医師により記録されたことがある(1点)
- X線で手足の骨新生像(付着部の骨棘形成)が認められる(1点)
- リウマトイド因子陰性である(1点)
CASPAR基準は2006年に発表されて以降、高い感度・特異度を持つ分類基準として研究や臨床で使用されています。
診断にあたっては鑑別すべき疾患(関節リウマチや痛風、変形性関節症など)を除外したうえで、乾癬の皮疹と関節炎の組み合わせを確認し、本基準を満たすか検討します。
乾癬性関節炎の症状
乾癬性関節炎(PsA)の症状は多岐にわたり、個人差も大きいです。代表的な症状としては、関節痛や関節の腫れ、朝起きたときのこわばり、皮膚や爪の変化などが挙げられます。
生活の質を左右する症状が多いので、自覚症状がある場合は早めの受診を検討しましょう。
| 症状 | 具体例 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 関節痛・腫れ | 腫れぼったい指、熱感 | 握力低下、歩行や動作の制限 |
| 朝のこわばり | 起床直後の手指や膝の強張り | 起き上がりや家事を始めるのに苦労 |
| 皮膚の乾癬 | 銀白色の鱗屑が見られる紅斑 | 見た目のストレス、痒み |
| 爪の異常 | 爪のくぼみ、肥厚、変色 | 日常生活での指先の使いづらさ |
関節痛と腫れ
もっとも多くみられる症状に、痛みと腫れがあります。
手指・足趾の関節(DIP関節を含む)や手首、膝や足首など様々な関節に炎症による疼痛、腫脹、朝のこわばりが生じます。
非対称に少数の関節が腫れるケースが多いですが、多関節に及ぶ人もいます。
手指の場合は物を握りにくい、足指の場合は靴を履くときに強い痛みを感じるなど、日常動作が妨げられる可能性があります。手指や足趾が腫れて「ソーセージ指」と呼ばれる状態になるのも特徴的です。
また、関節破壊が進行すると重症例では「ペンシルインカップ変形」(指骨末端が尖り、対向する骨がカップ状に侵食されるX線所見)などがみられます。
朝のこわばり
朝起きたときに手指や膝などがこわばって動かしにくい、あるいは数十分から1時間程度たつと徐々にほぐれてくる感覚を覚える人がいます。
これは炎症性の関節疾患に共通する特徴で、乾癬性関節炎でも比較的多く見られます。
こわばりが長時間続く場合は症状が進行しているサインの可能性があります。
皮膚や爪の変化
乾癬の皮膚症状は、銀白色のうろこ状の皮膚変化や、爪のくぼみ、爪の変色などとして現れます。
乾癬の皮疹はほぼ全例でみられます。皮膚症状と関節症状がほぼ同時期に始まる人もいれば、長年皮膚の乾癬で苦しんできた人が後になって関節に痛みを感じるケースもあります。
爪に細かい凹みがいくつもできているときや、爪が厚くなってきたときは、医師に相談すると参考になる場合があります。
PsA患者の60~80%では皮膚症状が関節炎に先行し、関節炎発症までの期間は平均で皮疹発現後約7~8年との報告があります。
疲労感や倦怠感
乾癬性関節炎では、関節だけでなく全身に慢性的な炎症が起きる場合があります。炎症が続くと疲労感や倦怠感を感じやすくなり、集中力ややる気が低下しがちです。
栄養状態や睡眠の質も影響するため、自己管理の観点からも日頃の生活習慣を見直すきっかけとなります。
その他の症状
乾癬およびPsAは炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)やぶどう膜炎(目のぶどう膜の炎症)を合併するケースがあります。
特にPsAを含む脊椎関節炎のグループでは虹彩炎・ぶどう膜炎の頻度が高く、目の充血・痛み・視力低下が起きた場合は眼科受診が必要です。
またPsA患者ではメタボリックシンドロームや心血管疾患の合併も多いことが報告されており、全身管理が重要です。
症状の進行を疑うサイン
- 朝のこわばり時間が長くなる
- 痛みの強さが増してくる
- 爪や皮膚の乾癬が増悪して関節の腫れも強くなる
- 疲労感の持続時間が長引いている
これらのサインを感じたら、早めに医療機関へ相談してください。
痛みなどの症状は我慢しても自然に回復する人は少なく、適切な治療を受けると関節機能の維持や生活の質向上を目指せます。
乾癬性関節炎の原因
乾癬性関節炎(PsA)の明確な原因は完全には解明されていませんが、免疫異常や遺伝、環境要因などが相互に作用して生じる免疫介在性炎症であると考えられています。
乾癬とPsAは密接に関連した疾患であり、共通の病態メカニズムを持つ一方で、皮膚と関節の症状に差異がみられる点から部分的に異なる免疫経路の関与も示唆されています。
免疫の異常
乾癬/PsAではIL-17、またIL-23やTNF-αなどの炎症性サイトカインが病態の中核をなしていることが分かっています。
実際、これらのサイトカイン経路を阻害する生物学的製剤(例:IL-17阻害薬やIL-23/12阻害薬、TNF阻害薬)の導入により、皮膚および関節の炎症が劇的に改善すると臨床で確認されています。
関節滑膜では炎症性サイトカインにより破骨細胞が活性化し骨びらんを生じる一方、関節付着部では炎症に伴う過剰な骨新生(付着部骨棘形成や骨の連続性形成による強直)が見られる点で、関節リウマチとは異なる骨病変を呈します。
こうした骨の破壊と過剰修復の両面がPsAの特徴です。
遺伝的素因
PsA患者の約40%に乾癬またはPsAの家族歴があり、第一度近親者※1にPsA患者がいる場合の発症リスクは一般人の30~50倍にもなるとの報告があります。
※第一度近親者:親、兄弟姉妹を指す。第一度近親者は遺伝情報の50%を共有しているとされる。
関連遺伝子として、皮膚型乾癬ではHLA-Cw6が強く関与する一方、関節炎型ではHLA-B27やHLA-B7といったHLA-B遺伝子との関連が指摘されており、特に脊椎炎を呈するPsAではHLA-B27陽性者が多い傾向があります。
このほかIL23RやIL12B、TNF-α遺伝子など免疫に関わる遺伝子多型もPsA感受性に影響するとされています。
環境要因
外傷や感染症および生活習慣が挙げられます。乾癬ではKoebner現象(健常皮膚に外傷を受けるとその部位に皮疹が現れる現象)が知られていますが、PsAでも外傷後に関節炎が発症する例が報告されており、「深部Koebner現象」とも呼ばれます。
重労働などによる機械的ストレスが付着部の炎症を惹起しうるとの知見もあり、肥満の人はPsA発症リスクが高いことが示唆されています。
感染症では、溶連菌感染が乾癬悪化の誘因となるケースがありますがPsAとの直接の関連は明確でなく、一方でHIV感染者に重症乾癬・関節炎が多いと知られています。
また腸内微生物叢の組成変化が乾癬/PsAの炎症に影響する可能性も近年示唆されており、発症に関わる環境要因は多岐にわたります。
以上のように、PsAは「遺伝素因を持つ個体に環境要因が加わり免疫異常が引き起こされる」という多因子疾患モデルで説明されています。
乾癬性関節炎の検査・チェック方法
乾癬性関節炎(PsA)が疑われる場合は、医師の診察や各種検査を通じて総合的に判断します。
画像検査や血液検査、問診などを組み合わせると、関節炎の有無や重症度、乾癬の皮膚症状との関連性を把握できます。
問診と視診
はじめに医師が、関節の痛みや腫れ、朝のこわばりなどの症状や、皮膚や爪の乾癬の有無・経過を確認します。さらに家族歴や生活習慣、症状が悪化・緩和する要因などを詳しく聞き取ります。
指先に炎症や腫れがあるか、皮膚に鱗屑があるかなどを直接目で見るのも、乾癬性関節炎を疑う重要な工程です。
目の充血があれば、ぶどう膜炎合併を考慮します。
画像検査(レントゲン、MRI、超音波など)
関節の内部構造や炎症状態を確認するために、レントゲンやMRI(磁気共鳴画像法)、超音波検査を活用します。
レントゲンでは骨の変形や関節の隙間の狭まりがわかり(骨びらんと骨棘形成が混在する所見)、MRIや超音波は軟部組織や炎症の状態をより詳しく確認できます。
MRIは早期の炎症変化を捉えるのに適しており、単関節型や脊椎型の診断に役立つ場合があります。
主な画像検査と特徴
| 検査方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| レントゲン | 骨の変形や関節の狭まりを確認可能 | 広く普及していて費用が比較的安い |
| MRI | 軟部組織や炎症の状態を詳細に把握 | 早期病変を捉えやすい |
| 超音波検査 | 関節周囲の腱や滑膜などの炎症をリアルタイムで観察できる | ベッドサイドで簡便に行える |
血液検査(炎症マーカーなど)
血液検査では、CRPやESR(赤沈)などの炎症マーカー、リウマトイド因子(RF)の有無、抗CCP抗体などを調べます。
乾癬性関節炎ではRFや抗CCP抗体は陰性の場合が多いですが、炎症マーカーが高い傾向にあります。
また、貧血の有無や肝機能・腎機能の状態も治療計画を立てる際の指標になります。PsAに特異的な血清マーカーは存在しません。
関節液の検査
関節に溜まった液(関節液)を針で抜いて分析する場合もあります。関節液の性状や白血球数などによって、感染症との鑑別などが可能になります。
感染による関節炎と乾癬性関節炎を区別するために必要な検査手段です。
医療機関で行う検査の例
- 問診・視診(皮膚と関節の状態)
- 画像検査(レントゲン、MRI、超音波)
- 血液検査(炎症マーカー、リウマトイド因子など)
- 関節液の採取と分析
これらの検査結果を総合的に判断して、乾癬性関節炎の有無と重症度を見極める場合が多いです。
医師が患者の症状や検査結果を丁寧に照らし合わせ、治療方針を決定していきます。
乾癬性関節炎の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
乾癬性関節炎(PsA)では、炎症や免疫反応をコントロールしながら、関節や皮膚のダメージを最小限に抑える治療を行います。
治療薬の選択や治療期間、リハビリテーションの内容は、患者さんの症状や生活環境によって異なります。
薬物療法
薬物療法は、炎症を抑えると同時に病気の進行を防ぎ、関節破壊や皮膚症状の悪化を防ぐ目的があります。
具体的な治療薬としては、NSAIDsやステロイド薬などが用いられます。
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)
痛みや腫れを一時的に和らげる目的で使用します。胃腸障害のリスクがあるため、長期使用する場合は胃薬の処方などが考慮されることがあります。
あくまで対症療法であり、症状コントロールのため短期間用いるか他の治療と併用します。
ステロイド薬
強い炎症がある場合や、関節の機能障害を抑えたい場合に医師が使用を判断するときがあります。
症状を早期に緩和する効果が期待できますが、副作用にも注意が必要です。
csDMARDs(疾患修飾性抗リウマチ薬)
メトトレキサートやサラゾスルファピリジンなど、炎症の進行を抑える薬です。飲み薬や注射薬などがあり、服用方法や副作用に関して医師の指示に従う必要があります。
安全性と費用の面で、まず試す価値のある標準治療です。
生物学的製剤
サイトカインと呼ばれる炎症物質を特異的にブロックする薬です。皮下注射や点滴による投与を行い、強い炎症を効率的に抑える効果があります。
費用が高額になりやすいため、保険適用などを含めて事前に相談するケースが多いです。
生物学的製剤には複数の作用機序の薬剤があり、病態に合わせて適切な薬剤を選択します。
例えば、軸性病変(仙腸関節炎や脊椎炎)が主体の場合は、従来DMARDは無効なため第一選択からTNF阻害薬やIL-17阻害薬を用いることが推奨されています。
一方、皮膚症状が極めて重い場合はIL-17またはIL-23経路を標的とする薬剤が適しています。
主な治療薬のポイント
| 薬剤種類 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|
| NSAIDs | ロキソプロフェン、セレコキシブなど | 痛みと炎症の対症療法的緩和 |
| ステロイド薬 | プレドニゾロン | 強力な抗炎症効果、長期使用は副作用注意 |
| DMARDs | メトトレキサート、サラゾスルファピリジンなど | 病気の進行を抑制、効果発現に時間がかかる |
| 生物学的製剤 | TNF阻害薬、IL-17阻害薬など | 免疫機構へ特異的に作用、高額になる場合が多い |
リハビリテーション
薬物療法と並行して、関節の可動域や筋力を維持するためにリハビリテーションを取り入れるのが一般的です。
関節に負担をかけすぎない範囲での運動療法やストレッチ、物理療法などを行い、炎症による関節の変形や拘縮を軽減する狙いがあります。
痛みを抱えていると動かすのが怖くなりがちですが、適切な運動は関節の健康を保つうえで大切です。
- 関節の可動域訓練(ストレッチ)
- 筋力強化トレーニング(軽度の負荷を用いた運動)
- 物理療法(温熱療法、低周波治療など)
- 日常生活動作の指導(立ち上がり方、歩き方の工夫など)
外科的治療
薬物治療にもかかわらず関節破壊が進行して強い疼痛や機能障害が残る場合、整形外科的手術を検討します。
変形の強い関節には人工関節置換術が有効ですし、指趾の亜脱臼には関節固定術や形成術を行う例もあります。
重度の変形では保存治療に限界があるため、適宜手術的に整復し装具を用いてADL(日常生活動作)の改善を図ります。
ただしPsA患者は多発関節炎を有する人が多いため、手術適応は慎重に検討され、可能な限り薬物療法とリハビリで対応するのが一般的です。
治療期間と通院
乾癬性関節炎は慢性疾患なので、症状が落ち着いても定期的な通院と継続的な治療が重要です。
症状が軽快するまで数カ月から半年程度かかる人もいますし、再発予防の目的で長期的に薬物療法を継続するケースもあります。
医師やリハビリスタッフと相談しながら、病状に合わせた通院スケジュールを組むのが望ましいです。
治療と通院に関する目安
| 項目 | 目安の期間 |
|---|---|
| NSAIDsによる対症療法 | 痛みや腫れが強い期間だけ数週間〜数カ月程度 |
| DMARDsの効果発現 | 服用開始から数週間〜数カ月程度 |
| 生物学的製剤の継続 | 数カ月〜数年単位での使用を検討 |
| 定期通院 | 1〜3カ月に1回程度、症状により調整 |
治療を始めたばかりの時期は頻回の通院が必要になる場合もあります。
状態が安定してきたら通院間隔を伸ばしながら、専門医によるフォローを継続する流れです。
薬の副作用や治療のデメリット
乾癬性関節炎(PsA)の治療薬は、症状をコントロールするうえで有用ですが、副作用やデメリットが生じるリスクもあります。
副作用やデメリットに対する正しい知識を持つと、自分自身の体調をしっかり観察しつつ治療に臨めます。
自己判断での中断や乱用はかえって症状を悪化させる場合があるので、医師とよく話し合うように心がけましょう。
NSAIDsの副作用リスク
NSAIDsは胃腸障害や腎機能への負担を引き起こす可能性があります。長期的に服用する場合は、胃腸を保護するための胃薬(プロトンポンプ阻害薬など)を併用するケースが多いです。
腎機能が低下している方や高齢の方は定期的に血液検査で腎機能をチェックする必要があるかもしれません。
ステロイド薬の副作用と注意点
ステロイド薬は強い抗炎症効果がある半面、血糖値の上昇や骨粗しょう症、感染症リスクの上昇などを引き起こす場合があります。
急激に減量するとリバウンドが起こりやすいため、医師は徐々に量を調整しながら治療を進めます。自己判断で減らしたり中止したりすると症状悪化の原因になります。
ステロイド薬使用時に気をつけたいこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血糖値管理 | 糖尿病リスク増加、血糖値のモニタリングが必要 |
| 骨粗しょう症対策 | 骨密度検査やカルシウム・ビタミンDサプリなど検討可能 |
| 感染症への注意 | 免疫力が低下するため、感染症にかかりやすくなる可能性 |
DMARDsの副作用
メトトレキサートをはじめとするDMARDsは効果発現に時間がかかる一方、肝機能障害や間質性肺炎などの副作用が報告されています。
定期的に血液検査や画像検査で副作用の有無をチェックして、問題がないかを確認しながら使用します。
- 肝機能の異常
- 間質性肺炎
- 胃腸障害(吐き気、食欲不振など)
服用スケジュールを守りながら慎重に経過を観察して、安全に効果を引き出します。
生物学的製剤の注意点
生物学的製剤は費用が高額になりやすい点が大きなデメリットです。また、免疫の働きを抑制するため、感染症のリスクが高まる場合があります。
投与期間中は結核などの潜在的な感染症を発症しやすくなる可能性があるため、結核検査や定期的な血液検査を受けるのが一般的です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
乾癬性関節炎(PsA)の治療にはさまざまな方法があり、費用は治療内容や薬剤によって大きく変わります。
日本では健康保険制度があるため、一定の自己負担割合で治療を受けられます。
保険適用の範囲
一般的な薬物療法やリハビリテーションは保険適用の対象となります。
ステロイド薬、DMARDs、炎症を抑えるためのNSAIDsなども処方されれば保険適用内で受けられます。
さらに、生物学的製剤を使う場合も多くのケースで保険が適用されますが、高額療養費制度の活用を視野に入れておくと安心です。
保険治療にかかる主な費用項目
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 通院・検査費 | レントゲン、MRI、血液検査、医師の診察料など |
| 薬剤費 | NSAIDs、ステロイド、DMARDs、生物学的製剤など |
| リハビリテーション費 | 運動療法、物理療法など |
| 追加検査費 | 結核検査など感染症リスクが懸念される場合に実施する検査費 |
治療費の目安
一般的に、NSAIDsやステロイド薬、DMARDsなどは比較的安価で、健康保険の自己負担(3割負担が多い)であれば数百円から数千円程度で済む人も多いです。
一方、生物学的製剤は1カ月あたりの薬剤費が数万円から10万円前後になる場合があります。3割負担とすると月に3万円〜数万円程度となり、負担は大きくなりがちです。
ただし、高額療養費制度を申請すれば自己負担上限額が設けられます。
治療費の一例(3割負担の場合)
| 薬剤 | ひと月あたりの金額 |
|---|---|
| NSAIDsやステロイド | 数百円〜数千円 |
| DMARDs | 数千円〜1万円程度 |
| 生物学的製剤 | 月あたり3万円〜6万円程度 |
もちろん個人差があり、治療内容や薬剤の選択次第で変動します。
さらに持病がある場合や、年齢区分による自己負担割合(2割、1割など)の違いによっても費用は変動します。
高額療養費制度の利用
生物学的製剤の導入などで治療費が高額になった場合は、高額療養費制度を利用できる可能性があります。
これは、1カ月の医療費自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
所得によって限度額が異なるため、詳細は市区町村の窓口や加入している健康保険組合に問い合わせて確認しておく必要があります。
- 1カ月あたりの自己負担額に上限が設けられる
- 所得区分に応じて上限額が異なる
- 事前に限度額適用認定証を取得しておくと便利
治療費に不安がある場合は、通院先の医療機関や健康保険組合の相談窓口でアドバイスを求めるのがおすすめです。
経済的な負担を少しでも軽減する手段を知っておくことは、治療を継続するうえでも意義があります。
以上
参考文献
MOLL, J. M. H.; WRIGHT, V. Psoriatic arthritis. In: Seminars in arthritis and rheumatism. WB Saunders, 1973. p. 55-78.
GLADMAN, Dafna D. Psoriatic arthritis. Moderate-to-Severe Psoriasis, 2008, 249-268.
GLADMAN, Dafna D. Psoriatic arthritis. Rheumatic Disease Clinics of North America, 1998, 24.4: 829-844.
RITCHLIN, Christopher T.; COLBERT, Robert A.; GLADMAN, Dafna D. Psoriatic arthritis. New England Journal of Medicine, 2017, 376.10: 957-970.
FITZGERALD, Oliver, et al. Psoriatic arthritis. Nature reviews Disease primers, 2021, 7.1: 59.
OCAMPO, Vanessa; GLADMAN, Dafna. Psoriatic arthritis. F1000Research, 2019, 8: F1000 Faculty Rev-1665.
SCARPA, Raffaele, et al. Psoriatic arthritis in psoriatic patients. Rheumatology, 1984, 23.4: 246-250.
VEALE, Douglas J.; FEARON, Ursula. The pathogenesis of psoriatic arthritis. The Lancet, 2018, 391.10136: 2273-2284.
OGDIE, Alexis; WEISS, Pamela. The epidemiology psoriatic arthritis. Rheumatic diseases clinics of North America, 2015, 41.4: 545.
GLADMAN, Dafna D. Psoriatic arthritis. Dermatologic therapy, 2004, 17.5: 350-363.