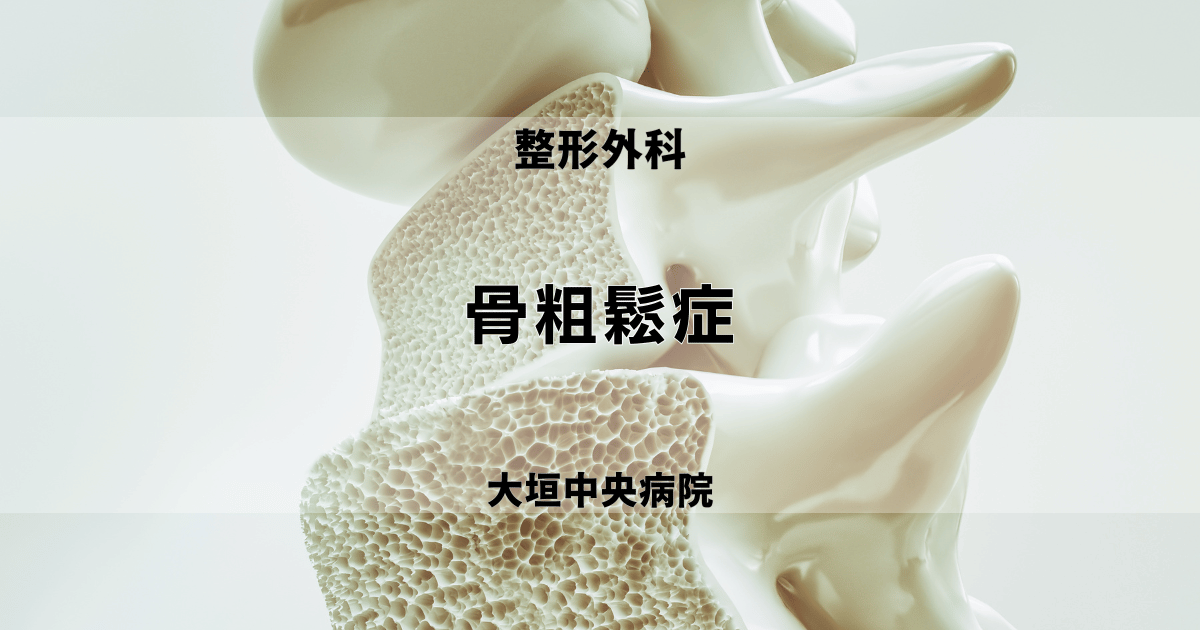骨粗鬆症(Osteoporosis)とは、骨量が減少して骨の強度が低下し、骨折を起こしやすくなる疾患です。WHOの定義では「骨量の低下と骨微細構造劣化による骨脆弱性の増大を特徴とする骨格疾患」とされています。
高齢者だけでなく、若い世代でも食生活の乱れや運動不足などで発症リスクが高まります。自覚症状が乏しい段階から骨密度が低下するため、予防や早期診断が大切です。
骨折を防ぐには定期的な検査や適切な治療を受けることが重要で、生活習慣の改善も大きな役割を担います。50歳以上では女性の3人に1人、男性の12人に1人が骨粗鬆症による骨折を一生のうちに経験するとされます。
この記事では、骨粗鬆症の病型、症状、原因、検査や治療について詳しく解説し、医療機関を受診する際の目安をご紹介します。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨粗鬆症の病型
骨粗鬆症にはいくつかのタイプがあります。原因や特徴によって分類でき、治療方針にも影響します。
原発性骨粗鬆症
女性の閉経後や高齢者によくみられるタイプで、加齢やホルモンバランスの変化が引き金になります。
エストロゲンの減少が骨量の急激な減少(特に海綿骨)につながりやすく、閉経後の女性に多く発症するものは閉経後骨粗鬆症と呼びます。
閉経後骨粗鬆症は、脊椎圧迫骨折※1や橈骨遠位端骨折※2が発症します。
男性も加齢によって骨量が減少しますが、女性ほど急激ではありません。こちらの老人性骨粗鬆症では大腿骨近位部や骨盤の骨折が増える傾向にあります。
※1脊椎圧迫骨折:脊椎を構成する椎体が、上下からの圧力によって潰れて(扁平に、あるいはくさび形に)骨折してしまう状態
※2橈骨遠位端骨折:前腕にある2本の骨のうち、親指側にある橈骨が、手首に近い端で折れる状態
続発性骨粗鬆症
ほかの疾患や内分泌異常、薬剤の使用などが原因で発症するタイプです。
糖尿病や甲状腺機能亢進症、リウマチなどの慢性疾患が存在すると骨代謝が障害されて発症につながりやすくなります。
ステロイド薬などを長期で使う場合にも骨粗鬆症のリスクが高まるため、主治医による骨密度の状態を定期的にチェックが重要です。
若年性骨粗鬆症
若い世代でも、無理なダイエットや食生活の乱れ、極端な運動不足などが原因で骨量が著しく低下するケースがあります。
10代や20代であっても骨密度が著しく低いと、将来の骨折リスクが高くなります。このタイプでは原因となる習慣改善が重要になります。
骨粗鬆症の主な病型と特徴まとめ
| 病型 | 主な対象・きっかけ | 特徴 |
|---|---|---|
| 原発性骨粗鬆症 | 閉経後の女性、高齢者 | エストロゲン減少や加齢により骨量が急激に減少しやすい |
| 続発性骨粗鬆症 | 糖尿病、甲状腺機能亢進症、ステロイド長期使用者など | 基礎疾患や薬剤使用が原因で骨量が低下 |
| 若年性骨粗鬆症 | 10代~20代の無理なダイエット、運動不足 | 成長期に十分な骨量が獲得できず将来のリスクが増大 |
骨粗鬆症の症状
骨粗鬆症は骨密度が低下している状態ですが、初期段階では症状が乏しい場合が多いです。ある程度進行すると、背骨や股関節などの部位に影響が出やすくなります。
初期の自覚症状の乏しさ
骨量が少しずつ減少していても、痛みや体の変化を感じにくいため、検診や健康診断で骨密度を測定しない限り気づきにくいです。
そのため、かなり進行した段階でようやく骨折を起こし、骨粗鬆症と診断されるケースが少なくありません。
慢性的な腰痛や背部痛
骨粗鬆症が進行すると、椎体(背骨の骨)が圧迫骨折を起こしやすくなり、慢性的な腰痛や背部痛を訴える人が増えます。
日常生活のちょっとした動作で痛みが出る場合もあります。痛みを放置すると運動量が減少し、骨量がさらに低下するおそれがあるため早めの対処が重要です。
身長の低下や姿勢の変化
背骨の圧迫骨折が起こると、身長が低くなったり、背中が丸まったりします。
50代や60代以降で身長が2cm以上低くなったと感じる場合は骨粗鬆症の可能性を考えるとよいでしょう。姿勢の変化は腰や膝への負担を大きくし、歩行能力にも影響を及ぼします。
骨折のリスク増大
骨粗鬆症が進行すると、軽い転倒や衝撃でも骨折しやすくなります。
特に大腿骨近位部骨折(股関節周囲の骨折)や椎体骨折、手首の骨折(橈骨遠位端骨折)などは高齢者に多く見られます。
骨折をきっかけに寝たきりになるリスクも高まるため、予防や早期治療が重要です。
骨粗鬆症の主な症状と影響
| 症状 | 具体例 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 初期の自覚症状の乏しさ | 無症状のまま骨密度が低下 | 気づかないうちに進行し、骨折リスクが高まる |
| 慢性的な腰痛や背部痛 | 軽い運動や姿勢変更で痛みを感じる | 運動量が減り、さらに骨量低下を招きやすい |
| 身長の低下や姿勢の変化 | 圧迫骨折による身長低下や円背(猫背 | 見た目の変化だけでなく、歩行能力低下の原因にもなる |
| 骨折のリスク増大 | 転倒や軽い衝撃で骨折 | 日常生活が制限され、要介護状態に移行する可能性がある |
- 症状の進行を放置せず、早期発見と対応を心がける
- 生活習慣の改善や定期的な検査を取り入れる
- 違和感や痛みを感じたら医療機関に相談する
このように、骨粗鬆症は初期段階での気づきが難しい一方、放置すると骨折リスクが急激に高まります。少しの違和感や身長変化などにも注意して、早めに受診しましょう。
骨粗鬆症の原因
骨粗鬆症の原因は単一ではなく、多様な要因が複雑に絡み合います。
遺伝的素因や加齢に伴う変化だけでなく、生活習慣や食事内容なども影響します。ここでは骨粗鬆症を引き起こす主な原因に焦点を当てて解説します。
骨粗鬆症の発症には様々なリスク因子が関与します。大きく分けて変えられない因子(年齢、性別、遺伝的要因など)と、変えられる因子(生活習慣や併存症、薬剤など)に分類できます。
加齢と性別
高齢と女性である要素は最大のリスク因子です。女性では閉経に伴うエストロゲン低下が骨量減少を加速させ、男性に比べ有病率が高くなります。
また、高齢になるほど骨折リスクは累積的に上昇します。実際、骨粗鬆症による骨折は女性では55歳以降、男性では65歳以降に増加していきます。
ホルモン異常
性腺機能低下症(女性の早発閉経や卵巣摘出、男性の低テストステロン血症)、甲状腺機能亢進症(甲状腺ホルモンの過剰により骨代謝亢進)、副甲状腺機能亢進症(PTH過剰により骨吸収亢進)、クッシング症候群(糖質コルチコイド過剰)などの内分泌異常は骨密度低下を招きます。
生活習慣
低体重・低BMI(痩せ体型)やカルシウム・ビタミンD摂取不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒などは骨形成を阻害し骨量を減少させる要因です。また長期間の寝たきり・不動状態も骨吸収を促進するためリスクとなります。
併存疾患
前述の内分泌疾患のほか、リウマチ性疾患(関節リウマチなど)、糖尿病、慢性腎臓病、消化吸収障害(炎症性腸疾患、セリアック病、胃切除後など)、慢性肝疾患、造血器疾患(多発性骨髄腫など)も続発性骨粗鬆症の原因となります。
薬剤
グルココルチコイド(ステロイド)の長期全身投与は骨芽細胞のアポトーシス促進※3と骨吸収亢進※4を招き、代表的な薬剤性骨粗鬆症の原因です。
※3アポトーシス促進:細胞が自らの役割を終えたり、異常をきたしたりした際に、能動的かつ計画的に死滅する現象が促進される状態
※4骨吸収亢進:古い骨を溶かして体内に吸収する作用が、新しい骨をつくる作用よりも過剰に活発になっている状態
その他、抗てんかん薬(酵素誘導によりビタミンD代謝亢進)、甲状腺ホルモン製剤(過剰投与)、ヘパリン製剤、アロマターゼ阻害薬(乳癌治療薬)、GnRHアゴニスト(前立腺癌治療薬)なども骨量減少を来すと知られています。
これらを必要とする場合、骨密度モニタリングや予防的な骨粗鬆症治療が考慮されます。
骨折既往と家族歴
自身に脆弱性骨折の既往がある場合、骨密度に関係なく将来の骨折リスクが大幅に増加します。また家族歴、特に親が大腿骨近位部骨折を起こした経験がある場合もリスク因子です。
これら複数のリスク因子が重なるほど骨粗鬆症発症および骨折の可能性は高まります。特に高齢女性で低体重、既往骨折あり、ステロイド服用中といったケースでは集中的な骨粗鬆症対策が必要です。
骨粗鬆症の検査・チェック方法
骨粗鬆症かどうかを判断するためには、骨密度を測定したり血液検査を行ったりといった専門的なチェックが必要です。
ここでは主な検査方法を紹介し、それぞれの特徴や目的を説明します。
骨密度測定(DXA法)
デュアルエナジーX線吸収測定法(DXA法)は、腰椎や大腿骨近位部などの骨密度を精度高く測定する方法です。
X線を2種類のエネルギーで照射し、骨の吸収率を測定して骨密度を算出します。検査時間は短く、被ばく量も少ないので安心して受けられます。
最も一般的な骨密度検査であり、診断の基準となる場合が多いです。標準的には腰椎(L2–L4)や大腿骨近位部の骨密度を測定します。
結果は若年成人平均との偏差値であるTスコアで表され、WHO分類では Tスコア -2.5以下を「骨粗鬆症」、-1.0〜-2.5を「骨量減少(オステオペニア)」、-1.0以上を「正常」と定義します(男性や閉経前女性ではZスコアが参考にされます)。
例えば閉経後女性でTスコアが-2.8であれば骨粗鬆症と診断されます。
また低エネルギー外傷による骨折(脆弱性骨折)の既往がある場合、たとえ骨密度が高くても「骨粗鬆症による骨折」として扱い、積極的な治療介入の対象となります。
血液検査や尿検査
骨代謝のマーカーを確認するために、血液や尿の成分を調べる検査です。
カルシウムやリン、ビタミンDの血中濃度、骨形成マーカー(オステオカルシンなど)や骨吸収マーカー(NTX、CTXなど)を測定し、骨の形成・吸収状態を把握します。
これにより、原因追求や治療方針の決定に役立ちます。
レントゲン検査
骨折の有無や骨形態の変化を確認するためにレントゲン撮影を行います。
レントゲンによって骨質の変化を大まかに把握できる場合もありますが、骨密度の正確な測定はできません。
骨折の有無をチェックする目的や、既に変形が生じていないかを見る際に活用します。
| 主な検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| DXA法 | X線を使い腰椎や大腿骨の骨密度を測定 | 高い精度、検査時間短い | 機器が大きく、医療機関での実施が必要 |
| 血液・尿検査 | 骨代謝マーカーや栄養状態を把握する | 骨粗鬆症の原因追求や治療方針に役立つ | 骨量そのものは測定できない |
| レントゲン検査 | 骨折や形態変化の有無を確認 | 骨変形や骨折を把握しやすい | 骨密度の正確な測定は不可能 |
- DXA法で正確に骨密度を知る
- 超音波測定は簡易チェックとして役立つ
- 血液検査で骨代謝や栄養状態を確認する
- レントゲンで骨折や変形の有無を把握する
骨粗鬆症かどうかを早期に知るには、定期的な骨密度測定や血液検査などを利用して、自分の骨の状態を確認しましょう。
骨粗鬆症の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
骨粗鬆症は骨の健康を回復・維持するために、薬物治療やリハビリテーション、生活習慣の改善が欠かせません。
治療薬の種類やリハビリの方法、一般的な治療期間について詳しく説明します。
薬物治療の種類
骨粗鬆症の薬には、骨吸収を抑える薬や骨形成を促進する薬など、作用が異なるものが存在します。代表的な薬には以下の種類があります。
- ビスホスホネート製剤:骨吸収を抑え、骨折リスクを低減する
- SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター):エストロゲンに似た働きで骨密度を維持
- カルシトニン製剤:骨吸収細胞の働きを抑え、痛みの軽減にも期待
- PTH(副甲状腺ホルモン)製剤:骨形成を促し、新たな骨を作り出す
リハビリテーションの重要性
骨粗鬆症の治療では、適度な運動を取り入れることが重要です。
リハビリでは、筋力トレーニングやバランス訓練を行い、転倒を防ぎながら骨に適度な刺激を与えます。ウォーキングや軽度のジョギング、水中運動などの有酸素運動も筋力維持や骨密度維持に役立ちます。
| リハビリテーションで取り入れる運動の例 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 筋力トレーニング | スクワット、ヒップリフトなど | 下肢や体幹の筋力強化、転倒予防 |
| バランス訓練 | 片足立ち、足踏み台昇降など | バランス能力の向上、転倒リスクの低減 |
| 有酸素運動 | ウォーキング、水泳、軽いジョギング | 骨への負荷と全身の血行促進、心肺機能向上 |
治療期間の目安
骨粗鬆症の治療は短期的に終わるものではありません。薬物治療に加えて、運動習慣や食生活の改善を継続し、少なくとも数年単位で骨密度の回復を目指します。
ビスホスホネート製剤は5年程度をめどに処方されるケースが多いですが、個人の病状や副作用のリスクなどを考慮しながら医師が継続期間を判断します。
生活習慣の改善と食事指導
治療薬やリハビリテーションだけでなく、日常の食事でカルシウムやビタミンD、たんぱく質を十分に摂ります。
魚や大豆製品、乳製品などをバランスよく取り入れ、過度の塩分摂取やアルコール摂取を控えるよう意識します。
栄養管理ではカルシウムは1日700~800mg以上、ビタミンDは800IU程度を目安に、食事(乳製品や小魚、緑黄色野菜など)や日光浴で補います。不足する場合はサプリメントも検討します。
十分なカルシウム・ビタミンD状態は治療薬の効果を高め、転倒予防効果も期待できます。
骨の健康を意識した食事例
| 食材カテゴリー | 具体例 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| カルシウム源 | 牛乳、ヨーグルト、小魚、チーズ | 乳製品以外にも小魚や海藻を積極的に活用する |
| ビタミンD源 | 鮭、サンマ、キノコ類 | 紫外線を適度に浴びると体内合成も期待できる |
| たんぱく質源 | 肉、魚、卵、大豆製品 | 毎食20g程度のたんぱく質を意識して摂取する |
| その他 | 野菜、果物、ナッツ類 | ビタミンやミネラルをバランスよく摂る |
骨粗鬆症の治療では、薬物療法と運動療法、そして食事を含む生活習慣の整備が相互に大切です。これらを無理なく継続すると、骨の健康を維持しやすくなります。
薬の副作用や治療のデメリット
骨粗鬆症の治療薬は一定の効果が期待できますが、副作用がまったくないわけではありません。治療に伴うリスクも知っておくと、より適切な判断ができます。
ビスホスホネート製剤の副作用
ビスホスホネート製剤は骨粗鬆症治療薬の中でも幅広く使われていますが、胃腸障害(胃もたれ、吐き気、便秘など)を起こしやすい人がいます。
服用後にしばらく横にならないよう指示を受ける場合もあります。また、まれに顎骨壊死という重い副作用が報告されています。歯科治療を受けるタイミングや口腔内ケアにも注意が必要です。
SERMの副作用
SERMはエストロゲンと似た働きをする一方、子宮内膜や乳腺に与える影響が心配されます。ただし、適切な用量と医師の管理下で使えば大きな問題になるケースは多くありません。
血栓症のリスクがやや上昇する可能性があるため、足の痛みや腫れ、呼吸苦などの異変を感じたら早急に受診するとよいでしょう。
PTH製剤のデメリット
副甲状腺ホルモン製剤は骨形成を促進する効果がある一方、注射療法が主流であるため、通院や自己注射の負担がかかります。
また、長期使用に関しては注意が必要で、一般的に2年を超えない範囲で使うのが通例となっています。費用の面でも比較的高額になる場合があります。
その他の考慮点
薬の種類によっては、継続的な血液検査や定期検診が欠かせない場合があります。
副作用リスクを踏まえながら、医師と相談しつつ適切な薬を選ぶ必要があります。飲み忘れや中断が効果の低下につながる点にも注意しなければなりません。
骨粗鬆症治療薬の副作用やデメリットまとめ
| 薬の種類 | 主な副作用・デメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| ビスホスホネート | 胃腸障害、顎骨壊死(まれ)、服用後の姿勢制限 | 服用方法や歯科受診のタイミングに注意 |
| SERM | 血栓症リスク増大、子宮内膜や乳腺への影響の懸念 | 定期的な検診と異変があれば早期受診 |
| PTH製剤 | 注射治療の負担、費用が高め | 使用期間や手技の理解が必要 |
| カルシトニン製剤 | 吐き気や発疹、注射時の痛みなど | 医師と症状を共有して、副作用をコントロールする |
副作用の程度には個人差があり、必ずしも発症するわけではありません。しかし、治療を続ける上でリスクを把握し、医師と相談して適切な対応を取ることが大切です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
骨粗鬆症の治療費は、検査費用や薬代、リハビリテーション費用など複数の要素から成り立ちます。
健康保険の適用範囲を理解しておくと、費用面の不安を軽減しやすくなります。ここでは治療費に関する目安を紹介します。
検査費用の目安
DXA法による骨密度検査の場合、健康保険適用の条件を満たせば3割負担の方でおよそ1000~2000円程度です。初診料や医師の診断料を含めると、合計で2000~3000円程度になる場合があります。
超音波検査のみを実施する場合はもう少し安価になる傾向がありますが、精度の面を考慮してDXA法を選択するケースが多いです。
薬代の目安
ビスホスホネート製剤の中でも週1回や月1回の服用タイプは、3割負担の方で1か月あたりおよそ1000~2000円程度です。
注射タイプの場合は医療機関での処置料も加わり、1回あたり2000~4000円程度かかることがあります。PTH製剤などはさらに高額になる場合があり、1か月あたり3割負担で5000円~1万円近くになるケースも珍しくありません。
リハビリテーション費用
医療機関でのリハビリ指導を受ける場合、保険適用で1回あたり数百円~1000円ほどの自己負担が発生します(3割負担の場合)。
回数や期間によって変動しますが、定期的に通うと月に数千円程度になる人が多いです。自宅で行う運動療法は費用がかからないメリットがありますが、正しい方法を習得するために初期段階で専門指導を受けるとよいでしょう。
治療にかかる総額のイメージ
骨粗鬆症の治療は長期間に及ぶため、月々の負担額が積み重なる点に注意が必要です。月1回の通院で薬と検査を合わせると、3割負担の方で1500~3000円程度が相場となります。
| 項目 | 3割負担の場合の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 骨密度検査(DXA法) | 約1000~2000円 | 初診料などを含めると2000~3000円に増える可能性がある |
| 薬代(ビスホスホネート) | 月1回タイプで1000~2000円程度 | 注射タイプは1回2000~4000円程度 |
| 薬代(PTH製剤) | 月1万円近くになる可能性がある | 費用が高めなので医師と相談しながら慎重に導入する |
| 薬代(PTH製剤) | 1回あたり数百円~1000円程度 | 回数・内容によって変動し、月数千円の負担となる場合が多い |
以上
参考文献
RACHNER, Tilman D.; KHOSLA, Sundeep; HOFBAUER, Lorenz C. Osteoporosis: now and the future. The Lancet, 2011, 377.9773: 1276-1287.
SÖZEN, Tümay; ÖZIŞIK, Lale; BAŞARAN, Nursel Çalık. An overview and management of osteoporosis. European journal of rheumatology, 2016, 4.1: 46.
SOZEN, Tumay; OZISIK, Lale; BASARAN, Nursel Calik. An overview and management of osteoporosis. European journal of rheumatology, 2017, 4.1: 46-57.
MARCUS, Robert, et al. (ed.). Osteoporosis. Academic Press, 2013.
LIN, Julie T.; LANE, Joseph M. Osteoporosis: a review. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 2004, 425: 126-134.
CHRISTODOULOU, C.; COOPER, C. What is osteoporosis?. Postgraduate medical journal, 2003, 79.929: 133-138.
MARCUS, Robert, et al. (ed.). Osteoporosis. Academic Press, 2007.
COOPER, Cyrus. Epidemiology of osteoporosis. Osteoporosis international, 1999, 9: S2.
LORENTZON, Mattias; CUMMINGS, Steven R. Osteoporosis: the evolution of a diagnosis. Journal of internal medicine, 2015, 277.6: 650-661.
GLASER, David L.; KAPLAN, Frederick S. Osteoporosis: definition and clinical presentation. Spine, 1997, 22.24: 12S-16S.