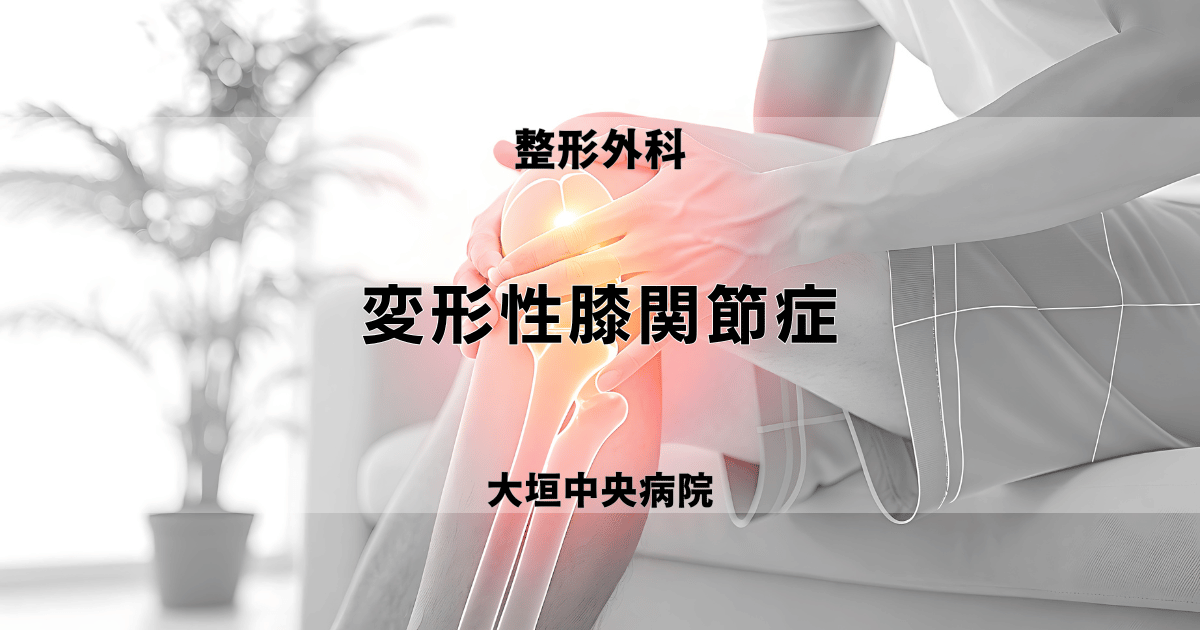変形性膝関節症(Osteoarthritis of the knee, OA)とは、膝の関節軟骨がすり減って変形や炎症を引き起こす疾患です。
加齢や使いすぎ、姿勢などの複数の要因が重なって発症し、痛みや動きの制限を生むため日常生活へ大きな支障が出る場合があります。
中高年のなかでも女性に多く、85歳までに変形性膝関節症を発症する生涯リスクは25~40%と報告されています。
症状の進行度合いは個人差があり、適切な治療と生活習慣の改善による症状のコントロールが大切です。
変形性膝関節症の人工膝関節手術なら大垣中央病院(岐阜県大垣市)
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
変形性膝関節症の病型
変形性膝関節症には、原因や変形の進む場所によって複数のタイプが存在します。
適切な治療方針を決めるためにも、どの病型に該当するかの確認が重要です。
| 病型 | 特徴 | 主な原因例 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 原発性 | 加齢・遺伝的要因による軟骨の摩耗 | 年齢、生活習慣、遺伝 | 高齢者に多い |
| 続発性 | 外傷や別の病気によって軟骨が傷む | スポーツ外傷、リウマチ、骨壊死など | 若年層にも見られる |
| 内側型 | 膝関節の内側が変形しやすくO脚のようになる | 体重負荷の不均衡、長期間の膝の酷使 | 日本人に比較的多い |
| 外側型 | 膝関節の外側が変形しやすくX脚のようになる | 外傷、関節炎、先天的要因 | 内側型より少ない |
| 膝蓋大腿関節型 | 膝蓋骨と大腿骨の間の軟骨変性 | 正座や階段昇降での負荷、骨格的要因 | 階段の昇降で痛みやすい |
原発性変形性膝関節症
加齢や遺伝的素因など、直接的な外傷や別の病気がない状態で発症するものを「原発性(一次性)」と呼びます。
膝の軟骨が加齢とともに摩耗し、痛みやこわばりを引き起こします。生活習慣や膝への負担のかかり方が影響するため、運動習慣や体重管理が症状の進行に大きく関係し、高齢者に好発します。
続発性変形性膝関節症
膝の外傷やリウマチなど、別の病気や要因が存在している場合に発症するものを「続発性(二次性)」と呼びます。事故やスポーツなどの怪我、関節内の炎症性疾患によって軟骨が傷みやすくなり、変形や痛みが生じます。
関節内骨折や半月板損傷などの外傷後変形、先天的な関節異常(例:発育不全)、関節炎性疾患(例:関節リウマチや痛風、偽痛風)、代謝性疾患(例:軟骨石症(CPPD)やヘモクロマトーシス)などが原因となります。
根本原因を特定し、適切な治療を並行して行って進行を抑制します。
内側型と外側型
膝関節のどの部分に変形が集中するかによって、内側型と外側型に分けられます。
一般的には内側型が多く、O脚のような変形が生じます。一方、外側型はX脚のような変形を起こすケースが多いです。
これらのタイプは歩行スタイル(歩き方)にも大きな影響を及ぼします。
膝蓋大腿関節型
膝のお皿(膝蓋骨)と太ももの骨(大腿骨)の間にある関節に起きる変形が膝蓋大腿関節型です。階段の上り下りや正座など、お皿に負荷がかかる動作で痛みを感じやすい傾向があります。
関節周囲の筋力低下やアライメント※1の崩れが原因となりやすいです。
※1アライメント:骨や関節が正しい位置に整列している状態。アライメントが正常であれば身体にかかる負担が最小限となる。逆にアライメントが崩れると痛みや運動能力の低下などのトラブルが起きやすく、一部のアライメントが崩れると連動するように他のアライメントも崩れやすい。
- 病型によって発症メカニズムや治療方法が異なる
- 違和感や痛みの種類・強度が変化する
- 合併症状の可能性がある
このように複数の視点から自分の膝の状態を把握しておくと、治療や予防を進めやすくなります。
重度分類
他に重症度分類があります。変形性膝関節症(膝OA)の重症度は、X線所見に基づいてKellgren–Lawrence(K-L)分類で5段階に評価されます。
| 分類 | 状態 |
|---|---|
| Grade 0 | 正常 |
| Grade 1 | 関節裂隙狭小化が不確実でわずかな骨棘形成のみ、Grade 2(軽度)で明らかな骨棘形成と狭小化の可能性 |
| Grade 3(中等度) | 複数の中等度骨棘と明確な関節裂隙狭小化、骨硬化像、骨端変形の可能性 |
| Grade 4(重度) | 大きな骨棘と関節裂隙の著明な消失、重度の硬化像と骨端の明らかな変形を伴う |
一般にK-L分類のGrade2以上を放射線学的に変形性膝関節症(膝OA)ありと定義し、Grade 3以上は進行期、Grade 4は末期的な重度の変形性膝関節症と判断されます。
レントゲン所見の重症度と症状の強さは必ずしも相関しない点も重要です。
変形性膝関節症の症状
変形性膝関節症の症状は、初期は軽度の違和感程度から始まり、進行すると強い痛みや機能障害につながるケースがあります。
主症状は膝の疼痛と可動域制限です。典型的には徐々に出現・進行する膝関節痛で、動作時や荷重時に増悪し休息で軽快します。
初期症状|朝のこわばりや動き始めの痛み
初期段階では、起床後や椅子から立ち上がるときなど、動き始めに膝に痛みやこわばりを感じる場合が多いです。
しばらく動くと痛みが緩和する場合もあるため、単なる「年齢のせい」と思って放置する人も少なくありません。
中期症状|膝の腫れや熱感、階段の昇降時の痛み
進行してくると膝関節内に炎症が起こりやすくなり、腫れや熱っぽさを感じるときがあります。
階段の上り下りがつらくなる、正座が苦痛になるなど、日常動作に支障が出る症状が増えます。慢性的なだるさや違和感を抱える人も多くいます。
変形の出現|O脚やX脚、膝のお皿周辺の痛み
内側型が進行するとO脚の傾向が強まり、外側型だとX脚に近い状態になります。見た目の変化だけではなく、膝がしっかりと曲げ伸ばしできないなど、機能面でも支障をきたします。
また、膝蓋大腿関節型の場合は、膝のお皿まわりに鋭い痛みが出るときが増えます。
重度症状|歩行困難や夜間痛
さらに進行すると、ひざが曲がらない、あるいは伸ばせないといった可動域の制限が顕著になります。
痛みで夜に眠れない夜間痛、歩行そのものが困難になる場合もあり、日常生活の質が大きく低下します。
症状の進行度比較
| 症状の段階 | 特徴 | 具体的な例 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 動き始めの痛み、こわばり | 朝起きた際や立ち上がり時の膝痛 | 軽度で済むことが多い |
| 中期 | 階段昇降時の痛み、腫れ、熱感、正座の困難 | 膝の内側・お皿周辺がズキズキと痛む | 生活に制限が出やすい |
| 変形期 | O脚・X脚などの変形が顕著 | 膝が曲がりにくい、歩き方の乱れ | 見た目・機能ともに影響大 |
| 重度 | 夜間痛、可動域制限、歩行困難 | 長距離移動が難しい、膝がほとんど曲げられない | 日常生活が大幅に制限される |
進行度が高まると日常動作に大きな影響が出るため、違和感を覚えた時点で整形外科への相談を検討しましょう。
- 症状が軽度のうちに適切なケアを始めるのが望ましい
- 痛みが強いと運動機会を失い、さらに筋力が低下する悪循環に陥る
- 変形が進行すると元の状態に戻すのは難しい
こうした点を念頭に置き、日頃から膝の調子をチェックしておくと早期発見につながります。
変形性膝関節症の原因
変形性膝関節症は、局所の関節要因と全身的な因子が複合的に関与します。早期から原因を理解しておくと、発症や進行の予防に役立ちます。
具体的な危険因子は、加齢や性別、体重やアライメント異常です。
加齢
加齢によって関節軟骨の再生能力が低下すると、膝関節にかかる衝撃を十分に吸収できなくなります。この結果、軟骨の摩耗が生じ、修復能力低下と重なり50歳以上で有病率が急増します。
性別
女性に多く、閉経後の女性ホルモン低下も関与すると考えられています
体重増加や肥満
膝関節は体重を支える重要な部位のため、体重が重ければ重いほど負荷が高まります。肥満(高BMI)は、膝への機械的負荷を増大させる最大のリスク因子です。
体重増加は変形性膝関節症や膝関節手術のリスクを有意に高めると報告されており、5~10%の減量で疼痛が有意に改善するとのエビデンスがあります。
運動不足や偏った運動
適度な運動は関節の血行促進と筋力維持につながる一方、激しい運動や偏った動きは関節を傷める原因になります。
また運動不足で太ももの筋力が低下すると、関節支持機構を弱め膝に集中的に負荷がかかりやすくなるため、変形性膝関節症のリスクが上がります。
アライメント異常
先天・後天的な下肢の変形(O脚・X脚)や膝関節の不安定性は、関節内荷重が偏るため軟骨を片側で過度に消耗させます。
実際、内側型変形性膝関節症では内反変形(O脚)が、外側型変形性膝関節症では外反変形(X脚)が進行します。
外傷や他疾患からの影響
スポーツ外傷や仕事中の事故などで膝を負傷すると(半月板損傷、靱帯断裂、骨折など)軟骨がダメージを受けやすくなります。
リウマチなどの関節炎でも軟骨や骨が侵されるため、結果として変形性膝関節症を引き起こしやすいです。
これらは続発性(二次性)変形性膝関節症として分類され、原因疾患の治療が必要です。
その他の原因
他にも、反復動作を伴う職業(ひざをつく作業や重労働など)、激しい運動歴(特に膝へ高負荷のスポーツ)、先天性股関節脱臼など他関節の変形、代謝疾患(糖尿病、痛風、石灰沈着性腱炎症など)も変形性膝関節症のリスクを高めるとされています。
主な原因
| 原因 | 具体的な内容 | 結果 | 対策の例 |
|---|---|---|---|
| 加齢 | 軟骨の再生能力低下 | 関節軟骨がすり減る | 早期のリハビリ、定期的な検診 |
| 体重増加・肥満 | 膝への負荷増大 | 軟骨の摩耗進行 | 体重管理、適度な有酸素運動 |
| 運動不足・偏った運動 | 血行不良・筋力低下や局所的な負荷 | 膝への負担増大 | ストレッチと筋力トレーニングの両立 |
| 外傷 | 事故やスポーツによる骨・軟骨損傷 | 軟骨破損、変形の加速 | 適切なリハビリと早期受診 |
| 他疾患 | リウマチや他の関節炎、骨壊死など | 二次的に変形を発症 | 原因疾患の治療と併行した膝のケア |
これらの要因が複数重なって変形性膝関節症を引き起こすケースも多いため、一つひとつのリスク要因をできる範囲で減らす工夫が予防につながります。
- 適正体重の維持と無理のない運動習慣が重要
- 膝を冷やさないように工夫すると血行促進に寄与する
- 怪我をした後は放置せず、専門家に相談してリハビリを行う
変形性膝関節症の検査・チェック方法
整形外科での検査やセルフチェックを通じて、膝の状態を客観的に把握できます。
正確な診断に基づいた治療を始めるために、どのような検査があるかを確認しておきましょう。
問診・視診・触診
医師が痛みの程度や場所、生活習慣などを詳しく尋ねます。その後、膝を見たり触ったりして腫れの有無や変形、熱感などをチェックします。
この初期段階でおおまかな見立てを立て、必要に応じて画像検査へ進みます。
例として「膝痛とX線骨棘があり、50歳以上、朝のこわばり<30分、運動時軋轢音を伴う」といった条件で診断精度が高いとされています。
実際にはレントゲン検査と合わせて診断するケースがほとんどです。
X線検査(レントゲン)
膝の関節空間の狭まり具合や骨の変形状態、骨棘(骨のとげ)の有無などを確認するためにX線検査を行います。
進行度合いの把握に役立ち、他の関節疾患との鑑別も行いやすいです。ただし、軟骨そのものは映りにくいです。
MRI検査
MRIでは軟骨や半月板、靭帯などの軟部組織を詳細に確認できます。早期段階の軟骨の損傷や炎症を正確に把握できるため、より精密な診断を行いたい場合に用いられます。
時間がかかるといった負担はありますが、手術の適応判断や複雑な外傷の有無を確認する際に役立ちます。
関節液検査
強い炎症や腫れがある場合、関節液を抜き取って検査するケースがあります。
感染症やリウマチなどが疑われる場合は特に重要で、変形性膝関節症かどうかを鑑別する手がかりとなります。
関節液の外観(透明~混濁)や白血球数・結晶の有無を解析すると、痛風・偽痛風など結晶誘発性関節炎や感染性関節炎との鑑別が可能です。
主な検査方法の特徴
| 検査方法 | 主な目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 問診・視診・触診 | 痛みの度合い、変形や腫れの状態を確認 | 簡易で即時性が高い | 主観的情報が中心 |
| X線検査 | 骨の変形や関節間隙の狭小化を確認 | 施設が多く、コストが比較的低い | 軟部組織の損傷は分かりにくい |
| MRI検査 | 軟骨や半月板、靭帯など軟部組織を詳細に確認 | 早期段階の軟骨異常を捉えやすい | 時間とコストの負担が大きい |
| 関節液検査 | 感染症や炎症性疾患の有無を判断 | 病因の特定が可能 | 採取時に痛みやリスクが伴う |
症状や疑わしい原因に応じて、医師が複数の検査を組み合わせて総合的に診断します。
自分の症状をしっかり観察し、医師との対話を大切にしながら検査を受けると、より正確な診断に近づきやすいです。
- 自宅でも膝の腫れや熱感を日々観察して、変化に気づくようにする
- 痛みの度合いを「いつ・どの程度・どんな動作で」感じるかをメモすると医師に伝えやすい
- 血液検査で炎症反応やリウマチ因子を調べる場合もある
変形性膝関節症の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
変形性膝関節症の治療は、痛みの緩和と機能の維持・向上を目指して進めます。患者さんの症状や生活スタイルに合った治療プランを選ぶと、日常生活の質を高められます。
基本的には保存療法を第一選択とし、十分な改善が得られない場合に外科的治療(手術)を検討します。
保存療法|薬物療法や物理療法
- 消炎鎮痛薬(NSAIDs)や塗り薬などで痛みと炎症を抑える
- ホットパックや低周波治療、超音波治療で血行を促進し、痛みを緩和する
- 適度な運動やストレッチによる筋力強化と可動域の維持
保存療法では、日常生活の改善やリハビリ、痛み止めの内服薬、外用薬、物理療法などを中心に行います。
軽度から中等度の症状に適しており、多くの患者さんが第一選択として受けます。
リハビリテーションの目的
| リハビリ項目 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 筋力強化 | 膝を支える太もも周りの筋肉を鍛えて負担を軽減 | スクワット、レッグエクステンションなど |
| 柔軟性向上 | 関節や筋肉のこわばりをほぐし可動域を広げる | ストレッチ、ヨガポーズ |
| バランス訓練 | 転倒予防と下半身の安定性の向上 | 片脚立ち、バランスディスクの活用 |
| 有酸素運動 | 血行促進と体重管理 | ウォーキング、水中ウォーキングなど |
こうしたリハビリを組み合わせながら膝の痛みを緩和し、長期的な機能維持を目指します。
関節内注射
痛みが強い場合や炎症が激しい場合、ヒアルロン酸やステロイド、PRP(多血小板血漿)などを膝関節内に注射する方法があります。
ヒアルロン酸には関節を潤滑にする効果が期待され、ステロイドには強い抗炎症作用があります。
ただし、注射の回数には制限があり、医師が慎重に判断します。
手術療法
保存療法で改善が見られない場合、手術が選択肢に入ります。代表的な手術には、人工膝関節置換術や骨切り術があります。
人工膝関節置換術
保存療法無効な末期の変形性膝関節症に対する根治的手段が人工関節手術です。変形の大きい骨や損傷した軟骨を削り取り、代わりに人工関節を装着します。
患者さんの80~90%が手術結果に満足するとの調査があり、痛みの軽減効果が高く、歩行機能を取り戻しやすいと考えられています。
ただし、術後のリハビリやリスク管理が必要です。
骨切り術
O脚やX脚などの脚の軸のずれを矯正するため、脛骨や大腿骨を一部切って角度を調整し、関節への負担を減らします。
軟骨の残存量が比較的残っている場合や若年で活動的な患者さんに検討されます。
治療期間とリハビリの継続性
- 保存療法は数か月~数年単位で根気強く続ける必要がある
- 注射療法は数週間から数か月間隔で行い、状態を見ながら継続する
- 手術の場合はリハビリを怠ると術後の回復が遅れる
保存療法や注射治療では数か月以上かけて継続し、症状の変化を見ながら治療内容を調整します。手術後は早期離床を目指しますが、通常2~3か月程度のリハビリ期間が必要です。
個人差は大きいですが、術後6か月から1年ほどで日常生活に大きな制限がなくなるケースも多いです。
症状の段階や患者さんの生活スタイルに応じて適切な治療法を見つけると、スムーズな回復につながります。
薬の副作用や治療のデメリット
治療には効果がある一方で、副作用やデメリットも存在します。事前に把握しておくと、安心して治療に向き合いやすくなるでしょう。
消炎鎮痛薬(NSAIDs)の副作用
痛みや炎症を抑えるためによく使う消炎鎮痛薬には、胃腸障害や腎機能への負担などの副作用があります。
長期にわたる内服で胃潰瘍を起こしやすくなるため、医師や薬剤師の指示に従った用法・用量を守る必要があります。
ステロイド注射のリスク
ステロイド注射には強力な抗炎症効果がある一方、過度の注射で軟骨がさらに傷む可能性があります。
糖尿病を持っている方は血糖値のコントロールが乱れやすくなる場合があるため、担当医との綿密な連携が欠かせません。
手術の合併症
人工膝関節置換術などの大きな手術には、感染症や血栓症などのリスクがあります。また、人工関節に寿命があるため、将来的に再手術が必要となるケースもあります。
高齢者や基礎疾患を持つ方では手術リスクが上昇するため、術前の検査での精査や、リハビリテーションなどでの筋力訓練などが大切です。
主な副作用・デメリット
| 治療方法 | 副作用・デメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 消炎鎮痛薬(NSAIDs) | 胃腸障害、腎機能低下、むくみ | 長期使用時には定期的な検査と医師の管理 |
| ステロイド注射 | 軟骨への影響、血糖値コントロール乱れ | 注射の回数や量を慎重に調整する |
| ヒアルロン酸注射 | 効果が一時的、注射時の痛みや腫れ | 定期的な注射が必要な場合がある |
| 人工膝関節置換術 | 感染症リスク、血栓症、再手術の可能性 | 術後のリハビリと定期的な検診が重要 |
| 骨切り術 | 骨癒合期間の負担、二度目以降は技術的に難度上昇 | 適応を慎重に判断し、術後ケアを丁寧に行う |
治療のメリットだけでなくデメリットも十分に理解し、症状や生活スタイルに合った方法を選びましょう。
- 薬や注射に頼りきらず、運動療法やリハビリを取り入れると副作用を抑えつつ効果を狙える
- 手術では成功率が高くても一定のリスクがあると認識する
- デメリットを理解しながら、医師と相談して治療選択を行う
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
変形性膝関節症の治療は内容によって費用が大きく異なり、保険適用の有無も考慮しなくてはなりません。ここでは、主な治療費の目安と保険について解説します。
外来治療と薬の費用
消炎鎮痛薬や塗り薬は医師の処方を受けると健康保険が適用され、自己負担は3割(もしくは1割または2割)となります。
薬の種類や量によって費用が変動しますが、1か月あたり数百円~数千円程度が一般的です。湿布のみであればさらに低額の場合があります。
関節内注射の費用
ヒアルロン酸注射やステロイド注射は保険診療の対象になります。1回あたりの自己負担額はおおよそ数百円~1,500円程度です(3割負担の場合)。
注射の頻度や種類によっても変動するため、医師に相談すると安心です。
手術の費用と入院費
人工膝関節置換術では、健康保険が適用される場合でも数十万円の自己負担になるケースがあります。
ただ、高額療養費制度※2を活用すると一定額以上は負担が軽減される可能性があります。
※2高額療養費制度:1ヶ月にかかる医療費が限度額を超えた際に、超過分が払い戻される制度。限度額は年齢や所得により決定される。
入院費は1日あたり数千円~1万円程度を目安に考えておきましょう。個室を利用すると追加費用が発生するので注意が必要です。
代表的な治療費の目安
| 治療内容 | 保険適用の有無 | 自己負担の目安(3割) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外来診察(初診・再診) | 保険適用 | 1,000~2,500円程度 | 検査内容によって変動 |
| 消炎鎮痛薬・塗り薬 | 保険適用 | 1か月あたり数百円~数千円 | 処方量や薬の種類による |
| ヒアルロン酸注射 | 保険適用 | 1回あたり数百円~1,500円 | 注射の種類・回数で変動 |
| ステロイド注射 | 保険適用 | 1回あたり数百円~1,500円 | 合併症のリスクを考慮 |
| MRI検査 | 保険適用 | 3,000~5,000円程度 | 撮影部位や施設によって差がある |
| 人工膝関節置換術(片膝) | 保険適用 | 数十万円前後(高額療養費適用) | 材料・入院期間で変動 |
| 骨切り術 | 保険適用 | 20万~40万円前後(高額療養費適用) | 術式や入院期間で大きく変化 |
自費診療やリハビリ費用
自費診療で再生医療や独自のリハビリメニューを受ける場合、自由診療として扱われ保険が効きません。
1回あたり数千円から数万円まで幅があり、選択するメリットや効果、リスクを考慮し、経済的な負担も含めて検討する必要があります。
- 高額療養費制度や限度額適用認定証※3を活用すると手術費の負担を軽減しやすい
- 医療保険や介護保険のサービスを組み合わせると費用とケアの両面で助けになる
- 手術を視野に入れる場合は、費用とリハビリ期間を見越した生活設計が大切
※3限度額適用認定証:最終的に負担する金額は高額療養費制度と同じだが、事前に申請して認定証の交付を受け、窓口に提示することで窓口での支払いを限度額までに抑えられる。一度医療費の全額(1~3割負担分)を支払う高額療養費制度に対して、一時的な負担が少なく済むのがメリット。
費用面の不安がある場合も、あらかじめ医師や医療機関の相談窓口などで確認し、必要に応じて制度の活用を検討してください。
以上
参考文献
SHARMA, Leena. Osteoarthritis of the knee. New England Journal of Medicine, 2021, 384.1: 51-59.
ROOS, Ewa M.; ARDEN, Nigel K. Strategies for the prevention of knee osteoarthritis. Nature Reviews Rheumatology, 2016, 12.2: 92-101.
FELSON, David T. Osteoarthritis of the knee. New England Journal of Medicine, 2006, 354.8: 841-848.
HSU, Hunter; SIWIEC, Ryan M. Knee osteoarthritis. 2018.
RINGDAHL, Erika; PANDIT, Sandesh. Treatment of knee osteoarthritis. American family physician, 2011, 83.11: 1287-1292.
HAME, Sharon L.; ALEXANDER, Reginald A. Knee osteoarthritis in women. Current reviews in musculoskeletal medicine, 2013, 6: 182-187.
LESPASIO, Michelle J., et al. Knee osteoarthritis: a primer. The Permanente Journal, 2017, 21: 16-183.
HUSSAIN, S. M., et al. Knee osteoarthritis: a review of management options. Scottish medical journal, 2016, 61.1: 7-16.
FAVERO, Marta, et al. Early knee osteoarthritis. RMD open, 2015, 1.Suppl 1: e000062.
LEE, Ryan; KEAN, Walter F. Obesity and knee osteoarthritis. Inflammopharmacology, 2012, 20: 53-58.