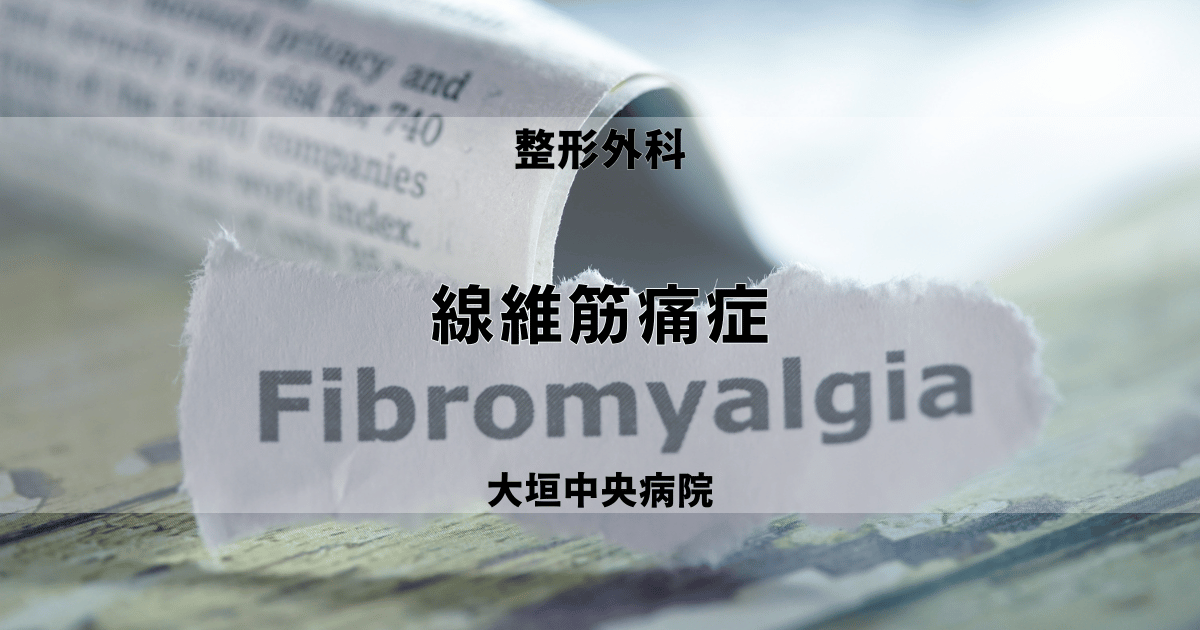線維筋痛症(Fibromyalgia)とは、全身の痛みや倦怠感など多彩な症状が慢性的に続く特徴を持つ病気です。
体の各部位にある筋肉や関節に強い痛みを感じ、日常生活や仕事に支障が生じることがあります。
痛みだけでなく、睡眠障害や精神的なストレス、認知機能低下(ブレインフォグ)などを伴うケースも多く、一人ひとりの症状が異なります。
慢性疾患なので長期的な管理が必要ですが、痛みを和らげる薬やリハビリテーションなどを組み合わせた治療によって症状をコントロールし、生活の質を高めることを目指せます。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
線維筋痛症の病型
線維筋痛症は原発性(一次性)と続発性(二次性)に大別されます。
原発性(一次性)
原発性線維筋痛症は明らかな他疾患による疼痛原因がない場合を指し、線維筋痛症自体が主たる診断名となるものです。
続発性(二次性)
続発性線維筋痛症は他疾患(例えば関節リウマチや変形性関節症、全身性エリテマトーデスなど)による持続的な疼痛刺激が存在する中で併発するタイプで、基礎疾患に付随して線維筋痛症の症候が現れるものを指します。
実際、関節リウマチ患者の約14%が線維筋痛症の診断基準を満たすとの報告もあり、基礎疾患の炎症による痛みと中枢性の過敏痛が重複して存在するケースがあります。
原発性(一次性)と続発性(二次性)のメカニズム
原発性と続発性では発症メカニズムが異なる可能性が示唆されており、原発性線維筋痛症では末梢での疼痛刺激がなくとも中枢神経系の痛覚過敏が発生すると考えられます。
若年性線維筋痛症:JPFS
小児・思春期発症の線維筋痛症(若年性線維筋痛症:JPFS)も知られており、学童~思春期人口の約1~6%にみられるとの報告があります。
JPFSは診断基準や症状は成人と類似しますが、発症年齢が低いため発達段階に応じた対応が必要です。さらに近年の研究では、線維筋痛症患者を症状や生物学的所見の違いからサブグループ分類しようとする試みもなされています。
例えば、炎症性サイトカインの上昇など「炎症性線維筋痛症」と呼べる亜群の存在や、心理的ストレス反応が強い高ストレス・高苦痛サブタイプなどが提唱されています。
ただしこれらのサブタイプ分類はまだ研究段階であり、一般診療に定着するには至っていません。
線維筋痛症の症状
線維筋痛症の代表的な症状は、全身または特定部位にわたる慢性的な痛みです。
ただし痛みの強さや部位は個人によって異なり、日によって変動する場合も多いです。さらに、痛み以外の症状が重なって、生活や仕事に大きく影響を及ぼす場合があります。
全身の筋肉痛やこわばり
全身(上下肢、体幹など広範囲)にわたる筋肉の痛みが最もよく知られています。
朝起きたときに体がこわばったり、筋肉が引きつれるような感覚があったりするため、起床後の準備や通勤がつらくなる人もいます。
体を温めたり、軽いストレッチを行ったりすると一時的に緩和されるケースがあります。
倦怠感や疲労感
体の痛みが続くと、慢性的な疲れを訴える人が非常に多いです。
ちょっとした家事でも疲労が増しやすく、休んでも回復しにくい状態が続く場合があります。仕事や育児、家事との両立が困難になり、日常生活全般に支障が生じるケースも珍しくありません。
集中力の低下や思考力の混乱
いわゆる「ブレインフォグ(頭のもやもや感)」が起こりやすいのも線維筋痛症の特徴の1つです。
痛みに気を取られたり、睡眠不足になったりすると集中力が落ち、思考力が鈍ると感じる患者が多いです。仕事でのミスが増えたり、会議や勉強への意欲が下がったりする場合もあります。
睡眠障害と気分変動
夜に熟睡しづらく、翌朝の寝起きも悪いという症状がよくみられます。慢性の寝不足がストレスを増大させ、イライラや落ち込みを引き起こしやすくします。
精神面での負荷がさらに痛みに影響し、負のサイクルに陥る場合があるため、適切な対策が重要です。
| 症状の広がりやすさ | 広がりやすい部位 | 併発の可能性 |
|---|---|---|
| 筋肉痛・こわばり | 首・肩・背中・腰など | 腱鞘炎や関節痛 |
| 倦怠感・疲労 | 全身 | 免疫力の低下 |
| 睡眠障害 | 日常生活全般 | 気分変動、集中力低下 |
| 集中力低下・ブレインフォグ | 脳機能全般 | 思考力低下によるミス増加 |
主な症状に対処する日常生活の工夫
- 痛みが強いときは無理をせず、こまめに休憩を入れる
- 寝る前にスマートフォンやパソコンの使用を控え、睡眠の質を保つ
- 体を冷やさないよう防寒や入浴を活用する
- 軽いストレッチやマッサージで筋肉を温め、こわばりを軽減する
全身の痛みや倦怠感は目に見えにくいため、周囲の理解が得にくいケースもあります。自分自身の体調変化を早期にキャッチし、医師や家族と相談しながら対策をとりましょう。
線維筋痛症の原因
線維筋痛症の明確な原因はまだ解明されていません。
ただし多くの研究や臨床経験からは、複数の要因が重なって発症リスクが高まるとされる、中枢神経系の疼痛制御異常を中心とした多因子的な病態と考えられています。
遺伝要因、ストレス、神経系の異常など、さまざまな角度から原因を考える必要があります。
近年の研究により、脳内の痛み処理ネットワークにおける機能的結合や神経化学伝達が線維筋痛症では変化していると示されています。
線維筋痛症患者では侵害刺激に対する脳の反応が過敏で、健常者なら痛みと感じない弱い刺激でも痛みとして認識し、繰り返し刺激すると痛みが増強していく時間的加重現象(wind-up)が顕著です。
これは脊髄後角レベルでの興奮性神経伝達(グルタミン酸など)の亢進と、脳内の内因性痛み抑制系の機能不全によるものと考えられます。
このような中枢性感作(central sensitization)こそが線維筋痛症の病態の核であり、痛みの「音量スイッチ」が常に上がった状態とも比喩されます。
その結果、痛覚だけでなく光・音・温度など他の刺激にも過敏となり、一種の全身的な感覚過敏状態が生じていると考えられます。以下に誘因(トリガー)となる要因を示します。
遺伝的要因
親や兄弟姉妹に線維筋痛症の患者がいる場合、発症リスクが高くなる傾向があります(本疾患の発症率が一般集団の約13.6倍に上昇するとの疫学データあり)。
複数の遺伝子が関与すると考えられており、特定の遺伝子変異によって痛みの感受性が高まる可能性があります。
さらに、家族内で同様の生活習慣やストレス環境も影響するようです。
ストレスや心理的要因
過度なストレスやトラウマ体験などがきっかけとなり、脳や神経系の調整機能が乱れるケースが報告されています。
慢性的なストレスを抱えると、痛みのシグナルを抑制する脳内物質が十分に働かなくなり、痛みが増幅されやすくなると考える専門家が多いです。
加えて、精神的な疲労が蓄積すると不安や落ち込みも強まり、症状をさらに複雑化させます。
中枢神経系の過敏性
慢性的な痛みが続く患者には、中枢神経系の過敏性が高まっているケースがあります。
神経が痛みを感じ取る閾値が下がり、通常なら痛みと認識しない程度の刺激でも強い痛みを感じる状態です。
神経伝達物質のアンバランスが原因として指摘されており、痛みが長期化しやすい要因となっています。
ホルモンバランスや免疫のかかわり
女性に多い傾向があるため、女性ホルモンの変動が痛みの増悪に影響するのではないかと考えられています。
さらに、免疫系との関連も指摘されており、自己免疫疾患と併存する患者も一定数います。ホルモンバランスや免疫系の不調が複雑に絡み合うと症状が悪化するケースもあります。
線維筋痛症の発症要因まとめ
| 要因 | 具体的な例 | 影響のメカニズム |
|---|---|---|
| 遺伝的要因 | 家族内で線維筋痛症の患者がいる | 痛み感受性を高める遺伝子変異や生活習慣が重なる |
| ストレス・心理的要因 | 過労、トラウマ、不安・抑うつ | 脳内物質の働きが低下し、痛みを抑制しにくくなる |
| 中枢神経系の過敏性 | 痛みの閾値低下、神経伝達物質の乱れ | 通常以上に痛みを強く感じ、長期化しやすい |
| ホルモン・免疫の異常 | 女性ホルモンの変動、自己免疫疾患 | ホルモンや免疫細胞が組織に影響し、痛みや炎症が増幅する |
上記の要因が1つだけでなく複数重なると、線維筋痛症が発症しやすくなると考えられます。
ストレスを抱え込みやすい性格、環境や生活リズムの乱れなども、複雑にからみあって発症へとつながりやすいです。
線維筋痛症の検査・チェック方法
線維筋痛症の診断には、患者の症状や身体所見を総合的に判断する必要がありますが、基本的には臨床症状に基づく除外診断です。
レントゲンや血液検査など通常の検査では異常が見つからない場合が多いので、痛みの分布や強度、他の疾患との鑑別など多面的なアプローチが求められます。
身体診察と問診
まず症状を詳細に聞き取り、痛みの場所や程度を把握します。全身の筋肉や関節を触診し、痛みを感じるポイントを確認します。
痛みに加えて、睡眠障害や疲労感、気分面なども重要な情報です。問診では普段の生活リズムやストレス状態などを把握し、他の病気との区別を進めます。
血液検査や画像検査
リウマチや甲状腺機能の異常、自己免疫疾患などと区別するために血液検査を行う場合があります。
また、筋肉や関節の構造的な問題を除外するためにレントゲンやMRI検査を用いる場合もあります。これらの検査で大きな異常が見つからない場合、線維筋痛症を疑う一歩となります。
痛み評価スケールや診断基準
近年は痛みの強度を数値化する「痛み評価スケール(VASなど)」や、線維筋痛症の国際的な診断基準(ACR基準)などを組み合わせて診断を行うケースが多いです。
全身のどの部位に痛みがあり、それがどのくらいの期間継続しているかを客観的に把握するためのツールとして役立ちます。
他疾患との鑑別
同様の症状を示す疾患として慢性疲労症候群やリウマチ性疾患などがあります。
これらの疾患との見分けには、血液検査や免疫学的検査、問診が重要な役割を果たします。専門医が多角的に判断し、総合的に線維筋痛症の診断を下します。
痛みの自己チェック例
次のようなポイントに当てはまるかどうかを振り返ると、医療機関を受診する目安になります。
- 朝起きたときに全身のこわばりや痛みを強く感じる
- 階段の上り下りや掃除、買い物などの家事で疲労感が急に強まる
- 夜になっても体の痛みが治まらず、寝付きが悪い
- 慢性的に疲れていて集中力が続かない
これらの症状が続いている場合、整形外科やリウマチ科、ペインクリニックなど専門的に診る医師の受診を検討する価値があります。
ただし診断は時に難しく、平均5年・多くの診療科を経てようやく線維筋痛症と診断される患者もいると報告されています。
| 主な検査方法と目的 | 目的 | 検査結果の特徴 |
|---|---|---|
| 身体診察・問診 | 痛みの部位や生活背景を把握 | 全身の痛みポイントを細かく確認する |
| 血液検査 | 他のリウマチ性疾患や自己免疫疾患などの除外 | 異常が見つからないケースが多い |
| 画像検査(X線・MRI) | 関節や筋肉など器質的な異常の有無を確認 | 目立った異常所見がないケース多数 |
| 痛み評価スケール | 痛みの強度や持続期間の客観的評価 | VASなどで数値化し変化を追いかける |
線維筋痛症の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
線維筋痛症の治療は、薬物療法、リハビリテーション、心理的アプローチなどを組み合わせて行います。痛みの原因が多岐にわたるため、個人に合わせた総合的な治療が重要です。
薬物療法
痛みや睡眠障害、不安・抑うつなどに対処するために、複数の薬を組み合わせる場合があります。主に使用される薬は次のとおりです。
| 薬の種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 抗うつ薬 | デュロキセチン、ミルナシプランなど | 脳内のセロトニンやノルアドレナリンを増やし、痛みを和らげつつ気分の落ち込みを軽減する効果が期待できます。 |
| 神経障害性疼痛薬 | プレガバリン、ガバペンチンなど | 神経の過敏を抑える働きを持ち、筋骨格系の痛みにも有用とされています。 |
| 鎮痛薬 | アセトアミノフェン、NSAIDs | 軽度〜中等度の痛みに対して併用します。ただし、あまり効果を実感しにくい場合もあります。 |
リハビリテーション
適度な運動やストレッチ、温熱療法などによって痛みをやわらげ、身体機能の回復を促します。医師や理学療法士と相談し、痛みの度合いに合わせたプログラムを作ります。
無理に激しい運動をすると逆効果になりやすいため、少しずつ負荷を上げる方法がよくとられます。
有酸素運動と筋力トレーニングは痛みと睡眠の質の改善に有用であり、太極拳やヨガ等の心身運動や筋力トレーニングは疲労感の軽減にも特に有効だったとする分析があります。
| リハビリの種類 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 有酸素運動 | ウォーキング、軽いジョギング、水中運動など | 血行促進、筋肉と心肺機能の改善 |
| ストレッチ | 筋肉を伸ばす動作を中心に行う | 筋肉のこわばりを解消、柔軟性向上 |
| 温熱療法 | ホットパックや温浴、温泉療法など | 血流の改善、痛み軽減 |
| 理学療法 | 専門家の指導のもと、筋力トレーニングやマッサージ | 体幹強化や負担の少ない姿勢づくり |
運動やリハビリを始めるときは、身体の状態を把握しながら、少しずつチャレンジしていきます。
心理的アプローチとカウンセリング
痛みが長期化すると気分の落ち込みや不安感を抱きやすいため、カウンセリングや認知行動療法など心理的ケアも有用です。
痛みに対する認識を整理し、ストレスや不安との向き合い方を学ぶと、痛みに対する反応が変化する可能性があります。
- 認知行動療法で痛みとの付き合い方を学ぶ
- ストレスマネジメントで交感神経の過緊張を和らげる
- リラクゼーション法で筋肉の緊張をほどきやすくする
治療期間の目安
線維筋痛症の治療は一時的なものでなく、長期にわたる場合が多いです。症状の変動が大きい人ほど治療期間が長くなる傾向があります。
半年から1年以上かけて段階的に痛みや疲労感をコントロールし、生活の質を改善していきます。
定期的な通院やリハビリを継続しながら、必要に応じて薬の種類や用量を調整します。
普段の生活のなかで意識すると良いポイント
- ストレッチや軽い体操を習慣化し、筋肉のこわばりを和らげる
- 睡眠時間や質を見直し、適度なリラックス方法を見つける
- 疲れを感じたら休憩をとり、体を冷やさない工夫をする
- 医師の指導に基づき、薬の服用を自己判断でやめたり増やしたりしない
このような取り組みを続けると、少しずつ痛みや疲労をコントロールできるようになるケースが多いです。
薬の副作用や治療のデメリット
線維筋痛症に用いられる薬は、痛みを緩和するために重要ですが、副作用が生じる可能性もあります。
抗うつ薬の副作用
抗うつ薬(SNRI、SSRIなど)は脳内物質のバランスを整えて痛みを緩和し、精神面の安定もサポートしますが、下記のような副作用が現れる場合があります。
- 眠気やだるさ
- 口の渇き
- 食欲変化
- 便秘や下痢
副作用が強いと感じた場合は、医師に相談したうえで薬の種類や用量を調整する必要があります。
神経障害性疼痛薬の副作用
プレガバリンやガバペンチンなどの神経障害性疼痛薬には、めまいやふらつき、体重増加などの副作用が報告されています。
最初は低用量から始め、徐々に増量して副作用を観察しながら使うケースが一般的です。
鎮痛薬のデメリット
アセトアミノフェンやNSAIDsなどの鎮痛薬は、痛みを抑えやすい一方で長期使用によって胃腸障害や肝機能への負担が懸念されます。
痛みが強いときに一時的に使うなど、適切な用量と頻度を守ることが大切です。
リハビリ・運動療法のリスク
適切な負荷量を守らずに急激に運動量を増やすと、筋肉や関節に負担がかかりすぎ、逆に痛みが増す場合があります。
専門家の指導を受けて、自分の体調に合わせた運動プログラムを実践すると安全です。
副作用と対処法の一覧
| 薬・治療法 | 主な副作用・デメリット | 対処法 |
|---|---|---|
| 抗うつ薬 | 眠気、口渇、消化器症状、体重変化など | 用量の調整、こまめな水分補給 |
| 神経障害性疼痛薬 | めまい、ふらつき、体重増加 | 徐々に増量し、注意深くモニタリング |
| 鎮痛薬 | 胃腸障害、肝機能への負担 | 長期連用を避け、必要時のみの服用 |
| 運動療法・リハビリ | 運動量が急激に増えると痛みや疲労が悪化 | 専門家のアドバイスに従い適切な負荷 |
治療中に「何となく調子が悪い」「いつもより強い痛みが続く」といった変化を感じたら、早めに医師に相談してください。
適切に対処すると、副作用やデメリットを最小限に抑えて治療を続けやすくなるでしょう。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
線維筋痛症の治療には保険が適用される場合が多く、患者の経済的負担を軽減する制度が整備されています。
ただし治療法や薬の種類によっては自費となるものもあるため、事前に医療機関で確認することをおすすめします。
保険適用の範囲
整形外科やリウマチ科、ペインクリニック、精神科など、医師が診断や治療に必要と判断した検査や処方薬、リハビリテーションなどは一般的に保険適用となります。
検査では血液検査やレントゲン撮影、MRI検査、薬の処方などで健康保険の適用を受けられる場合が多いです。
治療費の目安
保険適用による自己負担率が3割の場合を想定すると、1カ月あたりの治療費はおおむね次のようになります(個人差あり)。
- 外来受診料:約1000〜2000円
- リハビリテーション費用(週1〜2回):約1000〜3000円
- 薬代(抗うつ薬・神経障害性疼痛薬など併用):約2000〜5000円
慢性的な通院が必要な場合は、合計で毎月5000円〜1万円ほどかかるケースもあります。症状が重く検査や投薬が増える場合は、さらに費用が高くなる可能性があります。
治療費の大まかな内訳(3割負担の場合)
| 項目 | 目安料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 外来受診料 | 1000〜2000円 | クリニックや病院ごとに多少の差がある |
| 検査費(血液検査・画像) | 1000〜3000円程度 | MRIの場合はもう少し高額になる場合あり |
| リハビリテーション費 | 1000〜3000円(週1〜2回) | 内容や頻度によって変動 |
| 薬代(1カ月) | 2000〜5000円 | 複数の薬を併用する場合、金額が上乗せされる |
自費診療
一部のサプリメントや補完医療(鍼灸、マッサージなど)は保険適用外となることがあります。
保険適用外の施術や薬を希望する場合は、事前に金額を確認してから検討することが大切です。
以上
参考文献
HÄUSER, Winfried, et al. Fibromyalgia. Nature reviews Disease primers, 2015, 1.1: 1-16.
CHAKRABARTY, Sangita; ZOOROB, Roger. Fibromyalgia. American family physician, 2007, 76.2: 247-254.
RAHMAN, Anisur; UNDERWOOD, Martin; CARNES, Dawn. Fibromyalgia. Bmj, 2014, 348.
CLAUW, Daniel J. Fibromyalgia: a clinical review. Jama, 2014, 311.15: 1547-1555.
CLAUW, Daniel J. Fibromyalgia: an overview. The American journal of medicine, 2009, 122.12: S3-S13.
SUMPTON, Janice E.; MOULIN, Dwight E. Fibromyalgia. Handbook of clinical neurology, 2014, 119: 513-527.
CLAUW, Daniel J., et al. The science of fibromyalgia. In: Mayo clinic proceedings. Elsevier, 2011. p. 907-911.
WOLFE, Frederick. Fibromyalgia. Rheumatic Disease Clinics of North America, 1990, 16.3: 681-698.
BRADLEY, Laurence A. Pathophysiology of fibromyalgia. The American journal of medicine, 2009, 122.12: S22-S30.
BORCHERS, Andrea T.; GERSHWIN, M. Eric. Fibromyalgia: a critical and comprehensive review. Clinical reviews in allergy & immunology, 2015, 49: 100-151.