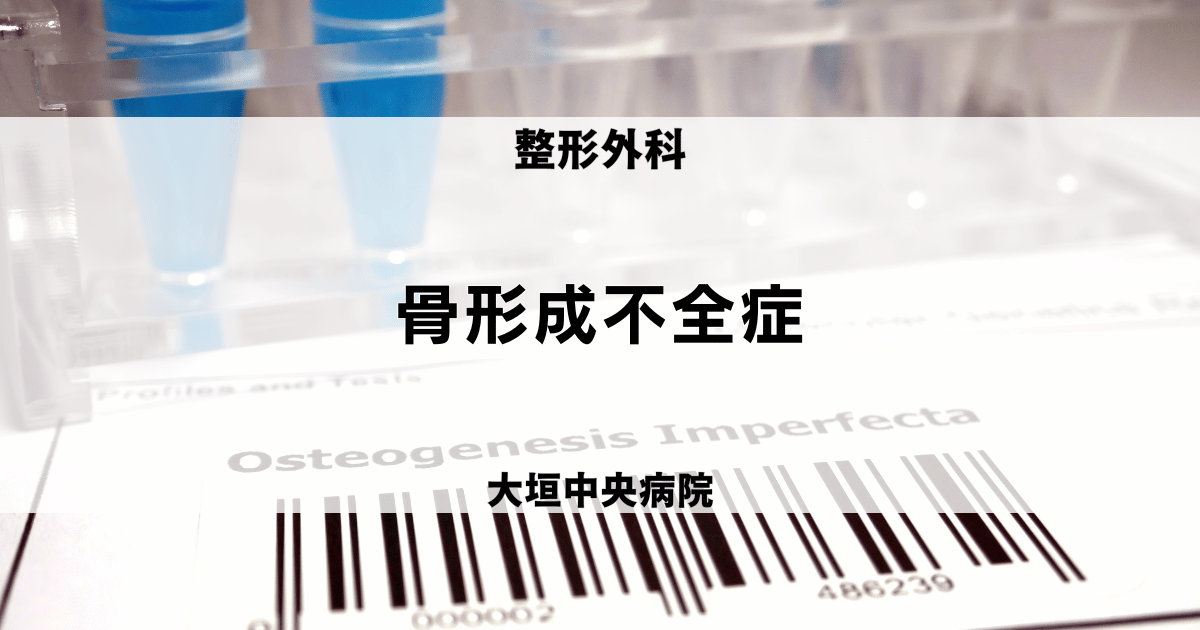骨形成不全症(Osteogenesis Imperfecta、OI)とは、先天的に骨の形成を担うコラーゲンに異常があることで骨が脆くなり、わずかな衝撃でも骨折を生じやすくなる遺伝性疾患です。
世界的にもまれな病気ではありますが、日本国内にも一定の患者様が存在し、子どもから成人まで幅広い年齢層で骨折や骨変形などの症状に悩む方がいます。
遺伝形式や症状には個人差が大きく、適切な知識と治療を得ることが大切です。
典型的には幼少期から軽微な衝撃で繰り返し骨折し、成長とともに骨変形や身長の低さが目立ちますが、青色強膜や歯の脆さ、難聴など骨以外の結合組織症状も伴う疾患です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨形成不全症の病型
骨形成不全症は 症状の重症度や遺伝形式に応じて複数の病型(タイプ)に分類 されます。
最も広く用いられているのは1979年にSillenceらが提唱した古典的分類で、I型(軽症・非変形型)、II型(周産期致死型)、III型(重症・進行変形型)、IV型(中等症型)の4つです。
後に特徴的な亜型として、V型(骨間膜の石灰化や過形成性仮骨〈異常な骨折治癒過程〉を伴う型)が追加で報告されています。
I型
四肢の変形を伴わない軽症で身長もほぼ正常ですが骨折しやすく、眼球強膜が青灰色を呈し(青色強膜)、成人期以降に難聴を来しやすいのが特徴です。
II型
出生前後に多数の骨折・骨変形を起こし、呼吸障害などで新生児期に致死的となる最も重篤な型です。
III型
出生時には存命するものの乳幼児期から繰り返す骨折により高度の骨変形と極度の低身長を呈する重症進行型です。
IV型
中等度の重症度で、骨変形はあるもののI型より重くIII型より軽い中間的な表現型です。
V型
中等症で骨折後に過剰な仮骨形成を起こしたり前腕骨間膜の異常石灰化が見られる特殊型です。近年の遺伝学的研究によりOIの原因遺伝子が次々と発見され、遺伝子型に基づく新たな分類も提案されています。
その他の型
2019年の骨系統疾患国際分類では上記I~V型に加えて、他の原因遺伝子による「その他の型」が含まれるとされ、2021年にはBotorらにより少なくとも19種類以上のタイプに及ぶ拡張分類も報告されています。
しかし臨床的にはSillence分類にもとづく「軽症・中等症・重症」の区分やタイプI~Vの呼称が依然有用であり、リハビリテーションなどの指針でもこちらが用いられる場合があります。
患者様個々の状態に応じて病型を踏まえた重症度評価を行い、治療方針を決定します。
Sillence分類の主なタイプと特徴
下記のように、Sillence分類ではいくつかのタイプを区別します。
骨形成不全症の主な病型
| タイプ | 主な特徴 | 遺伝形式 | 症状の程度 |
|---|---|---|---|
| 軽症型 | 成人になるまでに骨折回数がやや多い傾向 | 常染色体優性遺伝 | 比較的軽度の骨折、難聴、軽度の脆弱性など |
| 重症型 | 多くの場合、新生児期に重篤な骨折や呼吸困難が生じる | 常染色体優性遺伝など | 極端に短い四肢、肺の発達不良、致死的予後の場合も |
| 進行性かつ重症 | 出生直後から骨折や骨変形の頻度が高い | 常染色体優性遺伝 | 成長障害、重度の脊柱変形、車椅子生活になるケースも多い |
| 中間的な重症度 | 骨折の回数は多いがI型より重症化しやすい | 常染色体優性遺伝 | 四肢の骨変形、低身長、歯牙形成不全など |
Sillence分類はあくまで代表例であり、現代では遺伝子解析によりさらに多くの病型が報告されています。
重症度に個人差がある点を理解しながら、正しい分類と診断を得ましょう。
骨形成不全症の症状
骨形成不全症の主な特徴は骨の脆さですが、実際には骨折以外にも歯や聴覚など、さまざまな部位に変化が現れる場合があります。
骨折の特徴と頻度
骨形成不全症と聞くと、まず想起するのが骨折です。
軽い衝撃でも骨折が生じ、成長期には骨折回数が増える傾向があります。骨折の部位も多岐にわたり、腕や脚にとどまらず、肋骨や背骨の骨折を経験する場合もあります。
骨折の繰り返しによって骨が変形し、歩行や日常生活に支障をきたすケースが存在します。
骨変形と低身長の低下
骨折や骨の脆弱性が原因で、脊柱が湾曲(脊柱側弯症)したり、四肢が変形したりする場合があります。
成長期における骨変形は身長の伸びにも影響し、成人してからも低身長として症状に残る場合があります。重症度が高い病型の場合、車椅子生活を送るケースも少なくありません。
難聴や歯牙形成不全
骨形成不全症の中には、耳の小さな骨などにも影響が及び、難聴を引き起こすケースもあります。
さらに、歯のエナメル質や象牙質が弱くなる「Dentinogenesis Imperfecta」という症状がみられる場合も多いです。こうした症状は外見からわかりづらい部分もあるため、専門医のチェックが必要です。
肌や結合組織への影響
骨以外の結合組織も脆弱になり、皮膚がやや透けて見えやすくなる、関節が柔軟すぎる、あるいは腱や靭帯が傷つきやすいなどの症状がみられる場合があります。
また、眼球が青みがかった色味になる「青色強膜」も骨形成不全症の特徴の1つです。
骨形成不全症の原因
骨形成不全症は、主にコラーゲンをコードする遺伝子(Col1A1、Col1A2など)の変異によって生じます。
遺伝子変異によるコラーゲンの異常が、骨の構造や強度に大きな影響を与えます。
コラーゲン異常と骨の脆さ
骨の約3割を占める有機物質のうち、大半はI型コラーゲンです。
コラーゲンは骨に弾力や強度を与える大切なタンパク質であり、遺伝子の変異があると、コラーゲンの合成や構造が正常に機能しなくなります。
その結果、骨が折れやすい状態になります。
遺伝子変異の伝達
常染色体優性遺伝の場合、変異を持つ親がいれば、子に同じ変異が伝わる可能性が50%程度あります。
一方で、家族歴がなくても新生突然変異によって発症するケースもあり、こうした場合は両親は正常な遺伝子を持つケースが少なくありません。
親が症状を持たなくても、稀に劣性遺伝型の組み合わせで子が重症化する場合があり、遺伝の仕組みは複雑です。
環境因子との関連性
骨形成不全症は基本的には遺伝性の疾患ですが、骨を強化するためにはビタミンDやカルシウムなどの栄養バランス、適度な運動、日光浴といった生活習慣も重要です。
遺伝的素因に加え、これらの環境因子が骨密度の維持や骨折リスクの軽減に影響する可能性があります。
重症度のばらつきの要因
同じ病型であっても、骨折の頻度や変形の程度、難聴の有無などに個人差があります。
これは、単一の遺伝子変異だけでなく、他の遺伝子や環境要因、成長過程での骨の再形成能力など複数の要素が関与するためです。治療方針の決定にも、こうした個々の差を考慮します。
このような遺伝子背景がありますが、病因の本質はすべて「骨の有機基質であるI型コラーゲンの異常」による骨の脆弱化です。
したがってOIはコラーゲン異常症の一つに分類され、皮膚や腱など他のコラーゲンを含む組織にも異常が現れるのです。
なお、OIには性別や人種による発症頻度の大きな差は知られておらず、世界中で古くから存在する疾患です。
骨形成不全症の検査・チェック方法
骨形成不全症を疑う場合、さまざまな検査やチェックを行い、総合的に診断します。
医療機関受診時の流れ
整形外科や小児科などで、まず問診と視診、触診を行います。
家族の中に同じような症状を持つ人がいるか、これまでの骨折歴や成長段階での問題などを確認し、骨形成不全症の可能性を検討します。
その後、必要に応じて画像検査や遺伝子検査に進みます。
幼少児期からの多発骨折歴、骨変形、低身長、青色強膜や歯の形成不全といった特徴的な所見の組み合わせを認めれば、まず本症が疑われます。
画像検査(X線、CT、MRI)
骨形成不全症の診断には画像検査が有力な手段です。X線検査では骨折線や骨変形の有無、骨密度の低下などを確認します。
CT検査ではより詳細な骨の構造を把握し、微小な骨折や骨変形の程度を評価します。MRIでは骨だけでなく、軟部組織への影響も含めて調べられます。
骨折や変形を確認する際の主な画像検査と特徴
| 検査種類 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| X線 | 骨折や骨形状の把握 | 比較的簡易かつ低コストで実施できる |
| CT | 骨の詳細構造の評価 | 3D再構成が可能で、複雑な骨変形の把握がしやすい |
| MRI | 軟骨、筋肉、靭帯など軟部組織の確認 | 放射線被曝がなく、骨以外の組織も評価しやすい |
遺伝子検査
骨形成不全症の確定診断や病型の特定には、遺伝子検査が有用です。
血液サンプルを採取し、遺伝子変異の有無や種類を調べます。OI患者の約85%でCOL1A1またはCOL1A2の病的変異が検出でき、残りも他の原因遺伝子変異を同定できる場合が多いため、遺伝子パネル検査や全エクソーム解析による包括的な遺伝子診断が有用です。
遺伝子検査は確定診断に役立つだけでなく、遺伝カウンセリングや将来の家族計画にも役立ちます。
骨密度測定
骨の硬さや強度を数値化するためには骨密度測定が大切です。
DXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry)※1という機器を用いて、骨密度の低下度合いを客観的に評価し、治療効果や骨折リスクの判断を行います。
※1DXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry):二種類の異なるエネルギーを持つX線を用いることで、骨密度や体組成を測定する検査方法
骨形成不全症の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
骨形成不全症の治療には、薬物療法やリハビリテーション、手術など複数のアプローチがあります。治療のゴールは、骨折リスクを軽減し、痛みや日常生活の負担を減らすことです。
薬物療法
ビスホスホネート製剤(例:アレンドロン酸、リセドロン酸など)は、骨吸収を抑制し、骨折リスクの低減を目指します。
小児から成人まで幅広く使用例があり、一定の骨密度増加効果が報告されています。その他、骨代謝を改善する薬剤(テリパラチドなど)も使用するケースがあります。
薬物療法の主な種類と特徴
| 薬剤の種類 | 具体例 | 主な効果 | 投与形態 |
|---|---|---|---|
| ビスホスホネート | アレンドロン酸など | 骨吸収の抑制 | 経口または点滴 |
| PTH製剤 | テリパラチド | 骨形成を促進 | 皮下注射 |
| 骨代謝調整薬 | カルシトリオール | カルシウム代謝を整え、骨の回転を調整する | 経口 |
装具と理学療法
骨折を防ぐために、適切な装具(コルセットやブレース)を利用する方法があります。特に脊柱や下肢の保護には効果的です。
また、理学療法では筋力強化や関節の可動域維持を行い、骨折予防や日常生活動作の向上を図ります。
理学療法では以下のポイントを意識します。
- 筋力を少しずつ向上させる
- 関節可動域を保ち、姿勢を改善する
- バランス感覚を養い、転倒リスクを減らす
手術療法
骨折治癒が困難な場合や骨変形が強い場合、手術が選択される場合があります。
手術は、骨折や変形の再発を抑える目的で行われます。ただし、手術には麻酔のリスクや術後のリハビリが必要なので、適応を慎重に検討します。
治療期間と経過観察
骨形成不全症は遺伝性の疾患なので、完全に治癒するというよりは、骨折の回数を減らし、生活の質を高める長期的な管理が主な目標です。
薬物療法も一定期間で終わるというより、成長期や骨密度の推移を見ながら継続的に行う場合が多いです。
骨折が起きた場合は、その都度治療とリハビリを繰り返し、長い目で経過を追っていく必要があります。
薬の副作用や治療のデメリット
骨形成不全症の治療にはメリットだけでなく、副作用やデメリットも存在します。
ビスホスホネート製剤の副作用
ビスホスホネート製剤には、胃腸障害(胃痛、胸やけ、吐き気など)や、まれに顎骨壊死という重大な副作用が報告されています。
顎骨壊死は歯科治療との関係が指摘されるため、治療開始前に歯科検診を受け、口腔ケアを徹底します。
主なビスホスホネート製剤の副作用一覧
| 副作用名 | 症状例 |
|---|---|
| 胃腸障害 | 胃痛、吐き気、腹痛、胸やけ、食欲不振など |
| 骨・関節痛 | 投与後に骨や関節の痛みが出る場合がある |
| 顎骨壊死 | 顎の骨の露出、感染症、口腔内の潰瘍など |
| アレルギー | 皮膚発疹、呼吸困難などの重篤アレルギー反応は稀 |
PTH製剤のデメリット
PTH製剤(テリパラチド)は骨形成を促す一方で、高カルシウム血症のリスクがあるため、定期的に血液検査でカルシウムや腎機能などを確認する必要があります。
また、長期使用には制限がある場合も多く、医師が慎重に投与期間や投与量を調整します。
装具の負担
装具を着用することで骨折リスクや疼痛を和らげる反面、身体への圧迫感や行動範囲の制限がデメリットとして挙げられます。
また、成長期の子どもの場合は、適宜サイズ調整や新調が必要となり、コストや手間がかかります。
手術に伴うリスク
ロッディング手術を含めた手術では、麻酔リスクや術後感染症、金属材料の破損などの合併症を考慮する必要があります。
骨形成不全症は骨そのものが脆く、通常より術後のリハビリに時間を要する場合もあるため、手術を選択する場合は専門医の判断が不可欠です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
骨形成不全症の治療は、長期的に複数のアプローチを必要とする場合が多く、経済的な負担も気になるかと思います。最後に、保険適用と治療費の目安について解説します。
健康保険の適用範囲
日本では骨形成不全症に関わる検査や治療の大部分は、健康保険の対象になります。
骨折治療はもちろん、薬物療法の多くも保険適用があり、自己負担割合(3割・2割・1割など)に応じて治療費を支払います。
ただし、一部の遺伝子検査や特殊な検査は保険適用外となるケースがあります。
高額療養費制度の活用
入院や手術、点滴による薬物治療などで1カ月の医療費が高額になった場合、高額療養費制度を活用できます。
自己負担が一定額を超えた分が払い戻しとなるため、重症度が高く入院・手術を繰り返す可能性のある方は確認しておきましょう。
治療費の例
| 治療方法 | 治療費の目安 |
|---|---|
| ビスホスホネート製剤(経口薬) | 1カ月分の薬剤費はおおよそ1000円~3000円程度です。保険適用の有無やジェネリック薬剤の使用状況によって変動します。 |
| PTH製剤(自己注射) | 1回あたりの自己負担額は3割負担の場合で、おおよそ2000円~3000円ほどになる場合が多いです。 |
| 手術費用(ロッディング手術など) | 手術内容や入院期間にもよりますが、保険適用後の自己負担額で数万円~10万円程度になるケースが一般的です。 |
治療費や保険適用の概要
| 治療内容 | 保険適用 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|
| 外来診察 | 適用 | 1回あたり500円〜3000円程度 |
| ビスホスホネート製剤 | 適用 | 1カ月1,000円〜3,000円程度 |
| PTH製剤 | 適用 | 1回2,000円~3,000円程度 |
| ロッディング手術 | 適用 | 手術・入院合計で数万円~10万円程度 |
| 遺伝子検査(一部保険外) | 保険外の場合あり | 数万円〜十数万円 |
以上
参考文献
RAUCH, Frank; GLORIEUX, Francis H. Osteogenesis imperfecta. The Lancet, 2004, 363.9418: 1377-1385.
FORLINO, Antonella; MARINI, Joan C. Osteogenesis imperfecta. The Lancet, 2016, 387.10028: 1657-1671.
BYERS, Peter H.; COLE, William G. Osteogenesis imperfecta. Connective tissue and its heritable disorders: molecular, genetic, and medical aspects, 2002, 385-430.
FORLINO, Antonella, et al. New perspectives on osteogenesis imperfecta. Nature Reviews Endocrinology, 2011, 7.9: 540-557.
MARINI, Joan C.; CABRAL, Wayne A. Osteogenesis imperfecta. Genetics of bone biology and skeletal disease, 2018, 397-420.
HUBER, Michaell A. Osteogenesis imperfecta. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 2007, 103.3: 314-320.
KOCHER, Mininder S.; SHAPIRO, Frederic. Osteogenesis imperfecta. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1998, 6.4: 225-236.
TOURNIS, Symeon; DEDE, Anastasia D. Osteogenesis imperfecta–a clinical update. Metabolism, 2018, 80: 27-37.
GLORIEUX, Francis H.; ROWE, David. Osteogenesis imperfecta. Pediatric bone, 2012, 511-539.
VAN DIJK, F. S., et al. Classification of osteogenesis imperfecta revisited. European journal of medical genetics, 2010, 53.1: 1-5.