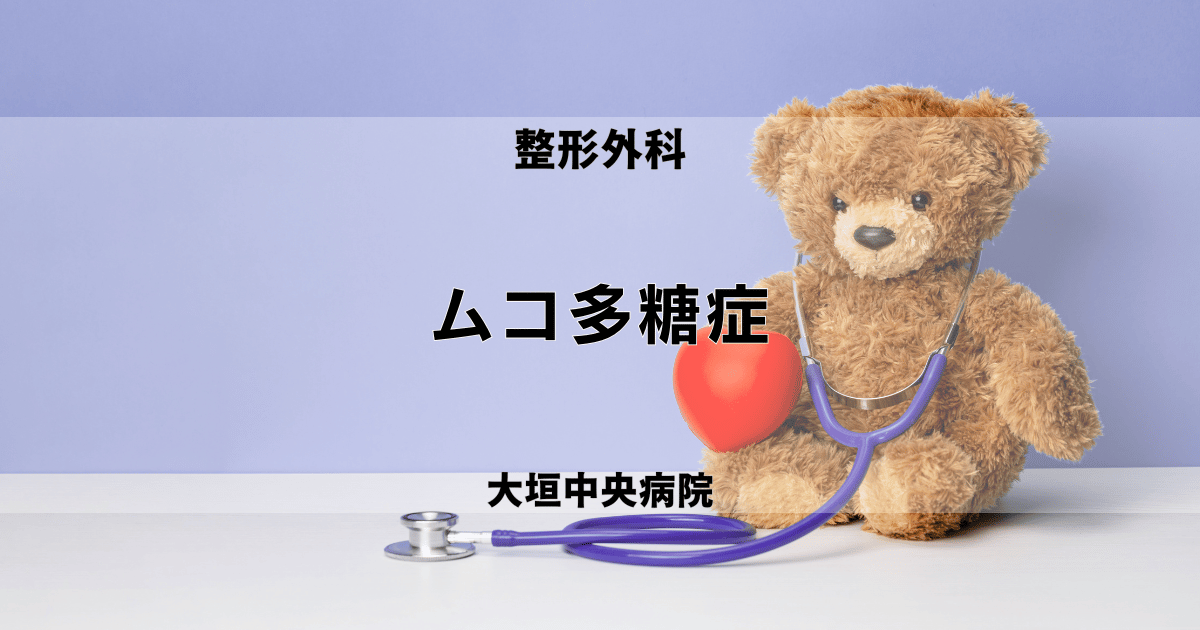ムコ多糖症(Mucopolysaccharidosis ,MPS)とは、先天的な酵素の欠損によって体内にあるムコ多糖(グリコサミノグリカン)が分解されにくくなり、さまざまな臓器や組織に蓄積していく疾患群です。
骨や関節、心臓や肝臓、気道などに症状が広範囲にわたって現れますが、その発症時期や重症度は病型によって異なります。
整形外科の視点からは、関節の可動域制限や骨の変形などが起こるケースが多く、日常生活や運動機能に影響が及びやすいといえます。
進行性の難病ですが、早期診断と適切な治療によって合併症を軽減し、生活の質を守る取り組みが大切です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
ムコ多糖症の病型
ムコ多糖症は、欠損酵素の違いにより古典的にI型からIX型までのタイプに分類されます。
現在知られているタイプは7種類(I、II、III、IV、VI、VII、IX型)で、各型に複数のサブタイプが含まれます(例えばIII型はA~Dの4亜型)。
V型(Scheie〔シャイエ〕症候群)やVIII型(DiFerrante症候群)という旧称もありますが、V型は現在ではI型の軽症型に統合され、VIII型は報告の誤りとされています。
ムコ多糖症各型の原因酵素と主な特徴
MPS I型
主に幼児期に発症します。重症例は、知的障害・発達遅滞があります。粗い顔つきや角膜混濁、ガーゴイル様体型や低身長、関節硬直や肝脾腫、気道狭窄や心臓弁膜症、心筋症が代表的な症状です。
軽症例(I-S型など)は知能正常で、関節や眼の症状が主体となります。治療しない重症型(Hurler)は10歳前後で死亡する傾向が見られます。
MPS II型
I型に類似する多系統症状(粗顔貌、肝脾腫、骨関節変形、心疾患、気道狭窄など)が認められます。角膜混濁はありません。
重症型では2~4歳頃から知的発達停滞・退行し、10~20歳代前半で死亡する傾向があります。軽症型は知能温存で、成人まで生存例も報告されています。
MPS III型
主に中枢神経症状が顕著に現れます。2~3歳頃から発達の遅れ・停滞が現れ、重症例では学童前半で知的能力が低下し退行します。
多動や自閉症様行動、睡眠障害やけいれん等が代表的な症状です。身体所見は比較的軽微ですが、軽度の粗顔貌や肝脾腫はあり得えます。四肢の拘縮は軽度であるものの、歩行能力は次第に低下していきます。
多くは思春期前後~20歳代で死亡するとの報告があり、現在有効な治療法が乏しく、介護負担の大きい病型です。
MPS IV型
骨格異常と関節のゆるさ(亜脱臼)が主体的な症状です。頚椎(首)の不安定や脊髄圧迫、胸郭変形による呼吸障害、低身長(軟骨発育不全性小人症)が認められます。
歩行困難で10代までに車椅子になる例もあり、角膜混濁を伴うケースが多いです。知能は正常ですが、重い肢体不自由と変形のため日常生活に高度の支援が必要となります。
心肺機能障害により寿命は短縮傾向が見られます。
MPS VI型
I型(Hurler型)に似た身体症状が顕著に認められます。具体的には、粗顔貌や角膜混濁、肝脾腫や重度の骨変形(脊柱後弯や胸郭変形)、関節拘縮や心臓弁障害が挙げられます。
知能は正常で、進行すると車椅子生活となり、呼吸不全や心不全などで若年~成人期に死亡するケースが多いです。
早期の酵素補充療法で症状進行の抑制が期待されています。
MPS VII型
最も稀少な型の一つです。胎児期から全身むくみにより非免疫性胎児水腫を呈し、新生児期に死亡する重症例もあります。
生存例ではI型に類似の多臓器症状(粗顔貌、角膜混濁、関節硬直、肝脾腫、骨異常など)を示し、知的障害を伴う場合が多いです。
進行が早く予後不良ですが、軽症例では小児期以降まで生存する例もあります。2017年に本症初の酵素補充療法薬が承認されました。
MPS IX型
報告症例が極めて少ない超希少型です。1996年に初めて報告され、2023年現在でも世界でわずか数例のみ確認されています。
特徴は関節周囲の軟部腫瘤(ヒアルロン酸塊)形成、軽度の顔貌変化、身長低め程度で、知的発達は正常とされています。症状がきわめて軽く、治療法は確立していません。
病型ごとの原因や傾向
各型はいずれも単一遺伝子の変異が原因です。
遺伝形式はほとんどが常染色体劣性遺伝(両親から劣性遺伝子を受け継ぐことで発症)ですが、MPS II型(ハンター症候群)のみX染色体上の遺伝子異常による伴性劣性遺伝であり、発症の大部分は男児です。
男女比で見ると、日本ではMPS全体の患者数は男性約70%:女性約30%と偏りが見られます(主にMPS II型患者が多いため)。
各疾患の発症頻度は前述の通り非常に低く、中でもMPS VII型(スライ症候群)やIX型(ナトウィッツ症候群)は極めて稀少です。
病型ごとの症状の重さ
症状の重さ(重症度)は同じ型の中でも患者さんごとに幅があり、遺伝子変異の種類や残存酵素活性の程度で異なります。
特にMPS I型(Hurler=重症~Scheie=軽症まで)やMPS II型(重症=知的障害あり~軽症=知能正常)では疾患スペクトラムとして重症型から軽症型まで連続的なバリエーションがあります。
一方でMPS III型(A~D)はいずれも主に中枢神経症状が中心の重症例で、多くが知的退行を伴います。MPS IV型A/BやVI型では、知能は保たれ、身体症状のみが問題となります。
このように型により症状の性質が異なるため、患者さんの生活への影響(例:知的障害の有無による教育支援の違い、肢体不自由の程度による介護・補助具の必要性など)も型ごとに大きく異なります。
適切なケアと治療選択のために、各型の特徴の正しい理解が重要です。
ムコ多糖症の症状
ムコ多糖症は全身に影響を及ぼす可能性があるため、症状の現れ方は人によってさまざまです。
骨と関節、呼吸器や心臓血管系、視覚や聴覚など多くの臓器や器官に障害が起こりえます。
骨格や関節の異常
| 主な骨格・関節症状 | 具体的な例 |
|---|---|
| 脊椎の変形 | 亀背(後弯)、側弯 |
| 四肢の骨変形 | 肘、膝の可動域制限、X脚あるいはO脚 |
| 頚椎不安定性 | 首の脊髄圧迫による神経症状 |
| 関節硬化 | 関節が動かしづらくなる、可動域の減少 |
骨や関節に起こる異常は、ムコ多糖症の大きな特徴です。成長に合わせて骨格の変形が進行し、背骨(脊椎)の湾曲や胸郭の変形、股関節や膝の可動域制限などが生じます。
これらは姿勢や歩行機能に大きな負担をかけるため、整形外科的なケアが必要です。
呼吸器や心臓血管系の症状
顔面骨の特徴的な変化や気道周辺組織の肥厚によって、上気道が狭くなる場合があります。睡眠時無呼吸症候群や呼吸困難が起こりやすく、息切れが日常生活において負担となります。
心臓弁の異常や心筋症が起こる病型もあり、循環機能に深刻な影響が及ぶケースも珍しくありません。
視覚や聴覚への影響
角膜混濁や網膜の異常が生じて視力が低下したり、耳の骨伝導障害によって難聴が起こったりします。
視力や聴力の低下は学習やコミュニケーション面で課題を生むため、必要に応じて眼科や耳鼻科でのフォローが大切です。
- 角膜移植などの外科的介入
- 眼科的検査の定期実施
- 補聴器の装用や補聴指導
- 聴覚検査や耳鼻科受診
発達面への影響
中枢神経系への蓄積が進む病型では、知的発達の遅れや行動面での問題が顕著になります。学習障害や認知機能の低下によって日常生活のセルフケアが難しくなる場合もあります。
そのため、特別支援教育やリハビリテーション、家族のサポートが重要です。
神経症状と発達支援の関係
| 病型 | 神経症状の特徴 | 必要とされるサポート例 |
|---|---|---|
| III型 (Sanfilippo) | 行動障害、重度知的障害 | 特別支援教育、行動療法 |
| I型 (Hurlerなど) | 知的障害が比較的著しい | 定期的な神経学的評価、早期療育 |
| II型 (Hunter) | 中枢神経症状の有無は個人差が大きい | 個別指導計画の作成、ヘルパー導入 |
ムコ多糖症の原因
ムコ多糖症はいずれも遺伝子の先天的な変異が原因です。各型ごとに対応する酵素をコードする遺伝子があり、その変異により酵素の活性が大幅に低下するか、あるいは酵素が全く作られなくなります。
欠損する酵素の種類によって分解できないムコ多糖(グリコサミノグリカン)が変わり、結果として蓄積する部位や症状の現れ方が異なります。
遺伝子変異と酵素の働き
体内でグリコサミノグリカンを分解する過程には多くの酵素が関与します。
いずれかの酵素が遺伝子変異によって機能低下すると、その酵素が担当する分解段階が滞り、代謝産物が細胞内のリソソームに蓄積します。この蓄積によって細胞の機能が乱れ、全身に症状が広がります。
常染色体劣性遺伝とX連鎖劣性遺伝
多くのムコ多糖症は常染色体劣性遺伝です。両親がともに変異遺伝子を持つ場合に子へ遺伝し、子がその変異を両方受け継ぐと発症リスクが高まります。
一方、II型(Hunter症候群)はX連鎖劣性遺伝のため、男性のみが臨床症状を示すのが一般的です。
ムコ多糖症の遺伝形式
| 病型 | 遺伝的形式 | 特徴 |
|---|---|---|
| I型, III型, IV型, VI型, VII型 | 常染色体劣性 | 両親の遺伝子変異が揃うと発症しやすい |
| II型 | X連鎖劣性 | 男性が発症、女性は保因者 |
酵素欠損の程度
同じ病型でも、酵素の活性がどの程度失われているかによって症状の重さが変わります。
酵素活性が完全に失われていれば重症化しやすく、少しでも酵素活性が残存していれば比較的軽度でゆるやかな進行になる場合があります。
ムコ多糖症の検査・チェック方法
ムコ多糖症は早期に診断して治療につなげることが望ましい疾患です。とくに骨や関節の変形が急速に進行するタイプでは、整形外科的ケアを含めた総合的なサポートが必要です。
症状からの初期アプローチ
乳幼児健診や小児科外来で特徴的な症状(発達の遅れ、肝脾腫、骨変形、角膜混濁、ヘルニア反復など)がみられた場合などかかりつけ医や小児科、整形外科医がムコ多糖症を疑います。
骨X線検査で独特の骨変形が確認される場合や、血液や尿検査でグリコサミノグリカンの蓄積を示唆する結果が得られた場合、専門機関への紹介が考えられます。
- 関節可動域のチェック
- 体格や体型の変化(胴体が短い、脊椎の湾曲など)
- 角膜混濁や難聴などの有無
- 運動発達や知的発達の遅れ
尿中グリコサミノグリカン検査
尿中のグリコサミノグリカン(GAG)を定量・定性すると、ムコ多糖症の可能性を高めたり絞ったりできます。
特異的な構造を持つGAGが増加していれば、各病型の鑑別につながる手がかりになります。
グリコサミノグリカン検査の種類と特徴
| 検査名 | 主な測定内容 | 利点 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 定性検査 | グリコサミノグリカン全般 | 簡易的にスクリーニング可能 | 病型の特定まではできない |
| 定量検査 | GAG濃度の数値測定 | 病気の重症度推測に有用 | 特殊な検査機器が必要 |
| タンデム質量分析 | 特定のGAG分子の検出 | 病型鑑別が進む可能性がある | 保険収載の状況を確認要 |
酵素活性測定
血液や培養細胞を用いて、欠損が疑われる酵素の活性度を直接測ります。これによってどの酵素がどの程度働いていないかを確認し、病型をより正確に確定します。
酵素活性測定はムコ多糖症の診断における重要な工程です。
遺伝子検査
酵素活性測定だけでは判別が難しい場合や、家族内リスクを評価するために遺伝子検査を行います。特定の遺伝子変異が同定されれば、病型の確定とともに将来の発症リスクなどを評価できます。
保因者の判定や出生前診断を考える場合にも、この検査を利用します。
早期診断の意義
できるだけ早い診断の確定が極めて重要です。放置すれば不可逆的な臓器障害や発達の退行が進んでしまうため、治療可能なタイプでは治療開始の時期が予後を左右します。
例えばMPS I型の重症(Hurler)では1歳代で造血幹細胞移植を行うと知的発達の維持が期待できますが、2~3歳を過ぎると手遅れになる恐れがあります。
MPS II型でも2~4歳までに酵素補充療法や中枢神経への治療を開始すれば認知機能の保持に寄与する可能性があります。
逆に未診断のままだと、原因不明の発達障害や器質疾患として対症療法を受けつつ進行してしまい、適切な遺伝カウンセリングや治療の機会が失われます。
特に兄弟児への遺伝的対応(次子の出生前診断など)や、患者が出生した家族に対する公的支援策の案内など、診断によって得られるメリットは計り知れません。
ムコ多糖症の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
ムコ多糖症の治療では、酵素補充療法を中心にさまざまな医療手段を組み合わせますが、根治させる治療法は存在しません。
整形外科的処置やリハビリテーションも適宜行い、生活の質の維持・向上を目指します。
酵素補充療法の概要
欠損している酵素を補うために酵素製剤を定期的に静脈内投与する治療法です。欠損酵素を補充してグリコサミノグリカンの蓄積を抑制し、症状の進行を緩やかにします。
病型によって使用できる酵素製剤が異なりますが、I型やII型、VI型などに対して承認されています。現在、ムコ多糖症治療の中心となっています。
酵素補充療法の主な特徴
| 病型 | 補充される酵素 | 投与方法 | 効果が期待できる症状 |
|---|---|---|---|
| I型 (MPS I) | ラロニダーゼ | 点滴静注 | 肝脾腫、関節症状、気道症状など |
| II型 (MPS II) | イデュルスルファーゼ | 点滴静注 | 骨・関節症状、呼吸器症状など |
| VI型 (MPS VI) | ガルスルファーゼ | 点滴静注 | 骨格異常、関節可動域、心臓症状など |
骨や関節への外科的アプローチ
骨格の変形が進む場合、整形外科医が手術を検討します。脊椎の固定術や上肢・下肢の骨切り術、人工関節置換などが選択肢に入ります。
成長期のうちに手術を行うと変形の進行を抑えやすい場合もありますが、患者さんの全身状態や呼吸機能を考慮しながら計画を立てる必要があります。
造血幹細胞移植
患者さんにドナー由来の造血幹細胞(骨髄・臍帯血など)を移植し、体内で正常な酵素を産生する細胞を定着させる治療です。主にMPS I型(重症Hurler症候群)で有効性が確立されており、1980年代から実施されています。
原理としては、骨髄から生着したドナー細胞(白血球系細胞)が各組織に入り込み、ライソゾーム酵素を分泌して周囲の患者細胞にも取り込まれることで、蓄積したムコ多糖を分解できるようにするものです。
造血幹細胞移植の最大の利点は、一度成功すれば生涯にわたり体内で酵素が産生され続ける点です。また造血細胞は一部が中枢神経系にも入り込む(ミクログリア化する)ため、血液脳関門の制約を越えて脳内でも酵素供給が期待できます。
実際、MPS I-Hurler症候群では1~2歳未満で移植が成功した例では知的発達の大幅な改善が示されており、現在も重症Hurler型には標準治療として推奨されています。
リハビリテーションと補助具
ムコ多糖症では、関節の硬さや筋力の低下によって日常生活動作が制限される場合があります。理学療法士や作業療法士が関わり、歩行訓練や関節可動域の維持訓練を行います。
補助具や装具の活用によって移動を助けたり、姿勢を保持したりするのも有効です。
治療やリハビリでよく用いる方法の一例
| 治療法 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 理学療法 | 関節可動域訓練、筋力増強訓練、歩行指導 |
| 作業療法 | 日常生活動作の練習、環境調整 |
| 補助具や装具 | コルセットや装具で脊椎や関節をサポート |
治療期間の目安
ムコ多糖症は慢性的に進行する疾患であり、酵素補充療法も長期にわたる点滴投与が必要です。週1回から2週に1回など、病型や薬剤によって投与頻度が決まります。
| 治療法 | 期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 酵素補充療法 | 一生涯継続が基本 | 定期的な血液検査や画像検査による評価が必要 |
| リハビリ | 長期継続が望ましい | 関節可動域や筋力を維持しながら生活を支える |
薬の副作用や治療のデメリット
治療にはメリットがある一方で、薬の副作用やデメリットも存在します。
酵素補充療法、外科手術、リハビリテーションに伴うリスクを正しく理解し、医療チームと相談しながら治療方針を決めましょう。
酵素補充療法の副作用
酵素製剤への過敏反応によって、点滴中に発熱や発疹、血圧低下などのアナフィラキシー様症状が生じる場合があります。
医師や看護師は投与時に常に観察を行い、緊急時に迅速に対応できるよう準備します。また、長期投与によって注射針を刺す静脈が硬化したり、感染症リスクが高まったりする可能性があります。
主な副作用や留意点
| 副作用・リスク | 対応・予防策 |
|---|---|
| 過敏反応 | 投与速度の調整、アナフィラキシー対策 |
| 感染症リスクの増加 | 清潔操作の徹底、点滴ルート管理 |
| 血管の硬化・損傷 | 投与部位の定期的な変更 |
リハビリテーションによる負担
リハビリテーションは長期にわたり取り組む必要があります。通院の負担や、体に痛みがある中での運動療法による苦痛もあります。
ただし、無理のない範囲での継続が関節可動域や筋力の維持に有益です。
治療による生活への影響
定期的な点滴やリハビリ、場合によっては入院治療が必要になるため、学業や仕事への負担が大きくなることも考えられます。
家族や周囲の理解を得ながら計画を立てると、生活リズムを整えやすくなります。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
ムコ多糖症は指定難病※1に含まれており、保険や公的補助の対象になります。
※1指定難病:難病法に基づいて、国が定めた基準を満たし、医療費助成の対象となる病気。ムコ多糖症はライソゾーム症という疾患郡の一つとされ、I型、II型、IVA型、VI型など多くの病型が指定難病となっている。
酵素補充療法は高額になるケースが多いため、経済的な負担を軽減する仕組みを活用することが重要です。
公的医療保険と高額療養費制度
日本の公的医療保険(健康保険)では、ムコ多糖症の治療においても自己負担割合は基本的に3割です。
しかし、高額療養費制度を利用すれば、一定の自己負担限度額を超えた分については払い戻しを受けられます。所得や年齢によって自己負担限度額は異なります。
特定医療費(指定難病)助成制度
ムコ多糖症は厚生労働省の指定難病に該当する場合が多く、特定医療費助成の対象となります。
自己負担の月額上限が設定され、家計の負担を緩和できます。認定を受けるには指定医に書類を作成してもらい、所定の手続きを行う必要があります。
治療費の具体的な金額
酵素補充療法の薬剤費は非常に高額で、1回の投与で数十万円~100万円程度になるケースがあります。
例えば、月に4回の点滴が必要な場合、総額で数百万円を超える例も少なくありません。しかし、上記の公的補助や保険適用を活用すると、自己負担額は大幅に抑えられます。
外科手術やリハビリの費用も保険で3割負担になり、高額療養費制度の対象になります。
治療費の目安
| 治療内容 | 1回の費用目安 | コメント |
|---|---|---|
| 酵素補充療法 | 数十万円~100万円程度 | 保険適用後は自己負担3割 高額療養費でさらに軽減 |
| 外科手術 | 数十万円~200万円程度 | 麻酔や入院費含む 内容によって差が大きい |
| リハビリテーション | 数千円~数万円(1か月) | 外来・通院ベースの場合 定期的に長期継続が必要 |
費用面での注意点
高額療養費制度や指定難病助成制度の手続きには書類の準備や役所への申請が伴います。
主治医やソーシャルワーカーと相談しながら早めに準備を進めると良いでしょう。通院や入院の回数が多い方ほど、こうした制度の恩恵が大きくなります。
以上
参考文献
CLARKE, Lorne A. Mucopolysaccharidosis type I. 2021.
VALAYANNOPOULOS, Vassili, et al. Mucopolysaccharidosis vi. Orphanet journal of rare diseases, 2010, 5: 1-20.
SCARPA, Maurizio; LAMPE, Christina. Mucopolysaccharidosis type II. GeneReviews®[Internet], 2025.
MUENZER, Joseph, et al. Mucopolysaccharidosis I: management and treatment guidelines. Pediatrics, 2009, 123.1: 19-29.
GIUGLIANI, Roberto, et al. Mucopolysaccharidosis I, II, and VI: Brief review and guidelines for treatment. Genetics and molecular biology, 2010, 33: 589-604.
MARTINS, Ana Maria, et al. Guidelines for the management of mucopolysaccharidosis type I. The Journal of pediatrics, 2009, 155.4: S32-S46.
CLEARY, M. A.; WRAITH, J. E. Management of mucopolysaccharidosis type III. Archives of disease in childhood, 1993, 69.3: 403.
KUBASKI, Francyne, et al. Mucopolysaccharidosis type I. Diagnostics, 2020, 10.3: 161.
WRAITH, J. E.; JONES, Simon. Mucopolysaccharidosis type I. Pediatric Endocrinology Reviews: PER, 2014, 12: 102-106.
KAKKIS, Emil D., et al. Enzyme-replacement therapy in mucopolysaccharidosis I. New England Journal of Medicine, 2001, 344.3: 182-188.