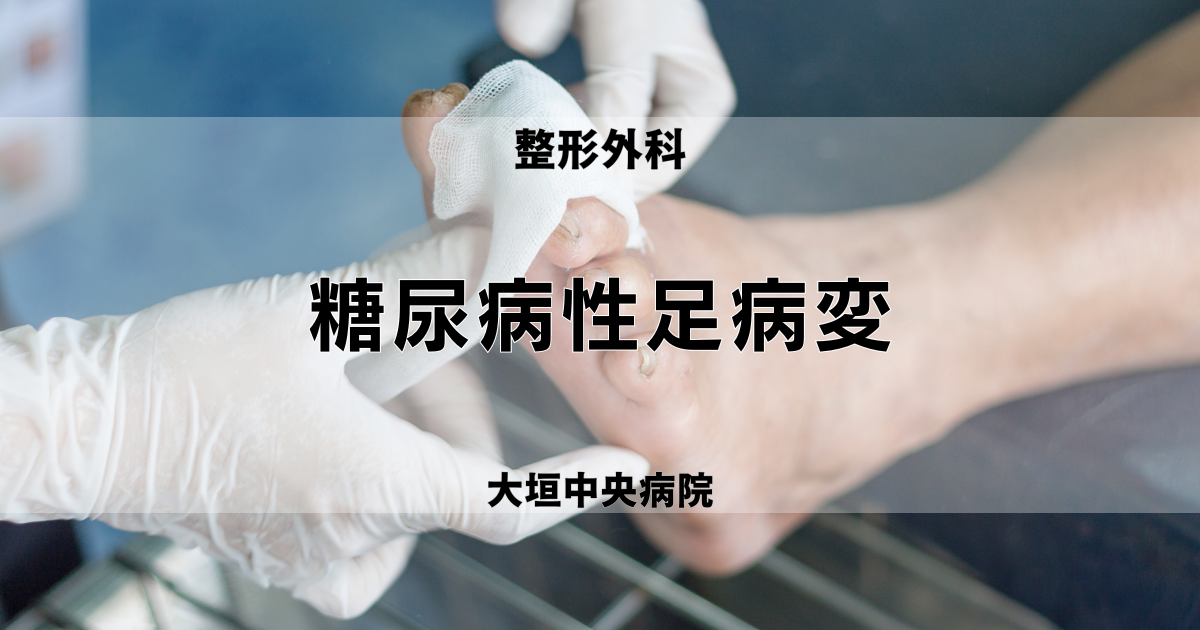糖尿病性足病変(Diabetic foot)とは、糖尿病による深刻な合併症のひとつです。長期的な高血糖状態から足の神経や血管が損傷し、感染や潰瘍、場合によっては壊疽を引き起こします。
日常の小さな怪我が大きな合併症につながる可能性があり、足のケアと血糖コントロールの欠如によって悪化するケースもあるため、予防措置と早期治療が重要です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
糖尿病性足病変の病型
糖尿病性足病変は糖尿病が原因で起こる足の合併症の一つですが、診断がなされた後に病期分類を行う必要があります。
糖尿病性足病変(潰瘍)の病期分類で広く利用されているものは、1981年のWagnerによるものです。
Wagnerによる分類
Wagnerによる分類では、潰瘍を深さに基づいて6つのグレードに分けています。
| 分類 | 所見 |
|---|---|
| グレード1 | 表在性潰瘍。表皮の部分もしくは全層にわたって病変がある時のグレード。 |
| グレード2 | より深い潰瘍。靱帯、腱、関節包、骨、深在性筋膜に及ぶ潰瘍で膿瘍や骨髄炎を伴わないもの。 |
| グレード3 | 膿瘍または骨髄炎を伴う深い潰瘍。 |
| グレード4 | 前足部の壊疽が生じる状態。 |
| グレード5 | 足全体を含む壊疽が生じる状態。 |
Wagnerによる分類は単に潰瘍の深さを評価するものであり、転帰への影響が知られている他の因子を組み込んでいないとの批判があります。
このほかに、現在最も一般的に使用されている分類の1つにテキサス大学分類があります。
テキサス大学分類では、深さだけでなく感染の種類や虚血の評価も含まれており、創傷の最終的な転帰にも基づいています。
糖尿病性足病変の症状
糖尿病性足病変の主な症状としては、足の感覚低下や麻痺、足の形の変化、皮膚の変化などが挙げられます。
- 足の感覚低下や麻痺
- 足の形の変化
- 足の皮膚や爪の変化
- 腫れや炎症
- 潰瘍の形成
足の感覚低下や麻痺
糖尿病による神経障害が進行すると、足の感覚が鈍くなったり、完全に感じなくなったりする場合があります。
これにより、足に傷ができても痛みを感じず、その存在に気づきにくくなります。
足の形の変化
足の骨や関節の異常により、足の形が変わる場合があります。足の形が変わると歩行時の圧力分布の変化を引き起こし、歩行に影響が出ます。
足の皮膚や爪の変化
足の皮膚が乾燥し、ひび割れたり、硬くなったりしやすくなります。また、糖尿病による血流不良は、皮膚の色や温度変化にも影響します。
足の皮膚が通常よりも冷たく感じたり、色が蒼白、紫色、または赤みを帯びたりするのが主な例です。さらに、爪が厚くなったり、色が変わったり、異常に成長する場合もあります。
腫れや炎症
足の腫れや炎症は、糖尿病性足病変の一般的な症状です。
感染の兆候や血流の悪化によるものである場合が多く、特に足の特定の部位だけが腫れている場合、感染や局所的な問題の可能性が疑われます。
潰瘍の形成
糖尿病性足病変の最も重篤な症状の一つが足の潰瘍です。潰瘍は皮膚が破損し、開いた傷ができる状態を指します。
潰瘍は感染を引き起こしやすく、治癒が非常に困難です。さらに、糖尿病性足病変では足の感覚が鈍くなるために潰瘍を早期に発見できない場合があります。
糖尿病性足病変を引き起こす主な要因
糖尿病性足病変の原因としては、高血糖や神経損傷、血管損傷などがあります。
- 高血糖
- 神経損傷(ニューロパシー)
- 血管損傷
- 感染
- 足の構造の問題
- 不適切なフットケア
高血糖
長期間にわたる高血糖は血管と神経に損傷を与え、足の問題を引き起こす原因となります。
神経損傷(ニューロパシー)
高血糖によって足の神経が損傷を受けると、痛みや温度の感覚が低下し、足に傷ができても気づかない場合があります。糖尿病患者の約60%に神経障害が発症します。
血管損傷
糖尿病は血管を狭め、硬化させる場合があります。これにより足への血流が悪くなり、傷の治癒が遅れたり、感染のリスクが高まったりします。
感染
神経損傷や血流の低下により、足は感染しやすくなります。糖尿病患者様は感染に対する抵抗力も低下しているため、小さな傷が重大な問題に発展する場合があります。
足の構造の問題
足の構造に問題(扁平足や変形など)があると、足全体に不均衡なストレスがかかり、足の潰瘍や傷の原因となります。
不適切なフットケア
足を清潔に保てなかったり、足に合わない履物が原因となります。
糖尿病性足病変が生じるメカニズム
高血糖によって神経伝導が低下した結果、足の保護感覚が欠如し、外傷や潰瘍を発症しやすくなります。
また、糖尿病は知覚神経障害に加えて、神経細胞の自律神経機能障害を引き起こすケースがあります。その結果、発汗障害が起こり、足の乾燥、皮膚のひび割れ、亀裂が生じやすくなります。
さらに、運動ニューロン機能障害は、筋肉の衰えや足の構造的異常を生じさせる原因にもなります。
これにより、足底の様々なゾーンで局所的に圧力が上昇し、潰瘍形成のリスクが高まります。
要因①に加えて、創傷治癒の障害による影響も重要です。通常、創傷は止血、炎症、増殖、リモデリングを含むいくつかの治癒段階を経て治癒していきますが、糖尿病性足病変がある場合、1つ以上の段階で停滞します。
これは、高血糖によるサイトカイン放出、NETosis(NETs 放出をともなう細胞死)、AGE(終末糖化産物)産生の調節異常が主な原因です。
炎症とともに細胞外マトリックス(ECM)の大幅な変化もまた、なかなか治らない糖尿病性足病変の原因のひとつです。
正常な創傷治癒の場合、コラーゲンやフィブリンなどのECMタンパク質の産生と分解は厳密に制御されています。
しかし、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)として知られるコラーゲン分解酵素が亢進し全体として、ECMは無秩序になり、創傷治癒を支えるには不十分な状態になります。
血管新生の障害も糖尿病性足病変の要因として挙げられます。
血管新生は通常、創傷治癒の増殖期に起こり、肉芽組織の形成と創傷への栄養と酸素の供給の両方を担っています。血管新生が阻害されると、創傷治癒力が低下します。
糖尿病性足病変の検査・チェック方法
糖尿病性足病変は早期発見と対応が非常に重要とされています。
自己チェック
| 足と足指の間の観察 | 毎日、足と足指の間をチェックし、赤み、腫れ、切り傷、潰瘍、かさぶたなどの異常がないか確認する。足の裏や指の間など、自分で見えにくい部分も鏡を使用して確認。 |
|---|---|
| 足の皮膚の状態の確認 | 足の皮膚の乾燥や硬化がないかを確認し、異常が見られる場合は、保湿を心がける。ただし、指の間には保湿剤を塗らないよう注意。 |
| 足の形状の確認 | 足の形状に変化がないか、靴擦れや圧迫の跡が残っていないかを確認する。足の形状が変わると、特定の部位に過度の圧力がかかり、傷ができやすくなる。 |
| 感覚の確認 | 足の感覚が正常かどうかを自分で確認。冷たさ、痛み、ピリピリ感などの異常が感じられた場合は、専門医に相談する。 |
| 靴と靴下の選択 | 足を圧迫しない適切なサイズの靴と靴下を選び、足に負担をかけないようにする。 |
自己チェックは日常的に行い、少しでも異常を感じた場合は、専門医の診察が推奨されます。
病院での検査方法
糖尿病性足病変の検査には、足の外観の検査や感覚検査などがあります。
| 足の外観の検査 | 足の皮膚の状態、爪の異常、潰瘍や感染の有無などを詳しく観察します。 足の形状の変化や圧迫による跡もチェックし、足に不適切な負荷がかかっていないかを評価します。 |
|---|---|
| 感覚検査(モノフィラメントテスト等) | 専用の器具を使用し、足の感覚の鈍化をチェック。 検査にはモノフィラメントテストや振動感覚試験があり、足の感覚神経の損傷の有無と程度を評価します。 |
| 血行のチェック | 足の脈拍を触診するほか、ドップラー超音波検査を行い、血流の状態を調べます。この検査により、血管が狭窄していないか、血流が適切かどうかを確認できます。 |
| 温度の比較 | 両足の温度を触って比較し、温度差がないかをチェック 温度差がある場合、血流の問題や感染の兆候がある可能性があります。 |
| 骨髄炎の有無チェック | 無菌の金属プローブで潰瘍をプローブして行うプローブ・トゥ・ボーン・テスト(PTB)は、骨髄炎の診断に役立ちます。 プローブが骨に当たれば、陽性となります。 |
画像検査
画像検査では、基礎にある骨髄炎や皮下組織内の空気の存在、骨折の徴候や異物の存在を調べるために単純X線検査を行います。
- 基礎にある骨髄炎の有無の確認
- 皮下組織内の空気の存在の確認
- 骨折の徴候の確認
- 異物の存在の確認
ただし、骨髄炎が疑われる場合は、MRI検査を行う場合が多いです。
糖尿病性足病変の治療方法と治療薬、リハビリテーション
糖尿病性足病変の治療には、予防ケアや創傷被覆材、オフローディング(免荷)、高圧酸素療法などがあります。
- 予防的ケア
- オフローディング(免荷)
- 高圧酸素療法
- 幼虫療法(マゴット療法)
- 局所成長因子
- 衝撃波治療
- 幹細胞治療
- 全身および局所の抗生物質
- 局所陰圧閉鎖療法
- デブリードマン
- 血行再建術
- 植皮
- 切断
治療方法とリハビリテーションプログラムは、患者様の具体的な状態に応じて専門医によって選択されます(複数の治療方法が組み合わされる場合もあります)。
予防的ケア
糖尿病性足病変は、ある程度進行するまで無症状である場合が多く、気付いた時にはかなり進行しているケースが少なくありません。
したがって、糖尿病性足病変の早期発見を可能にする定期的な糖尿病足部スクリーニングを行い、適切であれば治療を開始する選択が第一の予防戦略とされています。
もちろん、積極的な血糖コントロール(目標ヘモグロビンA1C 6.5~7.0%)、高血圧、肥満、高脂血症、喫煙などの危険因子の管理も必要です。
創傷被覆材
創傷被覆材(創傷を覆うための材料)は最も基本的で一般的な治療手段です。
糖尿病性足病変の管理において重要な役割を果たしていますが、これだけでは不十分なケースも多く、他の治療と併用する必要があります。
オフローディング(免荷)
オフローディングは、患部に及ぶ圧力を軽減する治療方法です。
主に神経障害を伴う潰瘍において、糖尿病性足病変の主要な治療法の1つであり、多くの種類が利用されています。(虚血性糖尿病性足病変に対しては、血行再建術がより一般的に用いられています。)
オフローディングの一般的な方法には、ベッド上安静、車椅子の使用、松葉杖補助歩行の実施、トータル・コンタクト・キャスティング、フェルト・フォームの使用、治療靴の使用、取り外し可能なギプス歩行器の使用などがあります。
最も効果的なものはフルギプスで、1~2週毎に交換します。
高圧酸素療法
全身的な高気圧酸素療法(HBOT)が行われる場合もあります。
この治療は、特に感染性糖尿病性足病変の治療で広く行われており、通常の創傷ケアの補助療法として使用されます。(治療回数に制限があります。)
幼虫療法(マゴット療法)
幼虫療法とは、創傷部にウジ虫を配置する慢性創傷の治療です。この治療法はデブリードメント※1を著しく促進するとされています。(ただし、日本では施行可能な施設が限られています。)
ある研究では、マゴット療法はハイドロゲルドレッシング材などの他の局所治療と比較して、肉芽組織の発達を早め、創傷表面積をより有意に減少させたとしています。また、創傷の消毒や完全治癒率にも影響を及ぼさないとの報告もされています。
※1デブリードメント:壊死組織や感染した組織を除去、創を清浄化し、創傷治癒を促進する外科処置。
局所成長因子
血小板由来成長因子も、プラセボと比較して潰瘍治癒率を高める効果が証明されています。
成長因子は創傷治癒の主要な即時型メディエーターとして機能し、糖尿病性足病変に適用すると潰瘍治癒を促進します。
あるメタアナリシス※2では、2088人が参加した26のRCTを評価し、遺伝子組換え上皮成長因子、自己血小板豊富血漿、遺伝子組換えヒト血小板由来成長因子に焦点を当てています。
全体として、標準治療と並行して使用した場合、3つの治療法はそれぞれ治癒率を有意に改善する結果となりました。
※2メタアナリシス:複数の研究結果を統合・統計的に分析し、より高い見地から分析したもの。
衝撃波治療
体外衝撃波治療※3(ESWT)は、糖尿病性足病変の治療において軟部組織の創傷治癒を促進すると報告されています。
ESWTは骨芽細胞を刺激し、軟部組織の治癒を促進する治療方法です。
ESWTは、従来の方法と比較しても、糖尿病性足病変治療に効果的であることを示す有望な臨床試験結果が出ています。
標準治療や他の糖尿病性足病変治療と併用した場合のESWTの有効性を比較するため、2つの多国籍RCTが実施されました。
試験期間はいずれも12週間で、標準治療単独と比較して、ESWTの使用により創傷量が50%以上減少したと報告されています。
※3体外衝撃波治療:超音波や電磁波などを用いて衝撃波を発生させ組織に当てる治療。
幹細胞治療
炎症、細胞遊走、新生血管、組織増殖からなる組織リモデリングプロセス※4の理解が深まった背景から、幹細胞を用いた治療が糖尿病性足病変の治療にも取り入れられることになります。
幹細胞は、細胞遊走、血管新生、細胞外マトリックスのリモデリング、神経の再生に重要な役割を果たすサイトカインを分泌し、創傷治癒を助けます。
また、幹細胞は筋線維芽細胞や内皮細胞など、様々な細胞型に分化する能力があり、創傷治癒を最適化する働きも持ちます。
※4リモデリングプロセス:組織や構造を変化させ、新たな機能や形態を生み出すこと。
全身および局所の抗生物質
全身および局所の抗生物質の使用は、糖尿病性足病変の管理において非侵襲的な治療法として役立ちます。
好気性グラム陽性球菌およびブドウ球菌が最も一般的な関与微生物です。
感染の徴候がない創傷では、通常、抗生物質による治療は必要ありません。
局所陰圧閉鎖療法
糖尿病性足病変治療における最近の進歩のひとつに、局所陰圧閉鎖療法(NPWT)の利用があります。
NPWTは、真空圧を利用して創傷から体液を引き抜き、患部への血流を増加させて治癒プロセスを刺激する治療法です。
NPWTでは、創傷の収縮に代表されるマクロ変形と、顕微鏡レベルで起こるミクロ変形の主に2種類の組織変形が生じます。
どちらの変形も血流を刺激し、組織肉芽形成、血管増殖、新生血管新生、上皮化生、過剰な細胞外液の除去などの創傷治癒カスケード(段階)を促進します。
デブリードマン
デブリードマンは、糖尿病性足病変の治療において重要な治療法です。
特に治癒プロセスを阻害する壊死組織や非生存組織、異物の除去によって慢性創傷の環境を良好にする効果が期待できます。
デブリードマンは必ずしもDFUの完全治癒につながるとは限りませんが、治療の重要な前段階として機能します。
血行再建術
糖尿病性足病変と末梢四肢虚血の両方がある場合、血行再建は有望な治療選択肢となります。
血行再建術の選択肢には、ステント留置術や、他の治療が不可能な場合の外科的バイパス術などがあります。
アテレクトミー、石灰化病変に対する衝撃波治療、バルーンによる血行再建術(カッティング、薬剤コーティング、クライオプラスティ)は単独、あるいはステント留置術と併用できます。
植皮
糖尿病性足病変が重症化した場合の解決策として、皮膚移植があります。
皮膚移植には、生体工学的手法や人工皮膚、自家移植(患者から採取)、同種移植(他人から採取)などの手法があります。
切断
切断は、DFUを治療する際の最終的な管理オプションであり、感染などによって足が機能しなくなった場合にのみ行われます。
切断には小切断と大切断があり、小切断はより小さな部位の切断(足の指や足の一部の切断など)。一方、大切断は膝や肘などの主要な関節の上または下で行われます。
リハビリテーション
糖尿病性足病変のリハビリテーションには、理学療法や歩行訓練、装具の使用があります。
| リハビリテーション | 内容 |
|---|---|
| 理学療法 | 足の筋力を強化し、血流を促進するための運動を行う。 |
| 歩行訓練 | 適切な歩行技術を学び、足への不適切な圧力を避ける。 |
| 装具の使用 | 足の位置を正しく保つために、特殊な靴や装具を用いる。 |
糖尿病性足病変の治療期間と予後
糖尿病性足病変の治療期間は、軽度の潰瘍であれば数週間から数ヶ月程度、重度の潰瘍では数ヶ月から1年以上が目安です。
糖尿病性足病変の治療期間と予後は、患者様の病状、治療への反応、および適切なケアの継続性に大きく依存します。
治療期間
糖尿病性足病変の治療期間は、症状の重さや治療方法によって大きく異なります。
軽度の潰瘍や感染であれば数週間から数ヶ月の治療で改善する場合がありますが、重度や合併症がある場合は、より長期間の治療が必要になる場合が多いです。
また、足の構造に関わる問題や血流の大きな障害がある場合には、手術を含む治療後も長期にわたるフォローアップが必要になります。
| 状況 | 治療期間の目安 |
|---|---|
| 軽度の潰瘍 | 数週間から数ヶ月 |
| 重度の潰瘍 | 数ヶ月から1年以上 |
| 手術を行う場合 | 手術後の回復期間に加えて長期フォローアップが必要 |
予後
糖尿病性足病変の予後は、早期診断と治療の開始、糖尿病の適切な管理、定期的な足のチェックとケアによって大きな差が生まれます。
治療指示が守れない場合や糖尿病のコントロールが悪い場合では、感染の悪化や足の損失を招く恐れがある点には注意が必要です。
糖尿病患者様の約15%が最終的に糖尿病性足病変を発症し、その14%~24%が骨感染やその他の潰瘍関連合併症のために潰瘍足の切断を余儀なくされます。
糖尿病性足病変は再発しやすいため、治癒後も定期的な足の自己チェックと医療機関でのフォローアップが必要です。
| 状況 | 予後 |
|---|---|
| 軽度の潰瘍 | 早期治療と適切なケアにより良好な予後が期待できる。 |
| 重度の潰瘍 | 長期間の治療と管理が必要。予後は治療の適切性に依存する。 |
| 手術を行う場合 | 定期的なフォローアップにより再発防止と予後改善が見込まれる。 |
薬の副作用や治療のデメリット
糖尿病性足病変の治療に使用される薬や治療法は、症状の緩和に役立つ一方で、副作用やデメリットがあります。
治療薬の副作用
糖尿病性足病変の薬の副作用には、胃腸の不調や腹痛、下痢、アレルギーなどがあります。
| 治療薬 | 副作用 |
|---|---|
| 抗生物質 | 胃腸の不調、腹痛、下痢、アレルギー反応など |
| 消炎鎮痛薬 | 長期使用による胃腸障害、腎機能の損傷、心血管系への影響など |
| 糖尿病薬 | 低血糖、体重増加、消化器系の問題など |
糖尿病性足病変の治療のデメリット
糖尿病性足病変の治療のデメリットは治療方法によって異なりますが、痛みや感染リスクの増加、回復期間の長期化などが挙げられます。
| 治療方法 | デメリット |
|---|---|
| デブリードマン | 痛みを伴い、感染リスクの増加 |
| 圧力軽減装具の使用 | 一部の患者様にとっては不便であり、装具に適応するまでに時間がかかる場合があります。また、装具の誤った使用は、足の他の部位に問題を引き起こす可能性があります。 |
| 手術 | 感染のリスク、回復期間の長期化の可能性、機能の損失が伴う場合がある |
保険適用の有無と治療費の目安について
糖尿病性足病変の治療は、基本的には健康保険の適用範囲内となります(通院治療や薬剤療法、必要に応じた検査などを含みます)。
また、特定疾患療養管理料や再診料なども保険適用となります。
一方で、血小板由来成長因子や幹細胞治療、体外衝撃波などは保険適用外治療であり、全額自己負担です。
治療費の目安
1か月あたりの治療費は患者さんの状態や治療内容により異なるものの、通院治療で約8,900円~10,240円、入院治療で数万円以上が目安です。
| 治療方法 | 保険適用 | 1か月あたりの治療費 |
|---|---|---|
| 通院治療 | あり | 約8,900円から10,240円 |
| 入院治療 | あり | 数万円以上 |
| 保険外治療 | なし | 医療施設による |
以上
参考文献
Armstrong DG, Tan TW, Boulton AJ, Bus SA. Diabetic foot ulcers: a review. Jama. 2023 Jul 3;330(1):62-75.
Edmonds M, Manu C, Vas P. The current burden of diabetic foot disease. Journal of clinical orthopaedics and trauma. 2021 Jun 1;17:88-93.
Monteiro‐Soares M, Boyko EJ, Jeffcoate W, Mills JL, Russell D, Morbach S, Game F. Diabetic foot ulcer classifications: A critical review. Diabetes/metabolism research and reviews. 2020 Mar;36:e3272.
Reardon R, Simring D, Kim B, Mortensen J, Williams D, Leslie A. The diabetic foot ulcer. Australian Journal of General Practice. 2020 May;49(5):250-5.
Schaper NC, van Netten JJ, Apelqvist J, Bus SA, Hinchliffe RJ, Lipsky BA, IWGDF Editorial Board. Practical guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update). Diabetes/metabolism research and reviews. 2020 Mar;36:e3266.
Chang M, Nguyen TT. Strategy for treatment of infected diabetic foot ulcers. Accounts of chemical research. 2021 Feb 17;54(5):1080-93.
Pourkazemi A, Ghanbari A, Khojamli M, Balo H, Hemmati H, Jafaryparvar Z, Motamed B. Diabetic foot care: knowledge and practice. BMC endocrine disorders. 2020 Dec;20:1-8.
Van Netten JJ, Bus SA, Apelqvist J, Lipsky BA, Hinchliffe RJ, Game F, Rayman G, Lazzarini PA, Forsythe RO, Peters EJ, Senneville E. Definitions and criteria for diabetic foot disease. Diabetes/metabolism research and reviews. 2020 Mar;36:e3268.
McDermott K, Fang M, Boulton AJ, Selvin E, Hicks CW. Etiology, epidemiology, and disparities in the burden of diabetic foot ulcers. Diabetes Care. 2023 Jan 2;46(1):209-21.
Lipsky BA, Senneville É, Abbas ZG, Aragón‐Sánchez J, Diggle M, Embil JM, Kono S, Lavery LA, Malone M, van Asten SA, Urbančič‐Rovan V. Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). Diabetes/metabolism research and reviews. 2020 Mar;36:e3280.