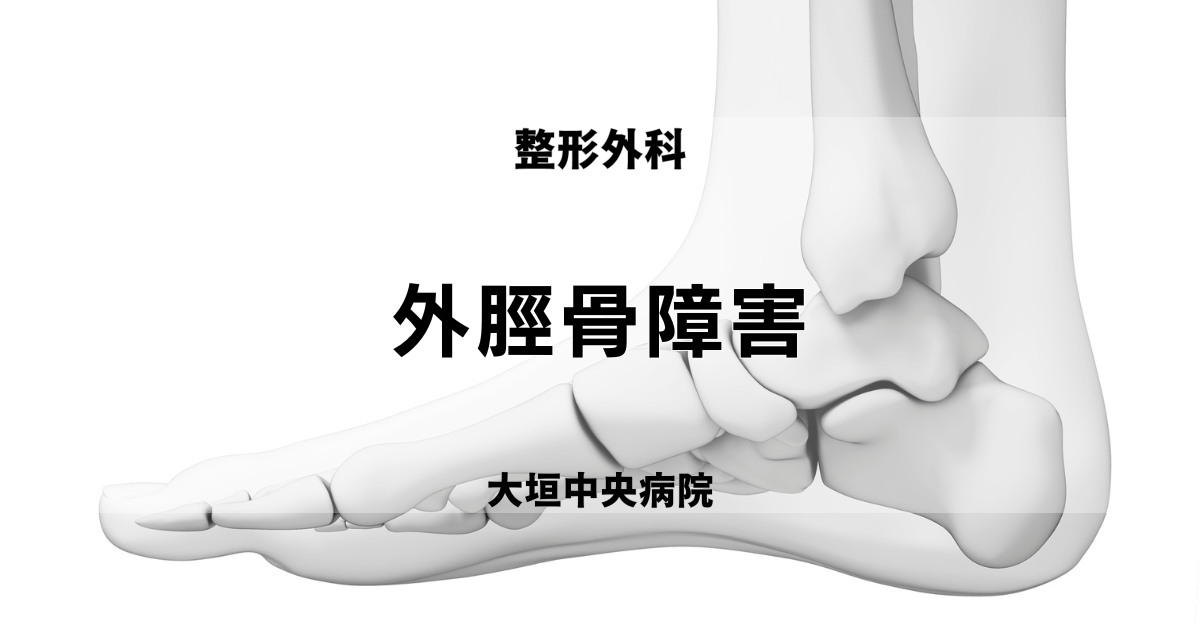外脛骨障害(がいけいこつしょうがい、Accessory Navicular Syndrome)とは、足首の内側に位置する小さく余分な骨である外脛骨に異常が認められ、痛みや腫れを引き起こす疾患です。
足の使いすぎや特定の動きによって発症しやすく、特にランナーやアスリートに多く見られます。
外脛骨障害が生じると、歩行や走行時の不快感が増し、日常生活に支障をきたすおそれがあります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
外脛骨障害の分類
外脛骨(がいけいこつしょうがい)は、海外ではAccessory Navicular boneと呼ばれ、正しい表現は副舟状骨です。
この余分な骨は後脛骨筋腱の中に存在し、外脛骨があるのは全体の10%程度で、ほとんどの場合特に問題は見られません。
しかし、骨や周囲の腱が刺激を受けて炎症を起こすと、足の内側に痛みを引き起こす外脛骨障害となる場合があります。
通常、舟状骨の痛みは適切な治療によって数週間で落ち着きますが、長引く場合は手術の検討が必要です。
外脛骨障害は大きく3つのタイプに分類され、症状や痛みの現れ方が異なります。
| Type1 | 後脛骨筋腱の内側にある小さな円形または楕円形の小さな副骨です。舟状骨とはつながっていません。副舟状骨の約30%が1型でほとんど無症状です。後脛骨筋腱の足底側、底側踵舟靭帯の高さに見られます。外脛骨骨(os tibiale externum)または外舟状骨(os naviculare secundarium)とも呼ばれます。 |
|---|---|
| Type2 | 直径12mm前後のハート型または三角形の骨です。舟状骨とは厚い軟骨層でつながっています。副舟状骨の約55%が2型で、付着する角度によって2つに区別されます。IIA型は距骨突起とあまり鋭角に付着せず、IIB型はより下方に付着します。 |
| Type3 | 副舟状骨が骨を介して舟状骨に癒合(結合)し、角状骨となる最も大きなタイプです。付属舟状骨の約15%が3型で、画像上の外観によりさらにa・b・cのサブタイプに分かれます。 |
外脛骨(副舟状骨)は通常、無症状の小骨であり、レントゲン写真で偶然発見されますが、特に2型では疼痛が報告されています。
症候性外脛骨の疼痛の原因については、常に議論の的となっており、最近では靴に対する圧迫、使い過ぎ、捻りによる損傷から生じる緊張、剪断、圧迫力などの局所的な機械的要因に関連していると考えられています。
足部および足関節における副骨の発生率は、一般集団で2~25%と幅がありますが、疫学的にはヨルダンの研究で21%、中国の研究で20%、アジアの研究で46.0%、トルコの研究で11%です。
外脛骨障害の鑑別診断は剥離骨折、足根骨骨折、関節炎、後脛骨筋腱断裂で、さらに扁平足や後脛骨筋腱(PTT)不全などの特定の病態は、特に2型と3型に関連します。
外脛骨障害の症状
外脛骨障害の一般的な症状は、足の特定の部位に生じる痛みや腫れ、不快感です。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 痛み | 足の外側、特に外踝の直下に生じる。活動中に悪化しやすい。 |
| 腫れ | 痛みのある部位の周囲に見られる。 |
| 圧痛 | 痛みのある部位を軽く押したときに感じる痛み。 |
| 活動時の制限 | 走る、ジャンプするなどの活動を行う際に、痛みや不快感が増し、パフォーマンスに影響が出る。 |
痛み
外脛骨障害による痛みは、足の内側のアーチ部分に集中する傾向があります。鈍痛やズキズキするような痛みで、運動中や運動後に悪化するケースが多いです。
また、付属舟状骨に直接圧力が加わったり、足を急にひねったりすると、内側アーチに鋭い痛みが生じる場合もあります。
腫れ
痛みがある部位の周囲に腫れが生じる場合もあります。また、足の内側、土踏まずの上部に小さなしこりができます。
しこりは目で見たり触ったりでき、靴と擦れると不快に感じるケースも少なくありません。
圧痛
痛みや腫れが出ている部分を軽く押すと、圧痛が生じるのが一般的です。
腫れや圧痛の程度は、活動量や日によって異なる場合があります。
活動時の制限
外脛骨障害になると、走る、ジャンプする、あるいは急な方向転換を伴うスポーツ時に痛みや不快感が増すため、パフォーマンスの低下につながりかねません。
特に、外脛骨による後脛骨筋腱の炎症がある場合、つま先立ちが困難となるおそれがあります。
外脛骨障害の原因
外脛骨障害は、足の過度な使用や構造上の問題、不適切な靴の使用などによって生じます。
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 過度の使用 | 足の使いすぎによる過剰なストレス |
| 不適切な足のアライメント(骨格の配列) | 扁平足やハイアーチなど、足の構造的問題による不均等な圧力分散 |
| 不適切な靴 | 足の形状に適していない靴の使用 |
| 急激な活動量の増加 | 新しい運動プログラムを始めたり、運動の強度を突然上げたりすると起こる |
| 人種、性別 | アジア人、女性に発症しやすい |
過度の使用(オーバーユース)
外脛骨障害の最も一般的な原因は、運動や活動による過度の使用です。
特に、ランニングやジャンプ、長時間の立ち仕事など、足に繰り返し負担をかける動作は、外脛骨に対して過剰なストレスを与えるおそれがあります。
こうした過度のストレスにより外脛骨周辺の組織に炎症を引き起こし、痛みや腫れの原因となります。
不適切な足のアライメント
足のアライメント(骨格の配列)が不適切であると、外脛骨障害につながるリスクが高まります。
扁平足やハイアーチなど、足の構造的な問題によりバイオメカニクスが変化している人は、足への圧力分散が不均一となり、後脛骨筋腱や外脛骨に過度のストレスをかける場合があるためです。
不適切な靴
適切なアーチのサポートがない靴を履いていると、足の力学的問題が悪化し、外脛骨にさらなるストレスがかかります。
窮屈な靴は、余分な骨片と擦れ合い、慢性的な刺激や炎症を引き起こして外脛骨障害につながるため注意が必要です。
急激な活動量の増加
新しい運動プログラムを始めたり、運動の強度を突然上げたりすると、外脛骨とその周辺組織に対して適応する時間が不足し、炎症や痛みを引き起こす可能性があります。
また、思春期に骨化(副舟状骨が軟骨から骨に変化すること)と運動量の増加が相まって発症するケースも多いです。
後脛骨筋の硬さは、後脛骨筋腱の緊張と炎症を高め、外脛骨を刺激するおそれがあります。
人種、性別
アジア人は外脛骨の有病率がかなり高く、また女性は男性の約2倍の有病率です。
外脛骨障害の検査・チェック方法
外脛骨障害の診断には、身体所見や画像検査が用いられます。
- 身体所見
- X線
- MRI
- 超音波
身体所見
身体所見では足の構造を詳細に観察し、外脛骨の位置や腫れ、痛みの有無をチェックします。
- 圧痛点の同定:外脛骨周囲を軽く圧迫し、痛みの有無を確認します。
- 足のアライメントの評価:足の形状、特に扁平足やハイアーチなどの異常が外脛骨に影響を与えていないかを評価します。
- 歩行分析:歩行時や走行時の足の動きを観察し、外脛骨に異常な負担がかかっていないかをチェックします。
画像検査
X線、MRI、超音波などの画像検査により、外脛骨の程度や、周囲の組織に影響があるかどうかを詳細に調べられます。
- X線:骨の変形や外脛骨自体の異常を検出します。
- MRI:軟部組織や骨の詳細なイメージを提供し、損傷の程度を評価します。
- 超音波:腱や靭帯の損傷を視覚化し、外脛骨の位置異常を確認します。
外脛骨障害の治療方法と治療薬、リハビリテーション
外脛骨障害の治療の目的は、患部への負担を減らして痛みを和らげ、正常な機能を回復させることです。
通常は非手術的な治療から開始しますが、重度の場合は手術が必要となる場合もあります。
非手術的治療法
非手術的治療では、安静を維持して足への負担を軽減することが重要です。
痛みが強い場合は、装具による固定やアイシングなどを行います。
- 安静:足に過度の負担がかかる運動や活動など、症状を悪化させるような活動を避けます。
- 固定:重症の場合は、患部を休ませて治癒させるために、通常2~3週間、ギプスや取り外し可能なウォーキングブーツを装着します。
- アイシング:定期的に冷やす(薄いタオルで覆った氷の入った袋を患部に当てる)と、外脛骨障害の痛みや炎症を抑えられます。
治療薬について
外脛骨障害の痛みや炎症を軽減するために、イブプロフェンやロキソニンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が一般的に処方されます。
しかし、これらの薬剤には副作用やリスクも伴うため、医師の指示に従い、適切な用量と期間を守って使用しなければなりません。
また、炎症を抑えるために、副腎皮質ステロイド注射を行う場合もあります。
リハビリテーション
リハビリテーションの目的は、足首や足の筋肉を強化し、支える機能を高めることです。柔軟性を高めるストレッチング、筋力を強化するエクササイズ、バランス能力を向上させる訓練などが含まれます。
また、適切な靴(クッション性のある幅広の靴)への変更や、整形外科用のインソールの使用なども治療の一環です。
理学療法士は、歩行の改善や歩行の再教育についてもアドバイスします。
手術療法
非手術的治療では改善が見られない場合、または再発を繰り返す場合は手術の検討が必要です。
外脛骨のタイプや関連する足の問題によって、外脛骨切除術やキンダー法、再調整または再建手術の選択肢があります。
最も一般的な手術は、外脛骨を切除する方法です。足の内側を切開し、外脛骨を取り除きます。
足の甲のすぐ上を切開します。後脛骨筋腱を外脛骨から切り離します。外脛骨を舟状骨から切り離し、余分な骨を取り除きます。その後、後脛骨筋腱を舟状骨に再接着します。
生体力学的な問題があると、アライメントを矯正する手術も同時に行う場合があります。腓腹筋などの硬くなった構造をリリースしたり、後脛骨筋腱を引き締めたりするほか、足の骨の一部を切断して金属プレートやスクリューで位置を変える扁平足再建術が含まれます。
外脛骨障害の治療期間と予後
外脛骨障害の治療期間は数週間から数か月で、予後は多くのケースで良好です。
治療期間の目安
外脛骨障害の治療後、日常生活に戻るまでの期間は、治療方法や個々の状態によって大きく異なります。
非手術的治療法を行った場合、通常は数週間から数か月で少しずつ、以前のように活動できるようになります。外科的治療を受けた場合は、完全な回復までに数か月程度かかるのが一般的です。
回復期間中は、医師の指導の下でリハビリテーションを行い、徐々に足への負担を増やしていきましょう。
予後について
外脛骨障害の治療後は、適切なリハビリテーションを続ければ以前の活動レベルに戻れるケースがほとんどです。
しかし、症状が重度の場合や治療が遅れた場合、長期的な痛みや不快感が残るおそれがあります。
良好な予後のためには、定期的なフォローアップと、必要に応じた生活習慣の調整が欠かせません。また、治療が完了したあとも、足部に負担をかけないような生活を心がけると再発防止につながります。
薬の副作用や治療のデメリット
外脛骨障害の治療に用いられる薬物や理学療法、手術療法などには副作用やデメリットもあります。
| 治療法 | 副作用及びデメリット |
| 非ステロイド性抗炎症薬 | 胃腸障害、心臓病リスクの増加、腎機能低下 |
|---|---|
| ステロイド注射 | 組織の弱化、感染リスク増大、骨損傷 |
| 理学療法 | 時間がかかる、完全な解決には至らないこともある |
| 装具 | 一時的な解決策、根本的な問題解決にはならない |
| 手術療法 | 感染、長期的な痛み、機能回復に時間がかかる |
薬物療法の副作用
痛みや炎症を和らげるために使用される非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、胃腸障害、心臓病のリスク増加、腎臓機能の低下などの副作用を引き起こす危険性があります。
長期間にわたってNSAIDsを服用する場合は特に注意が必要です。
また、ステロイド注射は短期間で痛みを大幅に減少させられる一方、関節周囲の組織の弱化、感染リスクの増大、関節内での繰り返し注射による骨の損傷などの副作用が生じるおそれがあります。
装具使用のデメリット
装具の使用は足を適切な位置にサポートし、痛みを軽減するのに役立ちますが、装着時に不快感を覚えたり、日常生活における活動が制限されたりする可能性があります。
また、装具によって症状を緩和できても、根本的な問題の解決には至らず、継続的な使用が必要となるケースもあります。
手術療法のリスクとデメリット
外科手術には感染や合併症などを引き起こすリスクがあります。
術後は長期にわたるリハビリテーションが必要となり、回復期間が長引きやすい点もデメリットです。また、手術後に完全な機能回復が保証されるわけではなく、再発するリスクもあります。
保険適用の有無と治療費の目安について
外脛骨障害の治療は、基本的には保険が適用されますが、治療法によっては一部保険適用外となるケースもあります。
保険適用の治療
理学療法や運動療法、装具療法、注射療法などは健康保険の適用範囲内で行われます。
保険適用外の治療
対外衝撃波療法は骨障害(偽関節や骨端症)が適応となり、除痛効果が期待できますが、保険適用外のため自己負担となります。
1か月あたりの治療費の目安
| 治療方法 | 保険適用の有無 | 1か月の治療費の目安 |
|---|---|---|
| 理学療法 | あり | 数千円 |
| 装具療法 | あり | 数千円 |
| 注射療法 | あり | 数千円 |
| 対外衝撃波療法 | なし | 数万円~十数万円 |
保険適用の治療であれば、1回あたり数千円程度が目安です。
ただし、自己負担額は保険の種類により異なるため、詳しい費用については治療を受ける医療機関に確認してください。
一方、対外衝撃波療法のような保険適用外の治療では、数万円から十数万円程度かかります。
参考文献
Rammelt S, Sands AK. The accessory navicular and its association with flatfoot. Fuß & Sprunggelenk. 2020 Mar 1;18(1):60-71.
Campbell JT, Jeng CL. Painful accessory navicular and spring ligament injuries in athletes. Clinics in Sports Medicine. 2020 Oct 1;39(4):859-76.
Pothiawala S. Os Navicular Syndrome: A Symptomatic Accessory Ossicle of the Foot. Case Reports in Clinical Practice. 2022 Nov 13.
Gursoy M, Mete BD, Cetinoglu K, Bulut T, Gulmez H. The coexistence of os trigonum, accessory navicular bone and os peroneum and associated tendon and bone pathologies. The Foot. 2022 Mar 1;50:101886.
Kim J, Day J. Medial Displacement Calcaneal Osteotomy as a Novel Treatment for Recurrent Pain after Kidner Procedure for Accessory Navicular Syndrome. Foot & Ankle Orthopaedics. 2020 Oct 22;5(4):2473011420S00291.
Wariach S, Karim K, Sarraj M, Gaber K, Singh A, Kishta W. Assessing the Outcomes Associated with Accessory Navicular Bone Surgery—a Systematic Review. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2022 Oct;15(5):377-84.
Yang A, Hennrikus WL, Bone PS, Institute Joint, Hershey PA. SURGICAL OUTCOMES OF ACCESSORY NAVICULAR IN ADOLESCENT ATHLETES. Orthopaedic Journal of Sports Medicine. 2021 Jul 30;9(7_suppl3):2325967121S00140.
Kim J, Day J, Seilern Und Aspang J. Outcomes following revision surgery after failed kidner procedure for painful accessory navicular. Foot & Ankle International. 2020 Dec;41(12):1493-501.
Özbalcı AB, Erdoğan F, Coskun HS. Avascular Necrosis of the Type II Accessory Navicular Bone: A Rare Case Report. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2022 May 1;112(3).
Candan B, Torun E, Dikici R. The prevalence of accessory ossicles, sesamoid bones, and biphalangism of the foot and ankle: a radiographic study. Foot & Ankle Orthopaedics. 2022 Jan;7(1):24730114211068792.