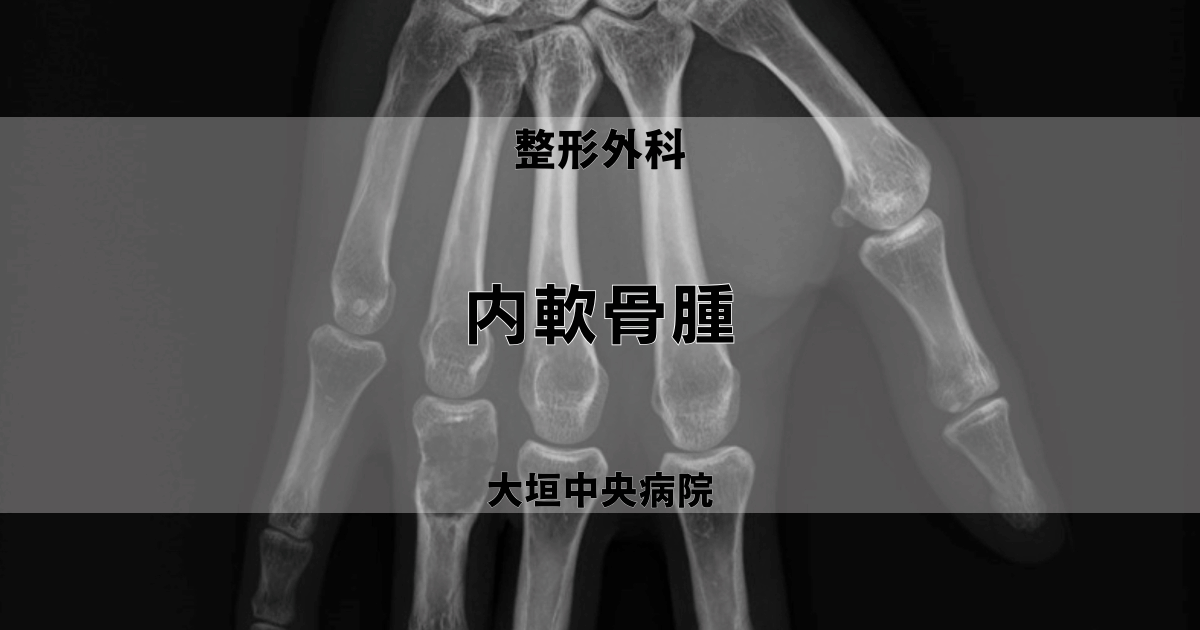内軟骨腫(Enchondroma)とは、骨の内部に軟骨が発生する良性腫瘍の一種です。
骨の成長や修復の過程で生じる可能性があり、多くの場合は手や足の小さな骨に生じますが、長管骨(大腿骨や上腕骨など)にも発生するときがあります。
痛みがなく経過するケースもありますが、骨折につながる症例もあり、早めに処置が必要です。
良性骨腫瘍の約10~25%を占める比較的一般的な骨腫瘍であり、男女性差なく発生します。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
内軟骨腫の病型
内軟骨腫は、主に発生部位や病変の広がり方で大きく3つの分類が存在します。
病型によって治療方針や経過観察の期間が変わる場合があるため、内軟骨腫を把握するときには病型の特徴を理解しておく必要があります。
単発性内軟骨腫
多くの内軟骨腫は単発(孤発性)で発生します。
孤発例の悪性化(軟骨肉腫への移行)リスクは極めて低く、報告によれば1%未満~最大でも数%程度とされています。
多発性内軟骨腫症(軟骨腫症)
複数の内軟骨腫が全身の骨に発生する病態で、Ollier病(オリエ病)と呼ばれます。左右非対称に多発する孤発的な疾患で、思春期までに発症します。
多発例では時間経過とともに一部が悪性化するリスクが高く、Ollier病では約25~30%の症例で軟骨肉腫への悪性転化が起こると報告されています。
Maffucci(マフチ)症候群
多発性内軟骨腫に加え、軟部組織の血管腫(主に静脈奇形)を合併するまれな疾患です。
悪性化リスクはOllier病と同程度(約25~30%)と高く、さらに中枢神経系や消化管など他臓器の悪性腫瘍(グリオーマや肉腫など)を合併する率も非常に高い点が知られています。
Maffucci(マフチ)症候群を含めた多発性内軟骨腫症では定期的な経過観察と、必要に応じた治療介入が重要です。
骨膜性軟骨腫(periosteal chondroma)
内軟骨腫と類似の組織学的特徴を示す良性軟骨腫瘍ですが、骨の内部ではなく表面(骨膜下)に発生する点が異なります。
骨膜軟骨腫は骨の表面にできる軟骨性病変であり、X線では骨表面の局所的な骨皮質の陥凹を伴う陰影として現れます。
内軟骨腫との違いは発生部位(骨内か骨表面か)のみで、治療方針は同じです。
その他の軟骨系腫瘍との比較
内軟骨腫と区別すべきものに骨軟骨腫(外骨腫)があります。
骨軟骨腫は骨の外表面に骨と軟骨の突起ができる良性腫瘍で、発生部位やX線像が明確に異なります(骨軟骨腫は骨端部から突出する角状の骨棘様病変)。
また、内軟骨腫と低悪性度軟骨肉腫(グレード1軟骨肉腫)の鑑別が臨床上重要です。
組織学的・画像的に両者の境界が曖昧な場合、軟骨肉腫グレード1相当の病変は現在では異型軟骨腫瘍(ACT: atypical cartilaginous tumor)と分類され、四肢に限っては局所的に浸潤・再発しうる「中間悪性」の腫瘍として取り扱われます。
鑑別には臨床症状や画像所見を総合的に評価する必要があります。
内軟骨腫の症状
内軟骨腫は初期に特有の症状が出ない方が多く、健康診断や他のケガの検査などで偶然発見されるケースもしばしばあります。
症状の有無によって治療の必要性や時期を検討するため、どのような症状が生じる可能性があるのかの理解が重要です。
| 症状 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 無症状 | 痛みや腫れなし | 偶然に発見されることが多い |
| 軽度の痛みや違和感 | 運動時や負荷時に痛みを自覚する | 慢性的・強い痛みはまれ |
| 骨折 | 小さな外力でも骨折を起こす | 骨折後の検査で初めて分かるケース |
| 骨変形 | 成長期に骨形成が偏る場合がある | 多発性内軟骨腫で顕著 |
無症状での経過
- 日常生活に支障がない
- 痛みや腫れがない
- 稀にレントゲンで偶然発見
内軟骨腫の特徴として、無症状のまま経過する例が多い点が挙げられます。
小さな病変や骨の強度に大きく影響しない部位に発生した場合、長期間放置されるケースも少なくありません。
軽度の痛みや違和感
- 運動や負荷時に出現
- 休めば改善することが多い
- 持続的な痛みは少ない
骨が脆くなる程度に腫瘍が大きくなると、周辺組織や骨膜に負荷がかかって軽い痛みや違和感を生じる場合があります。
痛みは慢性的というより、運動時など骨にストレスが加わったときに感じるケースが多いです。通常軽度ですが、軟骨肉腫への変化が起こっている場合は安静時にも持続する強い痛みが出現するときがあります。
このため疼痛の有無は鑑別上重要な要素です。
- 指や手首、足首を動かしたときにピリッとした軽い痛みがある
- 重い物を持つときに骨の深部で違和感がある
- 長時間運動したあとに鈍痛がある
軽い痛みや骨の深部での違和感程度のため、放置されがちです。
骨折
- 軽い転倒や衝撃で骨折
- 骨折を契機に発見されるケース
- 痛みや腫れが著明になる
内軟骨腫によって骨の内部が脆くなると、外力が小さくても骨折を起こす病的骨折(pathological fracture)が発生するケースがあります。
無症状で経過していても、骨折がきっかけとなり発覚する例があるため(特に指の骨で多いです)要注意です。
骨変形
- 指の変形や短縮
- 手足の変形
- 見た目の問題による精神的ストレス
多発性の内軟骨腫症(Ollier病など)では、骨の成長が不均衡になりやすく、四肢や指の変形が生じる場合があります。
小児期や思春期に骨の成長が盛んな時期に病変が目立つと、変形が大きくなる場合があり、機能面だけでなく外見上の問題にもつながります。
内軟骨腫の原因
内軟骨腫の原因は完全には解明されていませんが、分子遺伝学的異常と発生過程の異常の両面から原因が考えられています。
成長過程における軟骨形成の異常
- 正常な骨化過程の乱れ
- 遺伝子変異の関与が指摘される
- 骨の端(骨端近く)での病変が多い
骨の発生過程では軟骨組織が徐々に骨組織に置き換わる仕組みがありますが、この過程で異常が起こると骨内に軟骨組織が残るときがあります。
つまり、骨の成長板(骨端線)※1から軟骨の一部が髄内に取り残されたり逸脱した結果、骨内でその軟骨片が増殖することで腫瘍化するという仮説です。
※1成長板(骨端線):骨の端にある軟骨組織。成長期にしか存在せず、小児が十分な身長に達するまで骨を伸ばす働きがある。成長が止まるとこの部分は骨に置き換わる。
長管骨の骨端線閉鎖(成長終了)後は新たな発生がほとんどみられない点から、この発生要因が示唆されています。
遺伝子変異
近年、内軟骨腫の大部分でIDH1またはIDH2遺伝子の変異が見つかることが明らかになりました。
多発性内軟骨腫症(Ollier病やMaffucci症候群)の内軟骨腫では87%という高率でIDH1/2変異が報告されており、孤発性内軟骨腫でも約52%に同様の変異が検出されています。
外傷との関連
- 骨折治癒過程における軟骨修復の異常
- 局所的な炎症や刺激
- エビデンスはまだ不十分
大きな外力や骨折をきっかけに、局所で軟骨修復機構が活性化して腫瘍化する可能性を指摘する意見もあります。
ただし、明確に外傷だけが原因で内軟骨腫が生じるという確立された説はありません。
生活習慣や環境要因
- 喫煙やアルコールは骨代謝に影響を与える可能性があるが、因果関係は不明
- 骨粗鬆症とは異なり、カルシウムやビタミンDの不足との関連性は薄い
- 現時点で予防的な生活習慣指導は確立していない
生活習慣や食事、環境要因との直接的な関連性は確認されていません。内軟骨腫は遺伝的要因や成長過程の異常が主たる原因と考えられるため、喫煙や飲酒、食事バランスとの因果関係は明確ではありません。
基本的には偶発的な遺伝子変異や発生過程の異常による良性腫瘍と位置づけられます。
内軟骨腫の検査・チェック方法
内軟骨腫の診断には画像検査が中心となります。痛みや骨折などの自覚症状で発見に至るケースもありますが、無症状で偶然見つかる例も多いため、複数の検査を組み合わせて正確な診断を行います。
最初の診察では問診と身体所見を確認し、その後にレントゲン検査やCT検査、MRI検査などの画像検査を行うのが一般的です。また、必要に応じて骨シンチグラフィや血液検査を追加します。
レントゲン検査
- 低コストで受けやすい
- 画像上の特徴的な石灰化パターン
- 進行状況の目安が分かる
レントゲン検査(X線検査)は内軟骨腫を疑う際の基本的な検査です。
骨の内部に“ポップコーン状”や“リング状”の石灰化像(軟骨成分の石灰沈着)が見られるケースが多く、腫瘍の位置や大きさ、骨皮質の状態などを確認します。
骨皮質は薄く膨隆するときがありますが、連続性は保たれ骨破壊像はありません。また、骨膜反応も認めません。
レントゲン検査の特徴
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| コスト | 比較的安価な検査 | – |
| 被ばく量 | 一般的なX線量でリスクは低い | 被ばくを完全に回避はできない |
| 情報量 | 骨の状態や石灰化を把握可能 | 軟部組織の評価には不十分 |
| 実施時間 | 短時間 | – |
CT検査
- 骨構造の詳細を観察
- 手術前のシミュレーションに便利
- 被ばく量はレントゲンより多い
レントゲン検査より詳細な骨の構造を3次元的に把握できるのがCT検査です。
腫瘍の広がりや骨皮質の厚み、内部の石灰化の様子を立体的に観察できるため、手術の計画にも役立ちます。
MRI検査
- 軟骨組織や骨髄の状態を評価
- 被ばくの心配なし
- 高コストで検査時間が長め
MRI検査は軟骨組織の評価に優れ、内軟骨腫の良性・悪性鑑別にも有用です。軟骨特有の信号強度を確認でき、骨髄内の変化や周辺組織への広がりも分かります。
内軟骨腫はMRIで髄内の境界明瞭な腫瘍として描出されます。
造影MRIでは腫瘍辺縁や内部中隔に沿って造影剤の取り込みが見られますが、これは低悪性度軟骨肉腫でも類似のパターンを示すため鑑別点にはなりません。
画像検査の活用場面
| 検査 | 活躍場面 |
|---|---|
| レントゲン | 初期スクリーニング、簡易的な経過観察 |
| CT | 腫瘍範囲と石灰化分布、手術計画 |
| MRI | 腫瘍の良性・悪性鑑別、周辺組織の状態把握 |
骨シンチグラフィ・血液検査
骨シンチグラフィは、骨代謝の活性度合いをチェックできる検査です。高い集積がみられる場合は腫瘍の活動性が強い可能性も示唆しますが、良性腫瘍でも多少は集積がみられるため総合的な判断が必要です。
血液検査では腫瘍マーカーなどを測定し、悪性化の可能性などを把握する場合もあります。補助的な位置づけの検査です。
病理組織学的検査
画像上明らかに良性と判断できれば必ずしも組織診断は行いませんが、悪性との鑑別が問題となる場合や手術で摘出した場合には病理検査を行います。
内軟骨腫の病理組織像は、硝子軟骨が充実性あるいは小葉状に増殖した所見を示します。
軟骨細胞は比較的整然と配列し、核の肥大化や二分裂像(binucleation)はあっても強い異型や多核巨細胞の増生は認められません。細胞密度もまばらで、粘液変性を伴うケースもあります。
軟骨肉腫との違い
これに対し軟骨肉腫(特にグレード1)は、わずかながら細胞密度の増加や核異型の強さ、骨浸潤の所見などで内軟骨腫と異なります。
しかしその差は微妙で、経験豊富な専門家でも鑑別に苦慮するケースがあります。
そのため診断には病理所見だけでなく、患者の症状(安静時痛の有無など)や画像上の所見(骨皮質の破壊や軟部腫瘤の有無など)を総合して判断することが推奨されます
内軟骨腫の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
内軟骨腫の治療は、腫瘍の大きさや症状の有無、骨折リスク、患者の年齢や活動レベルなどを総合的に考慮して決定します。
無症状で骨折リスクが低い場合には経過観察を選択する例もありますが、痛みがある場合や骨折リスクが高い場合は手術的治療を検討します。
経過観察
- 症状のない小さな内軟骨腫
- 定期的な画像検査が中心
- 骨折リスクが高くなるようなら治療方針を再検討
小さく症状のない内軟骨腫では、定期的な画像検査による経過観察が一般的です。
半年から1年おきにレントゲン検査などを行い、大きさの変化や骨の状態をチェックします。症状が無ければ過度な治療介入を避けるのが原則です。
外科的治療
- 腫瘍掻爬術(腫瘍のかき出し)
- 骨移植(自家骨移植または人工骨)
- 術後の固定やリハビリテーション
痛みを伴うケースや骨折リスク(骨皮質が薄い、大きく膨隆しているなど)があるケース、悪性の可能性を否定しきれないケースでは、掻爬術(そうはじゅつ)と呼ばれる腫瘍部位を削り取る手術を行う場合があります。
掻爬後の骨欠損部には骨移植や人工骨を充填して骨強度を補います。
外科的治療の流れ
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 1. 診断 | 画像検査や生検で病変の性質を把握 |
| 2. 掻爬術 | 腫瘍をかき出し、残存腫瘍組織が残らないよう処置 |
| 3. 骨移植 | 欠損部に骨移植や人工骨を充填 |
| 4. 固定 | ギプスやプレートなどで骨を安定化 |
| 5. リハビリ | 骨癒合を促進し、機能回復を図る |
治療薬
- 鎮痛薬(NSAIDsなど)
- 消炎鎮痛薬
- ビタミンD、カルシウム製剤(骨折時の補助として)
内軟骨腫そのものを直接縮小させる薬剤はありません。悪性腫瘍ではないため抗がん剤などの化学療法や放射線療法の適応もありません。
痛みがある場合や骨折後の炎症を抑える目的で鎮痛薬や消炎鎮痛薬を使用します。
また、骨癒合を促すためにビタミンDやカルシウム製剤を補助的に利用するケースがありますが、あくまでサポート的な位置づけです。
リハビリテーション
- 固定期間終了後に運動療法を開始
- 筋力強化と関節可動域の確保
- 痛みや炎症があるときは無理をしない
外科的治療を行ったあとのリハビリテーションは、骨折の有無や手術の方法に応じて異なります。
適切な時期に関節運動や筋力トレーニングを行い、関節可動域の低下や筋力低下を防ぎます。
治療期間の目安
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 掻爬術+骨移植のあとの骨癒合 | 3~6か月 |
| スポーツ復帰 | 6~12か月 |
| 痛みがない場合 | 定期検査のみ(半年~1年ごと) |
外科的治療後の骨癒合には3~6か月程度かかるのが一般的です。
骨折の有無や年齢、健康状態によって差がありますが、完全なスポーツ復帰や重労働への復帰までには6~12か月を要する人もいます。
経過観察の場合は、半年から1年に1回程度の検査で十分なケースが多いです。
薬の副作用や治療のデメリット
内軟骨腫の治療では、手術時のリスクや使用する薬剤の副作用、長期的な機能障害などが考えられます。
鎮痛薬・消炎鎮痛薬の副作用
内軟骨腫に直接作用する薬剤がないため、痛みや炎症に対しては鎮痛薬(NSAIDsなど)を使うケースがあります。
これらは長期連用すると胃腸障害や腎機能への影響が出る場合があります。
- 胃腸障害(胃もたれ、胃潰瘍など)
- 腎機能障害
- 血圧上昇の可能性
外科的治療におけるリスク
掻爬術や骨移植などの外科的処置には、手術に伴う一般的なリスクのほか、骨移植部の定着不良や感染、再発などの可能性があります。
手術を実施する際には、これらのリスクを事前に医師と十分に相談しましょう。
| デメリット | 対策・備考 |
|---|---|
| 感染リスク | 滅菌環境下での手術、抗菌薬予防投与 |
| 再発リスク | 適切な掻爬と定期的な画像フォローアップ |
| 骨移植部の定着不良 | 術後の安静や適切なリハビリ |
| 神経・血管損傷の可能性 | 解剖学的知識を踏まえた丁寧な手技 |
リハビリテーションの負担
手術を行ったあとのリハビリテーション期間は、患者さんにとって身体的・精神的な負担になります。
決められたメニューを根気強く続ける必要があるため、仕事や学業、家事との両立に苦労するかもしれません。
- 定期的な通院リハビリ
- 運動や生活制限のストレス
- 長期的な計画が求められる
長期観察の必要性
無症状であっても、内軟骨腫の経過を長期的に観察する必要があります。
症状が出なくても数年後に変化が生じる場合があり、骨折や変形が起こる可能性がゼロではありません。
- 定期的なレントゲンやMRI検査
- 痛みや腫れ、変形の自己チェック
- 医療費や時間的負担
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
内軟骨腫の治療は日本の公的医療保険(健康保険)の対象となるため、一定の自己負担割合(通常3割、年齢や所得により異なる)が適用されます。
治療の内容や入院の有無によって費用が変わりますので、大まかな目安を把握しておくと良いでしょう。
診察・検査費用
レントゲン検査やMRI検査、CT検査などは保険適用内で受けられます。
自己負担3割の場合、初診料とレントゲン検査を合計すると3,000~5,000円前後、MRI検査を追加すると1回あたり5,000~10,000円ほどになるケースが多いです。
| 検査項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| レントゲン検査 | 1,000~2,000円 |
| CT検査 | 3,000~6,000円 |
| MRI検査 | 5,000~10,000円 |
| 血液検査 | 1,000~2,000円 |
手術・入院費用
掻爬術や骨移植を伴う手術を受ける場合、入院期間は1~2週間程度になるのが一般的です。
自己負担3割として、手術費用と入院費を合計すると10万円以上になるケースもあります。個室や差額ベッド代などを選ぶとさらに費用が加算されます。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 手術基本料 | 2万~5万円 |
| 麻酔費 | 5,000~2万円 |
| 入院基本料 | 5,000~1万円/日 |
| 検査費・処置費 | 数千円~1万円程度 |
リハビリテーション費用
- 通院リハビリは1回あたり数百円~1,000円前後
- 週に2~3回通院するケースもあり
リハビリテーションについても健康保険の適用があります。通院リハビリの場合は1回あたり数百円から1,000円程度の自己負担で受けられる人が多いです。
回数や期間によって費用は変動しますが、月に数千円~1万円程度になるのが一般的です。
高額療養費制度
- 高額療養費制度の事前申請で限度額認定証の交付を受けられる
- 月ごとに上限を超えた分が還付される
- 所得区分によって上限額は変動
高額な治療が長期化するときは、高額療養費制度を利用できます。
この制度を活用すると、自己負担額が一定の上限を超えた分が後から払い戻しされるため、入院や手術費が高額になった場合でも経済的負担が軽減します。
所得や年齢に応じて上限額が異なるので、事前に確認すると安心です。
以上
参考文献
FLEMMING, Donald J.; MURPHEY, Mark D. Enchondroma and chondrosarcoma. In: Seminars in musculoskeletal radiology. Copyright© 2000 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA, 2000. p. 0059-0072.
LUBAHN, John D.; BACHOURA, Abdo. Enchondroma of the hand: evaluation and management. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2016, 24.9: 625-633.
TANG, Chris, et al. Current management of hand enchondroma: a review. Hand Surgery, 2015, 20.01: 191-195.
MIRRA, JOSEPH M., et al. A new histologic approach to the differentiation of enchondroma and chondrosarcoma of the bones: a clinicopathologic analysis of 51 cases. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 1985, 201: 214-237.
MURPHEY, Mark D., et al. Enchondroma versus chondrosarcoma in the appendicular skeleton: differentiating features. Radiographics, 1998, 18.5: 1213-1237.
CHUN, Kyung Ah, et al. Enchondroma of the Foot. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 2015, 54.5: 836-839.
CRIM, Julia, et al. Can imaging criteria distinguish enchondroma from grade 1 chondrosarcoma?. European journal of radiology, 2015, 84.11: 2222-2230.
WANG, X. L., et al. Low-grade chondrosarcoma vs enchondroma: challenges in diagnosis and management. European radiology, 2001, 11: 1054-1057.
GEIRNAERDT, M. J., et al. Usefulness of radiography in differentiating enchondroma from central grade 1 chondrosarcoma. AJR. American journal of roentgenology, 1997, 169.4: 1097-1104.
CHOI, Bo-Bae, et al. MR differentiation of low-grade chondrosarcoma from enchondroma. Clinical imaging, 2013, 37.3: 542-547.