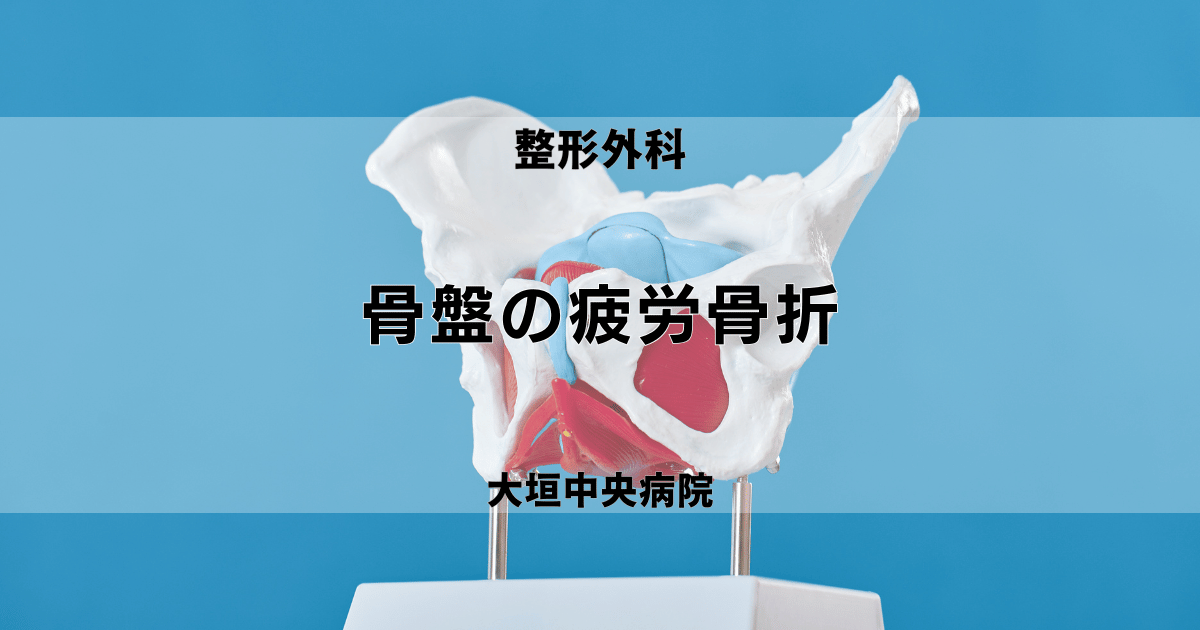骨盤の疲労骨折(Pelvic stress fracture)とは、ランニングやジャンプなど反復的な衝撃が骨盤周辺に蓄積し、骨の微小なひび割れが徐々に進行して起きる骨折の一種です。
軽い痛みや違和感から始まり、無理を続けると筋肉や関節への影響が大きくなって日常動作もつらくなるケースがあります。
早めに専門医へ相談して治療を始めると、回復までの期間を短縮しやすく、再発予防にもつながります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨盤の疲労骨折の病型
骨盤は腰椎の下部に接合し、寛骨(腸骨・恥骨・坐骨)という複数の骨が組み合わさる形で成り立っています。日常的に体重を支えながら、歩行や立ち座りなどでも負担を受ける重要な部位です。
疲労骨折が起こる場合、特定の部位に集中的なダメージが加わることで複数の病型が生じることがあります。
部位や骨の形態によって痛みや治療方法が異なるので、それぞれの特徴を把握することが重要です。
| 骨の名称 | 主な位置 | 症状が出やすい動作 | 痛みの拡散範囲 |
|---|---|---|---|
| 腸骨 | 腰側 | ランニング、ジャンプ | 腰〜仙腸関節 |
| 恥骨 | 前側下腹部 | 歩行、階段の昇降 | 股関節内側、下腹部 |
| 坐骨 | 臀部奥側 | 座位維持、長距離走 | お尻〜太ももの裏側 |
腸骨に生じるケース
腸骨は腰に近い部分を構成する広い骨です。ランニングやジャンプなどで体幹を支え続ける動作を繰り返すと、腸骨の一部に細かなひびが入る場合があります。
腸骨付近の疲労骨折は腰痛と似た感覚になりやすく、病院を受診するタイミングを逃しやすいです。
- 腰部とお尻の間あたりに鈍痛を感じることが多い
- 日常的な立ち上がりで違和感が増す
- 走った後に痛みが強まることがある
- 仙腸関節付近まで痛みが広がるケースがある
適切な診断が遅れると炎症が広がり、回復に長時間を要することが多いです。
恥骨に生じるケース
恥骨は前側で左右の骨が結合している場所で、下腹部あたりに位置しています。歩行や姿勢保持で地味に負担をかけ続けると、微妙な痛みが続き疲労骨折に至るケースがあります。
初期ではお腹まわりや股関節内側のつっぱりを感じることが多いです。
- 下腹部の奥のほうが重苦しい
- 股関節を深く曲げると痛みがはっきりする
- 階段の上り下りで股関節付近が痛む
- ふとももの付け根がだるくなる
レントゲンでの判断が難しいこともあるため、MRIやCTを活用すると確実に発見しやすいです。
坐骨に生じるケース
坐骨は臀部の深い部分を形作る骨で、座るときに体重を支えます。長距離走などで下半身の後方にストレスが蓄積すると坐骨付近が疲労骨折を起こす場合があります。
お尻から太ももの裏まで痛みが拡散し、長時間座ることがつらくなる人もいます。
- お尻にある坐骨付近を押すと痛む
- 長く座るとじわじわ痛みが強くなる
- イスや床から立ち上がるときに響く痛み
- 太ももの裏側まで違和感が及ぶ
日常生活で座る場面が多い人は要注意です。
複数部位への波及
疲労骨折が骨盤の一部だけで起こっていると考えていても、実際には隣接する骨にまで影響が広がっているケースがあります。
腸骨や恥骨、坐骨が連続性をもって動くため、どこか1か所に生じた疲労骨折がさらに広範囲に及ぶことも考えられます。
痛みの場所に限定されず、体幹や股関節なども含めて総合的にチェックすることが大切です。
骨盤の疲労骨折の症状
初期症状は気付きにくい場合が多いです。日常的に運動習慣がある人や、スポーツ競技の練習量が多い人ほど、少しの違和感を「筋肉痛や疲労感かもしれない」と軽視してしまいがちです。
しかし、休んでも痛みが引かない、もしくは痛みの箇所が変化してきた場合は要注意です。放置して負荷をかけ続けると、症状が急激に悪化して日常動作に支障をきたすケースがあります。
初期段階の特徴
- 軽いストレッチでも骨盤付近が突っ張る
- 座ったり立ったりする際に違和感がある
- 休んでも完全に痛みが消えず、むしろ動き始めに痛む
- 手で押すと骨に沿って鈍痛が感じられる
疲労骨折の初期段階では、骨自体のヒビが細かいため、鋭い痛みよりも鈍い痛みや重だるい感覚が主になります。
運動直後は軽度の痛みですみますが、就寝前に痛みが増しているといった変化も起こりやすいです。
初期症状の一般的な訴え
| 訴えの内容 | 観察されるタイミング | 可能性が考えられる部位 |
|---|---|---|
| 鈍痛を感じる | 朝起きた時、運動の最中 | 恥骨付近 |
| 軽いひきつり感 | ランニング後、立ち上がり時 | 腸骨・坐骨周辺 |
| しこりのような圧痛感 | 長時間座った後など | 坐骨 |
中期段階の特徴
- 痛みでスポーツの練習量を減らさざるを得ない
- 少しの移動でも骨盤周辺に響くような痛み
- テーピングやサポーターで一時的に痛みが軽減するが根本的に解消しない
- お尻や股関節が腫れているように感じる場合もある
初期を過ぎても負担を続けると、骨の亀裂が進み始め、痛みが動作全体に波及するケースがあります。歩行だけで痛む、階段の昇降がきついなど、生活動作に支障が出始めると、疲労骨折が中期に入っている可能性が高いです。
痛みをかばって歩き方が変化すると、反対側の腰や膝に負担をかけやすくなります。
中期に想定される動作制限
- スムーズな歩行が難しい
- 腰を深く曲げると痛む
- 下半身のストレッチをしづらい
- 体をひねると骨盤周辺が痛む
後期段階の特徴
- 骨盤周辺が腫れたようになり、熱感がある
- わずかな振動やくしゃみでも痛みが走る
- ほぼ常時痛みを感じ、日常動作が困難
- 他の部位を無意識にかばうことで二次的な障害を起こす可能性
亀裂が大きくなり、骨折状態がはっきりしてくると、ちょっとした動きでも鋭い痛みを感じるようになります。痛みが断続的に強くなり、夜間でも寝返りで目が覚めるケースもあります。
長期にわたり運動を休止する必要が生じるため、競技者にとっては大きなリスクです。
慢性化と再発リスク
疲労骨折は骨の自然治癒を待てば徐々に回復に向かいますが、適切な治療やリハビリを行わず急いで競技復帰すると、再び骨折リスクが高まります。
慢性化すると痛みが再燃しやすく、習慣的に炎症が起こってしまう場合があります。
再発を防ぐためには医師と相談し、段階的なリハビリやトレーニング内容の見直しが必要です。
痛みが長引く場合の考えられる要因
| 要因 | 具体例 | 回避策 |
|---|---|---|
| トレーニング過多 | ハードな練習を連日続ける | 休息日を十分に設定 |
| 栄養不足 | カルシウムやビタミンDの不足 | 食事バランスやサプリメント検討 |
| リハビリ不十分 | 痛みが取れた直後に競技へ復帰 | 段階的に負荷を上げる |
| 骨の密度低下(骨粗しょう症) | 加齢やホルモンバランスの乱れ | 骨密度検査・治療の併用 |
骨盤の疲労骨折の原因
骨盤の疲労骨折は、正常な骨に加わる繰り返しの荷重や衝撃がきっかけとなります。一方似ている疾患として、異常な骨に正常なストレスがかかることで生じる脆弱性骨折というものがあり、区別は必ずしも容易ではありません。
一般人口における疲労骨折の発生率は1%程度ですが、ランナーでは20%に達します。身体のコンディションや生活習慣が加わると、骨へのダメージが増大して疲労骨折のリスクが高まります。
骨の自然修復力を超える繰り返しの荷重が骨にかかり、骨折が生じるのが特徴です。
日常的に身体を動かすと骨に微小骨折が生じますが、破骨細胞の骨吸収と骨芽細胞の骨形成によって修復されていきます。骨が弱かったり、微小骨折が多かったり、修復過程が遅れたりすると、微小骨折が蓄積して疲労骨折につながります。
運動量と負荷のかけ方
- 急に練習量を増やした
- 体幹が弱く、骨盤に頼りすぎる動き方をしている
- 硬い路面でのランニングを長時間行っている
- シューズが摩耗して衝撃吸収能力が低下している
骨盤は体を支える土台として常に負担がかかる部位です。マラソンなどの長距離走、跳躍を多用する競技、サッカーやバスケットボールなど接触プレーの多いスポーツでは、とくに骨盤周辺に大きな負荷が繰り返しかかります。
ほとんどの疲労骨折は骨盤と下肢に起きますが、これは大きな力学的負荷がかかるためです。下肢の長管骨では、微小骨折が蓄積しやすいです。
運動負荷と疲労骨折の関連性
| 原因となりやすい運動負荷 | 具体例 | 疲労骨折への影響 |
|---|---|---|
| 長時間のランニング | トレッドミル連続60分以上等 | 骨への反復衝撃の蓄積 |
| 瞬発系のジャンプ | バスケ・バレーボールの練習 | 骨盤周辺への負担増加 |
| 多方向の激しい動き | サッカーの切り返し動作など | 捻転ストレスの増大 |
適度な休息やコンディショニングが不足すると、骨組織の微小損傷が修復しきれずに蓄積します。
骨密度の低下
- ダイエットや過度な減量で栄養が偏る
- 加齢や閉経後に骨密度が急に下がる
- 遺伝的要因で骨がもともと脆い
- 睡眠不足によるホルモンバランスの乱れ
骨の強度が十分に保たれていれば、ある程度の衝撃に耐えられます。ただし、栄養状態の悪化や加齢、ホルモンバランスの乱れなどで骨密度が低下していると、わずかな衝撃でも骨に大きなダメージが残りやすくなります。
骨粗しょう症の診断を受けていなくても、若年層でも食生活の乱れや無理なダイエットで骨が弱っている場合があります。
筋力不足・フォームの問題
- 姿勢が悪く、骨盤が前傾・後傾に偏っている
- ウォーミングアップやクールダウンが適切でない
- コアトレーニングの不足により、骨盤が不安定
- 偏った動作(片脚に体重をかける習慣)が多い
骨盤周辺の筋肉は衝撃を吸収し、骨を保護する役割を担います。しかし筋力不足や不適切なフォームだと、骨盤に直接負担が集中します。特に体幹や股関節の安定性が低いと、運動時に骨盤への衝撃が増えやすいです。
骨盤周辺の筋肉バランス
| 筋肉名 | 役割 | 不足時の影響 |
|---|---|---|
| 中殿筋 | 骨盤の安定性を保つ | 骨盤の左右傾きが増大 |
| 大腿四頭筋 | 大腿骨と股関節を伸展させる | 走行時の衝撃が骨盤へ集中 |
| 腹横筋 | 体幹の内圧を高め、腰椎を保護する | 骨盤周辺への負荷増加 |
| ハムストリングス | 下肢の屈曲・伸展をサポート | 坐骨付近の疲労増大 |
適切なフォームを習得し、筋力をバランスよく高めることが疲労骨折予防に役立ちます。
運動以外の生活習慣
- 立ちっぱなしの業務が多い
- 不規則勤務による睡眠不足
- 喫煙や過度な飲酒で栄養吸収が低下
- ストレス過多でホルモン分泌が乱れる
疲労骨折はアスリートだけがなるものではなく、日常生活でも起こり得ます。立ち仕事や重い荷物を持ち歩く習慣、過労や睡眠不足など、身体の回復力が落ちる要因が重なると、骨盤の疲労骨折に至る可能性があります。
疲労回復を促す休息やバランスの良い栄養摂取を心がけることが大切です。
女性特有の要因
- 過度なダイエットで生理不順が続いている
- 女性アスリートトライアド(エネルギー不足・無月経・骨粗しょう症)の可能性
- 妊娠・出産を経て骨量が一時的に減少している
女性は男性に比べて骨密度が低めで、ホルモンバランスも変化しやすいため、疲労骨折を起こしやすいといわれています。特に生理不順や無月経の状態が続くとエストロゲン分泌が減少し、骨が弱りやすくなります。
女性は特にホルモンバランスと栄養管理に注意を払う必要があります。
放射線治療後の疲労骨折
放射線治療後のストレス骨折はまれではなく、しばしばストレス骨折と転移性疾患を鑑別する診断上の課題となっています。
放射線治療後の骨盤ストレス骨折はよく知られており、一般的な原発病変は子宮頸癌と直腸癌です。骨折リスクは男性よりも女性の方が有意に高く、一般に放射線量が高いほど高くなります。
骨盤への線量が40Gy未満では、放射線誘発性ストレス骨折はまれです。40Gyを超えると、線量が増加するにつれて骨折の頻度は増加していきます。
最近の総説によると、女性の放射線治療後の骨盤不全骨折の累積発生率は5年間で13%であり、その約3/4は最初の1年間に、大部分は最初の2年間に発生しています。
個々の研究での発生率には大きなばらつきがあり、ある研究では最大89%の骨折発生率を示しています。
放射線療法は直接的な細胞死を引き起こし、微小血管構造にも損傷を与えるため、赤色骨髄の枯渇と脂肪骨髄の増殖につながります。数週間続く骨髄水腫の初期段階の後、脂肪骨髄置換が起きます。
放射線治療は直接的な骨壊死につながりますが、通常は不完全で、反応性の炎症反応が起きます。このため、機械的強度や修復能が低下した骨梁や皮質の硬化性骨変化が頻繁に生じ、その結果、骨は応力骨折を起こしやすくなります。
骨盤の疲労骨折の検査・チェック方法
骨盤付近の痛みは、他の腰痛や筋損傷と症状が類似しており、自己判断だけでは疲労骨折かどうか判別が難しいです。
専門医は、画像診断や身体所見を総合的に評価して診断を行います。検査ではレントゲンやMRI、CTなどを組み合わせて正確な部位と程度を把握します。
問診と触診
- 日常での痛みの頻度・強さ
- 運動時や負荷がかかった時の痛みの変化
- 寝返りや立ち上がりでどの程度痛むか
- 骨盤周辺を手で押した時の圧痛箇所
医師が問診で痛みの部位や生活習慣、運動強度、既往歴などを確認します。
その後、患部の圧痛点を探し、腫れや熱感などの有無をチェックします。痛みの出る角度や動作を詳しく調べ、骨折の可能性を推測します。
医師がチェックする主なポイント
| チェック項目 | 具体的な方法 | 意味 |
|---|---|---|
| 圧痛点の確認 | 手指で骨盤周辺を軽く押す | 疲労骨折部位の特定 |
| 熱感・腫れの有無 | 触った際の温度差を感じる | 炎症や軟部組織の損傷確認 |
| 痛みが増す動作の再現 | 患者さんにゆっくり体を動かしてもらう | 骨折ラインに負荷がかかる角度 |
| 既往歴や生活習慣のヒアリング | スポーツ経験・日常の姿勢・栄養状態 | 発症リスク要因を探る |
画像検査(レントゲン・MRI・CT)
| 検査名 | 特徴 | 疲労骨折の診断精度 |
|---|---|---|
| レントゲン | 手軽でコストも比較的低い | 初期には発見が難しい |
| MRI | 軟部組織や骨膜の炎症もわかる | 初期段階の診断に有用 |
| CT | 骨の断面を詳細に描写 | 痛みの部位が特定しやすい |
疲労骨折は初期段階ではレントゲンに映りにくい特徴があります。
より詳細な断面画像を得られるMRIやCTを使うと、微小な骨折線や周辺組織の炎症も確認しやすいです。
レントゲン
骨の変形や骨折線をざっくり確認します。初診時のレントゲンの感度は50%未満であり、低いという報告があります。
MRI
骨内の水分量や骨膜の炎症、軟部組織の損傷状態を把握します。検査のゴールドスタンダードです。
CT
骨の断面を三次元的に可視化し、亀裂の広がりを確認します。
骨密度検査
| 検査方法 | 特徴 |
|---|---|
| DXAスキャン | 腰椎や大腿骨近位部の骨密度を測定 |
| 超音波 | かかとや手首など測定しやすい部位で骨の状態を簡易チェック |
骨盤の疲労骨折が疑われる際、骨そのものの強度を確かめる目的で骨密度検査を行うことがあります。
DXA(デキサ)スキャンや超音波検査などを活用し、患者さんの年齢や性別と比較して骨密度に問題がないかを評価します。骨密度が低い場合は栄養指導や骨密度改善の治療も視野に入れます。
血液検査
- 赤血球数・ヘモグロビン値のチェックで貧血を把握
- ビタミンDやカルシウム、リンなどのミネラルバランス
- CRP値や白血球数で炎症の有無を確認
疲労骨折の直接的な診断には使いにくいですが、血液検査で貧血や栄養不良がないか、炎症反応が高まっていないかを確認する場合もあります。
総合的に健康状態を把握し、疲労骨折の背景となる要因(栄養不足やホルモン異常)を見つける手がかりにします。
骨盤の疲労骨折の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
骨盤の疲労骨折は、基本的に安静とリハビリテーション、必要に応じた薬物療法で回復を目指します。
重症度や患者さんの生活スタイルによって治療期間は変わりますが、いずれにしても骨が修復するまでの期間を確保することが重要です。
場合によっては手術を検討することもありますが、疲労骨折の場合は保存療法が中心です。
保存療法(安静・固定)
- 痛みが強い間は通勤や家事も最小限に抑える
- コルセットやサポーターを装着して腰回りをサポート
- 無理のない範囲で軽度の運動を取り入れ、血流を保つ
- 骨折部位に過度な衝撃がかからないよう工夫
疲労骨折と診断された場合、骨の回復を妨げないよう安静にする期間が必要です。骨盤を完全に固定する装具は少ないですが、コルセットなどで腰周辺をサポートし、痛みを軽減しながら生活するケースが多いです。
ランニングなどの負荷が高い運動は避け、ウォーキングや水中歩行など軽い運動に切り替えて骨が回復するのを待ちます。
保存療法の主な内容
| 主な手段 | 具体策 | 目的 |
|---|---|---|
| 安静 | 運動を中止または制限 | 骨折部位の自然回復を促す |
| 装具の使用 | コルセット・サポーターなど | 骨盤周辺への負担軽減 |
| 痛みの管理 | 痛み止め、アイシング、温熱療法など | 痛みを抑えて回復をスムーズに |
| 適度な運動 | 水中リハビリ、軽い筋力トレーニング等 | 関節の硬直と筋力低下を防ぐ |
薬物療法
- NSAIDs(ロキソニン、イブプロフェンなど)で炎症・痛みを軽減
- 医師の指示に従い、使いすぎを避けながら適切に服用
- 骨代謝を促進する薬(活性型ビタミンD製剤など)を併用する場合もある
痛みが強い場合や炎症が長引く場合、医師は非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や鎮痛薬を処方するケースがあります。
薬物はあくまで痛みのコントロールが目的であり、骨の再生を直接うながすわけではありません。しかし痛みを緩和することでリハビリを進めやすくし、生活の質を保つ上でも有効です。
リハビリテーション
- 体幹トレーニングで骨盤の安定性を高める
- ラバーバンドを使ったヒップアブダクションやスクワット
- 痛みが出ない範囲でのジョギングやサイクリング
- 専門の理学療法士と相談しながらメニューを調整
骨折部位の痛みが和らいできたら、リハビリを始めます。最初は軽いストレッチや水中ウォーキング、下半身や体幹の筋力トレーニングなどで骨盤周辺をサポートする筋肉を鍛えます。
急に高負荷のトレーニングに戻ると再度骨にダメージを与えるため、段階的に運動強度を上げる取り組みが大切です。
リハビリで取り入れやすいメニュー
| メニュー名 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| ブリッジ | 仰向けで膝を立て、腰を持ち上げる | 大殿筋や体幹の強化 |
| クラムシェル | 横向きに寝て膝を曲げ、上側の膝を開く | 中殿筋の強化、骨盤の安定性向上 |
| プランク | うつ伏せで前腕とつま先で体を支える | 体幹全体の筋持久力アップ |
| 水中ウォーキング | プールで歩行 | 衝撃を低減しながら有酸素運動 |
治療期間の目安
疲労骨折は個人差が大きいですが、骨盤の場合は軽度でも回復に4~6週間ほどかかる方が多いです。
痛みが落ち着いて日常動作が無理なくできるようになるまでに、さらに数週間のリハビリを行うケースも珍しくありません。
重度の場合は3か月以上の安静や装具の使用が必要となるときもあります。医師の指示に従って段階的に負荷を上げることが、再発防止につながります。
薬の副作用や治療のデメリット
疲労骨折の痛みを和らげるために使用する薬には、当然ながら副作用が存在します。また長期的に安静が必要なことや、リハビリにも労力と時間がかかるため、治療にはいくつかのデメリットがあります。
治療のメリットとデメリットを理解したうえで、自分に合った方法を選ぶと納得感が高まります。
NSAIDsなど鎮痛薬の副作用
- 胃もたれや胸やけ
- 腹痛や下痢
- 腎機能への影響
- 発疹やかゆみなどのアレルギー症状
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は炎症や痛みを抑える効果が高い一方で、胃腸障害や腎機能への負担、稀にアレルギー反応を起こす場合があります。
長期使用すると胃が荒れやすくなるため、胃腸薬の併用を提案されるときがあります。
安静生活によるリスク
- 筋力低下による再発リスク増
- 体力や柔軟性の低下
- 代謝の低下による体重増加や生活習慣病リスク
骨折部位を休めるために安静を保つ必要があるものの、過度な安静が筋力低下を引き起こす場合があります。高齢者は筋力が落ちると、回復後も日常動作のレベルが下がるリスクがあります。
若年層でも安静期間が長引くと、再び運動を始めるときに筋力や持久力が低下していることに気付くケースがあります。
手術リスク(まれなケース)
- 麻酔のリスク
- 術後感染のリスク
- ボルトやプレートで固定した際の違和感
- 術後のリハビリに時間がかかる
骨盤の疲労骨折で手術を行うケースは多くありませんが、ヒビの範囲が大きい場合や、保存療法で治りきらない場合に手術を選択する例があります。
手術には麻酔や出血などのリスクが伴い、術後はリハビリ期間がさらに長くなる点も考慮が必要です。
手術を検討する場合の考慮ポイント
| ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 骨折部位・亀裂の大きさ | 広範囲に及ぶヒビや変形を伴う |
| 痛みの度合い | 保存療法でも日常生活が難しい |
| 他の治療法の効果 | 数か月の保存療法で回復が不十分 |
治療に要する時間と費用
保存療法やリハビリ中心でも、長期的な通院が続くと通院費や薬代、交通費などのコストがかかります。
アスリートの場合は、練習や試合に参加できない間のパフォーマンス低下や社会的影響もデメリットです。時間的・経済的負担を踏まえたうえで、早期回復を目指す計画を医師と立てることが大切です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
骨盤の疲労骨折に関する検査や治療は、一般的に健康保険の適用範囲内です。ただし、リハビリの内容や使用する装具の種類によっては一部自己負担が発生します。
自己負担の割合は通常3割ですが、高齢者や子ども、特定の疾患を持つ場合は負担割合が異なるケースもあります。
ここでは主な費用の目安を紹介しますが、実際の金額は医療機関や地域によって変わる可能性があります。
検査費用の目安
| 検査項目 | 自己負担目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| レントゲン | 1,000〜3,000円 | 骨折ラインの有無を確認 |
| MRI | 6,000〜10,000円 | 骨膜の炎症・軟部組織も可視 |
| CT | 5,000〜8,000円 | 骨の断面を立体的に確認 |
| 骨密度検査 | 1,500〜3,000円 | 骨の強度を評価 |
治療費用の目安
| 治療法 | 費用 |
|---|---|
| 診察料・処置料 | 1回あたり数百円~1,500円程度(保険適用後) |
| リハビリ・理学療法 | 1回あたり300円~1,000円程度(保険適用後) |
| コルセットなどの装具 | 2,000円~1万円程度(種類による) |
| 手術(まれなケース) | 術式によって10万円~数十万円程度 |
薬剤費用の目安
| 薬の種類 | 費用 |
|---|---|
| NSAIDsや鎮痛薬 | 1種類あたり1日数十円~数百円(保険適用後) |
| 胃腸薬や湿布 | セットで月数百円~数千円 |
| 骨代謝を促進する薬 | 数百円~数千円/月(保険適用後) |
高額療養費制度の活用
治療や検査、手術などで医療費の自己負担額が一定の基準を超える場合、高額療養費制度を活用すると負担が軽減されます。所得や年齢によって上限額が異なるので、加入中の健康保険組合や市区町村の窓口に確認する必要があります。
- 所得区分に応じた自己負担限度額の設定
- 入院や外来での医療費が高額になる場合でも、上限額以上は払わなくて済む
- 手続きをすれば後日差額が払い戻されるか、事前申請で立て替えを減らすことが可能
骨盤の疲労骨折は検査回数やリハビリ頻度が多くなるケースがあり、経済的負担も無視できません。保険制度を上手に利用しつつ、完治と再発予防を両立する治療計画を立てることが必要です。
以上
参考文献
LIONG, S. Y.; WHITEHOUSE, R. W. Lower extremity and pelvic stress fractures in athletes. The British journal of radiology, 2012, 85.1016: 1148-1156.
TINS, Bernhard J., et al. Stress fracture of the pelvis and lower limbs including atypical femoral fractures—a review. Insights into imaging, 2015, 6: 97-110.
NOAKES, Timothy D., et al. Pelvic stress fractures in long distance runners. The American Journal of Sports Medicine, 1985, 13.2: 120-123.
BEHRENS, Steve B., et al. Stress fractures of the pelvis and legs in athletes: a review. Sports health, 2013, 5.2: 165-174.
KELLY, Edward W., et al. Stress fractures of the pelvis in female navy recruits: an analysis of possible mechanisms of injury. Military medicine, 2000, 165.2: 142-146.
KIURU, Martti J.; PIHLAJAMAKI, Harri K.; AHOVUO, Juhani A. Fatigue stress injuries of the pelvic bones and proximal femur: evaluation with MR imaging. European radiology, 2003, 13: 605-611.
MAJOR, Nancy M.; HELMS, Clyde A. Pelvic stress injuries: the relationship between osteitis pubis (symphysis pubis stress injury) and sacroiliac abnormalities in athletes. Skeletal radiology, 1997, 26: 711-717.
OBERKIRCHER, Ludwig, et al. Osteoporotic pelvic fractures. Deutsches Ärzteblatt International, 2018, 115.5: 70.
SULLIVAN, Dennis, et al. Stress fractures in 51 runners. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 1984, 187: 188-192.