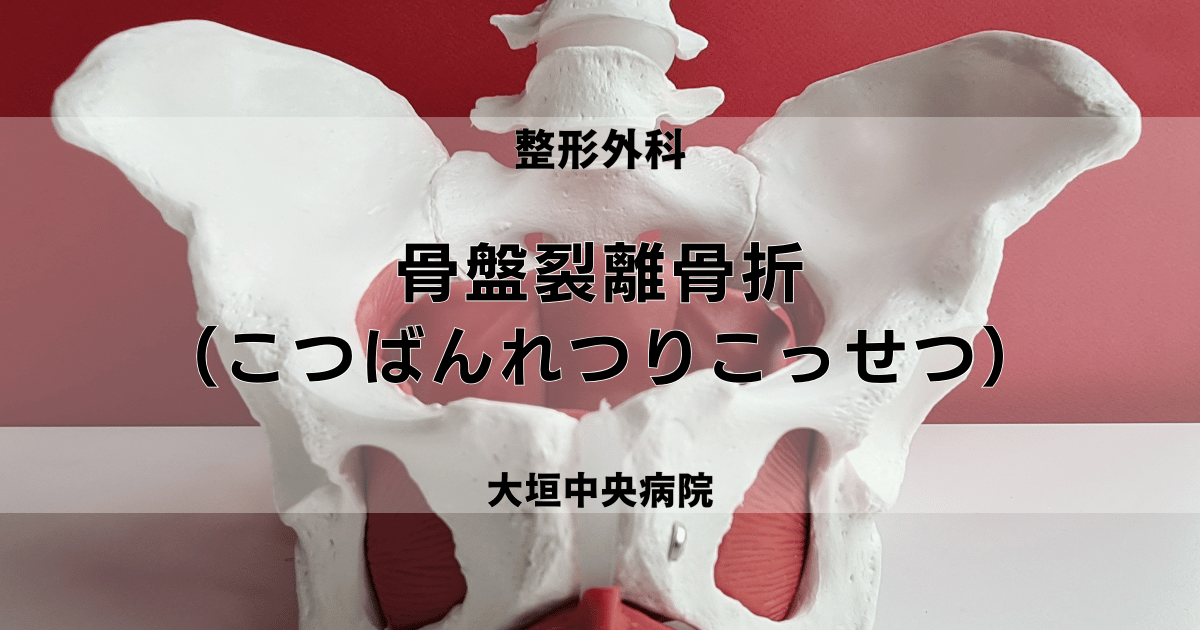骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)(Pelvic avulsion fracture, avulsion fracture of the pelvis)とは、股関節や骨盤まわりに強い牽引力が加わり、骨盤の一部が剥がれるように骨折を起こす状態です。
スポーツ活動で起こりやすく、特に成長期の男性アスリートに多く見られます。
放置すると慢性的な痛みや可動域の制限につながり、歩行や日常動作が困難となるおそれがあります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨盤裂離骨折の病型
骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)は発生部位によって大きく5つの病型に分類できます。
それぞれの病型で痛みの感じ方や可動域への影響が異なるため、医療機関を受診して診断を受けることが大切です。
| 病型 | 特徴 |
|---|---|
| 上前腸骨棘付近の骨折 | サッカーなど太ももの筋肉を酷使する競技で多い。股関節前側に痛みを感じる。 |
| 下前腸骨棘付近の骨折 | 大腿直筋(大腿四頭筋の一部)が強く引っ張ることが原因。階段の上り下りで痛みを感じやすい。 |
| 坐骨結節付近の骨折 | ハムストリング筋群の過度な牽引が誘因。ダッシュ・ジャンプ動作が多いスポーツで起こりやすい。 |
| 寛骨臼付近の骨折 | 股関節の可動域制限が顕著。コンタクトスポーツで急な外力が加わった場合などに発症しやすい。 |
| 成長期の骨端線付近の骨折 | 骨端線が未成熟なため剥がれやすい。中高生アスリートに多く、適切な休養が必要になる。 |
骨成熟度によって受傷部位の傾向に違いがみられ、骨盤の成長軟骨が閉鎖し始める年長の思春期ではASISや腸骨稜の裂離が多く、骨端が未熟な若年思春期ではAIISや坐骨結節の骨折が多いとの報告があります。
これは各骨端の骨化完了時期の差によるもので、例えば下前腸骨棘は比較的早期に骨化が完了する一方、上前腸骨棘や腸骨稜は遅くまで軟骨が残るためと考えられています。
骨盤前方に生じる骨折
骨盤の前方には上前腸骨棘(ASIS)や下前腸骨棘(AIIS)と呼ばれる部位があり、大腿部の筋肉(縫工筋や大腿筋膜張筋、大腿直筋)が強く牽引したときに、骨盤から骨が剥がれるように折れやすくなります。
特にサッカーや陸上競技など、太ももを強く使うスポーツでの発症例が多いです。
骨盤前方に生じる骨折は頻度が高く、全体の6~7割を占めます。
骨盤後方に生じる骨折
骨盤の後方に付着するハムストリング筋群が強く引っ張られ、坐骨結節付近で裂離骨折が起こるケースがあります。
ダッシュやジャンプを繰り返すバスケットボールやバレーボールなどで経験する人が多く、全体の10~15%を占めます。
骨盤の寛骨臼付近に生じる骨折
寛骨臼は股関節を構成するくぼみで、この付近の骨が剥がれるように折れると、股関節の可動域制限が顕著になりやすいです。
動きの多い格闘技や柔道などの接触プレーでも起こる可能性があります。
骨端線付近に生じる骨折(成長期特有の病型)
成長期は骨の端(骨端線)が未成熟なため、筋肉や腱の牽引力が骨端線部分に過剰な負荷として加わり、裂離を起こす場合があります。
部活動で激しい練習を続ける中高生アスリートに比較的多くみられます。
骨盤裂離骨折の症状
骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)の症状は、骨折部位や程度によりさまざまです。
軽度であれば少し痛みを感じる程度ですが、重度の場合は強い痛みや歩行障害などが生じます。
急性期の痛み
典型的には急に「ビリッ」とした鋭い痛みを骨盤周囲に感じ、特に足を上げる動作や走る動作が困難になるケースが多いです。
運動中に発症すると、その場でプレーを続行できなくなるほどの激痛を伴う場合もあります。
痛みは動作の継続で増悪し、安静にすると軽減するのが一般的です。
安静時の鈍痛・違和感
急性期の痛みが落ち着いても、椅子に座るときやベッドで横になっているときなど、安静時にも鈍い痛みや違和感を覚えるケースがあります。
無理に動かしていないのに、じわじわとした痛みが続くときは注意が必要です。
歩行や階段昇降での痛み
日常生活における大きな支障として、歩行や階段昇降時の痛みがあります。
脚を上げる動作、足を前方に振り出す動作で違和感や痛みが強くなるケースが多く、長時間の立ち仕事や歩行も困難になるおそれがあります。
周辺筋肉の緊張と可動域の低下
骨盤裂離骨折による痛みをかばい続けると、周辺の筋肉に過度な負担がかかり、筋緊張や筋疲労を起こしやすくなります。
結果として股関節や腰の可動域が低下し、普段の動作がスムーズにできなくなってしまいます。
症状を理解して対策を立てる
骨盤裂離骨折の症状は、放置すると慢性化した痛みや歩行障害につながる危険性があります。
痛みや違和感を覚えたら、できるだけ負担をかけないように心がけ、早期に医療機関を受診しましょう。
- 急に走れなくなったり、激痛が走ったりした場合は競技を中断して医療機関を受診する
- 痛みが軽減してきても、再発を予防するために十分な休息期間を設ける
- 歩行や動作に支障をきたす場合は、生活環境を工夫して痛みを軽減させる
- 軽症例では痛みを感じつつも競技を続行できる場合もある
骨盤裂離骨折の原因
骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)は多くの場合、骨盤付近の筋や腱に瞬間的に強い牽引力が働くことで発症します。
- ダッシュや急停止を繰り返すスポーツ
- 成長期特有の骨端線の未成熟
- 筋力のアンバランス(特に股関節周辺)
- 柔軟性の不足による衝撃吸収力の低下
- 重い物を持つなどの繰り返し動作による慢性的な負担
特に成長期の骨端部(骨の付着部の成長板)は周囲の骨より軟らかく弱いため、筋力が向上する時期に強い負荷がかかると、筋腱部ではなく骨端が裂けて骨折が生じます。
まれなケースとして、直接の外傷(例:転倒や衝突による骨盤への打撃)による骨端の剥離や、長期間の反復ストレスが蓄積して起こる疲労骨折的な裂離(慢性的な骨端炎の延長)もあります。
骨盤裂離骨折を誘発しやすいスポーツ
| スポーツ種目 | 発生要因 |
|---|---|
| サッカー | スプリントやキック動作で大腿部の筋肉を強く使う |
| 陸上競技(短距離走など) | ダッシュ・加速時に股関節を大きく動かし、筋・腱の牽引力が骨盤に集中的にかかる |
| バスケットボール | ジャンプや急停止が多く、ハムストリング筋群や大腿四頭筋への負荷が大きい |
| バレーボール | スパイクやブロックのジャンプ動作で骨盤周辺に瞬間的な強い力が加わる |
| 柔道や格闘技 | 相手との接触や投げ技など、外力が不意に加わる動作が多い |
方向転換や瞬発的な動きを要するスポーツでよく起こり、サッカーでのキック動作、短距離走でのダッシュ開始、バスケットボールやバレーボールでのジャンプ動作、体操競技などが典型的なシチュエーションです。
骨盤裂離骨折の検査・チェック方法
骨盤裂離骨折骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)は、骨折面が小さいうえに筋肉や腱に隠れた部位で起こるケースが多いです。
レントゲン写真では判断しにくい場合もあり、さまざまな方法を用いて診断を行います。
| 検査方法 | 内容 |
|---|---|
| 問診・視診・触診 | 痛みの部位や発症状況を確認。初期スクリーニングに重要。 |
| 単純レントゲン | 骨折線や骨片を確認する。ただし骨片が小さいと見落とす可能性がある。 |
| CT検査 | 骨構造の詳細を3次元的に把握。レントゲンで不明瞭な場合に有用。 |
| MRI検査 | 軟部組織の損傷を含め、より詳しい情報を得られる。骨髄浮腫の有無なども確認可能。 |
| 超音波検査 | 筋・腱の状態を動的に観察。骨折の確定診断よりも補助的な評価として利用。 |
問診・視診・触診
痛みの部位や発症状況、スポーツ経験や仕事について聞き取り、視診や触診を行います。
受傷の状況(どのような動作で痛みが走ったか)や音の有無は、診断の重要な手がかりです。
痛む部位を押して骨折かどうかを判断する場合もありますが、触診だけでは確定診断が難しいケースも少なくありません。
患部に対応する筋群のストレッチや収縮で痛みが誘発されれば、該当骨端の裂離骨折を疑います。
単純レントゲン撮影
骨の状態を確認するうえで最初に行う検査です。
ただし、裂離した骨片が小さい場合や、骨盤の構造上の重なりで映りにくい場合もあり、レントゲンだけでは見落としが生じる可能性があります。
CT検査やMRI検査
レントゲン撮影で不明瞭な場合や、より詳しく状態を知る必要がある場合はCT検査やMRI検査を行います。
CT検査は骨の構造を詳細に捉えやすく、MRI検査は筋肉・腱・靭帯などの軟部組織を含めて確認しやすいのが特徴です。
超音波検査
超音波検査は、筋・腱・靭帯の様子をリアルタイムで可視化できる利点があります。
骨折そのものの診断としてはやや限界があるものの、損傷した筋・腱の状態把握や骨片との位置関係を把握するのに役立ちます。
骨盤裂離骨折の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
骨盤裂離骨折の治療には大きく分けて保存療法と手術療法がありますが、どの症例で手術適応とするべきかについては議論があり、一律のガイドラインは存在しません。
個々の症例に応じた治療により、痛みを軽減し、長期的な後遺症が残るリスクを減らせます。
保存療法(ギプスやサポーター)
骨がわずかにずれただけの場合や、骨片が小さい場合は保存療法が選ばれるケースが多く、ギプスやサポーターを使用して、患部を安静に保ちながら骨の自然治癒を促します。
治療は安静、疼痛管理、リハビリが中心です。
- 過度な負荷をかけないように安静を保つ
- 痛みが落ち着くまで歩行を制限する
- 松葉杖の使用などで負担を軽減する
ギプスではなくサポーターを使う場合もあり、医師が必要に応じて期間や装着方法を決めます。
スポーツ復帰はで2.5~4か月程度を要するのが一般的です。
手術療法
骨盤裂離骨折が重度の場合、手術によって骨片を元の位置に固定します。金属プレートやスクリューなどを使って正しい位置で安定させ、早期の回復と再発予防を図ります。
- 骨片が大きくずれている(15~20mm以上)
- 関節近くで骨折が起こり可動域が大きく制限されている
- 骨片が大きく偽関節リスクが高い
- ハイレベルで競技をやっている
骨盤裂離骨折に用いられる主な手術方法
| 手術方法 | 概要 |
|---|---|
| 金属スクリュー固定 | 剥がれた骨片を元の位置に戻し、スクリューで固定する方法。 |
| 金属プレート固定 | 広範囲に骨片がずれている場合、プレートで一括して固定する方法。 |
| ワイヤー固定 | 小さい骨片はワイヤーで固定する場合がある。 |
手術後は患部を安静に保ち、医師の判断に応じて少しずつ可動域訓練を行います。
治療薬(痛み止め・消炎鎮痛薬など)
骨折や炎症による痛みを軽減するために、消炎鎮痛薬(NSAIDs)が処方されます。
強い痛みに対して麻薬系鎮痛薬などを短期間使用したり、炎症を抑える目的でステロイド薬を局所注射したりするケースもまれにあります。
リハビリテーション
痛みが落ち着いたらリハビリテーションを開始し、周辺筋力を整えながら可動域を回復させていきます。
| リハビリ段階 | 内容 |
|---|---|
| 急性期(痛みが強い時期) | 安静を中心に、筋肉の軽いストレッチやアイソメトリック筋トレを行う。痛みを引き起こさない範囲で実施する。 |
| 亜急性期(痛みが落ち着き始めた時期) | ウォーキングや軽い荷重運動を取り入れ、徐々に可動域を広げていく。 |
| 回復期 | ジョギングや自転車こぎなど、骨盤周辺に適度な負荷をかける運動を導入し、本格的に筋力強化を図る。 |
| 復帰期 | スポーツ動作や生活動作を実践的に行い、再発予防のためのフォーム指導などを受ける。 |
リハビリでは、理学療法士や医師の指導のもとで段階的に運動を行い、無理な負荷を避けながら回復を促します。
治療期間の目安
骨盤裂離骨折の治療期間は、骨折の程度や治療方法、患者の年齢・回復力によって大きく変動します。
- 軽度の場合(保存療法中心):約2~3か月
- 中等度の場合(保存療法+リハビリ):約3~4か月
- 手術を伴う重度の場合:術後約2~6か月程度でスポーツ復帰を検討
長引かせないためには、痛みが軽減しても焦らずにリハビリを継続し、再発を防ぐことが大切です。
薬の副作用や治療のデメリット
骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)の治療で用いられる薬には痛みや炎症を抑える効果がある一方で、一定の副作用が起こる可能性があります。
消炎鎮痛薬(NSAIDs)の副作用
- 胃もたれや腹痛
- 吐き気
- 下痢や便秘
- まれにアレルギー反応(発疹など)
痛み止めとしてよく使われるNSAIDsは、長期的に服用すると胃や腸の粘膜を刺激し、胃潰瘍などのリスクを高めるため、用法や用量に注意が必要です。
麻薬系鎮痛薬の副作用
強い痛みがある場合に処方される麻薬系鎮痛薬は、傾眠やふらつきなどの副作用が起こる場合があります。
作用が強力な分、医師の管理のもとで短期間のみ使用する必要があります。
保存療法のデメリット
- 転位が大きい例では、保存療法で半数近くに偽関節が生じた報告あり
- 骨癒合の過程で異常な骨増生が起こる可能性があり、インピンジメント症状(※)を呈する場合がある
- 治癒に時間がかかり、筋力低下や柔軟性低下が生じやすい
※インピンジメント症状:鼠径部や股関節の疼痛、内旋が制限される股関節の可動域制限など
手術治療のデメリット
- 入院や手術に伴う身体的・精神的負担
- 合併症(感染症、血栓など)のリスク
- 神経障害
- 金属プレートやスクリューの抜去手術が必要となる場合がある
手術によって骨折部位を確実に固定しやすい反面、体への侵襲や費用面の負担が大きくなる可能性があります。
リハビリテーションのデメリット
- 運動を再開するまでに時間がかかる
- 痛みを感じながらの訓練が必要になる場合がある
- 精神的ストレス(思うように動けない状態が続く)
リハビリは長期戦になるケースが多く、痛みや思うようにいかない状況からくるストレスに注意が必要です。
焦って無理をすると、再発や別の部位の障害を引き起こすリスクが高まります。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
骨盤裂離骨折(こつばんれつりこっせつ)の検査や治療は、一般的に健康保険の適用対象となります。
ただし、治療内容や医療機関によって費用が変動する場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
治療費の目安
| 項目 | 費用目安(3割負担) |
|---|---|
| 初診料・再診料 | 約500~1,000円 |
| レントゲン検査 | 1,000~2,000円 |
| MRI検査 | 約5,000~8,000円(検査内容で変動) |
| 手術費用(1週間入院) | 約5万~10万円 |
| リハビリ(理学療法) | 1回あたり約500~1,500円 |
| ギプス・サポーターなどの材料 | 2,000~5,000円(種類による) |
上記はあくまで目安であり、病院の規模や地域、個室利用などの状況によって変わります。
リハビリの頻度や期間によっても通院費用は増減するため、主治医や医療機関に詳細を確認することが大切です。
また、手術により治療費が高額となった場合、高額療養費制度の活用により、一定額以上の自己負担を抑えられる可能性があります。
保険外診療(自由診療)は通常行われません。
以上
参考文献
PORR, Jason; LUCACIU, Calin; BIRKETT, Sarah. Avulsion fractures of the pelvis–a qualitative systematic review of the literature. The Journal of the Canadian Chiropractic Association, 2011, 55.4: 247.
SCHUETT, Dustin J.; BOMAR, James D.; PENNOCK, Andrew T. Pelvic apophyseal avulsion fractures: a retrospective review of 228 cases. Journal of Pediatric Orthopaedics, 2015, 35.6: 617-623.
FILIPPO, Calderazzi, et al. Apophyseal avulsion fractures of the pelvis. A review. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 2018, 89.4: 470.
MCKINNEY, Bart I.; NELSON, Cory; CARRION, Wesley. Apophyseal avulsion fractures of the hip and pelvis. Orthopedics, 2009, 32.1: 42-48.
ROSSI, F.; DRAGONI, Stefano. Acute avulsion fractures of the pelvis in adolescent competitive athletes: prevalence, location and sports distribution of 203 cases collected. Skeletal radiology, 2001, 30: 127-131.
SUNDAR, Manthravadi; CARTY, Helen. Avulsion fractures of the pelvis in children: a report of 32 fractures and their outcome. Skeletal radiology, 1994, 23: 85-90.
METZMAKER, Jeffrey N.; PAPPAS, Arthur M. Avulsion fractures of the pelvis. The American journal of sports medicine, 1985, 13.5: 349-358.
SANDERS, Timothy G.; ZLATKIN, Michael B. Avulsion injuries of the pelvis. In: Seminars in musculoskeletal radiology. © Thieme Medical Publishers, 2008. p. 042-053.
FERNBACH, S. K.; WILKINSON, R. H. Avulsion injuries of the pelvis and proximal femur. American Journal of Roentgenology, 1981, 137.3: 581-584.
EBERBACH, H., et al. Operative versus conservative treatment of apophyseal avulsion fractures of the pelvis in the adolescents: a systematical review with meta-analysis of clinical outcome and return to sports. BMC musculoskeletal disorders, 2017, 18: 1-8.