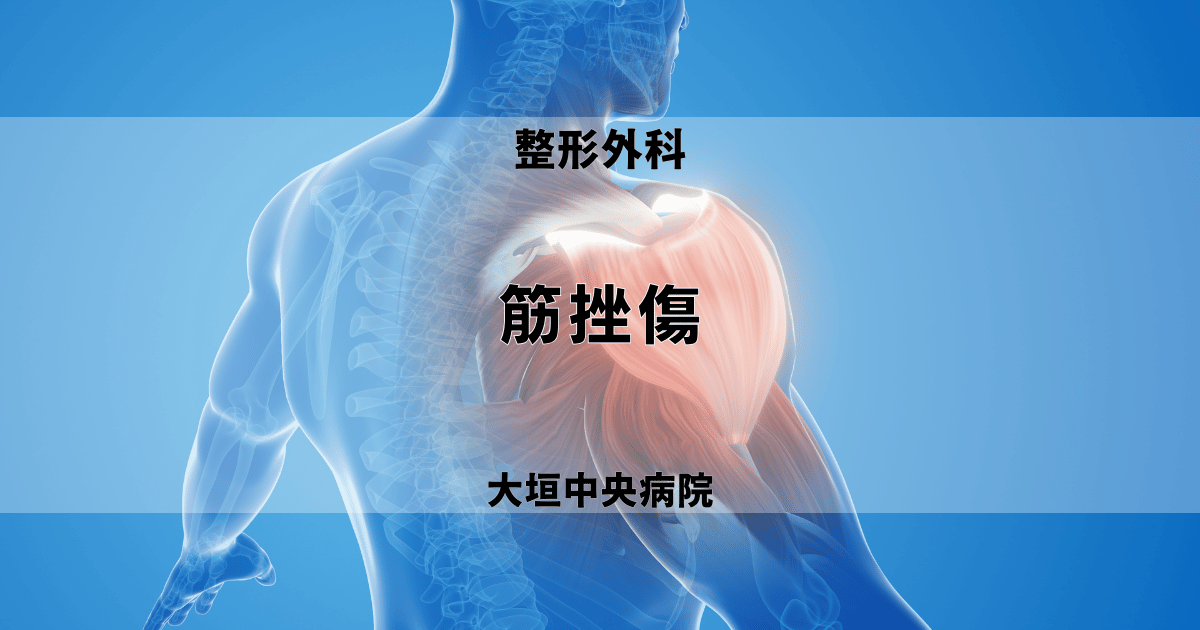筋挫傷(muscle contusion, muscle bruise)とは、外力や衝撃などによって筋肉が傷つき、炎症や痛みが起こる状態です。打撲やスポーツ中の衝突などが原因となり、急に受けた強い衝撃で生じるケースが多いです。
痛みだけでなく、内出血による腫れや皮膚の変色が生じる場合もありますが、皮膚は破れず、筋繊維が挫滅される点が特徴的で早めの受診と適切な治療で回復を目指せます。
慢性化を防ぐためにも、初期対応やリハビリテーションの流れを知っておくことが大切です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
筋挫傷の病型
筋挫傷と一口にいっても、筋肉の損傷度合いや発生部位などによりさまざまな病型に分かれます。受傷の程度や症状の出方によって、治療や経過も異なります。
筋繊維の損傷度による分類
筋挫傷は、筋繊維のダメージがどの程度かで分類することが多いです。
軽度の打撲であっても筋肉内部では微細な損傷が起こり、痛みや腫れを起こすケースがあります。重度の場合は、筋組織が大きく傷つくだけでなく、動かしづらさや強い痛みが長引く人もいます。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 軽度 | 筋肉の細かなダメージが中心で、内出血や腫れは比較的小さい |
| 中等度 | 筋肉の一部が断裂したり、大きめの内出血が生じたりする |
| 重度 | 筋肉全体的に強いダメージが及ぶケースや筋腱の付着部にまで達するような損傷 |
大腿四頭筋の筋挫傷の分類
大腿四頭筋の筋挫傷ではJacksonとFeaginの分類が使用され、屈曲可動域で評価します。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 軽度 | 膝関節を90度以上曲げることが可能で歩行も支障ない(痛みはあるが跛行しない) |
| 中等度 | 膝の曲がりが45〜90度に制限され顕著な腫れと跛行を伴う |
| 重度 | 膝が45度以下しか曲がらず筋肉内に硬い血腫を触知することもある |
筋挫傷の症状
筋挫傷による症状は、受傷の程度や発生からの時間によって変化します。痛みや腫れ、皮下出血などの見た目の症状だけでなく、機能面でも動きづらさが生じる場合があります。
急性期の特徴的な症状
- 強い圧痛
- 皮膚や筋肉の腫れ、変色(青紫色など)
- 動かしたときの鋭い痛み
- 筋力低下による動作の制限
- 出血が広がるため、受傷後24~48時間かけて症状が悪化することもある
受傷直後から数日間にかけては、炎症反応が強く、患部の痛みや腫れが中心となります。
この時期にきちんと対処しないと、その後の回復が遅れたり、合併症を引き起こしたりする可能性があります。
急性期の受傷後ケアの目安
| 時期 | ケア |
|---|---|
| 初期(1~3日程度) | アイシング・圧迫を中心に患部を安静に |
| 中期(4~7日程度) | 腫れや内出血が落ち着いてきたら患部の軽いストレッチを追加 |
後期(1~2週間) | 痛みが軽減してきたら筋力回復を意識したトレーニングを開始 |
亜急性期の症状の変化
- 深層部の痛みや突っ張り感
- 動作時に違和感や鈍痛を感じる
- 回復に向けたリハビリ開始時に起こる軽度の痛み
受傷後数日から1~2週間くらいにかけては、痛みや腫れがやや落ち着いてきます。
しかし、筋肉内部には修復途中の組織や血腫が存在する例も多く、無理な動作や強い負荷をかけると再び痛みがぶり返すときがあります。
この時期は適度にリハビリを行い、再損傷を避けるように注意が必要です。
慢性化した場合の症状
- 繰り返し起こる痛みや腫れ
- 筋肉全体の硬さと可動域の制限
- 周辺組織にかかる負担の増大
- 骨化性筋炎への進展
適切に治療やリハビリを進めないまま復帰すると、痛みが長期間続いたり、筋肉の柔軟性が低下したままになったりする場合があります。慢性化すると再発のリスクも高まるため、注意が必要です。
日常生活における症状の出方
- 通勤・通学時の長時間歩行で疲れやすい
- 階段での昇降時に膝や太ももに痛みを感じる
- 家事などで重い物を持つときに支障が生じる
強い症状があるときはスポーツはもちろん、普段の動作にも支障をきたします。歩行や階段の昇降などでも痛みを感じる場合は、患部に負担をかけすぎないよう工夫しましょう。
症状が悪化すると生活の質が落ちるため、早めのケアが重要です。
- 適切な休息を取る
- 温熱療法やマッサージで筋肉の柔軟性を保つ
- 痛みが強い時は医師に相談して鎮痛剤を使う
筋挫傷の原因
筋挫傷は、主に直接的な鈍的外力が筋肉に加わって起こる損傷です。どんな場面や要因が筋挫傷のきっかけになりやすいかを把握しておくと、予防につなげやすくなります。
思いもよらない場面で起こるケースもあるため、普段から注意が必要です。
スポーツでのコンタクトや衝突
- 相手選手とのタックルや衝突
- ボールの強打が筋肉に直接当たる
- 床やコートへの激しい転倒
- プロテクターの未装着
- 衝突時に筋肉に力が入っていない状態
サッカーやラグビーなど、コンタクトプレーが多いスポーツでは筋挫傷が起こりやすいです。相手選手との接触だけでなく、ボールやゴールポストなどの物体にぶつかってしまう場合もあります。
バスケットボールやバレーボールなどでも、激しく転倒すれば筋挫傷につながります。
日常生活での転倒や事故
- 階段や段差で足を踏み外して強打する
- 交通事故でシートベルトやエアバッグの衝撃を受ける
- 家庭内での事故(風呂場やトイレなどの転倒)
必ずしもスポーツをしている人だけが筋挫傷になるわけではありません。段差につまずいて転倒したり、階段を踏み外して強く体を打ったりするのも大きな原因です。
高齢者や小さな子どもは転びやすいため、注意が必要です。
日常生活で転びやすいシーン
| 場面 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 室内 | 玄関や階段でのつまずき | 段差を見やすくする工夫が必要 |
| 屋外 | 雨の日や雪の日のスリップ | 滑り止め付きの靴を利用 |
| 移動手段 | 自転車・バイク・車での事故 | 安全運転と装備の確認が大切 |
筋肉疲労や柔軟性の低下が誘因になる場合
- ウォーミングアップ不足
- クールダウンを省略した後の筋硬化
- 長時間のデスクワークで筋肉がこわばっている
筋肉が疲労や硬さを抱えていると、衝撃を受けた際のダメージが大きくなります。
筋挫傷のリスクを下げるためには、運動前の準備運動や定期的なマッサージで筋肉をほぐしておくことが大切です。
予防するためのポイント
- スポーツ前後の入念なストレッチ
- 防具やサポーターの着用
- 筋力バランスを整えるトレーニング
- 転倒を防ぐ安全な環境作り
筋挫傷は予防しきれない部分もありますが、ストレッチや防具の着用、トレーニングなどに気をつけるとリスクを軽減できます。適度なケアと心がけで、筋挫傷の発生率を下げられます。
筋挫傷の検査・チェック方法
筋挫傷の程度を正しく把握するには、医療機関での検査が重要です。受傷直後は痛みが強くても、軽度の損傷で済んでいる例もあれば、その逆もあります。
正しい検査を受けて損傷の状況を把握すると適切な治療計画を立てられます。
医師の視診・触診
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 視診 | 皮膚の変色、腫れ、傷跡などを目視でチェック |
| 触診 | 押したときの圧痛点や筋肉の硬さを確認 |
| 動作確認 | 筋力テストや関節の可動域テスト |
| SLRテスト | 膝を伸ばしたまま大腿を挙上する |
まず医師が患部を直接見たり、触ったりして確認します。痛みの場所や範囲、腫れや変色などの有無、筋肉の緊張度合いなどを総合的に判断して、筋挫傷の程度を推察します。
画像検査の活用
| 検査方法 | 特徴 | 確認できる情報 |
|---|---|---|
| X線検査 | 骨の状態を主に評価 | 骨折の有無や骨膜損傷の可能性を確認 |
| MRI | 筋肉や軟部組織を詳細に評価 | 筋繊維の断裂、血腫の位置・大きさ |
| 超音波検査 | リアルタイムで筋肉の状態を映像化 | 筋肉内部の出血や腱付着部の損傷の確認 |
医師の判断で必要とされる場合、X線検査やMRI、超音波検査などを行います。
骨折や重度の筋断裂などが疑われるときは、画像検査で状態を確認しないと正確な治療方針を立てにくいです。
自宅での簡易チェック
- 触ると強い痛みがあり、内出血が確認できる
- 動かすと痛みが増す、または関節がうまく曲げ伸ばしできない
- 痛みが数日経っても軽減しない、または悪化する
痛みのレベルや腫れ具合は人それぞれ異なりますが、痛みや内出血などのチェックをすると早期の受診判断ができます。
ただし、自宅での自己判断だけで無理をするより、早めに医療機関に相談したほうが安心です。
検査を受けるタイミングと注意点
- 受傷当日~翌日にかけての早い段階で受診
- 痛みが落ち着いても、内出血や腫れが続く場合は再度受診
- 激痛や変形、発熱を伴うときは救急を考慮
受傷直後に痛みがある場合は、なるべく早めに医師に診てもらうことが大切です。痛みを我慢して日常やスポーツを続けると、症状が悪化しやすくなります。
筋挫傷の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
筋挫傷の治療は、損傷の程度や患部の状態に合わせて行います。治療期間も部位や重症度によって変動し、必要な薬やリハビリテーションの内容も異なります。
急性期のRICE処置(受傷直後~48時間)
| 処置 | 方法 |
|---|---|
| Rest(安静) | 無理な動きを控えて患部を休ませる |
| Ice(冷却) | アイシングで炎症や内出血の進行を抑制 |
| Compression(圧迫) | 弾性包帯などで適度に圧迫し、腫れを軽減 |
| Elevation(挙上) | 患部を心臓より高い位置に保ち、血液やリンパの循環を良くする |
受傷直後から数日間の急性期には、RICE処置(Rest・Ice・Compression・Elevation)が基本となります。早めに炎症を抑え、出血や腫れを少なくすることが回復を早めるうえで大切です。
急性期の処置・費用例
| 処置内容 | 使用物品 | 費用目安 |
|---|---|---|
| アイシング | 氷嚢や保冷剤 | 数百円程度 |
| 圧迫バンテージ | 弾性包帯 | 1,000円前後 |
| 松葉杖(必要時) | レンタルまたは購入 | レンタルで1日数百円〜購入で3,000~5,000円程度 |
リハビリテーションの流れ
リハビリテーション(理学療法)は筋挫傷治療の中心的役割を担います。リハビリの進行は痛みの程度と筋の治癒段階に応じて段階的に進められます。
基本原則は「痛みの出ない範囲で徐々に運動を再開し、筋力と可動域を回復させる」です。
可動域回復訓練
腫れと痛みが落ち着いたら、関節の曲げ伸ばしや筋のストレッチを開始します。
最初は他動的(治療者の補助)あるいは自動介助的にゆっくりと筋を伸ばす運動から始め、徐々に自動運動(自分の力でのストレッチ)へ移行します。
これを痛みが強まらない範囲で1日に数回、短時間ずつ行い、関節拘縮を防ぎ、瘢痕による筋短縮を最小限に抑えます。
等尺性筋収縮訓練
まだ関節可動域が制限されている早期でも、筋力維持のために関節を動かさない筋トレ(等尺性収縮)が推奨されます。例えば四頭筋挫傷では膝を伸ばしたまま腿に力を入れる運動を、痛みのない強度で頻回に行います。
これにより廃用性筋萎縮を防ぎ、神経筋の再教育にもつながります。痛みがなければ徐々に収縮力を高めていきます。
等張性筋力強化訓練
筋の損傷部位がある程度治癒し、痛みなく関節可動域が確保できるようになったら、関節の動きを伴う筋力訓練(等張性運動)に移行します。軽い負荷から始めて徐々に重量や回数を増やします。
四頭筋なら座位での膝伸展運動、ハムストリングなら膝屈曲運動などを、ゴムバンドやマシンを使って行います。
筋力が回復してきたらプライオメトリクストレーニング(瞬発力強化の跳躍系トレーニング)も取り入れ、筋の機能的回復を図ります。
固有感覚・バランス訓練
筋挫傷後は痛みにより一時的に筋出力や神経系の制御が低下しているため、平衡感覚や協調運動の練習も重要です。
バランスボードに乗る、片脚立ちでボール投げをする等の練習で、患部の神経筋協調性を高め再受傷を防ぎます。
スポーツ動作復帰訓練
筋力・柔軟性・バランスが十分に戻ったら、最後に競技特有の動作を段階的に再習得します。ランニングやジャンプ、急な方向転換など競技で必要な動作を洗い出し、練習します。
最初は50%程度のスピードで行い、問題なければ徐々に80%、100%と強度を上げていきます。
痛みが再発しないか慎重に確認しながら進め、全力動作でも痛みや不安感が全くない状態が確認できれば、競技復帰の許可となります。
各段階への移行時期は受傷の重症度によって異なりますが、一般的な目安として、軽症例は受傷数日で上記ステップ2〜3へ移行し、1〜2週間でステップ5に到達します。
中等度例では1週間前後でステップ3〜4、2〜3週間でステップ5となるケースが多いです。
重症例ではリハビリ期間が長引きますが、痛みや腫脹が完全になくなるまではスポーツ復帰しないのが大原則です。痛みを我慢して復帰すると再出血・再損傷し、かえって治療期間が延びるリスクがあります。
実際、治癒前に競技に復帰したり不十分な治療のまま放置すると、骨化性筋炎など合併症を招き完治が遅れる恐れがあります。
そのため、「痛みなく通常の力を発揮できる」という条件を満たしてから復帰することが大切です。復帰直後もしばらくは患部を保護し、テーピングやパッドで再発予防を図ります。
治療薬の種類
| 薬の種類 | 効果 | 形態 |
|---|---|---|
| NSAIDs | 痛みや炎症を抑える | 内服薬・貼付薬 |
| 筋弛緩薬 | 筋肉のこわばりを軽減 | 内服薬 |
| 局所冷却スプレー | 患部を冷却し、鎮痛効果を得る | スプレー |
筋挫傷の痛みや炎症を抑えるために、消炎鎮痛薬や筋弛緩薬などが使用される場合があります。内服薬だけでなく、塗り薬や貼り薬などの外用薬も補助的に使われます。
治療期間の目安
| 重症度 | 期間 |
|---|---|
| 軽度 | 1~2週間ほど |
| 中度 | 2~4週間程度 |
| 重度 | 1か月以上かかる場合もある |
軽度の筋挫傷では1~2週間程度の安静やリハビリで改善を実感する人が多いですが、中程度以上の損傷では1か月以上かかるケースも珍しくありません。完全復帰には個人差があるため、医師や理学療法士の指示を参考に進めてください。
回復を焦って無理に運動を再開すると、再挫傷や慢性化のリスクが高まるため、焦らず慎重に進めるようにします。
薬の副作用や治療のデメリット
筋挫傷に対する治療薬や、過度な治療行為には一定のリスクも伴います。病院から処方される薬やリハビリの進め方についても、副作用やデメリットを理解したうえで適切に付き合う必要があります。
NSAIDsの副作用
- 胃もたれや胃痛
- 胃潰瘍のリスク
- 腎機能への負担
筋挫傷でよく使われる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、痛みの緩和や炎症の抑制に効果的です。しかし、長期間の使用や空腹時の服用などで胃腸障害を引き起こす可能性があります。
また、筋組織の再生を阻害しうることも動物実験や一部の人間の研究から示唆されています。
NSAIDs使用時の留意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 服用タイミング | 食後に服用するのが望ましい |
| 併用薬 | 胃薬や整腸剤を処方される場合がある |
| 自己判断の中止 | 痛みが引いても、医師に相談してから使用を中断 |
筋弛緩薬の副作用
- 強い眠気
- 頭のふらつき
- 倦怠感や集中力の低下
筋肉の緊張を和らげる筋弛緩薬は、痛みの改善や可動域の拡大に役立ちます。一方で、眠気や倦怠感などの副作用が出るケースがあります。
運転や機械操作をする人は、副作用の出方によっては一時的に避けるようにしましょう。
リハビリにおけるオーバートレーニング
- 痛みが強くなる場合は一旦負荷を下げる
- 痛みの度合いを医師や理学療法士に報告して調整してもらう
- 十分な休息を取りながら進める
リハビリで筋肉を徐々に回復させていくのが非常に大切ですが、無理をすると再度痛みが生じたり、かえって組織が傷ついたりする可能性があります。トレーニング内容や回数は、専門家の指導に沿って行うようにしてください。
治療を急ぐリスク
- 炎症が治まりきらない状態で運動を再開
- 痛みを抑えるための薬の過剰使用
- 十分な休養を確保しないままのトレーニング
仕事やスポーツの大会などで焦りがちな方も多いですが、痛みを抱えたまま本格的な活動を再開すると、再度受傷する可能性が高いです。急ぎすぎは、結果的に治療期間の延長につながる場合があります。
短期的なメリットだけでなく、中長期的にみた体の健康を考えるようにしましょう。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
筋挫傷の治療は、整形外科や整骨院・接骨院などで受けることが多いです。治療内容によっては健康保険が適用され、自己負担金を抑えられます。治療費の目安を知っておくと、治療に踏み切りやすくなるでしょう。
健康保険の適用範囲
- 医療機関での診察、レントゲンやMRI検査
- 理学療法士によるリハビリテーション
- 投薬(内服薬、外用薬)の処方
通常、医師による診察、検査、処置、リハビリテーションなどは健康保険の適用対象になります。
接骨院や整骨院での施術も、医師の診断に基づいて受ける場合は保険適用となるケースがあります。
保険適用の主な条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医師の診断 | 医師が筋挫傷と診断し、治療が必要と判断 |
| 施術の必要性 | 施術を行う理由が明確である |
| 定期的な診察 | 継続して医師の経過観察を受ける |
治療費の目安
| 治療項目 | 費用(3割負担) | 頻度 |
|---|---|---|
| 初診・検査 | 2,000~3,000円 | 最初のみ |
| MRI | 5,000~7,000円 | 必要に応じて |
| 理学療法 | 1回300~500円 | 週1~2回 |
| 投薬 | 1日あたり100~200円 | 処方日数分 |
自己負担3割の場合を想定した場合の目安です。医療機関によって料金は異なるため、あくまで参考価格となります。
自費診療との違い
保険適用外の施術や機器を使った治療は、自費診療扱いになります。整骨院や整体院の一部サービス、特殊なリハビリ機器の使用などが該当する場合があります。
- 先進的な物理療法(特定の超音波治療器など)
- マッサージを中心とした整体プログラム
- サプリメント指導
保険が適用されない場合は全額自己負担となるため、治療を受ける前に費用を確認すると良いでしょう。
以上
参考文献
FERNANDES, Tiago Lazzaretti; PEDRINELLI, André; HERNANDEZ, Arnaldo José. Muscle injury: physiopathology, diagnostic, treatment and clinical presentation. Revista brasileira de ortopedia, 2011, 46: 247-255.
ARRINGTON, Edward D.; MILLER, Mark D. Skeletal muscle injuries. Orthopedic Clinics of North America, 1995, 26.3: 411-422.
DELOS, Demetris; MAAK, Travis G.; RODEO, Scott A. Muscle injuries in athletes: enhancing recovery through scientific understanding and novel therapies. Sports Health, 2013, 5.4: 346-352.
KUJALA, Urho M.; ORAVA, Sakari; JÄRVINEN, Markku. Hamstring injuries: current trends in treatment and prevention. Sports medicine, 1997, 23: 397-404.
BEINER, John M.; JOKL, Peter. Muscle contusion injuries: current treatment options. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2001, 9.4: 227-237.
KASEMKIJWATTANA, Channarong, et al. Development of approaches to improve the healing following muscle contusion. Cell Transplantation, 1998, 7.6: 585-598.
BEINER, John M.; JOKL, Peter. Muscle contusion injury and myositis ossificans traumatica. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 2002, 403: S110-S119.
DIAZ, J. Albert, et al. Severe quadriceps muscle contusions in athletes: a report of three cases. The American Journal of Sports Medicine, 2003, 31.2: 289-293.
PUNTEL, Gustavo O., et al. Therapeutic cold: an effective kind to modulate the oxidative damage resulting of a skeletal muscle contusion. Free radical research, 2011, 45.2: 133-146.
DENG, Peijun, et al. Contusion concomitant with ischemia injury aggravates skeletal muscle necrosis and hinders muscle functional recovery. Experimental Biology and Medicine, 2022, 247.17: 1577-1590.