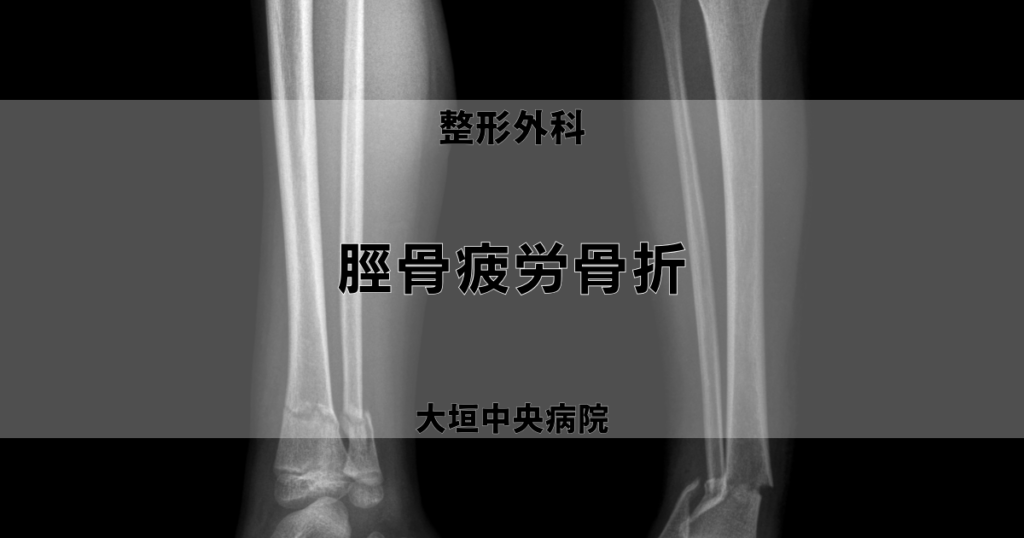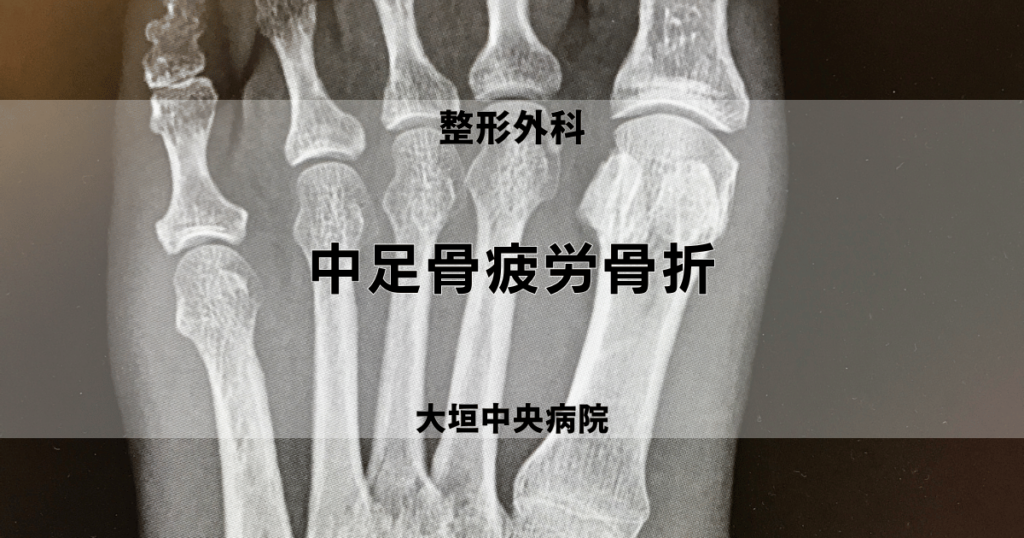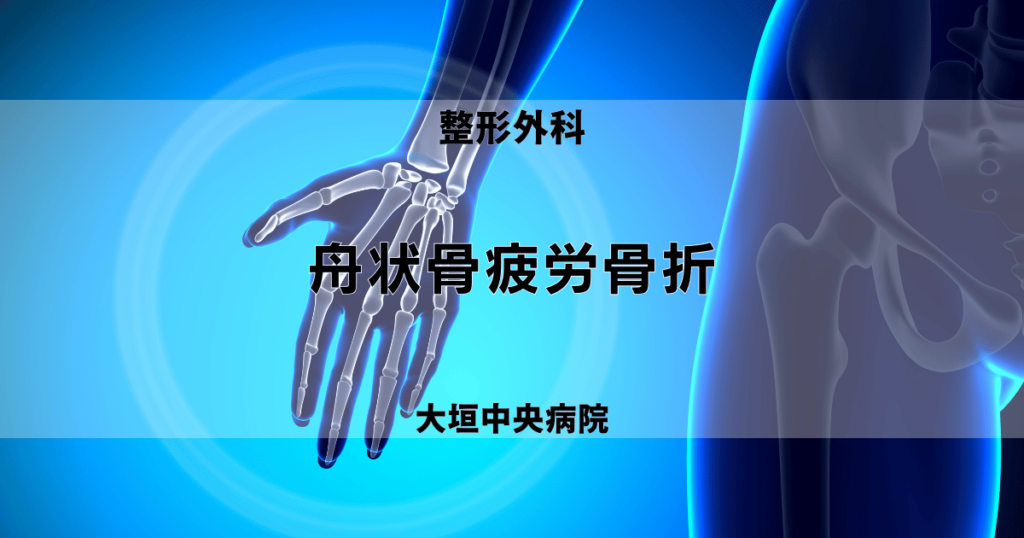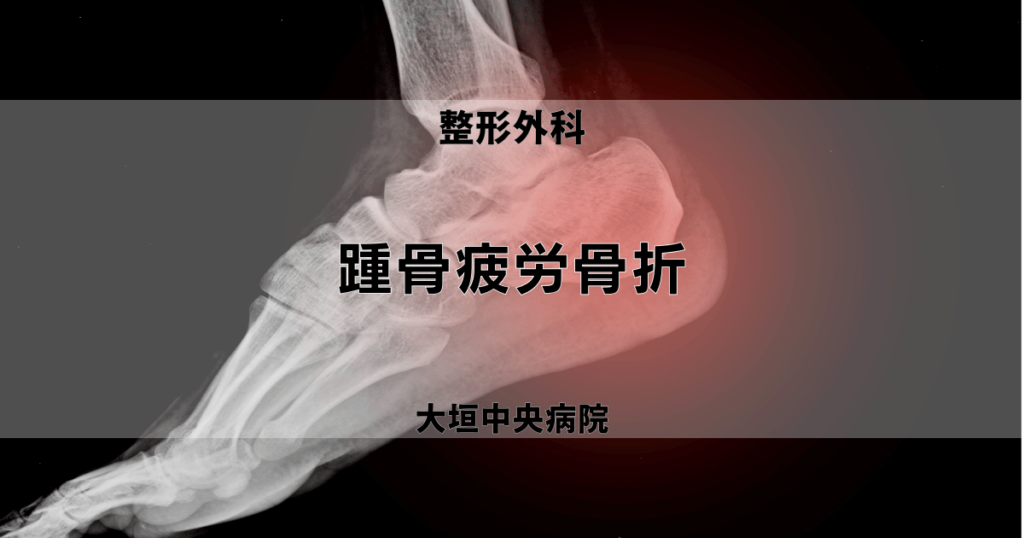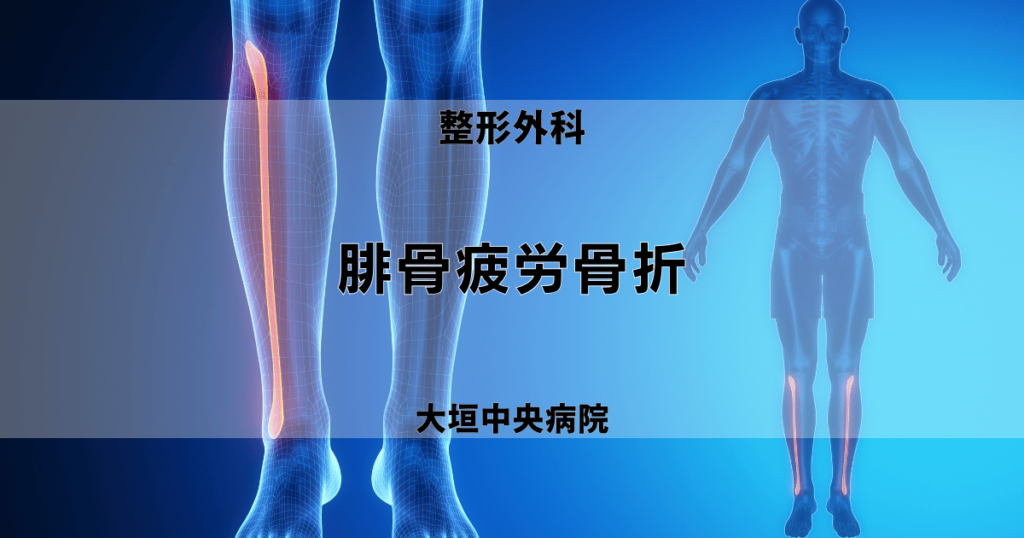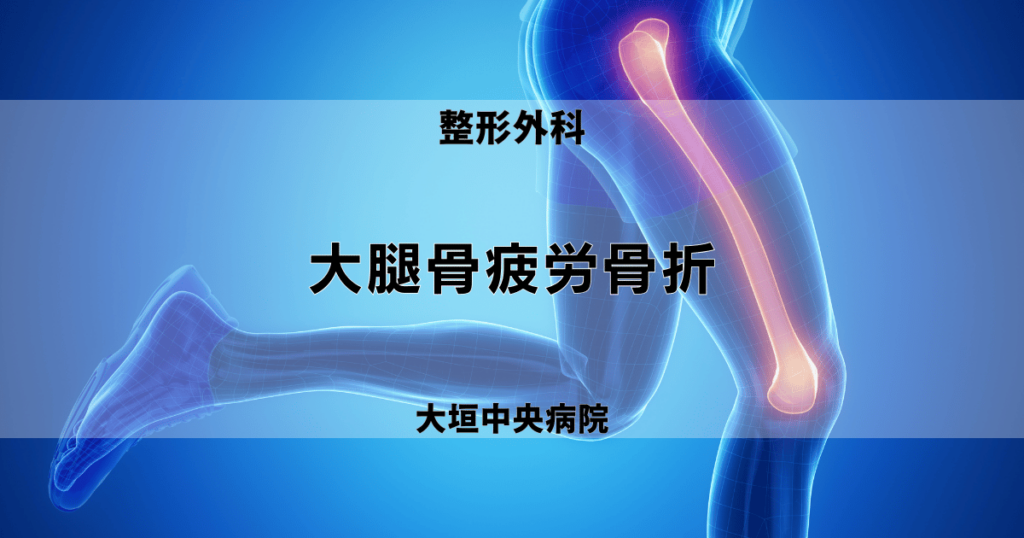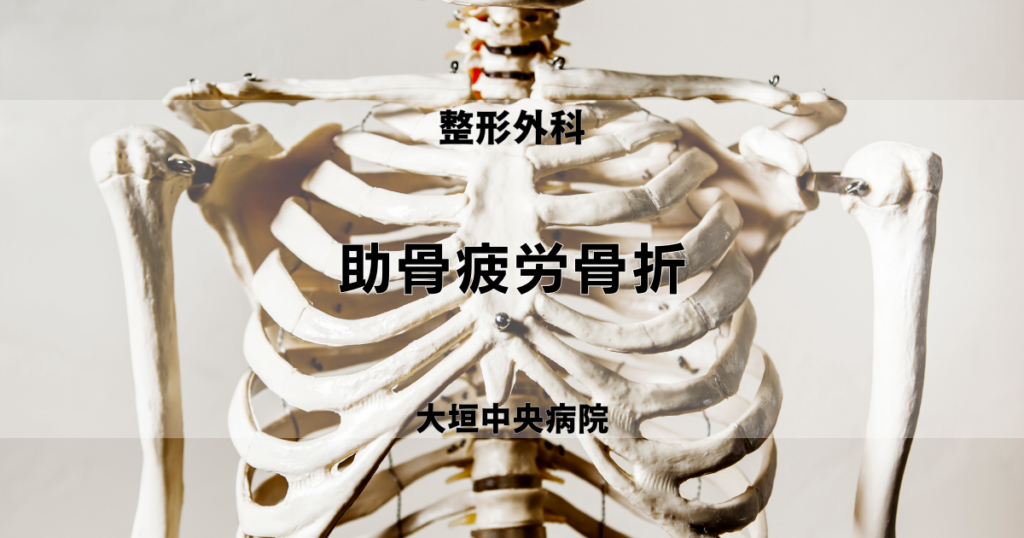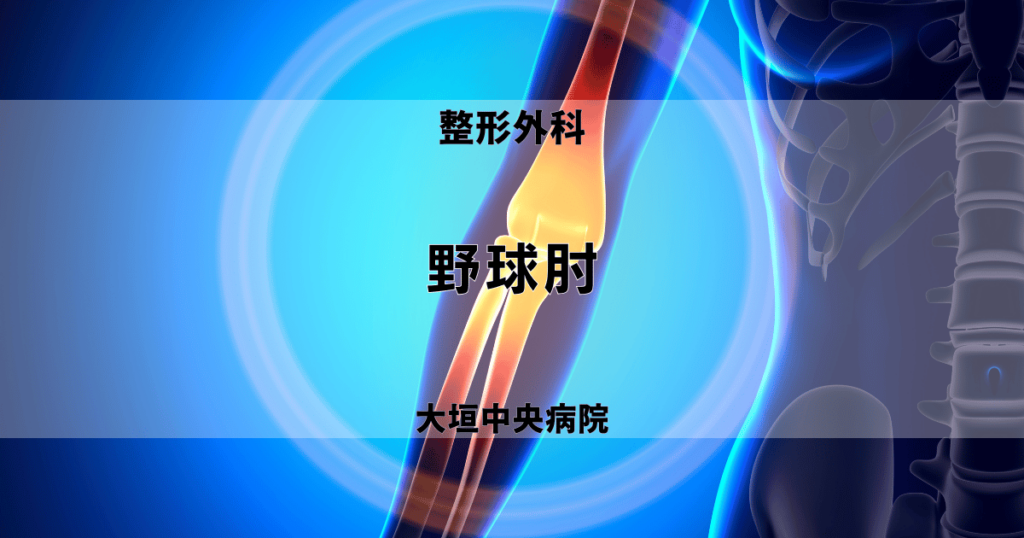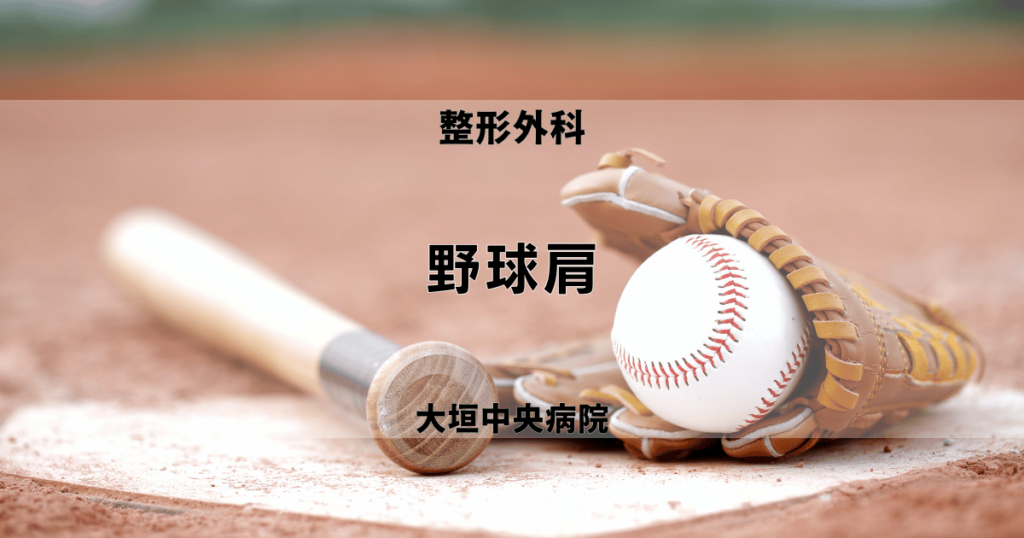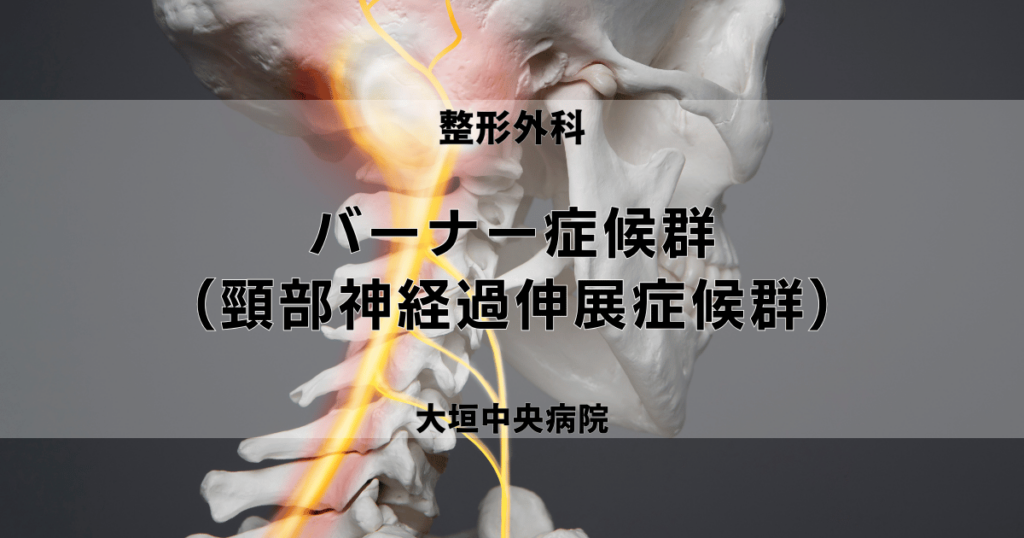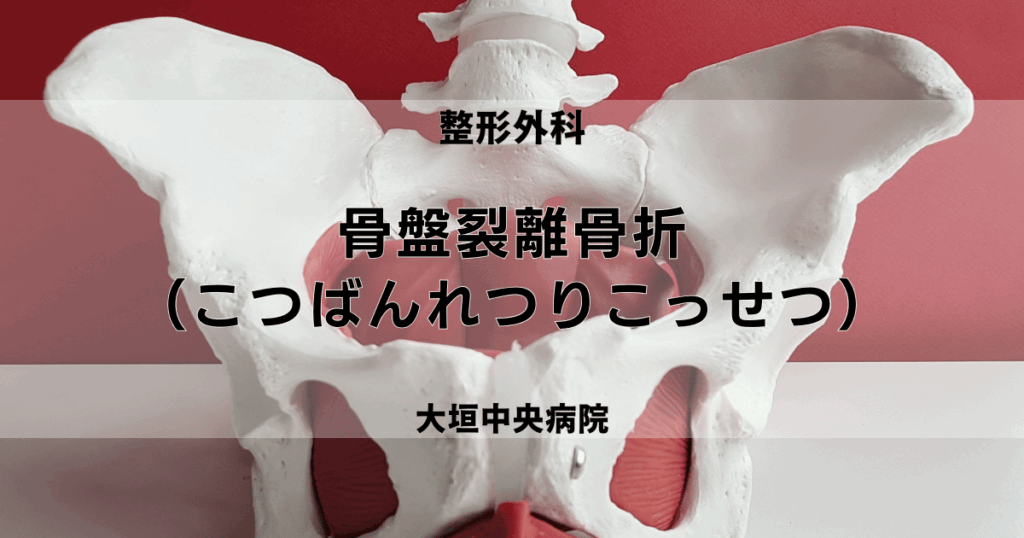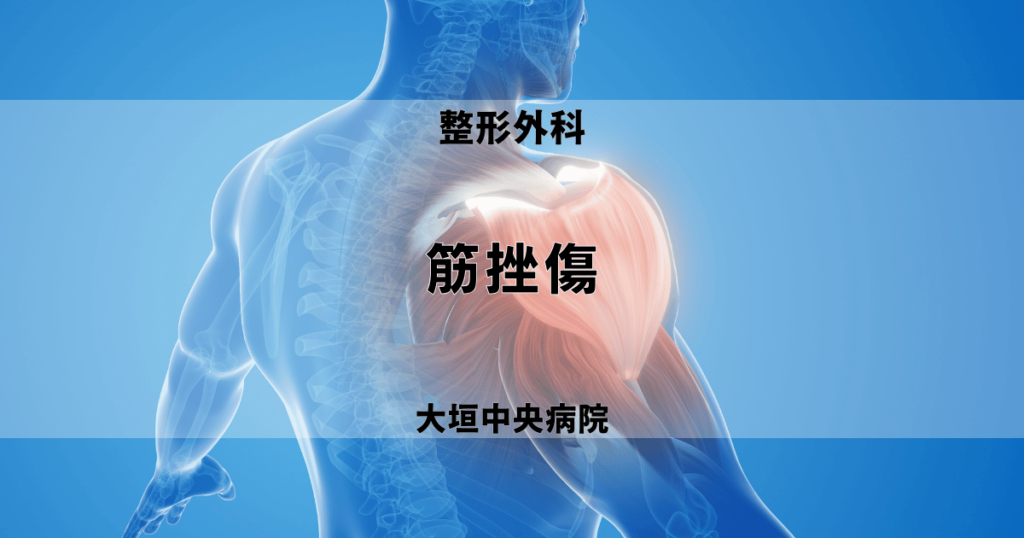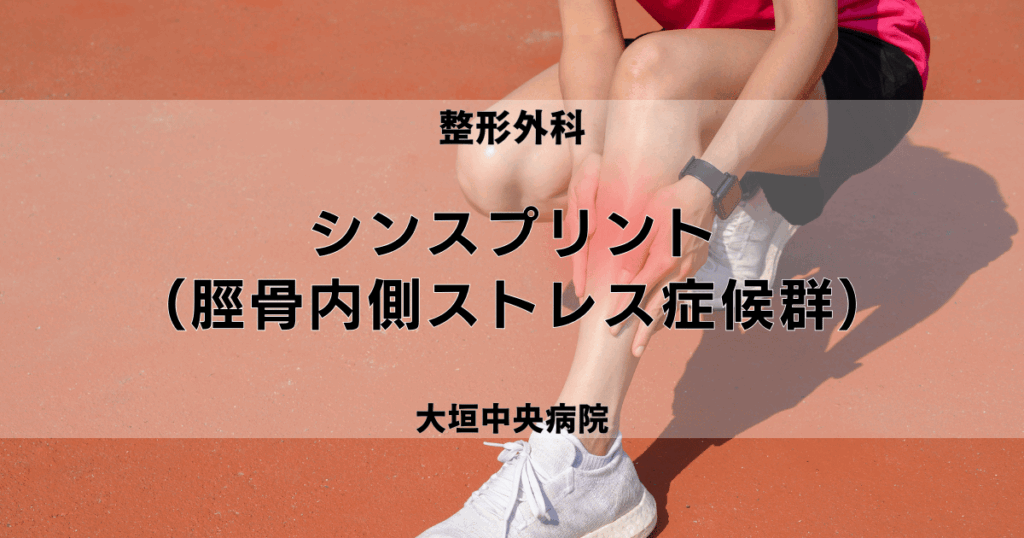スポーツ外傷とは、スポーツ活動中に発生する急性または慢性の損傷を指します。強い衝撃や転倒などによる「急性外傷」と、繰り返しの負荷により徐々に生じる「使いすぎ症候群(オーバーユース)」に大別されます。
スポーツ外傷の特徴は、日常生活では経験しない強度や角度の負荷がかかることで発生する点にあります。特に成長期のジュニアアスリートや、高い競技レベルを目指すアスリートでは、特有の外傷パターンがみられます。
適切な診断と治療、そして予防策を講じることで、多くのスポーツ外傷は回避または早期回復が可能です。
大垣駅より徒歩5分、大垣中央病院の整形外科では、アスリートの特性を理解した専門的な診療を提供し、スポーツ活動への早期復帰を支援しています。
こんな症状はご相談ください
以下のような症状でお悩みの方は、当院整形外科にご相談ください。
- スポーツ中や後に特定の部位に痛みがある
- 徐々に痛みが強くなり、スポーツを続けられない
- 休息しても痛みが改善しない
- 関節の腫れや熱感がある
- 関節の動きに制限がある
- 骨や筋肉に違和感や痛みがある
- トレーニング量を増やした後に症状が現れた
- 特定の動作で痛みが誘発される
- 以前の怪我が完全に治っているか確認したい
- 適切なトレーニング方法や予防法を知りたい
主なスポーツ外傷
疲労骨折
繰り返しの負荷によって骨に微小骨折が生じ、それが蓄積して発症する骨折です。通常の骨折とは異なり、明らかな外傷がなくても発生します。初期には運動時のみの痛みですが、進行すると安静時にも痛みを感じるようになります。
脛骨疲労骨折
ランニングやジャンプを頻繁に行うスポーツ(陸上競技、バスケットボールなど)で多く見られます。すねの内側に痛みが生じ、続けるとより強い痛みに発展することがあります。
治療
早期発見が重要で、初期には活動制限と適切な休息で改善します。進行例では、より長期の休息やギプス固定が必要となることがあります。
中足骨疲労骨折
足の甲の骨(中足骨)に生じる疲労骨折で、特に第2・3中足骨に多く見られます。ランニングや行進を多く行う競技やトレーニングで発生します。足の甲に局所的な痛みと腫れが特徴です。
治療
「行軍骨折」とも呼ばれ、適切な休息、足底板の使用、固定などで治療します。第5中足骨基部の疲労骨折(ジョーンズ骨折)は治癒遅延のリスクがあり、注意が必要です。
舟状骨疲労骨折
足の内側にある舟状骨に生じる疲労骨折で、治癒に時間がかかることが特徴です。バスケットボールやバレーボールなど、ジャンプを多用するスポーツに多く見られます。
治療
適切な診断と早期治療が重要で、見逃されると偽関節を形成するリスクがあります。保存療法が主体ですが、治癒遅延例では手術が必要となることがあります。
踵骨疲労骨折
かかとの骨(踵骨)に生じる疲労骨折で、長距離ランナーに多く見られます。かかとの痛みと腫れが特徴で、特に走り始めに痛みを感じることが多いです。
治療
適切な休息、かかとのクッション性を高める中敷きの使用などで治療します。
腓骨疲労骨折
すねの外側の骨(腓骨)に生じる疲労骨折で、ランニングや跳躍系の競技で多く見られます。すねの外側の痛みと腫れが特徴です。
治療
多くの場合、活動制限と適切な休息で改善します。
大腿骨疲労骨折
太ももの骨(大腿骨)に生じる疲労骨折で、長距離ランナーや体操選手に多く見られます。太ももや股関節周囲の痛みが特徴です。
治療
大腿骨頚部に生じると重篤化するリスクがあり、早期発見と適切な治療が特に重要です。多くの場合、長期の免荷(体重をかけない)期間が必要となります。
助骨疲労骨折
肋骨に生じる疲労骨折で、野球の投手やゴルファー、ボート選手などに多く見られます。深呼吸や体幹の回旋時に痛みが生じます。
治療
適切な休息と痛みのコントロールが基本的な治療となります。
骨盤の疲労骨折
骨盤に生じる疲労骨折で、長距離ランナーや体操選手に多く見られます。股関節や鼠径部の痛みが特徴です。
治療
適切な休息と免荷期間を設け、段階的にスポーツ復帰を目指します。女性アスリートでは、「女性アスリートの三主徴」(摂食障害、無月経、骨粗鬆症)との関連に注意が必要です。
スポーツ特有の外傷
野球肘
野球の投球動作によって肘に過度の負荷がかかり生じる障害の総称です。主に内側側副靭帯損傷、尺骨神経障害、離断性骨軟骨炎などが含まれます。肘の内側や外側の痛み、可動域制限などが症状として現れます。
治療
特に成長期の選手では適切な投球制限と正しいフォームの習得が重要です。症状によっては休息、理学療法、場合によっては手術が必要となります。
野球肩
野球の投球動作によって肩に過度の負荷がかかり生じる障害の総称です。回旋腱板損傷、関節唇損傷、関節弛緩などが含まれます。肩の痛み、可動域制限、筋力低下などが症状として現れます。
治療
適切な休息、投球フォームの改善、筋力強化、ストレッチなどの保存療法が基本となりますが、症状が重度の場合は手術を検討することがあります。
バーナー症候群
コンタクトスポーツ(特にアメリカンフットボールやラグビー)で、頭部や肩に衝撃が加わり、腕神経叢が一時的に損傷される状態です。腕や手のしびれ、痛み、一時的な筋力低下などが症状として現れます。
治療
多くの場合、症状は一過性ですが、繰り返す場合や症状が持続する場合は専門的な評価と治療が必要です。
離断性骨軟骨炎(OCD)
関節面の骨軟骨が部分的に血流障害を起こし、関節軟骨と骨の一部が剥離する疾患です。肘(特に野球選手)や膝(特にサッカーや体操選手)に多く見られます。関節の痛み、腫れ、引っかかり感などが症状として現れます。
治療
早期発見と適切な休息が重要です。症状や進行度によっては、ギプス固定、免荷、場合によっては手術(骨軟骨片の固定や除去など)が必要となります。
骨盤裂離骨折
成長期のアスリートが、急激な筋肉の収縮によって骨盤の筋肉付着部が骨ごと剥離する骨折です。サッカー、陸上などの競技で多く見られます。骨盤や股関節周囲の痛みが特徴です。
治療
適切な休息と段階的なリハビリテーションが基本的な治療となります。重度の場合は手術が必要となることもあります。
筋・腱の損傷
肉離れ(筋損傷・筋断裂)
筋肉に急激な負荷がかかり、筋繊維が部分的または完全に断裂する状態です。ハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)、ふくらはぎ、大腿四頭筋などに多く発生します。突然の鋭い痛み、腫れ、内出血などが症状として現れます。
治療
軽度の場合は安静、冷却、圧迫、挙上(RICE処置)と適切なリハビリテーションで回復しますが、重度の筋断裂では手術が必要となることがあります。
筋挫傷
外力によって筋肉が圧迫され、損傷する状態です。打撲とも呼ばれます。コンタクトスポーツで多く見られ、痛み、腫れ、内出血などが症状として現れます。
治療
RICE処置と適切な休息が基本的な治療となります。重度の場合、コンパートメント症候群に進展する可能性があり注意が必要です。
ジャンパー膝
膝蓋腱(膝のお皿と脛骨をつなぐ腱)の使いすぎによる炎症や変性です。バスケットボールやバレーボールなど、ジャンプを多用するスポーツで多く見られます。膝の前面の痛み、特にジャンプの踏み切りや着地時に痛みが悪化します。
治療
活動の調整、アイシング、ストレッチ、筋力強化などの保存療法が基本となります。重度の場合は、注射療法や手術を検討することがあります。
ランナー膝(腸脛靱帯炎)
腸脛靭帯(大腿骨外側から膝を越えて脛骨に至る靭帯様の組織)が膝関節外側で摩擦を起こして炎症を生じる状態です。ランニングやサイクリングなどの繰り返し動作で多く見られます。膝の外側の痛みが特徴です。
治療
活動の調整、アイシング、ストレッチ、筋力強化、フォーム改善などの保存療法が基本となります。長期化する場合は、注射療法や理学療法のさらなる介入が必要となることがあります。
シンスプリント
脛骨の内側縁に沿った痛みを特徴とする使いすぎ症候群です。ランニングや跳躍を多用するスポーツで多く見られます。運動時に増強する脛骨内側の痛みが特徴で、疲労骨折の前段階とも考えられています。
治療
活動の調整、アイシング、適切な靴の選択、ストレッチ、筋力強化などの保存療法が基本となります。進行すると脛骨疲労骨折に発展する可能性があるため、適切な休息と早期治療が重要です。
診断・検査
当院では、スポーツ外傷の正確な診断のために、以下のような検査を行っています。
問診・診察
スポーツ歴、トレーニング内容、症状の経過などを詳しく聞き取り、適切な診察を行います。
レントゲン検査
骨折や変形などの評価を行います。
MRI検査
筋肉、腱、靭帯、軟骨などの軟部組織の評価を行います。
CT検査
複雑な骨折や骨病変の詳細な評価を行います。
超音波検査
腱や筋肉の状態をリアルタイムで観察します。
骨シンチグラフィー
疲労骨折などの早期発見に有用です。
動作分析
スポーツ動作を分析し、外傷の原因となる動作パターンを評価します。
筋力・柔軟性評価
筋力や関節可動域を測定し、不均衡や制限を評価します。
治療方法
急性期の治療
スポーツ外傷発症直後の適切な対応は、回復を早め、合併症を防ぐために重要です。
- Rest(安静):損傷部位を休ませます。
- Ice(冷却):腫れや痛みを軽減するために冷却します。
- Compression(圧迫):腫れを抑えるために適度に圧迫します。
- Elevation(挙上):損傷部位を心臓より高い位置に挙上し、腫れを軽減します。
消炎鎮痛剤などで痛みや炎症を抑えます。
必要に応じて装具や松葉杖を用いて固定や免荷を行います。
回復期の治療
急性期を過ぎたら、機能回復と再発予防を目指したリハビリテーションを行います。
- 関節可動域訓練:制限された関節の動きを改善します。
- 筋力強化訓練:弱化した筋肉を強化します。
- バランストレーニング:姿勢制御や協調性を向上させます。
- スポーツ特異的トレーニング:競技復帰に向けた専門的なトレーニングを行います。
超音波療法、電気療法、温熱療法などを用いて治癒を促進します。
必要に応じてテーピングやサポーターなどを用いて、スポーツ活動中の保護や再発予防を図ります。
難治例・重症例の治療
保存療法で改善しない場合や、重度の損傷の場合は、さらなる介入が必要となることがあります。
ステロイド注射、高濃度血小板血漿(PRP)療法などを行うことがあります。
骨折の固定、断裂した腱や靭帯の修復・再建などを行います。
手術後や重度の損傷後に、専門的かつ集中的なリハビリテーションを行います。
当院では、患者様の年齢、競技レベル、スポーツ活動の目標などを考慮し、個々に最適な治療計画を立案します。また、早期の適切な対応と段階的なスポーツ復帰プログラムにより、安全かつ効果的な競技復帰を支援します。
スポーツ復帰プログラム
当院では、スポーツ外傷からの回復後、安全に競技に復帰するための段階的なプログラムを提供しています。
第1段階
(回復初期)
基本的な動作の回復を目指します。痛みのない範囲での基本的な運動、筋力・柔軟性の回復を行います。
第2段階
(機能回復期)
スポーツ特異的な動作の練習を始めます。スポーツに必要な筋力、持久力、協調性の向上を図ります。
第3段階
(スポーツ復帰準備期)
競技に近い環境での練習を行います。実践的なドリルやシミュレーションを通じて、競技復帰の準備を整えます。
第4段階
(競技復帰期)
実際の競技への段階的な復帰を進めます。練習量や強度を徐々に増やし、完全復帰を目指します。
段階的アプローチにより、再発リスクを最小限に抑えながら、効果的なスポーツ復帰が可能となります。