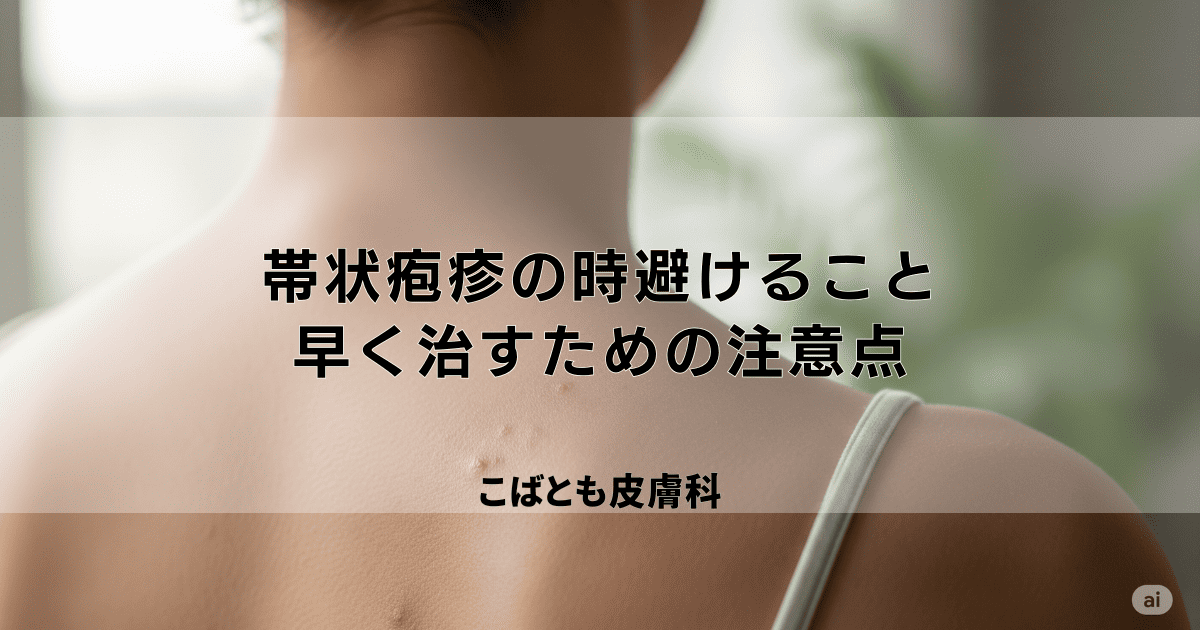ある日突然、体の片側にピリピリとした痛みや違和感が生じ、その後に赤い発疹や水ぶくれが現れる帯状疱疹。経験したことのない激しい痛みに、不安な日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。
つらい症状を一日でも早くきれいに治すためには、治療と並行して日々の過ごし方が非常に重要です。
この記事では、帯状疱疹の症状を悪化させず、回復を早めるために知っておくべき注意点を詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
そもそも帯状疱疹とは?原因と初期症状
帯状疱疹は、多くの人が子供の頃にかかる水ぼうそうと同じウイルスが原因であることを知り、驚くかもしれません。ここでは、なぜ帯状疱疹が発症するのか、そして見逃してはならない初期症状について掘り下げていきます。
水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化する
帯状疱疹は、水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされます。
多くの人が幼少期にこのウイルスに初めて感染し、水ぼうそうとして発症しますが、水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体から完全に消え去るわけではありません。
ウイルスは、背骨の近くにある神経の根元部分、神経節(しんけいせつ)と呼ばれる場所に、ウイルスはじっと潜伏し続けます。
健康で免疫力が正常に働いている間は、潜伏しているウイルスが活動することはないものの、加齢、過労、ストレス、病気、免疫抑制薬の使用など、何らかの理由で免疫力が低下すると、潜伏していたウイルスが再び目を覚まし、活動を始めます。
これをウイルスの再活性化と呼びます。再活性化したウイルスは、潜伏していた神経節から神経を伝って皮膚へと移動し、そこで増殖することで帯状疱疹特有の症状を起こすのです。
体の片側に現れるピリピリとした痛み
帯状疱疹の最も特徴的な初期症状の一つが、体の左右どちらか一方に限定して現れる痛みです。多くの患者さんが、皮膚に発疹が現れる数日前から1週間ほど前に、この前兆となる痛みを経験します。
痛み方は人それぞれで、チクチク、ピリピリ、ズキズキといった表現がよく使われます。時には焼けるような痛みや、かゆみとして感じることもあります。
痛みは、再活性化したウイルスが神経を傷つけながら皮膚に向かって移動するために起こります。ウイルスは特定の神経の支配領域に沿って広がるため、症状もその神経が分布する範囲、つまり体の片側に帯状に現れるのが特徴です。
胸から背中にかけてが最も多い発症部位ですが、顔、首、腕、足など、神経がある場所ならどこにでも発症する可能性があります。
この段階ではまだ皮膚に変化が見られないため、筋肉痛、神経痛、あるいは内臓の病気などと間違われることも少なくありません。
痛みから数日後に現れる赤い発疹と水ぶくれ
ピリピリとした痛みが始まってから数日経つと、痛みがあった部位の皮膚に、赤い発疹がポツポツと現れ始めます。発疹は、神経の走行に沿って帯状に広がっていくのが大きな特徴です。
初めは小さな赤い斑点ですが、次第に盛り上がり、その中心に液体を含んだ小さな水ぶくれ(水疱)が多発するようになります。
水ぶくれは、初めは透明な液体を含んでいますが、時間とともに黄色く濁り、膿が溜まった状態(膿疱)になることもあり、発疹と水ぶくれが現れる時期は、痛みが最も強くなることが多いです。
皮膚症状だけでなく、発熱や頭痛、全身のだるさといった全身症状を伴うこともあります。通常、水ぶくれは2週間ほどでかさぶたになり、3週間程度で自然に治癒していきます。
帯状疱疹の初期症状チェック
| 症状 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 皮膚の違和感・痛み | 体の片側にピリピリ、チクチク、ズキズキとした痛みやかゆみが生じる。 | 発疹が出る前なので、他の病気と間違えやすい。 |
| 赤い発疹 | 痛みのあった場所に、帯状に赤いポツポツが現れる。 | 虫刺されや湿疹と自己判断しないことが重要。 |
| 小さな水ぶくれ | 赤い発疹の上に、液体を含んだ水疱が多発する。 | 絶対に潰さないように注意が必要。 |
見逃しやすい初期症状と受診の目安
帯状疱疹の治療は、時間との勝負で、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬は、発疹が出てから72時間(3日)以内に服用を開始することが、重症化や帯状疱疹後神経痛という後遺症を防ぐ上で極めて重要です。
もし、体の片側に原因不明の痛みが現れ、数日経っても改善しない場合は、たとえ発疹がなくても帯状疱疹の可能性を疑い、早めに皮膚科を受診してください。
特に、過去に水ぼうそうにかかったことがある方で、最近疲れやストレスを感じている場合は注意が必要です。
患部に対してやってはいけないこと
帯状疱疹の症状が出ている患部は、ウイルスによって皮膚と神経がダメージを受け、非常にデリケートな状態になっています。
良かれと思ってやったことが、かえって症状を悪化させたり、治りを遅らせたり、さらには細菌感染を起こす原因にもなりかねません。
水ぶくれを潰す・破る
帯状疱疹でできた水ぶくれは、気になってつい触りたくなりますが、絶対に自分で潰したり、針で刺して破ったりしてはいけません。
水ぶくれの中には、水痘・帯状疱疹ウイルスが大量に含まれていて、破ってしまうと、ウイルスが周囲の健康な皮膚に付着し、発疹の範囲を広げてしまう可能性があります。
さらに、水ぶくれが破れた部分は、皮膚のバリア機能が失われた状態になり、そこから細菌が侵入し、二次感染(細菌感染)を起こすリスクが非常に高まります。
細菌感染を起こすと、傷口が化膿して痛みがさらに強くなるだけでなく、治りが遅くなったり、傷跡が残りやすくなったりします。水ぶくれは自然に乾燥してかさぶたになるのを待つのが鉄則です。
水ぶくれを潰してはいけない理由
- ウイルスの拡散
- 細菌感染のリスク増大
- 治癒の遅延
- 傷跡が残りやすくなる
患部を温める
痛みがあると、温めると楽になるようなイメージがあるかもしれませんが、帯状疱疹の場合は逆効果です。帯状疱疹の痛みや赤みは、ウイルスによって神経や皮膚が炎症を起こしていることが原因です。
炎症が起きている場所を温めると、血管が拡張して血流が増加し、炎症反応がさらに促進されてしまい、痛みやかゆみが悪化する可能性があります。
痛みやほてりがつらい時は、冷たいタオルや保冷剤をタオルで包んだもので優しく冷やす方が、症状の緩和に効果的です。ただし、冷やしすぎると血行不良を招くこともあるため、1回15分程度を目安に、心地よいと感じる範囲で行いましょう。
刺激の強い軟膏やクリームを塗る
皮膚に発疹や水ぶくれができると、市販のかゆみ止めや湿疹の薬を塗りたくなるかもしれませんが、自己判断で軟膏やクリームを塗ることは非常に危険です。
特に、ステロイド成分が含まれている軟膏は、免疫を抑制する作用があるため、ウイルスの増殖を助長し、症状を著しく悪化させる恐 れがあります。
また、メントールなどの清涼成分が含まれるものや、アルコール成分が強いものも、デリケートな患部には刺激が強すぎます。
患部のケア用品の選び方
| 種類 | 推奨されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 塗り薬 | 医師処方の抗生物質軟膏、亜鉛華軟膏など | 市販のステロイド軟膏、刺激の強いかゆみ止め |
| 保護材 | 清潔なガーゼ、非固着性のドレッシング材 | 絆創膏(粘着部分が患部に触れるもの) |
| 洗浄料 | 低刺激性の石鹸やボディソープ | スクラブ入り、香料やアルコールが強いもの |
きつい衣服で患部を締め付ける
患部が衣服で擦れると、刺激で痛みが強まったり、水ぶくれが破れたりする原因になります。ジーンズやガードル、きつい下着など、体にぴったりとフィットする衣服は避けましょう。
摩擦によって皮膚が傷つくと、そこから細菌が侵入するリスクも高まります。帯状疱疹の治療中は、できるだけゆったりとした、通気性の良い衣服を選ぶことが大切で、素材は、肌触りの良い綿やシルクなどの天然素材がおすすめです。
患部を直接覆う場合は、清潔なガーゼなどで優しく保護し、その上からゆったりした服を着るように工夫しましょう。
日常生活で避けるべき行動
帯状疱疹は免疫力の低下が引き金となって発症するため、治療効果を高め一日も早く回復するためには、薬を飲むだけでなく、日常生活そのものを見直すことが重要です。
過労や睡眠不足
帯状疱疹の発症自体が、体が休息を求めているサインです。発症の背景には、仕事の忙しさや育児、介護などによる肉体的な疲労の蓄積がある場合が少なくありません。
このような状態で無理を続けると、体の免疫システムは正常に機能せず、ウイルスと戦う力が弱まってしまい、症状が長引いたり、重症化したりする可能性があります。
治療中は、仕事や家事はできるだけ周りの人に協力してもらい、無理のない範囲で行いましょう。また、質の良い睡眠を十分にとることも免疫力の回復には必要です。
強い精神的ストレス
精神的なストレスも、免疫力を低下させる大きな要因の一つです。心配事や悩み、人間関係のトラブルなどは、自律神経のバランスを乱し、免疫細胞の働きを鈍らせることが科学的にも知られています。
帯状疱疹の激しい痛み自体が大きなストレスとなり、さらに症状を悪化させるという悪循環に陥ることもあります。治療中は、できるだけストレスの原因から距離を置き、心穏やかに過ごすことを心がけましょう。
ストレスを溜めないための工夫
- 好きな音楽を聴く
- 軽い読書をする
- 腹式呼吸や瞑想
- 天気の良い日に少し散歩する
長時間の入浴やサウナ
体を清潔に保つことは大切ですが、長時間の入浴や熱いお湯に浸かること、サウナの利用は避けてください。
患部を温めると炎症が悪化し、痛みやかゆみが強くなる可能性があり、また、体力を消耗し、かえって免疫力を低下させることにもつながりかねません。
入浴する際は、ぬるめのお湯(38〜40度程度)で、短時間で済ませるようにしましょう。患部はゴシゴシこすらず、低刺激性の石鹸をよく泡立てて、手で優しくなでるように洗います。
シャワーで洗い流した後は、水ぶくれを破らないように、細心の注意を払うことが大切です。
入浴時の注意点
| 項目 | 推奨される方法 | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| 湯温 | 38〜40度のぬるま湯 | 42度以上の熱いお湯 |
| 入浴時間 | 10分程度のシャワー浴 | 長時間の入浴、半身浴 |
| 洗い方 | 低刺激性の石鹸を泡立て、手で優しく洗う | ナイロンタオルでゴシゴシこする |
過度な飲酒や喫煙
アルコールの摂取は、血行を促進させる作用があるため、患部の炎症を悪化させ、痛みやかゆみを増強させる可能性があります。また、アルコールを分解するために肝臓に負担がかかり、体全体の回復力を妨げることも考えられます。
さらに、薬の効果に影響を与えたり、副作用を増強させたりする恐れもあるため、治療中の飲酒は原則として控えるべきです。
タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、血行を悪化させ、傷ついた皮膚や神経の修復に必要な酸素や栄養素が届きにくくなり、治癒を遅らせる原因となります。また、喫煙は免疫機能そのものを低下させることも知られています。
食事で注意すべきこと
帯状疱疹との戦いは、体の内側からのアプローチも非常に重要です。日々の食事が免疫細胞の働きを左右し、ウイルスの活動に影響を与えることがあります。
免疫力を低下させる可能性のある食事
まず基本として、免疫システムを正常に保つためには、栄養バランスの取れた食事が大前提です。しかし、特定の食品や食生活は、免疫力を低下させ、炎症を助長する可能性があります。
特に、加工食品やインスタント食品、スナック菓子などに多く含まれるトランス脂肪酸や過剰な糖分、食品添加物は、腸内環境を悪化させ、免疫機能の乱れにつながることが指摘されています。
避けるべき食品・成分の例
| カテゴリ | 具体的な食品例 | 避けるべき理由 |
|---|---|---|
| 加工食品 | インスタント麺、冷凍食品、ハム、ソーセージ | 添加物や塩分が多く、栄養バランスが偏りやすい。 |
| 高脂肪食 | 揚げ物、ファストフード、洋菓子 | 過剰な脂質が炎症を促進する可能性がある。 |
| 高糖質食 | 清涼飲料水、菓子パン、ケーキ、白砂糖 | 血糖値の急上昇が免疫機能に悪影響を与える。 |
アルギニンを多く含む食品の過剰摂取
アミノ酸の一種であるアルギニンは、水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を助けるエサになると考えられています。
アルギニン自体は、成長ホルモンの分泌を促したり、免疫機能を助けたりする体にとって必要な栄養素ですが、帯状疱疹の治療中に過剰に摂取することは推奨されません。
アルギニンは、ナッツ類(特にピーナッツやアーモンド)、チョコレート、大豆製品、鶏肉、エビ、ゴマなどに多く含まれています。完全に断つ必要はありませんが、症状が出ている間は、意識して摂取量を控えましょう。
アルギニンと拮抗する働きを持つリジンというアミノ酸は、ウイルスの増殖を抑制する効果が期待されていて、魚介類、乳製品、牛肉、豚肉などに多く含まれています。
香辛料などの刺激物
唐辛子に含まれるカプサイシンや、胡椒、カレー粉などの香辛料は、交感神経を刺激し、血行を促進する作用があります。
健康な時には食欲増進などの良い効果もありますが、帯状疱疹で炎症が起きている時には、この作用が裏目に出ることがあります。血流が良くなることで、患部の炎症が強まり、痛みやかゆみが増す可能性があるのです。
また、辛いものを食べると汗をかきやすくなり、汗が患部に付着すると、刺激になったり、細菌が繁殖する原因になったりすることもあります。
症状が落ち着くまでは、香辛料を多用した激辛料理やエスニック料理などは避けて、胃腸に優しく、薄味の和食中心の食事を心がけると良いでしょう。
体を冷やす食べ物や飲み物
体の冷えは血行不良を招き免疫力の低下につながり、冷たい飲み物や食べ物を一度にたくさん摂ると、内臓が冷えてしまい、体全体の機能が低下しやすくなります。
免疫細胞が活発に働くためには、適度な体温が保たれていることが重要で、治療中は、体を内側から温める食事を意識することが大切です。
飲み物は、常温または温かいものを選び、サラダなどの生野菜よりは、スープや煮物、蒸し料理など、加熱調理したものを中心に摂るのがおすすめです。
体を温める作用のある根菜類(生姜、人参、ごぼうなど)を積極的に取り入れるのも良いでしょう。
体を温める食事の工夫
| 種類 | おすすめの食材・メニュー | ポイント |
|---|---|---|
| 飲み物 | 白湯、麦茶、生姜湯、ハーブティー | 冷蔵庫から出してすぐの冷たいものは避ける。 |
| 主食 | おかゆ、うどん、雑炊 | 消化が良く、体を温める。 |
| おかず | 根菜の煮物、野菜スープ、鶏肉の蒸し料理 | 加熱調理でかさを減らし、栄養を摂りやすくする。 |
自己判断による誤った対処法
突然の痛みや発疹に襲われると、つい手近にある薬で何とかしようとしたり、大したことはないと軽く考えてしまったりすることがあります。しかし、帯状疱疹における自己判断は、症状の悪化や重い後遺症につながる非常に危険な行為です。
市販の鎮痛薬だけで済ませる
帯状疱疹の痛みは非常に強いため、まずは市販の鎮痛薬で痛みを抑えようと考える方は少なくありません。
ロキソプロフェンやイブプロフェンといった鎮痛薬(NSAIDs)は、一時的に痛みを和らげる効果がありますが、あくまで対症療法に過ぎません。鎮痛薬には、痛みの原因であるウイルスの増殖を抑える作用はないのです。
鎮痛薬で痛みが少し和らいだために、医療機関の受診が遅れてしまうことが最大の問題で、その間にウイルスはどんどん増殖し、神経へのダメージを広げてしまいます。
受診が遅れ、抗ウイルス薬の開始が72時間を過ぎてしまうと、薬の効果が十分に得られず、帯状疱疹後神経痛というつらい後遺症が残るリスクが格段に高まります。痛みを感じたら、まず皮膚科を受診し、原因を特定することが先決です。
市販薬使用の注意点
| 薬の種類 | 期待できる効果 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 鎮痛薬(NSAIDs) | 一時的な痛みの緩和 | ウイルスの増殖は抑えられない。受診の遅れにつながる。 |
| ステロイド外用薬 | (なし) | 免疫を抑制し、症状を著しく悪化させる危険性がある。 |
| 抗真菌薬・抗菌薬 | (なし) | 原因が異なるため全く効果がない。 |
発疹をただの虫刺されや湿疹だと放置する
体の片側に帯状に広がるという特徴を知らないと、初期の赤いポツポツを「虫に刺されたかな」「かぶれただけだろう」と軽く考えてしまいがちです。
かゆみが主な症状の場合、湿疹やあせもと勘違いしてしまうこともありますが、初期段階での見極めが、その後の経過を大きく左右します。
帯状疱疹は、放置すればするほどウイルスが増殖し、神経の損傷がひどくなります。
治療の開始が遅れると、皮膚の症状が治った後も、数ヶ月から数年にわたって焼けるような、あるいは電気が走るような激しい痛みが続く帯状疱疹後神経痛に移行するリスクが高まります。
自己判断で様子を見るのではなく、少しでも怪しいと感じたら、すぐに専門医の診断を仰ぐことが、自分自身の体を守る最善の策です。
医療機関を受診すべきサイン
- 体の片側だけに痛みや発疹がある
- ピリピリ、ズキズキとした神経痛のような痛み
- 帯状に広がる赤い発疹と水ぶくれ
- 過去に水ぼうそうにかかったことがある
周囲の人への配慮と感染対策
自分が帯状疱疹にかかった時、気になることの一つが「周りの人にうつらないか」という点でしょう。特に、小さな子供や妊婦さん、高齢者など、免疫力が十分でない方が身近にいる場合は、心配も大きくなります。
帯状疱疹は他人にうつるのか
まず理解しておくべき重要な点は、帯状疱疹そのものが空気感染などで他人にうつることはない、ということです。帯状疱疹は、あくまで自分自身の体内に潜伏していたウイルスが再活性化して起こる病気です。
ただし、注意が必要で、帯状疱疹の原因である水痘・帯状疱疹ウイルスは、まだ水ぼうそうにかかったことがない人や、水ぼうそうのワクチンを接種していない人に感染する可能性があります。
感染経路は、帯状疱疹の水ぶくれの中に含まれるウイルスとの接触です。
水ぶくれが破れて中の液体に触れたり、ウイルスが付着したタオルや食器などを共有したりすることで、ウイルスが相手の体にうつり、水ぼうそうとして発症させることがあります。
特に注意が必要な人
水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を持っていない人は、感染のリスクが高いため、特に慎重な対応が求められます。また、免疫力が低下している人が水ぼうそうにかかると、重症化しやすいため、細心の注意を払わなければなりません。
感染リスクが高い人
| 対象者 | 理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 新生児・乳幼児 | まだ水ぼうそうにかかっておらず、免疫がない。 | 水ぶくれに触れさせない。タオルの共用を避ける。 |
| 妊婦 | 妊娠初期に感染すると胎児に影響が出る可能性がある。 | 発症中は接触を避けるのが望ましい。 |
| 免疫力が低下している人 | 高齢者、抗がん剤治療中の方、免疫抑制薬使用者など。 | 水ぼうそうが重症化するリスクが高い。 |
感染を防ぐための対策
周囲の人、特に免疫のない人にウイルスをうつさないためには、水ぶくれの管理が最も重要です。すべての発疹がかさぶたになれば、感染力はなくなると考えられていて、それまでの間は、以下の対策を徹底します。
まず、患部を清潔なガーゼや衣類で常に覆い、水ぶくれが破れたり、中の液体が外に漏れたりしないように保護します。水ぶくれは絶対に自分で潰してはいけません。患部に触れた後は、必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。
また、患者さんが使ったタオルや衣類は、他の家族のものとは別に洗濯し、入浴も最後に入るなどの配慮が大切です。特に、水ぼうそうにかかったことのない子供との接触は、発疹がかさぶたになるまでできるだけ避けてください。
感染対策のポイント
- 患部をガーゼで覆う
- こまめな手洗い
- タオルの共用を避ける
- 洗濯物を分ける
帯状疱疹を早く治すために積極的に行いたいこと
ここまで、帯状疱疹の時にやってはいけないことを中心に解説してきましたが、回復を早めるために積極的に行うべきこともあります。治療の基本は、ウイルスの増殖を抑え、体の免疫力を高めてウイルスを撃退することです。
早期の医療機関受診と抗ウイルス薬の服用
帯状疱疹の治療は時間との勝負で、体の片側の痛みや違和感、発疹など、少しでも帯状疱疹を疑う症状があれば、ためらわずに皮膚科を受診してください。
発症から72時間以内に抗ウイルス薬の服用を開始できれば、ウイルスの増殖を効果的に抑制し、症状の重症化を防ぎ、帯状疱疹後神経痛のリスクを大幅に減らすことができます。
十分な休息と栄養バランスの取れた食事
帯状疱疹は体が発するSOSサインで、このサインを真摯に受け止め、心と体をしっかりと休ませることが、何よりの薬になります。睡眠時間を十分に確保し、日中も無理せず横になる時間を設けましょう。
また、免疫細胞がウイルスと戦うためには、十分な栄養が必要です。特定の食品に偏るのではなく、主食、主菜、副菜をそろえ、バランスの取れた食事を心がけます。
免疫力アップに役立つ栄養素
- ビタミンC(ピーマン、ブロッコリー、柑橘類)
- ビタミンA(緑黄色野菜、レバー)
- ビタミンE(ナッツ類、植物油)
- 亜鉛(牡蠣、牛肉、卵)
患部を清潔に保ち冷やす
細菌の二次感染を防ぐため、患部は常に清潔に保つ必要があり、入浴やシャワーの際には、低刺激性の石鹸を使い、優しく洗いましょう。洗い流した後は、柔らかいタオルで水分をそっと拭き取ります。水ぶくれを破らないように注意してください。
また、痛みやほてりが強い場合は、我慢せずに冷やすのが効果的です。清潔なタオルで保冷剤を包み、1回15分程度を目安に患部に優しく当てます。
痛みを我慢せず医師に相談する
帯状疱疹の痛みは、我慢できるレベルを超えていることが少なくありません。痛みを我慢し続けることは、それ自体が大きなストレスとなり、睡眠を妨げ、免疫力をさらに低下させる悪循環を生み出します。
また、強い痛みが長期間続くと、脳が痛みを記憶してしまい、帯状疱疹後神経痛に移行しやすくなるとも言われています。
処方された鎮痛薬で痛みがコントロールできない場合は、遠慮なく医師に相談してください。
よくある質問
最後に、帯状疱疹に関して患者様からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 治療期間はどのくらいですか?
-
一般的に皮膚の症状は、発疹が現れてから治癒するまで約3週間かかります。抗ウイルス薬は通常7日間服用し、痛みが続く場合は、皮膚症状が治った後も鎮痛薬などの服用が必要になることがあります。
帯状疱疹後神経痛に移行した場合は、治療が数ヶ月から数年に及ぶこともあります。
- 跡は残りますか?
-
多くの場合はきれいに治りますが、症状が重かったり、水ぶくれを潰して細菌感染を起こしたりすると、傷跡や色素沈着が残ることがあります。
特に顔面に発症した場合などは、跡が残りやすいため、早期治療と適切な患部ケアが重要です。跡が気になる場合は、皮膚症状が治った後に、色素沈着を改善する治療を行うこともできます。
- 仕事や学校は休むべきですか?
-
痛みが強く、発熱や倦怠感などの全身症状がある場合は、無理せず休養することが望ましいです。
また、水ぼうそうにかかったことのない人が周囲に多い環境(保育園や学校など)で働く場合は、感染予防の観点から、全ての発疹がかさぶたになるまで休むことを検討しましょう。
- 再発することはありますか?
-
帯状疱疹は一度かかると二度とかからないと思われがちですが、再発することもあります。再発率は数パーセント程度とされていますが、免疫力が著しく低下している方は再発しやすい傾向があります。
日頃からバランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、免疫力を高く保つことが、再発予防につながり、また、50歳以上の方は、帯状疱疹ワクチンを接種することで、発症や重症化を予防することが可能です。
以上
参考文献
Toyama N, Shiraki K, Members of the Society of the Miyazaki Prefecture Dermatologists. Epidemiology of herpes zoster and its relationship to varicella in Japan: a 10‐year survey of 48,388 herpes zoster cases in Miyazaki prefecture. Journal of medical virology. 2009 Dec;81(12):2053-8.
Takao Y, Miyazaki Y, Onishi F, Kumihashi H, Gomi Y, Ishikawa T, Okuno Y, Mori Y, Asada H, Yamanishi K, Iso H. The Shozu Herpes Zoster (SHEZ) study: rationale, design, and description of a prospective cohort study. Journal of epidemiology. 2012 Mar 5;22(2):167-74.
Kawahira K, Imano H, Yamada K, Mori Y, Asada H, Okuno Y, Yamanishi K, Iso H. Risk of herpes zoster according to past history in the general population: The Japanese Shozu herpes zoster study. The Journal of Dermatology. 2023 Sep;50(9):1140-4.
Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports. 2008 Jun 6;57(5):1-30.
Kitaya S, Iyobe R, Kanamori H. Disseminated Herpes Zoster in an Immunocompromised Patient: Challenges for Preventing Transmission Before Diagnosis. The American Journal of Medicine. 2025 Feb 1;138(2):e9-10.
Yoshida M, Hayasaka S, Yamada T, Yanagisawa S, Hayasaka Y, Nakamura N, Mihara M. Ocular findings in Japanese patients with varicella-zoster virus infection. Ophthalmologica. 2005 Oct 1;219(5):272-5.
Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J, Gnann JW, Levin MJ, Backonja M, Betts RF, Gershon AA, Haanpää ML, McKendrick MW, Nurmikko TJ. Recommendations for the management of herpes zoster. Clinical infectious diseases. 2007 Jan 1;44(Supplement_1):S1-26.
Weber DJ, Rutala WA, Hamilton H. Prevention and control of varicella-zoster infections in healthcare facilities. Infection Control & Hospital Epidemiology. 1996 Oct;17(10):694-705.
Suzuki K, Yoshikawa T, Ihira M, Ohashi M, Suga S, Asano Y. Spread of varicella‐zoster virus DNA to the environment from varicella patients who were treated with oral acyclovir. Pediatrics International. 2003 Aug;45(4):458-60.
Ohfuji S, Ito K, Inoue M, Ishibashi M, Kumashiro H, Hirota Y, Kayano E, Ota N. Safety of live attenuated varicella-zoster vaccine in patients with underlying illnesses compared with healthy adults: a prospective cohort study. BMC Infectious Diseases. 2019 Jan 28;19(1):95.