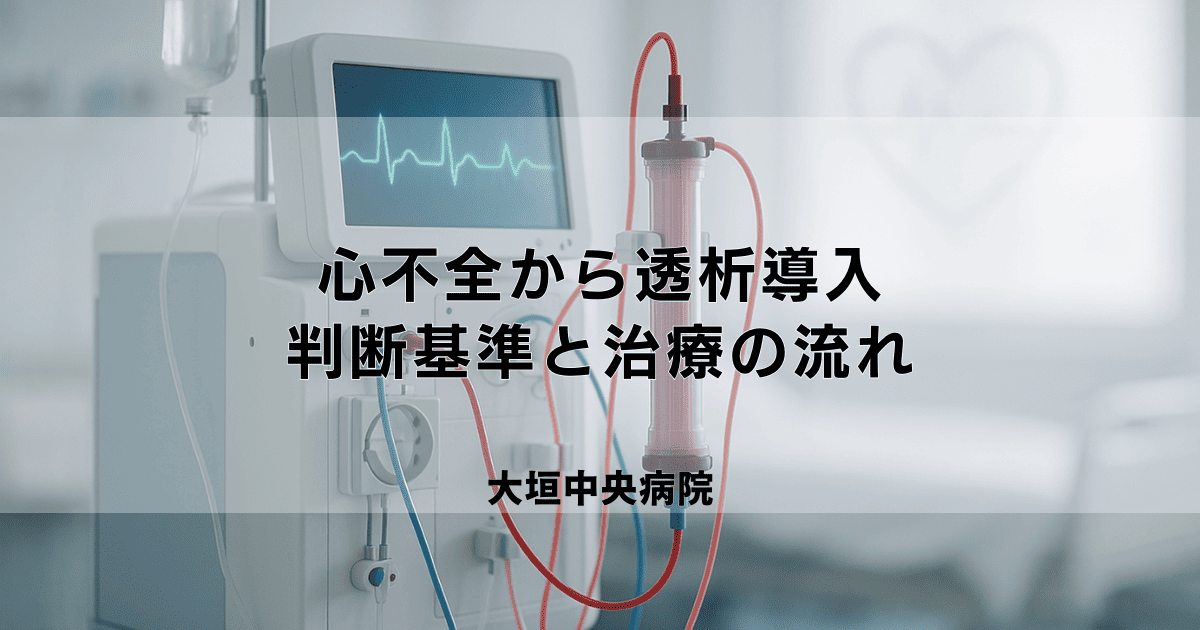心不全と診断され治療を続ける中で、医師から透析という言葉を聞き、不安に感じている方もいるかもしれません。心臓の病気である心不全と腎臓の治療である透析が、なぜ結びつくのでしょうか。
この記事では、心不全の治療過程で透析が必要になるのはどのような場合か、判断基準、そして治療が開始されるまでの流れについて、詳しく解説していきます。
心不全と腎臓の密接な関係
心臓と腎臓は、体の中で互いに連携し合う、いわばパートナーのような存在です。どちらか一方の機能が低下すると、もう一方にも大きな影響が及びます。
この深い結びつきを理解することが、心不全治療における透析の役割を知る上で基本です。
心腎連関とは何か
心臓と腎臓は、一方が悪化すると他方も悪化するという、相互に影響を及ぼし合う関係にあり、この状態を心腎連関と呼びます。
心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を担い、腎臓はその血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄するフィルターの役割を担っています。
ポンプの力が弱まればフィルターに十分な血液が届かず、フィルターが目詰まりすればポンプに負担がかかる、という悪循環に陥ってしまうのです。
心不全が腎機能に与える影響
心不全の状態では、心臓のポンプ機能が低下するため、全身に送り出す血液の量が減少します。
腎臓は、生きるために大量の血液を必要とする臓器であり、心臓から送り出される血液の約4分の1を受け取っているため、心臓からの血流が減ると、腎臓は虚血状態、つまり血液不足に陥り、機能が著しく低下します。
この状態が長く続くと、腎臓の細胞がダメージを受け、腎不全が進行していくことになります。
心機能低下が腎臓に及ぼす主な影響
| 心臓の状態 | 腎臓への影響 | 結果 |
|---|---|---|
| ポンプ機能の低下 | 腎臓への血流量が減少する | 腎臓のろ過機能が低下する |
| うっ血(血液の滞り) | 腎臓の静脈圧が上昇する | 腎臓がむくみ、機能が悪化する |
| 神経・ホルモンの異常 | 腎臓の血管が収縮する | さらなる血流量の低下を招く |
腎機能低下が心臓に与える影響
腎臓の機能が低下すると、心臓にも大きな負担がかかります。腎臓は体内の水分量や塩分(ナトリウム)量を調節する重要な役割を担っていて、腎機能が低下すると、余分な水分や塩分を十分に排泄できなくなり、体液量が過剰になります。
この増えすぎた体液が血液として循環するため、心臓はより多くの血液を送り出さなければならず、ポンプとしての負担が増大するのです。
また、腎臓は血圧を調節するホルモンも分泌しており、機能低下によって高血圧が悪化し、心臓の負担をさらに重くします。
なぜ心不全で透析が必要になるのか
心不全の治療は、薬物療法や生活習慣の改善が中心ですが、病状が進行し、腎臓の機能が極度に低下すると、体の恒常性を維持できなくなります。そのような状況下で、生命を維持するために透析治療が選択肢となります。
治療抵抗性の体液過剰(うっ血)
心不全治療の基本は、利尿薬などを用いて体内に溜まった余分な水分を排泄し、心臓の負担を軽くすることです。
しかし、心不全と腎不全がともに進行すると、腎臓が利尿薬に反応しなくなり、薬をいくら増量しても尿が出にくくなり、この状態を治療抵抗性と呼びます。
行き場を失った水分は、肺に溜まって呼吸困難(肺水腫)を起こしたり、足や顔に強いむくみ(浮腫)として現れたりします。
薬物治療ではコントロールできない体液過剰は、透析によって物理的に水分を取り除くしか方法がなくなります。
体液過剰(うっ血)の進行度と症状
| 進行度 | 主な症状 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 軽度 | 足のすねのむくみ、体重増加 | 靴下の跡がつく、靴がきつい |
| 中等度 | 坂道や階段での息切れ | 少し動くだけで息が上がる |
| 重度 | 横になると咳が出て息苦しい(起坐呼吸) | 眠れない、体を起こしていないと苦しい |
尿毒症(ウレミア)の出現
腎臓は、体内で作られた老廃物を尿として排泄する役割も担っていて、腎機能が著しく低下すると、老廃物、特に尿素窒素(BUN)などが毒素として体内に蓄積し、この状態が尿毒症です。
尿毒症になると、全身に様々な症状が現れ、吐き気や食欲不振、全身の倦怠感、皮膚のかゆみ、集中力の低下などが生じます。重篤になると、意識障害やけいれんを起こすこともあり、生命に危険が及びます。
尿毒症症状は、透析によって毒素を取り除くことで改善が期待できます。
主な尿毒症の症状
- 消化器症状(吐き気、食欲不振、口の中がアンモニア臭い)
- 精神神経症状(頭痛、集中力低下、不眠、意識混濁)
- 皮膚症状(強いかゆみ、色素沈着)
- 全身症状(極度の倦怠感、疲れやすさ)
電解質異常と酸塩基平衡の破綻
腎臓は、カリウムやナトリウムといった電解質のバランスを精密に調節していて、腎不全が末期の状態になると、この調節機能が失われ、特に危険なのが、高カリウム血症です。
血液中のカリウム濃度が異常に高くなると、致死的な不整脈を引き起こし、突然心停止に至る危険性があります。また、体は通常、弱アルカリ性に保たれていますが、腎機能が低下すると酸性物質が体に溜まり、アシドーシスという状態になります。
アシドーシスが進行すると、全身の臓器の働きが悪くなり、意識障害などを引き起こします。このような危険な状態を是正するためにも、透析治療が必要です。
透析導入の判断基準
透析を開始するタイミングは、単一の検査数値だけで決まるものではありません。患者さん自身の症状、血液検査のデータ、そして全身の状態や生活の質を総合的に評価し、医師と患者さん、ご家族が話し合いの上で慎重に決定します。
臨床症状に基づく判断
透析導入を検討する上で最も重視されるのが、患者さんが実際に感じている症状です。特に、尿毒症の症状や、薬物治療でコントロールできない重度の体液過剰(うっ血)は、透析開始の強い適応となります。
息苦しくて夜も眠れない、吐き気がひどくて食事が全く摂れない、体がだるくて起き上がれない、といった症状が生活の質を著しく損なっている場合、透析によって症状を和らげることが治療の目標です。
透析導入を強く検討する臨床症状
| 分類 | 具体的な症状 |
|---|---|
| 体液過剰による症状 | 重度の呼吸困難(肺水腫)、著しい全身のむくみ |
| 尿毒症による症状 | 悪心・嘔吐、高度の食欲不振、意識障害、けいれん |
| 電解質・酸塩基平衡異常 | 薬で改善しない高カリウム血症や重度のアシドーシス |
血液検査データに基づく判断
血液検査のデータも、客観的な判断材料として重要で、腎臓の働きを示す指標であるeGFR(推算糸球体ろ過量)が15 mL/min/1.73m²未満になると末期腎不全と診断され、透析の準備を始める時期とされています。
ただし、数値だけが先行して透析を開始するわけではありません。一般的には、eGFRが10を下回り、尿毒症の症状が出現してきた段階で導入を検討することが多いです。
また、血清クレアチニン値や尿素窒素(BUN)の値、血清カリウム値なども参考にします。
腎機能に関する血液検査の目安
| 検査項目 | 正常値の目安 | 透析導入を検討する値の目安 |
|---|---|---|
| eGFR (mL/min/1.73m²) | 60以上 | 10未満 |
| 血清クレアチニン (mg/dL) | 約1.0未満 | 8.0以上 |
| 血清カリウム (mEq/L) | 3.5~5.0 | 6.0以上(薬で下がらない場合) |
全身状態と生活の質(QOL)の評価
検査データが悪くても、比較的元気に日常生活を送れている方もいれば、データはそれほど悪くなくても、強い倦怠感で動けない方もいます。
食事はどのくらい摂れているか、夜は眠れているか、日中の活動はどの程度可能か、といった全身の状態や生活の質(QOL)を丁寧に評価することが大事です。
透析は、失われた腎臓の機能を代替し、QOLを改善させるための治療で、治療によって患者さんがより良い生活を送れるようになることが、導入を判断する上での大きな目標となります。
総合的な評価の重要性
最終的に透析を導入するかどうかは、これらの臨床症状、検査データ、QOLを総合的に評価して決定し、医師は、透析の必要性、利点、そして合併症などの欠点について十分に説明します。
その上で、患者さん自身の価値観や人生観、ご家族のサポート体制なども考慮に入れ、今後の治療方針を共に考えていく姿勢が重要です。
透析導入までの準備と流れ
透析を開始する方針が決まったら、安全かつ円滑に治療を始めるための準備期間に入ります。通常は入院の上で、心身ともに万全の体制を整えてから、最初の透析に臨みます。
意思決定とインフォームドコンセント
まず、医師や看護師、臨床工学技士、管理栄養士など多職種の医療チームから、透析治療に関する詳しい説明があります。
なぜ透析が必要なのか、血液透析と腹膜透析の違い、治療の具体的な内容、日常生活で注意すべき点、起こりうる合併症などについて、時間をかけてお伝えします。
患者さんやご家族が十分に理解し、納得した上で治療に同意すること(インフォームド-コンセント)が、治療を進める上での大前提です。
シャント造設手術
血液透析を行うためには、1分間に約200mlという大量の血液を体外に取り出し、きれいにしてから体内に戻すことが必要です。
通常の静脈では、この血流量を確保できないため、腕の動脈と静脈を手術でつなぎ合わせ、血流の豊富な太い血管(バスキュラーアクセス)を作成し、これを内シャントと呼びます。
通常は利き腕と反対側の腕の手首付近に、局所麻酔で1〜2時間程度の手術を行います。シャントは作成後、血管が十分に太くなるまで数週間かかるため、透析導入の決定後はなるべく早い段階で手術を計画することが大切です。
シャント作成後の自己管理
- シャント側の腕で重い物を持たない
- シャント側の腕で血圧を測ったり、採血したりしない
- シャント部分をぶつけたり、圧迫したりしない
- 毎日、シャントの血流音(スリル)を確認する
透析導入時の入院管理
多くの場合、初めての透析は入院して行い、シャント手術後、創部が落ち着き、シャントが使用可能になるのを待ってから透析を開始します。
長期間、腎不全の状態にあった体は、急激な環境の変化にうまく対応できないことがあるため、最初のうちは透析の時間や除水量を短く、少なく設定し、血圧の変動や体調の変化を慎重に観察しながら、少しずつ体を慣らしていきます。
この導入期に、食事療法や水分管理についての指導も行います。
透析導入入院の一般的な流れ
| 期間 | 主な内容 |
|---|---|
| 入院初日~数日 | シャント造設手術、術後管理 |
| 術後~約2週間 | シャントの成熟を待つ、栄養指導、リハビリ |
| 入院3週目頃 | 透析開始(短い時間から)、体調管理 |
| 入院4週目頃 | 維持透析の条件設定、退院に向けた準備 |
心不全患者に対する透析治療
心不全を合併している患者さんの透析治療は、心臓への負担を最小限に抑えるため、特に慎重な管理が大事です。血圧の変動や体液量の変化に注意を払いながら、個々の状態に合わせたオーダーメイドの治療を行います。
血液透析(HD)と腹膜透析(PD)
透析療法は、医療機関で週3回行う血液透析(HD)と、自宅で毎日行う腹膜透析(PD)の2種類です。
心機能が著しく低下している場合、血液透析中の急激な除水による血圧低下が心臓に負担をかけることがある一方、腹膜透析は、時間をかけて緩やかに除水を行うため、血圧の変動が少なく、心臓への負担が軽いとされています。
ただし、自己管理が重要であることや、腹膜炎のリスクなどもあり、どちらの治療法を選択するかは、医学的な状態、ライフスタイル、本人の希望などを総合的に勘案して決定します。
血液透析と腹膜透析の比較
| 項目 | 血液透析(HD) | 腹膜透析(PD) |
|---|---|---|
| 場所 | 医療機関 | 自宅 |
| 時間 | 1回4~5時間、週3回 | 1日数回のバッグ交換または夜間自動 |
| 心臓への負担 | 比較的大きい | 比較的小さい |
ドライウェイト(目標体重)の慎重な設定
透析治療では、体内に余分な水分がない、最も安定した状態の体重をドライウェイト(目標体重)として設定します。
透析のたびに、現在の体重からドライウェイトを引いた分だけ水分を除去(除水)し、心不全患者さんの場合、このドライウェイトの設定が非常に重要です。設定が高すぎると、体に水分が残り、心臓の負担(うっ血)が取れません。
低すぎると、脱水になって血圧が下がりすぎ、心臓や他の臓器への血流が不足してしまいます。定期的な胸部レントゲン検査や心エコー検査、心胸郭比などを参考に、常に最適なドライウェイトを探りながら、微調整を繰り返します。
血圧変動への対策
心不全の患者さんは、もともと血圧が低い傾向があったり、降圧薬を内服していたりすることが多く、透析中の除水によってさらに血圧が低下しやすい状態です。
透析中の急激な血圧低下は、心臓に大きな負担をかけるだけでなく、意識を失ったり、シャントが詰まったりする原因にもなります。
防ぐためには、除水速度を緩やかに設定したり、透析時間を長くしたり、透析液の温度を調整したりと、様々な工夫を行います。また、透析前後の血圧の変動を注意深く観察し、降圧薬の飲むタイミングを調整することも重要です。
透析導入後の生活で大事なこと
透析治療の開始は、生活の大きな変化を伴いますが、いくつかのポイントを守ることで、心臓への負担を減らし、安定した生活を送ることが可能です。自己管理が治療の成否を分けると言っても過言ではありません。
厳格な水分と塩分の管理
透析を始めると、尿がほとんど出なくなるため、飲んだ水分は次の透析まで体内に溜まり続け、透析と透析の間の体重増加は、すべて水分の増加によるものです。
体重増加が多いと、血圧が上昇し、心臓に直接的な負担がかかり、また、一回の透析で大量の水分を除去する必要が生じ、血圧低下などのトラブルの原因にもなります。
心不全患者さんの場合、中1日(月→水など)の体重増加はドライウェイトの3%以内、中2日(金→月など)では5%以内が目標です。塩分を摂りすぎると喉が渇き、水分摂取量が増えるため、厳しい塩分制限(1日6g未満)も同時に必要になります。
水分管理の工夫
- 1日に飲む量を決めて、目盛りのついた容器に入れる
- 氷にして少しずつなめる
- うがいをこまめに行う
- 汁物や麺類のつゆは飲まない
食事療法(リン・カリウム制限)
腎不全では、カリウムとリンも体内に蓄積しやすくなります。
高カリウム血症は致死的な不整脈を、高リン血症は骨がもろくなったり、血管の石灰化を進めて動脈硬化を悪化させたりする原因となるため、ミネラルを多く含む食品を制限する食事療法が大事です。
カリウムは生の野菜や果物、いも類に、リンは乳製品や加工食品、魚卵などに多く含まれます。管理栄養士と相談しながら、食べて良いもの、控えるべきものを正しく理解し、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。
透析患者さんはエネルギーを消耗しやすいため、たんぱく質やカロリーは適切に摂取する必要があります。
カリウム・リンを多く含む食品の例
| 栄養素 | 注意が必要な食品 |
|---|---|
| カリウム | バナナ、メロン、ほうれん草、かぼちゃ、いも類 |
| リン | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、レバー、しらす干し、インスタント食品 |
薬物療法との両立
透析導入後も、心不全や高血圧、貧血、ミネラルバランス異常などに対する薬物療法は継続します。
ただし、薬の種類によっては、透析で除去されてしまうものや、腎機能が低下した状態では体に蓄積しやすいものがあるため、薬の量や飲むタイミングの調整が必要です。
特に降圧薬は、透析前に飲むと透析中に血圧が下がりすぎる原因になるため、透析後に内服するなど、医師の指示に従って正しく服用することが大切です。
お薬手帳を活用し、処方されている薬をすべて医療スタッフに把握してもらうことも、安全な治療に繋がります。
よくある質問
心不全による透析治療に関して、患者さんやご家族から寄せられることの多い質問についてお答えします。
- 透析を始めたら心不全は治りますか
-
透析治療は、心不全そのものを治す治療ではありません。あくまで、腎不全によって引き起こされている体液過剰や尿毒症といった状態を改善し、心臓にかかる負担を軽減させるための対症療法です。
透析によって余分な水分が除去され、うっ血が改善することで、心臓の働きが多少改善したり、息切れなどの症状が楽になったりすることは期待できます。
ただし、心不全の原因となっている心臓の病気自体が治癒するわけではないため、心不全に対する薬物療法や生活習慣の管理は、透析開始後も継続して行う必要があります。
- 透析を始めたらどのくらい生きられますか
-
生命予後は、年齢、心不全の重症度、糖尿病や動脈硬化といった合併症の有無、透析導入後の栄養状態や自己管理の状況など、非常に多くの要因によって個人差が大きいため、一概に申し上げることはできません。
適切な透析治療と厳格な自己管理によって、心臓への負担をコントロールし、長期間にわたり安定した生活を送っている患者さんも大勢います。
大切なのは、医療スタッフと協力しながら、日々の体調管理を丁寧に行っていくことです。
予後に影響を与える主な因子
- 年齢
- 心不全の重症度と原因疾患
- 糖尿病などの合併症のコントロール状態
- 透析導入後の栄養状態と自己管理
- 透析をしながら仕事や旅行はできますか
-
血液透析の場合、週3回の通院が必要ですが、それ以外の日は基本的に自由に過ごせます。体力が許せば、透析のない日に仕事に復帰することもでき、多くの患者さんが、治療と仕事を両立させています。また、旅行も可能です。
事前に旅行先の近くで透析を受けられる施設(臨時透析施設)を予約しておくことで、国内はもちろん、海外旅行を楽しむこともできます。生活の質を維持するためにも、積極的に社会参加を続けることはとても重要です。
- 透析を拒否するという選択肢はありますか
-
透析治療を受けるかどうかは、最終的に患者さんご自身の意思で決定するものです。もし、透析を受けないという選択をした場合は、保存的腎臓療法(CKM)という選択肢があります。
これは、透析は行わずに、薬物療法や食事療法を最大限に行い、苦痛な症状を和らげる緩和ケアを中心とした医療に移行していく考え方です。
この選択をする場合は、その後の病状の進行や起こりうることについて、医師から十分な説明を受け、ご家族ともよく話し合うことが大切です。
以上
参考文献
Inaguma D, Koide S, Takahashi K, Hayashi H, Hasegawa M, Yuzawa Y. Relationship between history of coronary heart disease at dialysis initiation and onset of events associated with heart disease: a propensity-matched analysis of a prospective cohort study. BMC nephrology. 2017 Feb 28;18(1):79.
Shimizu Y, Nakata J, Yanagisawa N, Shirotani Y, Fukuzaki H, Nohara N, Suzuki Y. Emergent initiation of dialysis is related to an increase in both mortality and medical costs. Scientific Reports. 2020 Nov 12;10(1):19638.
Watanabe Y, Yamagata K, Nishi S, Hirakata H, Hanafusa N, Saito C, Hattori M, Itami N, Komatsu Y, Kawaguchi Y, Tsuruya K. Japanese society for dialysis therapy clinical guideline for “hemodialysis initiation for maintenance hemodialysis”. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2015 Mar;19:93-107.
Tanaka A, Inaguma D, Shinjo H, Murata M, Takeda A, Aichi Cohort Study of Prognosis in Patients Newly Initiated into Dialysis (AICOPP) Study Group. Presence of atrial fibrillation at the time of dialysis initiation is associated with mortality and cardiovascular events. Nephron. 2016 Feb 4;132(2):86-92.
Yamagata K, Nakai S, Masakane I, Hanafusa N, Iseki K, Tsubakihara Y, Committee of Renal Data Registry of the Japanese Society for Dialysis Therapy. Ideal timing and predialysis nephrology care duration for dialysis initiation: from analysis of Japanese dialysis initiation survey. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2012 Feb;16(1):54-62.
Yamagata K, Nakai S, Iseki K, Tsubakihara Y, Committee of Renal Data Registry of the Japanese Society for Dialysis Therapy. Late Dialysis Start Did Not Affect Long‐Term Outcome in Japanese Dialysis Patients: Long‐Term Prognosis From Japanese Society of Dialysis Therapy Registry. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2012 Apr;16(2):111-20.
Yamada S, Ishii H, Takahashi H, Aoyama T, Morita Y, Kasuga H, Kimura K, Ito Y, Takahashi R, Toriyama T, Yasuda Y. Prognostic value of reduced left ventricular ejection fraction at start of hemodialysis therapy on cardiovascular and all-cause mortality in end-stage renal disease patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2010 Oct 1;5(10):1793-8.
Nakamura S, Nakata H, Yoshihara F, Kamide K, Horio T, Nakahama H, Kawano Y. Effect of early nephrology referral on the initiation of hemodialysis and survival in patients with chronic kidney disease and cardiovascular diseases. Circulation Journal. 2007;71(4):511-6.
Tanaka A, Inaguma D, Shinjo H, Takeda A. Incidence rate of atrial fibrillation after dialysis initiation and its relationship with cardiovascular events. Acta Cardiologica. 2019 Nov 2;74(6):527-35.
Matsubara Y, Kimachi M, Fukuma S, Onishi Y, Fukuhara S. Development of a new risk model for predicting cardiovascular events among hemodialysis patients: Population-based hemodialysis patients from the Japan Dialysis Outcome and Practice Patterns Study (J-DOPPS). PloS one. 2017 Mar 8;12(3):e0173468.