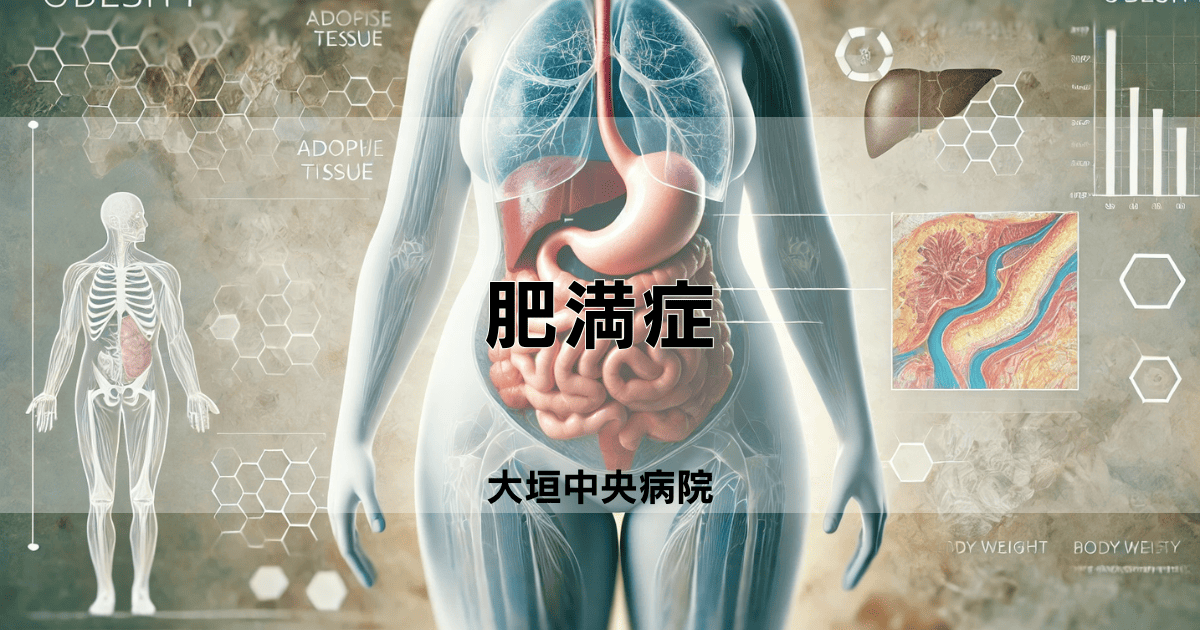肥満症とは、体に過度な脂肪が蓄積し、健康を損なうリスクが高まる状態を指し、体重が増えただけではなく、生活習慣病や運動機能の低下などさまざまな問題を引き起こす可能性がある病態です。
単純に「太っている」こととは異なり、医学的な観点で定義される肥満であり、背景には食習慣や運動量、遺伝的素因など多くの要因が複雑に絡み合っています。
肥満症を放置すると糖尿病や高血圧、脂質異常症といった合併症を併発する危険性が高まり、将来的には心血管疾患や脳卒中など深刻な病気につながることもあるため、早期に正しい知識を得て対策を検討することが大切です。
肥満症の病型
肥満症にはさまざまなタイプがあり、定義や病型の理解は治療方針を考える上で非常に重要です。
内臓脂肪型と皮下脂肪型
肥満症で特に重視されるのが「どこに脂肪が蓄積しているか」という点で、内臓脂肪型肥満は、腹腔内の内臓周辺に脂肪が集中するタイプで、いわゆる「リンゴ型肥満」と呼ばれます。
内臓脂肪は代謝が活発であり、生活習慣病を起こすリスクが高いとされており、血糖値や血圧のコントロールにも影響を与えやすい点が特徴です。
皮下脂肪型肥満は、お尻や太もも、腹部の皮下に脂肪が蓄積するタイプで「洋ナシ型肥満」と呼ばれ、内臓脂肪型と比べると生活習慣病のリスクはやや低いですが、運動器への負担などが大きくなります。
内臓脂肪型と皮下脂肪型の特徴
| 分類 | 脂肪の蓄積部位 | 代表的な見た目 | 生活習慣病リスク |
|---|---|---|---|
| 内臓脂肪型 | 腹腔内の内臓周辺 | 腹部が前方に突き出す | 高い |
| 皮下脂肪型 | 皮下組織(下腹部、臀部) | 下半身が大きく見える | やや低い |
原因別の分類
肥満症は、原因別に以下のように分類する考え方もあります。
- 摂取エネルギー過多による一次性肥満
- ホルモン異常や遺伝子疾患などによる二次性肥満
一次性肥満は、日常生活で消費エネルギーを大きく上回る食事量や栄養バランスの乱れ、運動不足が積み重なることで脂肪が過度に蓄積したタイプです。
二次性肥満は、甲状腺機能低下症やクッシング症候群といった内分泌疾患や特定の薬剤が原因で体重増加が促されるケースが該当し、根本原因の治療や対処が必要になります。
BMIによる病型の目安
肥満症かどうかを判定する指標の1つにBMI(Body Mass Index)があり、BMIは体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))で算出され、25以上が肥満と判定されることが多いです。
ただし、BMIのみでは内臓脂肪型と皮下脂肪型の判別はできないため、腹囲測定や体組成計での評価があわせて行います。
BMIの区分と肥満度の目安
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
合併症の有無での区別
合併症の有無も肥満症の病型を語る上で重要で、肥満症に伴う代表的な合併症には、高血圧、脂質異常症、糖尿病などがあります。
同時に複数存在するとメタボリックシンドロームの状態となり、心血管系のリスクがさらに高まり、合併症を抱える場合は、肥満そのものの改善だけでなく、合併症の管理を同時に進める治療戦略が必要です。
- 高血圧合併: 血圧コントロールが不安定になりやすい
- 糖尿病合併: 血糖値の上昇やインスリン抵抗性が進行
- 脂質異常症合併: LDLコレステロールの増加、HDLコレステロールの低下など
症状
肥満症は体重の増加や体形の変化だけにとどまらず、さまざまな症状を伴います。
生活習慣病の発症・悪化
肥満症になると、体内の脂肪細胞から炎症を促進する物質が放出されやすくなり、血糖値や血圧、脂質プロファイルに影響を与え、生活習慣病が発症しやすくなったり、すでに存在している場合には悪化するリスクがあります。
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症
肥満状態が続くことで生活習慣病リスクが高まる例
| 生活習慣病 | 肥満との関連 |
|---|---|
| 高血圧 | 血管抵抗が増え、血圧が上昇しやすい |
| 糖尿病 | インスリン抵抗性が進行して血糖値が上昇 |
| 脂質異常症 | LDLコレステロールや中性脂肪が増加 |
関節や骨への負担
体重増加は下半身や腰への負荷を大きくし、膝関節痛や腰痛を引き起こす一因で、また、長期にわたって体重が増えた状態が続くと運動機能の低下や変形性関節症などにつながり、歩行困難や日常生活の質が低下するケースも少なくありません。
- 膝や腰の痛み
- 変形性関節症
- バランス能力の低下
睡眠呼吸障害
肥満症の方に見られる特徴的な症状として、いびきや睡眠時無呼吸症候群があり、喉周辺に脂肪がつきやすくなることで気道が狭くなり、睡眠中に呼吸が一時的に止まることで十分な休息がとれなくなる状態です。
睡眠時無呼吸症候群が続くと、日中の眠気や集中力の低下、心臓や血管への負担が増大して高血圧や心不全のリスクを高めます。
肥満症と睡眠障害の関連
| 症状 | 影響 |
|---|---|
| いびき | 気道狭窄により音が発生 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 無呼吸や低呼吸が繰り返され、血中酸素が低下する |
肥満症の原因
肥満症の原因は、食事の過剰摂取や運動不足だけでなく、遺伝やホルモンバランス、心理的要素など多面的に影響し合って発症することが多いです。
エネルギー摂取と消費の不均衡
肥満症の最も基本的な要因は、摂取エネルギー が消費エネルギーが上回る状態が長く続くことです。
高カロリーな食事や間食の頻度増加、炭水化物や脂肪分の過剰摂取によって摂取エネルギーが増え、同時に運動不足やデスクワークの増加により消費エネルギーが減れば、必然的に余剰エネルギーが脂肪として蓄えられます。
リストでエネルギー摂取を増やす原因例
- ジャンクフードや甘い飲料の多量摂取
- 不規則な食事パターン
- 夜食や深夜の間食
遺伝や家族性
肥満症の発症には遺伝的要素が介在している場合があり、両親や祖父母が肥満傾向にある家庭では、体質的に脂肪が蓄積しやすい可能性があり、幼少期からの食生活やライフスタイルの影響も相まって肥満が進みやすくなります。
特定の遺伝子異常が肥満に関与しているケースも報告されており、こうした場合は根本的な体質改善を行うことが難しく、長期的な管理が求められることが多いです。
肥満症と遺伝の関連性
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 家族性肥満 | 親や兄弟など血縁関係に肥満者が多い |
| 遺伝子異常 | 遺伝子レベルでエネルギー代謝に影響がある場合 |
ホルモン・内分泌の異常
甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモン、インスリンなど、体重や代謝をコントロールするホルモンが異常に分泌されると、脂肪の蓄積が進んだり、食欲が制御しにくくなったりします。
クッシング症候群や甲状腺機能低下症、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)などの内分泌疾患が原因で肥満症になることもあり、二次性肥満の代表的な例です。
- クッシング症候群: コルチゾール過剰で脂肪蓄積
- 甲状腺機能低下症: 代謝低下で体重増加
- PCOS: インスリン抵抗性の進行による肥満
精神的ストレスや心理的要因
過度なストレス状態にあると、食欲を抑制するホルモンの働きが鈍くなる、あるいは甘いものや脂っこいものを摂取すると一時的に気分がよくなる反応が強まり、「ストレス過食」によって摂取カロリーが増え、肥満が進行することが少なくありません。
また、うつ状態や不安障害などの精神疾患があると、生活習慣を律することが難しくなることも関係しています。
- ストレス過食
- 不安障害やうつ状態
- 食行動のコントロール困難
肥満症の検査・チェック方法
肥満症の診断や治療方針を立てるには、身体測定や血液検査、画像検査など、多角的なチェックが重要です。
身体測定・腹囲測定
まずは体重や身長、腹囲、ウエストヒップ比などを測定し、BMIや内臓脂肪型かどうかの目安を確認し、単に体重だけでなく、体組成計で体脂肪率や筋肉量を把握することで、肥満の質をより正確に評価できます。
身体測定で把握する代表的な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 体重 | 体全体の重さ |
| 身長 | BMI算出の基礎 |
| 腹囲 | ウエスト周囲長。内臓脂肪型かどうか判断の目安 |
| 体脂肪率 | 体重に占める脂肪の割合を示す |
血液検査
肥満症に合併しやすい生活習慣病やホルモン異常の有無を調べるために、血糖値やHbA1c、脂質プロファイル(LDL、HDL、トリグリセリドなど)、肝機能(ALT、AST、γ-GTPなど)、甲状腺ホルモンや副腎ホルモンなどをチェックします。
肥満の原因や合併症の程度を判断し、適切な治療計画を立案するうえでも欠かせないデータです。
リストで血液検査のチェック項目
- 空腹時血糖値、HbA1c
- LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
- ALT、AST、γ-GTP(肝機能)
- TSH、Free T4(甲状腺機能)
- ACTH、コルチゾール(副腎機能)
画像検査(腹部CT・MRIなど)
肥満症の場合、内臓脂肪の蓄積状態をより正確に把握するために腹部CTやMRIを行うことがあり、内臓脂肪面積を計測し、皮下脂肪と内臓脂肪の比率を数値化することで、どの程度内臓に脂肪がたまっているのかを客観的に評価できます。
また、肝臓に脂肪がたまる脂肪肝の有無や重症度の判断、他の臓器の状態把握にも役立ちます。
主な画像検査の目的
| 検査方法 | 主な目的 |
|---|---|
| 腹部CT | 内臓脂肪量や脂肪肝の状態を可視化 |
| MRI | 軟部組織の描出に優れ、詳細な脂肪分布がわかる |
心電図・エコー検査
肥満症の方は心血管系への負担が増すため、心電図検査や心エコー検査を行って、心臓の肥大や不整脈、弁膜症などの有無を確認する場合があります。
脂肪組織が増えると循環器系への負荷が高まり、高血圧や心不全などのリスクが上がるため、早期の段階で心臓の状態をチェックすることは大切です。
- 心電図: 不整脈や左室肥大の兆候
- 心エコー: 弁の動き、心室壁の厚みなど
治療方法と治療薬について
肥満症の治療はライフスタイルの改善を基本としながら、必要に応じて薬物療法や外科的治療を組み合わせる形で進められます。
食事療法と運動療法
肥満症の治療で最も基礎となるのが、食事内容の見直しと運動の習慣化です。
カロリー制限や栄養バランスの調整、炭水化物や脂質の摂取量を管理することで摂取エネルギーをコントロールし、有酸素運動や筋力トレーニングを組み合わせて消費エネルギーを増やすことで体脂肪の減少を促します。
取り組み例
- 高エネルギー食品を減らし、野菜やタンパク質を中心に食事を組み立てる
- ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を週3~4回実施する
- スクワットやプランクなど筋力トレーニングも取り入れ、基礎代謝を上げる
薬物療法
ライフスタイル改善だけでは効果が十分に得られない場合、肥満症治療薬を使用する選択肢があり、医師の判断に基づき処方され、食欲を抑制したり、脂肪吸収を抑制したりすることで、体重の減少をサポートします。
肥満症治療薬の例と作用機序
| 薬剤名 | 主な作用機序 | 特徴 |
|---|---|---|
| 食欲抑制薬 | 中枢神経に働きかけて食欲を抑える | 食事量を減らす効果が期待できる |
| 脂肪吸収抑制薬 | 消化管での脂肪分解・吸収を抑える | 摂取脂肪のカロリー吸収を減らす |
外科的治療(減量手術)
高度肥満(BMI35以上など)で、深刻な合併症を抱えている場合には、外科的治療の検討がなされることがあり、胃の容積を小さくするスリーブ状胃切除術や胃バイパス術などで食べられる量を物理的に制限し、体重の大幅な減少を目指す方法です。
代表的な減量手術の種類
| 手術名 | 主な方法 |
|---|---|
| スリーブ状胃切除術 | 胃の大部分を切除して細長い管状にする |
| 胃バイパス術 | 胃を小さく切除し、腸の一部をバイパスする |
肥満症の治療期間
肥満症は短期間での劇的な体重減少を目指すのではなく、長期的に体重コントロールを行い、合併症リスクを下げながら健康的な体づくりを続ける必要があります。
治療初期から中期
治療開始後数か月間は、食事や運動、薬物療法などの変更が大きく、体重や体調の変化が見えやすい時期で体重、が急激に減る方もいますが、その後減量ペースが鈍化する「停滞期」が訪れるケースが多いため、継続的な対策が肝要となります。
急激な体重減少はリバウンドのリスクを高める場合があるため、医師や管理栄養士と相談しながら適正ペースで減量することが必要です。
減量の目安
| 期間 | 目標体重減少率 |
|---|---|
| 3か月程度 | 体重の5~10%減少 |
| 6か月~1年 | 体重の10~15%減少 |
長期維持期
目標とする体重や体脂肪率に近づいてきたら、体重を長期的に維持するための戦略を強化し、食事制限や運動習慣を緩めすぎるとリバウンドが起こりやすくなるため、定期的な受診や栄養指導を続けることが大切です。
多くの方がこの維持期で気を抜き、体重が再び増加する「リバウンド」を経験するため、心理面や生活習慣のサポートが重視されます。
維持期のポイント
- 定期的に体重や腹囲を測り変化を数値化
- 運動メニューの見直しを行い適度に負荷を変化
- 外食や間食の頻度をチェックして適正化
外科的治療後のフォローアップ
減量手術を行った場合、術後に急激な体重減少や栄養失調が起こることがあり、ビタミンやミネラルを補充しながら定期チェックを受けることが欠かせません。
また、術後数年経過すると胃や腸の形状変化に体が慣れ、再度体重が増え始めるリバウンドも起こりえるので、手術後も根気強いライフスタイル管理が大切です。
| 手術後の期間 | 主なチェック内容 |
|---|---|
| 術後~数か月 | 栄養状態の確認、消化能力の評価 |
| 数年後 | 体重の維持状況、ビタミン・ミネラル欠乏の有無 |
肥満症薬の副作用や治療のデメリットについて
肥満症治療薬は効果的な手段になりえますが、一方で副作用やデメリットがあるため、利用の際には注意が必要です。
食欲抑制薬の副作用
中枢神経に作用して食欲を抑えるタイプの薬では、いくつかの副作用が生じることがあります。
- 頭痛、めまい
- 口の渇き
- 不眠や神経過敏
- 動悸や血圧上昇
食欲抑制薬の主な副作用
| 副作用 | 内容 |
|---|---|
| 中枢神経症状 | めまい、神経過敏、不眠など |
| 循環器症状 | 血圧の変動、動悸、不整脈など |
脂肪吸収抑制薬の副作用
消化管での脂肪分解を抑制する薬は、摂取した脂肪分が未消化のまま排泄されるため、脂肪の過剰摂取時には腹痛や軟便、脂肪便などの消化器症状を伴うことがあります。
また、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、Kなど)の吸収障害が起こりやすい点にも注意が必要で、医師や管理栄養士の指示に従ってバランスの良い食事を考慮します。
- 消化器症状(腹痛、下痢、脂肪便)
- 脂溶性ビタミン吸収阻害
リバウンドのリスク
薬物療法だけに頼ると、治療薬を中止した後に再び食欲や脂肪吸収が元に戻りやすく、短期間で体重が増えてしまう「リバウンド」のリスクが高くなる可能性があります。
特に食事療法や運動療法との併用を怠っていると、薬の効果が切れた段階で体重や体脂肪が急速に元の状態に戻ってしまうことが少なくありません。
リバウンドリスクを抑える工夫
- 薬服用中から適切な食事習慣を身につける
- 運動習慣の確立で基礎代謝を高める
- 治療終了後も定期的な体重測定を続ける
肥満症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
検査費用
肥満症の診断や合併症の確認に際しては、血液検査や画像検査、ホルモン検査などが行われます。
| 検査項目 | 保険適用後の実費目安(3割負担) |
|---|---|
| 血液検査(基本項目) | 1,000~2,000円程度 |
| 甲状腺ホルモン検査 | 1,000~2,000円程度 |
| 腹部CT | 4,000~7,000円程度 |
| 腹部MRI | 5,000~9,000円程度 |
治療薬の費用
肥満症治療薬は健康保険でカバーされるものもあり、1か月あたりの自己負担額は薬の種類や処方量によって差があります。
- 食欲抑制薬: 1か月分で3,000~5,000円程度
- 脂肪吸収抑制薬: 1か月分で5,000~8,000円程度
外科的治療にかかる費用
胃縮小術など一部の減量手術は保険対象となるケースがあり、合併症の有無なども考慮して保険適用の可否が判断されます。
| 手術名 | 保険適用後の目安費用(自己負担3割) |
|---|---|
| スリーブ状胃切除術 | 10万~20万円程度 |
| 胃バイパス術 | 15万~30万円程度 |
以上
参考文献
Kanazawa M, Yoshiike N, Osaka T, Numba Y, Zimmet P, Inoue S. Criteria and classification of obesity in Japan and Asia-Oceania. Nutrition and fitness: obesity, the metabolic syndrome, cardiovascular disease, and cancer. 2005;94:1-2.
McCurry J. Japan battles with obesity. The Lancet. 2007 Feb 10;369(9560):451-2.
Yoshiike N, Kaneda F, Takimoto H. Epidemiology of obesity and public health strategies for its control in Japan. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2002 Dec;11:S727-31.
Examination Committee of Criteria for’Obesity Disease’in Japan. New criteria for’obesity disease’in Japan. Circulation journal: official journal of the Japanese Circulation Society. 2002 Nov;66(11):987-92.
Kubo T. Common approach to childhood obesity in Japan. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2014 Jul 1;27(7-8):581-92.
Kanazawa M, Yoshiike N, Osaka T, Numba Y, Zimmet P, Inoue S. Criteria and classification of obesity in Japan and Asia‐Oceania. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2002 Dec;11:S732-7.
Tanaka H, Kokubo Y. Epidemiology of obesity in Japan. Japan Med Assoc J. 2005 May 4;48(1):34-41.
Kuriyama S, Tsubono Y, Hozawa A, Shimazu T, Suzuki Y, Koizumi Y, Suzuki Y, Ohmori K, Nishino Y, Tsuji I. Obesity and risk of cancer in Japan. International journal of cancer. 2005 Jan 1;113(1):148-57.
Nishi N. Monitoring obesity trends in health Japan 21. Journal of nutritional science and vitaminology. 2015;61(Supplement):S17-9.
Sone H, Ito H, Ohashi Y, Akanuma Y, Yamada N. Obesity and type 2 diabetes in Japanese patients. The Lancet. 2003 Jan 4;361(9351):85.