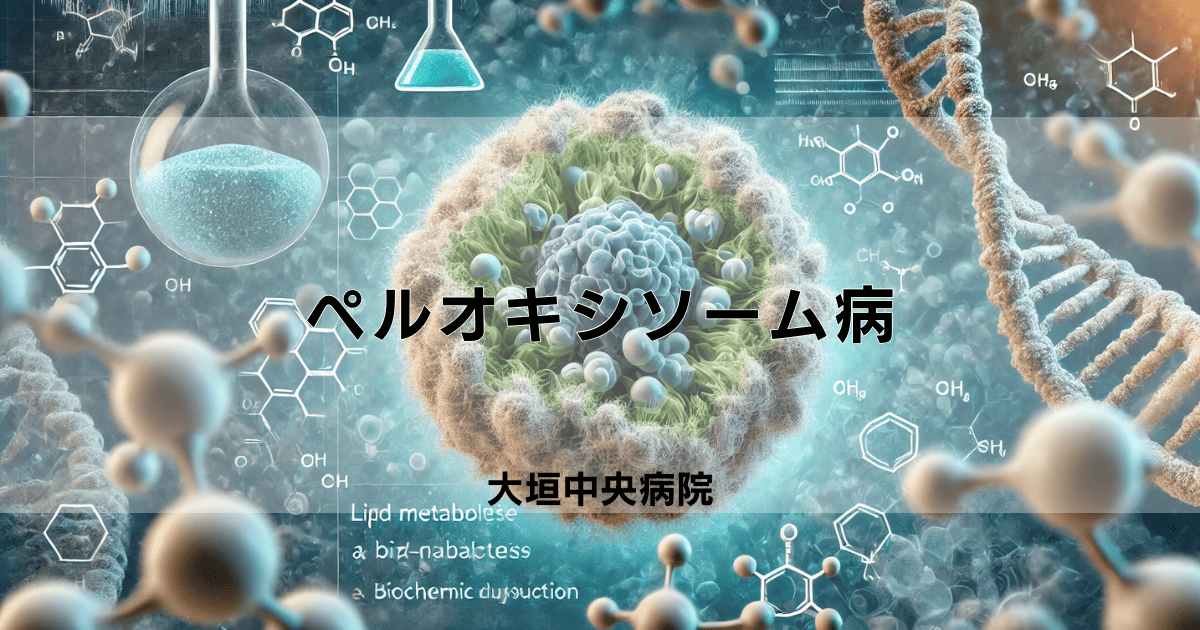ペルオキシソーム病とは、遺伝子の変異によって細胞内にあるペルオキシソームの機能が低下または失われることで、神経・肝臓・腎臓などに多彩な症状が現れる疾患群です。
症状の強さや現れ方は人によって異なり、早期発見と治療の検討が重要で、遺伝性の要素が絡むため、家族の中に同様の症状をもつ人がいる場合には特に注意が必要になります。
まれな疾患のひとつですが、進行性の合併症を招くケースもあり、正確な情報を得ておくことが大切です。
病型
ペルオキシソーム病はいくつかの病型に分かれ、それぞれで特徴的な症状や進行速度の違いがみられ、分類を知っておくと、自分や家族の状態に合った治療法を考えるうえで指針になりやすいです。
総合的な分類の概要
ペルオキシソーム病は、大きく分けると「ペルオキシソームの生合成そのものに異常があるもの」と「特定の酵素がうまく働かないもの」に分類できます。
前者の場合、ペルオキシソームが細胞内で十分に形成されず、代謝に関連する多くの機能が同時に損なわれ、後者は主に1種類または少数の酵素だけが欠損するため、影響範囲は比較的限定的ですが身体各所でさまざまな症状が起こります。
どちらも遺伝的な要因が深く関わっていますが、発症年齢や症状の程度には個人差があります。
| 分類 | 主な特徴 | 代表例 |
|---|---|---|
| 生合成異常型 | ペルオキシソーム自体の形成に障害があり、多彩な症状が出やすい | ゼルウェガー症候群(Zellweger syndrome)など |
| 酵素欠損型 | ある特定の酵素のみが欠損し、それに対応した代謝異常が強く出る | 副腎白質ジストロフィー(ALD)など |
多くの専門家は、個々の疾患の分類だけでなく、患者さんの年齢や合併症状の有無にも注目して総合的に評価し、より的確に治療計画を立てることが重要です。
全般性ペルオキシソーム生合成異常
全般性のペルオキシソーム生合成異常は、ペルオキシソームをつくるために必要な複数の遺伝子が変異しており、代表的なのがゼルウェガー症候群で、新生児期や乳児期の早い段階から重篤な症状が現れます。
脳や肝臓、腎臓などに深刻な障害が及ぶため、日常生活でのケアが難しくなることが多いです。重度になると、発育の遅れ、筋肉の緊張異常、けいれん発作、視力や聴力の低下などが組み合わさって顕著に表れます。
- 低緊張や筋力低下
- けいれん発作や意識レベルの低下
- 肝機能障害や胆汁うっ滞
- 成長不良や頭蓋顔面の奇形
生合成異常型は多彩な症状が一度に起こりやすく、経過観察やケアが欠かせないことから、医療チームと連携を密にすることが大切です。
部分的ペルオキシソーム酵素欠損症
部分的ペルオキシソーム酵素欠損症は、ペルオキシソーム自体は形成されていても、特定の酵素や輸送体タンパク質が正常に働かないタイプです。
代表例として副腎白質ジストロフィー(ALD)やレフサム病などが挙げられ、これらは血中や組織内に異常な脂肪酸が蓄積することで様々な神経症状を起こします。
身体機能が徐々に低下しながら、日常生活の制限が広がっていくため、早めの診断と対処が重要です。
部分的酵素欠損症の場合、脳神経系だけでなく、筋肉や網膜にも異常が出るケースがあり、症状は時間をかけて進行することが多いので、定期的な検査を受けながら経過をみる必要があります。
子どもの頃に見られるケースと成人になってから進行が明らかになるケースがあり、発症年齢が異なると治療計画や日常のケアの内容も変わってきます。
病型による進行速度の差
同じペルオキシソーム病でも、病型によって進行速度には大きな違いがみられます。
生合成異常型は重症化しやすく、乳幼児期から多臓器に深刻な影響をもたらし、部分的酵素欠損症は、乳幼児期に発覚するタイプもあれば、思春期から成人期にかけて緩やかに進行するタイプも含まれます。
疾患ごとに特徴が異なるため、あらかじめ病型の性質を知ることが大切です。
ペルオキシソーム病における発症時期と進行速度
| 疾患名 | 発症時期 | 進行速度 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| ゼルウェガー症候群 | 新生児期〜乳児期早期 | 速い | 重度の多臓器障害 |
| 副腎白質ジストロフィー | 幼児期〜成人期 | やや緩やか〜中程度 | 中枢神経・副腎機能障害が中心 |
| レフサム病 | 思春期〜成人期 | 緩やか | 網膜変性や多発性ニューロパチー |
ペルオキシソーム病の症状
ペルオキシソーム病の症状は多岐にわたり、中枢神経系や肝臓・腎臓などの臓器に影響が及ぶだけでなく、骨格や筋肉に不調がみられることもあります。
重症度や症状の出方は人それぞれで、乳幼児期に顕著に表れるケースもあれば、成人になって初めて日常生活に支障を感じるケースもあります。
中枢神経系への影響
中枢神経系に異常が生じると、脳の発達遅延やけいれん発作、知的発達障害などがみられる可能性があり、副腎白質ジストロフィーでは、白質と呼ばれる脳の部分に障害が起こり、認知機能の低下や視覚・聴覚の異常などへつながります。
発作が起きやすくなることで日常生活が制限される場合もあるため、治療だけでなくリハビリテーションや生活支援も含めた包括的な対策が欠かせません。
中枢神経系が受ける影響の例
- けいれん発作
- 視力・聴力の低下
- 行動面や学習面での困難
- 運動発達の遅延
こうした症状は早期の段階では気づきにくいこともあるため、小さい頃からの健康診断や育児中の観察が大切です。
肝臓・腎臓の症状
ペルオキシソーム病では、肝臓や腎臓にも障害が生じることがあり、胆汁うっ滞や肝機能障害、腎機能の低下などが問題になり、肝機能が低下すると、黄疸や貧血、全身の倦怠感が目立つようになり、日常生活に大きく影響します。
腎機能が下がると、体内の老廃物の排泄がうまくいかなくなり、高血圧や電解質バランスの乱れを起こすリスクが高まります。
肝臓・腎臓に生じる典型的な症状と影響
| 臓器 | 典型的な症状 | 影響 |
|---|---|---|
| 肝臓 | 胆汁うっ滞、黄疸、肝硬変など | 消化不良、全身倦怠感、貧血など |
| 腎臓 | 電解質異常、血圧上昇など | むくみ、疲労感、体液バランスの乱れなど |
症状は、初期段階では軽度な不調程度かもしれませんが、時間を経ると合併症のリスクが増すことがあるので、異常を感じたら早めに受診し、必要に応じた検査を受けることが重要です。
骨格や筋肉の症状
骨格や筋肉にも影響が及ぶことがあり、骨格の形成不全がある場合、関節の可動域が狭まったり、脊椎の変形などが進んだりするケースがあります。
筋肉への影響としては、筋力低下や筋緊張の異常がみられ、歩行や姿勢保持に支障が出る可能性があり、乳幼児期に重度の骨格や筋肉の症状が出ると、離床やリハビリテーションが難しくなるため、早めの対処が大切です。
骨格や筋肉への症状は中枢神経系からの指令異常とも相互に影響し合い、けいれん発作が頻繁に起こる場合は筋疲労や骨格への負担も増えるため、症状の複合的な把握が不可欠です。
乳幼児期と成人期の症状の違い
ペルオキシソーム病の一部は生まれてまもない時期から顕著に症状が現れ重篤化しやすく、ゼルウェガー症候群などの重症型では、呼吸困難や筋力低下、けいれんなどが新生児期から見られることが多いです。
一方、副腎白質ジストロフィーやレフサム病などでは、思春期や成人期に発症するケースもあり、進行がゆるやかなぶん気づくのが遅れる場合があります。
成人期に出現する症状としては、視覚や聴覚の障害、筋力低下、慢性的な肝機能異常などが挙げられます。
子どもの頃に見落とされがちな軽度の症状(成長の遅れ、軽い難聴など)でも、成人になってから進行が急に早まることがあります。
年齢によって身体の代謝状態やホルモンバランスも変わりやすいため、定期的なチェックを継続することが重要です。
年齢による症状
- 乳幼児期:呼吸困難、けいれん、高度な筋力低下など
- 幼児期〜学童期:発達の遅れ、学習面の遅れ、視力低下など
- 思春期〜成人期:運動機能の低下、認知機能障害、内臓機能の悪化など
自分や家族がどの時期に発症リスクが高いかを知り、継続的に体調の変化を観察することが大切です。
原因
ペルオキシソーム病は、遺伝子変異によって引き起こされる代謝障害の一種で、ペルオキシソームという小器官が正常に働かなくなることで、体内での長鎖脂肪酸の分解や過酸化水素の処理など、さまざまな生化学反応に問題が起こります。
遺伝子変異のメカニズム
ペルオキシソーム病の根本原因は、遺伝子変異です。
ペルオキシソームを形成・維持するための遺伝子や、ペルオキシソーム内で機能する酵素をコードする遺伝子に変異が生じると、正常なペルオキシソームが生成されなかったり、特定の酵素が働かなかったりします。
このため、脂肪酸分解などの重要な代謝経路で代謝産物が蓄積し、細胞に毒性を及ぼしたり、全身に悪影響が広がったりします。
ペルオキシソーム病に関わる主な遺伝子
| 遺伝子名 | 主な機能 | 関連疾患例 |
|---|---|---|
| ABCD1 | 長鎖脂肪酸の輸送 | 副腎白質ジストロフィー |
| PEX遺伝子群 | ペルオキシソーム生合成に関わる複合体 | ゼルウェガー症候群、その他PEX関連疾患 |
| PHYH | フィタン酸の酸化 | レフサム病 |
遺伝子変異を起こす要因はさまざまですが、多くの場合は生まれつき両親から受け継ぐ形で起こされ、変異が起きている遺伝子がどのタイプかによって、具体的な病名や病態が異なります。
ペルオキシソーム機能不全の流れ
遺伝子変異があると、まずペルオキシソームの構造的・機能的な異常が生じ、ペルオキシソームが本来担っている「脂肪酸分解」「過酸化水素の分解」などが正常に進まず、体内に有害な物質が蓄積したり、エネルギー生成が滞ったりします。
そういった代謝の乱れが、やがて神経系や肝臓、腎臓などのさまざまな組織・臓器にダメージを与え、複数の症状が表れます。
脂肪酸代謝の異常によって特定の代謝産物が増えると、その産物を分解できない細胞は機能不全に陥りやすいです。
また、過酸化水素を十分に除去できない場合、酸化ストレスによって細胞膜やタンパク質、遺伝子へも悪影響が及ぶことが考えられます。
常染色体劣性遺伝とX連鎖性遺伝
ペルオキシソーム病は、常染色体劣性遺伝の形式をとるものとX連鎖性遺伝の形式をとるものがあります。
常染色体劣性遺伝の例としてはゼルウェガー症候群やレフサム病などが挙げられ、両親双方が変異遺伝子を保有している場合に子どもが発症リスクをもちます。
一方、副腎白質ジストロフィーはX連鎖性遺伝に分類され、男性に発症しやすい特徴がありますが、女性でも保因者として遺伝子変異を受け継ぐケースがあります。
代表的な遺伝様式の特徴
- 常染色体劣性遺伝:男女問わず発症の可能性があり、親ともに変異遺伝子をもっている場合に子どもが発症する可能性が高くなる。
- X連鎖性遺伝:X染色体上の遺伝子に変異があるため、男性のほうが病気を発症しやすい。女性は保因者として遺伝子を受け継ぎ、症状が軽度にとどまるケースもある。
家族性発症のリスク
ペルオキシソーム病は遺伝性をもつため、家族内で同じ疾患が複数みられる可能性があります。
常染色体劣性遺伝の場合、両親が保因者でも表面的には健康であるケースがあるため、最初の子どもが発症したときにはじめて家系内のリスクが判明することもあります。
こうした状況では、次の子どもにも同じリスクが潜在的に存在するため、詳細な遺伝子検査やカウンセリングが望ましいです。
また、X連鎖性遺伝の場合は娘に遺伝子が受け継がれ、次の世代で男児が生まれたときに発症リスクが高まるといったパターンも考えられます。
親戚にペルオキシソーム病の患者がいる場合は、将来的に子どもをもつ際に遺伝リスクについて医師と相談することが重要です。
ペルオキシソーム病の検査・チェック方法
ペルオキシソーム病を疑った場合、症状の出かたや家族歴などを考慮した上で、血液検査や画像検査、遺伝子検査などを組み合わせて総合的に診断を進め、病型や進行度を評価していきます。
血液検査と脂肪酸測定
ペルオキシソーム病の疑いがあるとき、最初の段階で行うことが多いのが血液検査です。特に長鎖脂肪酸やフィタン酸など、ペルオキシソームによる分解を必要とする脂肪酸の血中濃度を測定すると、過剰に蓄積しているかどうかを調べられます。
血液検査の結果をみることで、ペルオキシソーム病を高い確率で示唆できる場合があり、具体的な病型を推定する材料になります。
血液検査で注目する主な項目
| 検査項目 | 意義 |
|---|---|
| VLCFA(超長鎖脂肪酸) | 副腎白質ジストロフィーなどで上昇がみられやすい |
| フィタン酸 | レフサム病の診断補助になる |
| プラズマローゲン | ゼルウェガー症候群などで減少がみられることがある |
血液検査だけでは確定診断には至らないことが多いですが、疑いを強くするうえで非常に役立ち、医師は必要に応じて、さらに詳しい検査を提案します。
画像検査による臓器評価
ペルオキシソーム病では、脳や肝臓、腎臓などの内部臓器に変化が生じやすいため、画像検査を用いて状態を確認します。
MRI(磁気共鳴画像)検査を行うと、脳の白質部分に異常がないかや内臓の形態に問題がないかを視覚的に把握でき、副腎白質ジストロフィーの場合、脳の白質に特有の変化がみられることが多いため、MRI検査は診断の過程で重要な手段です。
また、肝臓や腎臓に関しては超音波検査(エコー)を活用する場合があり、血液検査で肝機能・腎機能の低下が示唆されるとき、エコーによって臓器の形態や血流状態を確認することで、障害の程度や合併症の有無を推測しやすくなります。
CT検査を使うこともありますが、被ばくを考慮してMRIやエコーのほうが優先されるケースが多いです。
遺伝子検査の役割
ペルオキシソーム病の確定診断や、具体的な病型を特定するには遺伝子検査が効果的です。遺伝子検査によって、どの遺伝子に変異があるかを直接確認できるため、病気の型や今後の治療方針をより正確に立てられます。
家族内で同様の症状がある場合や、遺伝子を特定することで発症リスクを把握したい場合に検討されることが多いです。
遺伝子検査を受けるにあたっては、検査費用の問題や結果の取り扱い、将来的な保険の問題など、さまざまな課題も浮上する可能性があり、検査前に医師や遺伝カウンセラーと相談し、納得できる形で検査を進めることが重要です。
遺伝子検査を検討するときに考慮したいポイント
- 費用の目安
- 検査結果の告知方法とタイミング
- 家族への情報共有の範囲
- 結果をもとにした将来のライフプラン
その他の補助診断法
血液検査や画像検査、遺伝子検査以外にも、組織生検や尿検査などが補助的に利用されることがあります。
組織生検は身体への負担が大きいため、重症例で詳細な情報が必要なときに限って検討される場合が多く、尿検査では、脂肪酸代謝物質の排泄状態を確認することで、病態を推測することが可能です。
また、神経学的検査として脳波検査や聴力検査を行い、症状の進行度合いをチェックする手段もあります。
ペルオキシソーム病の治療方法と治療薬について
ペルオキシソーム病の治療方法は、遺伝子治療や酵素補充療法が研究対象になっていますが、現時点では症状の改善や進行速度の遅延を目指したサポート的な治療や薬物治療が中心です。
食事療法やサプリメント
ペルオキシソーム病では、長鎖脂肪酸やフィタン酸が過剰に蓄積するタイプの病型が少なくないため、脂肪酸の摂取量を制限する食事療法が行われます。
動物性脂肪や乳製品など、長鎖脂肪酸を多く含む食品を控えめにしたり、フィタン酸を含む食品を制限し、医師や管理栄養士が個人の病型や栄養状態を考慮してメニューを提案する場合が多いです。
さらに、抗酸化作用をもつビタミンEやCのサプリメントを補給して、細胞の酸化ストレスを軽減することも試みられます。
ペルオキシソーム病の食事療法で意識される主なポイント
| 食事療法のポイント | 目的 |
|---|---|
| 長鎖脂肪酸を多く含む食品の制限 | 脂肪酸の異常蓄積を防ぎ、臓器障害を緩和する |
| フィタン酸を多く含む食品の制限 | レフサム病などの進行を遅らせる |
| 抗酸化ビタミンの補給 | 酸化ストレスを和らげ、細胞傷害を抑える |
食事療法に取り組むとき、無理な制限で栄養不足に陥らないよう注意が必要で、定期的に血液検査を行いながら、必要に応じてメニューを修正します。
対症療法とリハビリテーション
ペルオキシソーム病の多くは、特定の症状を緩和しながら生活の質をできるだけ維持するための対症療法が重要です。
けいれん発作に対しては抗てんかん薬を使う場合がありますし、肝機能障害がある場合には肝臓の負担を軽くする薬剤を使用し、腎機能が低下している場合には、むくみや電解質異常をコントロールする薬が必要になるケースもあります。
筋力や関節の可動域を保つためには、リハビリテーションが有効で、理学療法士や作業療法士が、一人ひとりの症状や体力に合わせたメニューを作成して、筋力低下や拘縮を予防することが大切です。
副腎白質ジストロフィーなどで歩行が困難になるケースでは、歩行補助具の使用や定期的なリハビリテーションを取り入れることで、生活の自立度を高める効果が期待できます。
対症療法で用いられる主なアプローチ
- 抗てんかん薬の投与
- ステロイド剤による副腎機能サポート
- 血圧管理薬による腎保護
- 理学療法・作業療法での身体機能維持
ステロイドや抗酸化薬の活用
ペルオキシソーム病のなかでも、副腎白質ジストロフィーは副腎機能の低下を伴うことが多く、ステロイド薬が不足したホルモンを補う目的で使われることがあります。
ステロイドは副腎機能を補うだけでなく、炎症を抑える効果も期待できるため、神経系の炎症が強い場合にも処方を検討します。
抗酸化薬としては、ビタミンEやビタミンCのサプリメントが活用されるほか、酸化ストレスを低減する効果を狙った薬剤が試験的に使われることもありますが、直接的に病気を治すわけではありません。
ステロイドや抗酸化薬を利用する場合の概略
| 薬剤の種類 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| ステロイド | 副腎機能を補い、炎症を軽減 | 長期使用で副作用のリスクあり |
| 抗酸化薬 | 酸化ストレスを軽減し、細胞保護を図る | 劇的な効果は期待しにくい |
ペルオキシソーム病の治療期間
ペルオキシソーム病の治療期間は、一般的に慢性的な経過をたどるものが多く、継続的に治療や経過観察を行う必要があります。
急性期と慢性期の治療の流れ
一部のペルオキシソーム病は、新生児期や乳幼児期に急性期を迎えて、重篤な症状が急に出ることがあり、その際には、呼吸管理や栄養管理などを集中して行い、危機的な状態を乗り越えます。
急性期を脱すると、症状がある程度落ち着く一方で、慢性的な管理が必要です。
慢性期の治療では、食事療法や薬物療法、リハビリテーションなどを並行して行いながら、定期的に検査をして病状をチェックします。
定期的なフォローアップの重要性
ペルオキシソーム病は進行性の病気であり、時間の経過とともに症状の部位や重症度が変化することがあります。
一度診断を受けて治療を始めた後も、定期的なフォローアップを続けて症状の変化を把握し、必要な治療の微調整を行うことが重要です。
| フォローアップ項目 | 目的 |
|---|---|
| 血液検査(脂肪酸値、肝腎機能など) | 病状の進行度や治療効果を評価 |
| 画像検査(MRI、超音波など) | 脳や内臓の変化を観察 |
| リハビリテーション評価 | 筋力や関節可動域の変化を記録し、リハビリ内容を調整 |
| 神経学的検査(脳波など) | けいれん発作の頻度や脳機能の変化を捉える |
ペルオキシソーム病薬の副作用や治療のデメリットについて
ペルオキシソーム病の治療では、症状に応じて多彩な薬を使用しますが、薬による副作用や治療そのものがもたらすデメリットも考慮する必要があります。
ステロイド使用時の注意点
副腎白質ジストロフィーなどでステロイドを使うときは、炎症や副腎機能低下を抑制するメリットがある一方、長期使用に伴う副作用が問題になります。
骨粗しょう症や体重増加、皮膚の脆弱化などが起こりやすくなるため、定期的な骨密度測定や栄養指導が必要です。
また、ステロイドの服用を急に中断すると体内のホルモンバランスが崩れるリスクがあるため、医師の指示に従って段階的に減量します。
ステロイド服用で気をつけたいポイント
- 骨密度の低下を防ぐカルシウムやビタミンDの摂取
- 塩分や糖分の過剰摂取を避ける食事管理
- 血圧や血糖値の定期チェック
- 急激な減量を避ける
長期投薬による身体への影響
抗てんかん薬や抗酸化薬、その他の対症療法で使用される薬剤も、長期にわたる投与で肝機能や腎機能に影響を与える可能性があり、薬の作用機序によっては、疲労感が増したり、めまいが起こりやすくなったりするケースがあります。
多剤併用の状態が続くと相互作用が複雑になるため、定期的な血液検査で薬剤の血中濃度や臓器機能を確認して、副作用リスクを下げる工夫がいります。
肝腎機能がもともに低下している患者さんは、投薬量や投薬間隔を慎重に設定する必要があるため、主治医との綿密なコミュニケーションが重要で、少しでも異常を感じたら、我慢せずに医療スタッフに相談して投薬プランを再調整しましょう。
サプリメント依存のリスク
ペルオキシソーム病では、脂肪酸代謝の異常や酸化ストレスへの対策としてビタミン類や各種サプリメントを継続的に利用することがあります。
ただし、サプリメントの過剰摂取による影響も無視できません。脂溶性ビタミン(A、D、E、Kなど)は体内に蓄積しやすく、ビタミンEなどは大量摂取で出血傾向を高める可能性が指摘されています。
自己判断でサプリメントを増量したり、複数のサプリを同時に飲んだりすると過剰症を招くので危険です。
サプリメントはあくまで補助的な存在であり、主治医の監督のもとで適量を守ってください。
ペルオキシソーム病の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
外来治療にかかるおおよその費用
血液検査の内容によって費用は変わりますが、保険適用で自己負担が3割の場合、月に1回の検査で2,000〜3,000円程度で、画像検査(MRIなど)は保険適用で自己負担が3割なら1回あたり5,000〜10,000円ほどの負担が目安です。
| 診療内容 | 頻度 | 自己負担額の目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 血液検査 | 月1回 | 約2,000〜3,000円 |
| 画像検査(MRI) | 数か月に1回 | 約5,000〜10,000円 |
| 遺伝子検査 | 必要に応じて | 数万円以上になる場合あり |
治療薬の価格帯と保険適用
抗てんかん薬やステロイド、血圧管理薬などは保険適用されるケースが多く、1か月の薬代で1,000〜3,000円程度の自己負担で済むことがあります。
しかし、特殊な薬剤やサプリメントは保険の対象外になる場合があり、そうした場合は1か月で数千円〜数万円の費用がかかることも珍しくありません。
- 保険適用が多い薬:抗てんかん薬、ステロイド薬、利尿薬など
- 保険適用にならない可能性があるもの:特定のサプリメント、輸入薬、研究段階の治療薬など
遺伝子検査や画像検査の自己負担
遺伝子検査に関しては10万円以上の負担が発生するケースもあれば、症状が重く学会などの指針で推奨される検査であれば一部保険適用が認められ、1〜2万円台になる場合もあります。
画像検査は標準的なMRI検査であれば先述のように保険適用されることが多いですが、特殊な造影剤を使う場合は自己負担額がさらに上乗せされます。
定期検査の費用と通院の頻度
ペルオキシソーム病は進行性の病気であるため、定期的に通院して病状を確認するスタイルが主流で通院頻度は月1回から数か月に1回程度が一般的です。
| 通院頻度 | 主な実施検査 | 自己負担額(3割負担)の目安 |
|---|---|---|
| 月1回 | 血液検査(脂肪酸値、肝腎機能など) | 2,000〜3,000円程度 |
| 2〜3か月ごと | MRI検査や超音波検査など | 5,000〜10,000円以上になる場合あり |
以上
参考文献
Shimozawa N, Takashima S, Kawai H, Kubota K, Sasai H, Orii K, Ogawa M, Ohnishi H. Advanced diagnostic system and introduction of newborn screening of adrenoleukodystrophy and peroxisomal disorders in Japan. International Journal of Neonatal Screening. 2021 Aug 25;7(3):58.
Suzuki Y, Shimozawa N, Yajima S, Inoue K, Orii T, Kondo N. Incidence of peroxisomal disorders in Japan. Japanese Journal of Human Genetics. 1996 Mar;41(1):167-75.
Takashima S, Saitsu H, Shimozawa N. Expanding the concept of peroxisomal diseases and efficient diagnostic system in Japan. Journal of Human Genetics. 2019 Feb;64(2):145-52.
Shimozawa N. Molecular and clinical aspects of peroxisomal diseases. Journal of Inherited Metabolic Disease: Official Journal of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism. 2007 Apr;30(2):193-7.
Suzuki Y, Shimozawa N, Orii T, Igarashi N, Kono N, Matsui A, Inoue Y, Yokota S, Hashimoto T. Zellweger-like syndrome with detectable hepatic peroxisomes: a variant form of peroxisomal disorder. The Journal of pediatrics. 1988 Nov 1;113(5):841-5.
Koto Y, Sakai N, Lee Y, Kakee N, Matsuda J, Tsuboi K, Shimozawa N, Okuyama T, Nakamura K, Narita A, Kobayashi H. Prevalence of patients with lysosomal storage disorders and peroxisomal disorders: a nationwide survey in Japan. Molecular Genetics and Metabolism. 2021 Jul 1;133(3):277-88.
Shimozawa N. Diagnosis of peroxisomal disorders. InPeroxisomes: Biogenesis, function, and role in human disease 2020 Jan 17 (pp. 159-169). Singapore: Springer Singapore.
Imanaka T, Shimozawa N, editors. Peroxisomes: biogenesis, function, and role in human disease. Springer Nature; 2020 Jan 16.
Shimozawa N. Molecular and clinical findings and diagnostic flowchart of peroxisomal diseases. Brain and Development. 2011 Oct 1;33(9):770-6.
Takahashi Y, Suzuki Y, Kumazaki K, Tanabe Y, Akaboshi S, Miura K, Shimozawa N, Kondo N, Nishiguchi T, Terada K, Orii T. Epilepsy in peroxisomal diseases. Epilepsia. 1997 Feb;38(2):182-8.