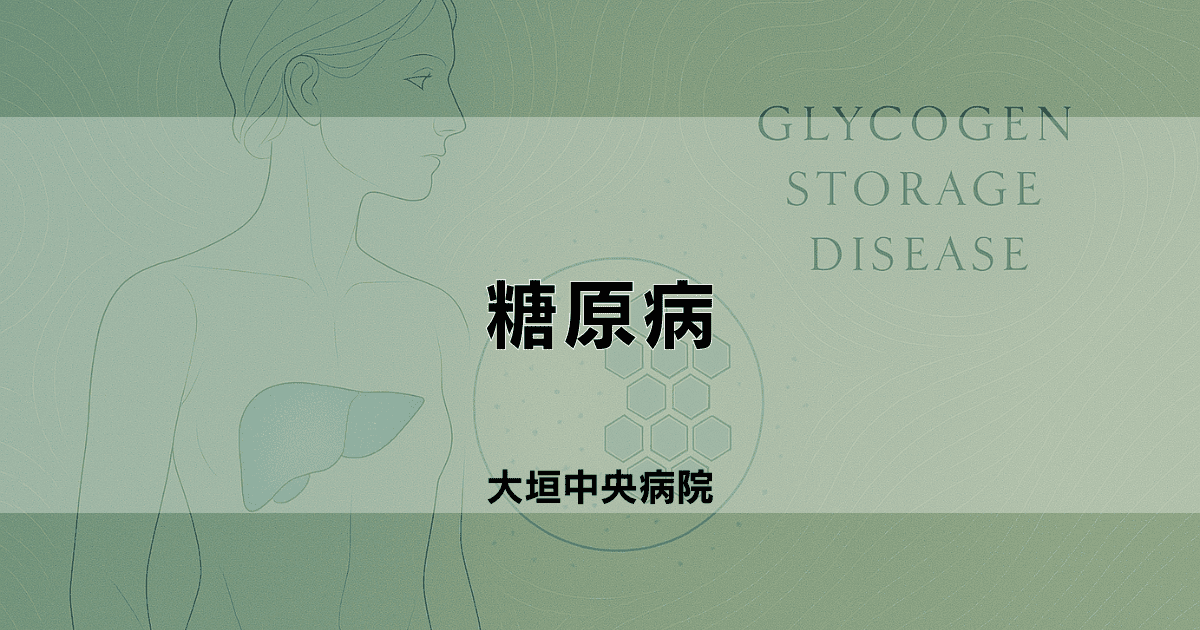糖原病とは、体内の糖分であるグルコースをエネルギー源として利用する過程に関連する遺伝子や酵素の異常によって発症し、筋肉や肝臓などに糖原が正しく貯蔵・分解されにくくなる病気の総称です。
肝機能障害や筋力低下だけでなく、重症になると低血糖発作など生命にかかわる合併症を引き起こす場合もあるため、早めの理解と治療が重要になります。
病型によって特徴や症状が異なるため、自分の状態に合う治療法を知ることが大切です。
糖原病の病型
糖原病には、遺伝的な酵素障害によって引き起こされる多種多様なタイプがあり、それぞれ異なる症状や臨床経過をたどることが特徴です。
肝臓が中心に障害を受けるタイプもあれば、筋肉が影響を受けるタイプもあり、複合的にいくつかの臓器が同時に障害されるものもあります。
主に国際的な分類では、酵素の欠損や異常部位によってナンバリングされた形で区別しており、I型、II型、III型などアルファベットや番号を用いて表記します。
肝臓に主眼をおくタイプ
肝臓に異常な形で糖原が蓄積しやすくなるタイプは、低血糖を起こしやすいのが大きな特徴になります。
I型では、グルコース-6-ホスファターゼの機能不全があり、血中へグルコースを放出しにくいために、血糖値が急激に下がることがあります。
また肝腫大(肝臓が大きくなること)がみられることも多く、乳幼児期から症状が強く出る場合があります。肝機能を管理するうえで、継続的な血糖コントロールと栄養バランスの調整が大切です。
筋肉中心のタイプ
筋肉に蓄積するタイプは筋力低下や運動耐容能の低下に直結するため、日常生活で疲れやすくなったり、運動時に筋肉痛や脱力を感じたりすることが多くみられます。
V型(マッカードル病)では、筋肉のグリコーゲンホスホリラーゼに異常があり、激しい運動の際に筋肉がうまくエネルギーを作り出せない状態になるため、運動開始直後の痛みやこむら返りが起きやすいです。
複合的に複数臓器が影響を受けるタイプ
ときには、肝臓と筋肉の両方に同時に異常がみられるタイプもあり、低血糖だけでなく、運動耐容能の低下や心臓への影響が含まれることがあります。
III型やIV型などは、病態が複雑で多彩な症状を示すことが多く、幼少期から注意深い経過観察が必要です。
こうしたタイプでは栄養指導が特に重要になり、血糖値をどのように安定させながら筋肉の状態を管理するかに焦点を当てた治療方針を考えます。
病型分類の目安と注意点
糖原病の病型は十数種類におよび、それぞれ固有の酵素異常があるため、診断時にはどの酵素が関与しているかを詳細に調べる必要があります。
ただし、同じ病型でも症状の強弱は人によって異なり、成長とともに変化していくケースも多いです。家族性の遺伝パターンをたどるときにも、どのような経過をたどりやすいかを事前に把握しておくことが大切になります。
代表的な病型の分類
| 分類名 | 欠損酵素の例 | 主な症状 | 影響を受けやすい臓器 |
|---|---|---|---|
| I型 | グルコース-6-ホスファターゼ | 低血糖、肝腫大 | 肝臓、腎臓 |
| II型 | 酸性マルターゼ(α-1,4-グルコシダーゼ) | 筋力低下、心肥大 | 心臓、骨格筋 |
| III型 | デブランチング酵素 | 低血糖、肝肥大、筋症状 | 肝臓、筋肉 |
| V型 | 筋グリコーゲンホスホリラーゼ | 運動不耐性、筋痛 | 骨格筋 |
| IX型 | 肝ホスホリラーゼキナーゼ | 軽度低血糖、肝腫大 | 肝臓 |
どの病型がどの臓器に主に影響を与えるのかを押さえておくと、治療方針や今後起こりうる合併症に対してより深い理解が得られます。
症状
糖原病が発症すると、主に肝臓と筋肉を中心とした症状が現れやすくなりますが、病型によっては心臓や腎臓などほかの臓器にも問題が起こります。
症状の出現時期や程度は大きく個人差があり、乳児期から顕著にわかるケースもあれば、成人期にいたるまで軽症で見過ごされるケースもありm早い段階で気づいて適切な管理を行うことが、合併症を防ぐうえで重要です。
低血糖による症状
肝臓型の糖原病では、グルコースを血中に放出するための経路がうまく機能しない状態になりやすく、低血糖を起こしやすくなります。
低血糖時にはめまいや冷や汗、脱力感や意識障害が出ることがあり、重症になるとけいれん発作を引き起こす場合もあります。
特に乳幼児期では、血糖値が下がりすぎた結果、成長障害や発育不良に結びつくことがあるため、早期発見とこまめな食事管理が必要です。
肝腫大・肝機能障害
肝臓が障害を受けやすいタイプでは、糖原が過度に蓄積し肝臓が大きくなる(肝腫大)現象が生じる場合があり、外見的にも腹部が膨らんだように見えることがあります。
肝腫大の程度は個人差がありますが、肝炎と誤認されることもあるため注意が必要です。肝機能検査を行うと、酵素値の異常などを示す場合がありますが、管理によって症状の進行を抑えられる場合もあります。
筋力低下・運動不耐性
筋肉に異常が生じやすいタイプでは、日常的に筋肉の疲れやすさや痛み、こむら返りの頻度が高まる可能性があります。
運動を始めるときの瞬発的な筋力発揮が難しくなるため、体育の授業やスポーツ活動で支障が出て、本人の生活の質を大きく下げてしまうことがあります。
無酸素的な激しい運動時には代謝が追いつかず、筋肉の損傷やミオグロビン尿症を引き起こすこともあり、急に尿の色が濃くなるなどの症状で気づくケースもあります。
心臓やその他の臓器への影響
II型やIII型の一部などでは、心臓の筋肉に糖原が蓄積することによって心肥大や心不全のリスクが高まることがあり、また、腎臓に合併症が生じるタイプもあり、腎機能障害へと進展する例も報告されています。
こうした症状は早期に出現しにくいことが多く、定期的な健診や専門医によるフォローアップが大切です。
糖原病で生じやすい症状
| 症状 | 代表的な病型 | 出現時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 低血糖 | I型、III型 | 乳児期~小児期 | 成長障害や発作に注意 |
| 肝腫大 | I型、III型、IX型 | 乳児期~ | 腹部の膨隆感に留意 |
| 筋力低下 | II型、V型 | 幼児期~成人 | 運動耐容能の低下 |
| 心肥大 | II型、III型の一部 | 幼児期~思春期 | 心不全リスク |
上記のように、どの病型でどの症状が出やすいのかを把握しておくと、日常生活での注意点や受診のタイミングを考えやすくなります。
代表的な自覚症状に関して注意すべきポイント
- めまいや冷や汗などの低血糖に関連する症状
- 運動開始時の急激な筋肉痛やこむら返り
- 腹部の違和感や明らかな肝腫大
- 以前は感じなかった疲労感が増大
- 感染症などで体力が落ちたときに症状が悪化
日常生活を送るうえで、これらの兆候を見逃さずに早期に受診を検討することが予後に大きく関わります。
糖原病の原因
糖原病は、体内に存在する複数の酵素群のうち、糖質の分解や合成、変換を行う特定の酵素に遺伝子レベルで異常が生じることによって起こされます。
多くの場合、常染色体劣性遺伝のパターンを取るため、両親がともに原因遺伝子の保因者である場合に子どもに発症する可能性が高いです。
酵素の欠損や活性低下の度合いはさまざまで、まったく酵素が機能しない重症例から、一部機能低下にとどまる軽症例まで幅広い臨床像を示します。
遺伝的背景
糖原病は、生まれつき存在する遺伝子の変異が根本原因であるため、いわゆる後天的な生活習慣病や感染症のように外部環境だけが要因になるものではありません。
ただし、同じ変異でも発症時期や症状の強さには個人差があり、研究の進展により、原因遺伝子の詳細が解明されつつあり、今後は精密な遺伝子検査で早期診断の可能性が広がっていくと期待されています。
代謝経路の異常
グルコースからグリコーゲンへの合成、あるいはグリコーゲンを分解して血中へグルコースを放出する経路のいずれかが障害されることで、糖原が蓄積したり、血糖の維持が難しくなったりします。
たとえば、肝臓の酵素がうまく働かない場合は全身の血糖調節に影響が及び、筋肉の酵素が異常の場合は筋内で十分なエネルギー産生ができずに運動時の筋損傷を招きやすくなります。
タンパク質の合成異常やミスフォールディング
酵素はタンパク質であるため、遺伝子変異によって正しい形に折りたたまれなかったり、合成されても速やかに分解されてしまったりすることが原因になるケースもあります。
その結果、酵素活性が大幅に低下したり消失したりして、糖質代謝がうまく回らなくなる可能性があります。こうしたメカニズムは、複雑な立体構造をもつ酵素で顕著です。
家系内での注意点
家族や親戚に糖原病を持つ方がいる場合、遺伝子を受け継いでいる可能性が高まるため、結婚や子どもを持つことを考える際には、事前のカウンセリングや検査を検討するケースがみられます。
ただし、両親が保因者であっても、必ず子どもが糖原病を発症するわけではなく、理論上の確率や酵素活性の程度を踏まえたうえでの判断が必要です。
糖原病の主な原因となる酵素や遺伝子的特徴
| 病型 | 原因酵素・遺伝子 | 遺伝形式 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| I型 | G6PC(グルコース-6-ホスファターゼ) | 常染色体劣性 | 重度の低血糖 |
| II型 | GAA(酸性マルターゼ) | 常染色体劣性 | 心肥大を伴うことが多い |
| III型 | AGL(デブランチング酵素) | 常染色体劣性 | 肝臓と筋肉の両方に症状 |
| V型 | PYGM(筋グリコーゲンホスホリラーゼ) | 常染色体劣性 | 運動不耐性が主症状 |
| IX型 | PHKAなど | X連鎖性、常染色体劣性 | 軽度症状から中程度まで |
一つの酵素に関する遺伝子だけでもさまざまな変異があり、同じ病型内でも症状のばらつきが生じる点が糖原病の特徴です。
遺伝的原因に関して知っておくと便利なポイント
- 常染色体劣性遺伝の場合、両親が保因者であるときに発症リスクが高まる
- X連鎖性のものもあり、性別によって発症率に偏りがあるケースもある
- 遺伝子変異の部位により、同じ病型でも重症度に違いが生じる
- 遺伝カウンセリングで将来的なリスクを把握することができる
こうした背景を知っておくと、もし家族歴がある場合や、原因がわからずに続く症状がある場合に、糖原病の可能性を視野に入れやすいです。
糖原病の検査・チェック方法
糖原病は、症状だけではほかの肝疾患や筋疾患との鑑別が難しいことが多く、正確な診断を行うには多角的なアプローチが必要です。
血液検査や尿検査、画像検査などでおおまかな兆候を探り、必要に応じて筋生検や遺伝子検査まで進めます。
小児期に発覚しやすい病型だけでなく、成人期になってから検査を受けてわかる場合もありますので、気になる症状があれば積極的に相談することが大切です。
血液検査
血糖値や肝酵素値(AST、ALT)、筋肉由来の酵素(CK:クレアチンキナーゼ)などを調べ、肝臓や筋肉の状態を概括的に把握します。
肝型では特に肝酵素値が上昇し、低血糖を示すことが多いですし、筋型では運動後のCK値の大幅な変動が指標になることがあり、また、血中の乳酸やケトン体の値も重要で、特定の病型を想定する材料です。
画像検査
肝臓の状態を確認するため、超音波検査やCT、MRIなどを用いて肝臓の大きさや構造的異常をチェックすることがあります。
筋肉の評価にはMRIが有用で、筋組織内の糖原の蓄積度合いや炎症の有無を詳細に見ることが可能で、II型やV型などは筋MRIで特徴的な所見を示す場合があるため、検討されやすいです。
筋生検や肝生検
症状が筋肉中心の場合には、筋組織の一部を採取して病理学的に調べ、糖原の蓄積具合や酵素活性の評価を行い、病型を絞り込みます。
肝臓中心の場合は肝生検を検討することもありますが、侵襲的な検査であるため患者さんの状態やリスクを考慮したうえで慎重に行うことが重要です。
生検の結果は確定診断に役立ちますが、近年では遺伝子検査の進歩によって必ずしも生検が必要とは限らない場合も増えています。
遺伝子検査
糖原病が疑われる場合、遺伝子解析によって原因となる変異を特定する方法があり、確定診断につながりやすく、家族内の発症リスクや保因者を知る上でも有用です。
ただし、遺伝子検査には専門的なカウンセリングが欠かせません。検査の結果によっては心理的な影響も大きいため、実施のタイミングなどを慎重に検討するケースが多いです。
糖原病診断に用いられる主な検査
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 血液検査 | 血糖値、肝酵素、CKなどを測定 | 非侵襲的で簡便 | 病型の特定には不十分なことが多い |
| 画像検査 | 超音波、CT、MRIなど | 臓器の形態を視覚化 | 放射線被ばく(CT)のリスクなど |
| 生検(筋/肝) | 組織内の糖原蓄積や酵素活性を直接評価 | 病型確定に有用 | 侵襲的で合併症リスクもある |
| 遺伝子検査 | 原因変異を特定可能 | 確定診断に直結 | 費用が高めの場合や心理的負担 |
こうした検査を組み合わせながら、総合的に判断して糖原病の診断を進めます。
検査の受け方や選択について覚えておきたいポイント
- 軽度の症状でも血液検査や画像検査で手掛かりを見いだせる
- 成長期の子どもでは運動負荷試験や食事負荷試験を行うこともある
- 遺伝子検査を実施するかどうかは医師と相談して決める
- 生検はリスクとメリットをよく比較してから判断する
検査は一度で確定できる場合もあれば、複数回にわたるフォローアップが必要なケースもありますので、担当の医師と計画を立てながら進めることが望ましいです。
糖原病の治療方法と治療薬について
糖原病の治療は、主に症状のコントロールと合併症の予防を目的とし、酵素自体を根本から補う治療法を研究する動きはありますが、現在一般的に行われる治療は、食事療法や低血糖対策、症状に応じた薬物療法などの組み合わせです。
ただし、病型ごとに治療の力点が異なるため、一律に同じ方法をすべての患者に適用するわけではありません。
栄養管理・食事療法
肝型の糖原病では、低血糖を防ぐためにこまめに食事をとり、体内の血糖値を安定させる必要があります。
特にI型では、深夜や早朝の低血糖を防ぐため、コーンスターチを用いたり、高カロリー食を複数回に分けて摂取したりするケースが多いです
。筋型の場合でも、筋肉へのエネルギー供給を補助するために、適度な炭水化物摂取や運動とのバランスを図る栄養管理が必要になります。生活習慣に合わせた食事指導を行うことがポイントです。
薬物療法
II型の糖原病(ポンペ病)では、酵素補充療法という治療が保険適用で行われることがあり、これは、不足している酸性マルターゼを人工的に補う薬剤を点滴で定期的に投与し、心筋や骨格筋への負担を和らげる狙いがあります。
その他の病型でも、症状に合わせて血糖値を安定させる薬や、肝保護作用のある薬、痛みを抑える薬などが使われることがあり、いずれにしても、医師の判断のもと、患者の病状や副作用リスクを考慮して処方を行います。
運動療法とリハビリテーション
筋型の糖原病では、過度な負荷がかかる運動は筋損傷リスクを高めますが、適度な有酸素運動やストレッチ、リハビリテーションは体力の維持に役立つことがあります。
専門の理学療法士と連携して、個々の運動耐容能に合わせたプログラムを組み、少しずつ持久力を養うことが大切です。運動量を誤るとミオグロビン尿症などを起こしやすいため、定期的な検査をしながら取り組むことが望まれます。
合併症への対策
心不全や腎不全リスクがある病型では、定期的な心エコー検査や腎機能検査が必要で、万が一、心臓や腎臓に明確な異常が認められた場合、早期に専門医のフォローを受け、薬物調整や栄養管理を強化します。
これらの合併症が進行すると、生命予後に直結するケースもあるため、対策の優先度が高いです。
糖原病で用いられる主な治療法や薬剤
| 治療法・薬剤 | 対象となる病型 | 主な目的 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 酵素補充療法 | II型(ポンペ病) | 酵素活性の補充 | 点滴投与を定期的に実施 |
| 食事療法(コーンスターチなど) | I型、III型 | 低血糖の予防 | 就寝前や夜間の補食が重要 |
| 肝保護薬 | 肝型全般 | 肝機能の保護 | 病状に合わせて処方 |
| 疼痛管理薬 | 筋型全般 | 筋肉痛の緩和 | 運動負荷と併用で調整 |
| リハビリテーション | 筋型全般 | 筋力低下の抑制 | 有酸素運動を中心に計画 |
こうした方法を組み合わせて、個々の患者さんに合わせた治療計画を立案します。
糖原病の治療法を選ぶときに知っておくと良いポイント
- 低血糖への対策として食事内容や回数を増やす
- 筋型でも過度な運動は避け、体調に合わせた運動療法を行う
- 合併症が疑われるときは速やかに専門科へ相談
- 酵素補充療法や点滴などは定期通院が必要
このように、糖原病の治療は多方面にわたり、栄養管理や運動プログラムとの組み合わせが中心になります。
糖原病の治療期間
糖原病は先天性の遺伝性疾患であり、酵素の異常が根本原因になっているため、一般に根本的な完治をめざすというよりも、慢性的に症状をコントロールして合併症を予防していくアプローチが中心です。
治療期間はそのまま生涯にわたり、定期的な通院や検査を継続する必要がありますが、病型や症状の強度によっては小児期から成人期にかけて状態が安定しやすいケースもあります。
乳幼児期から小児期にかけて
I型やIII型など、乳幼児期に強い低血糖や肝腫大がみられるタイプは、特に小児期の管理が重要です。
低血糖予防のための厳密な食事スケジュールや、栄養補助食品(コーンスターチなど)の使用を長期にわたり続けることが多く、日常生活にも大きく影響します。
しかし、管理によって成長につれ症状が安定し、日常生活に支障をきたさないレベルまで改善する例もあります。
思春期以降
思春期以降になると、体格やホルモンバランスの変化に伴って症状が変動することがあります。
糖原病の場合、運動負荷や食事パターンの変化に対応しきれないと、低血糖リスクが増したり、筋症状が悪化したりするケースがあるため、この時期も定期受診と自己管理が必要です。
特にスポーツ活動を行う場合には、運動強度のコントロールや補食のタイミングに注意を払いながら、長期的にケアしていくことが大切です。
成人期
成人期になると、職業や家事・育児などの生活スタイルが多様化し、糖原病を抱えている場合は、長時間の空腹や無理な肉体労働を避ける工夫が必要であり、勤務形態や職場の理解が得られると、より安定した生活を送れる可能性が高まります。
また、筋型の場合は運動習慣を途切れさせず、定期的なリハビリや有酸素運動を取り入れることで、筋力の低下をできるだけ緩やかに抑制できる場合があります。
高齢期
最近では診断技術の向上や医療の充実により、糖原病の患者さんが高齢期まで生存する機会が増えてきていて、高齢になると、糖原病以外の生活習慣病や加齢性変化が重なることで、一層のケアが必要です。
肝機能の低下や心機能の変化など、個人の健康状態を総合的にチェックしながら、食事や運動を無理なく続けることが治療の継続に結びつきます。
糖原病の主な年代別治療ポイント
| 年代 | 主な課題 | 治療の中心 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 乳幼児期 | 重度の低血糖管理、成長 | 栄養管理、頻回授乳 | 合併症予防と発育維持 |
| 学童期 | 学校生活との両立 | 食事療法、定期検査 | 日常生活の支障軽減 |
| 思春期 | ホルモン変化と運動量 | 運動制限と栄養補助 | 体力確保と自己管理習得 |
| 成人期 | 職業・生活習慣との調整 | 通院とリハビリ | 安定した生活と症状コントロール |
| 高齢期 | 他疾患との併存 | 総合的な健康管理 | QOL維持 |
このように、生涯にわたって糖原病と向き合うことになりますが、病型や症状に合わせて段階的に治療方針を調整すれば、日常生活での不自由を抑えながら生活を続けることも可能です。
治療期間における注意点
- 病状の変化やライフステージに応じた治療計画の見直し
- 定期的な血液検査や画像検査で合併症を早期発見
- 無理のない範囲で運動習慣を継続すること
- 栄養管理を継続し、低血糖や体力低下を防ぐ
こうした継続的なアプローチによって、糖原病と上手に付き合うことを目指します。
副作用や治療のデメリットについて
糖原病の治療では、補酵素や酵素補充療法、さまざまな医薬品を使用することがありますが、薬剤には必ず副作用や制限があります。
また、定期的な投薬や通院に伴う生活面での制約も、患者と家族にとって負担となる場合があります。ここでは、主な副作用やデメリットについて説明します。
酵素補充療法の副作用
II型のポンペ病で実施される酵素補充療法は、点滴によって人工的に合成された酸性マルターゼを体内に投与する治療法です。
投与時にアレルギー反応や発疹、発熱、血圧低下といった副作用が見られることがあるため、投与の際には医療機関で観察を受けながら行い、症状が出た場合にはすぐに対処できるように体制を整えます。
ステロイド剤などの副作用
病型によってはステロイド剤や免疫調整薬、肝保護薬などを併用するケースがあり、ステロイド剤の副作用としては、体重増加や高血糖、骨粗しょう症などが知られています。
長期服用の場合は、医師が必要最小限の量に調整しながら使う方針を取ることが多いため、自分の判断で勝手に中断したり減量したりしないように注意が必要です。
治療に伴う生活上の負担
糖原病の管理には、定期的な通院や検査が欠かせないうえ、日常的な食事療法や運動制限が求められます。
特に、低血糖を起こしやすい病型では、夜間や外出時にも間食やコーンスターチの摂取を行うなど、生活リズムをコントロールしにくくなるため負担感が大きいです。
また、筋型では、日常の運動や体力仕事に制限がかかり、職業選択の幅が狭まることが精神的負担となる場合もあります。
長期間の薬剤費用
治療薬が長期間にわたって必要になる場合、費用面がデメリットとして挙がることがあり、酵素補充療法などは保険適用になりますが、一定の自己負担額が生じる可能性があります。
加えて、サプリメント的なコーンスターチや高エネルギー食品なども日々の生活で使うため、それらの経済的負担が少なくないという現実もあります。
主な副作用や治療上のデメリット
| 治療・薬剤 | 副作用・デメリットの例 | 対策・注意点 |
|---|---|---|
| 酵素補充療法 | アレルギー反応、発疹、発熱 | 定期投与時の医療機関での監視 |
| ステロイド | 体重増加、高血糖、骨粗しょう症 | 服用量を最小限に調整、定期検査 |
| コーンスターチ | 味の好みの問題、服用タイミングの煩雑さ | 個別の食事指導と量の調整 |
| 通院・検査 | 時間的・経済的な負担 | 計画的な通院スケジュール |
これらはあくまでも一般的に見られるデメリットで、必ずしも全ての患者さんに当てはまるわけではありません。
注意すべきポイント
- 治療薬の副作用を早期発見するために定期的な検査や問診が重要
- 治療費や通院の負担は、事前に医療機関と相談して見通しを立てる
- 食事療法と運動制限は心理的ストレスになりやすいので、家族や専門家のサポートが大切
- 個人差が大きいので、同じ病型でも治療反応や負担感は異なる
デメリットは確かに存在しますが、正しい知識とサポート体制のもとで治療を続けることで、糖原病の症状や合併症によるリスクを抑えることを目指せます。
糖原病の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用になる主な治療と費用の目安
酵素補充療法(II型のポンペ病など)は、特殊な薬剤を用いるため、自己負担割合が存在するとしても月額で数千円から数万円台になることがあり、内容や頻度によって変動します。
肝型や筋型の糖原病でも、定期的な血液検査や画像検査、薬物療法の費用がかかりますが、医師の指示のもと保険診療内で進める場合がほとんどで、検査費用や薬剤費は数千円から数万円程度を見込む方が多いです。
食事療法にかかる費用
糖原病では日常の食事管理が大切であり、低血糖を防ぐ目的でコーンスターチなどを購入する場合があります。
コーンスターチ自体は市販品でもさほど高額ではありませんが、大量に使うケースや患者さんに合った商品を選ぶとなると、月々で数千円ほどの出費になることがあります。
また、病型によっては栄養補助食品や特殊ミルク、サプリメントを使うことがあるため、それらにかかる費用も検討が必要です。
検査と投薬の具体的な金額
主な治療項目と保険適用後のおおよその負担額目安
| 治療項目 | 保険適用の有無 | 自己負担額の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 血液検査 | 有 | 数千円 | 頻度や項目数による |
| 画像検査(MRIなど) | 有 | 数千円~1万円超 | 病状に合わせた頻度で実施 |
| 酵素補充療法 | 有 | 数千円~数万円 | 投与間隔や症状で変動 |
| 内服薬・点滴 | 有 | 数百円~数千円 | 種類・処方量による |
| コーンスターチ等の栄養補助 | 原則保険外 | 数千円/月 | 市販品の場合が多い |
主な治療項目は保険対象になりやすいですが、栄養補助食品については保険外になるケースが多いです。
費用面で知っておきたいポイント
- 酵素補充療法は公的保険の支援対象であり、自己負担が一定に収まる可能性がある
- 画像検査や血液検査の頻度が高いと通院費用がかさむ
- 栄養補助食品は自費になる場合があるため、月々の支出に留意が必要
- 治療費は病状や医療機関によって大きく変動するので、担当医とこまめに相談
以上
参考文献
Kido J, Nakamura K, Matsumoto S, Mitsubuchi H, Ohura T, Shigematsu Y, Yorifuji T, Kasahara M, Horikawa R, Endo F. Current status of hepatic glycogen storage disease in Japan: clinical manifestations, treatments and long-term outcomes. Journal of human genetics. 2013 May;58(5):285-92.
Iijima H, Ago Y, Fujiki R, Takayanagi T, Kubota M. Novel GYS2 mutations in a Japanese patient with glycogen storage disease type 0a. Molecular Genetics and Metabolism Reports. 2021 Jan 10;26:100702.
Özen H. Glycogen storage diseases: new perspectives. World journal of gastroenterology: WJG. 2007 May 14;13(18):2541.
Fukuda T, Ito T, Hamazaki T, Inui A, Ishige M, Kagawa R, Sakai N, Watanabe Y, Kobayashi H, Wasaki Y, Taura J. Blood glucose trends in glycogen storage disease type Ia: a cross‐sectional study. Journal of Inherited Metabolic Disease. 2023 Jul;46(4):618-33.
Kumamoto S, Katafuchi T, Nakamura K, Endo F, Oda E, Okuyama T, Kroos MA, Reuser AJ, Okumiya T. High frequency of acid α-glucosidase pseudodeficiency complicates newborn screening for glycogen storage disease type II in the Japanese population. Molecular genetics and metabolism. 2009 Jul 1;97(3):190-5.
Okubo M, Horinishi A, Takeuchi M, Suzuki Y, Sakura N, Hasegawa Y, Igarashi T, Goto K, Tahara H, Uchimoto S, Omichi K. Heterogeneous mutations in the glycogen-debranching enzyme gene are responsible for glycogen storage disease type IIIa in Japan. Human genetics. 2000 Jan;106:108-15.
Akanuma J, Nishigaki T, Fujii K, Matsubara Y, Inui K, Takahashi K, Kure S, Suzuki Y, Ohura T, Miyabayashi S, Ogawa E. Glycogen storage disease type Ia: molecular diagnosis of 51 Japanese patients and characterization of splicing mutations by analysis of ectopically transcribed mRNA from lymphoblastoid cells. American journal of medical genetics. 2000 Mar 13;91(2):107-12.
Takahashi K, Akanuma J, Matsubara Y, Fujii K, Kure S, Suzuki Y, Wataya K, Sakamoto O, Aoki Y, Ogasawara M, Ohura T. Heterogeneous mutations in the glucose‐6‐phosphatase gene in Japanese patients with glycogen storage disease type Ia. American journal of medical genetics. 2000 May 15;92(2):90-4.
Oki Y, Okubo M, Tanaka S, Nakanishi K, Kobayashi T, Murase T. Diabetes mellitus secondary to glycogen storage disease type III. Diabetic medicine. 2000 Nov;17(11):810-2.
Toda G, Yoshimuta T, Kawano H, Yano K. Glycogen storage disease associated with left ventricular aneurysm in an elderly patient. Japanese circulation journal. 2001;65(5):462-4.