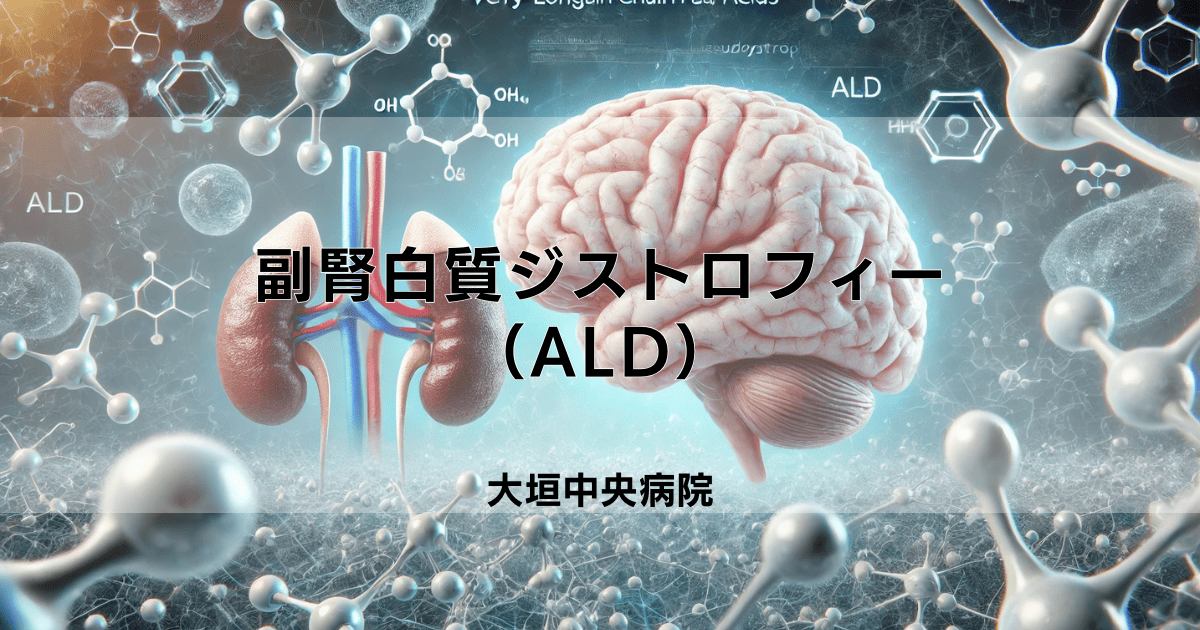副腎白質ジストロフィー(ALD)とは、主にX染色体の変異によって生じる遺伝性疾患であり、副腎機能不全や中枢神経の障害を起こすことが特徴です。
極長鎖脂肪酸の分解に関連する遺伝子に異常が生じると考えられており、体内に蓄積した脂肪酸が神経やホルモン系に負担を与えやすくなります。
特に男性に多く見られ、発症する年齢や症状の進行度は病型によって異なるため、早期の発見と正しいケアが重要です。
副腎白質ジストロフィー(ALD)の病型
ALDには、発症年齢や臨床的特徴によっていくつかの病型があり、それぞれの経過や対処法に違いが見られ、病型によっては深刻な中枢神経障害を招くこともあれば、副腎機能への影響が中心となる場合もあります。
小児期発症型とは何か
小児期発症型は、幼児から学童期にかけて症状が始まりやすい形態であり、脳の白質に病変が広がると考えられます。
学習障害や行動の変化など、学校生活や家庭生活で見過ごされやすい症状から始まり、視力障害や聴覚障害が徐々に進行することもあります。
重症化すると知的障害や運動機能低下が顕著になり、日常生活を送るのが困難になりやすいです。
成人期発症型の特徴
成人期発症型は、思春期以降に神経症状がゆっくり進むケースや、比較的軽度な症状が長期間続くケースがあります。
人格変化や軽度の歩行困難などが見られる場合もありますが、小児期発症型に比べると進行速度が緩やかであることが多いです。ただし個人差が大きいため、定期的な検査を受けるなどの予防的な取り組みが重要です。
副腎不全型
この病型は主に副腎皮質の機能障害が中心となって症状が現れ、ホルモンバランスの乱れが副腎機能に大きく影響すると考えられます。
副腎ホルモンの分泌が十分でない場合は低血圧や倦怠感、脱力感を生じやすく、感染症にも弱くなる傾向があります。
このタイプでは神経症状が表面化しにくいものの、ホルモン補充療法を怠ると身体的ストレスに対処しにくくなり、緊急搬送が必要です。
その他の亜型
ALDは多面的で、年齢や症状の進行具合などによってさらに細かな分類が行われることがあり、例えば、脊髄型と呼ばれるものでは主に下肢の痙性まひなどが中心となり、上肢には目立った症状が出ないケースも報告されています。
このように、同じALDでも病態は多様であり、医療現場では個々の状況に合わせた診断と治療方針の検討が必要です。
ALDの主要な病型分類
| 病型 | 主な発症時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 小児期発症型 | 幼児期~学童期 | 急速に進行する脳白質病変、学習障害、行動異常など |
| 成人期発症型 | 思春期以降 | ゆっくり進む神経症状、人格変化、歩行障害など |
| 副腎不全型 | 年齢を問わない | ホルモンバランス乱れ、低血圧や倦怠感、脱力感が中心 |
| 脊髄型 | 成人期~高齢期 | 下肢の痙性まひが多い、手足のしびれや感覚障害 |
病型を知るうえで注意したいポイント
・家族内の発症状況を参考にする場合、女性キャリアの健康状態にも注目する
・脳神経症状がないからといって副腎障害が起こらないわけではない
・医師による総合的な判断を踏まえて適切な治療計画を立てる
症状
ALDの症状は極長鎖脂肪酸が蓄積する臓器によって多岐にわたり、脳や副腎、脊髄などに異常が生じると想定され、複数の症状が重なって個々の病態を形作ります。
中枢神経に現れる主な症状
ALDの典型的な特徴として、脳の白質や神経線維が徐々に損傷を受けることが挙げられ、初期段階では集中力の低下や記憶力の衰え、感情の起伏が激しくなるなどの精神症状が目立つ場合があります。
その後、進行とともに運動機能に影響が及ぶ可能性があり、歩行がぎこちなくなる、手先の微細運動が難しくなるなどの変化を生じやすいです。症状が悪化すると意識障害や痙攣発作を起こすリスクも指摘されています。
副腎機能不全が起こす影響
副腎皮質ホルモンの分泌量が低下すると、体がストレスを受けた際の防御システムがうまく働かなくなり、日常的に疲労やだるさを感じやすくなり、また低血糖症状や血圧の不安定さ、食欲減退などが起こりやすくなる点も見逃せません。
重度の場合にはアジソン危機と呼ばれる急性副腎不全に陥り、命に関わる重篤な状態を招く可能性があります。
運動能力や感覚面への影響
小児期発症型では顕著に見られますが、成人期発症型や脊髄型でも、下肢を中心に筋力の低下や痙攣を伴う歩行障害が生じることがあります。手足の痛みやしびれを訴えるケースもあり、日常動作の制限が強まると生活の質が大きく損なわれます。
時間が経つにつれて自力での歩行が難しくなるケースもあるため、早期のリハビリ介入や補助具の活用が大切です。
視覚や聴覚への影響
視神経や聴神経が障害されると、物が二重に見える複視や視力の低下、難聴などの症状が表面化し、学習や仕事、コミュニケーションに影響を及ぼす可能性があるため、専門医による定期的な検査や補聴器、視力補正具などの活用が考慮されます。
特に小児の場合は、早期の支援が学習の進捗や社会的な発達に大きく関係してくるので、注意が必要です。
ALDでよく見られる症状
| 身体・精神面 | 具体的症状 |
|---|---|
| 神経障害 | 記憶障害、注意力低下、運動失調、痙攣、人格変化 |
| 副腎機能低下 | 倦怠感、血圧低下、低血糖症状、食欲不振、脱力感 |
| 運動・感覚機能 | 歩行障害、下肢の痙性まひ、手足のしびれ |
| 視覚・聴覚 | 複視、視力低下、難聴 |
症状の種類や組み合わせは個人差が大きいですが、特に発症初期の段階で一見すると別の病気に思える症状が出るケースもあり、発見を遅らせやすい要因です。
症状に気づいたら考慮したいこと
・些細な集中力の低下や軽微な歩行障害でも医師に相談してみる
・家族や学校、職場での評価も重要な判断材料になりうる
・小児での急な学習成績の変化や行動異常に着目して早めに受診を検討する
症状が多岐にわたり、しかも徐々に進行する場合は、素早い対応こそが将来的な合併症の予防や生活の質の確保に直結します。
副腎白質ジストロフィー(ALD)の原因
ALDはX染色体に存在する特定の遺伝子変異が原因とされており、体内で極長鎖脂肪酸(Very Long Chain Fatty Acids: VLCFA)の分解がうまく行われなくなることが病態の根底にあると考えられています。
遺伝子変異が関与する仕組み
ALDを引き起こす主な原因遺伝子は、ABCD1と呼ばれるもので、この遺伝子は細胞内の脂質代謝に関与し、VLCFAを分解する働きを担うタンパク質を産生する役割があります。
変異が起こるとこのタンパク質が正しく機能せず、過剰なVLCFAが中枢神経や副腎に蓄積しやすくなり、細胞に障害を与えやすくなる仕組みです。
遺伝子変異と性別の関係
| 性別 | 病気の発症リスク |
|---|---|
| 男性 | X染色体変異を1つ持つだけで症状が発現しやすい |
| 女性キャリア | 通常はもう1つのX染色体が正常で症状が軽度または無症状の場合が多い |
男性はX染色体が1本しかないため、変異を受け継ぐと高い確率でALDを発症します。
対して女性はX染色体を2本持つため、一方に変異があってももう片方が正常なら軽症または無症状で過ごすことがあり、キャリアとして次世代に遺伝する可能性があります。
VLCFAの蓄積がもたらす影響
VLCFAが細胞内に蓄積すると、細胞膜の安定性が損なわれたり、炎症や免疫反応を誘発しやすくなると考えられています。
特に神経細胞のミエリン鞘が破壊されると、神経伝達が阻害され、運動障害や認知機能の低下などを起こすリスクが高いです。また、副腎皮質の細胞がダメージを受けると、ホルモンの産生能力が低下し、身体の恒常性が乱れる一因になります。
遺伝以外の要因はあるか
多くの場合は遺伝が主原因となりますが、遺伝子以外の環境的要因が病態を悪化させるリスクを高める可能性も指摘されています。過度なストレスや免疫力の低下、食事バランスの乱れなどが二次的な要因として働く場合があります。
しかし、これらの要因だけでALDを発症するわけではないため、「遺伝子変異があること」と「身体の状態に影響する複数要因」が組み合わさって症状が進行すると捉える方が自然でしょう。
遺伝カウンセリングの意義
家族内にALDの既往歴がある場合、遺伝カウンセリングを通じて将来的なリスクや発症可能性を見極める手段が確立されつつあります。
特に女性キャリアの立場にある方や、男児を授かった家族などは、早期の段階で遺伝情報を把握することが大切で、子どもの成長段階で必要な定期検査や生活上の注意点を明確にしやすくなります。
原因を理解する際に認識したい事柄
・X染色体上の変異により、男児での発症率が高い
・家族内の発症状況やキャリアである女性の健康状態に注目する
・遺伝的要因に環境要因が重なると進行が早まる可能性がある
原因のメカニズムを知ることは、症状を正しく理解し、予防や対策に向けた一歩を踏み出すための基盤として重要です。
副腎白質ジストロフィー(ALD)の検査・チェック方法
ALDは症状だけでは他の神経難病やホルモン異常症と区別しにくい場合があり、正確な検査と診断が非常に大切です。
血液検査によるVLCFA測定
ALDの診断で最も基本的な方法の1つは、血液中に含まれるVLCFAの濃度を測定する血液検査です。
健康な人に比べて極長鎖脂肪酸の濃度が高くなる傾向が見られ、特にC26:0と呼ばれる炭素数26の飽和脂肪酸が上昇しやすいことが指摘されています。この検査は比較的簡便でありながら診断精度が高いため、多くの医療機関で実施されています。
ALD診断に関わる主な検査項目
| 検査名 | 特徴 |
|---|---|
| VLCFA測定 | 血液中の極長鎖脂肪酸濃度を確認し、基準値を大きく上回るかを評価 |
| 副腎皮質ホルモン測定 | コルチゾールやアルドステロンなど、副腎ホルモンの分泌量を調べる |
| MRI検査 | 脳の白質部分の変性を画像で評価し、進行度を把握する |
| 遺伝子検査 | ABCD1遺伝子変異の有無を直接調べ、家族性リスクを確認する |
血液検査の結果だけでは病型や進行度までは判断できないため、他の検査と組み合わせて総合的に判断します。
MRI検査での画像診断
ALDにおいては、脳の白質が炎症や脱髄を起こしているケースが多いため、MRI検査が有用です。特にT2強調画像で後頭葉や側頭葉の白質部分に高信号域が認められることが多く、これがALD特有の所見として知られています。
小児期発症型では急速に脳病変が広がることもあるため、定期的なMRI検査を行うことで病態の推移を把握し、治療の効果や新たな治療方針を検討しやすくなります。
副腎機能検査
副腎機能の低下はALDの大きな特徴の1つでもあり、血中コルチゾールやアルドステロンのレベルを測定することが実施され、さらにACTH刺激試験によって、副腎がコルチゾールを産生できるかどうかを確認する方法もあります。
副腎機能に異常が見つかった場合は、早期にホルモン補充療法を開始することで重篤な合併症のリスクを低減できる可能性が高まります。
遺伝子検査と家族検査
家族内での発症例がある場合や、血液検査でVLCFA濃度が高い場合は、遺伝子検査でABCD1遺伝子の変異を直接確認することが検討され、また、女性キャリアの有無を確かめるためにも遺伝子検査が役立ちます。
家族検査を行うことで、まだ症状が出ていない人々でも発症リスクを早期に把握し、今後の生活や定期検査の頻度を計画しやすくなるでしょう。
検査の進め方で考慮したい点
・血液検査だけでなくMRIや副腎機能検査の組み合わせが必要
・家族内に小児期発症型がいる場合は特に早い段階で遺伝子検査を検討する
・症状の進行具合と検査頻度を医師と相談しながら決定する
複数の検査結果を総合的に判断することで、病型の特定や治療方針の選択が正確に行いやすくなります。
ALDの検査が進む流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.問診と身体診察 | 症状の経過や家族歴の確認、基本的な神経学的評価 |
| 2.血液検査 | VLCFA測定、副腎ホルモンの確認 |
| 3.MRI検査 | 脳の白質の変性や脱髄状況を画像で把握 |
| 4.遺伝子検査 | ABCD1遺伝子変異を直接確認 |
| 5.診断と治療方針決定 | 生活習慣や治療薬、必要ならホルモン補充の検討 |
治療方法と治療薬について
ALDは遺伝子変異によって発症するため、根本的な治療はまだ限られています。ただし、症状を抑えたり進行を遅らせたりするための治療は複数あり、組み合わせることで生活の質を高めることが期待できます。
ホルモン補充療法
副腎機能が低下している場合、コルチゾールやアルドステロンなどのホルモンを外部から補充する治療が一般的に行われます。
コルチゾールが不足すると低血糖や低血圧、重度の疲労感が顕著になりやすいため、経口薬などを用いて不足分を補います。この治療により重篤な副腎不全を防ぎ、日常生活の安定を図ることが可能です。
主なホルモン補充薬
| 薬剤名 | 役割 |
|---|---|
| 経口ステロイド | コルチゾール補充 |
| ミネラルコルチコイド | ナトリウムやカリウムのバランス調整に寄与 |
ホルモン補充は適切な量やタイミングの調整が大切になり、自己判断で中断するとリスクが高まるため、医師との連携が重要です。
食事療法と Lorenzo’s Oil
ALDの治療としてしばしば挙げられるのが、食事からのVLCFA摂取を可能な限り低減する取り組みで、飽和脂肪酸を控えめにするなどの食事指導が行われることがあります。
また、Lorenzo’s Oilと呼ばれる特定の長鎖脂肪酸を含むオイルを使用し、体内に過剰なVLCFAが蓄積しないようバランスを調整する方法も選択肢です。効果は個人差が大きいですが、進行の抑制に寄与すると期待できるケースもあります。
造血幹細胞移植
急速に進行する小児期発症型などでは、造血幹細胞移植(骨髄移植や臍帯血移植)があり、健康なドナーの造血幹細胞を移植し体内で正常なABCD1遺伝子を発現する細胞を増やし、VLCFA蓄積による神経障害の進行を抑えることを目指します。
ただし、移植そのものに伴うリスクや適合ドナーの有無、年齢制限などさまざまな課題があるため、慎重に判断することが必要です。
対症療法やリハビリ
神経症状が進行している場合は、対症療法による管理やリハビリが欠かせません。理学療法士や作業療法士と連携し、歩行訓練や筋力維持トレーニングを行い、可能な限り日常動作を保つ工夫が大切です。
また、痙攣が頻発する場合は抗てんかん薬を使用し、視覚や聴覚に問題がある場合は補助具の活用で生活を補っていく方法が取られています。
ALDの治療を考えるときに押さえたい要点
・ホルモン補充は生命維持に直結するため、自己調整は危険
・食事療法の効果には個人差があり、継続的なモニタリングが必要
・造血幹細胞移植にはリスクがあるため、家族と医師の綿密な相談が不可欠
・リハビリやサポート体制を整え、生活の質を確保する視点が重要
主な治療方法と特徴
| 治療方法 | 特徴 |
|---|---|
| ホルモン補充療法 | 副腎機能をサポートして急性症状を予防する。用量やタイミングの管理が必要。 |
| 食事療法・Lorenzo’s Oil | VLCFAの摂取制限や特殊なオイルで脂肪酸バランスを調整する。効果は個人差が大きい。 |
| 造血幹細胞移植 | ドナーとの適合や術後管理が課題になるが、進行抑制が期待される場合がある。 |
| 対症療法・リハビリ | 痙攣や運動障害などの症状をケアしながら、社会参加を維持しやすくする。 |
複数の選択肢があることで、症状や年齢、進行度に合わせた多角的なアプローチが可能になります。
副腎白質ジストロフィー(ALD)の治療期間
ALDの治療期間は、病型や症状の進行度、選択する治療法などによって異なり、小児期発症型か成人期発症型かによっても大きく違いが生じるため、一概に何年という形で区切ることは難しいのが現状です。
病型ごとの進行スピード
小児期発症型は脳に急速な変性が進むケースが多く、発症から数年で重篤な状態に至ることがあります。
そのため、幼児期や学童期に治療を開始しても長期間の専門的ケアが必要であり、経過観察を含めると成人期まで継続的に医療と関わりを持つ場合が少なくありません。
一方で成人期発症型は比較的ゆっくり進行し、急激な悪化のリスクは小児期発症型に比べて低いです。
治療法による差
ホルモン補充療法に関しては、基本的に生涯にわたって続けることを視野に入れる必要があり、定期的な血液検査や副腎機能検査を受けながら投与量を調整する作業が続きます。
造血幹細胞移植を行った場合、術後の経過が良好であっても排斥反応のリスクや合併症の監視が必要です。移植を成功させたとしても、すぐに治療が終わるわけではなく、長期にわたるフォローが欠かせません。
治療期間に関係する主な要素
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 発症年齢 | 小児期発症型ほど進行が早く、長期的な治療が必要になりやすい |
| 病型の種類 | 脊髄型や成人期発症型はゆるやかに進む場合が多い |
| 治療方法の選択 | 造血幹細胞移植やLorenzo’s Oilなどアプローチにより必要な期間が変動 |
| 合併症の有無 | 感染症や内臓障害などが発生するとさらに治療期間が延びる可能性 |
定期的な検診とフォローアップ
ALDは一度にすべての治療が完結するわけではなく、徐々に姿を変えながら長期戦となるケースが多いです。たとえ症状が落ち着いたように見えても、再燃や新たな症状の出現を早期に捉えるため、定期的なMRI検査や血液検査が重要になります。
特に副腎機能はストレスや体調不良の影響を受けやすいため、ホルモン値の変動を定期的に確認し、必要に応じて処方量を調整する取り組みが不可欠です。
治療期間を考えるときに知っておきたいポイント
・小児期発症型は症状の進行が早く、成人まで長い管理が必要になる場合が多い
・成人期発症型もゆっくりとはいえ、定期検査や投薬管理がずっと続く可能性がある
・造血幹細胞移植を実施しても術後ケアや合併症予防が大切で、短期間で完結しない
・病型や治療方針に合わせ、本人と家族が長期的展望をもって臨むことが必要
副作用や治療のデメリットについて
ALDの治療には複数のアプローチがありますが、それぞれに副作用や制限、リスクが伴うことも事実です。
ホルモン補充療法の副作用
ホルモン補充を行うと、身体が本来持っているホルモン分泌調整機能に影響を及ぼす可能性があり、ステロイドの過剰投与によるむくみや血糖値の上昇、骨粗しょう症のリスクが高まるケースがあります。
また、急に投薬を中断すると副腎クリーゼのような急性症状が出ることもあり、自己判断による投薬中断は危険です。
ホルモン補充療法における考慮点
・過剰投与による体重増加や高血糖
・長期使用で骨密度が低下するリスク
・自己判断での投薬中断は急性副腎不全のリスクを高める
Lorenzo’s Oilや食事療法の限界
Lorenzo’s Oilは特定の脂肪酸を組み合わせたオイルであり、VLCFAの蓄積を抑制することを目的に開発されました。しかし、その効果は個々の症例によってばらつきがあるうえ、過剰な制限を行うと栄養不足に陥る可能性があります。
食事療法でも、摂取栄養のバランスを間違えると成長期の子どもに悪影響が及びかねないため、専門家の指導や定期検査が欠かせません。
造血幹細胞移植のリスク
造血幹細胞移植は、進行を抑える手段として期待される一方、移植そのものに伴う合併症や排斥反応、感染症リスクが大きいです。
ドナーとの適合が見つかるかどうかも大きな課題であり、術後の長期にわたる免疫抑制剤の使用が必要になることも珍しくありません。こうしたリスクを踏まえ、移植の決断は家族や医療チーム全体で検討する必要があります。
リハビリや対症療法の難しさ
運動機能や認知機能の低下に対してリハビリテーションを行う場合、進行度や年齢に合わせたプログラムの変更が頻繁に生じるため、一貫して効果が得られるわけではありません。
神経症状が強い段階に達すると、リハビリだけで改善が見られないケースも多く、精神的な負担が大きくなる恐れがあります。
注意しておきたい治療のデメリット
・ホルモン補充ではステロイド副作用による身体的負担が生じる
・Lorenzo’s Oilや食事療法には効果の個人差が大きく、継続管理が必要になる
・造血幹細胞移植はドナー探しや排斥反応など、侵襲性の高い治療法となる
・リハビリは効果が不確実なうえ、本人と家族のモチベーション維持が難しい
副腎白質ジストロフィー(ALD)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
ホルモン補充療法の費用
1か月分の薬剤費は、保険適用後で数千円から数万円程度になることが一般的ですが、使用する薬の種類や用量によって変わり、重度のホルモン不足がある場合は高めの投薬量になるため、薬剤費の負担は増える傾向があります。
ALD治療にかかる費用
| 項目 | 概算費用(保険適用後の目安) |
|---|---|
| ステロイドやミネラルコルチコイド | 月数千円~数万円 |
| 定期血液検査(VLCFA、ホルモン値等) | 1回あたり1,000~3,000円程度 |
| MRI検査 | 1回あたり5,000~15,000円程度 |
| 食事療法関連費(Lorenzo’s Oil等) | 月数千円~数万円 |
上記はあくまで目安であり、実際の費用は医療機関や検査項目、薬剤の種類によって変わります。
造血幹細胞移植の費用
造血幹細胞移植は高度医療に該当するため、通常の治療に比べて大きな費用がかかり、移植前の検査やドナー検索、手術費用、術後管理費などが加算され、数十万円から数百万円単位の負担が発生します。
ただし、これらも保険適用の範囲内であれば自己負担割合が軽減され、最終的に支払う金額は一定額に収まることが多いです。
定期検査と通院回数
ALDでは、進行状況や副腎機能の変動を把握するために定期検査が欠かせません。血液検査やMRI検査を数か月ごとに受けると、年間で合計数万円から数十万円の検査費用がかかります。
Lorenzo’s Oilやサプリメントの費用
Lorenzo’s Oilは日本国内の医療機関では保険適用外の場合が多く、全額自己負担で輸入販売会社を通じて購入するケースが見受けられます。
月数万円ほどのコストがかかることもあり、長期間にわたる継続使用を検討するならば、経済的な面も踏まえた計画が欠かせません。
さらに、食事療法と組み合わせる場合は栄養士などの専門家の指導を受けることも検討し、コストと効果のバランスを意識してください。
参考文献
Shimozawa N, Honda A, Kajiwara N, Kozawa S, Nagase T, Takemoto Y, Suzuki Y. X-linked adrenoleukodystrophy: diagnostic and follow-up system in Japan. Journal of human genetics. 2011 Feb;56(2):106-9.
Takemoto Y, Suzuki Y, Tamakoshi A, Onodera O, Tsuji S, Hashimoto T, Shimozawa N, Orii T, Kondo N. Epidemiology of X-linked adrenoleukodystrophy in Japan. Journal of human genetics. 2002 Nov;47(11):590-3.
Suzuki Y, Takemoto Y, Shimozawa N, Imanaka T, Kato S, Furuya H, Kaga M, Kato K, Hashimoto N, Onodera O, Tsuji S. Natural history of X-linked adrenoleukodystrophy in Japan. Brain and Development. 2005 Aug 1;27(5):353-7.
Shimozawa N, Takashima S, Kawai H, Kubota K, Sasai H, Orii K, Ogawa M, Ohnishi H. Advanced diagnostic system and introduction of newborn screening of adrenoleukodystrophy and peroxisomal disorders in Japan. International Journal of Neonatal Screening. 2021 Aug 25;7(3):58.
Kato K, Yabe H, Shimozawa N, Adachi S, Kurokawa M, Hashii Y, Sato A, Yoshida N, Kaga M, Onodera O, Kato S. Stem cell transplantation for pediatric patients with adrenoleukodystrophy: a nationwide retrospective analysis in Japan. Pediatric Transplantation. 2022 Feb;26(1):e14125.
Koto Y, Ueki S, Yamakawa M, Sakai N. Experiences of patients with metachromatic leukodystrophy, adrenoleukodystrophy, or Krabbe disease and the experiences of their family members: a qualitative systematic review. JBI evidence synthesis. 2024 Jul 1;22(7):1262-302.
Onuki T, Tajika M, Sugiyama Y, Shimura M, Ichimoto K, Tanaka T, Nyuzuki H, Kosuga M, Migita O, Ito T, Sasai H. Japanese experience of newborn screening for lysosomal storage diseases and adrenoleukodystrophy.
Miyoshi Y, Sakai N, Hamada Y, Tachibana M, Hasegawa Y, Kiyohara Y, Yamada H, Murakami M, Kondou H, Kimura-Ohba S, Mine J. Clinical aspects and adrenal functions in eleven Japanese children with X-linked adrenoleukodystrophy. Endocrine journal. 2010;57(11):965-72.
Sakurai K, Ohashi T, Shimozawa N, Joo-Hyun S, Okuyama T, Ida H. Characteristics of Japanese patients with X-linked adrenoleukodystrophy and concerns of their families from the 1st registry system. Brain and Development. 2019 Jan 1;41(1):50-6.
Takano H, Koike R, Onodera O, Sasaki R, Tsuji S. Mutational analysis and genotype-phenotype correlation of 29 unrelated Japanese patients with X-linked adrenoleukodystrophy. Archives of neurology. 1999 Mar 1;56(3):295-300.