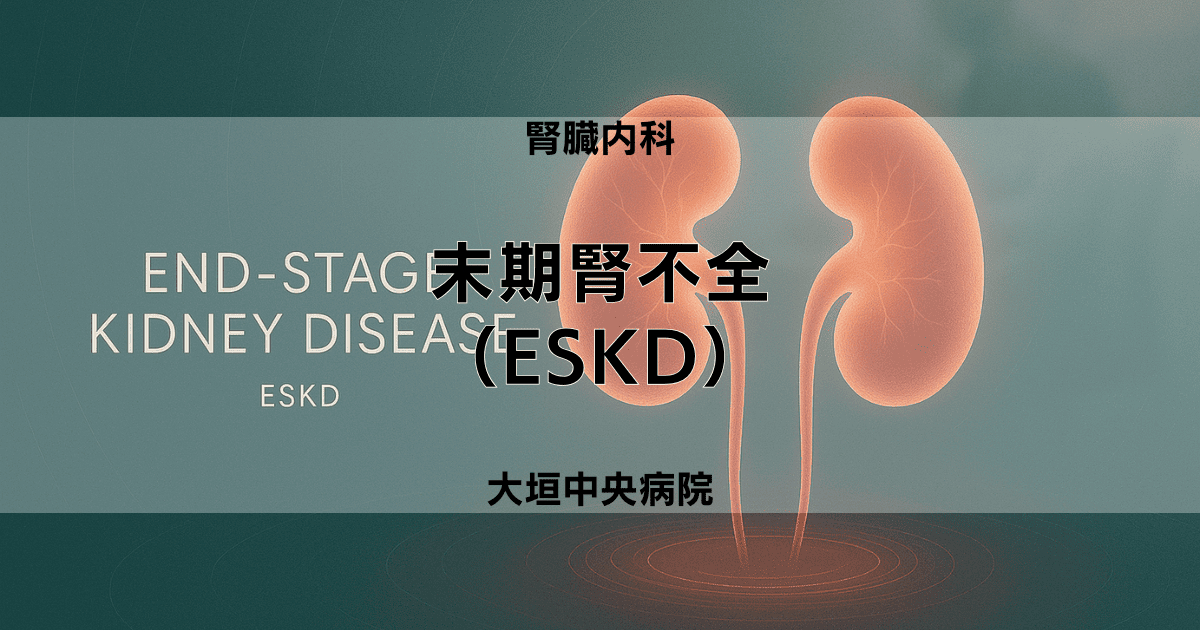末期腎不全(ESKD)とは、腎臓の機能が著しく低下し、体内の老廃物や水分、電解質のバランスを自力で十分に調整できなくなる段階で、腎臓のろ過能力を示す糸球体ろ過量(GFR)が極端に下がった状態が持続することで診断されます。
高血圧や糖尿病などの基礎疾患が長期間にわたり腎臓へダメージを与え続け、発症する場合が多いです。
人工透析や腎移植などの手段を含めた長期的な治療を視野に入れなければならない段階でもあり、早期の腎保護や合併症の管理が非常に重要です。
末期腎不全(ESKD)の病型
末期腎不全は、慢性腎臓病(CKD)の最終ステージとも呼ばれ、腎機能の著しい低下によって透析や腎移植を現実的に検討する段階ですが、そこに至るまでの背景にはいくつもの病型があります。
糸球体障害型
糸球体障害型は、腎臓のろ過機能を担う糸球体に炎症や硬化が起こる病態を指し、慢性糸球体腎炎や膠原病などに伴う自己免疫反応が長期にわたって続くことで組織が損傷を重ね、末期腎不全まで進むケースがみられます。
初期の段階であればステロイドや免疫抑制薬の使用によって進行をある程度抑制できる可能性がありますが、炎症が慢性化すると糸球体そのものが不可逆的な変性を起こし、GFRが極端に低下します。
・慢性糸球体腎炎が長期化している
・自己免疫異常を背景とする膠原病を合併している
・タンパク尿が持続的に増加する傾向がある
・組織検査で高度の糸球体硬化が認められる
糸球体障害型末期腎不全の主な特徴
| 特徴 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自己免疫反応や炎症が持続 | IgA腎症、膜性腎症、ループス腎炎など | 慢性化するとステロイドや免疫抑制薬でも進行を完全には止めにくい |
| 尿蛋白や血尿の長期持続 | 定期的な尿検査で蛋白量が増えていく | 治療経過を見ながら薬剤調整が欠かせない |
| 糸球体の不可逆的変性が進行 | 糸球体硬化や線維化が末期まで拡大 | 腎生検による診断が治療戦略に寄与する場合がある |
| 合併症のリスク増加 | 高血圧、心血管系合併症、貧血など | 多角的な管理とフォローアップが重要 |
血管障害・高血圧型
高血圧が長期に及ぶと腎臓の細小血管がダメージを受け、腎実質が硬化して血流が不足し、ろ過能力が大きく損なわれることがあります。
血管障害による腎硬化症が進行し、末期腎不全を起こすパターンは特に高齢者や糖尿病を合併する患者さんに多いです。
高血圧によって血管壁に強い圧力がかかると、血管の内皮細胞に微小な損傷が頻発し、修復反応を繰り返すうちに管腔が狭く硬くなるため、腎臓全体の血液供給量が低下します。
初期段階なら降圧薬や生活習慣の見直しで腎機能の安定が期待できますが、血圧コントロールがうまくいかないまま長い期間が経過すると腎のろ過機能が徐々に失われ、やがて透析や腎移植が選択肢となる末期に至るのです。
糖尿病性腎症型
糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症として代表的な存在であり、血糖コントロールが長年不十分だと毛細血管を介する腎臓組織に持続的な高血糖ダメージが蓄積します。
初期には微量アルブミン尿がみられ、そこからたんぱく尿の増加や腎機能の低下へと移行し、最終的に末期腎不全に至るリスクが高いです。
糖尿病性腎症は近年、透析導入の原因疾患として最も多い割合を占めると報告されています。
2型糖尿病であっても10年以上の罹病期間があれば腎障害を警戒する必要があり、合併症の予防や進行抑制のために食事療法や降圧薬、血糖降下薬などを組み合わせることが大切です。
遺伝性・その他の病型
多発性嚢胞腎などの遺伝性疾患では、腎臓に多数の嚢胞が形成されて機能が徐々に失われ、最終的に末期腎不全へ移行するケースがあり、ほかにも薬剤性腎障害や先天的な奇形など、多彩な要因が絡む場合もあります。
長期にわたって使用している薬が腎毒性を持つことが判明したときには、医師が定期的な血液・尿検査で腎機能を監視し、早めに使用量や薬剤の種類を変更することで進行を抑えられることがあります。
末期腎不全へ至る主な病型と発症リスク
| 病型名 | 代表的原因 | 発症リスクが高まる要素 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 糸球体障害型 | 慢性糸球体腎炎、膠原病 | 自己免疫反応、長期にわたる炎症 | ステロイドや免疫抑制薬の継続使用 |
| 血管障害・高血圧型 | 高血圧、動脈硬化 | 塩分過多、喫煙、メタボリックシンドローム | 血圧管理を怠ると急激に悪化する |
| 糖尿病性腎症型 | 血糖コントロール不良 | 高血糖期間の長期化、HbA1cが高い状態が続く | 早期の血糖管理とアルブミン尿検査が重要 |
| 遺伝性・その他 | 多発性嚢胞腎、薬剤性腎障害 | 家族歴、特定の薬剤を長期服用する環境 | レントゲンやCTなどの画像検査で形態変化を確認 |
末期腎不全(ESKD)の症状
末期腎不全は、慢性的に機能を損なわれた腎臓が遂にろ過や排泄の役割をほとんど果たせなくなる状態を意味します。初期から中期の段階は比較的症状が軽微なこともありますが、末期に近づくほど全身症状が顕著になりやすいです。
尿量と老廃物蓄積
末期腎不全では、尿量が極端に減ったりほとんど出なくなったりするケースが多々あり、体内に水分と老廃物が蓄積しやすくなります。
血液中のクレアチニンや尿素窒素(BUN)が大幅に上昇し、疲労感や倦怠感が強まる一方で、むくみや肺水腫などを起こすリスクが高まります。
また、余分なカリウムやリンが排泄されにくい状態になると、心臓や骨への悪影響が顕著になり、不整脈や骨粗鬆症が合併しやすいです。
末期腎不全時の尿量と老廃物蓄積に伴う代表的症状
・ほとんど尿が出ない(乏尿または無尿)
・血液検査でクレアチニンやBUNが高値を示す
・カリウムやリンの血中濃度が上昇しやすい
・体内の余分な水分が肺や組織に溜まり、呼吸困難や重度のむくみが出現する
貧血と酸塩基平衡異常
腎臓はエリスロポエチンという造血ホルモンの産生にも関与しているため、末期腎不全になるとエリスロポエチンの分泌量が不足し、重度の貧血を生じることがあります。
貧血は全身の組織に十分な酸素を運べなくする要因であり、疲労感や冷え、集中力低下などを助長します。
さらに腎臓は体内の酸塩基平衡を調整する役割も担っており、末期になると酸性物質の排泄が滞って慢性代謝性アシドーシスを発症しがちです。血液が酸性に偏ると、呼吸数が増加して息苦しさを感じたり、骨や筋肉にも悪影響が及んだりします。
末期腎不全による代表的な全身症状
| 症状 | 原因となる病態 | 影響や合併症 |
|---|---|---|
| 乏尿・無尿 | 腎ろ過能力の極度低下 | 水分・電解質バランス崩壊 |
| 重度貧血 | エリスロポエチン産生不足 | 倦怠感、虚弱、心負荷増大 |
| 高カリウム血症 | カリウム排泄不良 | 不整脈、心停止リスク |
| カリウム・リン・酸塩基バランス異常 | 老廃物や酸性物質の排泄困難 | 骨粗鬆症、アシドーシス |
| 皮膚のかゆみ | 老廃物蓄積や乾燥 | 皮膚トラブルや不眠 |
心血管系への負担
末期腎不全は心血管疾患リスクを大きく引き上げることが知られています。高血圧が進行すると心臓にかかる負荷が増し、心肥大や心不全を誘発しやすくなるほか、血管内皮障害が進んで動脈硬化が急速に進行するおそれがあります。
加えて高カリウム血症や貧血などは心臓への負荷を倍増させる原因となり、心筋梗塞や脳卒中などの合併症を起こすリスクにも直結します。
原因
末期腎不全を起こす直接的な要因は、長期間に及ぶ腎臓の機能低下ですが、背景にはさまざまな疾患やライフスタイル、遺伝的因子が存在し、複数の要素が組み合わさることで末期への移行を早めるケースがあります。
糖尿病と高血圧の相互影響
糖尿病と高血圧は、それぞれが腎機能を低下させる独立したリスクでありながら、両者が併存すると相乗的に腎臓を傷害し、末期腎不全へ至る速度を早めると考えられています。
糖尿病性腎症では血糖値が慢性的に高いことで糸球体に負荷がかかる一方、高血圧が加わるとさらに血管障害が深刻化し、腎血流が低下して糸球体硬化が急速に進行する恐れがあります。
・糖尿病性腎症の発症リスクを高めるHbA1cの高値が続く
・高血圧で血管が硬くなり腎臓への血液供給量が減る
・両疾患を同時に抱えると末期化が加速しやすい
2つの疾患が連動して重い腎障害を生み出すため、血糖コントロールと降圧療法を同時に進めることが非常に大切です。
免疫関連疾患と慢性炎症
自己免疫疾患や慢性炎症を伴う病気(関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど)は、糸球体に影響を及ぼすことがあり、長期間にわたって炎症が続くと組織が繊維化して回復しにくくなる場合があります。
膠原病による腎障害であるループス腎炎などは、治療を受けても悪化を繰り返して最終的に末期腎不全を起こすケースがみられます。
末期腎不全に関わる主な要因とメカニズム
| 原因分類 | 具体的要因 | 腎機能低下のメカニズム |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 血糖値の慢性的な上昇 | 糸球体への高濃度グルコース負荷と毛細血管障害 |
| 高血圧 | 長期にわたる血管への圧力負荷 | 腎血管の硬化と血流低下 |
| 免疫疾患 | 膠原病、自己免疫性腎炎 | 糸球体における免疫複合体沈着や持続的炎症 |
| 薬剤性障害 | 腎毒性のある薬剤の長期服用 | 尿細管や糸球体の直接的な損傷 |
| 遺伝性疾患 | 多発性嚢胞腎など | 嚢胞増大や構造的異常による腎組織破壊 |
| その他のライフスタイル | 塩分過多、喫煙、アルコール多量摂取など | 血圧上昇や血管機能低下を通じた腎ダメージ |
薬剤や毒性物質の蓄積
鎮痛薬や抗がん剤、免疫抑制薬などの一部は腎毒性を持つことがあり、長期間あるいは高用量で使うと腎障害を進行させやすいです。
また、特定の重金属や農薬に曝露される環境にいる場合も、腎臓に慢性的なダメージが加わり、末期腎不全に至るリスクが高くなります。
鎮痛薬の長期使用で起こる間質性腎炎は、初期には明確な症状が出にくく、気づいたときには腎不全が進んでいることがあります。
また、職業的に有害化学物質を扱う場面でも、腎機能チェックを怠ると自覚症状のないままに進行していることがあるため注意が必要です。
遺伝的要素や加齢
多発性嚢胞腎のように明確な遺伝子異常で起こるケースがあるほか、加齢による腎機能の自然な低下がベースにあり、そこへ高血圧や糖尿病が重なることで一気に末期腎不全へ傾くパターンもみられます。
高齢者では腎臓の予備力が低いため、病気の進行が速く、透析導入の年齢が上がっている現状も指摘されています。
末期腎不全(ESKD)の検査・チェック方法
末期腎不全の診断や治療方針を決定するにあたっては、血液検査や尿検査をはじめとする基本的な検査だけでなく、腎臓の形態や血行動態を確認する画像検査などを総合的に活用することが欠かせません。
血液検査
末期腎不全かどうかを判断するうえで重要なのが血清クレアチニン値と推算GFR(eGFR)です。
クレアチニンは筋肉由来の老廃物で、腎機能が著しく低下すると血液中に蓄積しやすくなり、その値が高いほど腎のろ過能力が落ち込んでいると考えられます。
さらにeGFRは、性別や年齢、血清クレアチニン値などから算出し、腎臓が1分間に何ミリリットルのろ過を行えるかの目安を示します。
末期腎不全と診断される段階では、eGFRが15未満や10未満にまで低下しているケースが多く、症状の重篤度と照らし合わせて透析や移植を検討します。
・クレアチニンが通常の基準値を大きく超える
・eGFRが15未満かそれに近い値で推移する
・加齢や性差で補正した計算式を用いる
尿検査
尿検査も末期腎不全の状態を評価する際に欠かせない検査です。特に尿蛋白の量や尿アルブミンの測定、尿沈渣での円柱や赤血球の有無をチェックすることで、糸球体の障害や出血性の変化がどれほど進んでいるかを把握できます。
中には尿量が極端に減ってしまうため十分なサンプルを採取しづらい場合もありますが、それでも少量の尿からでも何らかの手掛かりを得られることがあるため、医療現場では根気強く検体を確保しようとすることが多いです。
末期腎不全の主な検査項目
| 検査名 | 主な目的 | 代表的な評価指標 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 腎機能(クレアチニン、BUN、電解質)を数値化 | eGFR、血中カリウム、リン、酸塩基平衡 |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿アルブミン、尿沈渣で腎損傷を評価 | 尿蛋白定量、尿沈渣での円柱の種類 |
| 画像検査(超音波) | 腎臓の大きさや形状、嚢胞の有無などを観察 | 腎萎縮、嚢胞、腎結石 |
| 画像検査(CT/MRI) | 血管や周囲臓器との関係、構造的異常を詳細に把握 | 血流評価、腫瘍の検出 |
| 腎生検 | 糸球体や尿細管を直接観察 | 病理学的診断(線維化、炎症の程度) |
画像検査
腎エコー(超音波検査)は侵襲性が低く、腎臓の大きさや実質の厚み、血流状態をある程度把握できる有用な手段です。
末期腎不全の段階では、腎臓が萎縮し実質が薄くなっていることが多く、また多発性嚢胞腎などの場合は多数の嚢胞が確認されることがあります。
また、CTやMRIを用いると、腎動脈の狭窄や腫瘍、血流障害の程度をより詳細に評価できるため、病型の特定や手術的治療の計画に役立ちます。
腎生検と意義
腎生検は、実際に腎臓の組織を採取して顕微鏡で観察する検査であり、糸球体の炎症や硬化の有無、免疫反応の様子などを直接評価できます。
末期腎不全まで進行しているケースでは、腎生検を実施しても得られる情報が限られる場合やリスクが大きい場合もありますが、ステージが移行期の段階で腎生検を行うと、病型の確定診断や薬物療法を選択するための重要な資料です。
末期腎不全を含む重症度が高い腎障害で検討されることが多い検査
・腎エコーで大きな萎縮や嚢胞、結石を確認
・CT/MRIで血流や腎組織の詳細を調べ、手術の適応や合併症を確認
・腎生検は末期近くでリスクがあるため、移行期や疑問点が残る場合に慎重に実施
末期腎不全(ESKD)の治療方法と治療薬について
末期腎不全では、体内の水分や電解質を腎臓だけで調整することがほぼ不可能に近くなるため、人工透析や腎移植などの集中的な治療法を検討する時期に入ります。
血液透析(HD)と腹膜透析(PD)
末期腎不全の代表的な治療法が血液透析(HD)と腹膜透析(PD)で、血液透析は、体外に血液をくみ出して透析装置で老廃物と余分な水分を除去し、浄化された血液を体内に戻す方法であり、週に複数回の通院が必要になることが多いです。
腹膜透析は、自分の腹腔を膜として利用し、透析液を体内に注入・排出するサイクルを繰り返すことで老廃物を除去します。通院頻度が減る利点がある一方で、自宅管理や感染防止などの課題が伴います。
血液透析と腹膜透析の比較
| 項目 | 血液透析(HD) | 腹膜透析(PD) |
|---|---|---|
| 実施場所 | 透析センターや病院の透析室 | 自宅で行うケースが多い |
| 透析頻度 | 週2~3回程度、1回あたり4時間前後 | 1日数回の透析液交換、もしくは就寝時の自動装置使用 |
| メリット | 医療スタッフが管理するため安全面での安心感がある | 自由度の高い生活が送りやすい、通院頻度が少ない |
| デメリット | 通院回数が多く拘束時間が長い | 手技ミスや感染症リスクがある、自宅管理の負担が大きい |
腎移植
腎移植は、ドナーから提供された健常な腎臓を移植して、外部の透析機能に依存しない生活を目指す方法です。
移植が成功すれば腎臓が本来の機能を取り戻す可能性がありますが、ドナーの確保や術後の拒絶反応対策など、乗り越えなければならない課題が少なくありません。
免疫抑制剤を生涯にわたって服用し続ける必要があるため、感染症リスクも上がりますが、移植を選ぶことで生活の質が向上する場合が多いです。
・提供者が生体ドナーか脳死ドナー・心停止ドナーかによって待機期間や手術の難易度が変化
・術後は免疫抑制薬の種類と用量を細かく調節しながら拒絶反応を最小限に抑える
・腎移植が成功した後も定期的に外来通院して血液検査や尿検査を継続する
薬物療法
末期腎不全の状態でも、残っている腎機能を活かすために薬物療法を並行して行うケースが多くあります。ACE阻害薬やARBなどの降圧薬は、血圧をコントロールするだけでなく、蛋白尿を軽減する効果も期待できます。
利尿薬を使って体内に余分な水分が溜まらないように管理することもあり、むくみや肺水腫などを抑えるために有用です。さらにエリスロポエチン製剤や鉄剤を用いて貧血の改善を図ることで、疲労感や倦怠感を軽減する試みも行われます。
末期腎不全の薬物療法
| 薬剤の種類 | 主な目的 | 使用上の注意 |
|---|---|---|
| ACE阻害薬、ARB | 血圧コントロール、蛋白尿の軽減 | 低血圧や高カリウム血症に注意 |
| 利尿薬(ループ系等) | 余分な水分・ナトリウムの排出促進 | 血液量の変動や電解質異常に留意 |
| エリスロポエチン製剤 | 貧血の改善 | ヘモグロビン値の上昇幅を定期的にチェック |
| リン吸着薬 | リン過剰をコントロール | 便秘や胃腸障害に注意する必要がある |
| ビタミンD製剤 | 骨ミネラル代謝改善 | 高カルシウム血症や腎結石に注意 |
食事療法とミネラル管理
末期腎不全の治療においては、薬物療法と同じくらい食事管理が重視されます。塩分やたんぱく質、カリウム、リンなどの摂取量をコントロールしなければならない場合が多く、透析を行っていても制限が必要になることがあります。
特にカリウム過剰は心拍異常につながりやすく、リン過剰は骨や血管の石灰化を促すため、専用のリン吸着薬を活用することも選択肢です。
末期腎不全時に意識することが多い食事のポイント
・塩分摂取を控え、むくみと高血圧を防ぐ
・たんぱく質は体重や透析頻度に応じて適切に制限する
・野菜や果物はカリウムの含有量に留意しながら計算して摂取する
・リンの多い加工食品や乳製品を摂り過ぎないよう調整する
治療期間
末期腎不全の治療は、基本的に長期にわたる継続管理が前提です。腎移植によって機能回復が得られる場合もありますが、多くの患者は透析を生活の一部として続けざるを得ず、治療期間は事実上、生涯にわたります。
透析治療の長期性
透析を導入すると、週に数回の通院で血液透析を行う方法か、または自宅で腹膜透析を行う方法を継続する形になり、これを止めてしまうと体内に老廃物や水分が急速に蓄積し、生命の維持が困難になります。
一度透析が開始されると病状が改善して腎機能が回復しない限り、ずっと透析を続ける必要があるのです。
透析導入後のスケジュール
| 時期 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 透析導入時 | 週2~3回の血液透析開始 or 腹膜透析開始 | 老廃物と水分除去による生命維持 |
| 数カ月後 | 透析の適応やスケジュール調整 | 過剰除水や低血圧を防ぎ、生活リズムを安定させる |
| 長期継続中 | 定期的な血液検査・画像検査 | 合併症予防や食事・薬物療法の見直し |
| 腎移植の検討段階 | ドナー探しや術前評価を進める | 透析依存からの解放と生活の質向上 |
| 腎移植後 | 拒絶反応チェック、免疫抑制薬の調整 | 移植腎の機能維持、長期安定 |
腎移植後のフォローアップ
腎移植が成功した場合も、移植腎が拒絶反応を起こさないように免疫抑制薬を継続しながら定期的な通院と検査を受ける必要があります。
移植後数年たってからでも慢性拒絶が進むことがあり、移植腎の機能が再び低下してしまうリスクがあるため、一度移植がうまくいってもフォローアップは生涯にわたって大切です。
合併症との付き合い方
末期腎不全では、心血管疾患や骨ミネラル代謝異常、貧血など複数の合併症が同時進行することが珍しくありません。
降圧薬やリン吸着薬、骨を守るための活性型ビタミンD製剤などを続けることで合併症の進行をなるべく抑え、透析治療や移植後の生活を安定させることにつなげます。
・高血圧や糖尿病のコントロールを怠ると心不全や脳血管障害を併発しやすい
・リンやカルシウムのバランスを崩すと骨粗鬆症が進行し、骨折リスクが高くなる
・貧血や栄養不良が長引くと身体活動量が下がり、筋力の低下を招く
副作用や治療のデメリットについて
末期腎不全は生命維持に直結する深刻な状態であるため、積極的な治療が必要ですが、副作用や日常生活への負担増が避けられないケースも多々あります。
降圧薬や利尿薬の副作用
腎機能が大きく低下している患者は血圧管理が難しく、ACE阻害薬やARB、利尿薬などを使用するときには投与量や使用方法に注意を要する場面が増えます。
ACE阻害薬やARBは腎保護効果も期待できますが、特に高カリウム血症が起こりやすくなるなどのリスクを伴い、利尿薬は過度な除水によって脱水や低血圧を起こす可能性があります。
副作用は、めまいや倦怠感、カリウムやナトリウムのバランス異常が代表的です。定期的な検査で電解質と血圧をチェックしながら細かく薬剤の調整を行います。
透析による合併症と制約
血液透析には大きな効果がありますが、長時間安静にして血液を体外に循環させるため、低血圧や血栓、出血などのトラブルが起こりえます。
透析終了後は疲労感や頭痛を感じる人も少なくなく、週複数回の通院によるスケジュールの制約や通院交通の負担、待合時間の長さなどが日常生活の自由度を下げる要因にもなります。
腹膜透析の場合は自宅で実施できるメリットがある一方、カテーテル挿入部からの感染リスクや腹部に溶液を入れている不快感などが問題になることがあります。
また、腹腔内圧の上昇により臍ヘルニアなどのリスクが高まるケースもあり、手技そのものの習得が必要であることから精神的・身体的ハードルがあるのも事実です。
透析治療のデメリットと合併症
| 治療法 | デメリット・合併症 | 対応・注意点 |
|---|---|---|
| 血液透析 | 週数回の通院負担、低血圧、血栓リスクなど | セッション前後の水分・食事管理、バスキュラーアクセスのケア |
| 腹膜透析 | カテーテル部位感染、腹膜炎リスク、操作ミス | 手技の正確な学習と清潔操作の徹底 |
エリスロポエチン製剤の副作用
末期腎不全では貧血対策としてエリスロポエチン製剤を使うケースが多いですが、過剰に投与すると血液の粘度が上昇し、血栓症のリスクが高まる可能性があります。
また、急速にヘモグロビン値が上昇すると高血圧を助長する恐れもあるため、医師は投与量を慎重に設定し、定期的に血液検査を実施してヘモグロビンレベルを監視することが大切です。
末期腎不全(ESKD)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
透析治療の費用
血液透析の場合は週2~3回通院し、1回あたり数千円~1万円前後の自己負担が発生するケースがあります。腹膜透析では透析液やカテーテル管理にかかる費用が定期的に生じ、月単位で見ると数万円程度の自己負担です。
| 治療項目 | 自己負担の目安 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 血液透析(1回) | 数千円~1万円前後 | 週3回の場合、月あたり数万円に達することがある |
| 腹膜透析(1カ月) | 数万円程度になることも | 透析液や交換キット、カテーテル管理など |
| 腎移植手術 | 数十万円ほどの負担になる場合がある | 術式やドナー状況、入院期間により大きく変動 |
| 腎移植後の管理 | 数千円~数万円 | 免疫抑制剤や定期的な検査費 |
薬剤費の負担
降圧薬や利尿薬、リン吸着薬、エリスロポエチン製剤など、末期腎不全では複数の薬剤を併用するケースが多いため、薬剤費も月あたり数千円から数万円程度です。
エリスロポエチン製剤は注射や自己注射キットが必要な場合もあり、その分費用が加算されます。
腎移植における費用
腎移植手術を受ける場合、手術費用や入院費用、術後の経過観察などで一時的にまとまった出費となる可能性がありますが、保険適用により負担が軽減されることが一般的です。
術後には免疫抑制剤を服用し続ける必要があるため、薬剤費が継続的な支出になります。
以上
参考文献
Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, Hishida A, Matsuo S. Kidney disease screening program in Japan: history, outcome, and perspectives. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2007 Nov 1;2(6):1360-6.
Ishikura K, Uemura O, Hamasaki Y, Ito S, Wada N, Hattori M, Ohashi Y, Tanaka R, Nakanishi K, Kaneko T, Honda M. Progression to end-stage kidney disease in Japanese children with chronic kidney disease: results of a nationwide prospective cohort study. Nephrology Dialysis Transplantation. 2014 Apr 1;29(4):878-84.
Matsushita K, Chen J, Sang Y, Ballew SH, Shimazaki R, Fukagawa M, Imai E, Coresh J, Hishida A. Risk of end-stage renal disease in Japanese patients with chronic kidney disease increases proportionately to decline in estimated glomerular filtration rate. Kidney international. 2016 Nov 1;90(5):1109-14.
Tsukamoto Y. End-stage renal disease (ESRD) and its treatment in Japan. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008 Aug 1;23(8):2447-50.
Yamagata K, Yagisawa T, Nakai S, Nakayama M, Imai E, Hattori M, Iseki K, Akiba T. Prevalence and incidence of chronic kidney disease stage G5 in Japan. Clinical and experimental nephrology. 2015 Feb;19:54-64.
Hasegawa T, Sakamaki K, Koiwa F, Akizawa T, Hishida A, CKD-JAC Study Investigators. Clinical prediction models for progression of chronic kidney disease to end-stage kidney failure under pre-dialysis nephrology care: results from the Chronic Kidney Disease Japan Cohort Study. Clinical and experimental nephrology. 2019 Feb 15;23:189-98.
Fukuma S, Ikenoue T, Shimizu S, Norton EC, Saran R, Yanagita M, Kato G, Nakayama T, Fukuhara S. Quality of care in chronic kidney disease and incidence of end-stage renal disease in older patients: a cohort study. Medical care. 2020 Jul 1;58(7):625-31.
Usami T, Koyama K, Takeuchi O, Morozumi K, Kimura G. Regional variations in the incidence of end-stage renal failure in Japan. Jama. 2000 Nov 22;284(20):2622-4.
Yang CW, Harris DC, Luyckx VA, Nangaku M, Hou FF, Garcia GG, Abu-Aisha H, Niang A, Sola L, Bunnag S, Eiam-Ong S. Global case studies for chronic kidney disease/end-stage kidney disease care. Kidney international supplements. 2020 Mar 1;10(1):e24-48.
Gupta R, Woo K, Jeniann AY. Epidemiology of end-stage kidney disease. InSeminars in vascular surgery 2021 Mar 1 (Vol. 34, No. 1, pp. 71-78). WB Saunders.