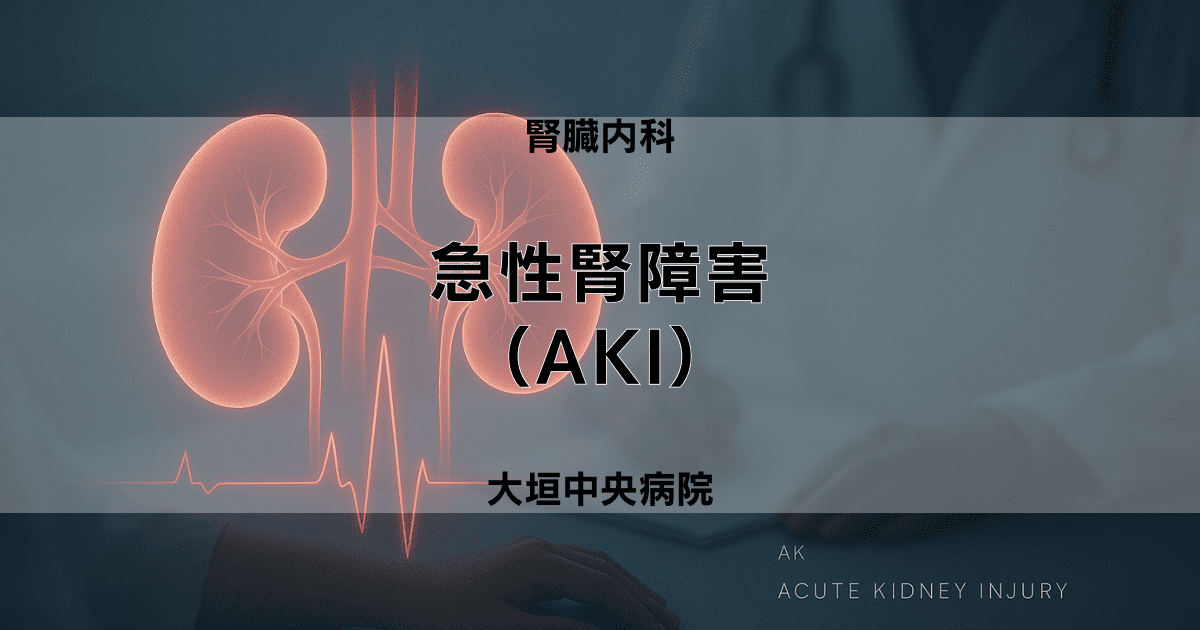急性腎障害(AKI)とは、腎臓が急激に機能低下を起こし、体内の老廃物や余分な水分をうまく排泄できなくなる病態です。
数日から1週間ほどの短期間で腎機能が明らかに悪化すると、電解質バランスの異常や体液の過剰な貯留などが生じて、さまざまな合併症につながりやすくなります。
比較的軽度な状態であれば腎機能が回復する可能性もありますが、重症化した場合は生命の危機に直結するケースもあるため、早めに正しい知識を得て、適切な検査・治療を受けることが重要です。
急性腎障害(AKI)の病型
急性腎障害(AKI)は、腎臓の血流低下によるものや腎臓そのものに直接起こる障害、または尿路の閉塞など、原因となる部位の違いで大きく分類できます。
腎臓は血液をろ過して老廃物を排泄し、体内の水分や電解質のバランスを保つ働きを担っていますが、短期間に何らかのトラブルが起こると急性腎障害が発症します。
腎前性AKIとは何か
腎前性AKIは、心臓から腎臓への血液の循環が何らかの要因で低下して、腎機能が急激に落ち込むタイプです。
血液量が減少している状態や、心臓のポンプ機能の低下によって腎臓に行き渡る血液量が少なくなる場合に発生し、大量出血で循環血液量が足りなくなったり、心不全で末梢の循環不良が起こると、腎臓への血流が減り、急性腎障害につながります。
腎前性AKIの原因
- 大量出血や脱水による循環血液量の著しい減少
- 重症感染症や敗血症による血圧低下
- 心筋梗塞や重度の不整脈などで心拍出量が著しく低下した場合
- 高度の低血圧が続いて腎血流が十分に確保されない状態
腎前性AKIは、血流低下を補う治療や対処が早ければ、比較的良好に腎機能が回復する可能性がありますが、急激な低血圧や循環不全が長期間続くと、腎臓へのダメージが大きくなりやすいです。
腎実質性AKIと主な病態
腎実質性AKIは、腎臓を構成する組織そのもの(糸球体や尿細管など)が直接障害を受けて急性腎障害が起こる病型です。
腎前性AKIが悪化して腎臓の組織が傷つく場合もありますし、特定の薬剤や重度の感染症が原因となることもあり、急性尿細管壊死(ATN)が代表的な病態として知られています。
| 病態名 | 特徴的な要因や発症メカニズム |
|---|---|
| 急性尿細管壊死(ATN) | 腎虚血や腎毒性物質によって尿細管が障害され、糸球体でろ過された液が再吸収されにくくなる |
| 急性間質性腎炎 | 薬剤やアレルギー反応が原因で腎間質の炎症が急激に起こり、腎機能が低下する |
| 急性糸球体腎炎 | 糸球体が炎症を起こし、ろ過機能が急激に低下する |
| 放射線性腎障害 | 高線量の放射線被曝によって腎細胞がダメージを受ける |
このように腎実質性AKIは、腎臓組織の直接的な損傷が鍵になります。急性尿細管壊死(ATN)は血液供給の不足や腎毒性物質の影響で尿細管上皮細胞が壊れてしまうため、症状が進行すると急激にろ過機能が落ちてしまいます。
薬剤性急性間質性腎炎は、薬が引き金となるアレルギー反応によって腎間質が炎症を起こすことで発症します。
腎後性AKIが起こる仕組み
腎後性AKIは、腎臓から排泄される尿の通り道に閉塞や狭窄が生じ、最終的に腎臓の機能が阻害されるパターンです。
尿路系は腎盂、尿管、膀胱、尿道と続いていますが、どこかがふさがると尿が逆流し、腎臓に圧力がかかり続けて機能障害が進行します。
結石や腫瘍、前立腺肥大症などが原因となりやすく、両側の尿路がふさがるか、片側しかない腎臓の尿管が閉塞するケースで急性腎障害が顕著です。
腎後性AKIの場合、閉塞を取り除く治療がうまく進めば腎機能が回復することもありますが、高い圧力に長くさらされると尿細管のダメージが深刻化し、回復まで時間がかかったり、改善が限定的になったりするケースもあるので注意が必要です。
病型ごとの主な特徴と注意点
病型によって発症メカニズムや治療アプローチが異なるため、早期に原因を正しく特定することが大切です。
腎前性AKI、腎実質性AKI、腎後性AKIそれぞれは独立して存在するというより、ある病型が悪化して別の病型を起こすという連鎖も否定できず、特に、腎前性AKIが長引いて腎実質性AKIを併発するケースは多く、複雑な経過をたどりやすいです。
いずれのタイプでも「急激に腎機能が低下している」という点を見逃さず、速やかな検査と対処が肝心になります。
症状
急性腎障害(AKI)は、何らかの要因で数日から1週間程度で腎機能が急激に低下する病態ですが、その症状は多岐にわたります。
初期には目立った異常を感じにくいケースもありますが、進行すると排尿量の変化やむくみ、高血圧などが生じてきます。
典型的な排尿量の変化
急性腎障害で特徴的な症状として、排尿量の変化が挙げられ、急激に腎機能が低下すると、体内のろ過や再吸収・排泄の調整がうまくいかなくなり、以下のような排尿量の異常が起こりやすいです。
- 尿量が急に減少し、1日に500mL以下になる乏尿
- 1日に50mL以下にまで激減する無尿
- 反対に多尿になることもある
乏尿や無尿になると、老廃物や余分な水分が体内に蓄積しやすくなり、むくみや血圧上昇を招きやすくなります。
急性期を過ぎた回復期に多尿になるケースもあり、その場合には大量の水分や電解質が尿中に失われることで脱水や電解質異常を起こす可能性があるため注意が必要です。
むくみと血圧上昇をチェックする
腎臓の機能が落ちると、ナトリウムや水分の排泄が滞り、体内に水分が過剰にたまってしまう状況が起こりやすくなり、足や顔にむくみが出たり、血圧が上昇したりすることが少なくありません。
| 代表的な症状 | 起こりやすい原因や背景 |
|---|---|
| 足や顔のむくみ | 余分な水分・塩分が体内に滞り、血管外へ水分が漏出しやすくなる |
| 血圧上昇 | 体液量が増加することで循環血液量が増え、血圧が高くなる |
急性腎障害がさらに進むと、胸水や腹水が溜まる重篤な状態へ移行してしまう場合もあり、むくみや血圧上昇は日常的にも確認しやすい変化なので、こうした異常が続くときは早めの受診が重要です。
尿毒症状に注意を向ける
腎機能が低下すると、老廃物が血液中に蓄積して全身に悪影響を与え、いわゆる尿毒症状と呼ばれる状態では、次のような全身症状がみられます。
- 食欲不振
- 悪心や嘔吐
- 倦怠感や頭痛
- 意識がはっきりしない
尿毒症状の中には、脳機能にまで影響が及ぶケースもあり、重症になると意識レベルの低下や痙攣などが見られます。
一般的な風邪や疲労とも混同しやすい部分がありますが、急性腎障害では急速に症状が悪化する可能性が高いため、状況を冷静に判断して医療機関へ相談することが大切です。
皮膚や神経系にも及ぶ影響
急性腎障害では、皮膚や神経系にも多様な影響が及ぶことがあり、腎臓の機能低下により電解質バランスが崩れると、かゆみや筋肉のけいれん、手足のしびれなどが発生しやすくなります。
また、重篤な状態になると呼吸困難や不整脈を伴うこともあり、身体のあらゆる機能に悪影響を与える可能性があります。
とくに電解質異常が急に進行すると心臓に負担をかけ、不整脈や心停止のリスクが高まるため、医療の現場では迅速かつ的確な対応が必要です。
急性腎障害(AKI)の原因
急性腎障害(AKI)の原因は多岐にわたり、腎臓そのものに直接ダメージを与える病態だけではなく、体全体の血液循環障害や薬剤性の影響、尿路の閉塞など、さまざまな要素が絡み合う場合もあります。
循環血液量の低下や低血圧
急性腎障害のなかでも、腎前性AKIは全身の血液循環が不十分になって腎臓への血流量が著しく低下することで起こり、大怪我による大量出血や、激しい下痢や嘔吐で体液が失われる脱水、重症感染症による血圧低下などが代表的な引き金です。
このような状況下で腎臓に運ばれる血液量が激減すると、老廃物のろ過機能を保ち続けることが困難になり、急激な腎障害を招きます。
循環血液量の低下は心不全や重度の不整脈による心拍出量低下も含まれるため、心疾患と合わせて注意が必要です。
- 交通事故などによる外傷性の大量出血
- 激しい嘔吐や下痢で水分不足に陥る脱水
- 心筋梗塞や重症不整脈による心拍出量の減少
- 敗血症(セpsis)に伴う血圧の大幅な低下
薬剤や毒性物質による腎障害
急性腎障害の原因として、特定の薬剤や毒性物質が腎臓の組織に直接ダメージを与えるケースが挙げられます。
抗生物質や消炎鎮痛薬、造影剤など、医療に欠かせない薬剤が腎臓に負担をかけることもあり、患者さんの既存の腎機能や体液バランスによっては急性腎障害が発症しやすいです。
また、農薬や重金属、溶剤などの毒性物質が体内に入り込む機会がある環境下では、腎臓がフィルターとして機能する過程で組織に負荷がかかり、急性腎障害へつながる場合もあります。
| 薬剤・物質 | AKIを引き起こすメカニズムの一例 |
|---|---|
| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 腎血流の制御を妨げる作用があり、ろ過圧が低下しやすくなる |
| 抗生物質(アミノグリコシド系など) | 尿細管の細胞に毒性を持ち、障害を引き起こす |
| 造影剤 | 腎血管の収縮や尿細管への負担により、急性腎障害が生じる場合がある |
| 重金属(鉛、水銀など) | 腎組織に蓄積し、細胞を変性や壊死へ導く |
医療機関では造影剤の使用時や特定の抗生物質を用いる場合、腎機能検査を行いながら慎重に投与量を調整しますが、持病や基礎疾患を抱えている方は特に注意が必要です。
尿路閉塞による腎後性AKI
腎臓でろ過された尿がスムーズに排泄されず、尿路のどこかがふさがると、尿の逆流や圧力上昇によって腎機能が低下し、結石や腫瘍が尿管をふさいだり、前立腺肥大で尿道付近が閉塞したりするケースが代表的です。
両側の尿路が同時にふさがるか、単腎(片側しか腎臓がない)の方の尿管が障害されると、短期間で急性腎障害が生じる恐れがあります。
既存の疾患や高齢者におけるリスク
既に慢性的な腎疾患を抱えている方や、高血圧や糖尿病、心疾患などで腎臓に負担がかかりやすい方は、急性腎障害を発症するリスクが高くなります。
特に高齢者は加齢に伴って腎機能が低下していることも多く、適度な水分補給や定期的な検査を行わないと、ちょっとした脱水や感染症で腎臓に大きなダメージが及ぶ可能性があります。
検査・チェック方法
急性腎障害(AKI)は、短期間で腎機能が低下する厄介な病態ですが、検査と評価を行うことで正確な診断を下し、迅速に治療方針を立てられます。
血液検査で腎機能を把握する
血液検査は、急性腎障害の診断において基本的な位置づけを持ち、血液中のクレアチニンや尿素窒素(BUN)を調べることで、腎臓のろ過機能が低下しているかどうかを短時間で把握しやすいです。
- 血清クレアチニン(sCr)値の上昇
- BUN/クレアチニン比の変化
- 電解質(ナトリウムやカリウムなど)の異常
指標は腎機能を推測するための重要な数値ですが、クレアチニンやBUNは個人差や筋肉量、栄養状態などの影響を受けやすいため、総合的な判断が必要です。
また、急性期には急激に数値が上がる前に異常が隠れていることもあるため、定期的な採血や他の検査との組み合わて行います。
尿検査と尿沈渣観察のポイント
急性腎障害の診断では尿検査も欠かせません。尿タンパク、尿潜血、尿中の電解質濃度などをチェックするだけでなく、顕微鏡で尿沈渣を観察することで尿細管障害の兆候や結晶の有無が確認できます。
| 尿検査項目 | 主な意味・特徴 |
|---|---|
| 尿比重・浸透圧 | 腎臓の尿濃縮機能を推定する指標 |
| 尿タンパク | 糸球体や尿細管レベルの障害の目安 |
| 尿潜血 | 血尿の有無をチェックし、腎実質障害などを推定 |
| 尿沈渣 | 円柱(顆粒円柱や赤血球円柱)や結晶の存在を確認 |
超音波検査での観察
超音波検査(エコー)は、腎臓や尿路の構造を非侵襲的に確認できるため、急性腎障害の原因究明にも役立ち、腎臓の大きさや形態的な異常、腎結石や腎腫瘍の有無、さらには尿管が拡張していないかなどを探ることができます。
とくに腎後性AKIの可能性がある場合、超音波検査で腎盂や尿管の拡張がみられれば、尿路閉塞を疑う重要な手がかりです。
- 腎臓のサイズが縮小していないか、あるいは腫れがないか
- 腎結石や結晶の存在
- 水腎症(腎盂の拡張)の有無
いろいろな所見を短時間で安全に確認できる点が超音波検査の利点です。
CTやMRIを用いた詳細検査
超音波検査だけでは原因が特定しにくい場合、CTやMRIなどの画像検査でより詳細な情報を得ます。
造影剤を使うCT検査では、腎血流や腎実質の状態をしっかり把握できますが、腎機能が低下した状態での造影剤使用は腎障害の悪化リスクがあるため、医師がメリットとデメリットを比較検討しながら実施可否を判断します。
MRIは放射線被曝がなく、軟部組織の評価に優れますが、金属インプラントがある方などには注意が必要です。
急性腎障害(AKI)の治療方法と治療薬について
急性腎障害(AKI)の治療は、発症原因や病型によって異なるアプローチが必要で、早期に正しい診断を行い、病態を引き起こしている要因を取り除くとともに、腎機能をサポートする治療を受けることで回復を期待できる場合もあります。
原因除去と輸液管理
急性腎障害の治療では、まず原因除去が基本方針で、脱水や低血圧が原因であれば、輸液による循環血液量の回復を図ります。感染症がある場合は抗生物質を使用し、心不全が背景にある場合は心機能を安定化させる薬剤治療を行います。
一方で、腎毒性を持つ薬剤の使用が疑われる際には、早急に投与を中止したり別の薬剤に切り替えたりします。
- 循環血液量の確保のための輸液
- 必要に応じた抗生物質や心不全治療薬
- 腎毒性薬剤の早期中止や代替
患者さんの体液バランスを整えながら、血圧や電解質の維持を図るために、静脈点滴を用いるケースが多いです。
薬物療法の実際と注意点
急性腎障害の薬物療法は、病態の進行を抑えるとともに腎臓への負担を軽減することを目指します。
例えば利尿薬は、腎臓が十分に機能していれば水分排出を促す目的で用いることがありますが、急激な血圧低下や循環量の減少を避けるためにも慎重な投与が求められます。
また、カリウムやリンなどの電解質異常が重篤化すると致命的な合併症を起こすことがあるため、レニン-アンジオテンシン系阻害薬やカリウム吸着薬などを状況に応じて使用します。
| 治療薬 | 目的・特徴 |
|---|---|
| 利尿薬(フロセミドなど) | 尿量を増やし、体内の水分や電解質バランスを調整(ただし病態によっては慎重投与) |
| 降圧薬 | 高血圧状態をコントロールし、腎臓への過度なストレスを軽減 |
| カリウム吸着薬 | 高カリウム血症を改善し、不整脈のリスクを低減 |
| リン吸着薬 | 高リン血症を抑えて骨代謝障害を防止 |
| エリスロポエチン製剤 | 貧血が顕著な場合に赤血球産生を補助(急性期にはあまり使用しない場合も) |
特にカリウムが上昇すると不整脈を誘発し、突然死のリスクが高まるため、こまめな血液検査と必要な薬剤投与によるコントロールを重視します。
尿路閉塞の解除や外科的処置
腎後性AKIの場合、結石や腫瘍による尿路閉塞を取り除くことが治療の大きな柱で、尿管ステントや腎瘻チューブを挿入して尿の流れを確保したり、結石砕石術(ESWL)や内視鏡的手術などで結石を除去したりする処置を行います。
透析療法を検討するタイミング
急性腎障害のなかには、透析が必要となる重症例もあります。
体内に過剰な老廃物や水分が蓄積し、利尿薬やその他の内科的治療だけでは改善が見込めないとき、あるいは重篤な高カリウム血症や肺水腫などの合併症が発生したときに透析導入が検討されます。
急性血液透析では、短い時間で老廃物や余分な水分を効率的に除去できるメリットがありますが、低血圧や出血傾向などの副作用にも注意しながら治療を進めることが必要です。
急性腎障害(AKI)の治療期間
急性腎障害(AKI)は、発症から回復までの期間が比較的短いものから、長引くものまで個人差が大きいです。治療期間を左右する要因には、原因や病型、初期対応のスピード、患者さんの基礎疾患の有無などさまざまな条件が関係しています。
原因と病型による回復度合い
腎前性AKIや腎後性AKIは、原因となる血流不足や尿路閉塞を早期に改善できれば、比較的短期間で腎機能が回復しやすいです。
腎前性AKIの場合は、循環血液量の確保や血圧管理がスムーズに進めば、数日から1~2週間ほどでクレアチニンなどの数値が安定に向かうことがあります。
腎後性AKIでは外科的処置や結石の除去などで尿の流れが再び正常化すれば、回復は意外と早まる可能性があります。
- 腎前性AKI:数日~2週間程度で回復する例がある
- 腎後性AKI:尿路閉塞を解消した直後から腎機能改善の兆しが出る場合もある
しかし、腎実質性AKI(とくに急性尿細管壊死など)は、組織が直接ダメージを受けている分だけ回復までに時間がかかるケースが多いです。
軽度なら2~3週間で良好に改善する場合もありますが、ダメージが強いと数か月の長期経過を要し、最終的に慢性腎不全へ移行することも考えられます。
重症度と合併症による変化
急性腎障害が重症化して、透析療法を導入したり、合併症が起こったりすると、治療期間はさらに長期化します。
心不全や肺水腫、電解質異常が深刻化した場合、これらの合併症の管理が優先されますが、腎機能の回復を妨げる要因にもなり得ます。
また、集中治療室(ICU)レベルの管理が必要な急性腎障害の患者では、全身の状態が安定するまでに時間を要するため、退院までの道のりも長くなりやすいです。
副作用や治療のデメリットについて
急性腎障害(AKI)の治療にはさまざまな薬剤が用いられますが、腎機能をサポートする反面、副作用のリスクを伴うものもあります。
また、積極的な治療を行うほど身体への負担が増えるケースもあり、特に重症の場合は透析導入の可否など難しい判断を迫られます。
利尿薬の影響と注意点
利尿薬は体内の余分な水分や電解質を排泄し、むくみや肺水腫などを改善するのに役立ちますが、過度な使用によって循環血液量が不足し、腎血流量が下がることがあり、かえって腎機能を悪化させるリスクもあります。
また、利尿薬の種類によってはカリウムやナトリウムの過度な排泄を起こし、不整脈や倦怠感などを招く可能性があるため、投与量や投与期間を慎重に調整することが大切です。
- 低血圧やめまいを起こしやすくなる
- 電解質バランスが崩れることで不調が出る
- 過度な利尿は腎臓への血液供給を減少させるリスクがある
カリウム吸着薬やリン吸着薬の副作用
急性腎障害では、カリウムやリンの排泄がうまくいかないため、血中濃度が高まる場合があります。
これに対処するためにカリウム吸着薬やリン吸着薬を使用しますが、薬の種類によっては消化器症状(便秘や下痢、吐き気など)を引き起こすことがあります。
また、吸着薬によっては薬剤同士の相互作用が起こりやすいものもあるため、服用スケジュールに注意が必要です。吸着薬を飲んだタイミングや他の薬との組み合わせによって、効き方や副作用が変化します。
| 吸着薬 | 主な注意点 |
|---|---|
| カリウム吸着薬 | 消化器症状、ほかの薬の吸収への影響 |
| リン吸着薬 | 便秘や胃腸障害、カルシウムレベルとの連動 |
カリウム吸着薬は高カリウム血症の緊急事態を和らげる効果が見込めますが、大腸に負担をかけて潰瘍や出血を起こすリスクも指摘されており、使用時には適切なモニタリングが大切です。
治療の複雑化による合併症リスク
急性腎障害は合併症が起こりやすく、治療が複雑になるほど新たなトラブルが重なる懸念があります。
心不全や肺水腫が同時に存在する場合、循環管理と腎保護のバランスを取るのが難しく、治療内容が交差することで副作用のリスクが高まる可能性があります。
また、抗生物質の大量投与が必要な感染症を抱えていると、腎毒性のある薬剤の使用が避けられないケースもあり、腎ダメージと感染症コントロールの板挟みになる場面も少なくありません。
こうした複雑な状況では継続的なモニタリングが必須です。
急性腎障害(AKI)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
血液検査や尿検査にかかる費用
急性腎障害のスクリーニングや経過観察では、血液検査と尿検査が頻繁に行われ、公的医療保険を利用した場合、以下のような目安が参考になります。
- 血液検査(クレアチニン、BUN、電解質などの一般的な腎機能関連項目)
保険適用後の自己負担額:約1,000円~2,000円前後(検査項目数により変動) - 尿検査(尿沈渣、尿タンパクなど)
保険適用後の自己負担額:約300円~600円前後
急性期には状態の変化を逐次把握するため検査の回数も増える傾向があり、それに応じて費用も重ねて発生する場合があります。
画像検査や外科的処置に伴う費用
急性腎障害の原因特定や、腎後性AKIでの尿路閉塞を調べるためにCTやMRI、超音波検査などの画像診断が行われ、保険適用後でも自己負担額は数千円から数万円程度と、検査の内容や撮影部位、機器の種類によって幅があります。
CT検査(造影あり)の場合は保険適用後でも1回あたり5,000円~10,000円程度が目安になることがあり、MRI検査は機器によって金額が変わりやすいですが、保険適用後でも1万円前後になる場合もあります。
尿管ステント留置や結石砕石術などの外科的処置は症状の程度や実施する医療機関の設備によって費用に幅があり、保険適用後の自己負担額が2万円から5万円程度です。
薬剤や点滴の費用
急性腎障害で使用する薬剤は、カリウム吸着薬や利尿薬、抗生物質、降圧薬など多岐にわたります。
保険適用後の自己負担額の目安としては、1種類あたり月に1,000円~3,000円ほどになるケースが多いですが、重症度や併用薬の数によって大きく変動します。
点滴療法による輸液管理では、1回の点滴セットで数百円から千円程度の自己負担になることが一般的ですが、集中治療管理が必要な場合は複数種の点滴や高価な製剤を使うこともあるため、総額はさらに上がります。
透析治療の費用
急性腎障害で重症化して透析を導入すると、血液透析1回につき保険適用後でも数千円~1万円程度の自己負担が発生することがあります。
週に数回行う場合はその回数分の費用が積み重なりますが、腎機能が回復して透析が不要になれば、その分の費用はかかりません。
なお、病状によっては入院中に緊急透析が繰り返し行われる場合もあり、入院費と合わせて負担が大きくなる場合があります。
以上
参考文献
Fujinaga J, Kuriyama A, Shimada N. Incidence and risk factors of acute kidney injury in the Japanese trauma population: a prospective cohort study. Injury. 2017 Oct 1;48(10):2145-9.
Yamada H, Yanagita M. Global perspectives in acute kidney injury: Japan. Kidney360. 2022 Jun 30;3(6):1099-104.
Fujii T, Uchino S, Doi K, Sato T, Kawamura T, JAKID Study Group. Diagnosis, management, and prognosis of patients with acute kidney injury in Japanese intensive care units: The JAKID study. Journal of critical care. 2018 Oct 1;47:185-91.
Inohara T, Kohsaka S, Miyata H, Ueda I, Maekawa Y, Fukuda K, Cohen DJ, Kennedy KF, Rumsfeld JS, Spertus JA. Performance and validation of the US NCDR acute kidney injury prediction model in Japan. Journal of the American College of Cardiology. 2016 Apr 12;67(14):1715-22.
Yasuda H, Kato A, Fujigaki Y, Hishida A, Shizuoka Kidney Disease Study Group. Incidence and clinical outcomes of acute kidney injury requiring renal replacement therapy in Japan. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2010 Dec;14(6):541-6.
Negi S, Koreeda D, Kobayashi S, Yano T, Tatsuta K, Mima T, Shigematsu T, Ohya M. Acute kidney injury: Epidemiology, outcomes, complications, and therapeutic strategies. InSeminars in dialysis 2018 Sep (Vol. 31, No. 5, pp. 519-527).
Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. The Lancet. 2012 Aug 25;380(9843):756-66.
Ronco C, Bellomo R, Kellum JA. Acute kidney injury. The Lancet. 2019 Nov 23;394(10212):1949-64.
Kellum JA, Romagnani P, Ashuntantang G, Ronco C, Zarbock A, Anders HJ. Acute kidney injury. Nature reviews Disease primers. 2021 Jul 15;7(1):52.
Kellum JA, Romagnani P, Ashuntantang G, Ronco C, Zarbock A, Anders HJ. Acute kidney injury. Nature reviews Disease primers. 2021 Jul 15;7(1):52.